会社設立前後にやることとは?具体的な手順や費用も解説!
カテゴリー:
公開日:2025年8月
更新日:2026年1月24日
会社設立を検討するとき、多くの方が「手続きが複雑でやることが多い」と感じるのではないでしょうか。実際に会社設立では、定款の作成や登記申請などの法的なやることに加え、資本金の準備や印鑑作成といった細かなやることも発生します。さらに、会社設立後も税務署や自治体への届出、社会保険や労働保険の加入、法人口座の開設など、やることは途切れることなく続きます。
この記事では、会社設立の基本や必要な費用、会社設立前後にやることの具体的な手順と注意点をわかりやすく解説します。
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
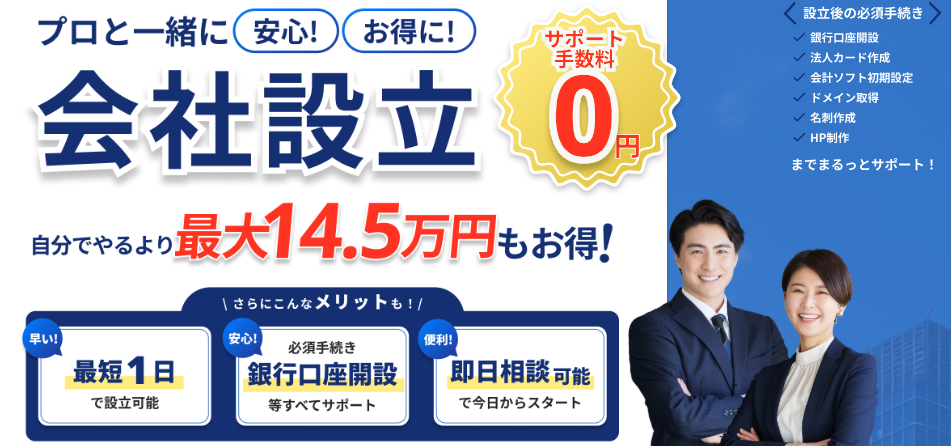
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
会社設立とは

会社設立と聞くと、手続が複雑でやることが多く、ハードルが高いと感じる方も少なくありません。しかし、個人事業主と比べると、会社設立には社会的信用度の向上や資金調達の幅の広がり、節税効果といった大きなメリットがあります。一方で、費用や手間がかかり、設立後も社会保険への加入や事務作業などの負担が増える点には注意が必要です。ここでは、会社設立のメリットとデメリットを整理します。
会社設立前後にやることに関するおすすめ記事
会社設立とは
会社設立とは、法務局に登記申請を行い、法人格を取得することを指します。法人は個人事業主とは異なり、独立した存在として権利や義務を持ちます。これにより、事業は経営者個人とは切り離され、信用度の向上や資金調達の選択肢拡大、節税の可能性などの効果が期待できます。ただし、登記や定款作成などの準備が必要で、運営には費用や手続きの負担も伴います。
会社設立のメリット
会社設立の大きなメリットは、社会的信用度の向上、資金調達の多様化、節税効果、有限責任の4点です。
SoVa税理士ガイド編集部
法人格を持つことで、取引や融資が受けやすくなり、経費計上の範囲も広がります。
役員報酬や保険料を経費にできる点は節税につながり、また出資額以上の責任を負わない有限責任はリスク軽減に役立ちます。
会社設立のデメリット
一方で、会社設立には費用と手間がかかります。設立時には登録免許税や定款認証費用などが必要で、合同会社は約10万円、株式会社は約25万円が目安です。設立後は社会保険への加入が義務付けられ、税務申告や各種届出など事務作業も増えます。そのため、個人事業主に比べて管理体制の整備が求められる点がデメリットといえるでしょう。
会社設立に必要な費用

SoVa会社設立編集部
会社設立の際に必要な印鑑については以下の記事をご覧ください。
「 合同会社を設立するのに必要な印鑑の種類は?印鑑を準備する際の注意点も解説! 」
株式会社の会社設立を行う場合、登記費用だけでなく、定款認証料や印鑑作成費用など、会社設立に伴うさまざまなやることに費用が発生します。会社設立に必要な主な費用のやることは以下の通りです。
| 費用の項目 | 金額 | 支払い先 |
|---|---|---|
| 定款に貼付する収入印紙代 | 4万円 | 公証人役場 |
| 定款認証の手数料 | 5万円 | 公証人役場 |
| 株式払込事務取扱手数料 | 払込資本金×約0.25% | 銀行など |
| 登録免許税 | 払込資本金×約0.7% | 登記所 |
| 印鑑の作成代金 | 5,000〜5万円 | 購入先 |
| 司法書士などへの委託料 | 契約で定められた金額 | 契約先 |
会社設立前後にやることに関するおすすめ記事
このほか、会社設立に必要なやることとして、名刺や会社用紙の作成など、細かな諸費用が発生するケースもあります。会社設立を円滑に進めるためには、上記の費用ややることを事前に把握し、準備しておくことが重要です。
SoVa税理士ガイド編集部
会社設立では必ず必要となるコストであるため、計画的に資金を確保しておくことが成功のポイントとなります。
会社設立までのスケジュール例

会社設立には通常1~2ヵ月程度の期間が必要です。株式会社や合同会社を設立する場合も、準備状況や法務局の混雑によって会社設立までの期間は前後します。
会社設立時にやることはここがポイント!

特に事業目的の設定や事前調査などは時間がかかるやることの一つであり、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
また、会社設立支援サービスや専門家に依頼することで、会社設立にかかる期間を短縮できるケースもあります。自分の状況に応じて効率的にやることを進めましょう。
株式会社設立までのスケジュール例(合計:約4~5週間)
STEP①:法人の基本情報の決定(約1週間)
会社名、所在地、事業目的、役員構成、資本金など、会社設立に必須の基本情報を決定する。
STEP②:会社実印の作成(数日~約1週間)
代表者印(実印)、銀行印、角印など会社設立後に必要となる印鑑を準備する。
STEP③:定款作成と認証(約1週間)
定款を作成し、公証役場で認証を受ける。電子定款を利用すれば印紙代が不要となる。
STEP④:出資金の払い込み(約1週間)
出資金を発起人の口座に振り込み、払込証明書を作成するやることを行う。
STEP⑤:設立の登記申請(約1~2週間)
登記申請に必要な書類を準備し、法務局に申請する。申請から登記完了までは通常約1週間である。
SoVa税理士お探しガイド編集部
会社設立前後にやることについてさらに詳しく知りたい人は、こちらの記事もご参照ください。

合わせて読みたい「法人番号と会社法人等番号の違い」に関するおすすめ記事
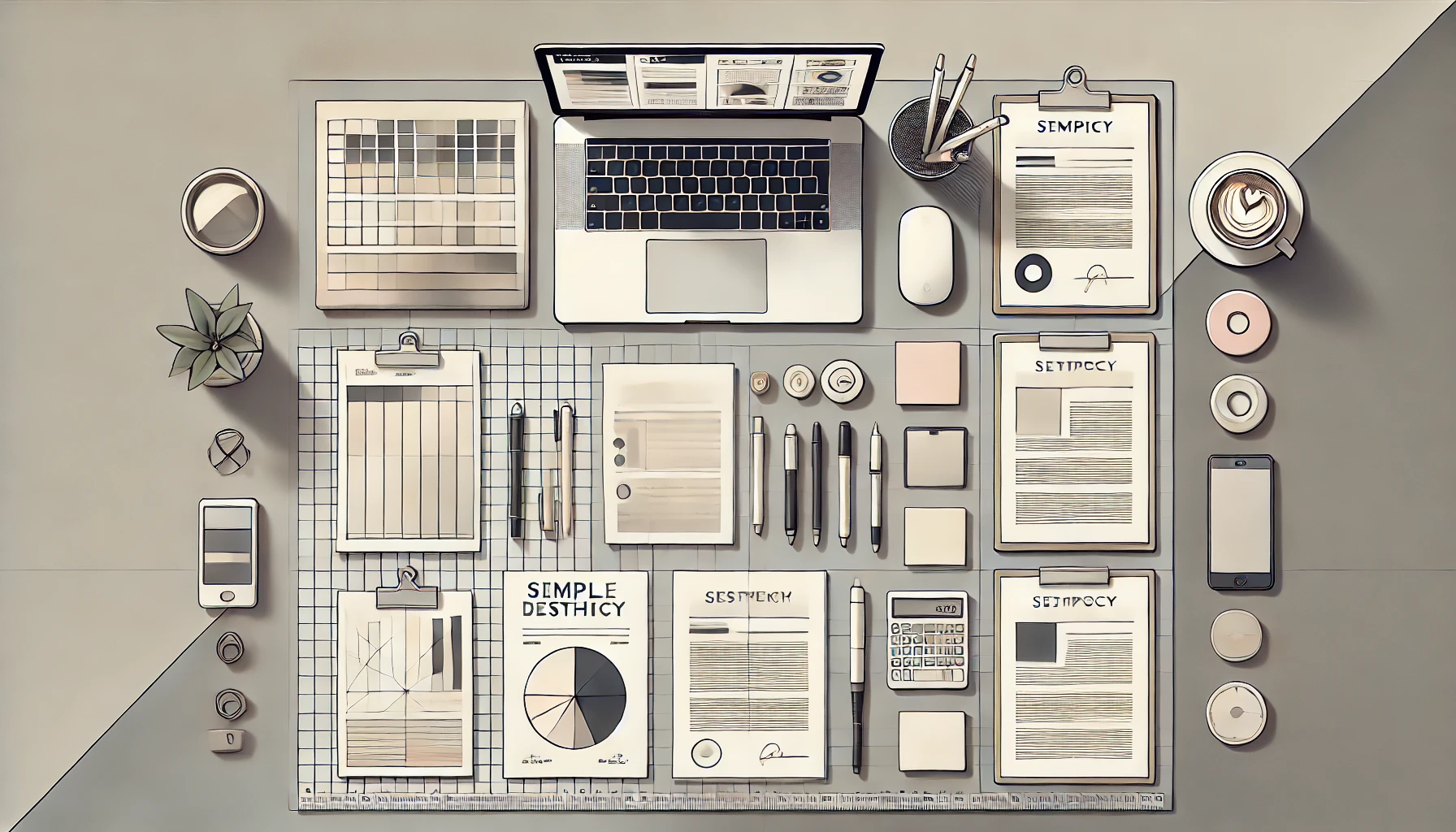
法人番号と会社法人等番号の違いとは?調べ方や使い道も紹介!
合同会社設立までのスケジュール例(合計:約2~3週間)
STEP①:法人の基本情報の決定(約1週間)
会社名、所在地、事業目的、代表社員など会社設立に必要な情報を決定する。
STEP②:会社実印の作成(数日~1週間)
代表者印(実印)、銀行印、角印などを準備するやることを進める。
STEP③:定款作成(数日)
定款を作成する。ただし株式会社と異なり、公証役場での認証は不要である。
STEP④:出資金の払い込み(数日)
代表社員に出資を履行し、払込証明書や出資金領収書を作成するやることを行う。
STEP⑤:設立の登記申請(約1週間)
必要書類を準備し、法務局に登記申請を行う。申請から完了までは通常1週間弱である。
会社設立前にやること

会社設立を進めるには、登記に必要な準備や基本情報の決定など、いくつかのやることがあります。ここでは、会社設立前に押さえておきたい具体的な流れを整理します。
会社設立前にやること①:会社の基本情報の決定
会社設立を進めるためには、まず会社の基本情報を決定する必要があります。商号(会社名)、本店所在地、事業目的、発起人、資本金、事業年度といった情報は、定款に記載する内容でもあるため、会社設立前にしっかり検討することが重要です。これらのやることは会社の土台となるため、将来の事業展開を見据えて慎重に決めましょう。
会社設立前後にやることに関するおすすめ記事:【2024年版】会社設立の流れ・やる事をチェックリストにそってわかりやすく解説
会社設立前にやること②:社印の購入
会社設立時には実印の登録が必須であり、登記申請に必要となります。印鑑には材質やサイズの種類があり、値段も異なります。会社設立後は銀行印や認印を使用する場面も多いため、社印・銀行印・認印の3つを用意しておくと安心です。会社設立をスムーズに進めるための欠かせないやることです。
会社設立前にやること③:資本金の準備
会社設立に必要な資本金を準備します。資本金は会社の信用力や事業の体力を示す指標であり、額が大きいほど金融機関や取引先からの信用を得やすくなります。
会社設立時にやることの中で気をつけておきたい注意点

ただし、資本金が1,000万円を超えると、会社設立初年度から消費税の課税事業者となる点には注意が必要です。
最低資本金制度の撤廃により1円から会社設立は可能ですが、信用度を考慮して事業内容に合った額を設定することが大切です。
会社設立前にやること④:定款の作成と定款認証の申請
会社設立においては、会社の基本規則をまとめた定款を作成します。定款には「商号」「本店所在地」「目的」「資本金の額」「発起人の氏名・住所」といった絶対的記載事項があり、漏れると定款自体が無効になります。株式会社を設立する場合は、公証役場で認証を受ける必要があり、合同会社設立では認証は不要です。会社設立前に必ず確認して進めるべきやることです。
会社設立の関連記事:「会社の作り方を徹底解説!必要な手続きと費用について」
会社設立前にやること⑤:会社設立の登記申請(法人登記)
資本金の払い込みが完了したら、会社設立の登記申請を行います。必要書類は登記申請書、定款、登録免許税納付用台紙、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、役員の就任承諾書や印鑑証明書など多岐にわたります。会社設立の際には登録免許税の納付が必要で、株式会社と合同会社では金額が異なります。法務局や法務省の資料を確認しながら、会社設立手続きを確実に進めましょう。
会社設立前後にやることに関するおすすめ記事
会社設立前にやること⑥:登記事項証明書の取得
会社設立登記が完了すると、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得できます。この書類は会社に関する各種手続きで必ず必要となるため、複数通をあらかじめ取得しておくと手間を省けます。会社設立後すぐに活用するために、早めに対応すべきやることです。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
会社設立前にやること⑦:印鑑カードの取得
会社設立後、実印を証明するために印鑑カードを取得します。印鑑証明書を発行する際に必要となるため、印鑑届出書と同時に申請するのが一般的です。印鑑カードの取得は、会社設立を完了させるために不可欠なやることのひとつです。
会社設立後にやること

会社設立が完了しても、すぐに事業を開始できるわけではありません。会社設立後にも税務署や年金事務所への届出、社会保険や労働保険の加入、法人口座の開設など多くのやることが待っています。これらの会社設立後に必要なやることをきちんと把握し、期限を守って対応することが重要です。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
会社設立後にやること①:税務署へ法人設立の届出
会社設立後は、法人設立届出書を税務署に提出する必要があります。提出期限は会社設立から2か月以内であり、必ず法人番号を記載しなければなりません。法人番号は、会社設立登記が完了すると国税庁から通知されます。提出漏れがないよう注意が必要です。
SoVa税理士ガイド編集部
会社設立前後にやることについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
会社設立後にやること②:法人青色申告承認申請書の提出
会社設立後の最初の決算期から青色申告を利用したい場合は、会社設立から2か月以内に税務署へ法人青色申告承認申請書を提出します。青色申告を選択すると、欠損金の繰越控除など税務上のメリットが大きいため、会社設立後に必ず検討すべきやることです。
SoVa税理士お探しガイド編集部
青色申告はメリットが多いため、会社設立をしたら必ず提出するようにしておきましょう!
会社設立後にやること③:地方税の届け出
会社設立後は、本店所在地を管轄する都道府県税務事務所や市町村役場に法人設立届出書を提出します。これは法人住民税や法人事業税に関わる手続きであり、会社設立後の重要なやることです。提出期限や様式は自治体ごとに異なるため、必ず各自治体のホームページを確認して準備を進めましょう。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
会社設立後にやること④:厚生年金・健康保険の手続き
会社設立後は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に必ず加入する必要があります。社長一人の会社であっても加入義務があり、会社設立から5日以内に年金事務所へ新規適用届を提出します。従業員を雇った場合も、雇用後5日以内に届け出を行う必要があります。会社設立後の社会保険の手続きは期限が短いため、優先度の高いやることのひとつです。
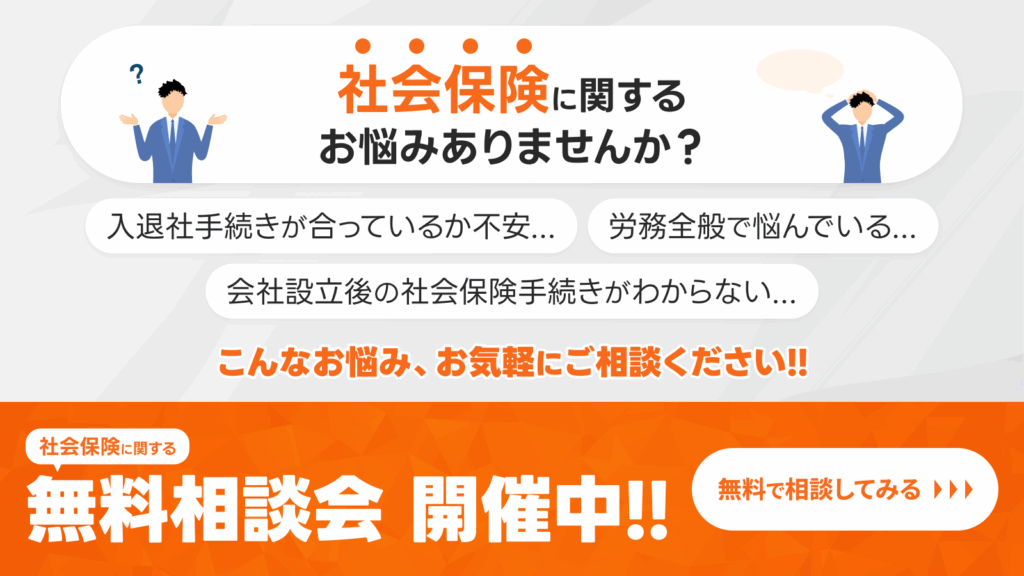
会社設立後にやること⑤:労働基準監督署での労働保険手続き
従業員を雇った場合、会社設立後には労働基準監督署で労災保険などの手続きを行います。適用事業報告書は従業員を雇った時点で速やかに提出が必要です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
また、労働保険関係成立届は雇用日の翌日から10日以内に提出し、概算保険料申告書を提出して保険料を納付します。会社設立後に従業員を採用する場合、必須のやることです。
会社設立後にやること⑥:ハローワークでの雇用保険手続き
会社設立後に従業員を雇った場合、雇用保険への加入も義務です。雇用日の翌日から10日以内にハローワークへ届け出を行う必要があります。会社設立後の労務管理の基本となるやることなので、忘れずに対応しましょう。
会社設立後にやること⑦:銀行で法人口座を開設
会社設立後には、会社名義の法人口座を開設します。会計処理や税務処理を正しく行うために不可欠であり、さらに融資や取引先からの信用度を高める効果もあります。法人口座の開設に期限はありませんが、会社設立後の初期手続きと併せて進めると業務をスムーズに始められます。
まとめ

会社設立は事業の信用を高め、資金調達や節税の選択肢を広げる大きな一歩です。しかし、会社設立には登記や定款認証などの法的手続きだけでなく、資本金の準備や印鑑作成といった多様なやることが伴います。さらに会社設立後も、税務署や自治体への届出、社会保険・労働保険の加入、法人口座の開設といったやることを期限内に進める必要があります。
会社設立をスムーズに進めるためには、事前に流れとやることを把握し、計画的に準備を進めることが成功への近道です。
会社設立前後にやることに関するおすすめ記事:会社設立の流れとは?株式会社を設立するためにやることや必要書類を解説
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!