所得税の計算方法は?給与にかかる所得税を抑える方法についても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年5月
更新日:2026年1月8日
毎月の給与から天引きされる所得税について、「どのように計算されているのか」「そもそも給与がいくらから所得税が発生するのか」と疑問に思ったことはありませんか?
所得税は、一定の控除を差し引いた後の課税所得額に応じて計算される税金で、会社員やアルバイトを含むすべての給与所得者に関係する身近な税金です。
本記事では、所得税の基本的な仕組みや、給与にかかる所得税の計算方法、源泉所得税の計算手順についてわかりやすく解説します。また、所得税の負担を抑えるために活用できる控除制度や節税対策についても紹介します。
給与明細に記載される「所得税」の金額の仕組みを正しく理解し、自分に合った対策で賢く節税しましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
所得税とは

「所得税の計算方法」編集部
個人の所得税以外に、法人が基本的に支払う税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・消費税の5種類があります。詳しい法人が支払う税金の種類についてはこちらの記事を参照ください。
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される税金です。ここでいう「所得」とは単なる年収ではなく、収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額を指します。
たとえば会社員の場合、給与の総額から「給与所得控除」や「所得控除(基礎控除・扶養控除など)」を引いた金額が「課税所得」となり、その金額を基に所得税が計算されます。
所得税の対象となる人とは?
所得税は、会社員のような給与所得者だけでなく、自営業の個人事業主や、副業収入、不動産収入、株式や土地の売却益を得た人など、さまざまな所得に対して課税されます。
どの所得が課税対象となるかは、収入の種類とその金額、控除の適用状況によって変わるため、正確な所得税の計算には注意が必要です。
所得税の計算方法と所得税を抑える方法に関するおすすめ記事
源泉所得税と所得税の違い
源泉所得税とは、企業や個人が、報酬や給与の支払い時に所得税をあらかじめ差し引いて納める制度です。たとえば会社員が毎月の給与から引かれる税金がこれに該当します。
源泉徴収では、給与の総支給額から社会保険料などを差し引いた後の金額に対して、扶養人数に応じた税率を適用して概算の所得税額を計算します。この金額は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて決定されます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
ただし、源泉所得税はあくまでも暫定的な金額です。年末調整や確定申告で実際の所得税を再計算し、源泉徴収額との差額を清算する必要があります。
【参考】所得税の源泉徴収に関連する判例
破産管財人による退職金や報酬の支払いにおいて、所得税の源泉徴収義務があるかが争点となった重要な判例があります。本件では、破産した企業の破産管財人が、元従業員への退職金および自身への報酬を支払う際、所得税の源泉徴収を行わなかったことから、所得税およびそれに付随する不納付加算税の納付義務があるかが争われました。原告である破産管財人は、所得税法上の支払者には該当しないと主張し、所得税の源泉徴収義務はないと訴えました。
※平成18年10月25日判決
しかし、裁判所は、所得税法に基づいて、実際に報酬や退職金を支払ったのは破産管財人であり、その行為は所得税の源泉徴収義務を伴うと判断しました。また、破産管財人の職務は弁護士としての業務の延長とされ、所得税法204条に定められた源泉徴収の対象である報酬に該当するとされました。これにより、破産管財人は退職金に係る所得税および自身の報酬に対する所得税、さらに不納付加算税の納付義務を負うとされ、原告の請求は棄却されました。

合わせて読みたい「税務署から電話がくる理由」に関するおすすめ記事

税務署から電話がきた理由とは?対応方法や相談する際のポイントも解説!
この判例からは、破産手続き中であっても、所得税の源泉徴収義務が免除されるわけではないこと、また、実質的に報酬や退職金を支払う立場にある者には、所得税法上の義務が発生する可能性があることが明らかとなります。就業規則や労働契約の設計・運用においては、所得税に関する正確な理解と、支払者としての責任を意識することが重要です。
参照:裁判所「裁判例検索」
所得税は給与いくらから発生する?
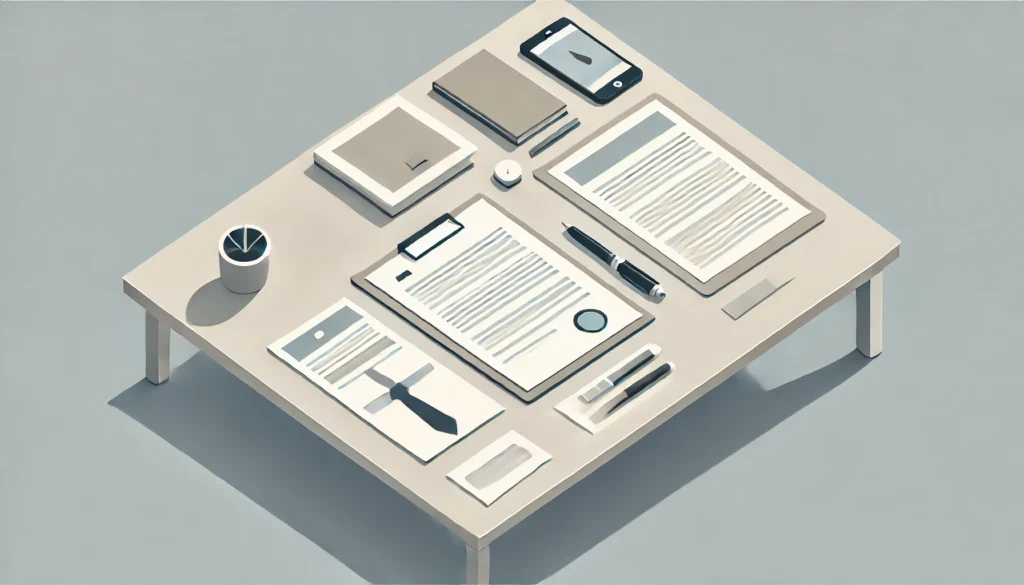
所得税の計算では、収入があっても各種控除を活用することで課税対象となる所得が減り、最終的に所得税の負担を軽減することが可能です。場合によっては、所得税がかからない年収になることもあります。
ただし、控除額は働き方や収入形態によって異なるため、自分の状況に応じて適切に所得税の計算を行うことが重要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社勤めの場合:年収103万円を超えると所得税がかかる
給与所得者(会社員・正社員・契約社員など)の場合、所得税が発生する年収の目安は103万円です。この基準は、給与所得控除と基礎控除の合計額に基づいています。
「税金を滞納したらどうなる?」編集部
法人税、所得税や消費税を滞納した場合どうなるのかに関しては「 税金を滞納したらどうなる?リスクと対処法も解説! 」の記事が参考になるでしょう。
たとえば、合計所得金額が162万5,000円以下であれば、給与所得控除は55万円。さらに、合計所得金額が2,400万円以下なら、基礎控除48万円が適用されます。つまり、55万円+48万円=103万円までの給与収入であれば、課税される所得金額(課税所得)はゼロとなり、所得税はかかりません。
パート・アルバイトの場合:月収8万8,000円が所得税の境界線
パートやアルバイトなど短時間労働者の場合も、所得税の計算方法は給与所得控除と基礎控除の合計が基本です。月収が8万8,000円を超えると、給与の支払い時点で源泉徴収によって所得税が差し引かれるケースが増えます。
所得税の計算に関するここがポイント!

ただし、年間所得が103万円以下であれば、年末調整で源泉徴収された所得税の還付が受けられる可能性があります。
年収が103万円を超えると、給与に対して所得税が正式に課税されるため、月収が増えるほど所得税の負担額も増加します。
個人事業主の場合:年間所得が48万円を超えると所得税が発生
個人事業主の場合の所得税の計算方法は、以下のようになります。
所得税の課税対象額 = 総収入 − 必要経費 − 所得控除
このように、給与所得者のように給与所得控除は使えませんが、基礎控除(48万円)は合計所得金額が2,400万円以下であれば適用されます。つまり、年間の所得が48万円を超えると所得税の課税対象になるのが基本的な目安です。

合わせて読みたい「住民税の特別徴収と普通徴収」に関するおすすめ記事

住民税の特別徴収とは?普通徴収との違いや手続き方法についても解説!
SoVa税理士お探しガイド編集部
所得税の計算方法と所得税を抑える方法について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:所得税の計算方法は?税率や控除などをわかりやすく解説
副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
給与とは別に副業収入がある場合でも、副業の年間所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。この際の所得とは、売上や報酬から経費を差し引いた後の金額です。
なお、所得税の申告が不要な場合でも住民税の申告は必要なことがあります。確定申告を行わなかった場合は、自身で住民税の申告を行わなければなりません。副業がある方は、所得税と住民税の手続きを混同しないよう注意が必要です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
役員賞与の所得税については以下の記事も是非参考にしてください。
「 役員賞与に所得税はかかる?役員賞与を支給する際の注意点や、損金算入し節税する方法も紹介! 」
給与計算における所得税の計算方法

所得税の計算は、「課税所得金額×所得税率-控除額」で求めるのが基本です。
SoVa税理士ガイド編集部
国税庁が公表している所得税の速算表を使えば簡単に計算できますが、2037年までは復興特別所得税が加算されるため、通常の所得税に追加で2.1%を上乗せする必要があります。
所得税と復興特別所得税の計算式
- 所得税の金額 = 課税所得金額 × 所得税率 − 控除額
- 復興特別所得税の金額 = 所得税の金額 × 2.1%
上記のように、まず所得税を計算し、その金額に対して復興特別所得税を計算して合算する流れになります。以下では、所得税を正しく計算するための手順を解説します。
所得税を計算するためのステップ①:年間の収入を計算する
最初に、1年間の収入を把握します。個人事業主の場合は、年間の売上金額が収入に該当します。会社員やアルバイト、パートの場合は、毎月の給与や賞与(ボーナス)などを含めた年間の給与総額が対象です。
所得税を計算するためのステップ②:年間の収入から経費または給与所得控除を差し引く
個人事業主であれば、収入から家賃・水道光熱費・人件費・仕入代などの必要経費を差し引いて所得を計算します。
一方、給与所得者(会社員・アルバイト・パートなど)の場合は、「給与所得控除」を差し引くことで課税対象額を求めます。給与所得控除は給与収入に応じて金額が決まっており、詳細は国税庁の「No.1410 給与所得控除」で確認できます。
所得税を計算するためのステップ③:所得控除を差し引いて課税所得金額を算出する
次に、②の金額から「所得控除」を差し引きます。所得控除は、納税者の生活状況に応じて税負担を軽減できる制度で、全部で15種類あります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
代表的な所得控除には、以下のようなものがあります。
- 基礎控除(すべての納税者に適用)
- 扶養控除(扶養家族がいる場合)
- 医療費控除(一定額以上の医療費を支払った場合)
- 社会保険料控除、配偶者控除など
控除の適用後の金額が「課税所得金額」となり、これを基に所得税の計算を行います。詳細は国税庁の「No.1100 所得控除のあらまし」を参照してください。
所得税の計算方法と所得税を抑える方法に関するおすすめ記事
所得税を計算するためのステップ④:所得税の税率をかけて税額を計算する
③で算出した課税所得金額に、所得税率をかけて所得税の金額を計算します。所得税率は「超過累進税率」が適用されており、課税所得に応じて5〜45%まで7段階に分かれています。
所得税を計算した後は、その金額に対して復興特別所得税(2.1%)を乗じた金額を加算する必要があります。これにより、実際に納めるべき所得税の合計額が決まります。
所得税を計算するためのステップ⑤:税額控除を適用して最終的な所得税額を決定する
最後に、④で計算した税額から「税額控除」を差し引きます。税額控除は、計算された所得税の金額から一定額を直接差し引く制度で、以下のような種類があります。
- 配当控除
- 寄附金控除
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
税額控除の適用後に残る金額が、最終的に納める所得税の金額となります。
給与にかかる所得税を抑える方法

所得税の計算において、負担を軽減するためには、控除制度や非課税制度を適切に活用することが重要です。会社員の給与所得や個人事業主の事業所得に対しても、それぞれの働き方に応じた所得税の節税方法があります。以下では、所得税を抑えるための具体的な制度や計算のポイントを解説します。

合わせて読みたい「法人 赤字 税金」に関するおすすめ記事

法人で赤字の場合に免除される税金とは?納税の有無や赤字決算のメリット・デメリットを紹介!
所得税を抑える方法①:所得控除と税額控除を活用する
所得税の計算方法は、収入から必要経費や各種控除を差し引いて課税所得を求め、その金額に対して税率をかけて税額を算出します。ここで重要なのが、所得控除と税額控除の2つの制度です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
- 所得控除:給与や事業収入などから、基礎控除、扶養控除、医療費控除などを差し引いて課税所得を減らす仕組み。
- 税額控除:計算された所得税額から、住宅ローン控除や寄附金控除などにより、直接所得税を差し引く仕組み。
これらの控除は、会社員の給与所得に対しても、個人事業主の事業所得に対しても適用されます。ただし、適用には年末調整や確定申告などの手続きが必要です。所得税の負担を減らすには、自分が使える控除制度を正しく把握し、計算に反映させることが重要です。
所得税の計算方法と所得税を抑える方法に関するおすすめ記事
所得税を抑える方法②:iDeCoに加入する
所得税の節税対策として効果的なのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入です。
iDeCoは、将来の老後資金を自分で準備する制度で、掛金が全額所得控除の対象になります。たとえば、給与所得者が毎月の給与からiDeCoの掛金を支払うことで、その分だけ課税所得が減少し、所得税の計算上有利になる仕組みです。
また、iDeCoによる運用益はすべて非課税で、60歳以降に受け取る際も一定の退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。
所得税を抑える上でここがポイント!

給与所得者だけでなく、フリーランスや個人事業主も加入できるため、所得税対策をしながら老後の資産形成ができる制度として注目されています。
所得税を抑える方法③:確定申告を青色申告にする
個人事業主が所得税を抑える計算方法として効果的なのが「青色申告」です。
白色申告と比べて、青色申告を選択することで最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
SoVa税理士ガイド編集部
つまり、同じ収入でも所得税の計算上、課税所得が大幅に減り、結果的に納めるべき所得税額が少なくなる可能性があります。
青色申告の適用には、事前に税務署へ申請し、複式簿記による帳簿管理や電子申告(e-Tax)などの条件を満たす必要があります。会計ソフトを活用すれば、仕訳や帳簿作成の作業も効率化でき、所得税の正確な計算や節税効果の最大化にもつながります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
所得税の計算方法と所得税を抑える方法に関するおすすめ記事:所得税の計算方法とは?源泉所得税や月額表の見方についても解説
また、支出管理を明確にするために、仕事専用のクレジットカードや銀行口座を用意するのも有効です。青色申告は手間がかかりますが、所得税の負担軽減に大きな効果がある方法として、特に売上や経費が大きくなってきた個人事業主におすすめです。
Q&A|よくある質問
Q: 所得税の計算方法はどうなっていますか?
A: 所得税の計算方法は、まず給与総額から社会保険料を差し引き、さらに給与所得控除や基礎控除などの各種控除額を差し引いた課税所得に、所得税率を掛けて計算します。所得税の計算方法では、社会保険料は重要な控除項目であり、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などが対象となります。
Q: 給与にかかる所得税の計算方法で社会保険料はどのように反映されますか?
A: 所得税の計算方法では、社会保険料は全額が控除対象となり、課税所得を減らす効果があります。具体的には、給与総額から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料を差し引くことで、所得税の課税対象額が下がります。このため、社会保険料は実質的に所得税を抑える重要な要素です。
Q: 所得税を抑えるための計算方法の工夫はありますか?
A: 所得税を抑える計算方法としては、社会保険料控除のほか、扶養控除や生命保険料控除、医療費控除などを最大限活用することが有効です。また、年末調整や確定申告で必要な控除を漏れなく申請することで、所得税を最小限に抑えることができます。社会保険料は必ず反映されるため、計算時には正確な金額を把握することが大切です。
Q: 所得税の計算方法を間違えるとどうなりますか?
A: 所得税の計算方法を誤ると、本来より多く所得税を払ってしまったり、逆に不足分を追加納付する必要が出てきます。社会保険料額の記載ミスや控除漏れも誤算の原因になります。正しい計算方法を理解し、給与明細や源泉徴収票で社会保険料の反映を確認することが重要です。
まとめ
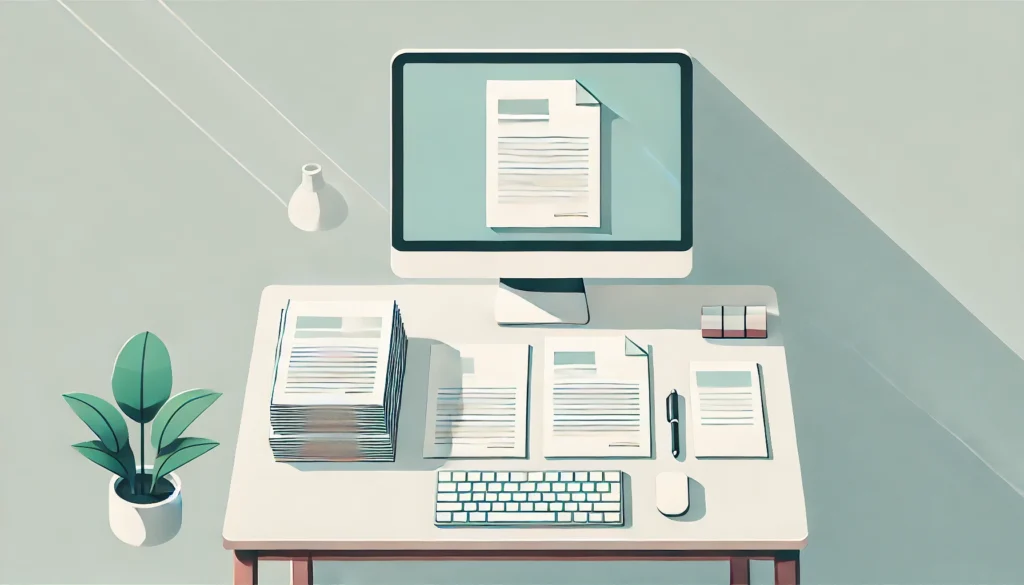
所得税は、給与収入に応じて計算される税金であり、収入が一定の水準を超えると誰もが負担することになります。
SoVa税理士ガイド編集部
特に、給与計算における所得税の計算方法や源泉徴収の仕組みを正しく理解することは、日々の資金管理やライフプランを立てるうえでとても重要です。
また、基礎控除や給与所得控除などの制度を活用すれば、所得税の負担を軽減できる可能性もあります。iDeCoの加入や扶養控除、医療費控除など、自分に合った方法でしっかりと対策を講じましょう。
この記事で紹介した内容を参考に、正しい所得税の計算と節税対策を行い、給与から引かれる所得税額を賢くコントロールしていきましょう。
所得税の計算方法と所得税を抑える方法に関するおすすめ記事
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!