合同会社の確定申告は自分でできる?自分でやる際の手順やメリット・デメリットを解説!
カテゴリー:
公開日:2025年8月
更新日:2026年2月12日
合同会社を設立すると、株式会社と同じように毎年の決算と確定申告が必要になります。では、合同会社の確定申告は自分でできるのでしょうか?結論から言うと、会計ソフトなどを活用すれば、合同会社の確定申告を自分で進めることは十分可能です。ただし、メリットだけでなくデメリットや注意点もあるため、正しい知識を持って取り組むことが大切です。
この記事では、合同会社の確定申告を自分で行う場合の流れや必要書類、メリット・デメリット、そして申告期限までをわかりやすく解説します。
合同会社や株式会社のメリットなども無料相談可能!
株式会社と合同会社のどちらの法人格が良いのか?資本金はいくらにするのが良いのか?決算月はいつが良いのか?なども相談できるので、自分でやるよい安心して会社設立が可能です。設立後のサポートも充実しています。
※自分で会社設立するより○万円お得という設立支援業者は、条件が厳しい傾向があるのでご注意ください。
目次
合同会社も確定申告は必要?

合同会社も株式会社と同じく法人形態のひとつであり、合同会社を設立すると事業の利益や損失を正確に計上し、財務状況を把握する必要があります。そのため合同会社であっても、毎年の決算申告を行わなければなりません。特に合同会社は小規模事業者に選ばれることが多く、「決算申告を自分でやるか、それとも税理士に依頼するか」という判断が重要になります。
合同会社の確定申告を自分でやる方法に関するおすすめ記事
株式会社と合同会社の違いとしてよく挙げられるのが決算手続きです。株式会社の場合は株主総会を開き、決算書などの計算書類を承認したうえで、その確定した決算をもとに法人税の計算を行い、確定申告を進める必要があります。一方、合同会社には株主総会のような煩雑な手続きがなく、出資者である社員の合意で迅速に決定できるため、合同会社の決算や確定申告は株式会社に比べてスピーディーに進めやすいという特徴があります。
さらに、合同会社は規模が小さいケースが多いため、会計ソフトを活用して確定申告を自分で行う人も少なくありません。合同会社を自分で運営しながら確定申告も自分で対応できればコスト削減にもつながります。
SoVa税理士ガイド編集部
ただし、複雑な仕訳や節税対策を考える場合には、合同会社であっても税理士に依頼する方が安心です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
合同会社の確定申告を自分でやるメリット・デメリット

「合同会社」編集部
合同会社にかかる税金については、【合同会社が売上なしでも払う税金とは?赤字(利益ゼロ)の場合の納税について解説】の記事も是非ご覧ください。
合同会社を運営する際、決算や確定申告を税理士に依頼せず、自分で行うかどうかは大きな判断ポイントになります。特に設立したばかりの合同会社では、費用を抑えたいと考える経営者も多いでしょう。本章では、合同会社が確定申告を自分で行う場合のメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
合同会社が確定申告を自分で行うメリット
- 税理士に依頼する費用を節約できる(15万円~25万円程度)
- 合同会社の経営状況を自分でより詳細に把握できる
合同会社の法人決算や確定申告を外部の税理士に依頼すると、事務所ごとに異なりますが15万円から25万円程度の費用がかかるのが一般的です。これを合同会社が自分で行えば、その分の費用を節約することができます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
特に売上が少ない開業初期の合同会社にとっては、税理士報酬を削減できることは大きなメリットとなります。
また、合同会社の決算や確定申告を自分で対応することで、収益・費用・資産・負債などを細かく確認でき、経営状況をより深く理解することが可能になります。自分で数字を整理する過程が、そのまま合同会社の経営改善につながるのも利点です。
合同会社が確定申告を自分で行うデメリット
- 税務や会計に関する正確な知識が必要
- 自分や社内のリソースを大きく割く必要がある
- 効果的な節税対策ができない可能性がある
SoVa税理士ガイド編集部
合同会社の確定申告を自分でやる方法についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:法人決算を自分で(税理士なしで)やる手順を簡単に紹介!
法人決算や確定申告は複雑で、税法や会計基準の知識がなければ正確に処理するのは難しいです。合同会社であっても誤った決算を提出してしまうと、税務調査などのリスクが高まります。
さらに、自分で確定申告を進める場合、合同会社の経営者や従業員の時間を大きく取られるため、本業に支障をきたす可能性があります。特に小規模な合同会社では、経営資源の分散が大きな負担となるでしょう。
また、税理士など専門家に依頼しなければ、合同会社に適した節税策を逃すリスクもあります。自分で確定申告を行うと、節税のチャンスを活かせず、結果的に税負担が増えてしまうことも考えられます。
合同会社の確定申告を自分でやる際の手順

合同会社を経営していると、毎年必ず決算と確定申告を行う必要があります。特に合同会社は小規模でスタートするケースが多いため、「確定申告を税理士に依頼するか、それとも自分で対応するか」を検討する経営者も多いでしょう。ここでは、合同会社の確定申告を自分で行う際の基本的な流れを解説します。
確定申告に関する参考記事:「タックスナップのデメリット全解説!口コミ、メリットも紹介」

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
確定申告を自分でやる際の手順①:帳簿書類の整理
合同会社の確定申告を自分で行う第一歩は、帳簿や書類の整理です。1年間の売上や経費を正確に記録した帳簿を確認し、領収書・請求書をまとめておきます。合同会社が確定申告を正しく行うためには、この基礎データの正確性が欠かせません。
合同会社の確定申告を自分でやる方法に関するおすすめ記事
確定申告を自分でやる際の手順②:決算整理仕訳をする
次に、合同会社の決算時には必要な仕訳を行います。たとえば減価償却費の計上や未払い費用の処理、売掛金の整理などです。これらを自分で行うことで、合同会社の損益状況をより深く理解でき、確定申告の精度を高めることができます。
確定申告を自分でやる際の手順③:決算書の作成
合同会社の確定申告を自分で進めるためには、決算書の作成が必須です。貸借対照表では合同会社の資産や負債の状態を明確にし、損益計算書では収益・費用・利益を整理します。自分で作成する場合、会計ソフトを活用すると効率的です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
合同会社の確定申告(決算)を顧問税理士に依頼する場合、別途料金であるケースが多数です。
確定申告を自分でやる際の手順④:計算書類の承認
合同会社では株式会社のような株主総会は不要ですが、出資者である社員の合意による承認手続きが必要です。この承認を経て、初めて合同会社の確定申告に進むことができます。
合同会社の確定申告を自分でやる際はここがポイント!

自分で経営している一人合同会社の場合は、自ら承認する形になります。
確定申告を自分でやる際の手順⑤:確定申告と納税を行う
最後に、合同会社の確定申告書を作成し、税務署や地方自治体に提出します。法人税や住民税、事業税を納付して初めて合同会社の確定申告は完了です。自分で行う場合は、申告期限を守ることが非常に重要です。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため注意しましょう。
SoVa税理士お探しガイド編集部
以下の記事も是非参考にしてください。
「 合同会社に税理士は必要か?依頼する場合のメリット・デメリットを解説! 」
合同会社の確定申告を自分でやる際に必要な書類

合同会社を経営していると、毎年必ず決算と確定申告が必要になります。税理士に依頼する方法もありますが、費用を抑えるために確定申告を自分でやる合同会社の経営者も少なくありません。その場合、必要な書類を正確に揃えておくことが大切です。

合わせて読みたい「確定申告はタックスナップ」に関するおすすめ記事
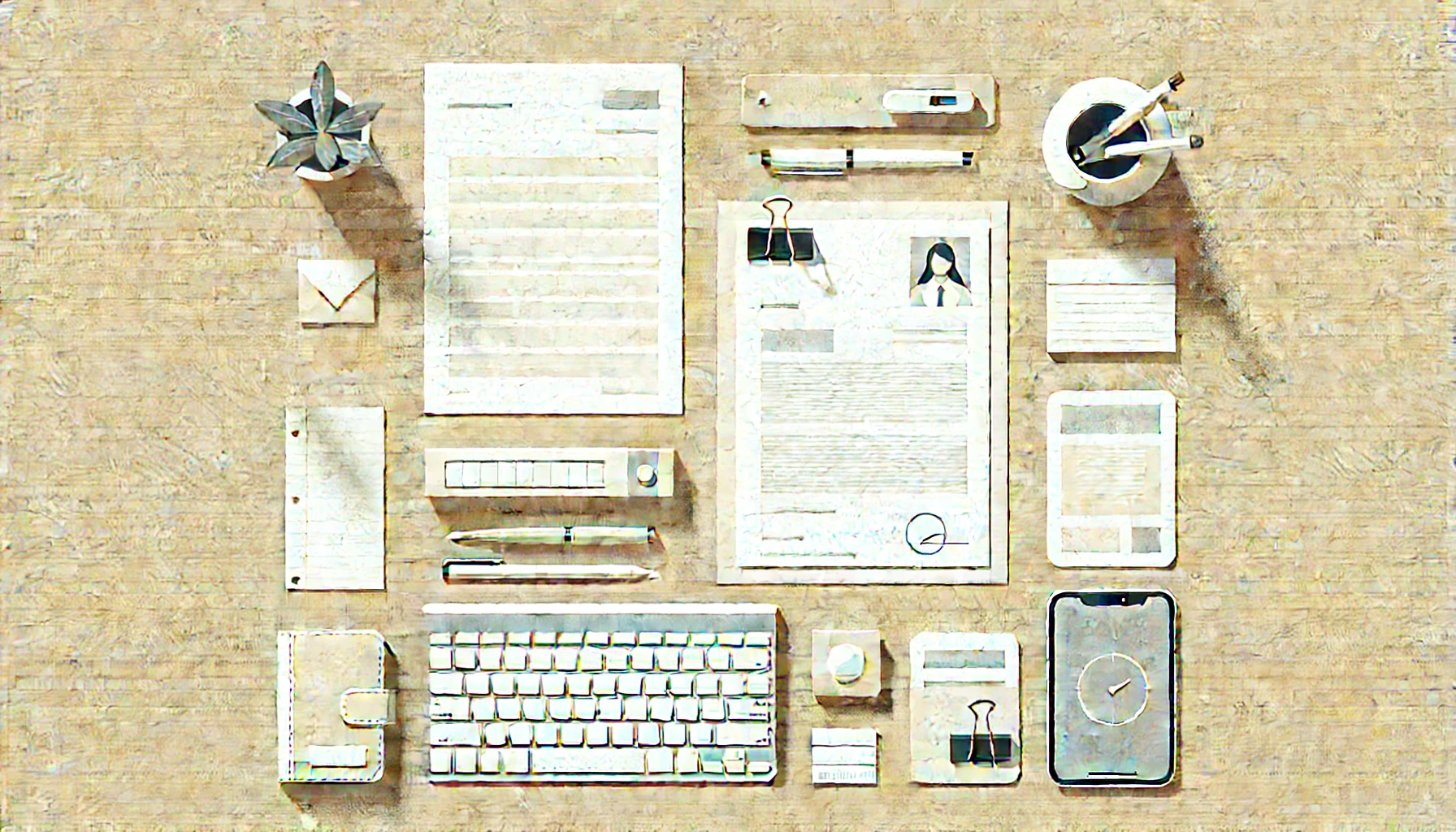
確定申告はタックスナップでサクッと完了!おすすめの理由とは
SoVa税理士ガイド編集部
合同会社の確定申告を自分でやる方法についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
これらの書類は税務署に提出するだけでなく、合同会社の財務状況を自分で正しく把握するためにも重要な役割を果たします。
合同会社の確定申告を自分でやる際に必要な書類①:法人税申告書
法人税申告書は、合同会社が確定申告を行う際の基本となる書類です。課税所得や控除額、納付すべき税額を記載し、法人税額を正しく計算します。合同会社が確定申告を自分で行う場合、この書類を正しく作成できるかどうかが最も重要なポイントとなります。

合わせて読みたい「合同会社 一人社長 給料」に関するおすすめ記事

合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を決める際の決め方と注意点
合同会社の確定申告を自分でやる際に必要な書類②:適用額明細書
適用額明細書は、法人税の軽減税率や特別控除を受ける際に必要な書類です。合同会社が確定申告を自分で進める場合、これを正しく作成しないと控除が認められない可能性があります。税額に大きく関わるため、記載漏れには注意が必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
合同会社の確定申告を自分でやる方法に関するおすすめ記事:法人決算は自分でできる?税理士なしでの流れや必要書類について解説
合同会社の確定申告を自分でやる際に必要な書類③:貸借対照表
貸借対照表は、合同会社の資産・負債・純資産の状況を示す書類です。確定申告を自分で行う場合、合同会社の財務状況を一目で理解できるよう作成することが大切です。会計ソフトを使えば、自分で効率的に作成することも可能です。

合わせて読みたい「スマホで確定申告」に関するおすすめ記事
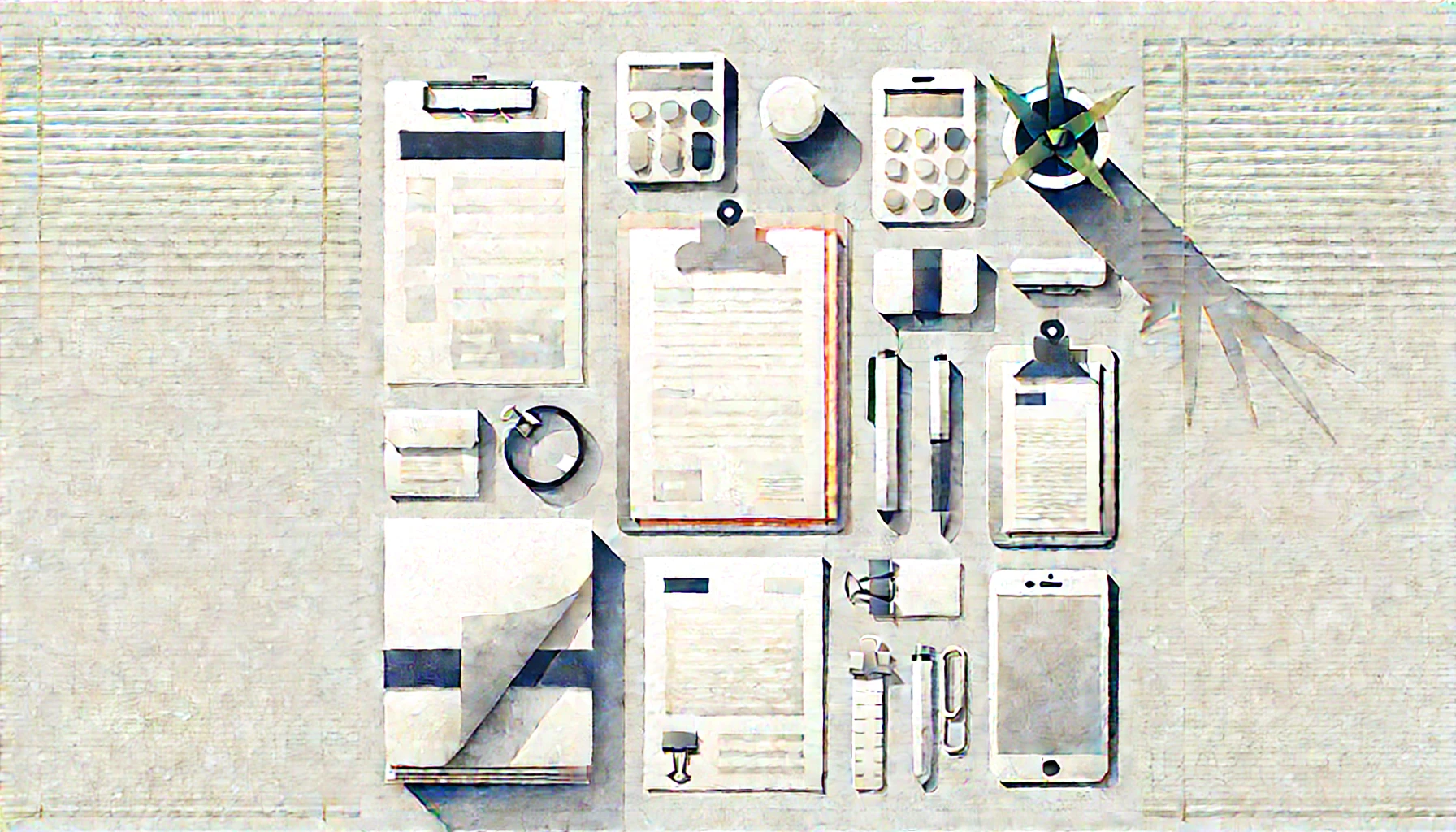
確定申告をスマホで行う方法は?おすすめの確定申告アプリも紹介
合同会社の確定申告を自分でやる際に必要な書類④:損益計算書
損益計算書は、合同会社の収益や費用を記録し、一定期間の利益や損失を明らかにする書類です。法人税の計算はこの損益計算書を基に行われるため、確定申告を自分で行う際には、特に正確性が求められます。
合同会社の確定申告を自分でやる際に必要な書類⑤:社員資本等変動計算書
社員資本等変動計算書は、合同会社の資本金や純資産の増減を記録するものです。
合同会社の確定申告を自分でやる際はここがポイント!

合同会社では社員の出資割合が財務に直結するため、確定申告を自分でやる場合でもこの書類は必須です。
合同会社の確定申告を自分でやる際に必要な書類⑥:勘定科目内訳明細書
勘定科目内訳明細書は、貸借対照表や損益計算書に記載された勘定科目の詳細を示す書類です。売上高の内訳や借入金の詳細を明確にすることで、合同会社の確定申告を自分で進める際にも信頼性の高い内容になります。
確定申告の関連記事:「確定申告アプリおすすめ8選!初心者におすすめなのは?」
合同会社の確定申告を自分でやる際に必要な書類⑦:法人事業概況説明書
法人事業概況説明書は、合同会社の事業内容や規模を説明するための書類です。従業員数や主要な事業活動、売上の構成を記載し、税務署に合同会社の実態を伝える役割を果たします。確定申告を自分で進める際にも忘れてはいけない重要書類です。
合同会社の確定申告はいつまでにすべき?

合同会社を運営するうえで、決算日と確定申告の期限を正しく把握することは欠かせません。合同会社は株式会社と異なり、事業規模が小さいことも多いため「確定申告を自分で行う」経営者も少なくありません。ここでは、合同会社の決算日と確定申告の期限について、自分で進める際に押さえておくべき基本を解説します。
合同会社の確定申告を自分でやる方法に関するおすすめ記事
合同会社の決算日はいつ?
合同会社の決算日は、法人化後に自由に設定できます。事業年度は1年以内の任意の期間で決められるため、多くの合同会社は「3月」「9月」「12月」などを決算月としています。例えば、1月1日〜12月31日を事業年度とすれば決算月は12月、4月1日〜翌年3月31日であれば決算月は3月です。
日本では3月決算が一般的ですが、合同会社の場合は事業内容や繁忙期を考慮し、業務が落ち着く時期に合わせて設定するのが合理的です。特に確定申告を自分で行う合同会社では、作業負担を減らせる決算月を選ぶことが重要です。
合同会社の確定申告はいつ?
合同会社の確定申告と法人税の納付期限は「事業年度終了の翌日から2か月以内」と定められています。例えば、3月決算の合同会社なら5月31日まで、9月決算なら11月30日までに確定申告と納税を完了させる必要があります。
期限までに確定申告を自分で仕上げるのが難しい場合は、合同会社でも申告期限の延長申請が可能です。
自分で合同会社の確定申告をする際に気をつけておきたい注意点

ただし、延長が認められるのは申告書の提出期限のみで、法人税や住民税などの納付期限は延長できません。
さらに、消費税に関しては延長制度がないため、合同会社が確定申告を自分で行う場合でも、期限を厳守することが求められます。
まとめ

合同会社にとって確定申告は必須の手続きであり、自分でやるか税理士に依頼するかは経営方針やリソースによって選択できます。自分で確定申告を行えば費用を抑えつつ経営状況を深く理解できますが、専門知識が不足していると申告ミスや節税機会の損失につながるリスクもあります。
大切なのは、合同会社の確定申告を自分で行うかどうかを事前に判断し、自社に合った方法で確実に期限内に対応することです。必要に応じて税理士にサポートを依頼することも視野に入れながら、合同会社の安定した運営につなげていきましょう。
合同会社の確定申告を自分でやる方法に関するおすすめ記事:合同会社の決算・法人税等の確定申告方法!自分で可能?いつ行う?
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい!