マイクロ法人は社宅を経費にできる?社宅制度を導入する方法や注意点を解説!
カテゴリー:
公開日:2025年8月
更新日:2026年2月12日
マイクロ法人を設立している、あるいはこれから設立を検討している方の中には、「社宅を導入すれば住居費を経費にできるのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。実際、マイクロ法人でも社宅制度を活用すれば、家賃や付随費用の一部を法人経費として処理することが可能です。
とはいえ、マイクロ法人が社宅を経費にするには、いくつかの条件やルールを守る必要があります。誤った運用をしてしまうと、税務上のリスクが生じることもあるため、制度の仕組みや注意点を正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、「そもそも社宅とは何か?」という基本から、マイクロ法人が社宅制度を利用するメリット、経費計上のポイント、導入方法、注意点までをわかりやすく解説します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
そもそも社宅とは

マイクロ法人でも活用できる節税策として注目されているのが「社宅制度」です。社宅とは、会社(マイクロ法人を含む)が物件を賃借、または保有し、その物件を役員や従業員に貸し出す仕組みです。社宅として貸与する場合、入居者からは賃料の一部(一般的に賃料相当額の50%以上)を徴収する必要があります。
福利厚生の一環として従業員社宅を導入するケースが多いですが、従業員がいないマイクロ法人や「ひとり社長」でも、役員社宅として制度を取り入れることが可能です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
マイクロ法人にとっては、個人の住居費を一部法人経費にできるという点で、大きな節税効果が期待できます。
かつては、社宅といえば集合住宅や寮のようなイメージが一般的でした。しかし、現代では社宅のあり方も多様化しており、マイクロ法人においても、個人のライフスタイルに合わせた柔軟な社宅の導入が進んでいます。たとえば本田技研工業の創業者・本田宗一郎氏も、生前「社宅は個々に離すべき」と語っており、現在ではその考えに基づく社宅運用も増加傾向にあります。
マイクロ法人が社宅を経費にする方法に関するおすすめ記事
本記事では、マイクロ法人が導入しやすい現代的な社宅制度について、2つのタイプを中心に解説します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社宅の種類①:借り上げ社宅
借り上げ社宅は、マイクロ法人が賃貸物件を借り上げ、それを役員や従業員に再貸与(転貸)し、一定の賃料を徴収するスタイルです。マイクロ法人にとって初期費用の負担が少なく、気軽に導入できるのが魅力です。
この方式には、マイクロ法人が自ら物件を探して契約するケースと、個人が条件を満たす物件を選定し法人が契約するケースがあります。いずれにせよ、法人が主契約者となることで、社宅としての制度が成立します。
「会社が家賃を一部補助すればよいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、住宅手当と社宅制度とでは税務上の扱いが大きく異なります。社宅ならば法人が負担した家賃の一部を経費計上できる一方で、住宅手当は基本的に給与として課税対象になる点がポイントです。
社宅の種類②:社有社宅
社有社宅は、マイクロ法人が不動産を購入し、それを社宅として役員や従業員に貸し出す形式です。
社宅の種類に関するここがポイント!

借り上げ社宅と異なり、マイクロ法人が物件を保有するため、資産形成という側面もあります。
ただし、物件の購入には多額の資金が必要であり、固定資産税や維持費などのコストもかかるため、マイクロ法人にとっては導入ハードルがやや高めです。
そのため、本記事ではマイクロ法人でも導入しやすい借り上げ社宅を中心に取り上げ、社有社宅には必要な範囲で触れるにとどめます。
マイクロ法人の関連記事:「マイクロ法人は家賃も経費にできる?経費計上する方法や注意点を解説!」
マイクロ法人が社宅制度を利用するメリット

マイクロ法人における社宅制度とは、会社が物件を用意し、その物件を役員や従業員に貸し出す制度です。とくに「借り上げ社宅」の場合、「それなら住宅手当で賃料を補助すればよいのでは?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。
しかし、マイクロ法人があえて社宅制度を導入するのには明確な理由があります。マイクロ法人にとっても、個人側・法人側の両方に節税や実質的な負担軽減といったメリットがあるからです。以下では、住宅手当との違いを踏まえつつ、マイクロ法人が社宅制度を導入するメリットについて解説します。
マイクロ法人の役員が社宅を活用するメリット|手取りが増える
マイクロ法人における社宅制度には、個人側にも以下のような明確な利点があります。
【マイクロ法人の社宅制度で得られる個人のメリット】
- 住居費の自己負担を抑えることができる
- 所得税・住民税・社会保険料の負担が軽くなり、手取り収入が増える
まず、マイクロ法人が社宅を用意し、役員に貸し出すことで、賃料の一部を会社が負担するため、役員個人の住居費負担が軽減されます。次に重要な点は、住宅手当と異なり、社宅制度では所得税や住民税、社会保険料の対象外になる部分があることです。
「マイクロ法人」編集部
マイクロ法人に関連して、「 マイクロ法人のメリットとは?経費にできるものについても解説! 」の記事も是非ご覧ください。

合わせて読みたい「会計ソフト比較一覧」に関するおすすめ記事
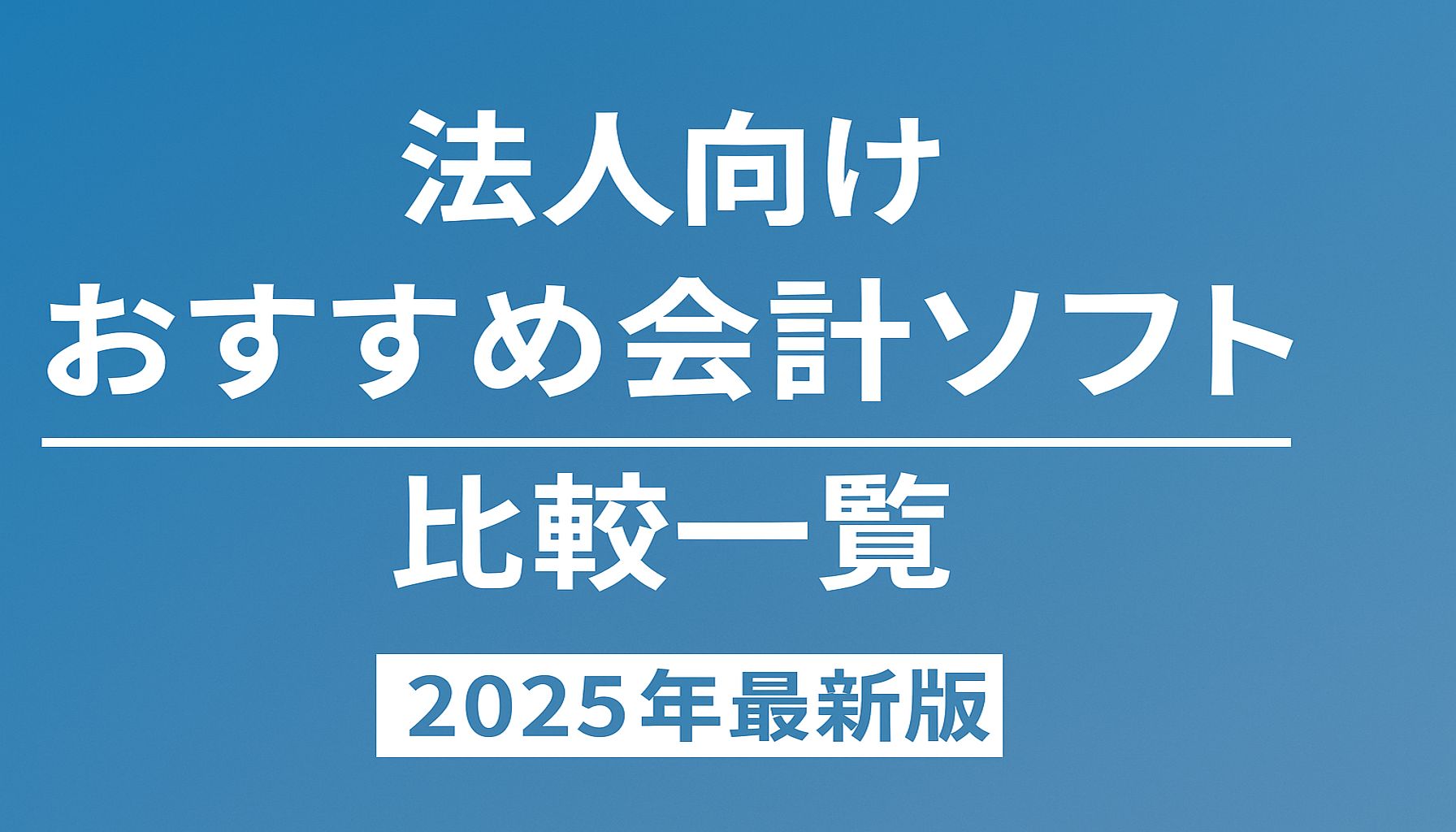
法人のおすすめ会計ソフト比較一覧【2025年最新版】
社宅制度のメリットはここがポイント!

住宅手当は給与の一部と見なされるため、課税対象となり、社会保険料も増加します。一方、社宅制度では会社が物件を借りて提供する仕組みであり、現物支給の福利厚生として扱われるため、課税される所得に含まれないのです。
とくに、マイクロ法人で一人社長として活動している場合、役員報酬を調整しつつ社宅を導入することで、実質的な手取りを増やす効果が期待できます。
マイクロ法人側のメリット|法人税や社会保険料の負担軽減
マイクロ法人が社宅制度を導入することは、法人側にとっても大きなメリットがあります。マイクロ法人の社宅制度で得られる法人のメリットは、賃料と転貸料の差額により、法人税と社会保険料の負担を軽減できる点です。
マイクロ法人が借り上げ社宅を利用する場合、会社が支払った賃料は全額を経費(損金)として計上できます。一方、役員から受け取る転貸料は会社の収益(益金)となりますが、これは通常、支払賃料よりも割安に設定されます。
SoVa税理士ガイド編集部
マイクロ法人が社宅を経費にする方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
そのため、マイクロ法人にとっては、転貸料との差額分だけ法人の課税所得が減少し、法人税や社会保険料の支払い負担が抑えられることになります。
もし住宅手当として支給した場合、たしかに損金扱いにはなりますが、手当額全体に社会保険料がかかってしまうため、マイクロ法人にとってはトータルの負担が重くなります。
したがって、マイクロ法人では、住宅手当よりも社宅制度を導入するほうが、税務上も資金繰りの面でも有利な選択となるのです。
マイクロ法人が社宅導入時に経費にできるもの・できないもの

マイクロ法人が社宅を導入する際には、通常の賃貸契約と同様に初期費用が発生します。マイクロ法人で社宅制度を取り入れる場合、これらの費用のどこまでが法人の経費として認められるかを事前に把握しておくことが大切です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
マイクロ法人の社宅で経費にできる初期導入費
以下のような費用は、マイクロ法人が社宅を契約する際に、法人の経費として計上することが可能です。
- 礼金:マイクロ法人が借り上げ社宅として契約する場合、借主が支払う礼金は法人の経費として処理できます。
- 仲介手数料:不動産会社に支払う仲介手数料は、社宅導入にかかる費用として全額経費にできます。
- 保証会社の保証料:マイクロ法人名義で社宅契約を結ぶ際に必要な保証料も、法人の経費として認められます。
- 火災保険料:社宅契約時に一括で支払う火災保険料も、マイクロ法人の業務関連費用として経費に計上可能です。
マイクロ法人の社宅で経費にできない可能性のあるもの
一方で、以下のような費用は、マイクロ法人の社宅導入時でも経費にできない、あるいは一部のみ経費にできる場合があるため注意が必要です。
- 前払い家賃:契約時に数ヶ月分を前払いする場合、経費ではなく「前払費用」などの資産として計上される可能性があります。
- 敷金:賃料の1ヶ月分などで設定される敷金は、原則として契約終了時に返還される「預り金」のため、マイクロ法人の経費にはできません。これは資産として処理されます。
- 返還されない敷金の一部:契約によっては、敷金の一部が返ってこないことがあります。その返還されない部分については、マイクロ法人の損金として経費計上が認められるケースもあります。
マイクロ法人が社宅を経費にする方法に関するおすすめ記事
マイクロ法人で社宅を導入する場合、これらの初期費用の性質を正しく理解し、帳簿上の処理を適切に行うことが求められます。
マイクロ法人の社宅で経費にできる毎月の費用
マイクロ法人が社宅制度を導入した後も、毎月発生する費用の一部を法人経費として計上することが可能です。以下に、マイクロ法人が社宅運用時に経費にできる代表的な費用項目をまとめます。
- 家賃の一部:マイクロ法人が借り上げ社宅として契約している場合、家賃の一定割合を業務使用分として経費に算入できます。個人からは社宅使用料(転貸料)を受け取る必要があります。
- 共益費・管理費:社宅の建物維持にかかる共益費や管理費も、マイクロ法人が支払うことで経費に計上可能です。
- 水道光熱費の一部:社宅として業務利用している割合をもとに按分し、マイクロ法人の経費にすることができます。
- インターネット代・通信費:業務利用の割合に応じて、社宅にかかる通信費もマイクロ法人の経費として認められます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
マイクロ法人における社宅制度では、これらの費用を適切に按分し、法人経費として処理することで、節税効果を得ながら役員や従業員の生活支援にもつながります。

合わせて読みたい「マイクロ法人 赤字」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の赤字経営は大丈夫?赤字になったときの注意点や対処法を解説
マイクロ法人が社宅制度を導入する方法

マイクロ法人が社宅制度を導入するには、税務面での適正な運用が欠かせません。法人名義での契約や賃料設定のルールなど、いくつかの条件をクリアしてはじめて、マイクロ法人として社宅を経費に計上することが可能になります。この章では、マイクロ法人が社宅を導入する際に押さえておくべき基本条件と、導入をスムーズに進めるための実務ポイントを詳しく解説します。
マイクロ法人の税理士に依頼に関する参考記事:「資金調達を税理士に依頼するメリットやおすすめポイントについて詳細に解説!」
マイクロ法人が社宅を導入する際に必要な条件とは?
マイクロ法人で社宅制度を導入する際には、税務上の要件を満たすことが前提となります。適切な手続きと運用を行うことで、節税効果を得ながら安心して社宅を活用することができます。以下に、マイクロ法人が社宅を導入する際に押さえるべき条件をまとめます。
マイクロ法人が社宅を経費にする方法に関するおすすめ記事:借り上げ社宅を活用した節税
条件①:法人名義での賃貸契約を行う
マイクロ法人が社宅を導入するには、物件を法人名義で契約する必要があります。個人名義ではなく、マイクロ法人名義で賃貸契約を締結することによって、社宅としての制度が正式に成立します。法人契約であることが、経費処理や税務対応の基本となります。
条件②:通達に基づいた賃料(転貸料)を個人が支払う
マイクロ法人が社宅を提供する場合、役員や従業員は「賃料相当額」に基づく一定の家賃(転貸料)を会社に支払う必要があります。これは形式的な処理ではなく、税務上の要件として重要です。適正な金額の賃料を徴収しない場合、税務調査で否認される可能性もあるため注意が必要です。
マイクロ法人が社宅を経費にする方法に関するおすすめ記事
条件③:契約内容が適正であること
社宅制度をマイクロ法人で導入する際は、家賃設定が不自然でないことが重要です。通達では、役員や従業員が支払うべき家賃は、通常の賃料の50~60%程度とされています。不適切な金額設定は「給与」とみなされ、追加の税負担が発生するおそれがあります。社宅導入前に税理士などの専門家に相談するのが安心です。
マイクロ法人が社宅導入を進めるなら、社宅に強い不動産会社の活用を
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
マイクロ法人でスムーズに社宅制度をスタートさせるためには、社宅契約に精通した不動産仲介業者を活用することをおすすめします。とくに初めて社宅を導入するマイクロ法人では、専門的な知識を持つプロのサポートが大きな安心材料になります。
社宅に強い不動産会社の活用するメリット①:適切な物件選びができる
マイクロ法人の社宅利用に適した物件の紹介や、税務・法務の観点から契約条件を最適化してくれる点は大きなメリットです。
SoVa税理士お探しガイド編集部
事業目的や利用頻度に応じた社宅を見つけるためにも、専門知識のある仲介業者に依頼するのが効果的です。
社宅に強い不動産会社の活用するメリット②:法人契約の手続きをスムーズに進められる
マイクロ法人での社宅契約には、登記簿謄本や印鑑証明書などの法人関連書類の提出が求められます。不動産仲介会社のサポートを受けることで、法人契約に必要な準備や手続きを効率的に進めることができます。
社宅に強い不動産会社の活用するメリット③:税務面でのアドバイスも受けられる
社宅制度の導入・運用にあたっては、マイクロ法人にとって重要な税務処理も伴います。社宅に強い不動産業者であれば、税理士と連携して社宅の適正運用についてアドバイスを受けられることもあります。
一人社長に関する参考記事:「一人社長が経費にできるものは?個人事業主との違いや節税ポイントについても解説!」
マイクロ法人が社宅を導入する際の注意点

マイクロ法人が社宅を活用して節税効果を得るためには、単に物件を法人で借りるだけでは不十分です。税務上も法的にも適正に社宅制度を運用するには、まず社内規定の整備が欠かせません。とくにマイクロ法人のように小規模な組織では、規定をあいまいにしたまま運用を始めると、思わぬトラブルや否認リスクを招く可能性があります。
この章では、マイクロ法人が社宅制度を導入するうえで必ず整備しておくべき社内規定のポイントについて解説します。
マイクロ法人が社宅を導入する際の注意点①:社内規定の策定は必須
マイクロ法人で社宅制度を導入する際は、まず明確な社内規定を策定することが必要です。社宅に関する規定が曖昧なままだと、税務上の否認リスクや社内トラブルを招く恐れがあります。
たとえば以下の項目は、最低限社内規定に盛り込んでおくべきです。
- 社宅の利用条件(誰が対象か、使用期間はどの程度か)
- 賃料設定の基準(通達に基づく適正な割合か)
- 費用負担の内訳(光熱費や共益費を誰が負担するか)
マイクロ法人が社宅を経費にする方法に関するおすすめ記事
これらを明文化することで、マイクロ法人としての透明性を保ち、税務調査の際にも説明責任を果たしやすくなります。社宅規定の策定には、税理士や社会保険労務士、法務の専門家の意見を反映させると安心です。
マイクロ法人が社宅を導入する際の注意点②:賃貸契約は必ず法人名義で
マイクロ法人で社宅制度を導入する場合、賃貸契約は必ず法人名義で行う必要があります。
マイクロ法人で社宅制度を導入する際に気をつけておきたい注意点

個人契約で社宅を運用してしまうと、家賃がマイクロ法人の経費として認められず、節税効果が得られません。
また、法人契約であることを証明するために、賃貸契約書はマイクロ法人がしっかりと保管しておくことも大切です。税務調査で社宅の適正運用を確認される際、契約書の提示を求められるケースもあります。
マイクロ法人のような小規模体制では、つい個人契約で進めてしまいがちですが、社宅制度の正しい導入には「法人名義での契約」が大前提です。

合わせて読みたい「出張費を経費」に関するおすすめ記事

出張費はどこまでが経費になる?経費処理の仕訳や相場感を解説!
まとめ

マイクロ法人における社宅制度の活用は、住居費の一部を法人経費にできるという大きなメリットがある反面、税務上の取り扱いや契約形態に注意が必要です。正しく運用すれば、役員個人の手取りを増やしつつ、マイクロ法人としても節税効果を得られる実用的な制度といえます。
社宅をマイクロ法人で導入する際は、法人名義での契約や社内規定の整備、適正な家賃設定など、基本的なルールをきちんと押さえたうえで進めることが重要です。必要に応じて税理士などの専門家に相談しながら、マイクロ法人の経営にとって有益な社宅制度を上手に取り入れていきましょう。
マイクロ法人が社宅を経費にする方法に関するおすすめ記事:社宅を「経費」にして節税する方法|「一人社長」も使える!会社と個人の双方にメリットがある制度を解説
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい!