マイクロ法人のメリットとは?経費にできるものについても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2025年12月16日
近年注目を集めている「マイクロ法人」は、個人事業主が節税や信用力向上を目的に法人化する際の有力な選択肢として支持を集めています。とくに、一人社長で運営できる気軽さや、経費として計上できる範囲の広さが魅力です。
本記事では、マイクロ法人の基本的な概要から、設立によるメリット、さらにはマイクロ法人が経費として計上できる具体的な支出や、経費にできるかどうか判断が難しいケースまで、わかりやすく解説します。これからマイクロ法人を設立しようと考えている方や、すでにマイクロ法人を運営しているものの経費処理に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、中小企業の中でも特に規模が小さく、代表者1人で運営されることが多い法人形態です。最近では、個人事業主が節税や信用力の向上を目的として、マイクロ法人を設立するケースが増加しています。特に、必要な経費を最小限に抑えつつ法人化できる点が、マイクロ法人の大きな魅力です。
マイクロ法人は、一般的な中小企業と比べて設立手続きがシンプルで、運営にかかる経費も抑えやすいため、個人事業主にとっては法人化の第一歩として選ばれやすい存在です。
マイクロ法人と一般的な会社との違い
マイクロ法人と一般的な会社の最大の違いは、その小規模さにあります。マイクロ法人では、経営者1人で業務を担い、資本金も最低限で済むことが多く、経費も必要最小限で抑えられます。
また、マイクロ法人の組織体制は非常にシンプルで、意思決定も迅速に行える点が特徴です。一般的な中小企業は、複数の従業員を雇用し、資本金や人件費など経費負担も大きくなりがちですが、マイクロ法人であれば経費管理もしやすく、スリムな経営が可能です。
マイクロ法人のメリットや経費にできるものに関するおすすめ記事
このように、マイクロ法人は柔軟性とコストパフォーマンスの両面で優れており、個人規模のビジネスにはぴったりです。では、どのようなケースでマイクロ法人の設立が向いているのでしょうか。以下に、マイクロ法人が適している主な状況を紹介します。
マイクロ法人に向いているケース①:事業が小規模な場合
事業規模が小さく、必要経費も限定的で済む場合は、マイクロ法人が最適です。個人事業主からマイクロ法人に移行する際も、業務内容や支出の規模が変わらないため、設立・運営コストを抑えながらスムーズに法人化できます。
マイクロ法人に向いているケース②:個人事業主として一定の利益が出ている場合
個人事業主として年間の利益が増えてくると、所得税の負担が大きくなる傾向があります。
SoVa税理士ガイド編集部
そこで、マイクロ法人を設立して法人税を活用することで、経費を適切に計上しながら節税効果を高めることが可能です。
さらに、マイクロ法人として経費を明確に管理できるため、事業運営の透明性も向上します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
マイクロ法人に向いているケース③:将来的に事業を拡大したい場合
将来的に規模を拡大したいと考えている個人事業主にとっても、マイクロ法人は有力な選択肢です。初期段階では最低限の経費で運営をスタートし、実績を積んだ後に、必要に応じて従業員の雇用や資本金の増資といったステップに移行できます。
マイクロ法人として段階的に成長を目指すことで、リスクを抑えながら法人としての信用力も高めていくことができるのです。
マイクロ法人を設立するメリット

マイクロ法人を設立するメリットは、以下の3つが挙げられます。
マイクロ法人を設立するメリット①:社会保険料を大幅に節約できる
個人事業主の場合、原則として国民健康保険への加入が必要ですが、マイクロ法人を設立して会社役員(=法人の従業員)となることで、健康保険や厚生年金への加入が可能になります。条件を満たせば、国民健康保険料の半額以下に抑えられるケースもあり、マイクロ法人としての社会保険の負担は非常に効率的です。
SoVa税理士ガイド編集部
マイクロ法人のメリットや経費にできるものについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
このように、マイクロ法人の設立によって社会保険料という経費を大きく削減できるのは、個人事業主にはない大きなメリットです。
マイクロ法人を設立するメリット②:所得税・住民税を節税できる
マイクロ法人を活用することで、個人事業主時代にかかっていた所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。売上をすべて個人の所得として扱うのではなく、マイクロ法人の売上として法人側で受け取り、役員報酬として分配する形にすることで、給与所得控除を活用でき、所得税・住民税の節税につながります。
さらに、法人としての経費処理が可能になるため、節税対策の幅も広がります。これにより、税負担を抑えながら手元資金を残すことができ、より健全な経営が実現できます。
マイクロ法人を設立するメリット③:経費として損金算入できる範囲が広がる
マイクロ法人では、個人事業主に比べて経費として認められる支出の幅が格段に広がります。
マイクロ法人はここがポイント!

たとえば、個人では経費にできないケースが多い生命保険料や家賃、自動車保険料、出張手当なども、マイクロ法人では損金(=経費)として計上可能です。
特に保険料に関しては、個人では控除額に上限がありますが、マイクロ法人として法人契約にすれば、掛金の金額に応じて全額を損金扱いにできることもあります。このように、経費を戦略的に使えるのがマイクロ法人の大きな強みです。
マイクロ法人が経費にできるもの

ここでは、マイクロ法人として事業を行う場合に、どのような支出が経費として計上できるのかを具体的に解説します。とくに個人事業主からマイクロ法人へ移行する方にとって、経費の扱いがどう変わるのかを理解することは極めて重要です。
マイクロ法人を設立した後に発生する支出は、大きく分けて人件費(役員報酬)とその他の経費に分類されます。以下はマイクロ法人における代表的な経費の一例ですが、事業内容によって異なるため、実態に応じて判断することが必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
役員報酬
マイクロ法人では、代表者である一人社長が自らに役員報酬を支払う形になります。
SoVa税理士ガイド編集部
この役員報酬はマイクロ法人の経費として処理できるため、法人税の節税効果が期待できます。
マイクロ法人の税理士に依頼に関する参考記事:「資金調達を税理士に依頼するメリットやおすすめポイントについて詳細に解説!」
また、報酬は給与として扱われるため、給与所得控除も適用され、所得税・住民税・社会保険料の節約にも貢献します。
PC・ソフトウェア関連費用(事業用経費)
マイクロ法人で業務に使用するPCやプリンター、業務用ソフトウェアなどの購入費用も経費として計上可能です。一定金額を超える場合は減価償却の対象となりますが、それでもマイクロ法人の損金として認められる範囲が広いため、事業用資産への投資がしやすくなります。
消耗品費(文房具・コピー用紙など)
文房具やコピー用紙、封筒、郵送費など日常的に使用する消耗品もマイクロ法人の経費として処理可能です。こうした細かい支出も積み重なれば大きな節税効果につながります。
マイクロ法人のメリットや経費にできるものに関するおすすめ記事:マイクロ法人とは?個人事業主より節税できる法人化のメリットと注意点、設立の手順

合わせて読みたい「会計ソフト比較一覧」に関するおすすめ記事
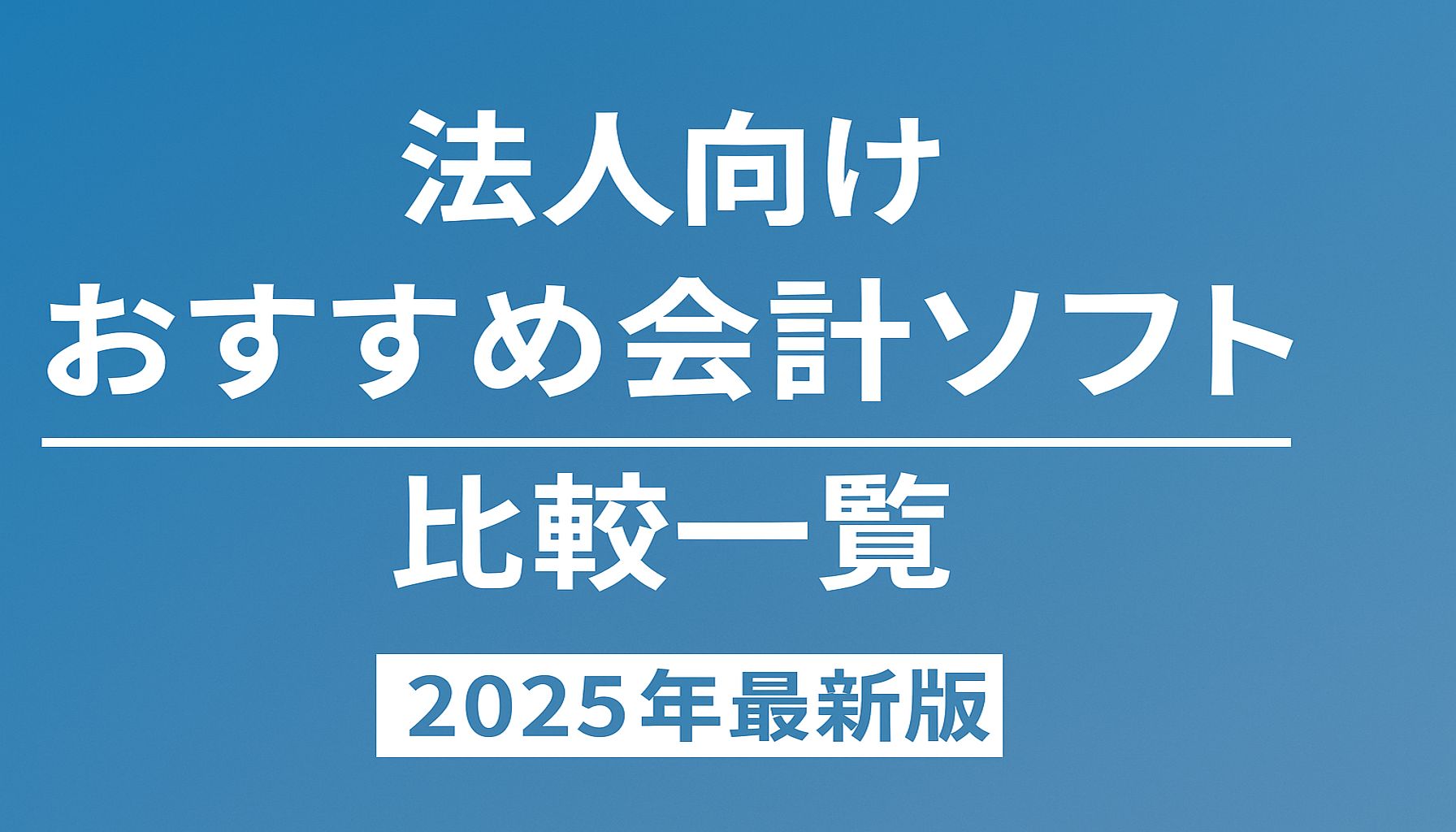
法人のおすすめ会計ソフト比較一覧【2025年最新版】
通信費(インターネット・SaaSなど)
マイクロ法人での通信手段として必要な電話代、インターネット回線、クラウドサービス、サーバー利用料なども経費化の対象となります。特にSaaSやWebツールを使った業務が多いマイクロ法人にとって、通信費は日常的かつ必要不可欠な経費項目です。
広告宣伝費(SNS運用・機材費など)
SNSやWeb広告を活用した集客活動に関する支出も、マイクロ法人では広告宣伝費として経費計上できます。SNS運用に必要なカメラや照明機材なども含めて、広く対応可能です。個人事業主では私的利用との区別が難しいケースでも、マイクロ法人であれば明確に事業経費とできるのが利点です。
マイクロ法人の関連記事:「マイクロ法人は家賃も経費にできる?経費計上する方法や注意点を解説!」
オフィス関連経費(自宅兼オフィスも対応可能)
マイクロ法人が借りるオフィスの賃料、水道光熱費、修繕費などはすべて経費化可能です。また、自宅の一部をオフィスとして使用する場合でも、床面積や使用割合をもとにマイクロ法人の経費として処理することができます。

合わせて読みたい「マイクロ法人の社宅」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は社宅を経費にできる?社宅制度を導入する方法や注意点を解説!
この場合、役員と法人との間に賃貸借契約等の契約関係を明確にする必要があります。
- 役員が法人に自宅を貸す形(社宅扱い)
- 法人が役員に家賃相当額を支払う形
マイクロ法人のメリットや経費にできるものに関するおすすめ記事
いずれもマイクロ法人ならではの経費処理の幅広さを活かす方法です。
交通費・宿泊費(出張・訪問対応)
出張時の電車・バス・タクシー代や宿泊費も、マイクロ法人の経費として計上できます。取引先との打ち合わせや視察などでの移動費は、記録を残すことでしっかりと損金扱いが可能です。
接待交際費・会議費(事業活動の一環)
マイクロ法人でも取引先との関係構築にかかる接待交際費や、会議・打ち合わせにかかる費用(会議費)を経費化することができます。ただし、接待交際費には法人規模に応じた損金算入の上限があるため、マイクロ法人としては金額管理を徹底する必要があります。
マイクロ法人が経費にできるか悩むもの

マイクロ法人を経営していると、「これはマイクロ法人の経費として処理できるのか?」と迷う場面は日常的に発生します。とくに、一人社長や経理を兼任するケースの多いマイクロ法人では、支出がすべて経費になるわけではないため、判断基準を明確に持つことが重要です。
マイクロ法人において支出が経費(損金)として認められるかどうかのカギは、「損金算入の可否」です。
つまり、
- 損金に算入できるものは、マイクロ法人の経費として処理可能
- 損金に算入できないものは、経費として認められない
というのが原則となります。
SoVa税理士ガイド編集部
マイクロ法人のメリットや経費にできるものについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
実際には、多くの支出がマイクロ法人の経費にできますが、判断が分かれやすい項目もあるため注意が必要です。以下では、マイクロ法人の経費にできるか迷いやすい代表的な6つのケースを紹介し、判断のポイントを解説します。
マイクロ法人の経費にできるか迷いやすい例①:役員報酬・賞与
マイクロ法人であっても、役員報酬や役員賞与は要件を満たさなければ経費にできるものとは認められません。たとえば役員報酬は、毎月一定額を支給する「定期同額給与」であり、かつ会計年度開始から3カ月以内に設定されていなければ、マイクロ法人の経費とはならず、損金不算入とされます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
賞与も「事前確定届出給与」として税務署に届出を行い、届出通りに支給した場合に限り、経費処理が認められます。マイクロ法人での役員報酬設定は、節税効果や経費戦略に大きく関わるポイントです。
マイクロ法人の経費にできるか迷いやすい例②:交際費
マイクロ法人でも、取引先との関係維持やビジネス促進を目的とした飲食費や贈答品費用は交際費として経費にできるものです。ただし、その使用目的や金額によって制限があります。
たとえば1人あたり5,000円以下の飲食費は「社外交際費」として全額経費に計上可能ですが、これを超えるとマイクロ法人の規模や資本金額に応じた上限が設けられます。
マイクロ法人であっても、交際費の扱いは税務上のチェックポイントになりやすいため、支出の記録と明確な使用目的の管理が必要です。
マイクロ法人の経費にできるか迷いやすい例③:寄付金
マイクロ法人が行う寄付も、すべてが経費にできるとは限りません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
一般的な任意団体への寄付やイベント協賛金は、損金算入限度額内でのみ経費計上が可能です。
限度額は「資本金等の額 × 1/400 + 所得金額 × 1/40」という計算式で算出され、マイクロ法人であっても例外ではありません。
一方、国や地方自治体への寄付金は、マイクロ法人の支出であっても全額損金として認められるため、確実に経費にできます。寄付の種類と対象により、経費か否かを正しく判断しましょう。

合わせて読みたい「出張費を経費」に関するおすすめ記事

出張費はどこまでが経費になる?経費処理の仕訳や相場感を解説!
マイクロ法人の経費にできるか迷いやすい例④:同族会社と経営者の取引
マイクロ法人が同族会社である場合、経営者個人や親族との取引は税務上特に厳しい目で見られます。たとえば、社長が自宅を法人に貸し出し、相場を超える家賃を受け取っている場合は、経費にできるものとは認められません。
マイクロ法人の支出が経費として認められるには、第三者との取引と同様の妥当性・合理性があることが前提です。とくに同族関係では、「経費にできるかどうか」の線引きに慎重な判断が求められます。
マイクロ法人の経費にできるか迷いやすい例⑤:罰金・延滞税
マイクロ法人が支払う罰金や延滞税などのペナルティは、原則として経費にできるものではありません。たとえば法人税や消費税の延滞による延滞税や加算税は、法人の過失に対する制裁とされるため、損金不算入です。
マイクロ法人のメリットや経費にできるものに関するおすすめ記事
ただし、社会保険料の延滞金など、業務に直接起因する一部の支出については経費として扱われる場合もあります。一見経費に見えても、マイクロ法人の事業活動と直接関係があるかどうかが判断基準になります。
マイクロ法人の経費にできるか迷いやすい例⑥:債務が確定していない引当金
マイクロ法人で将来の支出を見越して設定する賞与引当金や退職給付引当金などの引当金は、債務が確定していない段階では経費にできるものではありません。
引当金を経費として計上できるのは、金額と支払時期が法的・経済的に確定している場合に限られます。マイクロ法人の会計においても、「今期中に確定した支出かどうか」が経費として認められるかどうかの重要な基準です。
まとめ

マイクロ法人の設立には、経費の柔軟な活用や節税、社会的信用の向上など多くのメリットがあります。とくに、個人事業主時代には経費にできなかった支出を、マイクロ法人では合法的に経費として処理できる可能性が広がる点は見逃せません。
ただし、すべての支出が自動的にマイクロ法人の経費として認められるわけではなく、税務上のルールに基づいた正しい判断が必要です。経費にできるかどうか悩むケースも多いため、定期的に情報を確認し、必要であれば専門家に相談することも検討しましょう。
マイクロ法人を最大限に活用し、経費戦略を味方につけることで、より安定した事業運営と賢い節税が実現できます。
マイクロ法人のメリットや経費にできるものに関するおすすめ記事:法人で経費にできるもの一覧まとめ!経費にできるものとできないものを紹介
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい!