会社設立後にやることとは?手続き方法を解説!
カテゴリー:
公開日:2025年8月
更新日:2026年1月24日
会社を設立後には、税務署や年金事務所、労働基準監督署などへの各種届出や、法人口座の開設といった数多くのやることが発生します。会社設立後にやることは、必須で行わなければならないものから、必要に応じて行うもの、任意で対応できるものまで幅広く存在します。設立後の手続きを正しく理解しておくことで、会社の運営をスムーズにスタートでき、将来的なトラブルも防ぐことができます。
この記事では、会社設立後に必要となるやることを一覧で整理し、それぞれの手続き方法をわかりやすく解説します。
目次
- 法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート - 会社設立後にやること一覧
- 会社設立後に必須でやること
- 会社設立後に必要に応じてやること
- 会社設立後に必要に応じてやること①:税務署へ消費税関連の届出を提出する
- 会社設立後に必要に応じてやること②:年金事務所へ健康保険の適用除外承認申請を提出する
- 会社設立後に必要に応じてやること③:年金事務所へ健康保険被扶養者(異動)届を提出する
- 会社設立後に必要に応じてやること④:労働基準監督署へ適用事業報告書を提出する
- 会社設立後に必要に応じてやること⑤:労働基準監督署へ就業規則を提出する
- 会社設立後に必要に応じてやること⑥:労働保険の保険関係成立届を提出する
- 会社設立後に必要に応じてやること⑦:労働保険概算保険料申告書を提出する
- 会社設立後に必要に応じてやること⑧:ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出する
- 会社設立後に必要に応じてやること⑨:ハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出する
- 会社設立後に任意でやること
- 会社設立後にやることで悩んだときは?
- まとめ
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
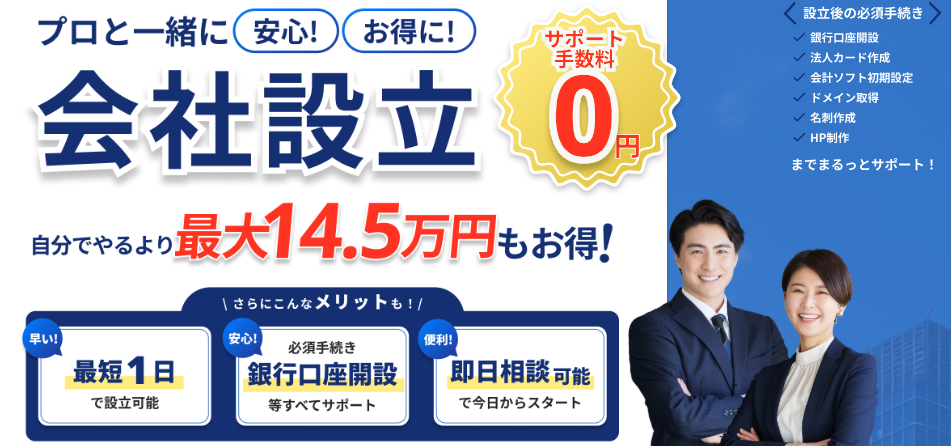
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
会社設立後にやること一覧

会社設立後には、税務署・都道府県税事務所・市町村役場・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク・金融機関など、さまざまな機関への手続きが必要です。会社を設立した直後は何を優先すべきか混乱しやすいため、会社設立後にやることを体系的に把握しておくことが大切です。
会社設立後のやることには、必須の手続きと任意の手続きがあります。
SoVa税理士ガイド編集部
特に法人税・消費税・社会保険・労働保険・雇用保険に関する手続きは期限が決められており、会社として確実に対応しなければなりません。
また、法人口座開設などは任意ですが、会社運営のためには早めに行っておくのが望ましいでしょう。
会社設立後のやること一覧表
| 提出先 | 会社設立後に必要なやること(書類名) | 添付書類 | 提出要否 | 提出期限 |
|---|---|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 定款の写しなど | 必須 | 設立日から2ヶ月以内 |
| 税務署 | 青色申告の承認申請書 | 特になし | 必要に応じて | 設立日から3ヶ月以内 or 最初の事業年度終了日の前日 |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 特になし | 必要に応じて | 開設から1ヶ月以内 |
| 税務署 | 源泉所得税の納期の特例承認申請書 | 特になし | 必要に応じて | 特になし(提出後、原則翌月から適用) |
| 税務署 | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 特になし | 必要に応じて | 特になし |
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 定款写し・登記事項証明書 | 必須 | 都道府県により異なる(例:東京23区は15日以内) |
| 市町村役場 | 法人設立届出書 | 定款写し・登記事項証明書 | 必須 | 市町村により異なる(例:東京23区は不要) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 登記簿謄本・法人番号通知書など | 必須 | 設立から5日以内 |
| 年金事務所 | 被保険者資格取得届 | 原則なし | 必要に応じて | 資格取得から5日以内 |
| 年金事務所 | 被扶養者(異動)届 | 戸籍謄本・収入証明書など | 必要に応じて | 扶養者がいる場合、取得日から5日以内 |
| 労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 登記簿謄本 | 必要に応じて | 従業員を雇った翌日から10日以内 |
| 労働基準監督署 | 労働保険概算保険料申告書 | 特になし | 必要に応じて | 従業員を雇った日から50日以内 |
| 労働基準監督署 | 就業規則(変更)届 | 就業規則本文・意見書 | 必要に応じて | 常時10人以上雇用した場合、速やかに |
| 労働基準監督署 | 適用事業報告書 | 特になし | 必要に応じて | 従業員雇用時に遅滞なく提出 |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 登記事項証明書・雇用契約書など | 必要に応じて | 適用事業所となった翌日から10日以内 |
| ハローワーク | 雇用保険被保険者資格届 | 特になし | 必要に応じて | 従業員雇用の翌日から10日以内 |
| 金融機関 | 法人口座開設(各行指定書類) | 定款・登記事項証明書・印鑑証明書・代表者身分証など | 任意 | 随時(会社運営に必須 |
SoVa会社設立編集部
会社設立の際に必要な印鑑については以下の記事をご覧ください。
「 合同会社を設立するのに必要な印鑑の種類は?印鑑を準備する際の注意点も解説! 」
会社設立後にやることに関するおすすめ記事
会社設立後に必須でやること

会社を設立後に必ずやることとして、税務署や都道府県税事務所、市町村役場、さらに年金事務所へ複数の書類を提出する必要があります。期限が短いものも多いため、会社設立後は計画的に進めることが重要です。
会社設立後に必須でやること①:税務署へ法人設立届出書を提出する
「法人設立届出書」は、会社を設立した事実と会社の概要を所轄税務署に知らせるための書類です。会社の法人番号は登記完了後に国税庁から通知されますが、不明な場合は国税庁の「法人番号公表サイト」で確認可能です。提出期限は会社設立後2か月以内となっています。
SoVa税理士ガイド編集部
会社設立後にやることについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:会社設立後(1期目)にやること一覧
会社設立後に必須でやること②:税務署へ給与支払事務所等の開設届を提出する
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、会社が給与や賞与から源泉徴収を行うために必要な書類です。従業員がいない場合でも、会社から役員報酬を支払うため、設立後1か月以内に必ず提出しなければなりません。最寄りの税務署は国税庁の「税務署所在地検索」で調べられます。
会社設立後に必須でやること③:都道府県税事務所・市町村役場へ法人設立届出書を提出する
会社設立後は、都道府県税事務所と市町村役場の両方に「法人設立届出書」を提出する必要があります。ただし、東京23区の場合は市町村への提出は不要で、都税事務所のみで完結します。
会社設立後にやることで気をつけておきたい注意点

提出期限は自治体によって異なり、東京都は事業開始から15日以内、神奈川県は2か月以内と差があるため注意が必要です。
会社設立後に必須でやること④:年金事務所へ健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出する
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、会社が社会保険に初めて加入する際に提出するものです。登記事項証明書や法人番号通知書なども添付が必要で、提出期限は会社設立後5日以内と非常に短いため、登記が完了したら速やかに対応する必要があります。
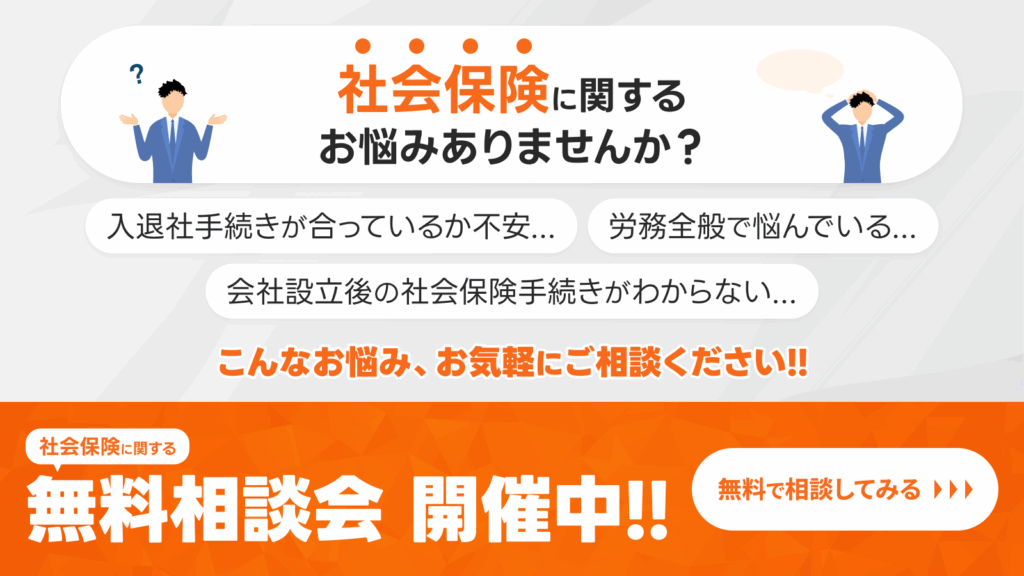
会社設立後に必須でやること⑤:年金事務所へ被保険者資格取得届を提出する
「被保険者資格取得届」は、従業員を雇用した際や、役員報酬が発生する場合に提出する書類です。役員も社会保険に加入するため、1人会社の場合でも必要となります。健康保険・厚生年金保険新規適用届と併せて、会社設立後に役員報酬が決まった段階で必ず提出しましょう。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
会社設立後に必要に応じてやること

会社設立後には必須の手続きに加え、会社や従業員の状況によって必要に応じて行うやることもあります。ここでは、会社設立後に該当する場合に提出が必要となる主な書類を整理します。
会社設立後に必要に応じてやること①:税務署へ消費税関連の届出を提出する
「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」は、会社設立後に資本金や出資金が1,000万円以上ある法人の場合に必要です。なお、法人設立届出書に記載して提出していれば、改めて提出しなくてもよい場合があります。
会社設立の関連記事:「会社の作り方を徹底解説!必要な手続きと費用について」
会社設立後に必要に応じてやること②:年金事務所へ健康保険の適用除外承認申請を提出する
国民健康保険組合に加入する従業員を雇用する場合、会社設立後に「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を提出します。
会社設立後にやることで気をつけておきたい注意点

ただし、労働時間や日数が少ない非常勤従業員で要件を満たさない場合には提出不要です。
会社設立後に必要に応じてやること③:年金事務所へ健康保険被扶養者(異動)届を提出する
役員や従業員に扶養者がいる場合、会社設立後5日以内に「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出します。被扶養者の追加や削除、氏名変更などの異動が生じたときも、事実発生から5日以内の提出が必要です。

合わせて読みたい「法人番号と会社法人等番号の違い」に関するおすすめ記事
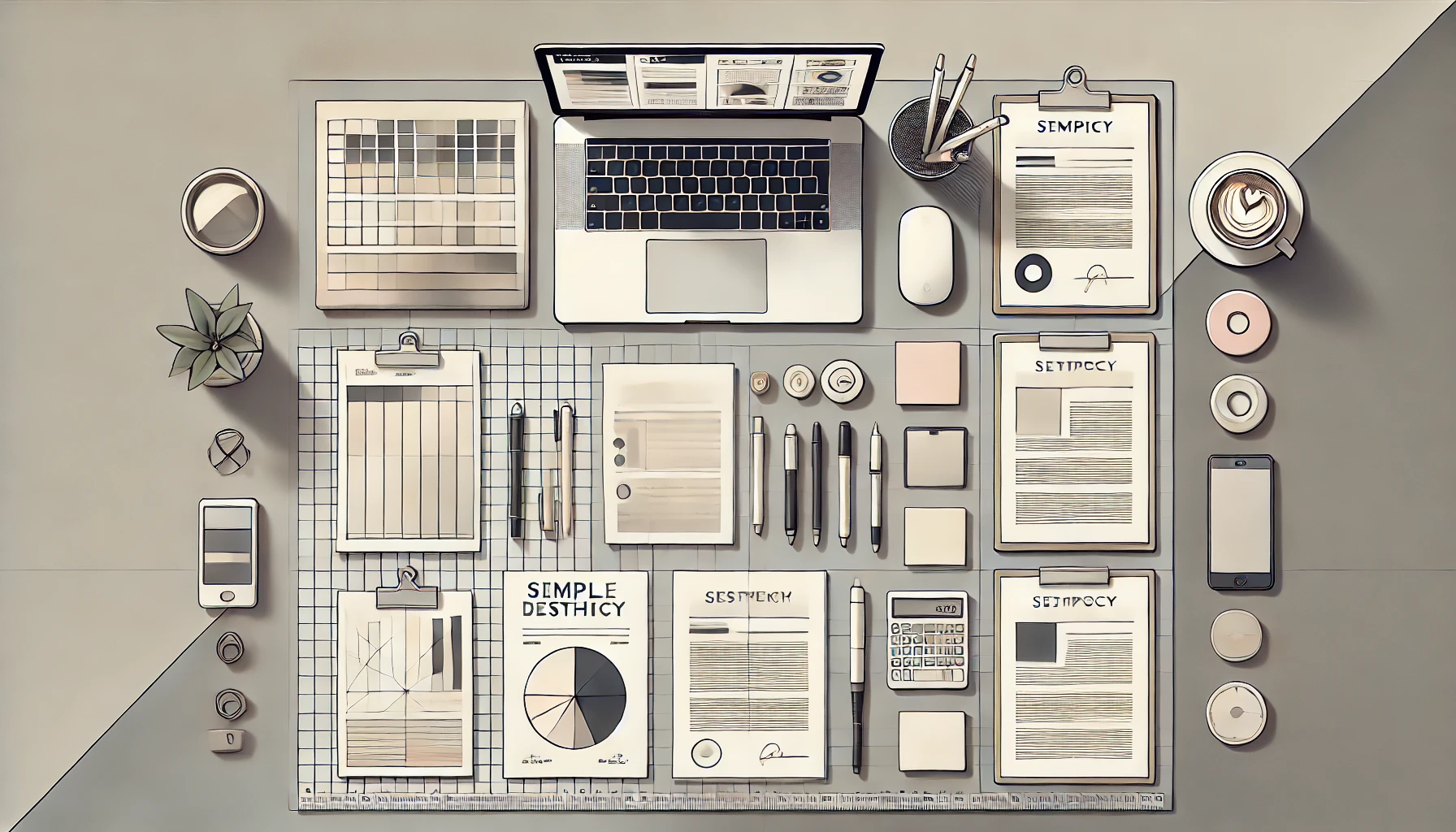
法人番号と会社法人等番号の違いとは?調べ方や使い道も紹介!
会社設立後に必要に応じてやること④:労働基準監督署へ適用事業報告書を提出する
会社が従業員を1人でも雇った場合、設立後に「適用事業報告書」を労働基準監督署に提出する必要があります。ただし、同居親族のみで会社を運営している場合は不要です。
会社設立後に必要に応じてやること⑤:労働基準監督署へ就業規則を提出する
常時10人以上の従業員を雇用する会社は、設立後に「就業規則」を作成し「就業規則(変更)届」を提出しなければなりません。すでに10人以上を雇って設立した場合は設立時点での提出が必須です。
会社設立後にやることに関するおすすめ記事
会社設立後に必要に応じてやること⑥:労働保険の保険関係成立届を提出する
会社が従業員を雇用した場合、設立後に「労働保険 保険関係成立届」を提出します。一元適用事業は労働基準監督署のみ、二元適用事業は労基署とハローワークそれぞれへの提出が必要です。
会社設立後に必要に応じてやること⑦:労働保険概算保険料申告書を提出する
労働保険料は給与の見込み額に基づき概算で前払いする仕組みのため、会社設立後に「労働保険概算保険料申告書」を提出します。年度末には精算も行う必要があります。
会社設立後にやることに関するおすすめ記事:会社設立後にやることは?やることリスト・提出書類・手続き期限まとめ
会社設立後に必要に応じてやること⑧:ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出する
会社が従業員を初めて雇用した場合、設立後10日以内に「雇用保険 適用事業所設置届」を提出します。農林水産業の一部を除き、原則すべての業種が対象です。
会社設立後に必要に応じてやること⑨:ハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出する
週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある従業員がいる場合、設立後に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。提出期限は雇い入れた月の翌月10日までですが、基本的には「適用事業所設置届」と同時に提出します。
会社設立後に任意でやること

会社設立後には必須の提出書類に加えて、任意で行う手続きも存在します。任意とはいえ、会社としてやることを正しく選ばないと節税のチャンスを逃す可能性があります。会社設立後に検討すべきやることを確認しておきましょう。
会社設立後に任意でやること①:税務署へ源泉所得税の納期特例を申請する
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、会社設立後に発生する源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。給与支給人数が10人未満の会社であれば利用可能で、提出後は毎月の納付手続きの負担を大幅に減らせます。
会社設立後に任意でやること②:税務署へ適格請求書発行事業者の登録をする
インボイス制度に対応するには、会社設立後に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
会社設立後にやることはここがポイント!

課税事業者を選択しなくても、2029年9月30日までは特例で登録のみで対応できるため、会社として取引先の要望に応えるためにも早めにやることがおすすめです。
会社設立後に任意でやること③:消費税簡易課税制度を選択する
会社設立後に課税事業者となり、売上が一定基準以下の会社は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できます。簡易課税を選ぶと事務作業の負担を軽減できるため、小規模会社にとっては有効なやることの一つです。
会社設立後に任意でやること④:青色申告の承認申請を行う
法人税の申告を有利に進めたい会社は、設立後に「青色申告の承認申請書」を提出すべきです。青色申告では欠損金の繰越控除など、会社経営に役立つ多くの節税メリットが受けられます。設立日から3か月以内か、第1期事業年度終了日のいずれか早い日までに提出する必要があります。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
会社設立後に任意でやること⑤:棚卸資産の評価方法を選んで届け出る
「棚卸資産の評価方法の届出書」は、会社設立後に在庫や仕入商品をどう評価するかを選ぶ書類です。任意のやることですが、提出しない場合は自動的に「最終仕入原価法」が適用されてしまうため、会社の経理方針に応じて判断すべきです。
SoVa税理士ガイド編集部
会社設立後にやることについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
会社設立後に任意でやること⑥:減価償却資産の償却方法を届け出る
会社で資産を取得した場合、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで、法定方法以外の償却方法を選べます。設立後に行う任意のやることですが、資産計上の仕方に影響するため、会社の資金計画に合わせて選択しましょう。
会社設立後に任意でやること⑦:金融機関で新規届出書を提出して法人口座を開設する
会社を設立後に事業を進めるには、金融機関で法人口座を開設することがほぼ必須です。各金融機関で必要な「新規届出書」のほか、定款や登記事項証明書、印鑑証明書なども求められます。任意のやることではありますが、会社運営の信頼性向上や経理の透明化のために欠かせません。
会社設立後にやることで悩んだときは?

会社設立後には、さまざまな届出書類の準備や、提出期限が定められている書類の対応など、会社としてやることが数多くあります。会社設立後に事業を円滑に開始するためには、必要な手続きや書類を洗い出し、優先順位をつけて早めに準備を進めることが重要です。会社の設立後は、単に事業を始めるだけでなく、会社運営に必要な環境を整えるやることも多いため、計画的な対応が求められます。
会社設立後の手続きや会社経営に関して不明点がある場合には、専門家に相談することも検討しましょう。
SoVa税理士ガイド編集部
税務関連のやることは税理士、社会保険や労務関連のやることは社会保険労務士、行政への書類提出などは行政書士と、会社設立後のやることの内容によって相談すべき専門家が異なります。
【専門家ごとの仕事内容】
税理士
- 税務書類の作成代行
- 税務に関する相談
- 会社経営の相談
- 会計処理のサポート
- 法人税の申告代行 など
社会保険労務士
- 就業規則の作成・変更の代行
- 給与計算事務
- 助成金の相談や申請手続きの代行
- 労務管理や社会保険・労働保険に関する相談 など
行政書士
- 各種許認可申請の手続き
- 知的財産権に関する手続き
- 会社経営の相談
- 会社設立代行(定款作成など) など
会社設立後にやることに関するおすすめ記事
会社設立後、事業を開始した後も、従業員の雇用や主業務以外の作業により、さまざまな届出や書類作成といったやることが発生します。業務内容によっては専門的な知識が求められるため、会社設立後のやることを一人でこなすのが難しい場合には、専門家への依頼を前向きに検討しましょう。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
まとめ

会社設立後には、必須のやることに加え、会社の状況に応じて必要になるやることや、任意で行えるやることがあります。どの手続きも会社経営を円滑に進めるために重要であり、期日を守って正しく対応することが求められます。
会社設立後のやることに不安がある場合は、税理士や社会保険労務士など専門家に相談するのも有効です。会社を設立後に必要なやることをしっかり把握して対応することで、安心して事業を進めることができるでしょう。
会社設立後にやることに関するおすすめ記事:【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!