年末調整とは?受けられる控除や目的についても解説!
カテゴリー:
公開日:2024年6月
更新日:2025年11月26日
年末が近づくと、多くの会社で行われるのが「年末調整」です。聞いたことはあるけれど、具体的に何をするものなのか、どんな控除が受けられるのかが分からないという方も多いのではないでしょうか?年末調整は、給与から引かれる所得税を正しく計算し、過不足を調整するための手続きで、サラリーマンや会社員にとって欠かせない重要な仕組みです。
この記事では、年末調整の目的や仕組み、受けられる控除の種類について分かりやすく解説します。年末調整の重要性を理解し、最大限に活用するためのポイントをぜひチェックしてみてください!
補助金や助成金、節税アドバイス・給与計算・役所手続き・記帳業務をまとめてSoVaに依頼!!
会計事務所SoVaでは、給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。補助金・助成金を活用したいと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
年末調整とは

年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収で天引きされた所得税の過不足を調整する手続きのことで、毎年行われます。年末調整により、所得税を納めすぎた場合は還付され、不足があれば追加で徴収されます。この手続きを行う理由は、源泉徴収で天引きされる所得税額が概算であるためです。
「年末調整」編集部
年末調整を理解する際には国税庁のこちらのサイトも是非参考にしてください。
基本的に会社は、従業員に支払う金額から所得税を計算し、その分を給与から差し引いて国に納税する源泉徴収を毎月行っていますが、その時点では1年間の収入や控除額が確定していません。そこで、年末に1年分の収入から控除額を差し引いた所得が確定した時点で、正しい所得税額を算出し、過不足なく納税するために年末調整が行われます。
おすすめ記事:年末調整とは?確定申告との違いや必要書類の書き方をわかりやすく解説
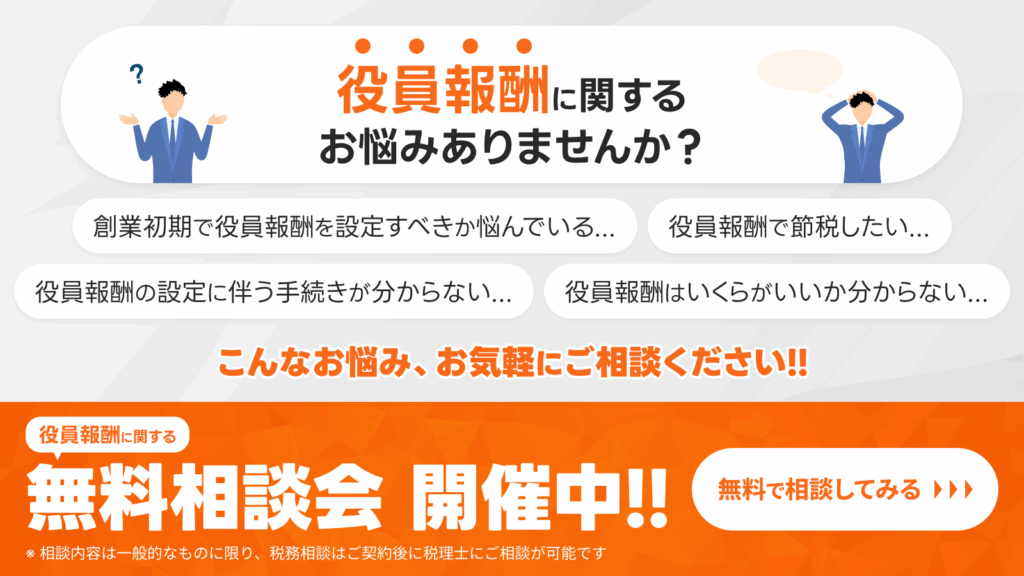
「年末調整の代行」編集部
年末調整は税理士の独占業務とされています。
それは年末調整が、毎月の給与から源泉徴収されてきた所得税の総額と、年末に1年間の正確な所得税額を算出して差額を精算する税務手続きであるためです。税金に関わる業務は、原則として税理士の業務範囲とされていることが、その理由とされています。
参考記事:「社労士が年末調整を行うのは違反?社労士と税理士の業務範囲を解説!」
おすすめ参考記事:年末調整を社労士に依頼
年末調整の詳しいやり方は国税庁の「年末調整のやり方」で解説されていますので、参考にしながら年末調整を行いましょう。
給与計算・労務手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
年末調整と確定申告との違い
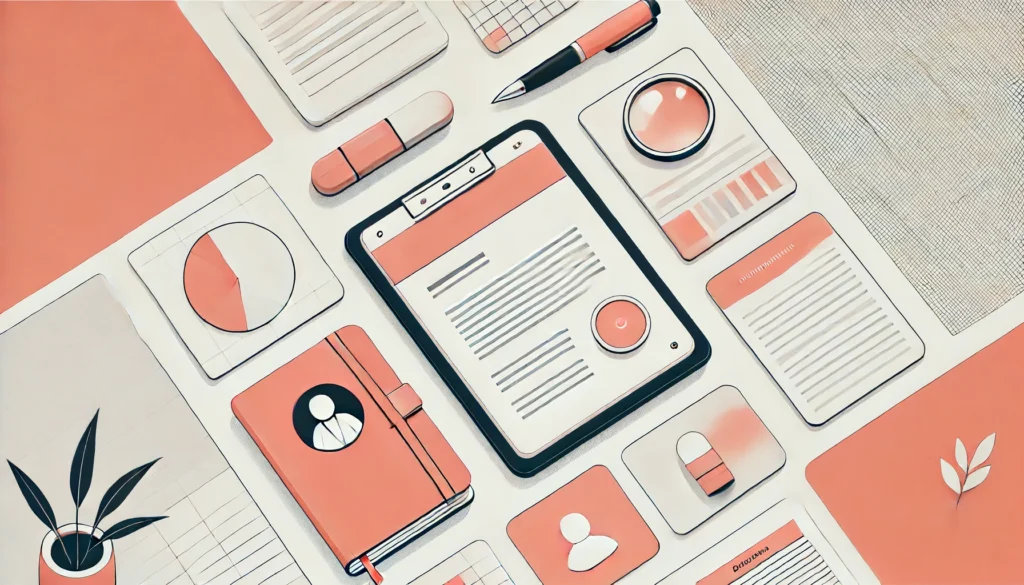
原則として、企業に勤めている場合は年末調整で所得税の過不足を調整しますが、企業に勤めていない自営業やフリーランスの人は、1年間の所得税額を確定するために確定申告を行います。確定申告は毎年2月16日から3月15日に行われ、納税者本人が1年間に得た収入や控除額を計算して申告します。
| 確定申告 | 年末調整 | |
|---|---|---|
| 目的 | 所得税を確定させ、還付または徴収を受ける | 源泉徴収税と所得税の差分を精算する |
| 時期 | 翌年の2月16日から3月15日に確定申告書を提出 | 会社の一般的な作業期間は11月から翌年1月 ※翌年1月31日までに会社は申告書等の必要書類を税務署に提出 |
| 実施者 | 個人 | 会社 |
| 受けられる控除 | 基礎控除・扶養控除・配偶者(特別)控除・ひとり親控除 ・寡婦控除・勤労学生控除・社会保険料控除・生命保険料控除 ・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・住宅ローン控除 【確定申告のみ】 雑損控除・医療費控除・寄附金控除 |
基礎控除・扶養控除・配偶者(特別)控除・ひとり親控除 ・寡婦控除・勤労学生控除・社会保険料控除・生命保険料控除 ・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・住宅ローン控除など |
おすすめ記事
控除の意味と年末調整の目的

年末調整の書類を記入する際に、多くの人が戸惑うのが「所得の記入欄」だと思います。 「収入と所得って同じだと思っていたけど、違うの?」と疑問に感じたことはありませんか?
実際、「収入」と「所得」は異なります。具体的には、収入から必要経費を差し引いたものが所得となります。収入は、サラリーマンやパート、アルバイトの方にとっては税込年収に相当します。 「収入」から給与所得控除を差し引いた後の「所得」の金額に対して、一定の税率をかけて1年分の所得税が計算されます。
おすすめ参考記事:給与所得と給与収入の違いとは?年末調整に関わる知識も解説!
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税込年収-給与所得控除=所得
所得×税率=所得税
「所得」の金額を減らすことができれば、その分適用される税率が低くなり、支払う税金も少なくなります。そこで「所得」の金額を減らす方法として様々な控除が存在します。年末調整では、個人や家族構成に応じて適用できる控除を申請することができます。代表的な控除には、基礎控除や配偶者控除などがあります。
毎月のお給料から天引きされている所得税は、あくまでも仮の税額です。 「所得」から「所得控除」を差し引くことで、1年間を通じて給与から天引きされた所得税が過払いである場合、本来納税すべき所得税額を再計算します。過払い分の所得税がある場合は還付を受けることができます。
-

SoVa税理士ガイド編集部
つまりは、年末調整の目的は、年末に本来納めるべき税額に調整し直すことです。
おすすめ記事:年末調整と確定申告の違いは?対象者・時期・控除について分かりやすく解説
年末調整の対象者

年末調整の対象になる人
年末調整の対象は、会社勤めで源泉徴収があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。主に、年間を通じて勤務している人や年の途中から年末まで勤務している人が対象で、正社員、契約社員、パート、アルバイトも含まれます。転職した場合は、転職先の会社で年末調整を行い、前職の源泉徴収票を提出する必要があります。
年末調整の対象外になる人
年末調整の対象外となるのは、会社勤めではない人や、以下の条件に該当する場合です。これらの人は自分で確定申告が必要です。
・自営業やフリーランスなどの個人事業主
・給与所得が2000万円を超える場合
・副業などで2カ所以上から給与の支払いを受けている場合
・災害減免法の規定に該当する人
・継続して同一の雇用主に雇用されない人
このように、年末調整の手続きと控除額の確認を行うことで、正確な所得税額の納税が可能となります。
おすすめ記事:年末調整と確定申告の違いは?対象者や控除できるものを解説

合わせて読みたい「扶養 控除」に関するおすすめ記事

扶養控除とは?年収の壁や種類についても解説!
年末調整時に受けることのできる控除

年末調整には、所得から差し引くことで納税額を抑えることができる様々な所得控除があります。
社会保険料控除
社会保険料控除は、年末調整をすることで受けられるその年に支払った(または給与から差し引かれた)健康保険料や介護保険料、国民年金保険料(税)、厚生年金保険料などの社会保険料の全額が対象となる控除です。自分の社会保険料だけでなく、扶養している家族や親族の社会保険料を支払った場合も控除の対象となります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、年末調整をすることで受けられる小規模企業共済法に基づいて支払った掛金に対する控除です。金額に上限はなく、その年に支払った掛金全額が控除対象となります。適用される掛金には以下の3つがあります。
1.小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金
2.確定拠出年金法に基づく企業型年金または個人型年金の掛金
3.地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

合わせて読みたい「2024年 年末調整」に関するおすすめ記事

2024年分の年末調整の変更点とは?定額減税の対応についても分かりやすく解説!
生命保険料控除
生命保険料控除は、年末調整をすることで、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除です。これらは民間の保険会社が提供する保険契約が対象です。新契約(2012年1月1日以降)と旧契約(2011年12月31日以前)の取扱いが異なり、契約区分ごとに控除限度額が設定されています。全て合わせて最大12万円の控除を受けることができます。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円超4万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)の場合
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万5,000円超5万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万2,500円 |
| 5万円超10万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
参考サイト:『国税庁』旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
地震保険料控除
地震保険料控除は、年末調整をすることで、その年に支払った地震保険料に対して受けられる控除です。2006年の税制改正により損害保険料控除は廃止されましたが、特定の要件を満たす長期損害保険料については、地震保険料控除の対象となります。

合わせて読みたい「2025年の年末調整変更点」に関するおすすめ記事

2025年度の年末調整に変更点はある?対応ポイントを解説!
地震保険料控除の対象となる長期損害保険料の要件
・2006年12月31日までに締結した契約であること
・期返戻金などがあるもので保険期間または共済期間が10年以上であること
・2007年1月1日以後にその損害保険契約の変更をしていないもの
地震保険料控除の金額
| 区分 | 年間の支払保険料の合計別控除額 |
|---|---|
| 地震保険料 | 5万円以下の場合:支払金額の全額 5万円超の場合:一律5万円 |
| 旧長期損害保険料 | 1万円以下の場合:支払金額の全額 1万円超2万円以下の場合:支払金額×1/2+5,000円 2万円超の場合:1万5,000円 |
| 両方がある場合 | 1・2それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
参考サイト:『国税庁』No.1145 地震保険料控除
ひとり親控除
ひとり親控除は、2020年分の所得税から適用される控除で、年末調整をすることでその年の12月31日時点で婚姻していない、または配偶者の生死が不明で、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子供がいる単身者に対し、35万円の控除が適用されます。
寡婦控除
寡婦控除は、年末調整をすることで、夫と離婚または死別した女性に適用される控除で、次のいずれかに該当する場合に27万円の控除が受けられます。
勤労学生控除
勤労学生控除は、年末調整をすることで、特定の学校に在籍し、給与所得などの勤労による所得があり、合計所得金額が75万円以下である場合に27万円の控除を受けられる控除です。
障害者控除
障害者控除は、納税者本人や生計を一にする配偶者や扶養親族に障害がある場合に年末調整をすることで受けられる控除です。障害者に対しては27万円、特別障害者に対しては40万円、特別障害者が同居している場合は75万円の控除が適用されます。
配偶者控除
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が年間48万円以下である場合に年末調整をすることで適用される控除です。納税者の所得金額によって控除額が異なりますが、最大で48万円の控除が受けられます。
配偶者控除の金額
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者の場合 | 老人控除対象配偶者の場合 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万 | 48万 |
| 900万円超950万円以下 | 26万 | 32万 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万 | 16万 |
参考サイト:『国税庁』No.1191 配偶者控除
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超える場合でも段階的に控除を受けられる制度で、年末調整をすることで、配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば、納税者の所得金額に応じて最大38万円の控除が受けられます。
配偶者特別控除の金額(2020年分以降)
| 配偶者の合計所得金額/ 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
参考サイト:『国税庁』No.1195 配偶者特別控除
扶養控除
扶養控除は、年末調整をすることで、年間の合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合に受けられる控除で、扶養親族の年齢や同居の有無によって控除額が異なります。
扶養控除の金額
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上の人) | 同居老親等以外の場合:48万円 同居老親等の場合:58万円 |
参考リンク:『国税庁』No.1180 扶養控除
なお、2023年分以降について、非居住者である扶養親族の扶養控除の要件が見直されることになりました。扶養控除の要件は下記のとおりです。
2023年分以降の非居住者である扶養親族の扶養控除適用要件 扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものは扶養控除の適用ができません。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者(※1)
2.障害者
3.その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者(※2)
※1 その非居住者である扶養親族であることを証する留学ビザなど相当書類の写し及び親族関係書類を提出する必要があります。
※2 38万円以上の送金関係書類を提出する必要があります。

合わせて読みたい「一人社長の年末調整」に関するおすすめ記事

一人社長も年末調整は必要?手順や注意点を解説!
このように、扶養控除の要件が見直されることで、非居住者である扶養親族に対する扶養控除の適用範囲が明確化されます。扶養控除の対象となる扶養親族の範囲や条件に注意して、適切に扶養控除を受けることが重要です。
基礎控除
基礎控除は、年末調整をすることで一定の所得以下の人なら誰でも受けられる控除で、納税者の合計所得金額に応じて最大48万円の控除が受けられます。
基礎控除の金額
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
参考サイト:『国税庁』No.1199 基礎控除
おすすめ記事:年末調整で受けることのできる控除まとめ!各限度額も紹介
年末調整ではできない控除について
控除の手続きの中には、年末調整ではできないものもあります。これらの控除は、確定申告で手続きします。会社員や公務員は通常、年末調整で済むため、確定申告は原則不要ですが、控除のために確定申告をしたほうがお得な場合もあります。
確定申告でするべき控除1:医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えたときに受けられる所得控除です。10万円を超えた部分が所得控除できます(最高で200万円)。医療費控除は自分だけでなく、同一生計の家族の医療費と合算して10万円を超えれば利用できます。
また、健康診断や予防接種を受けている人が、薬局などで1年間に1万2,000円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合には、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制が受けられます。セルフメディケーション税制では、1万2,000円を超えた部分が所得控除できます(最高で8万8,000円)。
気をつけておきたい注意点

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか片方しか使えませんが、自分だけでなく、同一生計の家族の分もまとめて利用できます。日頃から、医療機関にかかったときの領収書や明細書をためておき、控除額が大きくなるほうを利用すればよいでしょう。
おすすめ参考記事:セルフメディケーション税制と医療費控除はどっちが得?違いを解説
確定申告でするべき控除2:住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・リフォームした際に、年末の住宅ローン残高の1%が10年間所得税から控除できる制度です(注文住宅は2021年9月、分譲住宅等は2021年11月までに契約し、2022年末までに入居すると控除期間が13年に延長)。住宅ローン控除は所得控除ではなく、税金を直接差し引く「税額控除」なので、税金を大きく減らす効果があります。住宅ローン控除の手続きは、初年度だけ確定申告が必要です。次年度からは年末調整で控除ができます。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
確定申告でするべき控除3:ふるさと納税
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付ができる制度です。2,000円を超える金額について、所得税や住民税から控除できます。そのうえ、ふるさと納税をすると、多くの自治体ではお礼の品(返礼品)を送ってくれます。返礼品は食品、日用品、雑貨など、地域の特産品が盛りだくさん。これが実質2,000円で手に入るため、人気があります。
ふるさと納税をすると届く寄附金受領証明書を添えて確定申告を行うと、寄附金控除が受けられて税金が安くなります。
-

SoVa税理士ガイド編集部
また、ふるさと納税の納税先が5つまでならば、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告なしでも控除が受けられます。
このように、年末調整ではできない控除を確定申告で行うことで、より多くの控除を受けることが可能になります。年末調整で適用される控除と確定申告でしか適用できない控除の違いを理解し、最大限に活用しましょう。
おすすめ記事:年末調整・確定申告で損しないために必ずすべき7つの控除
Q&A|よくある質問
Q: 年末調整とは何のために行う手続き?
年末調整とは、1年間に給与から源泉徴収された所得税と、本来納めるべき税額との差額を精算するための手続きです。企業が従業員に代わって行うこの年末調整は、過不足の税金を調整する役割を果たします。年末調整の目的は、正しい所得税額に基づき、払い過ぎた税金があれば還付し、不足していれば追加徴収することにあります。給与所得者にとっては、確定申告をしなくても各種控除を反映できる便利な制度です。
Q: 年末調整で受けられる控除には何がある?
年末調整で受けられる控除には、所得税の算出に大きく影響する重要な控除が多数あります。具体的には、扶養控除、配偶者控除、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などがあります。
これらの控除を年末調整で正しく反映させることで、税金の負担を軽くすることが可能です。特に家族構成の変化や保険の加入状況などがある場合は、控除額が大きく変動するため、年末調整での正確な申告が求められます。
Q: 年末調整の控除申告で気をつけるべきポイントは?
年末調整で控除を受けるには、所定の控除申告書を正しく記入し、必要な証明書類を期限内に会社へ提出することが不可欠です。たとえば、生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合には、各保険会社から送付される控除証明書が必要になります。また、扶養控除などでは、家族の収入状況や生計維持の実態を把握しておく必要があります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
これらの控除申請を怠ったり不備があると、税額が本来より高くなることもあるため注意が必要です。
まとめ
年末調整は手間に感じられるかもしれませんが、仕組みを理解することで金銭的なメリットがあります。また、保険や共済を見直す良い機会でもあります。
また、もし年末調整で手続きを忘れてしまった場合でも、確定申告を行うことで控除を受けることが可能です。さらに、確定申告を忘れてしまった場合でも、5年以内であれば「還付申告」を行うことで払いすぎた税金が戻ってきます。該当する控除がある方は、ぜひ税務署に相談してみてください。
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
















SoVaをもっと知りたい!