36協定の特別条項を詳しく解説!要件や時間外労働の上限とは?
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2025年11月5日
企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせるには、「36協定(サブロク協定)」の締結が必要です。中でも、法定の時間外労働の上限を超えて残業をさせる場合には、「特別条項付き36協定」の導入が不可欠です。通常の36協定だけでは、時間外労働は月45時間・年360時間までと決められており、これを超えるには特別条項を定めた36協定がなければ違法となってしまいます。
とはいえ、特別条項付き36協定を結べば無制限に残業できるわけではありません。特別条項には、1カ月100時間未満、年間720時間以内という厳しい上限があり、加えて健康確保措置や発動条件なども明記する必要があります。特別条項の内容を正しく理解し、36協定に適切に反映させることが、法令遵守と従業員の安心につながるのです。
この記事では、「36協定の特別条項とは何か?」という基本から、特別条項の要件、特別条項による時間外労働の上限、特別条項の締結方法、特別条項違反時の罰則、そして特別条項付き36協定の届出手続きまで、幅広く解説していきます。
「36協定の特別条項」編集部
特別条項を含んだ36協定を導入すべきか迷っている方、すでに締結している36協定の特別条項の内容を見直したい方は、ぜひ最後までご覧いただき、特別条項付き36協定の実務対応にお役立てください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
36協定の特別条項とは?内容や記載項目を詳しく解説
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、企業が従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合に、労働者代表や労働組合と締結する必要がある労使協定です。そして、この36協定において、さらに法定の上限時間を超えて時間外労働をさせる場合には、特別条項付き36協定を締結する必要があります。
36協定の特別条項に関するおすすめ記事

36協定の特別条項とはなにか、特別条項付き36協定の手続きの方法、罰則については以下の記事も是非参考にしてください。
36協定の特別条項に関する参考記事:「36協定「特別条項」の発動手続きを適切に行っていますか?」
この36協定の特別条項は、いわゆる繁忙期など「臨時的な事情がある場合」に限定して、特別に時間外労働の上限を引き上げることができる制度ですが、労働者の健康を守るために、具体的かつ厳密な条件の設定が求められます。以下に、特別条項付き36協定で定めなければならない内容を、詳しく紹介していきます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
① 1カ月の時間外労働+休日労働の合計時間|100時間未満が必須条件

36協定の特別条項を定める際には、1カ月あたりの時間外労働と休日労働の合計時間数について、上限を100時間未満に設定する必要があります。たとえば、「時間外労働が80時間、休日労働が25時間」などのケースでは合計が105時間となり、36協定の特別条項でも認められない違法な働かせ方になります。

合わせて読みたい「アルバイトに有休を付与」に関するおすすめ記事

アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説!
この記事では、アルバイトやパートに対する有給付与の詳細や、有給休暇取得時の賃金計算方法、さらに有給付与に関する注意点について詳しく解説します。アルバイトの有給付与に関する正しい知識を身につけ、適切な運用を行いましょう。
この「1カ月100時間未満」というルールは、時間外労働と休日労働の合算時間で評価されるため、休日出勤が多い月であっても、時間外労働の調整によってトータルを100時間未満に抑える必要があります。
「36協定の特別条項」編集部
36協定の運用において最も重要なポイントのひとつです。
② 年間の時間外労働時間数|720時間以内に設定
36協定の特別条項を導入する場合でも、1年間における時間外労働の累計上限は720時間以内と法律で定められています。ここでいう720時間とは、あくまで時間外労働の合計であり、休日労働はカウントされません。
企業が特別条項付き36協定を届け出る際には、繁忙期を見越したうえで、年間の労働時間がこの上限を絶対に超えないように設計することが求められます。長期的な労働管理が重要となる場面です。
③ 限度時間の超過が可能な回数|年6回以内に明記する
通常の36協定では、時間外労働の限度時間は「月45時間」とされています。特別条項付き36協定ではこの限度を超えることが可能ですが、年6回(6カ月)を超えてはなりません。つまり、限度時間の超過を認める月は最大6回までという制限があります。
36協定の特別条項に関する注意点

特別条項の記載では、具体的に「どの月に」「何回まで」超過を認めるかを明確に記載する必要があり、これが曖昧だと労働基準監督署で指摘を受ける可能性もあります。
「36協定の特別条項」編集部
36協定の特別条項や、特別条項付き36協定の手続きの方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
36協定の特別条項に関する参考記事:「36協定の特別条項とは?一般との違い・新様式での書き方など詳しく解説」
④ 限度時間を超過できる具体的な事由|業務の実態に即して明記
36協定の特別条項では、限度時間を超過して時間外労働をさせる場合の具体的な理由を記載することが義務付けられています。これは「臨時的・突発的な業務」である必要があり、定常業務での使用は本来想定されていません。
【記載例】
- 製品の不良対応などによる一時的な対応
- 取引先からの突発的な仕様変更への対応
- 想定外の自然災害や緊急メンテナンス対応
- 年末年始、繁忙期などに発生する集中業務

給与計算に関する参考記事:「寡婦控除とは?適用条件や申告方法、ひとり親控除との違いについても解説!」
「36協定の特別条項」編集部
こうした具体例を記載することで、36協定の特別条項が「形だけの取り決め」にならず、実効性のある内容になります。
36協定の特別条項に関するおすすめ記事

36協定の特別条項とはなにか、特別条項付き36協定の手続きの方法、罰則については以下の記事も是非参考にしてください。
「36協定届の記載例(特別条項)」
⑤ 健康福祉確保措置の具体化|長時間労働に対する保護
特別条項付き36協定には、時間外労働が法定限度を超える場合における健康管理上の措置(健康福祉確保措置)の記載が求められます。これは、労働者の心身の健康を守るための最低限の配慮として、厚生労働省からも例示されています。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」
【具体例】
- 医師による健康診断・面接指導の実施
- 勤務間インターバル制度(11時間以上)の導入
- 深夜勤務の抑制や回数制限
- 長時間労働者の部署異動・業務配分の見直し
- 時短勤務制度や代替休暇制度の導入
- 年次有給休暇の集中的な取得推進
これらの施策を明記することで、36協定の特別条項が形式的でない、実効性あるものとして認められます。
⑥ 割増賃金率の設定|超過分には法律以上の水準も検討
36協定における特別条項では、法定の時間外労働の上限(45時間/月、360時間/年)を超えた時間に対して支払う割増賃金率を明記する必要があります。
36協定の特別条項に関する参考記事:「36協定の特別条項とは?上限時間のルール・締結の手続き・違反時の罰則などを分かりやすく解説!」
法令上の最低基準としては、月60時間以内の部分については25%以上、月60時間を超える部分については50%以上の割増賃金率が定められています。なお、中小企業には60時間超の割増率適用に猶予があります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
勤怠管理に関連してフレックスタイム制については、【 アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説! 】の記事も是非ご覧ください。
【法令上の最低基準】
企業によっては、36協定の特別条項に基づく長時間労働の負担に対する配慮として、30%や35%といった上乗せの割増賃金率を設定しているケースもあります。これは労働者のモチベーションや会社のコンプライアンス姿勢を示す方法として有効です。
⑦ 特別条項発動時の手続き|労使での適正な協議が不可欠
36協定の特別条項を実際に発動する場合には、必ず事前に手続きを行うことが必要です。以下のような対応が一般的です。

合わせて読みたい「みなし残業代(固定残業代)」に関するおすすめ記事

みなし残業(固定残業)制度とは?企業側のメリットと注意点を解説!
本記事では、みなし残業(固定残業)制度の基本的な仕組みから、企業が導入するメリット・デメリット、注意点までをわかりやすく解説します。これから制度の導入を検討している企業の方や、仕組みを正しく理解したい人事担当者にとって、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
労働者代表(または労働組合)への正式な申し入れと協議、上長と対象労働者との事前面談や勤務時間調整、特別条項の発動記録の保存、報告書の作成などが挙げられます。
「36協定の特別条項」編集部
36協定と特別条項の信頼性は、こうした手続きの透明性と誠実さに支えられています。
⑧ 特別条項でも超えてはならない絶対的上限時間
36協定に特別条項を定めた場合であっても、以下の労働時間は絶対に超えてはならない上限として法令で定められています。
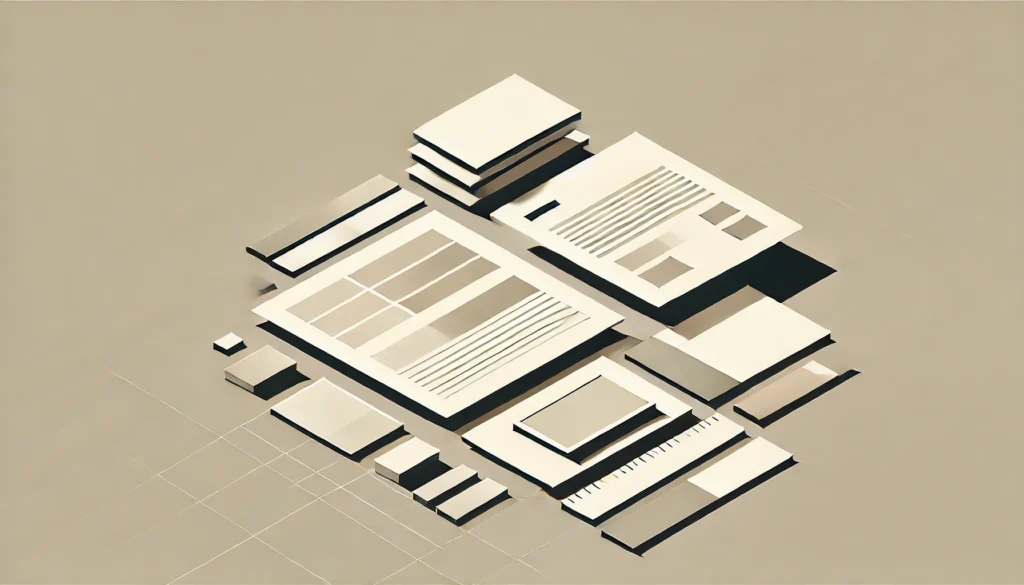
坑内労働など特に有害な業務に従事する場合、時間外労働は1日2時間以内に制限されます。また、任意の2~6カ月の平均時間外・休日労働時間は、いずれの期間においても月平均80時間以内に抑える必要があります。
36協定の特別条項に関する注意点

たとえ特別条項で労働時間の上限を引き上げていても、この上限を超えると重大な労働基準法違反となり、企業は厳しい行政指導や制裁の対象になります。
「36協定の特別条項」編集部
36協定の特別条項や、特別条項付き36協定の手続きの方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
「36協定(サブロク協定)とは?時間外労働の上限・特別条項の要件などを分かりやすく解説!」
36協定における特別条項は、企業が一時的な繁忙などに対応するために活用できる制度ですが、労働者の過重労働を防ぐための制約が多く定められています。すべての項目において具体的かつ合理的な記載が求められ、形式的な対応では法律違反になるおそれもあります。
企業が36協定の特別条項を導入・更新する際には、最新の法改正や労働基準監督署の指導内容を確認しつつ、労使間で丁寧な協議を重ねることが重要です。特別条項を適切に設けることで、業務と従業員の健康を両立させ、持続可能な働き方を実現していきましょう。
36協定の特別条項は定めておくと安心|特別条項付き36協定の導入が企業を守る
36協定を労働基準監督署へ届け出る際には、「特別条項ありの36協定」にするか、「特別条項なしの36協定」にするかを必ず選ぶ必要があります。このとき、どちらを選択するかは企業にとって非常に重要な判断となります。なぜなら、特別条項があるかどうかで、万が一の労務トラブルへの対応可否が大きく変わるからです。
そもそも36協定の特別条項とは、通常の法定上限である「月45時間・年360時間」を超えて時間外労働を行わせることを、一定の条件下で可能にする例外規定です。特別条項付き36協定をあらかじめ結んでおくことで、繁忙期や突発的な業務対応が発生した場合でも、法律に抵触することなく時間外労働をさせることができます。
36協定の特別条項に関するポイント!

たとえ日常的に残業が少ない企業であっても、1年のうちに一度でも繁忙期やトラブルが発生する可能性があるならば、特別条項付き36協定を締結しておくことが極めて重要です。
「36協定の特別条項」編集部
わずか1%でも残業が月45時間を超えるリスクがある場合には、特別条項の有無が企業の違法・合法を左右する事態になりかねません。
実際、厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査」によれば、特別条項付きの36協定を導入している企業の割合は非常に高く、企業規模が大きいほどその傾向が顕著に表れています。
【企業規模別|特別条項付き36協定の締結率】
- 従業員1,000人以上:87.9%
- 従業員300~999人:70.6%
- 従業員100~299人:58.4%
- 従業員30~99人:43.8%
- 全体平均(調査産業計):49.9%
この調査結果からもわかるとおり、大企業の多くが積極的に特別条項を導入した36協定を結んでいることが確認できます。これは、企業が法令違反のリスクを避け、労働環境を整えるうえで特別条項付き36協定の整備が極めて有効な手段であることを物語っています。
一方で、特別条項を付けていない36協定の場合、万が一残業時間が月45時間・年360時間を超えてしまった際には、たとえ一時的であっても即座に労働基準法違反となるリスクを抱えることになります。その結果、労働基準監督署の是正勧告を受けたり、企業名の公表など、企業の信用にも大きく影響を及ぼす可能性があります。

このような事態を未然に防ぐためにも、36協定の届出時には特別条項を明記した36協定を選択しておくことが企業のコンプライアンス対策として非常に有効です。特に、複数の部署やプロジェクトが同時進行するような中規模・大規模企業では、部門単位で残業が集中することもあり、特別条項があることで柔軟な労務対応が可能になります。
「36協定の特別条項」編集部
36協定の特別条項や、特別条項付き36協定の手続きの方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
36協定の特別条項に関する参考記事:「13.36協定と特別条項付き協定」
さらに、特別条項付き36協定を導入すること自体が、従業員との信頼関係を築く材料にもなります。法律を遵守しつつ、やむを得ず時間外労働が必要な状況でも、事前にルール化された特別条項があれば、労使間で無用な摩擦を回避することが可能です。
また、特別条項付きの36協定を締結しておけば、実際に特別条項を発動するかどうかは状況次第で判断でき、締結しておくだけでリスクヘッジとして大きな意味を持ちます。「使わないかもしれないから結ばない」のではなく、「使う可能性があるから結んでおく」という意識が大切です。
36協定の特別条項に関するおすすめ記事

36協定の特別条項とはなにか、特別条項付き36協定の手続きの方法、罰則については以下の記事も是非参考にしてください。
「36協定」
まとめると、企業が法令を遵守しながら安定的に業務を遂行していくためには、特別条項付き36協定の導入が極めて効果的です。労働時間の上限を適切に管理し、万が一に備えておくためにも、特別条項を備えた36協定をあらかじめ整備しておくことが、企業にとっての安心材料になるのです。
36協定の特別条項に関するポイント!

36協定の特別条項は、企業を守る「安全装置」とも言えます。迷ったら、特別条項を付けた36協定を選択することが、今後の安定経営とコンプライアンス強化の第一歩となるでしょう。
特別条項付き36協定に違反した場合の罰則とは?
企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせるには、まず36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。さらに、法定の上限(月45時間・年360時間)を超えて残業させる可能性がある場合は、特別条項付き36協定を結ぶ必要があります。
「36協定の特別条項」編集部
ただし、この特別条項付き36協定にも明確な上限があり、これを超えて労働させた場合には、罰則が科されることになります。
特別条項がない36協定で上限を超えた場合
特別条項のない36協定では、月45時間・年360時間を超える時間外労働は認められていません。これを超えて残業させた場合は、労働基準法第32条違反となります。
この場合、次のような罰則が科される可能性があります。
- 使用者本人(行為者):6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条第1号)
- 会社(法人):30万円以下の罰金(労働基準法第121条第1項)
特別条項を設けていない状態で上限を超えれば、それだけで違法な労働となってしまうのです。
36協定の特別条項に関するおすすめ記事

36協定の特別条項とはなにか、特別条項付き36協定の手続きの方法、罰則については以下の記事も是非参考にしてください。
36協定の特別条項に関する参考記事:「36協定の特別条項とは?上限時間を超えた場合の罰則や記載例も徹底解説」
特別条項付き36協定でも上限を守らなければ違反
36協定に特別条項を定めている場合でも、そこに記載された上限(月100時間未満・年720時間以内など)を超えてしまえば、やはり法律違反となります。
このケースでは、労働基準法第32条および第35条違反となり、罰則内容は以下のとおりです。
- 行為者:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 会社:30万円以下の罰金
36協定の特別条項に関する注意点

特別条項付き36協定があっても、定めたルールを超えてしまえば無効となり、通常の違法残業と同じ扱いを受けることになります。
36協定の届出をしていない場合も罰則の対象に
36協定を締結しただけでは不十分で、必ず労働基準監督署に届け出る必要があります。特別条項付き36協定であっても、提出していなければ法律違反となり、以下の罰則が科されます。
(労働基準法第121条第1項)
行為者(代表者・管理者など):30万円以下の罰金
書類を出し忘れていた、というだけでも法的責任が発生するため、36協定の特別条項を結んだ後は速やかに届出を行うことが重要です。
「36協定の特別条項」編集部
36協定の特別条項や、特別条項付き36協定の手続きの方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
「36協定の特別条項とは?時間外労働を制限する内容や注意点を解説」
違反があれば企業名が公表されることも
36協定や特別条項に違反した場合、労働基準監督署から企業名が公表されるケースがあります。いわゆる「ブラック企業リスト」として名前が出てしまうことで、採用活動や信用力に深刻なダメージを受けるおそれがあります。

合わせて読みたい「固定残業代のメリット・デメリット」に関するおすすめ記事

固定残業代とは?労働者と企業それぞれのメリットデメリットや注意点も解説!
この記事では、固定残業代の基本的な仕組みから、企業・労働者それぞれのメリット・デメリット、導入時の注意点まで、わかりやすく解説します。
たとえ一度の違反であっても、企業にとっては大きなリスクです。金銭的な罰則だけでなく、企業のブランドや評判を失う可能性もあるため、軽視できません。
特別条項付き36協定の手続き
企業が従業員に時間外労働や休日労働を命じるには、「36協定」の締結と労働基準監督署への届出が必要です。特に、月45時間・年360時間という法定の限度を超える残業を可能にするには、「特別条項付き36協定」の導入が不可欠です。
ここでは、36協定に特別条項を設ける際の手続きを5つのステップに分けて、わかりやすく解説していきます。
「36協定の特別条項」編集部
36協定を正しく活用し、法令を遵守した労働時間管理を実現しましょう。
① 36協定の特別条項について労使で協議する
まずは、36協定に特別条項を盛り込むかどうかを含め、労働者側と使用者側でしっかりと話し合います。この協議では、残業の上限時間、特別条項の発動条件、健康福祉確保措置など、36協定の内容を具体的に詰めていきます。
36協定の特別条項に関するおすすめ記事

36協定の特別条項とはなにか、特別条項付き36協定の手続きの方法、罰則については以下の記事も是非参考にしてください。
36協定の特別条項に関する参考記事:「36協定の特別条項とは?|時間外労働が上限を超えた場合は?」
特別条項付き36協定は、あくまで臨時的な対応を想定して設けられるものであり、労働者の健康と働き方のバランスを考慮した設計が求められます。36協定が単なる形式で終わらないよう、実効性のある内容にすることが重要です。
② 特別条項付き36協定を正式に締結
労使の合意が取れたら、次は書面による36協定の締結です。労働基準法第36条第1項では、36協定は文書で作成しなければならないと明記されています。もちろん、特別条項を設ける場合も同様です。
「36協定の特別条項」編集部
36協定の特別条項や、特別条項付き36協定の手続きの方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
36協定の特別条項に関する参考記事:「36協定の特別条項とは?届出の手順や時間外労働の上限を徹底解説」
36協定には、会社側の代表者と、従業員側の過半数代表者(または労働組合)が署名または押印を行い、内容を正式に確定させます。36協定の署名・捺印は法的な効力を持ち、後の監査等でも確認される重要な手続きです。
③ 就業規則に36協定の内容を反映
特別条項付きの36協定を締結した場合、その内容は労働条件に関係するため、労働基準法第89条により、就業規則にも記載する義務があります。
常時10人以上の労働者が在籍している事業場では、36協定で定めた時間外労働や休日労働の内容を就業規則にも反映させ、従業員が確認できるよう整備しておく必要があります。
36協定の特別条項に関する注意点

36協定と就業規則の記載に矛盾がないよう注意しましょう。
④ 36協定と特別条項の内容を労働者に周知
36協定とそれに基づく特別条項を定めたら、その内容を全従業員に周知しなければなりません。労働基準法第106条第1項では、労働者への周知が義務付けられており、36協定も例外ではありません。
36協定の特別条項に関する参考記事:「36協定の特別条項とは? 申請方法や注意点を解説」
「36協定の特別条項」編集部
周知の方法としては、以下のような手段が認められています。
- 各作業場の見やすい場所に36協定を掲示する
- 書面で36協定を配布する
- パソコンやタブレットなどで36協定の内容を閲覧可能な状態にする
特別条項付き36協定の内容は複雑なこともあるため、従業員が正しく理解できるよう丁寧な説明も大切です。

⑤ 労働基準監督署へ36協定を届出
締結・周知が完了した後は、36協定(特別条項付き36協定を含む)を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出る必要があります。届出期限は、協定の効力発生日の前日までです。
36協定を届け出ていなければ、協定自体が効力を持たず、労働者に時間外労働や休日労働をさせることは違法となってしまいます。また、特別条項付き36協定を締結していて、常時10人以上の労働者がいる事業場では、就業規則の変更届も同時に提出する必要があります。
「36協定の特別条項」編集部
36協定の特別条項や、特別条項付き36協定の手続きの方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
36協定の特別条項に関する参考記事:「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

合わせて読みたい「給与計算 注意点 (税理士)」に関するおすすめ記事

給与計算の注意点は?税理士に丸投げするメリットについても紹介
まとめ|36協定と特別条項
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
企業が従業員に時間外労働や休日労働を命じる際には、「36協定」の締結が法律で義務付けられています。特に、月45時間・年360時間という時間外労働の限度時間を超える可能性がある場合は、「特別条項付き36協定」を結ばなければ、36協定の効力が及ばず、違法な労働となってしまいます。
36協定は企業と労働者の間で取り決める労使協定であり、36協定に特別条項を追加することで、臨時的な長時間労働への対応が可能となります。しかし、36協定の特別条項は自由に設定できるものではなく、労働基準法に基づいて、1カ月の残業は100時間未満、年720時間以内など、明確な上限規制が定められています。

合わせて読みたい「36協定の残業時間の上限」に関するおすすめ記事

36協定の残業時間の上限は月45時間?80時間?規制や罰則について解説
また、36協定に特別条項を設けた場合には、36協定の内容を就業規則に反映し、36協定と特別条項の内容を労働者に周知し、36協定を労働基準監督署に届出るという一連の手続きが必要です。これらの手続きを正しく行ってはじめて、36協定とその特別条項が法的に有効となり、企業は適法に時間外労働を命じることができます。
36協定がなければ、たとえ従業員の同意があったとしても時間外労働や休日労働は認められず、企業は法違反のリスクを負うことになります。さらに、36協定の特別条項を締結していても、協定で定めた上限を超えてしまえば、36協定違反として罰則の対象になります。
だからこそ、36協定の締結、36協定の届出、36協定の特別条項の管理、36協定と就業規則の整合性、36協定に基づく従業員への周知といった流れを、企業は一貫して丁寧かつ適正に行うことが必要不可欠です。
結論として、企業が長期的に信頼され、安定した労務管理を実現するためには、36協定と特別条項の正確な理解と適切な運用が極めて重要です。今一度、自社の36協定や特別条項の内容・運用体制を見直し、法令遵守と従業員の健康を両立させる取り組みを進めていきましょう。36協定の整備と特別条項の適用は、企業経営の基盤を支える重要な要素なのです。
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!