振込手数料の勘定科目と仕訳方法は?仕訳例や混同しやすい支出についても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2026年2月12日
振込手数料は、日々の取引で発生しやすい費用のひとつです。適切な勘定科目を選んで振込手数料を正しく仕訳することは、帳簿管理の正確性を保つ上でとても重要です。しかし、振込手数料は「支払手数料」などの他の勘定科目と混同しやすく、仕訳方法を誤ると振込手数料の実態を正しく把握できなくなる恐れがあります。
本記事では、勘定科目「振込手数料」としての正しい仕訳方法を、売掛金や買掛金の具体的な振込手数料の仕訳例とともに解説します。さらに、振込手数料と間違えやすい勘定科目の違いや、振込手数料を経費計上する際のポイントについても詳しくお伝えしますので、ぜひ日々の経理業務に役立ててください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
勘定科目「振込手数料」とは

「支払手数料」は、取引された商品やサービスそのものではなく、商品やサービスに付随して発生する振込手数料や各種手数料、専門家へ支払う報酬を計上する際に使用する勘定科目です。損益計算書上では、この勘定科目は「一般管理費」に含まれます。
商品やサービスに付随して発生する費用
「支払手数料」という勘定科目は、商品やサービスに付随して発生する振込手数料など様々な手数料の計上に適しています。たとえば、クリーニング代、ネットショップの出店費用、火災報知器の保守点検費用、金融機関からの借入時に信用保証協会へ支払う費用などがあり、これらはすべて適切な勘定科目として「支払手数料」を使用できます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
振込手数料を含む、会計上よく発生する代表的な手数料には次のようなものがあります。
<「支払手数料」の勘定科目で仕訳できる振込手数料などの例>
- 銀⾏の振込手数料
- 為替手数料
- 代引き手数料
- 各種証明書の発行手数料
- 不動産賃貸の仲介手数料
- 取引の斡旋手数料(キャッシュレス決済手数料など)
- ローンの繰上返済手数料
- その他の事務手数料、登録手数料、解約手数料
振込手数料のように1回あたりは少額でも、発生頻度が高い場合は「雑費」ではなく勘定科目「支払手数料」で仕訳するのが適切です。「雑費」という勘定科目は、他の勘定科目に当てはまらない少額の経費や一時的な経費を処理する際に使用します。
勘定科目「振込手数料」の仕訳に関する気をつけておきたい注意点

しかし、振込手数料などが雑費に含まれ過ぎると、帳簿の明細が不透明になり、税務調査や会計監査の際に詳細を求められる可能性があります。
したがって、振込手数料のように一定の回数や金額が発生するものは、なるべく「支払手数料」という勘定科目を用いて計上することが望ましいでしょう。
また、ある月は振込手数料を「支払手数料」で仕訳し、翌月は「雑費」で仕訳するなど、同じ振込手数料の費用でも勘定科目を混在させてしまうと、経費の動きが正確に把握できなくなります。一度決めた振込手数料の勘定科目は変更せず、仕訳ルールを統一することが重要です。

合わせて読みたい「未払金勘定の仕訳」に関するおすすめ記事

勘定科目「未払金」はどう仕訳する?間違いやすい勘定科目との違いもわかりやすく解説!
専門家に支払う報酬
「支払手数料」という勘定科目は、専門家に支払う報酬にも利用できます。たとえば、弁護士や税理士、行政書士などに支払う報酬のほか、振込手数料を伴うフランチャイズのロイヤリティなども「支払手数料」の勘定科目に含めて仕訳できます。
勘定科目「振込手数料」の仕訳方法に関するおすすめ記事
<「支払手数料」の勘定科目で仕訳できる報酬例>
- 弁護士への報酬・相談料
- 税理士や行政書士への報酬・相談料
- 社労士への報酬・相談料
- 経営コンサルタントへの報酬・相談料
- フランチャイズ加盟店のロイヤリティ
専門家に支払う報酬については、「支払手数料」の勘定科目以外にも「支払報酬」や「支払報酬料」などの勘定科目を使用できます。ただし、弁護士報酬や税理士報酬などは源泉徴収の対象になるため、税金管理を正確に行うのであれば、報酬専用の勘定科目である「支払報酬」などを使い分けるのが理想です。振込手数料と同様に、どの勘定科目を使用するかは社内でルールを決め、一貫して処理することが大切です。

合わせて読みたい「ChatGPTを使った記帳」に関するおすすめ記事

ChatGPTなどのAIを使って記帳するやり方|経理業務は生成AIにお任せ?
振込手数料の仕訳例【売掛金ver.】

売掛金が普通預金口座に振り込まれる場合の仕訳例を紹介します。なお、以下の仕訳例では振込手数料はすべて500円として計算します。振込手数料の扱いによって勘定科目が異なる点を把握しておきましょう。
振込手数料が自社負担の場合
売掛金に対する振込手数料を自社が負担する場合、振込手数料分を差し引いた金額が普通預金に入金されます。このとき、振込手数料の金額は「支払手数料」という勘定科目を使用して仕訳します。振込手数料を勘定科目として正しく計上することで、帳簿が正確になります。
SoVa税理士ガイド編集部
勘定科目「振込手数料」の仕訳方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
例:売掛金10,000円があり、振込手数料500円を差し引いた9,500円が普通預金に入金された場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 9,500 | 売掛金 | 10,000 |
| 支払手数料(振込手数料) | 500 |
このように、振込手数料を勘定科目「支払手数料」として処理することがポイントです。
振込手数料が取引先負担の場合
売掛金にかかる振込手数料を取引先が負担する場合は、振込手数料は自社負担ではないため、振込手数料の勘定科目は仕訳に含まれません。取引先が振込手数料を負担するため、売掛金の満額が普通預金に入金されます。

合わせて読みたい「ChatGPTの勘定科目」に関するおすすめ記事

ChatGPT月額料金の勘定科目とは?を解説!消費税(インボイス)の取り扱いについて解説!
例:売掛金10,000円の代金が、振込手数料なしで普通預金にそのまま入金された場合の仕訳は次の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000 | 売掛金 | 10,000 |
勘定科目「振込手数料」の仕訳に関するここがポイント!

このように振込手数料が取引先負担の場合は、振込手数料を勘定科目として処理する必要はありません。振込手数料の負担区分を正しく把握し、適切な勘定科目で仕訳を行うことが大切です。
振込手数料の仕訳例【買掛金ver.】

買掛金における振込手数料の仕訳例を紹介します。振込手数料の負担先によって使用する勘定科目が変わるため、振込手数料の仕訳は注意が必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
振込手数料が自社負担の場合
買掛金に対する振込手数料が自社負担となる場合、振込手数料は「支払手数料」という勘定科目を使用して仕訳します。このように振込手数料を正しく勘定科目で分けて記帳することで、費用の内訳が明確になります。
勘定科目「振込手数料」の仕訳方法に関するおすすめ記事
例:買掛金10,000円を支払い、振込手数料550円を自社で負担した場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 10,000 | 普通預金 | 10,550 |
| 支払手数料(振込手数料) | 550 |
このように、振込手数料を「支払手数料」という勘定科目で計上し、買掛金と合わせて処理します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
振込手数料を雑費など他の勘定科目と混在させないように、振込手数料は必ず「支払手数料」の勘定科目で管理しましょう。
振込手数料が取引先負担の場合
買掛金に対する振込手数料を取引先が負担する場合は、振込手数料を差し引いた金額を振り込みます。このとき、自社側では振込手数料分を「雑収入」という勘定科目で仕訳します。振込手数料の扱いに応じて、適切な勘定科目を選ぶことがポイントです。
例
買掛金10,000円のうち、振込手数料500円を差し引き、取引先負担とした場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 10,000 | 普通預金 | 9,500 |
| 雑収入(振込手数料) | 500 |
このように、振込手数料を取引先負担とした場合は、振込手数料を「雑収入」という勘定科目で計上します。振込手数料の勘定科目を誤らないように整理し、帳簿を適切に管理しましょう。
振込手数料と混同しやすい勘定科目

支払手数料や振込手数料と混同しがちな支出について、それぞれの正しい勘定科目を確認しておきましょう。振込手数料を含め、勘定科目を正しく使い分けることが帳簿の正確性につながります。

合わせて読みたい「会社経費をクレジットカードで個人立替」に関するおすすめ記事
会社経費をクレジットカードで個人立替は問題ない?仕訳や注意点も詳細に解説!

混同しやすい勘定科目①:専門家への報酬は「支払報酬」で振込手数料と分ける
弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士、デザイナーなどの専門家へ報酬を支払う場合は、「支払手数料」ではなく「支払報酬」という勘定科目で仕訳するのが一般的です。振込手数料とは異なり、専門家への報酬は源泉徴収の対象になる点に注意が必要です。
勘定科目「振込手数料」の仕訳に関する気をつけておきたい注意点

もし専門家報酬を「支払手数料」の勘定科目で計上してしまうと、振込手数料を含めた支払手数料の総額が膨らんでしまい、振込手数料の金額が不明確になります。振込手数料の内訳を把握するためにも、報酬は「支払報酬」という勘定科目で分けて管理しましょう。
混同しやすい勘定科目②:利子や利息は「支払利息」として振込手数料と区別する
金融機関からの借入金の返済に含まれる利息は、「支払手数料」や振込手数料の勘定科目で計上するのではなく、「支払利息」という勘定科目で処理します。振込手数料と異なり、利息は本業以外で発生する費用として営業外費用に分類されます。
利息の振込時に振込手数料が発生する場合は、振込手数料部分だけを「支払手数料」の勘定科目で仕訳し、利息は「支払利息」の勘定科目で分けて計上することが大切です。
混同しやすい勘定科目③:販売に直接関連する手数料は「販売手数料」で処理
商品やサービスの販売促進のために、委託業者や仲介業者など外部に支払う報酬は「販売手数料」として処理します。これを振込手数料や「支払手数料」の勘定科目と一緒に計上してしまうと、振込手数料の把握が難しくなります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
勘定科目「振込手数料」の仕訳方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:勘定科目『支払手数料』とは?仕訳や税区分を解説
販売に直接関係する費用は、「販売手数料」という勘定科目を使い、振込手数料は振込手数料として「支払手数料」の勘定科目で明確に区分しましょう。
混同しやすい勘定科目④:行政への手数料は「租税公課」として振込手数料と区分する
納税証明書や印鑑証明書、住民票など公的書類の取得にかかる手数料は、「支払手数料」や振込手数料ではなく、「租税公課」という勘定科目で処理するのが原則です。租税公課の勘定科目は、事業に関連する税金や公課に広く使用され、印紙代や登録免許税も含まれます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
行政手続きに関する手数料と、金融機関などで発生する振込手数料は性質が異なるため、それぞれ適切な勘定科目で仕訳し、振込手数料の金額を他の経費と混同しないように管理しましょう。
振込手数料を経費にする際のポイント

振込手数料を経費として正しく計上するためには、振込手数料の勘定科目の使い方を含め、いくつかのポイントに注意が必要です。振込手数料の計上ミスを防ぐためにも、以下の勘定科目の扱いを確認しておきましょう。
ポイント①:「買掛金」の決済時は振込手数料の相殺処理が必要
買掛金を決済する際に、取引先が振込手数料を負担する場合は、振込手数料の金額を買掛金勘定から相殺します。振込手数料を含めた買掛金の支払い額を正しく計算し、振込手数料分を差し引いた残額を振り込むため、勘定科目の仕訳処理に注意が必要です。振込手数料をどの勘定科目で処理するかを間違えると、現金の動きと帳簿の内容にズレが生じます。
一方、売掛金の決済時に取引先が振込手数料を負担する場合は、振込手数料の相殺処理は不要です。売掛金の満額が入金されるため、振込手数料の勘定科目を別途計上する必要はなく、シンプルに売掛金勘定だけで処理が完結します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
買掛金の振込手数料の仕訳と混同しないようにしましょう。
ポイント②:販売手数料は振込手数料と勘定科目を分けて計上する
振込手数料と混同しやすい「販売手数料」は、取扱いに注意が必要です。販売手数料は、販売代理店に商品を販売してもらう際に支払う報奨金などで、売上に直接関係する経費です。そのため、振込手数料とは性質が異なり、「販売促進費」という勘定科目で計上します。

合わせて読みたい「会計ソフト比較一覧」に関するおすすめ記事
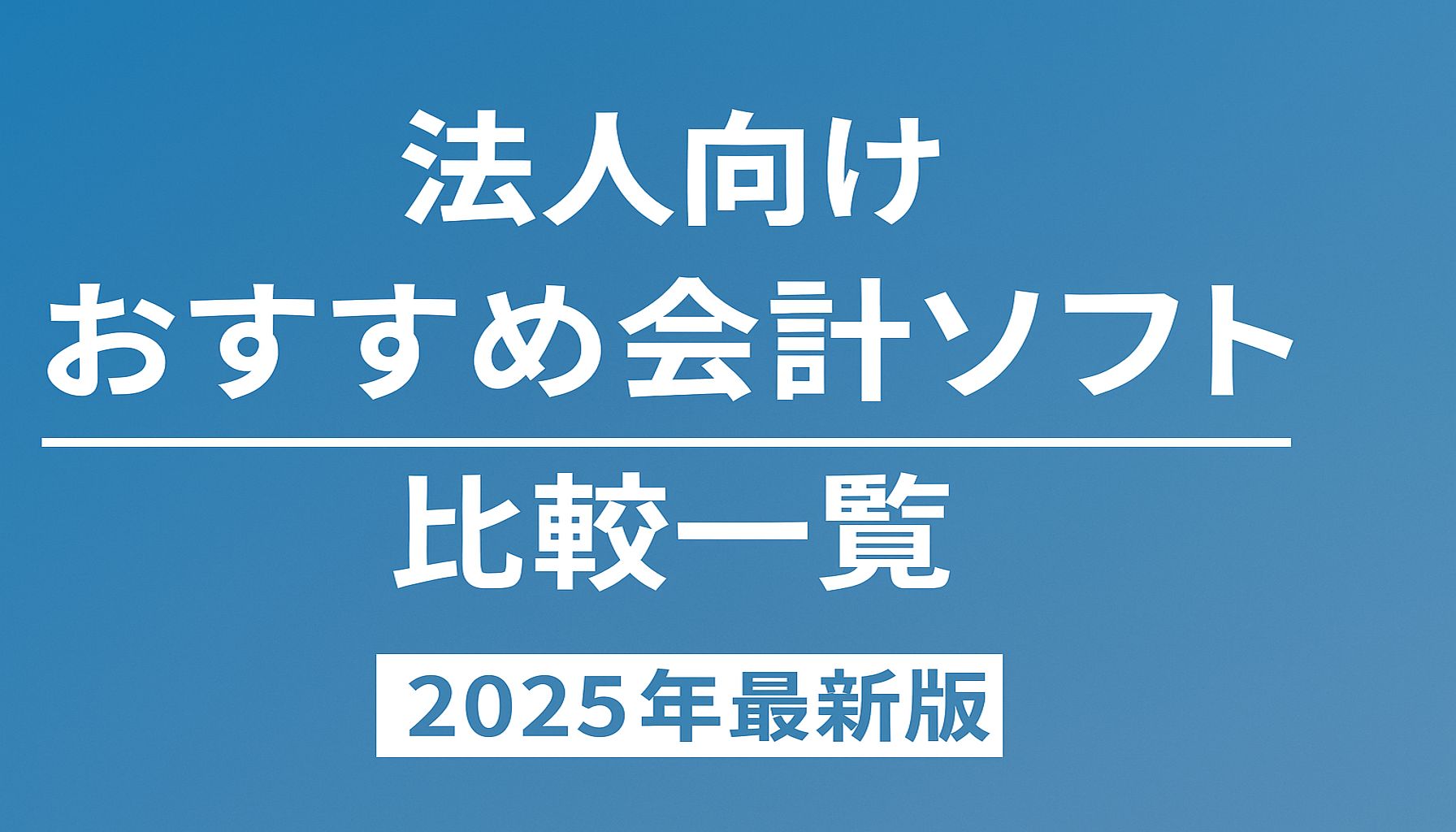
法人のおすすめ会計ソフト比較一覧【2025年最新版】
一方で、振込手数料は商品販売そのものには直接関係しないため、「支払手数料」という勘定科目を使って計上するのが原則です。振込手数料を販売手数料と一緒にまとめてしまうと、勘定科目の区分があいまいになり、経費の内訳が不透明になる恐れがあります。振込手数料は振込手数料として正しい勘定科目で管理しましょう。
ポイント③:専門家への報酬は振込手数料と勘定科目を分ける
税理士や弁護士、行政書士などの専門家へ報酬を支払う場合にも、振込手数料の勘定科目と混同しないようにしましょう。専門家への報酬は振込手数料のように「支払手数料」で計上することも可能ですが、一般的には「支払報酬」という勘定科目を使って処理します。
勘定科目「振込手数料」の仕訳方法に関するおすすめ記事
士業への報酬は源泉徴収が必要なケースが多く、振込手数料とは扱いが異なります。振込手数料を含む支払手数料の勘定科目と混在させると、振込手数料の金額を把握しにくくなるため、明細管理が煩雑になります。振込手数料は振込手数料、報酬は「支払報酬」という勘定科目で分けて仕訳し、帳簿を明確に保つことが大切です。
Q&A|よくある質問
Q. 振込手数料の勘定科目はどう分類するのが正しいですか?
振込手数料の勘定科目は、原則として「支払手数料」で処理するのが一般的です。勘定科目の中でも「支払手数料」は、取引の手数料や各種サービス利用時の料金など、振込手数料に限らず幅広く活用されます。ただし、会計処理上で曖昧になりがちな場合は「雑費」や「通信費」に仕訳されるケースもありますが、税務的には「支払手数料」にまとめる方が管理しやすくなります。
Q. 振込手数料は勘定科目ごとに分けたほうがいいのですか?
振込手数料の勘定科目は、原則として一元管理することが望ましいですが、頻繁に発生する手数料や取引種別が多い場合は、補助科目を使って明細ごとに管理するのも有効です。たとえば「支払手数料(ネットバンキング)」や「支払手数料(外注支払)」など、勘定科目の明細を整理することで、経費の内訳が明確になり、税務調査時にもスムーズな説明が可能になります。
Q. 法人の場合と個人事業主の場合で振込手数料の勘定科目に違いはありますか?
法人と個人事業主のどちらであっても、振込手数料の勘定科目としては「支払手数料」を使うのが基本です。ただし、個人事業主の場合は会計ソフトの初期設定で「雑費」に分類されていることもあります。正確な帳簿管理や節税を意識するなら、法人・個人を問わず、振込手数料の勘定科目は明確に「支払手数料」で登録し直すのが理想です。
Q. 振込手数料を経費にできないケースはありますか?
振込手数料でも、事業と関係のない私的な支払いに伴う手数料や、立替経費を未処理のまま経費化してしまった場合などは、税務上否認される可能性があります。また、他人名義の口座に対する送金手数料であっても、明確な業務目的が説明できなければ、振込手数料として「支払手数料」の勘定科目に仕訳しても経費として認められない場合があるため注意が必要です。
まとめ

専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
振込手数料は少額でも頻繁に発生するため、正しい勘定科目で振込手数料を仕訳し、帳簿を明確にすることが大切です。
売掛金・買掛金それぞれの振込手数料の仕訳例を参考にしながら、振込手数料と「支払手数料」「販売手数料」「支払報酬」など他の勘定科目を混同しないよう注意しましょう。
振込手数料をどの勘定科目で処理するかを統一することで、経費の内訳を把握しやすくなり、税務調査や監査の際にも安心です。正しい振込手数料の仕訳を実践し、経理の質を一段と高めていきましょう。
勘定科目「振込手数料」の仕訳方法に関するおすすめ記事:振込手数料を経費に計上することは可能?勘定科目や仕訳例を解説
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい!