会社設立を自分でする方法とは?設立費用や必要な手続きについて解説!
カテゴリー:
公開日:2025年10月
更新日:2026年1月10日
会社設立を考えたときに、多くの人が悩むのが「会社設立を自分でするべきか、それとも専門家に依頼するべきか」という点です。会社設立を自分で行えば、専門家に支払う報酬が不要になるため、設立費用を大幅に抑えることができます。さらに、会社設立を自分で経験することで、定款作成や登記の流れを理解でき、経営に役立つ知識も自分で身につけられます。
一方で、会社設立を自分で行う場合は、会社の概要決定から法人印鑑の準備、定款の作成、資本金の払い込み、登記申請、そして会社設立後の税務署や年金事務所への届出まですべてを自分で対応しなければなりません。慣れていない人にとっては負担が大きく、書類の不備や手続きの遅れが発生するリスクもあります。
この記事では、会社設立を自分で進める具体的な手順や流れ、必要となる費用の内訳、さらに専門家に依頼する場合との違いまで徹底解説します。
「会社設立を自分でする方法」編集部
会社設立を自分で行うメリット・デメリットを理解し、効率よく自分で設立を進めるためのポイントを知ることで、自分に合った方法を選べるようになるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
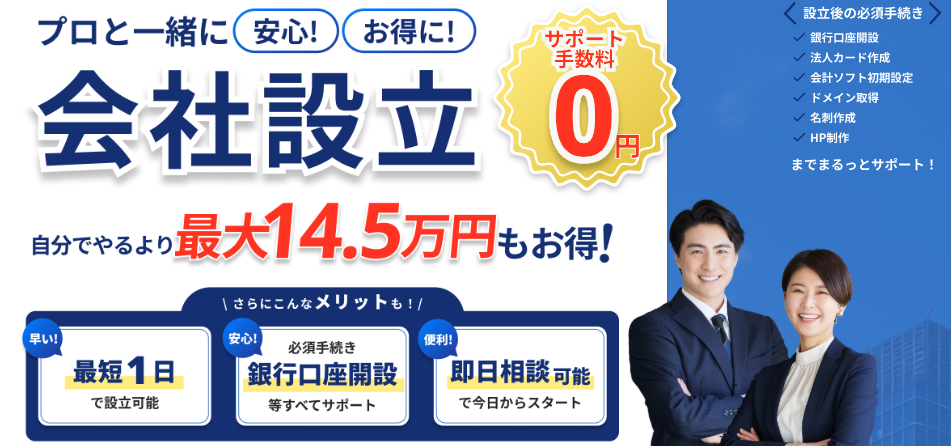
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
会社設立は自分で進めるか、それとも専門家に依頼するべきか?
会社設立を考えるとき、多くの人が悩むのが「自分で手続きを行うべきか、それとも専門家に依頼するべきか」という点です。会社設立を自分で行うと、設立に必要な書類作成から登記申請まで、すべてを自分で確認しながら進めることになります。そのため費用を抑えやすく、会社設立に関する知識を自分で身につけられるメリットがあります。
一方で、専門家に任せる方法を選べば、会社設立の煩雑な流れをスムーズに進められる安心感が得られます。どちらの方法も一長一短があるため、自分にとって最適な会社設立の進め方を考えることが大切です。
会社設立を自分でする方法に関するおすすめ記事

会社設立を自分でする方法や費用については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立を自分でする方法に関する参考記事:「会社設立を自分で行うには? 必要な手続き・費用・依頼するメリットを紹介」
会社設立を自分で行うメリットとデメリット
会社設立を自分で行う場合のメリットとデメリットは以下のようなものがあります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
自分で会社設立するメリット

会社設立を自分で行う一番のメリットは、外注費用がかからず最低限の設立費用で済む点です。司法書士や税理士へ依頼する必要がないため、実費だけで会社設立を完了できます。
また、自分で会社設立を経験することで、会社法や税務に関する基礎知識を学び、今後の経営に役立てることができます。自分で会社設立を進めた経験は、設立後の経営判断にもプラスになる財産といえるでしょう。
「会社設立を自分でする方法」編集部
会社設立を自分でする方法や、かかる費用・必要書類については以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立を自分でする方法に関する参考記事:「会社設立手続きは自分でできる?かかる費用や必要な手続きを解説」
自分で会社設立するデメリット
ただし、自分で会社設立を行うと、慣れない書類作成に多くの時間を割く必要があります。特に定款作成や登記申請には専門的な知識が求められるため、誤記や不備があると再提出となり、時間と労力がさらにかかります。
会社設立を自分でする方法に関する注意点

自分で会社設立を進めると事業準備の時間を圧迫する可能性がある点にも注意が必要です。
自分で会社設立するのがおすすめな人
費用を可能な限り抑えたい人、会社設立に関する知識を自分で学びたい人、そして時間をある程度確保できる人には、自分で会社設立を行う方法が向いています。自分で取り組むことによって外注費用が不要になり、設立費用を最小限にできるのが大きな利点です。

合わせて読みたい「株式会社を自分で設立する方法」に関するおすすめ記事

株式会社の設立は自分でできる?自分で株式会社を設立する際のポイントや設立手続きを解説!
会社設立を専門家に依頼するメリットとデメリット
「会社設立を自分でする方法」編集部
会社設立を専門家に依頼する場合のメリットとデメリットは以下のようなものがあります。
専門家に依頼するメリット
会社設立を専門家に依頼する場合、手続きの流れを熟知したプロが対応するため、ミスのリスクを減らせます。
会社設立を自分でする方法に関するポイント!

自分で会社設立を進める場合に比べて、短期間で正確に設立を完了でき、本業に集中できる時間も確保できるのも大きなメリットです。
専門家が行うサポートは、会社設立を初めて経験する人にとって非常に心強いものです。
専門家に依頼するデメリット
一方で、会社設立を専門家に任せると外注費用が発生します。また、依頼する専門家の選定に時間がかかる場合があり、事務所によっては顧問契約を前提とするケースもあります。つまり、自分で会社設立をする場合に比べてコスト面では不利になる点を理解しておく必要があります。
会社設立を自分でする方法に関するおすすめ記事

会社設立を自分でする方法や費用については以下の記事も是非参考にしてください。
「会社設立を自分でするか、専門家に依頼するか?かかる費用・必要な手続きを解説」
専門家に依頼するのがおすすめな人
「自分で会社設立を進めるのは不安」「できるだけ早く会社を立ち上げたい」「事業の立ち上げに集中したい」という人は、専門家に依頼するのが最適です。専門家の知識と経験を活用すれば、会社設立の不安や手間を大幅に軽減でき、安心して経営の第一歩を踏み出せます。

会社設立を自分で行う場合と専門家に依頼する場合の費用比較
会社設立を考えるとき、多くの人が最初に悩むのが「会社設立を自分で行うべきか、それとも専門家に依頼するべきか」という点です。会社設立を自分で行う場合と専門家に依頼する場合とでは、かかる費用も手間も大きく異なります。
「会社設立を自分でする方法」編集部
会社設立を自分でする方法や、かかる費用・必要書類については以下のサイトも是非ご覧ください。
「法人設立は自分で行える?方法やかかる費用について解説!」
会社設立を自分で行えば初期費用を大幅に節約できますが、その分すべてを自分で調べて、自分で書類を準備して、自分で申請しなければなりません。
| 方法 | 費用 | 手間 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 全て自分で会社設立 | 株式会社:約18万円〜 合同会社:約6万円〜 |
書類作成から提出まで全て自分で | 費用を抑えたい人 会社設立を自分で学びたい人 |
| 電子定款のみ専門家依頼+他は自分で | 株式会社:約20万円〜 合同会社:約8万円〜 |
主要手続きは自分で、定款だけ依頼 | コストも効率も重視する人 会社設立を自分で体験したい人 |
| 全て専門家に依頼 | 株式会社:約28万円〜 合同会社:約16万円〜 |
基本的に自分でやるのは最小限 | 時間を節約したい人 会社設立を自分でやる余裕がない人 |
全て自分で会社設立を行う場合の費用
会社設立を全て自分で行う場合、専門家への報酬が不要になるため、最も安い方法といえます。会社設立を自分で行う場合にかかる費用は、法務局に納める登録免許税や定款の認証費用、印鑑作成費用などの実費のみです。株式会社であれば約18万円から、合同会社なら約6万円から、すべてを自分で行えば設立が可能です。
「会社設立を自分でする方法」編集部
会社設立を自分で行う場合の具体的な費用の内訳は次の通りです。
- 定款に貼る収入印紙代:4万円(電子定款を自分で作成すれば不要)
- 定款の謄本交付手数料:約2,000円
- 定款認証手数料:3万円〜5万円(株式会社の場合、自分で支払いが必要)
- 登録免許税:株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円
- 印鑑作成費用:1,000円〜1万円程度
これらをすべて自分で準備することで、会社設立を自分で最安の形で進められます。ただし、会社設立を自分で進める場合は、作業に時間がかかり、書類の記載ミスや提出忘れなどもすべて自分の責任になるため注意が必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
電子定款だけ専門家に依頼して会社設立を自分で行う場合の費用
会社設立を自分で進めたいけれど、定款の作成だけは不安という人は「電子定款だけ専門家に依頼して、その他の手続きは自分で行う」方法を選ぶことができます。会社設立を自分で進めつつ、電子定款を専門家に依頼すれば印紙税の4万円が不要になるため、結果的にコストを抑えられます。

合わせて読みたい「会社設立の費用」に関するおすすめ記事

会社設立の費用はいくらかかる?株式会社と合同会社の設立相場を解説!
「会社設立を自分でする方法」編集部
電子定款を自分で作成することも不可能ではありませんが、電子証明書付きのマイナンバーカードや専用のソフト・ICカードリーダーを準備する必要があり、自分で揃えるのは大きな手間です。
会社設立を自分でする方法に関するおすすめ記事

会社設立を自分でする方法や費用については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立を自分でする方法に関する参考記事:「一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!」
多くの人が電子定款だけを専門家に依頼し、その他は自分で行っています。この場合の費用は株式会社で約20万円〜、合同会社で約8万円〜が目安です。会社設立を自分で進めたいけれど、手間やリスクを少しでも減らしたい人に向いています。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
全て専門家に依頼して会社設立を行う場合の費用
会社設立の手続きをすべて専門家に任せてしまえば、基本的に自分でやることは少なく済みます。やるべきことは「依頼する専門家を選ぶ」「法人の印鑑を用意する」「資本金を入金する」といった最低限のみです。会社設立を自分でやる時間がない人にとっては効率的ですが、外注費用が10万円前後追加でかかるのがデメリットです。

合わせて読みたい「合同会社を自分一人で設立」に関するおすすめ記事
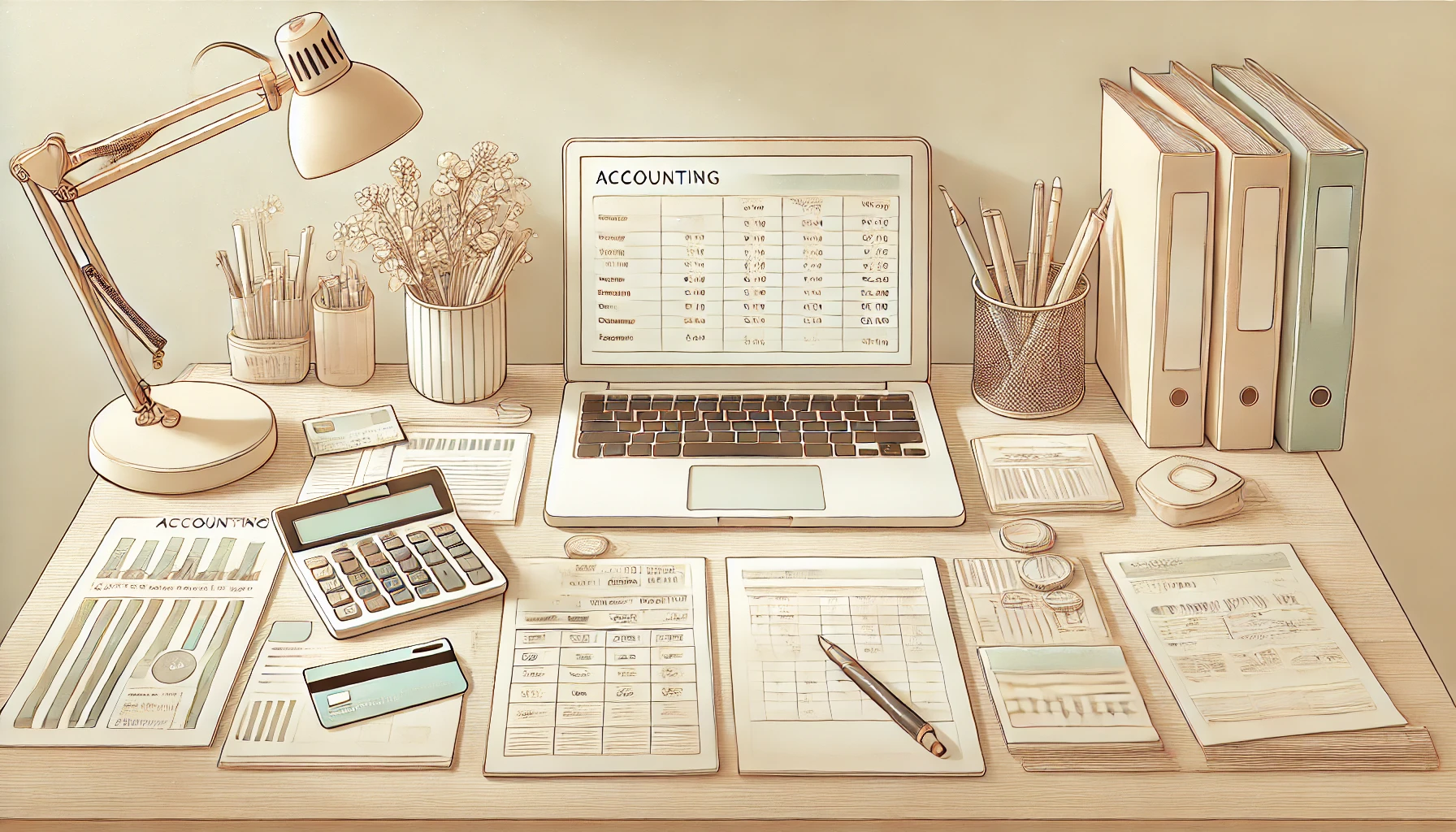
合同会社を自分で設立する方法とは?株式会社と合同会社の違いについても解説!
株式会社であれば合計28万円程度〜、合同会社であれば16万円程度〜が目安となります。
会社設立を自分でする方法に関するポイント!

会社設立を自分で行うより費用はかさみますが、すべてを任せられる安心感があります。
会社設立を自分で行うか専門家に依頼するかの判断
会社設立を自分で行う場合は、費用を徹底的に抑えられるのが大きな魅力です。しかし、会社設立を自分で経験するためには相応の時間と知識が必要であり、リスクも自分で背負うことになります。逆に専門家に依頼すれば、会社設立を自分でやる必要はほとんどなくなりますが、その分費用は増えます。
最終的には「会社設立を自分で行って学びと節約を取るか」「会社設立を専門家に任せて安心と効率を取るか」という選択になります。自分でやるかどうかの判断基準は、予算と時間、そして自分がどこまで自分で挑戦したいかにかかっています。
会社設立の流れと自分で進める具体的な手続き方法
会社設立を検討する際に大切なのは、全体の流れを理解し、自分でどこまで対応できるかを把握することです。会社設立の手続きは法律で細かく規定されているため、自分で進める場合には、ステップごとの内容をしっかり押さえておく必要があります。
「会社設立を自分でする方法」編集部
以下では株式会社を例に、会社設立の流れを「自分で進める場合」という視点で整理して解説します。
STEP1. 会社の概要を自分で決める
会社設立を自分でする方法に関するおすすめ記事

会社設立を自分でする方法や費用については以下の記事も是非参考にしてください。
「自分で会社設立するには?費用・流れ・必要書類を解説」
会社設立を自分で行う最初の作業は、会社の基本事項を決めることです。具体的には「商号(会社名)」「本店所在地」「資本金の額」「設立予定日」「事業目的」「決算期」「株主構成」「役員構成」などを自分で定めます。これらは会社設立の根幹を成す要素なので、後から変更するのは手間がかかります。自分で設立を進めるなら、事業計画と合わせて慎重に検討することが大切です。
STEP2. 法人用の実印を自分で作成する
会社設立登記を申請するには法人実印が必要です。自分で会社設立を行う場合は、印鑑を作成し、印鑑届書を提出するところまで自分で準備します。
会社設立を自分でする方法に関する注意点

2021年2月の法改正でオンライン申請時は印鑑提出が任意になりましたが、銀行口座の開設や契約手続きでは実印が必要になるため、会社設立時に実印を自分で用意するのが安心です。
この際に、銀行印や角印(社判)もあわせて自分で作っておくと、設立後の業務がスムーズに進みます。
STEP3. 定款を自分で作成し認証を受ける
定款は会社設立の「憲法」とも呼べる書類です。会社設立を自分で進める場合、定款を自分で作成し、公証役場で認証を受けなければなりません。絶対的記載事項として「商号」「事業目的」「本店所在地」「出資財産の額」「発起人の氏名と住所」が必須です。自分で定款を紙で作成すると印紙税4万円がかかりますが、電子定款を自分で作成すれば印紙代が不要となり、費用を大きく節約できます。ここは「自分で会社設立する場合にコストを抑える大きなポイント」です。
STEP4. 資本金を自分で払い込む
会社設立を自分で行う際、資本金は発起人の個人口座に振り込み、通帳のコピーを作成して払い込み証明書を自分で準備します。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
「会社設立を自分でする方法」編集部
会社設立を自分でする方法や、かかる費用・必要書類については以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立を自分でする方法に関する参考記事:「はじめてでも自分でできる!会社設立の流れ・全手順を徹底解説!」
法人登記が完了するまでは法人口座が開設できないため、自分で個人口座を活用して対応する必要があります。払い込み証明は登記書類の一部になるため、会社設立を自分で進める際には忘れないようにしましょう。
STEP5. 登記申請書類を自分で作成し法務局に提出する
最後に、登記申請書や付随する書類を自分で作成し、法務局に提出します。この日が正式な会社設立日となります。株式会社の場合、登録免許税は「資本金の0.7%」で計算され、最低でも15万円が必要です。必要な書類は「設立登記申請書」「定款」「発起人決定書」「取締役や監査役の就任承諾書」「印鑑証明書」「資本金払い込み証明」など多岐にわたります。
「会社設立を自分でする方法」編集部
自分で会社設立を進める場合は、法務局の公式サイトから申請書をダウンロードして、自分で必要事項を埋めて提出する流れになります。

合わせて読みたい「会社設立時に法務局で行う手続き」に関するおすすめ記事

会社設立時に法務局で行う手続きを解説!会社設立登記に必要な書類も紹介
会社設立を自分で行う際に注意すべきポイント
会社設立を自分で進める場合、時間と労力をかけて準備する必要があります。特に定款作成や登記書類の準備は専門知識が必要で、誤りがあれば再提出になる可能性があります。その一方で、会社設立を自分で経験すれば、法律や会計の知識が自然と身につき、経営に生かせるというメリットがあります。会社設立を自分で行うという選択は大変な作業ではありますが、将来的に経営者として自信につながる大きな学びの機会になるでしょう。
会社設立後に必ず自分で行うべき手続き
会社設立を完了したら、次に待っているのが「会社設立後の各種届出」です。会社設立を自分で行った人も、専門家に依頼した人も、この手続きは自分で責任を持って進めなければなりません。会社設立は登記だけで終わらず、設立後に自分で提出すべき書類を期限内に処理することが重要です。特に会社設立を自分で進めた人は、最後まで自分で一連の流れを完結させる必要があります。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
会社設立後に自分で提出する書類と期限
| 提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立から2か月以内 |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 開設から1か月以内 |
| 都道府県税事務所 | 法人設立・設置届出書 | 自治体によって異なる |
| 市町村役場 | 法人設立・設置届出書 | 自治体によって異なる |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生から5日以内 |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 事実発生から5日以内 |
会社設立を自分で進める場合、これらの書類はすべて自分で作成し、自分で提出します。専門家に依頼しない場合は、期限を守れるかどうかも自分の管理次第となります。
「会社設立を自分でする方法」編集部
会社設立を自分でする方法や、かかる費用・必要書類については以下のサイトも是非ご覧ください。
「会社設立を自分でする前に知るべきこと|税理士が解説する基礎知識」
会社設立後に自分で必ず行う手続き①
税務署への手続き
会社設立後にまず提出するのが「法人設立届出書」です。これは会社設立を自分で行った場合も必ず必要で、所轄の税務署に自分で届け出ます。法人番号は登記完了後に通知されますが、自分で確認したい場合には国税庁の法人番号公表サイトで調べられます。

次に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を自分で提出します。従業員がいない場合でも、会社設立を自分で進めた経営者本人に役員報酬を支払うため、この手続きは必須です。
会社設立を自分でする方法に関する注意点

提出期限は1か月以内なので、会社設立を自分で完了させた人は忘れないように注意が必要です。
会社設立後に自分で必ず行う手続き②
自治体への届出を自分で行う
会社設立を自分で行った場合、都道府県税事務所と市町村役場へ「法人設立・設置届出書」を自分で提出する必要があります。
会社設立を自分でする方法に関する参考記事:「会社設立の流れを7ステップで解説。メリットや費用、補助金まで」
「会社設立を自分でする方法」編集部
東京23区のように提出先が1か所で済む自治体もありますが、地方では複数の役所に自分で届け出なければなりません。
提出期限は自治体によって異なるため、会社設立を自分で行った人は必ず自分で事前確認を行うことが大切です。
会社設立後に自分で必ず行う手続き③
社会保険関連の手続きを自分で行う
会社設立を自分で行った場合でも、社会保険関連の手続きは避けられません。「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は設立から5日以内に年金事務所へ自分で提出します。法人登記簿謄本などの添付資料も必要になるため、会社設立を自分で経験した人にとっては負担の大きい部分ですが、必ずクリアしなければなりません。
会社設立を自分でする方法に関するおすすめ記事

会社設立を自分でする方法や費用については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立を自分でする方法に関する参考記事:「会社設立は自分でできる?難易度・費用・時間は?代行業者利用の場合と比較検討」
また、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」も会社設立を自分で行った場合には忘れず提出が必要です。従業員がいなくても、役員自身が加入対象となるため、会社設立を自分で行った1人会社でも提出義務があります。
会社設立後に自分で必ず行う手続き④
会社設立を自分で行った後の注意点
会社設立を自分で進めた場合、設立登記だけでなく設立後の手続きまで自分で対応する責任があります。期限を守れないとペナルティが発生するケースもあり、会社設立を自分で完了させた人は「提出書類のスケジュール管理」を徹底することが不可欠です。専門家に依頼すれば代行してもらえる部分も多いですが、自分で会社設立を行う場合には最初から最後まで自分の手で対応しなければならない点を理解しておきましょう。

合わせて読みたい「会社設立を行政書士に依頼」に関するおすすめ記事

会社設立を行政書士に依頼した場合の費用相場は?行政書士の業務範囲についても解説!
【参考】株式会社と合同会社の違いと選び方
会社設立を自分で行うとき、最初に考えるべき重要なポイントが「株式会社にするのか合同会社にするのか」という会社形態の選択です。会社設立の形態には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社がありますが、実際に会社設立を自分で行う起業家の多くが選ぶのは株式会社か合同会社です。会社設立を自分で行う場合には、それぞれの違いを理解して、自分で判断する必要があります。
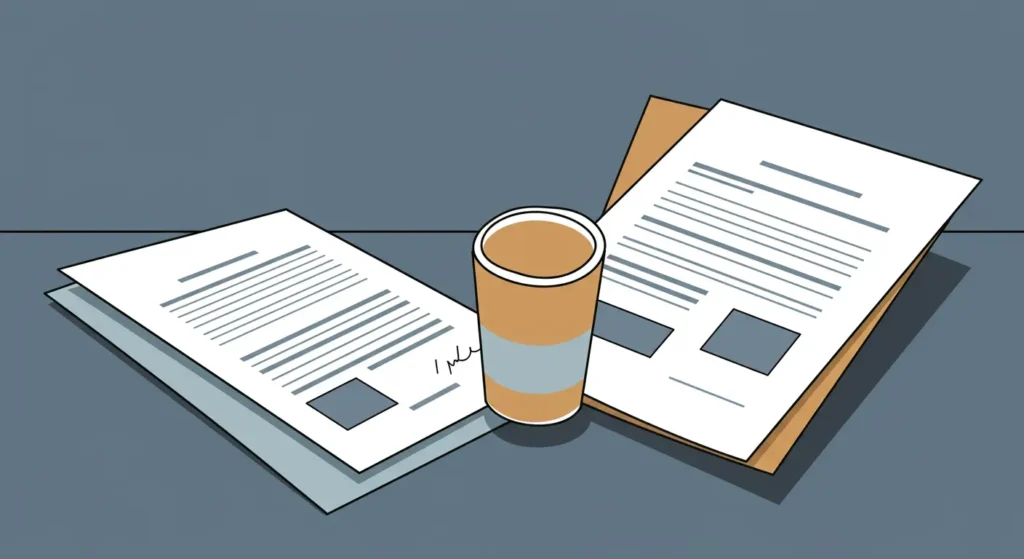
株式会社は信用力と資金調達に強い会社形態
会社設立を自分で行うときに、信用力を重視するなら株式会社が有力な選択肢です。株式会社は株式を発行して資金を集められる仕組みがあり、会社設立を自分で行った後でも外部からの投資を受けやすいのが大きなメリットです。
会社設立を自分でする方法に関するポイント!

株式会社という肩書き自体が社会的信用につながるため、名刺に「株式会社」と記載するだけで金融機関や取引先から信頼されやすくなります。

合わせて読みたい!「会社設立時の費用」に関するおすすめ記事
会社設立時に税理士に依頼した時にかかる費用とメリットを解説

また、株式会社は株主と経営者を分けられる構造を持つため、規模が大きくなっても運営しやすい点が特徴です。会社設立を自分で進める場合でも、株式会社を選べば将来的に株式上場や大規模な資金調達の道が開けます。ただし、株式会社で会社設立を自分で行う場合には、定款認証費用や登録免許税などで20万円前後の初期費用がかかり、決算公告などの維持コストも発生します。
「会社設立を自分でする方法」編集部
会社設立を自分でする方法や、かかる費用・必要書類については以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立を自分でする方法に関する参考記事:「会社設立「自分でやる」VS「専門家に依頼」どちらがおトクなの?」
合同会社は低コストで柔軟な会社設立が可能
会社設立を自分で行う際に、初期費用をできるだけ抑えたい人に向いているのが合同会社です。合同会社は2006年の会社法改正で導入された新しい会社形態で、会社設立を自分で進めるときにも非常に人気があります。合同会社では定款認証が不要で、登録免許税も株式会社に比べて安いため、会社設立を自分で行った場合の費用は6〜10万円程度に抑えられます。
さらに、合同会社は出資者がそのまま経営者になる仕組みのため、会社設立を自分で進めた後も意思決定がスピーディーに行えます。
「会社設立を自分でする方法」編集部
利益配分についても、出資比率にとらわれず定款で自由に決められるので、会社設立を自分で行う少人数の経営に最適です。
加えて、役員の任期管理や決算公告の義務もないため、会社設立を自分で進めた後の維持コストも低く抑えられるのが魅力です。ただし、合同会社は株式会社に比べて知名度や信用力が低いため、会社設立を自分で行った場合、大手企業との取引では不利になるケースもあります。
会社設立を自分で行う場合の会社形態の選び方
会社設立を自分で行う際に、将来的に株式上場や大規模な資金調達を目指すのであれば、株式会社を選ぶのが適しています。逆に、少人数で事業を始めたい、できるだけ安い費用で会社設立を自分で行いたいという場合には合同会社を選ぶのが合理的です。
また、会社設立を自分で合同会社として始め、事業が拡大してから株式会社へ変更することも可能です。つまり、会社設立を自分で行う際には、現在の資金状況だけでなく将来の事業計画も踏まえて、自分で最適な会社形態を選択することが大切です。
会社設立を自分でする方法に関するおすすめ記事

会社設立を自分でする方法や費用については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立を自分でする方法に関する参考記事:「自分で合同会社を設立するときの費用の目安と内訳は?設立後にかかるランニングコストと注意点」
まとめ|会社設立を自分で行う方法
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立は、自分で行う方法と専門家に依頼する方法のどちらを選ぶかによって、費用や手間、そして得られる経験が大きく変わります。会社設立を自分で行えば、登録免許税や定款認証料、印鑑費用といった法定費用だけで済むため、専門家に支払う報酬を節約できます。会社設立を自分で進めることは、コスト削減という大きなメリットがあるだけでなく、定款作成や登記の流れを自分で経験できるため、経営者として必要な法律・税務の知識を自分で身につけられるという学びにもつながります。
一方で、会社設立を自分で行う場合は、会社の基本事項を自分で決め、法人印鑑を自分で作成し、定款を自分で用意して認証を受け、資本金を自分で払い込み、登記申請書類を自分で作成して提出する必要があります。さらに、会社設立後には税務署や年金事務所、都道府県税事務所・市町村役場へ必要書類を自分で提出しなければならず、提出期限を守るためには自分でスケジュールを管理する力も求められます。会社設立を自分で完了させることは可能ですが、時間と労力をかけて全てを自分で処理する覚悟が必要です。
その一方で、会社設立を全て専門家に依頼すれば、自分でやる作業は最小限にとどまり、登記や定款に関するミスを防げます。費用はかかりますが、手間を大幅に削減でき、安心して会社設立を進められるのが大きな魅力です。また、電子定款だけを専門家に依頼して、それ以外は自分で会社設立を進めるという中間的な選択肢もあり、この方法なら費用と効率の両方をある程度両立できます。
結論として、会社設立を自分で進めるかどうかは「費用を節約したいのか」「効率を重視するのか」「知識や経験を得たいのか」といった観点で判断するのが良いでしょう。費用を抑えたいなら会社設立を自分で行うのが最適ですし、スピードと正確さを求めるなら専門家に依頼するのが安心です。そして、費用をある程度抑えつつ効率を求めたい人は、電子定款だけ専門家に任せて残りを自分で行う方法が適しています。
会社設立を自分で行うのは大変な作業ですが、得られる学びと経験は大きな財産となります。逆に、会社設立を自分で行う余裕がない場合は専門家の力を借りるのが賢い選択です。自分で挑戦するのか、専門家に依頼するのか、自分でしっかり比較検討し、納得できる方法で新しいスタートを切りましょう。

合わせて読みたい「freee会社設立で会社設立する方法」に関するおすすめ記事

freee会社設立で会社設立をする方法を解説!freeeで会社設立をするメリットとデメリットも紹介
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!