会社設立日と決算日はいつにすべき?決める際のポイントと決算日の変更手続きについて解説!
カテゴリー:
公開日:2025年4月
更新日:2026年2月12日
会社設立日が決まった後、「決算日」をいつにすべきか悩む方は多いのではないでしょうか。
会社設立日と決算日の関係は、法人運営において非常に重要です。なぜなら、会社設立日を起点として、事業年度が始まり、決算日までの期間で法人の収支や活動がまとめられるからです。会社設立日と決算日をどのように設定するかによって、税金の納付時期、会計処理の負担、消費税の免税期間、資金繰りのタイミングなど、さまざまな面で影響を受けます。
たとえば、会社設立日と決算日が近すぎると、設立直後の多忙な時期に決算業務が重なってしまい、業務負担が増加する可能性があります。一方、会社設立日からある程度期間を空けて決算日を設定すれば、準備期間を確保でき、初年度の資金計画や経営方針を整える余裕も生まれます。
また、会社設立日からの期間が短すぎると、消費税の免税期間が短縮されてしまう場合もあり、会社設立日と決算日の設定は、税務面でも非常に大きな意味を持ちます。
本記事では、会社設立日と決算日の関係を踏まえて、最適な決算日の決め方、会社設立日から見た決算日の注意点、そして決算日の変更手続きについても詳しく解説します。これから法人を設立する方、すでに会社設立日が決まっている方は、ぜひ参考にしてください。
「会社設立日と決算日」編集部
適切な決算日を選ぶことが、会社設立1年目をスムーズに乗り切る大きなカギとなります。

合わせて読みたい「会社設立日と事業開始日」に関するおすすめ記事

会社設立日の決め方とは?会社設立日と事業開始日の違いも解説!
会社設立日や決算日なども無料相談可能!
株式会社と合同会社のどちらの法人格が良いのか?資本金はいくらにするのが良いのか?決算月はいつが良いのか?なども相談できるので、自分でやるよい安心して会社設立が可能です。設立後のサポートも充実しています。
※自分で会社設立するより○万円お得という設立支援業者は、条件が厳しい傾向があるのでご注意ください。
目次
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
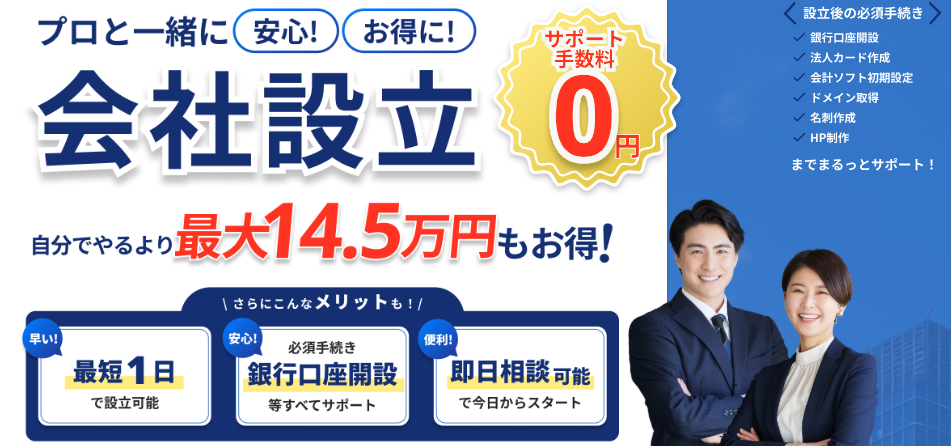
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
決算日とは
決算日とは、1年間の経営活動の締めくくりとして、収支や資産の状況を整理する日のことです。事業年度の最終月にあたるこの決算日は、会社の財務状況を明らかにする重要なタイミングです。個人事業主は12月が固定の決算日とされていますが、法人の場合は会社設立日に関係なく、1年のうち任意の月を決算日として自由に設定できます。
会社設立日と決算日に関するおすすめ記事

会社設立日と決算日に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立日と決算日に関する参考記事:「決算月はいつにする?会社設立時の決算月の決め方・変更方法を解説!」
「会社設立日と決算日はいつがおすすめ?」編集部
法人で一番多い決算月が3月(全体の約2割)で、次に9月・12月決算が多いのが現状です。
「決算月(決算期)とは?設定されることが多い月や決め方、変更手続きを紹介!」
決算日に行う業務

決算日には、会社設立日からその年度末までの収支や資産の状況を集計し、決算書の作成準備を行います。具体的には、棚卸や経過勘定の整理などを通じて、決算書の基礎となるデータをまとめます。こうした決算書は、株主総会の開催や、法人税などの税務申告手続きにも使われるため、会社設立日からの経営の流れを正確に反映させることが求められます。
会社設立日と決算日に関する参考記事:「【コラム】会社設立日はいつが良い?決算日とともに見る会社設立」
他社の決算日の傾向
すべての法人は、年1回の本決算を行うことが法律で定められています。なかには中間決算も併せて行う法人もあり、会社設立日に応じて柔軟に決算日を設定しているケースも見られます。
国税庁が公開している統計によれば、会社設立日に関わらず3月を決算日としている法人が最も多く、次いで9月決算を採用している法人が目立ちます。また、中間決算を含めて見ると、3月・9月、6月・12月を決算期とする法人も多く存在しています。
会社設立日と決算日に関するおすすめ記事

会社設立日と決算日に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
「会社設立をしたら決算月はいつがおすすめ?節税を考えた決め方」
「会社設立日と決算日」編集部
特に、3月を決算日として4月から新年度をスタートさせる企業が多いのは、会社設立日から逆算して行政機関や教育機関の年度に合わせている背景があるためです。
会社設立日と決算日に関するポイント!

大学の卒業や新卒採用のタイミングに合わせることで、事業運営がスムーズになるという理由からも、3月決算が主流になっています。
決算日は会社設立日から自由に設定できる
法人を設立する際、まず知っておくべきことの一つが「決算日」の決定です。決算日とは、会社が一定期間の経営状況や収支を締めて決算書を作成するための日であり、法人にとって極めて重要な節目となる日です。決算日は、会社の「事業年度の最終日」にあたるため、この日を基準に法人税などの税金の申告・納付期限が決まります。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
個人事業主とは異なり、法人では決算日を自由に設定することができます。たとえば、会社設立日が5月25日であった場合、そこから1年以内であれば、翌年の4月30日を決算日に設定することも可能です。
「会社設立日と決算日」編集部
法律上は、会社設立日の翌日から1年以内であれば、どの日を決算日にしても問題ありません。
さらに、決算日は必ずしも月末である必要はありません。4月18日や9月10日など、月の途中を決算日として指定することもできます。ただし、実務上の利便性や帳簿の整理、会計処理のしやすさを考慮すると、多くの法人が月末を決算日にしています。月末を決算日にすることで、支払いや請求などの経理業務とスムーズに連動させることができるため、効率的な運営が可能になります。
会社設立日と決算日に関する気をつけておきたい注意点

会社設立日と決算日の関係は、設立後の初年度の会計期間に直接影響を及ぼすため、非常に重要です。
もし会社設立日と決算日が近すぎると、初年度の営業期間が極端に短くなり、決算の準備に追われるだけでなく、売上や利益が不十分な状態で法人税や住民税の負担が発生するリスクもあります。

合わせて読みたい「合同会社 社会保険 設立」に関するおすすめ記事

合同会社を設立したときの社会保険への加入義務は?必要な書類や手続きをわかりやすく解説

「決算前にできる節税方法」編集部
決算前にできる節税方法に関しては、【決算前に経費を使う理由とは?利益調整や節税対策について解説】の記事も是非ご覧ください。
そのため、決算日は事業の立ち上がりや資金繰りの流れ、さらには税理士との連携タイミングなども含めて、戦略的に設定することが大切です。会社設立日を迎えたばかりのタイミングであっても、将来を見据えた適切な決算日の設定が、安定した法人経営への第一歩となります。
会社設立日と決算日に関するおすすめ記事

会社設立日と決算日に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立日と決算日に関する参考記事:「事業年度とは?会計期間との違いや決算期の決め方を解説」
このように、法人の決算日は、単なる締め日ではなく、経営判断・資金計画・税務戦略などに密接に関わる重要な日です。会社設立日とあわせて、自社のビジネスモデルや業界の特性を考慮しながら、最適な決算日を選びましょう。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立日と決算日を決める際の重要な注意点
会社は会社設立日から自由に決算日を決めることができます。しかし、安易に会社設立日の直後に決算日を設定してしまうと、事業開始後の運営や税務において不利になるケースもあります。ここでは、会社設立日とあわせて決算日をどう設定するべきか、その注意点を詳しく解説します。

合わせて読みたい「会社設立日の決め方」に関するおすすめ記事

会社設立日の決め方は?決め方のポイントやおすすめの日も紹介!
会社設立日と決算日を決める際の重要な注意点①
会社設立日と決算日が近すぎないようにする
まず、最も基本的な注意点は、会社設立日と決算日の間隔を十分に空けることです。会社設立日の直後は、登記や銀行口座の開設、税務署への届出などさまざまな手続きが集中するため、経営に専念する時間が限られます。
「会社設立」編集部
会社設立(法人化)のメリットとデメリットに関しては、【法人化のメリット・デメリットとは?法人化の適切なタイミングについても解説!】の記事も是非ご覧ください。
このような中で、会社設立日からすぐに決算日を迎えてしまうと、わずかな営業期間で決算を組む必要が出てきてしまい、売上が伸びないまま赤字決算となる可能性もあります。
会社設立日と決算日に関するポイント!

特に、赤字でも法人住民税の均等割などの税金は発生するため、会社設立日の直後に決算日を設定するのは避けた方が無難です。
会社設立日と決算日に関するおすすめ記事

会社設立日と決算日に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立日と決算日に関する参考記事:「決算日がわからないときの調べ方」

合わせて読みたい「法人設立ワンストップサービス」に関するおすすめ記事

法人設立ワンストップサービスとは?メリットや注意点を解説!
会社設立日と決算日を決める際の重要な注意点②
キャッシュフローと納税時期のバランスを取る
「合同会社の決算申告」編集部
決算や平時に合同会社にかかる税金については、【合同会社が売上なしでも払う税金とは?赤字(利益ゼロ)の場合の納税について解説】の記事も是非ご覧ください。
会社設立日から数えていつを決算日に設定するかは、納税時期との関係でも重要なポイントです。法人税、法人住民税、法人事業税、消費税といったさまざまな税金は、すべて決算日の翌日から2か月以内に申告・納付しなければなりません。
会社設立日と決算日に関する参考記事:「会社設立時の決算日の決め方。損をしないための3つのポイントを解説!」
たとえば、会社設立日からちょうど1年後を決算日に設定した場合、その2か月後には多額の納税資金が必要になるため、あらかじめ資金計画を立てておく必要があります。ボーナス支給や経費の集中などと納税時期が重なると、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性もあるため、会社設立日とキャッシュフローを基準に決算日を決定することが大切です。

合わせて読みたい「法人が赤字決算の場合の税金」に関するおすすめ記事

法人で赤字の場合に免除される税金とは?納税の有無や赤字決算のメリット・デメリットを紹介!

会社設立日と決算日を決める際の重要な注意点③
繁忙期との重なりを避ける
「会社設立日と決算日」編集部
会社設立日から業務が本格化していく中で、特定の時期が繁忙期になる企業も多くあります。
会社設立日と決算日に関する気をつけておきたい注意点

売上が最も高くなるタイミングと決算日が重なると、会計処理や経営判断に十分な時間が取れず、本業のパフォーマンスに悪影響が出るおそれがあります。
一方で、繁忙期に決算日を設定することで、利益のピークに合わせて財務報告を出すというメリットもあります。こうした判断も、会社設立日からの営業スケジュールをもとに検討するのが良いでしょう。
決算に関する参考記事:「法人の決算月は税理士に相談すべき?決め方と変更方法について解説!」

合わせて読みたい「会社設立時の借入方法」に関するおすすめ記事

会社設立時の借入方法を紹介!開業資金でおすすめの融資とは?
会社設立日と決算日を決める際の重要な注意点④
税理士の繁忙期を意識しておく
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立日からしばらく経つと、税理士との連携も必要になります。特に11月〜5月は税理士業界の繁忙期であり、確定申告や年末調整、決算対応が重なる時期です。もし会社設立日から1年以内に決算日を設定し、さらに税理士の繁忙期と重なると、十分なサポートを受けられない可能性もあります。

合わせて読みたい「会社設立を行政書士に依頼」に関するおすすめ記事

会社設立を行政書士に依頼した場合の費用相場は?行政書士の業務範囲についても解説!
「会社設立日と決算日」編集部
会社設立日を基準に、税理士と早めにスケジュールを調整し、相談しやすい時期に決算日を持ってくると安心です。
会社設立の関連記事:「会社の作り方を徹底解説!必要な手続きと費用について」
会社設立日と決算日を決める際の重要な注意点⑤
消費税の免税期間を最大限に活用する
資本金が1,000万円未満の法人は、会社設立日から原則として2期分、消費税の納税義務が免除されます。ただし、この「2期」というカウントは、「2年間」ではない点に注意が必要です。
「会社設立日と決算日」編集部
会社設立日と決算日に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
会社設立日と決算日に関する参考記事:「決算期(決算月)はいつにすべき?決め方や変更手続きについて解説」
たとえば、会社設立日から2か月後を決算日にしてしまうと、1期目がわずか2か月間となり、消費税の免税期間は合計でも14か月ほどに短縮されてしまいます。
会社設立日と決算日に関するポイント!

可能な限り免税期間を長く確保するには、会社設立日から1年程度離れた時期に決算日を設定するのが有効です。
「会社設立日と決算日」編集部
インボイス制度の影響で、課税事業者としてスタートする必要がある企業も増えていますが、状況に応じて会社設立日と決算日を見直し、戦略的に判断しましょう。

合わせて読みたい「インボイス 2割特例 いつまで」に関するおすすめ記事
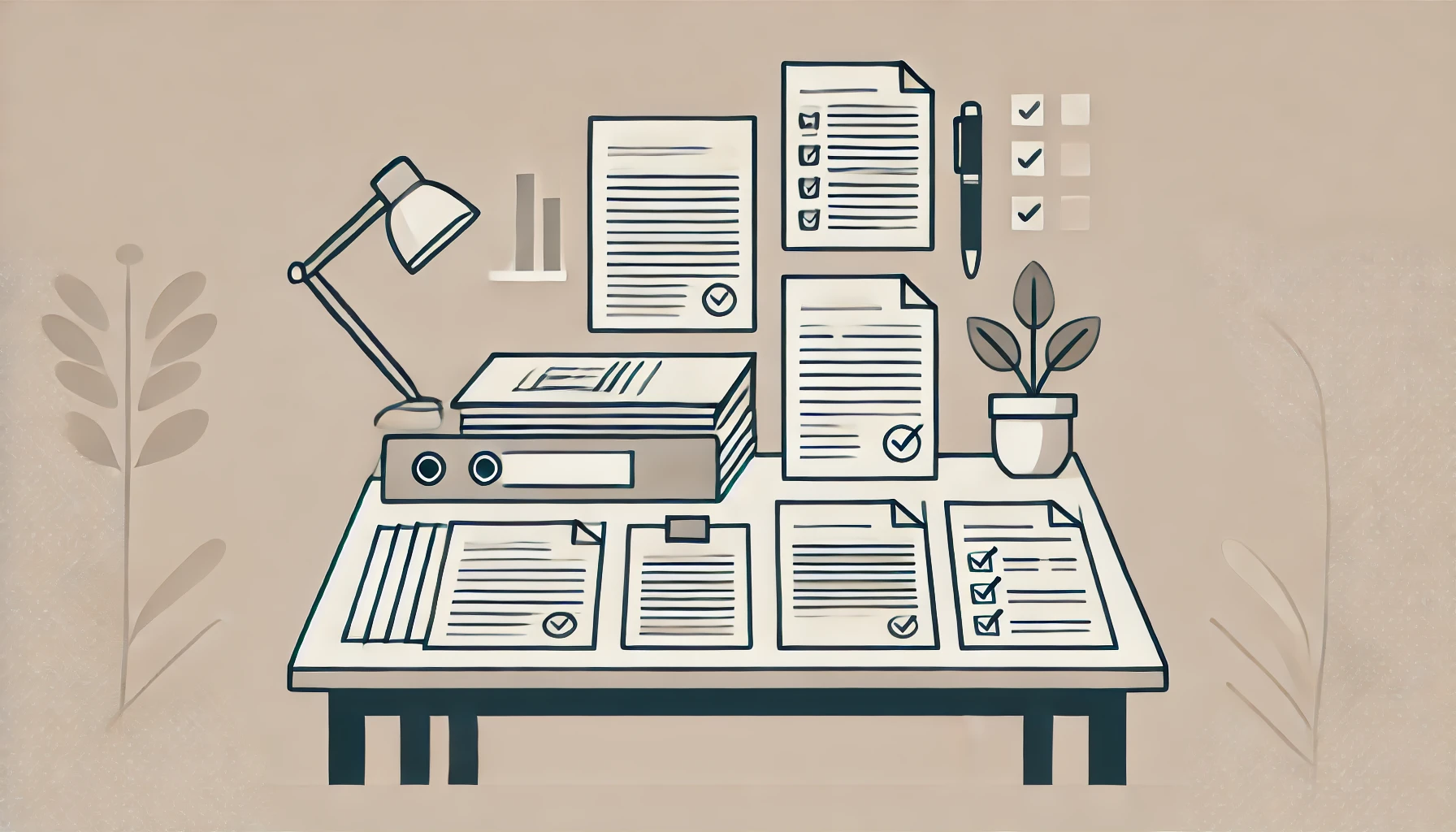
インボイスの2割特例はいつまで?2割特例の計算方法も解説!
会社設立日と決算日を決める際の重要な注意点⑥
取引先やグループ会社の決算日も確認する

合わせて読みたい「会社設立を司法書士に依頼」に関するおすすめ記事
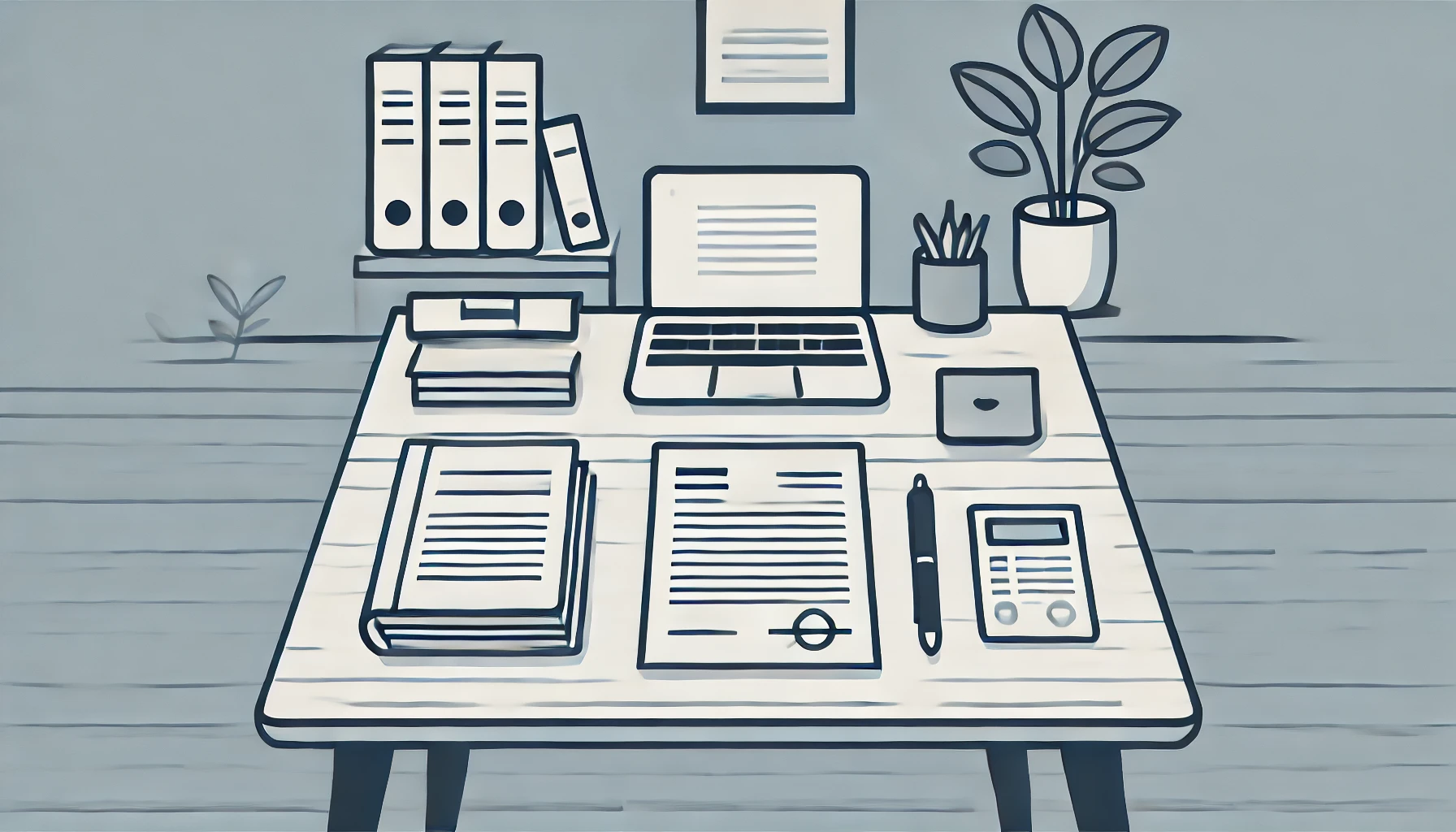
会社設立を司法書士に依頼した場合の費用相場を解説!司法書士に会社設立を依頼するメリットも紹介
会社設立日の段階で主要な取引先が決まっている場合は、相手先の決算日と足並みを揃えることで、資料の提出時期や取引の調整がスムーズになることもあります。また、親会社がある場合には、連結決算の都合上、同じ決算日を採用することが求められるケースもあるため、会社設立日からの計画とあわせて事前に確認しておくとよいでしょう。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
決算期の変更は可能
「会社設立日と決算日」編集部
会社設立日と決算日に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
「決算日とは?会社が決算日を決める際の注意点や変更方法などを解説」
会社を立ち上げた際に定める「決算期」は、企業の1年間の活動を締めくくる重要な時期であり、「決算日」はその最終月の中で事業年度を締める具体的な日を指します。多くの企業が「会社設立日」と同じタイミングで決算期や決算日を決める傾向にありますが、実はこの「決算日」は「会社設立日」に関係なく、後から変更することが可能です。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
例えば、会社設立日が5月1日であっても、初年度の決算日を4月30日にしたり、将来的に決算日を9月末に変更したりすることができます。このように、会社設立日から1年以内であればどの月を決算日にするかは自由であり、さらに後から決算日を見直すこともできます。
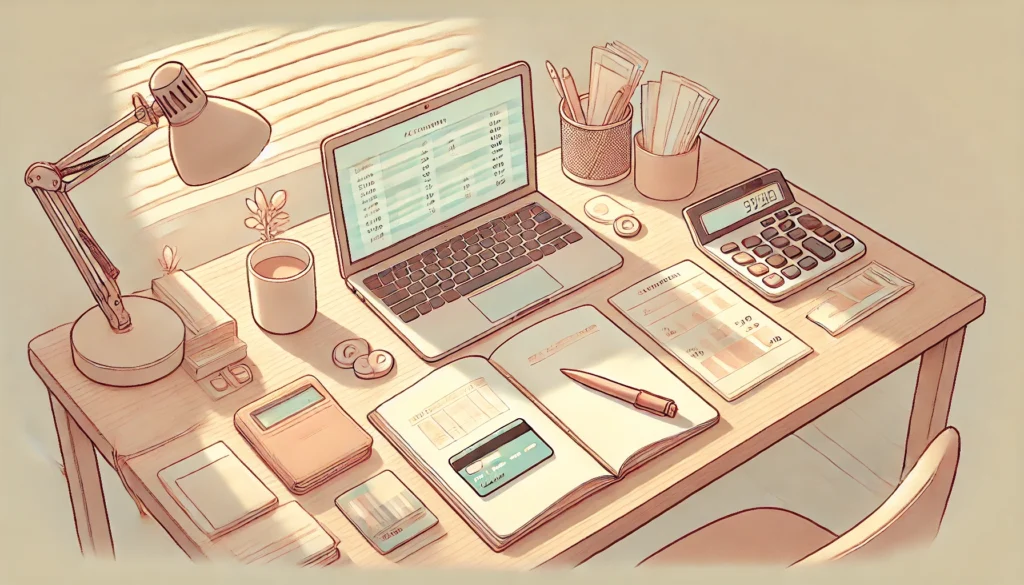
とはいえ、決算日を変更するには定款変更や株主総会での決議、税務署への届出など、正式な手続きが必要です。また、会社設立日からあまり日が経っていない時期に決算日を迎えてしまうと、売上が十分に上がらず赤字決算となるリスクもあります。赤字であっても、法人住民税の均等割など一部の税金は会社設立1年目から課税されるため、会社設立日と決算日の間隔には十分な余裕をもたせることが重要です。

合わせて読みたい「法人番号と会社法人等番号の違い」に関するおすすめ記事
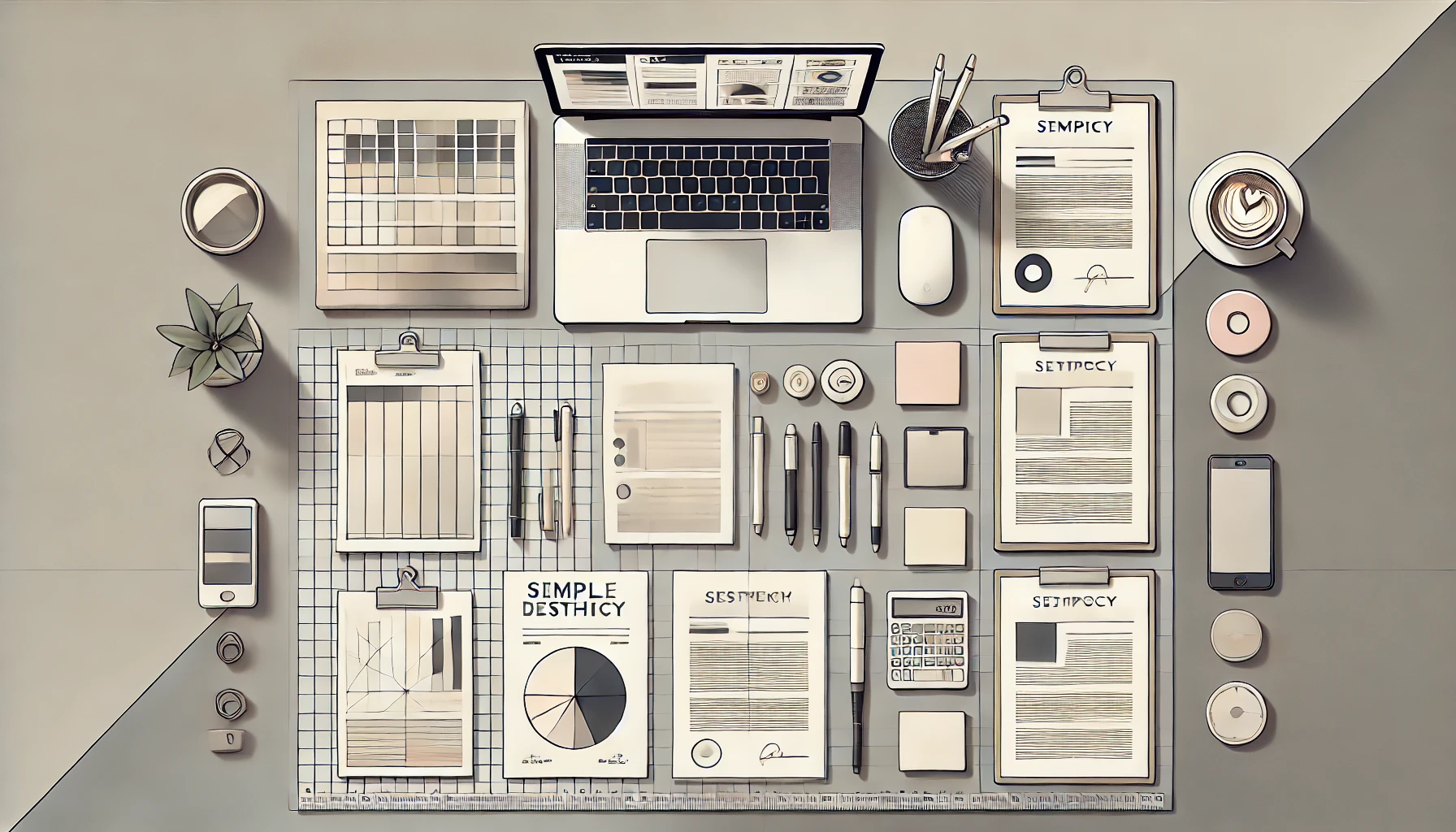
法人番号と会社法人等番号の違いとは?調べ方や使い道も紹介!
「会社設立日」編集部
間違えやすい会社設立日と登記日の違いについては以下の記事も是非ご覧ください。
会社設立日と登記日の違いに関する参考記事:「会社の設立日は登記日と同じ?設立に関する日付の違いや注意点を解説!」
会社設立日と決算日に関する気をつけておきたい注意点

さらに、決算日を変更するタイミングによっては、消費税の免税期間や資金繰りにも影響を与えることがあります。会社設立日からの2期が消費税の免税対象となるため、決算日をどう設定するかで消費税の負担が変わる可能性もあるのです。
このように、決算日は会社設立日から自由に設定・変更できるものの、その影響は資金計画・税金・業務負担にまで及びます。だからこそ、会社設立日と決算日の関係をよく理解した上で、慎重に決定・変更していくことが求められます。会社設立日からのスケジュールや今後の事業展開を見据えながら、最適な決算日を選びましょう。

合わせて読みたい「融資を税理士に相談したい場合」に関するおすすめ記事
融資を受けるために税理士は必要?依頼するメリットとポイントを解説

会社設立日と決算日に関するポイント!

決算日は会社設立日から自由に設定・変更できるものの、その影響は資金計画・税金・業務負担にまで及びます。だからこそ、会社設立日と決算日の関係をよく理解した上で、慎重に決定・変更していくことが求められます。会社設立日からのスケジュールや今後の事業展開を見据えながら、最適な決算日を選びましょう。
決算期を変更する手続き
会社の決算日や決算期は、法律で固定されているものではなく、会社設立日から自由に設定できるのが特徴です。そして会社設立日に一度決めた決算日であっても、後から変更することができます。つまり、会社設立日を基準に最初に決定した決算日であっても、事業の状況や資金繰り、経営戦略などを考慮して、最適な時期に見直すことが可能なのです。
「会社設立日と決算日」編集部
会社設立日と決算日に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
会社設立日と決算日に関するおすすめ記事
実際、会社設立日に合わせて決算日を短く設定してしまい、数ヶ月で初めての決算を迎えるというケースもありますが、思った以上に準備が大変で本業に支障が出ることもあります。こうした事情から、会社設立日と決算日とのバランスを見直して、後から決算日を変更する企業も少なくありません。

合わせて読みたい「マイクロ法人 決算 自分で」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の決算は自分でできる?税理士なしで自分でやる手順を解説!
本記事では、マイクロ法人の決算を自分で行う際に知っておくべき基本知識から、具体的な手順、注意点までを解説します。大きなミスを防ぎ、安全にマイクロ法人の決算を乗り越えられるよう、しっかりと知識を身につけていきましょう。
会社設立日と決算日に関するポイント!

決算期を変更するためには一定の手続きが必要ですが、費用は特にかかりませんし、登記変更も不要です。
「会社設立日と決算日」編集部
以下が基本的な流れです。
決算期を変更する手続き STEP1
株主総会での特別決議
多くの会社では、会社設立時に作成した定款に事業年度(=決算期)を記載しています。そのため、決算日を変更するには定款を修正する必要があり、株主総会にて特別決議を行う必要があります。会社設立日に定めた内容であっても、事業年度の見直しは可能です。

合わせて読みたい「会社設立時に法務局で行う手続き」に関するおすすめ記事

会社設立時に法務局で行う手続きを解説!会社設立登記に必要な書類も紹介
決算期を変更する手続き STEP2
株主総会議事録の作成
株主総会で決算日変更に関する決議がなされたら、その内容を正式に記録した株主総会議事録を作成します。会社設立日からまだ間もない企業でも、この書類は必須です。
「決算申告のみ税理士に依頼」編集部
法人の決算申告(確定申告)のやり方や申告する税金の種類については以下のサイトも是非ご覧ください。
「法人の確定申告のやり方とは?税金の種類・提出書類・申告期限・手続きの流れを解説」
決算期を変更する手続き STEP3
税務署などへの異動届出書の提出
会社設立日と決算日に関するおすすめ記事

会社設立日と決算日に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
「【4step】会社設立時の決算月の決め方を税理士が解説!」
変更後は、所轄の税務署・都道府県税事務所・市区町村に対し、異動届出書を提出します。この際、作成した議事録の写しを添付して提出します。会社設立日や前回の決算日と照らし合わせながら、提出期限を守るようにしましょう。

合わせて読みたい「法人設立届出書の添付書類」に関するおすすめ記事

法人設立届出書の添付書類は何が必要?税務署に法人設立届出書を提出するポイントも紹介!
決算期を変更する手続き STEP4
関係機関・取引先への通知

決算日の変更が完了したら、必要に応じて金融機関や主要な取引先、会計事務所などに決算日の変更を連絡します。とくに会社設立日直後から密に取引している相手には、早めに通知しておくと安心です。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
また、建設業・医療法人・人材派遣など許認可が必要な業種については、管轄省庁などへも別途決算日変更の届け出が求められる場合がありますので、会社設立日からの事業内容を再確認のうえ対応しましょう。
会社設立日と決算日に関する参考記事:「STEP1‐⑧ 事業年度を決める」
このように、会社設立日に決めた決算日であっても、必要があれば後から見直すことが可能です。会社設立日からの日数や事業の進行状況、資金繰り、消費税の免税期間なども考慮して、経営にとって最適な決算日へと変更していくことが、安定した成長の第一歩といえるでしょう。
決算期を変更する際の注意点
会社設立日から始まる最初の事業年度においても、決算日は自由に設定できますが、事業年度は法律上「1年以内」に収める必要があります。そのため、会社設立日から一度決めた決算日を変更すると、変更した年は必ず会社設立日と新たな決算日の間で1年未満の期間で決算を迎えることになります。
このように、会社設立日に対して変更後の決算日が早く設定されると、事業年度が短縮され、通常より早いタイミングで初回の決算日を迎えることになります。その結果、決算日までに準備すべき書類や会計処理などの作業が前倒しになり、会社設立直後で事業が安定していない時期に、慌ただしく決算を行わなければならない可能性があります。

合わせて読みたい「会社設立に必要な届出」に関するおすすめ記事

会社設立に必要な届出を詳細解説!会社設立後の手続きと届出書を紹介
また、決算日が早まるということは、法人税や法人住民税、法人事業税などの税金の申告と納付のタイミングも早くなるということです。つまり、会社設立日からあまり時間が経っていない段階で、税金の納付資金を確保しなければならず、資金繰りに影響が出る場合もあります。
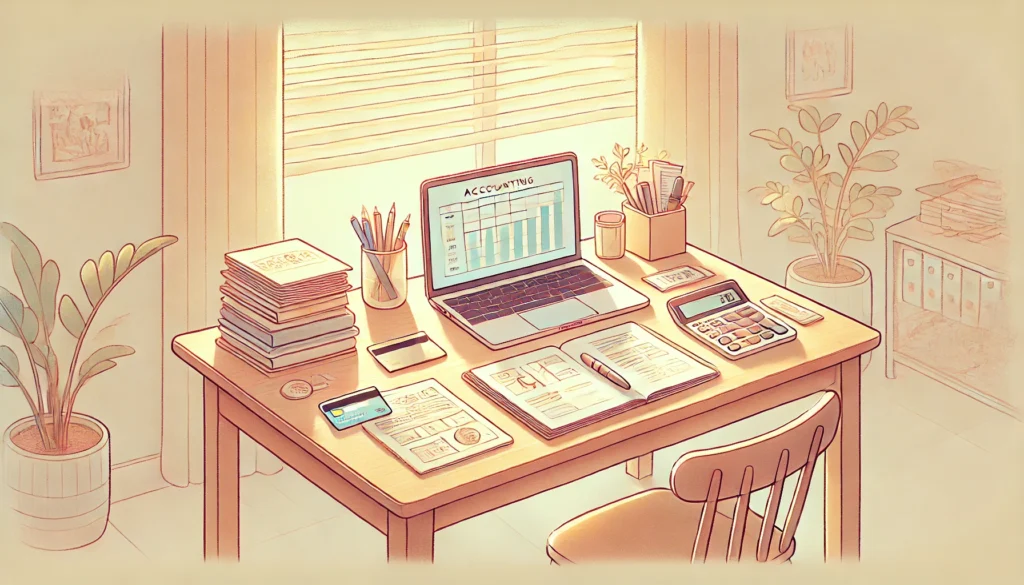
さらに、決算日の前倒しによって、税理士に依頼する決算業務の報酬なども会社設立日から予定していたよりも早く発生することになります。そのため、会社設立日に基づく決算日を変更する場合は、会計業務・納税資金・税理士報酬など、あらゆる費用とスケジュールを改めて見直す必要があります。
会社設立日と決算日に関するポイント!

このように、会社設立日と決算日の関係性は、会社運営のスケジュールやキャッシュフローに直結するため、安易な決算期の変更には十分な検討が必要です。
会社設立日と決算日に関する気をつけておきたい注意点

特に会社設立日から1年目は、経営基盤を固める重要な時期ですので、決算日の設定と変更には慎重を期すようにしましょう。
会社設立でよくある疑問|Q&A
Q.会社設立は最短何日でできる?
会社設立は最短で1週間程度で可能ですが、一般的には2週間~3週間程度と言われています。
また、株式会社よりも合同会社の方が定款の認証手続きが不要であるため、早く会社設立が可能です。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
Q.会社は会社設立後何年で廃業する?
会社の存続率は、会社設立をして3年で約65%、10年で約6%程度です。
つまり、会社設立後10年以内に9割近くが廃業するという事実があります。

合わせて読みたい「税理士に決算のみを依頼するメリット」に関するおすすめ記事

決算申告のみを税理士に依頼する場合のおすすめの方法を解説!
Q.会社設立に必要な資本金の最低額はいくら?
以前まで資本金の最低額は株式会社が1,000万円、有限会社が300万円でしたが、現在は資本金1円から設立することが可能になりました。
まとめ:会社設立日と決算日の関係性を理解しよう

会社設立日を迎えたあとは、次に決めるべき大切な要素が「決算日」です。会社設立日と決算日の関係は、事業年度の長さだけでなく、納税タイミングや経理体制の整備、さらには消費税の免税期間にも大きく影響を与えます。会社設立日からできるだけ離れた時期に決算日を設定することで、初年度の事業準備に余裕を持たせることが可能になります。
また、会社設立日を起点にすると、2期目までの期間で消費税の納税義務が免除されることもあるため、会社設立日と決算日の組み合わせ次第で節税につながるケースもあります。会社設立日から最初の決算日までの期間を戦略的に設定することは、創業初期の資金繰りや経営の安定において非常に重要な判断です。
さらに、決算日は会社設立日から1年以内であれば自由に設定できますが、会社設立日と決算日があまりに近すぎると、早期に決算処理や納税手続きが必要となり、実務負担が大きくなるリスクもあります。会社設立日と決算日をバランスよく調整し、無理のないスケジュールで経営をスタートさせましょう。
なお、一度設定した決算日も会社設立日以降に変更することが可能ですが、その際には株主総会での定款変更や税務署への異動届出書の提出など、手続きが必要です。会社設立日を起点に、将来の決算日をどのように計画するかは、法人経営における重要な戦略のひとつです。最適な決算日を選ぶことで、会社設立1年目から安定した成長を目指しましょう。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「会社を立ち上げるにはいくら必要か」に関するおすすめ記事

会社を立ち上げるにはいくら必要?会社設立費用の詳細を解説!

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日













SoVaをもっと知りたい!