従業員の入社手続き時に会社がすべき対応は?必要書類や保険の加入についても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年3月
更新日:2025年12月23日
新たに従業員を採用した際には、従業員の入社に伴うさまざまな入社手続きが必要となります。入社前の準備をはじめ、従業員の社会保険や税金に関する入社手続き、さらには入社後の社内対応まで、従業員に関わる業務は多岐にわたります。
また、入社手続きの中には期限が定められているものが多く、従業員の入社に際して手続きの漏れや不備がないよう、迅速かつ正確に進めることが重要です。従業員が入社後、スムーズに業務を開始できるよう、円滑に入社手続きを進めましょう。
本記事では、従業員の入社前後に必要な書類や入社手続きの流れについて、詳しく解説します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「新入社員の入社手続き」に関するおすすめ記事

新入社員の入社手続きで必要な準備は?必要書類や具体的な手続き内容を解説!
従業員の入社手続きに必要な書類

会社と従業員の間では、入社手続きの際に必要となる入社書類を準備する必要があります。
会社が従業員の入社前に用意する書類には、雇用契約書・労働条件通知書、扶養控除等申告書を含む全5種類の入社手続き関連書類が必要です。
一方、従業員となる内定者は、雇用保険被保険者証番号、基礎年金番号、給与振込先の口座情報、源泉徴収票、マイナンバーの5種類の書類を提出しなければなりません。
入社手続きにおいて、従業員が入社時に提出する必要がある書類を中心に、会社が用意すべき入社書類と従業員が準備すべきものに分けて解説します。
会社側が従業員の入社手続き時にすべき対応に関するおすすめ記事
会社が従業員の入社前に用意する書類
従業員の入社手続きに必要な書類には、従業員の押印が必要なものや交付義務があるものがあります。
会社が従業員の入社前に用意する主な入社手続き書類
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 扶養控除等申告書
- 健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
- 採用通知書(内定通知書)
- 入社誓約書
これらの入社書類は、返信用封筒を添えて郵送し、従業員が署名・捺印を行い、返送してもらうのが一般的です。
■ 雇用契約書・労働条件通知書
雇用契約書・労働条件通知書は、会社と従業員の間で雇用条件を明確にする重要な入社手続き書類です。雇用契約書には、双方の署名または記名押印が必要であり、労働条件通知書は労働基準法で交付が義務付けられています。
■ 扶養控除等申告書
扶養控除等申告書は、税金や社会保険手続きのために必要な書類で、すべての従業員が入社時に提出する必要があります。
■ 健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
従業員の社会保険加入手続きの際、扶養者がいる場合に必要となる入社手続き書類です。
■ 採用通知書(内定通知書)
採用通知書(内定通知書)は、従業員の入社を正式に通知する書類で、入社手続きの一環として交付されます。
■ 入社誓約書
入社誓約書は、従業員の入社時に必要な誓約書であり、就業規則や秘密保持に関する事項を明記する書類です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
従業員が入社前に用意すべき書類
従業員が入社前に準備する入社手続きに関わる書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者証番号
- 基礎年金番号
- 給与振込先の口座情報
- 源泉徴収票
- マイナンバー
入社手続きに必要なマイナンバーなど、一部の書類は従業員自身が役所で手続きを行う必要があるため、入社前に早めに準備してもらいましょう。

合わせて読みたい「入社 住民税 手続き」に関するおすすめ記事

入社時の住民税に関する手続きについて解説!退職時の住民税の手続きも併せて紹介!
■ 雇用保険被保険者証番号
雇用保険被保険者証番号は、従業員の入社手続きの際に必要な書類であり、過去に雇用保険に加入していた場合に提出が求められます。
■ 基礎年金番号
基礎年金番号は、社会保険手続きに必要な番号で、従業員の年金手帳や基礎年金番号通知書から確認できます。

合わせて読みたい「従業員の退職手続き」に関するおすすめ記事
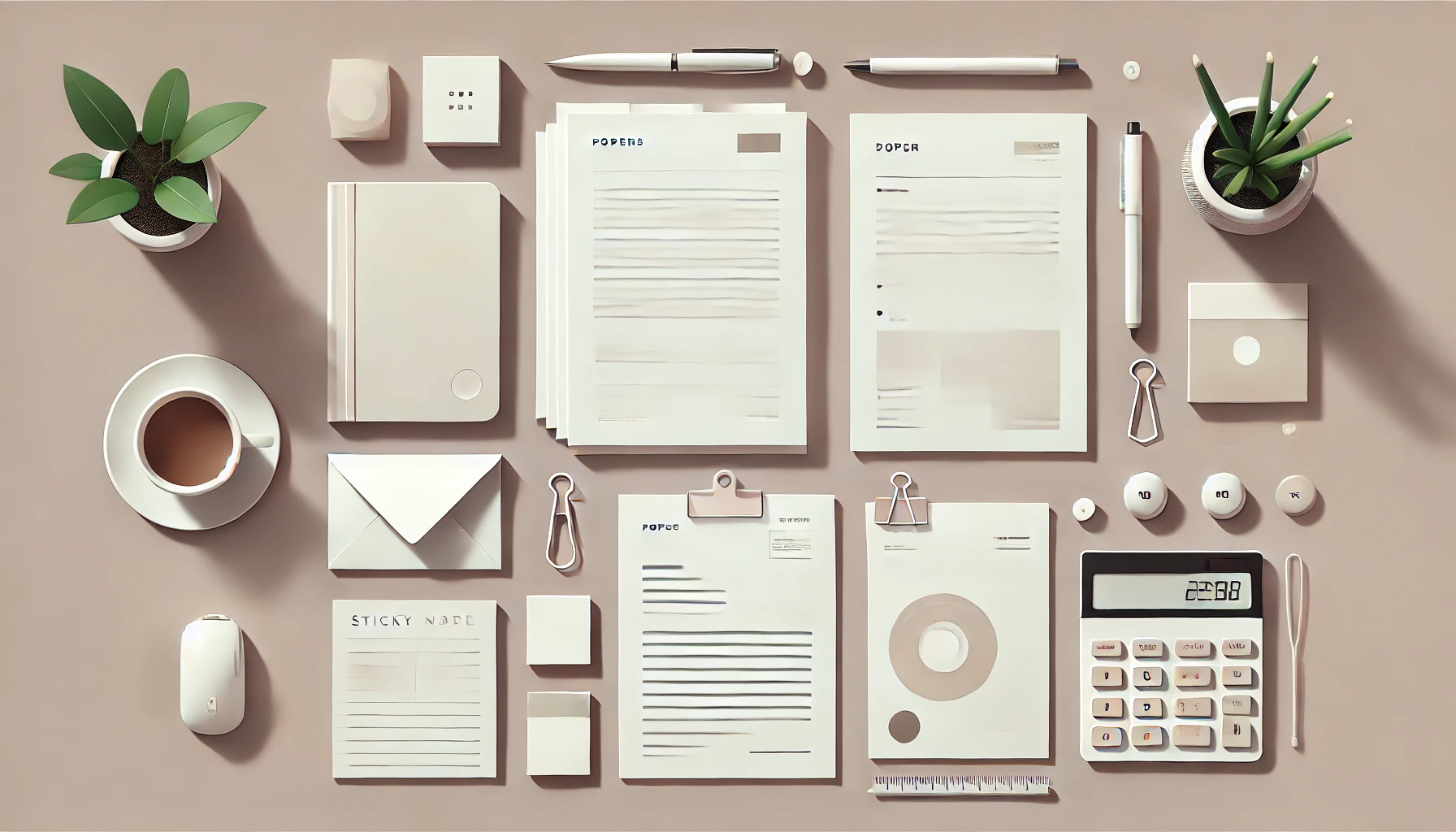
従業員の退職手続きは何をする?必要書類や会社側・従業員側でやることを解説
■ 給与振込先の口座情報
給与振込先の情報は、入社手続きの一環として、従業員が銀行名や口座番号を記入する書類を提出する必要があります。
■ 源泉徴収票
源泉徴収票は、税務手続きに必要な書類で、前職がある従業員は入社時に提出が求められます。
■ マイナンバー
マイナンバーは、税金や社会保険の手続きに必要な書類で、従業員が入社手続きの際に提出します。
SoVa税理士ガイド編集部
入社手続きは、従業員の入社前後に必要な重要なプロセスです。会社と従業員がスムーズに手続きを進めることで、円滑な入社準備を整えましょう。
従業員が入社する前に必要な手続き

従業員の入社手続きは、従業員の採用が決定したタイミングから開始されます。企業が新たに従業員を迎え入れる際には、入社前後に必要な手続きを確実に実施することが重要です。
従業員の入社手続き①:労働条件通知書の作成・送付
従業員の入社手続きの第一歩として、労働条件通知書を作成し、従業員に送付する必要があります。この書類には、給与、勤務時間、雇用形態などの労働条件が明記されており、会社が従業員と雇用契約を締結する際に交付しなければなりません。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
従業員の入社手続きに関するここがポイント!

すべての従業員に対し、入社手続きの一環として必ず作成・送付することが求められます。

合わせて読みたい「アルバイトに有休を付与」に関するおすすめ記事

アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説!
この記事では、アルバイトやパートに対する有給付与の詳細や、有給休暇取得時の賃金計算方法、さらに有給付与に関する注意点について詳しく解説します。アルバイトの有給付与に関する正しい知識を身につけ、適切な運用を行いましょう。
従業員の入社手続き②:雇用契約書の締結
雇用契約書は、従業員と会社の間で締結される契約書で、労働条件や権利義務を明確にするために重要な書類です。入社手続きの中で、労働条件通知書とともに交付し、従業員に署名捺印を求めることが一般的です。
従業員の入社手続き③:採用通知書(内定通知書)の作成・送付
採用が決定した従業員には、採用通知書(内定通知書)を発行し、入社手続きの一環として送付します。これにより、従業員に対し正式な採用決定を通知し、入社の意思を確認することができます。
会社側が従業員の入社手続き時にすべき対応に関する 人材を採用したら?入社手続き等で必要な書類、準備とは
従業員の入社手続き④:入社承諾書(入社誓約書)の締結

合わせて読みたい「新入社員の有休」に関するおすすめ記事

新入社員の有給はいつ・何日付与すべき?有給のルールや注意点を解説!
本記事では、新入社員の有給が発生する条件や付与日数、分割付与の注意点などを詳しく解説します。新入社員の有給を適切に管理し、円滑な職場環境を整えるために、ぜひ参考にしてください。
入社承諾書は、採用された従業員が入社の意思を企業に示すための書類です。入社手続きとして、労働条件通知書や採用通知書とともに送付し、返送を求めることで、入社の確約を取ることができます。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」
従業員の入社手続き⑤:入社時に回収する書類の依頼
入社する従業員には、入社手続きの一環として以下の書類を提出してもらう必要があります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
新入社員が入社した際の手続きなどはこちらの年金事務所のサイトを是非参考にしてください。
- 住民票記載事項証明書
- 源泉徴収票(前職にて給与収入がある場合)
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- マイナンバーの提示
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者証
- 通勤手当申請書
- 口座振込依頼書(給与振込先情報)
会社側が従業員の入社手続き時にすべき対応に関するおすすめ記事
これらの手続きは、従業員の入社を円滑に進めるために不可欠であり、事前に必要書類を従業員へ伝えておくことが重要です。

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
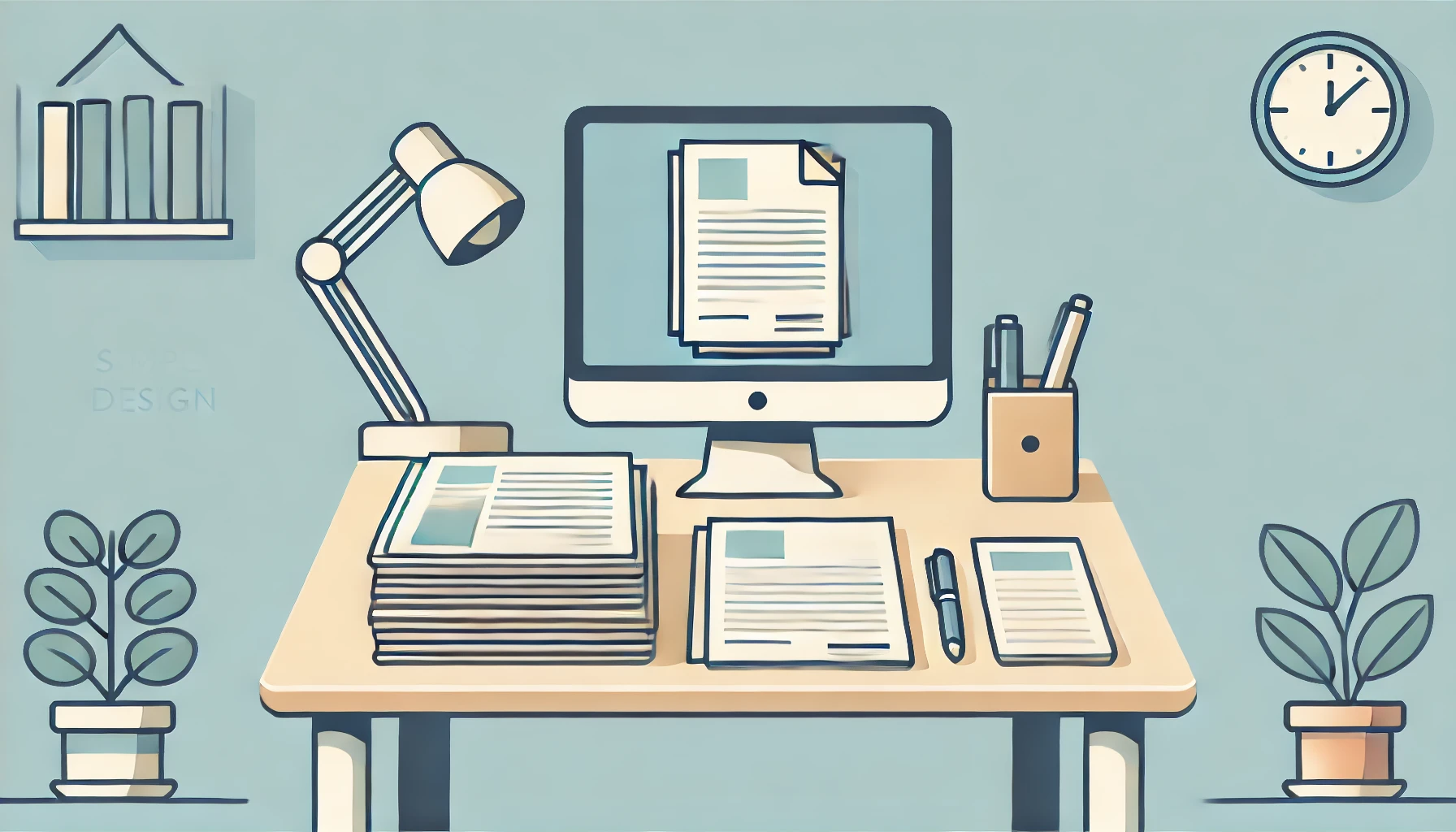
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
従業員が入社した後に必要な手続き

従業員が入社した後は、従業員に関する社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)、税金(所得税・住民税等)の手続きが必要です。入社後の手続きを適切に行うことで、従業員が安心して勤務できる環境を整えることができます。ここでは、従業員の社会保険の加入条件や資格取得手続き、所得税と住民税の手続きについて詳しく解説します。
会社側が従業員の入社手続き時にすべき対応に関するおすすめ記事
従業員の社会保険資格取得手続き
会社を含むすべての法人は、従業員の社会保険加入が義務付けられている「適用事業所」です。個人事業主でも、常時5人以上の従業員を雇用している場合は、一部の業種を除き、従業員に社会保険を適用しなければなりません。

合わせて読みたい「雇用契約書の書き方」に関するおすすめ記事

雇用契約書の書き方とは?2024年の改正についても解説!
適用事業所では、社会保険の加入要件を満たす従業員が入社した際に、社会保険の資格取得手続きを行う必要があります。従業員が社会保険に加入することで、健康保険や年金制度の恩恵を受けることができます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
健康保険・厚生年金保険の加入が必要な従業員の条件は以下のとおりです。
健康保険・厚生年金保険の加入条件
- 適用事業所に常時雇用されている70歳未満(厚生年金)・75歳未満(健康保険)の従業員
- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の従業員
- 40歳以上の従業員は介護保険の加入も必要
また、一定の条件を満たす短時間労働の従業員についても、特定適用事業所では社会保険の加入手続きを行う必要があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険の加入手続きは、従業員の入社日から5日以内に年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出することで完了します。協会けんぽ(全国健康保険協会)以外の健康保険組合に加入している場合は、各健康保険組合でも従業員の手続きを行います。
従業員の雇用保険資格取得手続き
従業員を1人でも雇用する事業所は、雇用保険の適用事業所となり、雇用保険の加入条件を満たす従業員について、適切な手続きを行う必要があります。
雇用保険の加入条件
- 31日間以上の雇用見込みがある従業員
- 週の所定労働時間が20時間以上の従業員
- 昼間部の学生ではない(休学中などの例外を除く)
雇用保険の加入手続きとして、「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。提出期限は、従業員を雇用した翌月10日までです。
従業員の労災保険に関する手続き
従業員を雇用している事業主は、従業員の雇用形態や雇用期間に関わらず、労災保険に加入する義務があります。パートやアルバイトを含めたすべての従業員が労災保険の対象です。
初めて従業員を雇用する際には、「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出し、従業員の労災保険加入手続きを行います。提出期限は、雇い入れから10日以内(労働保険概算保険料申告書は50日以内)ですが、同時提出も可能です。
従業員の税金に関する手続き
従業員の入社に伴い、所得税や住民税の手続きも行う必要があります。
所得税の手続き
従業員の所得にかかる所得税は、給与から源泉徴収(天引き)し、会社が国に納付します。正社員のほか、パートやアルバイトの従業員でも、月収8万8,000円を超える場合は源泉徴収が発生します。
従業員の入社手続きはここがポイント!

源泉徴収の正確な処理のために、入社時に従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、源泉徴収簿を作成します。
住民税の手続き
住民税の納付には「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。従業員が入社する前に普通徴収を選択していた場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出し、特別徴収へ切り替えます。前職で特別徴収を行っていた従業員については、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出し、手続きを継続します。
従業員の入社時に必要なその他社内手続き

従業員の入社にあたっては、社会保険や雇用保険の手続きだけでなく、社内での各種手続きも必要です。社会保険の手続きのように法的な期限が定められているわけではありませんが、従業員がスムーズに勤務を開始できるよう、できるだけ迅速に手続きを進めることが求められます。
法定三帳簿の作成手続き
従業員を1人でも雇用した場合、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の法定三帳簿を作成する手続きが必要です。これらの帳簿は、従業員の雇用状況を記録し、一定期間の保存が義務付けられています。従業員が入社した際には、速やかに作成し、適切に管理しましょう。
労働者名簿の作成手続き
労働者名簿は、従業員の氏名や生年月日、性別、住所などの個人情報を記録する重要な帳簿です。法令で定められた記載項目のほか、会社が従業員の管理を行うために必要な情報を追加することも可能です。従業員が入社した際には、正確な情報をもとに作成しましょう。
会社側が従業員の入社手続き時にすべき対応に関する 従業員の雇用手続きについて解説!必要書類や加入する保険は?
賃金台帳の作成手続き
賃金台帳は、従業員一人ひとりの賃金の支払い状況を管理する帳簿であり、従業員の給与計算に必要な情報を記載します。入社した従業員の基本給や手当、労働時間数、支給額などを正確に記録し、給与計算の際に活用します。
出勤簿の作成手続き
出勤簿は、従業員の出退勤状況を管理するための帳簿であり、労働時間の記録としても活用されます。従業員が入社したら、出勤日、労働時間、休憩時間、時間外労働の記録を適切に行うようにしましょう。
会社側が従業員の入社手続き時にすべき対応に関するおすすめ記事
従業員の入社に伴う執務環境の整備と手続き
従業員が入社した際、業務を円滑に進められるよう、執務環境の整備や貸与品・備品の提供手続きを行います。具体的には、以下のような準備を行います。
- 机、椅子、パソコン、事務用品の準備
- 名刺、社員証の発行手続き
- メールアドレスや社内ネットワークのID・パスワードの設定
- 制服の貸与(必要に応じて事前にサイズ確認を実施)
SoVa税理士お探しガイド編集部
入社した従業員がすぐに業務を開始できるよう、これらの手続きを入社前に完了させることが望ましいです。
従業員情報の給与計算・人事システムへの登録手続き
従業員が入社したら、給与計算や人事管理のために必要な情報を給与計算システムや人事システムへ登録する手続きを行います。具体的には、以下の情報を登録します。
- 従業員の氏名、住所、生年月日
- 扶養控除の適用状況(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づく)
- 通勤手当、家族手当などの支給手続き
- 社会保険や雇用保険の加入情報
これらの情報を正確に入力し、従業員の給与計算や各種手続きに支障がないように準備を整えます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
従業員の社会保険・雇用保険手続き遅延時の対処法

会社側が従業員の入社手続き時にすべき対応に関するおすすめ記事
従業員の入社後、社会保険や雇用保険の手続きが遅れた場合は、適切な対応が求められます。特に、手続きが本来の届出日から60日以上遡る場合には、必要な書類を準備し、速やかに報告を行うことが重要です。
手続き遅延時に提出すべき書類
| 保険の種類 | 提出書類 |
|---|---|
| 社会保険 | 遡る全期間分の賃金台帳、出勤簿 |
| 雇用保険 | 遡る全期間分の賃金台帳、出勤簿、遅延理由書 |
社会保険や雇用保険の手続き漏れが発覚した場合は、従業員の入社日を基に書類を準備し、提出を行う必要があります。
雇用保険の遡及適用は原則として過去2年間ですが、従業員の給与から雇用保険料の控除が確認できる場合に限り、2年以上遡ることも可能です(聴取書の提出が必要)。
従業員の年金手帳・雇用保険被保険者証の紛失時の手続き
従業員が年金手帳や雇用保険被保険者証を紛失した場合、再交付の手続きを行う必要があります。
年金手帳の再交付手続き
- 従業員の個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を記載した「年金手帳再交付申請書」を提出し、再交付を申請します。
- 再交付には手数料はかかりません。
雇用保険被保険者証の再交付手続き
- 従業員本人が前職の会社に問い合わせ、雇用保険被保険者番号を確認する。
- もしくは、従業員がハローワークに本人確認書類と前職の会社名・住所がわかる書類を持参し、「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して再交付を受ける。
- 雇用保険被保険者資格取得届に履歴書など前職の会社名が記載された書類を添付すれば、雇用保険被保険者番号が不明でも手続きを進めることが可能。
SoVa税理士ガイド編集部
いずれの再発行手続きも、電子申請による対応が可能です。
従業員の入社後の各種手続きが滞ることなく進められるよう、手続きの遅延や紛失が発生した場合には、速やかに対応を行いましょう。
まとめ

新入社員の入社手続きは、従業員の安心と会社の信用に直結するため、従業員ごとに丁寧かつ迅速な手続きを行うことが求められます。
従業員の入社手続きで気をつけておきたい注意点

入社手続きに不備があると、従業員に不安を与えるだけでなく、会社が行政指導を受ける可能性もあります。
従業員の入社手続きをスムーズに進め、作業ミスを防ぐためには、人事労務担当者間の緊密な連携が不可欠です。入社手続きを確実に完了させるためにも、この記事にある内容を参考にし、従業員の入社時の業務の参考にしてください。
会社側が従業員の入社手続き時にすべき対応に関するおすすめ記事
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!