雇用契約書の書き方とは?2024年の改正についても解説!
カテゴリー:
公開日:2024年8月
更新日:2025年11月27日
従業員を雇用する際に必要となる雇用契約書ですが、その書き方について正しく理解できているでしょうか?特に2024年には法改正があり、雇用契約書に記載すべき項目や雇用契約書のフォーマット、雇用契約書の取り扱い方法にも見直しが求められています。これまでの雇用契約書の書き方では不十分となるケースも出てきているため、最新の情報に基づいた雇用契約書の書き方を確認することが重要です。
「初めて雇用契約書を作成するが、書き方がわからない」「現在使っている雇用契約書の内容が古くなっていないか不安」「2024年の法改正後も問題のない雇用契約書の書き方を知りたい」など、企業担当者の悩みは尽きません。
雇用契約書の書き方に関する参考記事:「入社手続き時の会社側が注意すべきチェックリストを紹介!」
本記事では、雇用契約書の基本的な役割から、法的に必要な記載事項、実務で注意すべきポイントまで、詳しく丁寧に解説していきます。特に2024年の改正内容をふまえた雇用契約書の書き方についても、具体的なサンプルを交えて紹介します。
これから雇用契約書を作成する方も、すでに運用している雇用契約書を見直したい方も、ぜひこの記事を参考に、法令に準拠した正しい雇用契約書の書き方を押さえておきましょう。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、入社手続きに伴う従業員の社会保険手続き、さらには会社情報に基づいた助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!


雇用契約書とは?
雇用契約書の書き方を解説する前に、そもそも雇用契約書とはなんでしょうか?
雇用契約書は、企業と従業員が雇用契約を結んだことを証明する書類です。通常、雇用開始日、契約期間、業務内容、勤務時間などが記載されています。
この契約により、従業員は働く義務を負い、企業はその労働に対して賃金を支払う義務があります。
ただし、雇用契約書の発行は法律で義務付けられているわけではありません。民法第623条には、雇用契約の締結に書面の作成を求める規定はありません。
雇用契約は口頭でも成立しますが、口約束だけでは「言った」「言わない」のトラブルが起こりやすいです。したがって、特別な理由がない限り、雇用契約書を作成することをお勧めします。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「雇用契約書とは?必要性や記載内容、作成方法を解説」
「雇用契約書の書き方」編集部
近年増加している労務リスクを抑えるために会社設立直後から税理士だけではなく社労士とも顧問契約を結ぶ会社が増えています。会社設立後の雇用契約書の書き方や36協定の作成の仕方は社労士への相談がおすすめです。

合わせて読みたい「36協定の特別条項」に関するおすすめ記事

36協定の特別条項を詳しく解説!要件や時間外労働の上限とは?
雇用契約書の法的効力
雇用契約書を締結すると、労働者も企業も契約内容に従う必要があります。
さらに、労働条件通知書としても機能する雇用契約書に記載された労働条件と実際の条件が異なる場合、労働者は即座に契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。
したがって、雇用契約書を作成する際は、労働基準法、労働協約、就業規則の内容をしっかり確認し、それに基づいた契約内容にすることが重要です。もし、労働契約書の内容が労働基準法や労働協約、就業規則の基準を下回っている場合、その部分は無効となります。労働基準法で定められた最低基準を下回る契約は法的に認められないため、労働者の権利を守るために、これらの基準を厳守する必要があります。
雇用契約書の書き方に関するポイント!

雇用契約書において、労働基準法や労働協約、就業規則よりも労働者に有利な条件を記載する書き方は問題ありません。むしろ、労働者にとって有利な条件を設定することで、企業と労働者の信頼関係を強化することができます。これにより、法的な不備を防ぎ、労働者に不利益を与えないようにすることができます。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「労働契約書に必要な項目の書き方【テンプレ有】再発行や電子交付まで解説 !」
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
①労働基準法に反する内容である場合
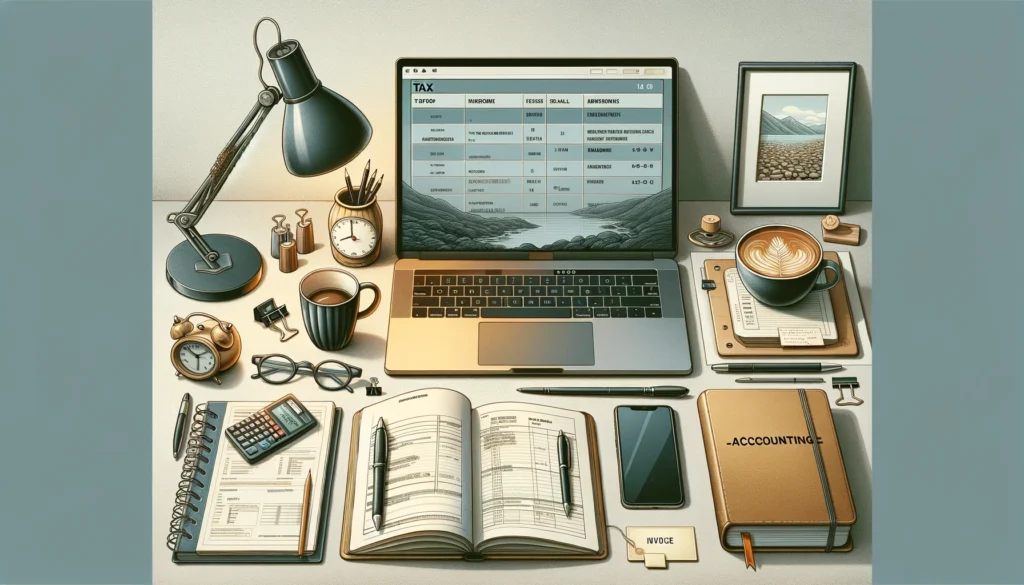
契約内容が労働基準法に違反している場合、その部分は無効です(労働基準法第13条)。
たとえば、「1日8時間を超える労働に対して割増賃金を支払わない」という規定は無効です。また、就業規則に記載されている労働条件よりも不利な内容も無効になります(労働契約法第12条)。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「雇用契約書とは?記載事項や労働条件通知書との違いを解説!」
②労働協約に反する内容である場合
雇用契約書の書き方解説部
「労働協約」とは、労働組合と使用者が行った取り決め、契約のことを指します。
「社労士が解説!労働協約とは?労働協約と労使協定の違いについて」
労働協約は、書面で作成し、両者が署名または押印することで効力を持ちます(労働組合法第14条)。
また、労働協約に反する個別の労働条件は無効となり、協約の内容が適用されます(労働組合法第16条)。
雇用契約書の書き方解説部
協約の定める基準を上回る労働契約との関係でも、同様に、その上回る部分の効力を否定する強行的効力が及ぶのでしょうか。結論は、有利原則を否定する学説が有力と言われています。詳しくはこちらの記事を参照してください。
※労働協約で定めた労働条件を上回る個別の労働契約を許すことを有利原則といいます。
雇用契約書の書き方に関連して気をつけておきたい注意点

ただし、労働協約は基本的に労働組合の組合員にのみ適用され、非組合員には効力がありません。
例えば、労働協約で年末年始に5日間の休暇が認められている場合、労働契約書にその記載がなくても、労働者は協約に基づいて休暇を取得できます。労働協約に従わない契約条項は、労働基準監督署の指導対象となる可能性があります。

合わせて読みたい「二以上事業所勤務届の書き方」に関するおすすめ記事
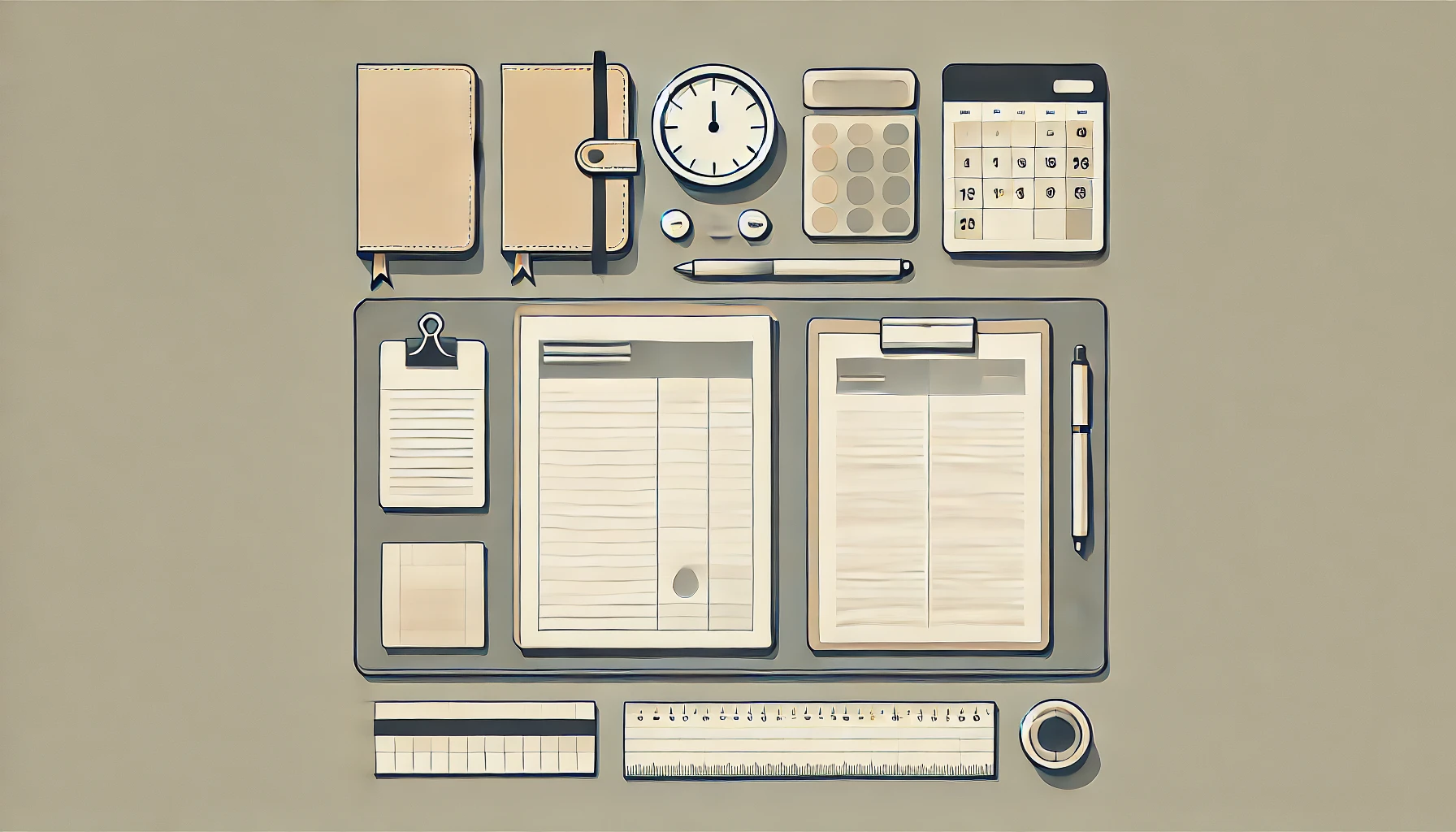
二以上事業所勤務届の書き方とは?手続きや社会保険の取り扱いも解説!
③就業規則に反する内容である場合

就業規則に反する個別の雇用契約は、その部分が無効になり、就業規則の内容に修正されます。(労働契約法12条)
雇用契約書の必要性
民法第623条では、雇用契約は当事者の合意だけで成立すると規定されており、雇用契約書の発行は義務付けられていません。そのため、雇用契約書を作成しなくても雇用契約は有効です。
ただし、前述の通り、口頭だけの契約では「言った・言わない」のトラブルが発生しやすいため、雇用契約書を作成することが望ましいとされています。
また、雇用契約書と似た書類に「労働条件通知書」があります。労働条件通知書は、労働基準法に基づき、賃金や労働時間などの労働条件を明示することが義務付けられた書類です。企業は労働者を採用する際、必ず労働条件通知書を発行しなければなりません。

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
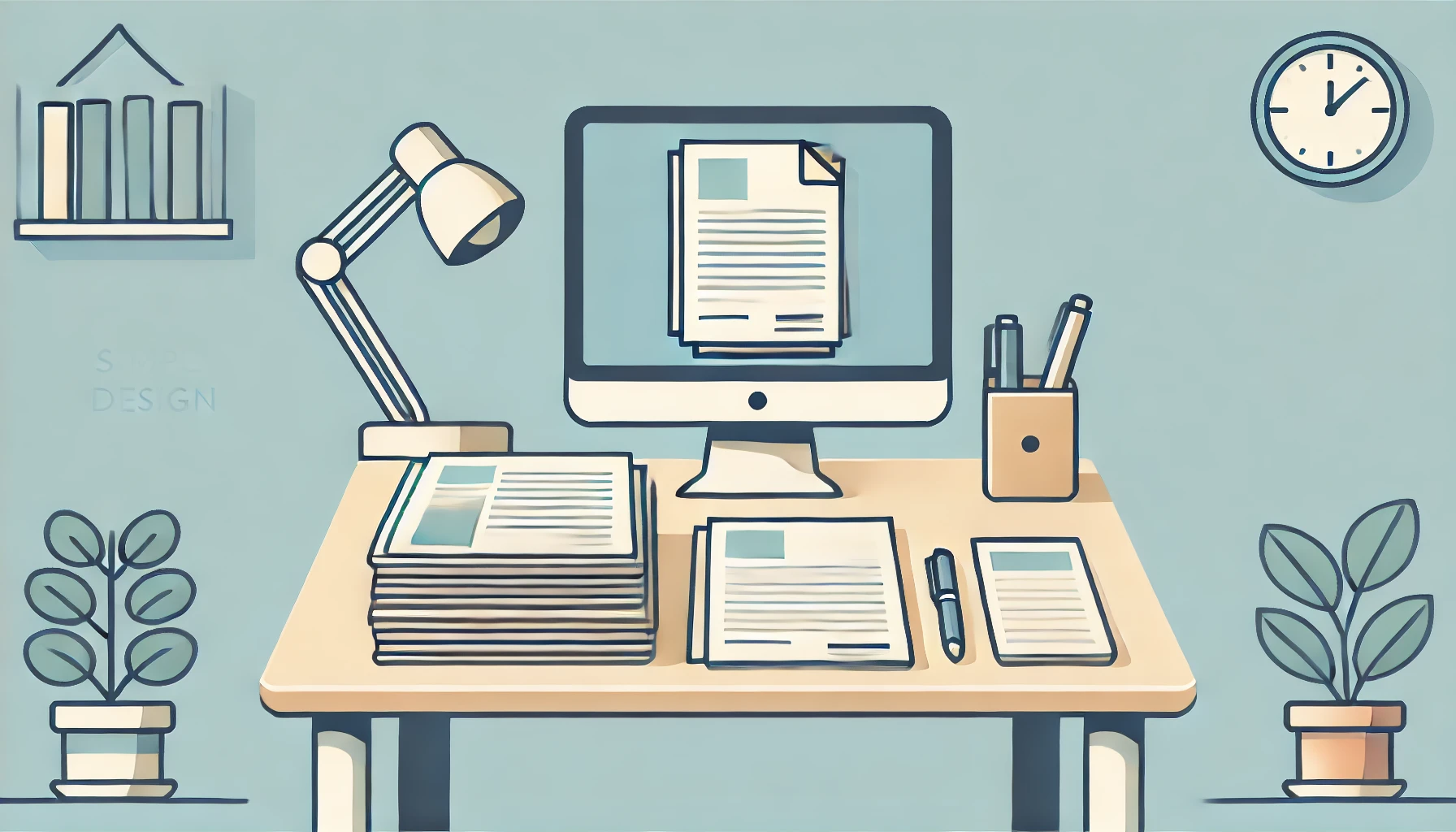
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
法的には、労働条件通知書が発行されていれば問題ありませんが、この書類は企業から労働者に一方的に交付されるため、労働条件に関する認識の違いによるトラブルが生じやすいです。こうしたトラブルを避けるため、労働者の同意を得る手段として、雇用契約書を発行することが一般的です。
雇用契約書の書き方
雇用契約書の書き方を理解するうえで、まずは雇用契約書には「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があることを認識しておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
絶対的明示事項は、労働基準法第15条で、企業が従業員を雇用する際には一定の労働条件を明示しなければならないと定められています。
引用:「労働条件の明示義務とは?労働条件通知書への記載事項や2024年の改正内容を解説」
相対的明示事項は、絶対的明示事項とは異なり、会社に定めがある場合のみ明示が必要です。 相対的明示事項については、書面の交付を要しません。
引用:「2024年4月から『労働条件明示事項』が法改正!追加される明示事項とは?」
| 絶対的明示事項 | 相対的明示事項 |
| ・労働契約期間 ・就業場所 ・従事する業務内容 ・就業時間(始業時間と就業時間) ・残業(所定外労働時間)の有無 ・休憩・交代制勤務の有無 ・休日、休暇 ・賃金や手当、支払日 ・退職に関連する事項 | ・退職手当の定めが適用される労働者の範囲 ・退職手当の計算や支払い方法 ・退職手当の支払い時期 ・安全衛生に関する事項 ・職業訓練制度 ・表彰や制裁の制度 ・休職に関する事項 ・最低賃金額 ・臨時に支払われる賃金、賞与、手当 |
雇用契約書の書き方① 労働契約期間
雇用契約書の書き方における最初のポイントは、「労働契約期間」の明記です。雇用契約書を作成する際は、まず労働契約の期間が「有期」か「無期」かをはっきりと記載することが基本となります。明確な書き方を心がけることで、後の認識違いやトラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば、正社員などの無期雇用であれば、雇用契約書には「契約期間:期間の定めなし」といった書き方を行いましょう。一方で、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員など、有期雇用の場合には、「契約期間:2024年4月1日〜2024年9月30日」といったように、期間を具体的に記載する雇用契約書の書き方が必要です。
また、試用期間を設ける場合も、雇用契約書にその旨を記載することが重要です。「試用期間:3ヶ月(2024年4月1日~2024年6月30日)」といった書き方をすることで、採用後の正式な雇用開始時期を明確にできます。このような雇用契約書の書き方は、労働者の不安を軽減し、安心感を与える効果もあります。
さらに、契約期間の更新がある場合には、雇用契約書に更新の可能性や条件を記載することが大切です。「契約更新あり。ただし、業務の進捗状況、勤務成績、出勤状況および会社の経営状況により判断する」といった具体的な書き方をすることで、客観的な基準が明示され、契約更新に関するトラブルを防ぎやすくなります。

合わせて読みたい「入社 住民税 手続き」に関するおすすめ記事

入社時の住民税に関する手続きについて解説!退職時の住民税の手続きも併せて紹介!
このように、雇用契約書の書き方では、契約期間の有無や更新の有無、更新条件、試用期間の取り扱いなどをすべて網羅的に記載することが求められます。特に労働条件の根幹となる「契約期間」に関しては、明確で誤解のない雇用契約書の書き方を徹底することが、法令遵守や信頼関係の構築にもつながります。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「雇用契約書の書き方は?記入例と注意すべきポイントを解説」
雇用契約書の書き方② 就業場所

雇用契約書の書き方として、就業場所についても雇用契約書に記載する必要があります。
業務を行う場所を明確に記載します。また、勤務地が変更される可能性がある場合は、その旨も記載する書き方が求められます。
雇用契約書の書き方解説部
また、「③業務内容」の注意点でも記載しますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」も明示する必要があることに注意してください。
雇用契約書の書き方③ 業務内容
雇用契約書の書き方として、業務内容も記載することが肝心です。
業務内容には、担当する具体的な仕事内容を明記します。業務範囲が広い場合は、それぞれの業務の詳細を列挙する書き方にしましょう。
雇用契約書の書き方に関連して気をつけておきたい注意点

労働契約を結ぶ際や有期労働契約を更新する際には、すべての労働者に対して労働条件を明示する必要があります。現在は、雇用開始直後の「就業場所」と「業務の内容」を明示すればよいとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」も明示する必要があります。
雇用契約書の書き方解説部
詳細は「2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール」や厚生労働省のホームページを参照してください。
雇用契約書の書き方④ 就業時間
SoVa税理士お探しガイド編集部
給与所得者の扶養控除申告書の書き方については、以下のサイトも是非ご覧ください。
「 給与所得者の扶養控除申告書の書き方と注意点を解説!」
雇用契約書の書き方として、就業時間についても雇用契約書に記載しておく必要があります。
雇用契約書には勤務時間も記載しましょう。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、入社手続きに伴う従業員の社会保険手続き、さらには会社情報に基づいた助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
勤務時間には、始業時間、終業時間、そして休憩時間が含まれます。
勤務時間は、法律や就業規則に従い、設定してください。
法定労働時間は1日8時間、週40時間が上限です(【参考】労働基準法第32条1項・2項)。
雇用契約書の書き方⑤ 残業の有無

雇用契約書の書き方において、5つ目に押さえておくべき重要な項目は「残業の有無」とそれに伴う残業代の取り扱いです。
雇用契約書には、所定労働時間を超える残業や休日出勤などの所定外労働について、明確に記載を行う必要があります。特に残業代の支払いに関する事項は、雇用契約書の中でも非常に重要な部分です。雇用契約書の書き方として、「残業の有無:有・無」といったチェック欄を設け、残業代の発生条件や支払い方法についても補足することが望ましいです。

合わせて読みたい「新入社員の入社手続き」に関するおすすめ記事

新入社員の入社手続きで必要な準備は?必要書類や具体的な手続き内容を解説!
こうした記載があることで、労使間の認識違いによる残業代トラブルを未然に防ぐことができます。雇用契約書の書き方で、残業代がどのように計算され、いつ支払われるのかを具体的に示しておくことは、後の紛争防止にもつながります。
ただし、たとえ雇用契約書に残業代についての記載がなかったとしても、会社には法律に基づき、実際に発生した残業に対して残業代を支払う義務があります。労働基準法では、時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、一定の割増率で賃金(= 残業代)を支払うことが義務付けられており、この義務は雇用契約書の書き方によって免除されるものではありません。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」
具体的には、時間外労働に対する残業代は通常の賃金の1.25倍以上、休日労働に対しては1.35倍以上、さらに深夜労働が加わる場合には、1.5倍を超えるケースもあります。このように、残業代には法定の割増率が適用されるため、雇用契約書にはその点を正確に反映させる必要があります。

合わせて読みたい「みなし残業代(固定残業代)」に関するおすすめ記事

みなし残業(固定残業)制度とは?企業側のメリットと注意点を解説!
本記事では、みなし残業(固定残業)制度の基本的な仕組みから、企業が導入するメリット・デメリット、注意点までをわかりやすく解説します。これから制度の導入を検討している企業の方や、仕組みを正しく理解したい人事担当者にとって、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
また、「残業代は支払わない」や「賃金に残業代を含む」などの書き方は、法的に無効と判断される可能性があります。雇用契約書にそのような書き方がされていたとしても、労働者は法律に基づき、正当な残業代を請求することができます。
したがって、雇用契約書の書き方では、残業代に関する取り扱いを明確にし、計算方法や支払い時期、対象労働時間なども丁寧に記載することが重要です。正確な残業代の記載は、会社の信頼性向上にもつながり、労使間のトラブルを回避する大きな要素となります。
このように、雇用契約書の書き方においては、残業の有無だけでなく、残業代の支払いに関する情報をしっかりと盛り込むことで、会社と従業員双方が納得のいく労働契約を結ぶことが可能になります。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「雇用契約書(書面等)に残業代についての記載がないから払わないは違法【弁護士監修】」
雇用契約書の書き方⑥ 休憩
雇用契約書の書き方の6つ目は、「休憩」についてです。
雇用契約書には、始業時間・終業時間、残業の有無に加えて、休憩時間の長さも記載しましょう。原則として、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を取らせる必要があります。
もちろん、法定の時間以上の休憩を設けることも可能です。休憩時間の具体的な時間帯や長さを雇用契約書に明記することで、労働者と雇用主の間で誤解や認識の違いを防ぐことができます。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「雇用契約書の書き方を徹底解説!作成時の注意点とは?」
雇用契約書の書き方⑦ 交代制勤務の有無
雇用契約書の書き方として、交代制勤務の有無も雇用契約書に記載する必要があります。
交代制勤務がある場合は、その旨を雇用契約書に記載しましょう。また、交代の順序や交代のタイミングなど、社内のルールや規則がある場合は、それも併せて記載しておく書き方にすると良いでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
雇用契約書の書き方⑧ 休日・休暇
雇用契約書の書き方における8つ目の重要なポイントは、「休日・休暇」の明記です。雇用契約書では、労働者が取得できる休日や休暇の内容を明確に記載することが求められており、特に休日の定義はトラブル防止のために欠かせない要素です。
休日については、決まった曜日に休む場合、雇用契約書の書き方として「休日:毎週土・日・祝日」や「休日:年末年始(12月29日~翌年1月3日)」といった具体的な記載をするのが一般的です。雇用契約書においては、こうした休日の書面化が、労働条件の明確化につながります。
一方、休日が不定期である場合には、「休日:週に2日」や「休日:月に10日」といった記載方法もあります。さらに、年単位の変形労働時間制を導入している企業では、「休日:年間105日」など、年間を通じた休日の総数を明記する雇用契約書の書き方も有効です。いずれにしても、休日に関する情報は正確かつ詳細に記載することが、トラブルの未然防止につながります。
雇用契約書に記載すべき内容は、休日だけではなく、休暇に関する情報も含まれます。年次有給休暇については、「6ヶ月間の継続勤務で10日の年次有給休暇を付与し、それ以降は労働基準法に従う」といった具体的な書き方をしましょう。さらに、慶弔休暇や特別休暇、傷病による休暇などがある場合も、雇用契約書にその旨を記載することで、休日と休暇の制度全体を労働者にしっかりと伝えることができます。
また、休日の取り扱いに関しては、労働基準法の規定に基づき、週に1回または4週に4日以上の休日を確保することが法律で義務付けられています。この基準を下回る休日設定は違法となるため、雇用契約書の書き方においても、法令に準拠した休日の設定が必要不可欠です。
このように、雇用契約書における休日の明記は非常に重要であり、適切な書き方によって、労働条件の透明性を確保することができます。休日の回数や取得方法、例外的な扱いをすべて文書化することで、企業と従業員双方にとって安心できる労働環境が築けます。正確でわかりやすい雇用契約書の書き方を実践し、すべての休日に関する情報を漏れなく記載しましょう。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「正社員の雇用契約書について解説!内容や書き方【雛形・テンプレートあり】」
雇用契約書の書き方⑨ 賃金・手当・支払日

雇用契約書の書き方における9つ目の重要なポイントは、「賃金・手当・支払日」に関する明確な記載です。賃金に関する取り決めは、従業員の生活に直結する非常に重要な項目であり、雇用契約書では必ず正確かつ具体的に記載する必要があります。
まず、賃金の計算方法については、月給制、日給制、時給制など、どの制度を採用しているのかを明示しましょう。たとえば、「基本賃金は月給〇〇円とする」といったように、制度と金額の両方を明記するのが適切な書き方です。
次に、賃金の支払い方法についても、雇用契約書の書き方として非常に重要です。「銀行口座への振込」や「現金による手渡し」など、具体的な賃金の支払い手段を明記しておきましょう。また、賃金の支払日は「毎月25日払い」「翌月末日払い」など、雇用契約書に明確に記載しておくことが必要です。
さらに、残業手当や通勤手当、役職手当などの各種手当についても、賃金に含めるのか、別途支給するのかを明確にし、それぞれの金額や支給条件も雇用契約書に記載します。このような賃金に関する詳細な情報を、漏れなく雇用契約書に記載することで、後の誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
なお、労働基準法では、賃金の支払いについて「通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日で支払う」という原則が定められています。したがって、雇用契約書の書き方としても、この原則に沿った賃金の記載が必要不可欠です。
このように、賃金に関する情報は、すべての労働条件の中でも特に誤解が起こりやすい部分であるため、雇用契約書においては正確かつ丁寧な書き方を心がけることが大切です。会社と従業員の間で安心して契約を結ぶためにも、賃金の体系・支払い方法・手当の有無などをすべて網羅した雇用契約書の書き方を意識しましょう。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「なくてもOK? 雇用契約書とは 〜記載事項や「労働条件通知書」との違い」
雇用契約書の書き方⑩ 退職に関する事項
雇用契約書の書き方として、退職に関する事項も雇用契約書に記載する必要があります。
雇用契約書には、定年退職の年齢、自己都合で退職する場合の通告期限、解雇の理由を記載します。特に有期雇用の社員との契約では、解雇や契約終了のルールを明確にしておくことが重要です。労働契約法の改正により、解雇や契約終了の基準が以前よりも明確に定められたためです。また、有期雇用と無期雇用の労働条件に不合理な違いがないようにするため、雇用契約書を作成する際には法的な問題がないか十分に確認することが求められます。
雇用契約書の書き方⑪ その他
雇用契約書の書き方で、以下のものも注意しましょう。
2024年4月1日から、労働条件に関して新たに明示すべき事項が追加されます。契約社員、パートタイマー、アルバイトなど有期雇用で働く従業員については、以下の情報を明示する必要があります。
まず、契約の更新に関する上限—つまり、契約期間や更新回数の上限について記載する書き方にしておく必要があります。また、無期転換の申し込み機会についても明示し、さらに無期転換後の労働条件についても明確にしておくことが求められます。
これらの新しい明示事項が導入された背景には、有期雇用の従業員の処遇改善を目的とした取り組みがあります。有期契約から無期契約に転換できることを明示する書き方にすることで、雇い止めなどの不当な待遇を防ぐことが期待されています。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや記載事項、注意点を解説」
雇用契約書でよくある疑問|Q&A
Q.従業員が執行役員になる場合に雇用契約書は必要?
従業員が執行役員になる場合、従業員時代の雇用契約を維持することになるため、新規に雇用契約書を締結する必要はありません。
しかし、外部からを執行役員を迎える際には、新たに雇用契約または委任契約(業務委託契約)を締結する必要があります。
Q.雇用契約書と就業規則に相違がある場合、どちらが優先されるのか?
雇用契約書に記載された内容と、就業規則の内容に違いがある場合、どちらが効力を持つのか疑問に思う方も多いでしょう。原則として、雇用契約書よりも就業規則が優先されるとされています。これは、労働契約法第12条の規定に基づき、職場全体に適用される就業規則が、個別の雇用契約書よりも強い効力を持つとされているためです。
雇用契約書の書き方に関連して気をつけておきたい注意点

例外として雇用契約書の内容が従業員にとってより有利である場合には、その雇用契約書の記載が優先されます。
まとめ|雇用契約書の書き方を正しく理解しよう
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
雇用契約書は、企業と従業員の間でトラブルを防ぎ、労働条件を明確にするために欠かせない重要な書類です。どのような業種・雇用形態であっても、適切な雇用契約書を交わすことが、信頼関係の構築や法令遵守の第一歩になります。だからこそ、雇用契約書の書き方を正しく理解し、最新の法改正にも対応することが求められています。
特に2024年の改正では、労働条件の明示項目の追加や、有期雇用契約の更新基準に関する説明義務など、雇用契約書の書き方にも大きな影響があります。今使っている雇用契約書が古い内容のままになっていないか、企業としては改めて見直すことが重要です。
今回の記事で紹介したように、雇用契約書の書き方には、必ず記載しなければならない法定項目や、企業ごとに追加すべき独自の条件などがあります。正確な雇用契約書の書き方を実践することで、労働トラブルのリスクを大幅に減らすことができます。
雇用契約書の書き方に関する参考記事:「入社手続きマニュアル<会社側編> 必要書類や手続きを解説!」
また、従業員が安心して働ける環境を整えるためにも、わかりやすく丁寧な雇用契約書の書き方を心がけましょう。形式だけでなく、実際の業務内容や働き方に即した内容を盛り込むことが、実務に強い雇用契約書につながります。
企業が継続的に人材を確保し、安定した組織運営を行うためには、常に適切な雇用契約書を準備しておくことが欠かせません。法改正のたびに雇用契約書の書き方を見直し、アップデートしていくことで、企業リスクを回避できます。
今後のためにも、法令に準拠した雇用契約書の書き方を見直し、正確な内容で従業員と合意を交わす体制を整えていきましょう。万が一、自社での対応に不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けながら雇用契約書の書き方をチェックすることをおすすめします。
雇用契約書の書き方に関連するおすすめ記事

雇用契約書の書き方に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。特に賃金、休日、業務内容、勤務日数、時間外労働などの書き方や記載例が気になる方は是非ご覧ください。
「雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや記載事項、注意点を解説」

合わせて読みたい!「会社設立サポート」の税理士依頼に関するおすすめ記事
会社設立時に税理士は必要?依頼するメリットとおすすめのタイミングとは

税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい!