正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!
カテゴリー:
公開日:2025年4月
更新日:2025年11月5日
労働基準法の改正により、2019年4月以降、有給休暇日数が年10日以上付与される正社員を含むすべての労働者に対し、年5日以上の有給休暇日数を取得させることが義務付けられました。
また、有給休暇日数の付与は正社員だけでなく、パートやアルバイトの従業員に対しても必要です。正社員の有給休暇日数は勤続年数に応じて増加し、最大で年20日が付与されますが、パートやアルバイトの場合も所定労働日数に応じた有給休暇日数が付与されます。
今回は、正社員やアルバイトなど各雇用形態別の有給休暇日数の計算方法や有給休暇日数の付与に関するルールについて、わかりやすく解説します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「 給与支払事務所等の開設届出書の提出」に関するおすすめ記事

給与支払事務所等の開設届出書の提出は不要?給与支払事務所等の開設届出書の書き方や記載例も解説
有給休暇とは?

有給休暇日数とは、正社員だけでなく一定の要件を満たす労働者に対して、有給休暇日数を付与する制度のことです。有給とは、「給与が支払われる」という意味であり、有給休暇日数に応じた期間の給与が労働者に支払われます。
有給休暇日数は、1年ごとに決まった日数が付与されることから「年次有給休暇日数」と呼ばれますが、一般的には「有給休暇」や「有休」とも呼ばれます。正社員の有給休暇日数は、入社6カ月経過後に10日が付与され、その後1年ごとに増加し、最大で20日となります。
正社員の有給休暇日数のルールに関するおすすめ記事

正社員の有給休暇日数を把握する前に、有給の定義を確認しておきましょう。
有給休暇とは?付与日数や計算方法、繰越保持日数の上限について解説
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
正社員の有給休暇日数を含む年次有給休暇制度は、労働基準法によって定められた制度であり、企業は要件を満たす労働者に対して適切な有給休暇日数を付与しなければなりません。
SoVa税理士ガイド編集部
通常、働いていない場合は給与が発生しない「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されますが、有給休暇日数に基づく休暇については、この原則の対象外となります。
有給休暇日数の付与要件については、次の段落で詳しく解説します。
有給休暇の発生条件

有給休暇日数が付与されるための条件は、以下の2点です。
- 雇入れの日から6ヶ月以上継続して雇用されていること
- 全労働日の8割以上出勤していること
この条件を満たしたすべての労働者に対し、企業は有給休暇日数を付与しなければなりません。特に、正社員の有給休暇日数は、入社6カ月後に10日付与され、その後1年ごとに増加し、最大で20日となります。
この有給休暇日数の付与条件は、労働基準法で定められており、企業には遵守する義務があります。
有給休暇日数に関するここがポイント

正社員の有給休暇日数だけでなく、アルバイトやパートタイムの従業員にも適用され、条件を満たせば有給休暇日数が付与されます。
ただし、有給休暇日数の付与条件に関わる出勤率の計算には注意が必要です。
「正社員の有給休暇日数」編集部
病気休暇や育児休業など、法律で認められている休暇は出勤したとみなされるため、有給休暇日数の付与に影響を与えることはありません。
【雇用形態別】有給休暇日数
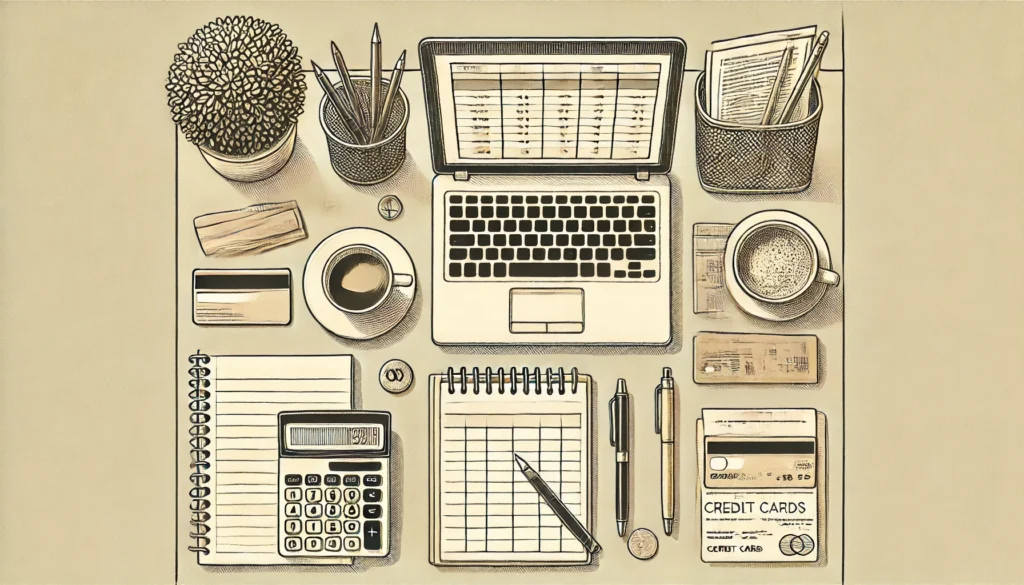
正社員の有給休暇日数は、勤続年数に応じて増加します。以下ではその付与日数の計算方法について詳しく解説します。
【正社員・契約社員の場合】勤続年数に応じた付与日数
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
正社員や契約社員などフルタイムで働く労働者は、勤続年数が長くなるごとに、有給休暇日数が増加します。労働基準法で定められた有給休暇日数の付与日数は以下の通りです。
| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
たとえば、正社員が入社して6ヶ月後に10日の有給休暇が付与され、その1年後(入社1年6ヶ月後)には11日に増加します。
正社員の有給休暇日数のルールに関するおすすめ記事:有給休暇の付与日数と義務、繰越の計算方法などルールをわかりやすく解説
勤続年数に応じて有給休暇が増える理由は、正社員の経験や貢献度が高まることを考慮しており、長期勤続者ほど多くの有給休暇日数を取得できるようになっています。
【正社員・契約社員の場合】最大付与日数は20日
有給休暇の最大付与日数は年間20日です。この上限に達するのは、勤続年数が6年6ヶ月以上で働いている労働者です。20日という有給休暇日数の上限は、労働者が十分に休養を取れると同時に、企業も業務を安定的に運営できるように配慮された結果です。

合わせて読みたい「新入社員の有休」に関するおすすめ記事

新入社員の有給はいつ・何日付与すべき?有給のルールや注意点を解説!
本記事では、新入社員の有給が発生する条件や付与日数、分割付与の注意点などを詳しく解説します。新入社員の有給を適切に管理し、円滑な職場環境を整えるために、ぜひ参考にしてください。
たとえば、月20日の勤務が必要な場合、有給休暇20日は丸1ヶ月の休暇に相当します。この制度により、労働者は十分な休息をとりつつ、企業は計画的に業務を進めることができます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
勤怠管理に関連してフレックスタイム制については、【 アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説! 】の記事も是非ご覧ください。
【正社員・契約社員の場合】繰越制度と有効期限
有給休暇日数は、1年以内に使用しなかった日数を翌年に繰り越すことができます。ただし、有効期間は付与日から2年間です。2年を過ぎると、有給休暇日数は時効で消滅しますので、計画的に取得する必要があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
たとえば、ある年に付与された10日の有給休暇日数のうち5日を使用し、残り5日を翌年に繰り越すことができます。翌年には新たに付与された有給と合わせて、長期休暇を取ることが可能になります。
正社員の有給休暇日数のルールに関するおすすめ記事

合わせて読みたい「給与計算 注意点 (税理士)」に関するおすすめ記事

給与計算の注意点は?税理士に丸投げするメリットについても紹介
パート・アルバイトの有給休暇日数
SoVa税理士お探しガイド編集部
正社員ではないパートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用者にも、一定の条件を満たせば有給休暇が付与されます。
週の労働日数や継続勤務年数に応じて、付与される有給休暇日数が決まります。
以下は、週所定労働日数ごとの付与日数の目安です。
| 週所定労働日数 | 0.5年目 | 1.5年目 | 2.5年目 | 3.5年目 | 4.5年目 | 5.5年目 | 6.5年目以上 |
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
たとえば、週3日勤務のパート労働者が1年間(入社1年6ヶ月後)勤務した場合、6日の有給休暇が付与されます。3年目に入ると、この日数は8日に増加します。
給与計算に関する参考記事:「寡婦控除とは?適用条件や申告方法、ひとり親控除との違いについても解説!」
このように、正社員ではないパートやアルバイトでも、週所定労働日数と勤続年数に応じて段階的に有給休暇日数が増える仕組みが設けられています。

合わせて読みたい「アルバイトに有休を付与」に関するおすすめ記事

アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説!
この記事では、アルバイトやパートに対する有給付与の詳細や、有給休暇取得時の賃金計算方法、さらに有給付与に関する注意点について詳しく解説します。アルバイトの有給付与に関する正しい知識を身につけ、適切な運用を行いましょう。
正社員の有給休暇日数に関するルール
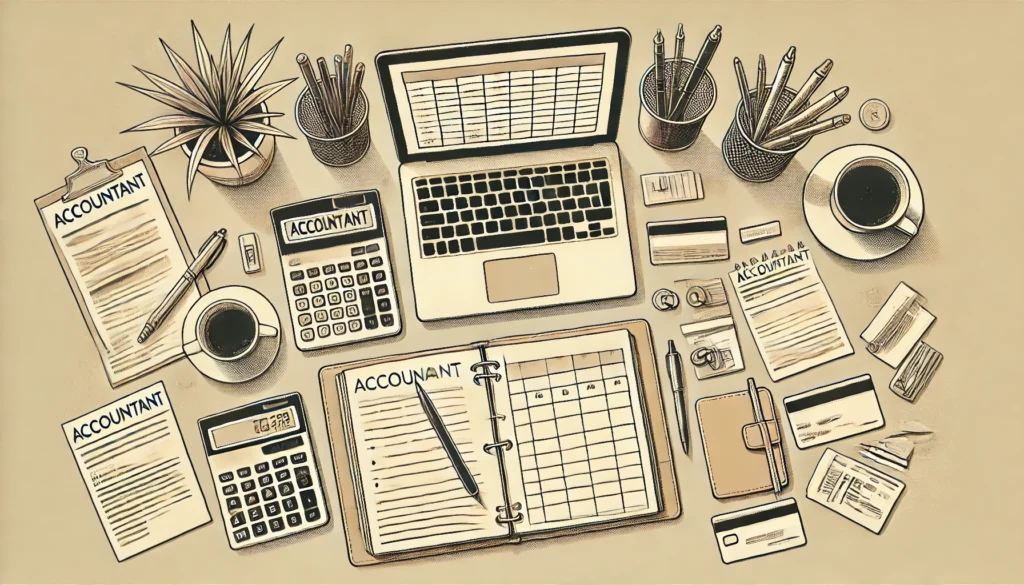
ここまで有給休暇の様々なルールについて解説してきましたが、正社員の有給休暇日数に関するルールにはどのようなものがあるのでしょうか。
正社員の有給休暇日数に関するルール①:有給休暇日数の時効は2年

合わせて読みたい「新入社員の入社手続き」に関するおすすめ記事

新入社員の入社手続きで必要な準備は?必要書類や具体的な手続き内容を解説!
労働基準法第115条により、有給休暇日数は付与日(基準日)から2年間が経過すると時効により消滅します。つまり、正社員に付与された有給休暇日数の有効期限は、付与日から2年間ということになります。
ただし、会社が独自の規定により、正社員の有給休暇日数の有効期限を長く設定することも可能です。例えば、失効する有給休暇日数を積み立てる「失効年休積立休暇制度」を導入する企業もあります。ただし、こうした独自の制度で設定された休暇は、年次有給休暇ではなく特別休暇となるため、「年5日の年次有給休暇の確実な取得義務」の対象外となります。
正社員の有給休暇日数のルールに関するおすすめ記事
正社員の有給休暇日数に関するルール②:有給休暇日数は繰り越しが可能
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
前年に付与された有給休暇日数を使いきれなかった場合、次の基準日を迎えた際に、2年の期限内であれば、使い切らなかった有給休暇日数を繰り越して取得することができます。この繰越制度により、正社員は、未使用の有給休暇日数を翌年に繰り越すことができます。なお、企業は有給休暇日数を無効にすることはできません。

合わせて読みたい「みなし残業代(固定残業代)」に関するおすすめ記事

みなし残業(固定残業)制度とは?企業側のメリットと注意点を解説!
本記事では、みなし残業(固定残業)制度の基本的な仕組みから、企業が導入するメリット・デメリット、注意点までをわかりやすく解説します。これから制度の導入を検討している企業の方や、仕組みを正しく理解したい人事担当者にとって、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
正社員の有給休暇日数に関するルール③:有給休暇日数の上限
正社員に対する有給休暇日数の付与日数の上限は、通常の労働者の場合、勤続6年6ヶ月以上で最大20日間の有給休暇日数が付与されます。そのうち5日は、有給休暇の義務化により取得義務があるため、1年後には有給休暇日数が最大で15日となります。
さらに、次の基準日を迎えたタイミングで、正社員は新たに20日間の有給休暇日数が付与されるため、最大で35日間の有給休暇日数が付与されることになります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
ただし顧問契約の場合であっても顧問料によって受けられるサービスはもちろんことなります。どのような業務を依頼できるかは税理士との契約時に確認しておくことをおすすめします。

正社員の有給休暇日数の取得率や取得日数を向上させるには、どのような施策が必要でしょうか?

合わせて読みたい「雇用契約書の書き方」に関するおすすめ記事

雇用契約書の書き方とは?2024年の改正についても解説!
正社員の有給休暇日数を向上させる施策①:有給休暇日数の取得促進と定期的なチェック
正社員の有給休暇日数の計画的な取得は、生産性の向上や企業イメージの改善、さらには優秀な正社員の確保といった大きなメリットをもたらします。
しかし、厚生労働省が発表した「令和4年度『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査報告書」によると、正社員の約40%が「周囲に迷惑がかかると感じる」や「休みを取りにくい雰囲気」などを理由に有給休暇日数の取得をためらっていると報告されています。
正社員の有給休暇日数のルールに関するおすすめ記事
この問題を解決するためには、正社員が有給休暇日数を取得しやすい環境を整えることが重要です。具体的には、正社員の有給休暇日数の定期的なチェックと、正社員の有給休暇の取得促進に向けた企業全体での取り組みが必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
上司やチームメンバーによる業務負担の軽減や、年次有給休暇日数管理簿の活用、そして正社員でも休みを取りやすい風土の醸成が効果的です。
正社員の有給休暇日数を向上させる施策②:計画的付与制度(計画年休)
「計画的付与制度」とは、正社員が有給休暇日数を事前に計画的に取得できるように割り振る制度です。この制度により、正社員は有給休暇日数をためらうことなく取得でき、企業側としても労務管理がしやすくなり、業務を計画的に運営できます。なお、有給休暇日数から5日を除いた残りの日数に適用されます。
正社員の有給休暇日数のルールに関するおすすめ記事:有給休暇まとめ!付与日数、条件などをわかりやすく解説
正社員の有給休暇日数を向上させる施策③:時間単位の年次有給休暇制度

合わせて読みたい「固定残業代のメリット・デメリット」に関するおすすめ記事

固定残業代とは?労働者と企業それぞれのメリットデメリットや注意点も解説!
この記事では、固定残業代の基本的な仕組みから、企業・労働者それぞれのメリット・デメリット、導入時の注意点まで、わかりやすく解説します。
年次有給休暇は原則として1日単位で取得しますが、労使協定を結ぶことにより、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。
SoVa税理士ガイド編集部
これにより、正社員は通院や子どもの行事参加、家族の介護など、有給休暇日数を柔軟に活用でき、結果として有給休暇日数の取得率が改善します。
なお、時間単位の有給休暇日数取得分からは、「確実な取得が必要な年5日間」を差し引くことはできません。
まとめ

今回は、正社員の有給休暇日数の付与日数の考え方や仕組みについて解説しました。
有給休暇日数は労働基準法に基づき、雇い入れ日から6ヶ月継続勤務し、出勤率が8割以上の正社員に付与されます。初回の有給休暇日数は、入社から半年後に付与され、その後は最初に付与された日(基準日)から1年ごとに有給休暇日数が増加し、次回の付与が行われます。
正社員の有給休暇日数について気をつけておきたい注意点

また、有給休暇日数を付与するタイミングは、正社員の不利益を避ける範囲で前倒しすることも可能です。その際、有給休暇日数の基準日が変更される点に注意が必要です。
有給休暇日数を適切に付与しないと、違法となり、罰則を科される可能性があるため、正社員の付与すべき日数と基準日を正確に把握し、遵守することが求められます。
正社員の有給休暇日数のルールに関するおすすめ記事
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「36協定の残業時間の上限」に関するおすすめ記事

36協定の残業時間の上限は月45時間?80時間?規制や罰則について解説
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!