勘定科目「未払金」はどう仕訳する?間違いやすい勘定科目との違いもわかりやすく解説!
カテゴリー:
公開日:2025年5月
更新日:2026年1月8日
経理業務において頻出する「未払金」の仕訳は、正しく理解していないとミスにつながりやすいポイントのひとつです。特に未払費用や買掛金といった他の勘定科目との違いがあいまいなまま仕訳してしまうと、帳簿が不正確になり、決算時や確定申告時に修正が必要になるケースもあります。
この記事では、未払金の意味や基本的な仕訳方法をはじめ、未払金と混同しやすい勘定科目との違い、実際の仕訳例、未払費用との誤仕訳による影響、そして未払金の仕訳でよくあるトラブルとその対応策まで、わかりやすく解説します。仕訳ミスを防ぎ、正確な帳簿管理を行うために、未払金に関する基礎知識をしっかり押さえておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
未払金とは

未払金とは、日常的な営業取引以外の単発的な取引により発生した債務を計上するための勘定科目です。仕訳では、後払いとなる取引の際に「未払金」として処理されます。
たとえば、事務用品や備品などをクレジットカードやショッピングローンで購入した場合、支払いは後日になるため、購入時点では未払金として仕訳します。このようなケースでは、「(借方)事務用品費/(貸方)未払金」といった仕訳を用いて記録します。
貸借対照表上では、未払金は原則として「流動負債」に分類されます。
未払金の仕訳で気をつけておきたい注意点

ただし、ワン・イヤー・ルールにより、支払期限が貸借対照表の日付の翌日から1年を超える場合は「固定負債」として「長期未払金」に分類されます。
したがって、仕訳においても「未払金」と「長期未払金」を正確に区別して記帳することが重要です。
たとえば、会社で使用する社用車を分割ローンで購入した場合、頭金を除いた金額については未払金として仕訳されます。しかし、支払期間が1年を超える場合は「長期未払金」として別の仕訳処理が必要になります。
このように、未払金の仕訳は取引内容と支払期間によって変化します。経理処理においては、適切な仕訳と未払金の区分管理が求められます。
勘定科目「未払金」の仕訳方法に関するおすすめ記事
未払金と間違いやすい勘定科目との違い

ここでは未払金に関するよくある疑問について、仕訳の観点も交えながら解説します。特に混同されやすい「未払費用」「買掛金」「長期未払金」との違いや、適切な仕訳方法について確認していきましょう。
SoVa税理士ガイド編集部
勘定科目「未払金」の仕訳方法にさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
未払金と未払費用の仕訳の違い
未払費用とは、継続的に発生するサービスの代金を後払いにする際に使用する勘定科目です。貸借対照表上では未払費用も「負債」に分類され、仕訳上も「(借方)費用科目/(貸方)未払費用」として処理されます。
たとえば以下のような費用が対象です:
- 土地の賃借料
- 車両や設備のリース代
- 借入金に対する利息
一方で未払金は、支払が確定しており、かつ商品やサービスの提供も完了している場合に使用します。たとえば「(借方)備品/(貸方)未払金」といった仕訳がされます。
SoVa税理士ガイド編集部
違いのポイントは、支払期日が到来しているかどうかです。
未払費用は、費用は発生しているものの支払期日がまだ到来していないケースで用いられます。したがって、仕訳上も未払金とは別の勘定科目を使い、適切に区分して処理する必要があります。
未払金と買掛金の仕訳の違い
買掛金とは、通常の営業取引、特に商品の仕入れや外注加工などから発生する未払い代金に対して使用される勘定科目です。仕訳例としては「(借方)仕入/(貸方)買掛金」と記帳します。
買掛金と未払金はいずれも「未払いの債務」を意味しますが、未払金は営業取引以外の支払いに関する債務を表します。たとえば、業務用のパソコンや事務机を購入した際には「(借方)備品/(貸方)未払金」という仕訳になります。
仕訳処理においては、取引の性質をよく見極めて、「未払金」と「買掛金」を使い分けることが重要です。
勘定科目「未払金」の仕訳方法に関するおすすめ記事
未払金と長期未払金の仕訳の違い
未払金は、通常1年以内に支払う予定の債務に対して使用され、「流動負債」として貸借対照表に計上されます。一方、長期未払金は1年を超えて支払う債務であり、「固定負債」として分類されます。
たとえば、社用車をローンで購入した場合、支払いが1年を超える分については「(借方)車両運搬具/(貸方)長期未払金」という仕訳になります。

合わせて読みたい「労働保険料の勘定科目」に関するおすすめ記事

労働保険料の勘定科目と仕訳はどうなる?法人と個人事業主別に詳しく解説!
長期未払金と未払金の違いは支払期間にあり、仕訳でもこの点を区別して記帳しなければなりません。流動負債と固定負債の違いは財務分析にも影響を与えるため、仕訳段階での正確な判断が求められます。
未払金の仕訳例

未払金が発生した場合、1回の仕訳で完結するとは限らず、複数回にわたって仕訳を行う必要があるため、記帳がやや複雑になる傾向があります。未払金の定義を理解していても、具体的にどう仕訳すべきか迷うことは少なくありません。
そこで以下では、未払金の仕訳方法を具体的な事例ごとに3つのケースに分けて解説します。各ケースの未払金に関する仕訳処理を確認しながら、理解を深めていきましょう。
勘定科目「未払金」の仕訳方法に関するおすすめ記事
未払金の仕訳例①:未払金の支払いが1度の場合の仕訳
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
未払金の支払いが1回で完了するケースについて、仕訳の流れを見てみましょう。
例: 1月10日に5,000円の備品を購入し、代金は2月15日に支払い。この会社の決算日は12月31日です。
【発生時の仕訳】
借方:消耗品費 5,000円 / 貸方:未払金 5,000円
→ 支払がまだ行われていないため、未払金として負債計上します。
【支払い時の仕訳】
借方:未払金 5,000円 / 貸方:普通預金 5,000円
→ 未払金を支払うことで負債を解消する仕訳を行います。
【決算時の仕訳】
→ このケースでは決算前に支払いが完了しているため、追加の仕訳は不要です。
未払金の仕訳例②:未払金の支払いが複数回に分かれる仕訳
未払金が分割で支払われる場合、支払ごとに仕訳が必要になります。
例: 5月10日に5,000,000円の土地を購入し、代金を6月と7月の2回に分けて支払い。

合わせて読みたい「ChatGPTを使った記帳」に関するおすすめ記事

ChatGPTなどのAIを使って記帳するやり方|経理業務は生成AIにお任せ?
【発生時の仕訳】
借方:土地 5,000,000円 / 貸方:未払金 5,000,000円
→ 土地の取得に対して未払金として全額を負債計上します。
【1回目支払い時の仕訳】
借方:未払金 2,500,000円 / 貸方:普通預金 2,500,000円
→ 未払金の半額を支払って負債を一部解消します。
【2回目支払い時の仕訳】
借方:未払金 2,500,000円 / 貸方:普通預金 2,500,000円
→ 残りの未払金を支払い、負債を全額解消します。
【決算時の仕訳】
→ 決算までにすべての未払金が支払われているため、決算仕訳は不要です。
勘定科目「未払金」の仕訳方法に関するおすすめ記事:経費精算時の未払金の扱いは?仕訳や年度またぎの際の注意点を解説
未払金の仕訳例③:決算をまたぐ未払金の仕訳
決算をまたぐ未払金がある場合は、決算日時点で未払いの金額を「未払金」として正しく計上する必要があります。
例: 11月・12月分の事務所賃料100,000円を計上。支払日は翌月末、決算日は12月31日です。
【11月分の賃料】
・11月30日:仕訳なし
・12月31日:
借方:地代家賃 100,000円 / 貸方:普通預金 100,000円
→ 支払も費用発生も同期中のため、通常の仕訳で問題ありません。
【12月分の賃料(未払金発生)】
・12月31日(決算時):
借方:地代家賃 100,000円 / 貸方:未払金 100,000円
→ 費用が発生したが支払いが未了のため、未払金として計上します。
・1月31日(支払い時):
借方:未払金 100,000円 / 貸方:普通預金 100,000円
→ 翌月に未払金を支払って、負債を解消する仕訳を行います。
SoVa税理士ガイド編集部
決算をまたぐ取引では、未払金の計上を忘れると費用の計上時期がずれ、決算書の信頼性に影響します。適切な仕訳処理が重要です。
未払金と未払費用を間違って仕訳するとどうなる?

未払金と未払費用は仕訳上での扱いが似ているため、特に個人事業主にとっては「どこまで厳密に使い分ける必要があるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
青色申告決算書の貸借対照表には、負債の部に「未払金」という勘定科目があらかじめ印刷されています。一方、未払費用は表示されていないため、別行に記載することで未払費用として仕訳を分けることも可能です。

合わせて読みたい「会計ソフト比較一覧」に関するおすすめ記事
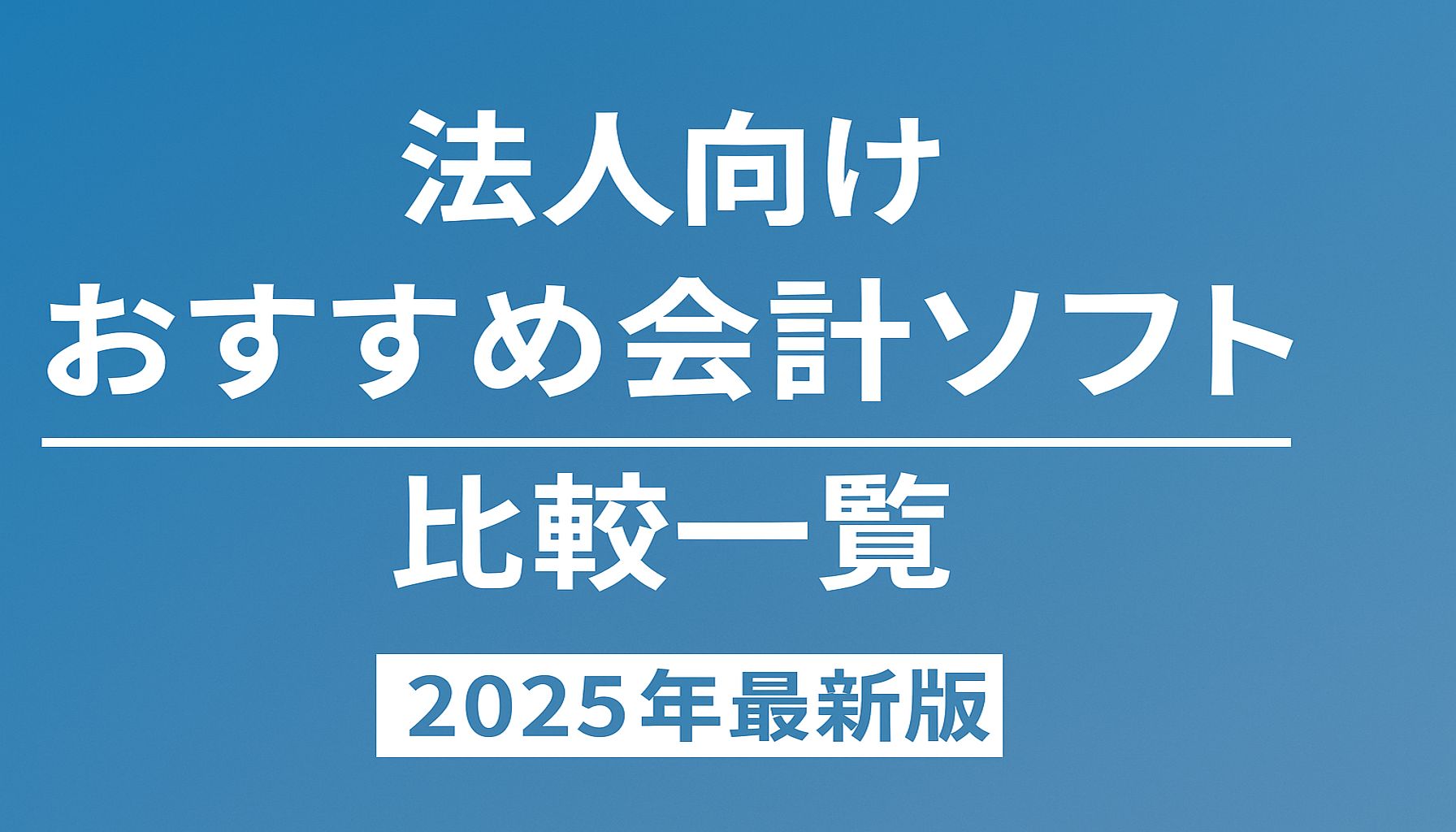
法人のおすすめ会計ソフト比較一覧【2025年最新版】
しかし、所得税の計算において重要なのは、収入から必要経費を差し引いた所得金額を正しく導くことです。したがって、未払費用の仕訳もすべて未払金に統一して処理しても、実務上は特に問題がないという考え方もあります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
ただし、簿記検定や会計の基本を学ぶ場面では、未払金と未払費用を仕訳の段階から正確に区別することが求められます。混在していると、勘定科目の性質や違いを理解していないと見なされる可能性があります。
SoVa税理士ガイド編集部
勘定科目「未払金」の仕訳方法についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
未払金と未払費用を仕訳上で使い分けるメリット
未払金と未払費用を仕訳で正確に分けることで得られるメリットもあります。
まず、仕訳例でも示したように、未払金と未払費用は発生タイミングや性質が異なるため、仕訳処理を分けておいたほうが記帳ミスを防げるという点が挙げられます。
たとえば、未払費用は利息・給与・賃料など、一定期間にわたり継続的に発生する費用を期間按分して記帳するため、毎年の変動が少ない傾向にあります。一方で、未払金は一時的な後払い取引に伴う仕訳であり、年度によって金額の増減が大きくなることがあります。
未払金の仕訳に関するここがポイント!

こうした背景から、未払金と未払費用の仕訳を分けることで、年度比較や予算管理がしやすくなります。帳簿の可視性を高める意味でも、仕訳の段階で分類することは有効です。
未払金と長期未払金は仕訳で明確に分けるべき?
次に、未払金と長期未払金の仕訳の使い分けについてです。
実務上、青色申告決算書では未払金に一括表示しても大きな問題はありません。ただし、長期未払金は支払期限が1年を超える債務に対して使用する仕訳科目であり、たとえば自動車の割賦購入など高額な固定資産の取得に伴うものが該当します。
このように、日用品や事務備品などの未払金の仕訳と、ローンで購入した車両などの長期未払金の仕訳とでは性質も金額も異なります。
未払金は短期的な負債として頻繁に変動しますが、長期未払金は定期的な返済により徐々に残高が減少する仕訳項目です。したがって、帳簿や貸借対照表で負債の内訳を正確に把握するためには、「未払金」と「長期未払金」を別々の仕訳科目として管理することが望ましいと言えます。
未払金の仕訳でよくあるトラブルと対応策


合わせて読みたい「会社経費をクレジットカードで個人立替」に関するおすすめ記事
会社経費をクレジットカードで個人立替は問題ない?仕訳や注意点も詳細に解説!

未払金の残高が実際の支払予定額と一致しない、あるいはマイナスになるといった問題が発生することがあります。こうした未払金に関するズレは、仕訳ミスや帳簿の管理不足が原因であるケースが多く見られます。
未払金の残高が合わない主な原因
- 期首の未払金残高の仕訳が誤っている
- 未払金の仕訳漏れ(計上し忘れ)がある
- 間違った勘定科目で仕訳している
勘定科目「未払金」の仕訳方法に関するおすすめ記事
未払金に関する仕訳が正しく行われているかを確認するためには、帳簿をさかのぼって、いつから未払金の残高と支払額が一致しなくなったかを追跡する必要があります。また、仕訳時には摘要欄に取引内容や相手先、支払期日を明記することで、後から見直しやすくなります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
解決策①:未払金の仕訳チェックは決算前だけでなく定期的に
未払金の仕訳確認を決算直前だけに限定してしまうと、金額の不一致やミスの発見が遅れ、修正に時間がかかってしまいます。
SoVa税理士ガイド編集部
未払金に限らず、定期的な仕訳の見直しや残高照合を行うことで、仕訳ミスや未払金の計上漏れを早期に発見でき、正確な帳簿管理につながります。
未払金の仕訳は、決算月や確定申告前だけでなく、月次・四半期ごとにチェックする習慣をつけておきましょう。
解決策②:確定申告後に未払金の仕訳漏れが発覚した場合の対応
確定申告を終えた後に、未払金の仕訳漏れが発覚するケースもあります。未払金が計上されていないと、本来差し引ける経費が減少し、所得が過大に計上されてしまうため、税負担が大きくなるリスクがあります。
申告期限内(個人事業主なら3月15日、法人は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内)であれば、確定申告書を訂正して、未払金の正しい仕訳を反映した修正申告が可能です。
もし申告期限を過ぎてしまった場合でも、「更正の請求書」を税務署に提出することで申告内容の訂正ができます。ただし、請求が通るかは税務署の調査次第であり、必ずしも還付が受けられるとは限りません。
Q&A|よくある質問
Q. 勘定科目「未払金」とはどういう意味ですか?
勘定科目「未払金」とは、すでに商品やサービスの提供を受けているにもかかわらず、まだ代金を支払っていない債務を処理するための勘定科目です。具体的には、備品の購入、外注費、設備工事代などの未払いに使われることが多く、「買掛金」と異なり、仕入以外の取引に用います。勘定科目「未払金」は、発生主義会計に基づき、支払いがまだでも費用や資産を計上する際に重要な役割を果たします。
Q. 勘定科目「未払金」はどんな場面で使いますか?
勘定科目「未払金」は、役員への報酬の未払い、車両やパソコンなど固定資産の購入代金の未払い、また広告費や保険料などの支払い遅延など、さまざまな取引で使用されます。「仕訳」を行う際には、支払義務が確定した時点で「未払金」として記録し、支払時に未払金を減少させます。勘定科目「未払金」は、支出の内容を明確に区分するため、正しいタイミングと取引内容の把握が不可欠です。
Q. 「未払金」と「買掛金」の勘定科目の違いは?
「未払金」と「買掛金」はどちらも未払いの債務を表す勘定科目ですが、使い分けが必要です。「買掛金」は主に仕入(商品や原材料の購入)に関する未払いを指す勘定科目であるのに対し、「未払金」はそれ以外の取引に用いられます。たとえば、PCや家具の購入でまだ支払っていない代金は「未払金」として処理します。勘定科目の選択を誤ると、帳簿の正確性に影響を与えるため注意が必要です。
Q. 「未払費用」と「未払金」の違いは?
勘定科目「未払費用」と「未払金」は似ていますが、発生するタイミングや費用の性質によって区別されます。「未払費用」は継続的に発生する費用(例:家賃、利息、人件費など)の未払いを処理するための勘定科目です。これに対し、「未払金」は一時的な支出の未払いに使用されます。仕訳の際に間違えやすいため、費用の継続性や性質に着目して勘定科目を選びましょう。
まとめ

勘定科目「未払金」の仕訳方法に関するおすすめ記事
未払金の仕訳は、取引の性質や支払時期に応じて正しく処理する必要があります。未払費用や買掛金など似た勘定科目との違いを理解せずに仕訳してしまうと、帳簿の信頼性が損なわれるだけでなく、税務上の問題が生じる可能性もあります。
SoVa税理士ガイド編集部
未払金の計上漏れや誤仕訳は、決算処理や確定申告の際に手間を増やす原因にもなります。
日頃から仕訳内容を明確に記録し、残高管理をこまめに行うことで、未払金に関するトラブルを未然に防ぐことができます。正しい仕訳を身につけ、未払金の処理をスムーズに行えるようにしておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドとの違いを徹底比較!ビジネスオーナーズ ゴールドを持つメリットとは
-
ビジネスカード

2026年1月27日
2
三井住友カードビジネスオーナーズ2枚持ちのメリットは?2枚持ちにおすすめの個人カードや選び方も紹介
-
ビジネスカード

2026年1月29日
3
三井住友ビジネスオーナーズのメリット・デメリットとは?ゴールドとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月27日
4
三井住友ビジネスオーナーズゴールドのメリットは?一般カードやfor Ownersとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月27日
5
即日ファクタリング来店不要おすすめ15選!選び方から注意点まで徹底解説
-
資金調達

2026年1月24日














SoVaをもっと知りたい!