合同会社を設立した場合、社会保険に加入義務はある?手続き方法についても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年8月
更新日:2026年2月24日
合同会社を設立したとき、多くの人が気になるのが「社会保険への加入義務はあるのか」という点です。実は、合同会社を含むすべての法人は、健康保険や厚生年金保険といった社会保険への加入義務があります。社会保険に加入することで、合同会社の経営者自身だけでなく、従業員やその家族の医療・年金・介護といった生活の基盤を守る仕組みが整います。
本記事では、合同会社を設立した際の社会保険の加入義務、社会保険の負担割合、実際の加入手続き、さらに加入義務を怠った場合のリスクについてわかりやすく解説します。
合同会社や株式会社のメリットなども無料相談可能!
株式会社と合同会社のどちらの法人格が良いのか?資本金はいくらにするのが良いのか?決算月はいつが良いのか?なども相談できるので、自分でやるよい安心して会社設立が可能です。設立後のサポートも充実しています。
※自分で会社設立するより○万円お得という設立支援業者は、条件が厳しい傾向があるのでご注意ください。
目次
【労務手続きを自分でするのはリスク大!】
社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由
社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。
社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。
ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。
また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」
社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。
だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
そもそも社会保険とは?

社会保険とは、国や地方公共団体が運営・管理する社会保障制度で、健康保険・厚生年金・介護保険などを含みます。合同会社を含む法人は、社会保険への加入義務を負うケースが多く、社会保険に加入することで、従業員やその家族が病気や怪我をした際の医療費や、老後の生活保障を受けられる仕組みが整います。
特に合同会社においても、従業員を雇用した時点で社会保険の加入義務が発生します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険は福利厚生というよりも、合同会社が法律上必ず対応しなければならない加入義務であり、加入しない場合は罰則の対象となる可能性もあります。
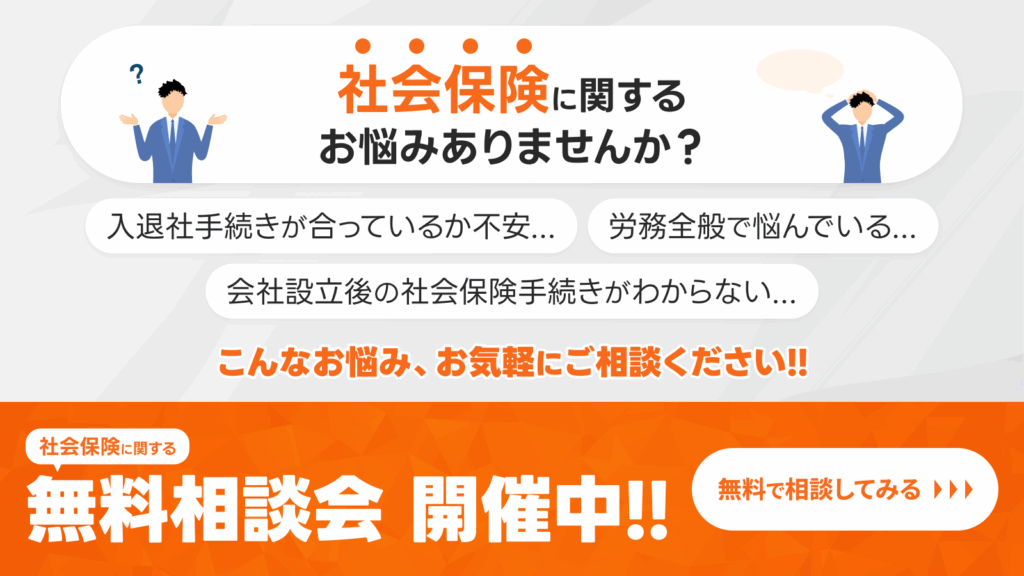
社会保険に含まれる主な制度
- 健康保険:合同会社が社会保険に加入することで、従業員と会社が医療費を分担し、病気や怪我の際の経済的負担を軽減する制度です。
- 厚生年金:合同会社における社会保険の中核で、老後の生活を支えるために、会社と従業員が折半で保険料を負担し、将来の年金額を増やす仕組みです。
- 介護保険:社会保険の一部として40歳以上の従業員に適用され、合同会社に勤務する人も要介護認定を受ければ介護サービスを受けられます。
合同会社の社会保険加入義務に関するおすすめ記事
このように、合同会社にとって社会保険の加入は「任意」ではなく「加入義務」であることを理解することが重要です。
合同会社を設立した場合に社会保険の加入義務はある?

社会保険とは、健康保険や厚生年金保険、介護保険などを含む制度であり、全ての法人には社会保険への加入義務が課されています。これは株式会社だけでなく合同会社においても同様であり、合同会社を設立した場合も社会保険への加入義務が発生します。特に健康保険と厚生年金保険は、合同会社であっても必ず加入しなければならない社会保険です。
合同会社の社会保険加入義務に関する気をつけておきたい注意点

ただし、合同会社の社会保険加入義務は「従業員を雇う場合」と「従業員を雇わず一人社長のみの場合」で異なります。
以下では、合同会社におけるそれぞれの社会保険加入義務について解説します。
一人社長の合同会社と社会保険の加入義務
従業員がいない一人社長の合同会社の場合、社会保険の加入義務は次のようになります。
- 健康保険:加入義務あり
- 厚生年金保険:加入義務あり
- 雇用保険:加入義務なし
- 労災保険:加入義務なし
一人社長の合同会社でも、健康保険と厚生年金保険は社会保険として必ず加入義務があります。一方、労災保険や雇用保険といった労働保険は「雇用される従業員」が対象のため、従業員を雇わない合同会社では加入義務がありません。
SoVa税理士ガイド編集部
合同会社の社会保険加入義務について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:合同会社設立時の社会保険【簡単に】いつから?手続きは?
従業員を雇用する合同会社と社会保険の加入義務
合同会社を設立し、従業員を雇う場合は社会保険加入義務の範囲が広がります。
- 健康保険:加入義務あり(短時間労働者は条件により対象外)
- 厚生年金保険:加入義務あり(短時間労働者は条件により対象外)
- 雇用保険:加入義務あり(週20時間以上勤務、31日以上の雇用見込みありの場合)
- 労災保険:全従業員に加入義務あり
合同会社に従業員を雇用した時点で、社会保険と労働保険の加入義務が発生します。パートやアルバイトなど短時間労働者は一定条件を満たさない場合、健康保険と厚生年金保険の加入義務が免除されます。
短時間労働者と社会保険の加入義務の例外
合同会社で雇用されるパート・アルバイトでも、次の条件に該当する場合は社会保険の加入義務がありません。
- 週の所定労働時間が20時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円未満
- 雇用の見込みが2ヶ月以内
- 学生である
合同会社の社会保険加入義務に関するおすすめ記事:合同会社設立後も社会保険の加入は義務!手続きや保険料、副業の場合を解説
ただし、これらの条件に当てはまらない場合は合同会社の従業員として社会保険加入義務が生じます。
社会保険に加入できない合同会社のケース
原則として合同会社には社会保険の加入義務がありますが、従業員がいない一人社長の合同会社で「役員報酬がゼロまたは極端に低額な場合」は社会保険に加入できないことがあります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
以下の記事も是非参考にしてください。
「 合同会社に税理士は必要か?依頼する場合のメリット・デメリットを解説! 」
健康保険・厚生年金保険は、合同会社から役員報酬を得ていることが加入義務の前提です。そのため、報酬がゼロであれば加入義務は生じません。また、報酬が低額すぎる場合も社会保険料の徴収が難しく、結果的に社会保険加入が認められないケースがあります。
このような場合は、合同会社の実態や役員報酬額を踏まえ、年金事務所に確認することが推奨されます。
合同会社における社会保険の負担割合

合同会社を設立すると、社会保険への加入義務が発生します。社会保険に加入した場合、合同会社が保険料の一部を負担し、残りを従業員が負担する仕組みになっています。合同会社における社会保険の負担割合は以下の通りです。
合同会社の社会保険加入義務に関するおすすめ記事
- 健康保険:合同会社と従業員が50%ずつ負担します。社会保険の中核であり、病気やケガの医療費を支える重要な制度です。
- 厚生年金:合同会社と従業員が折半(50%ずつ)で負担します。将来の年金額を支えるため、合同会社にとっても必ず加入義務がある社会保険です。
- 介護保険:40歳以上の従業員が対象となり、こちらも合同会社と従業員が50%ずつ負担します。社会保険の一部として、介護サービスを利用する際に役立ちます。
- 雇用保険:合同会社と従業員の双方で負担しますが、料率は年度ごとに変動します。社会保険と並んで、雇用の安定を守るための加入義務があります。
- 労災保険:労災保険については従業員の負担はなく、合同会社が全額を負担します。従業員を守るための保険であり、合同会社の重要な責務です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
これらの社会保険料は、従業員の給与から天引きされ、合同会社が従業員分と会社負担分を合わせて納付する仕組みです。
したがって、合同会社を運営する以上、社会保険の加入義務を正しく理解し、適切に対応することが不可欠です。
合同会社が社会保険に加入する方法

合同会社を設立すると、社会保険への加入義務が必ず発生します。社会保険は健康保険・厚生年金保険を中心に構成され、合同会社を含むすべての法人は適用事業所として扱われます。そのため、合同会社を設立した後は、社会保険の加入義務に基づき、健康保険や厚生年金保険の新規適用届を提出する必要があります。
ここでは、合同会社における社会保険加入義務の具体的な手続きや必要書類について詳しく解説します。

合わせて読みたい「合同会社 一人社長 給料」に関するおすすめ記事

合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を決める際の決め方と注意点
合同会社を設立したときの社会保険加入方法
合同会社は法人格を持つ事業体であるため、設立後には社会保険の加入義務が生じます。具体的には、健康保険と厚生年金保険の適用事業所として扱われるため、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必須です。
必要書類
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 商業登記簿謄本(コピー不可、90日以内発行の原本)
合同会社の社会保険加入義務に関するおすすめ記事
提出先は日本年金機構で、管轄の年金事務所に窓口持参、郵送、電子申請のいずれかで手続きを行います。合同会社の社会保険加入義務を果たすには、この新規適用届の提出が第一歩となります。
合同会社が従業員を雇用したときの社会保険加入方法
合同会社で従業員を雇用した場合、従業員を社会保険に加入させる義務が生じます。その際には「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
提出方法
- 管轄の年金事務所窓口に持参
- 郵送
- 電子申請
必要事項
- 氏名、生年月日、個人番号(または基礎年金番号)
- 被扶養者の有無など
合同会社が従業員を採用した時点で社会保険加入義務が発生し、加入対象者の情報を正しく届け出ることが求められます。
合同会社における労働保険の加入方法
合同会社で従業員を1人以上雇用する場合、社会保険だけでなく労働保険(労災保険・雇用保険)にも加入義務があります。
必要書類
- 保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
一元適用事業(一般的な業種)の場合、保険関係が成立した日から10日以内に「保険関係成立届」を労働基準監督署へ提出しなければなりません。また、雇用保険については「雇用保険適用事業所設置届」を10日以内に公共職業安定所へ提出します。

合わせて読みたい「合同会社で税理士に依頼する時の費用」に関するおすすめ記事

合同会社に顧問税理士は必要?費用やメリット・デメリットについても知りたい!
さらに、雇用した従業員については「雇用保険被保険者資格取得届」を雇入れ日の翌月10日までに提出する必要があります。加えて、保険関係成立日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署または都道府県労働局に提出し、日本銀行や歳入代理店で概算保険料を納付することが合同会社の義務となります。
二元適用事業に該当する合同会社の場合
農林漁業や建設業など、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要がある合同会社は「二元適用事業」に該当します。
合同会社の社会保険加入義務はここがポイント!

この場合、提出先は分かれ、労災保険分は労働基準監督署、雇用保険分は公共職業安定所へ提出しなければなりません。
合同会社の社会保険加入義務に加え、労働保険加入義務を正しく履行するためには、事業区分に応じた正確な対応が必要です。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
加入義務があるのに社会保険に加入しなかった場合

合同会社には社会保険への加入義務があります。もし加入義務を怠ると、さかのぼり加入や保険料の追徴、延滞金、行政指導、さらには従業員トラブルなど、合同会社に大きなリスクが及びます。ここでは未加入時の具体的な措置を解説します。
加入義務があるのに社会保険に加入しなかった場合の措置①:さかのぼり加入
合同会社は法人である以上、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務があります。もし合同会社が社会保険の加入義務を怠った場合、年金事務所によって未加入が発覚すると「さかのぼり加入」を命じられます。この場合、合同会社は設立時や従業員雇用時にさかのぼって社会保険料を納付しなければなりません。
加入義務があるのに社会保険に加入しなかった場合の措置②:保険料の追徴
合同会社が社会保険の加入義務を果たさず未加入のまま放置すると、後日、社会保険料を一括で追徴されます。
合同会社の社会保険加入義務に関する気をつけておきたい注意点

社会保険料は会社と従業員で折半する仕組みですが、未加入期間が長いほど合同会社の負担は重くなります。
追徴の対象は健康保険・厚生年金保険の両方に及び、合同会社にとって大きなリスクです。
加入義務があるのに社会保険に加入しなかった場合の措置③:延滞金・加算金
社会保険の加入義務を怠った合同会社には、延滞金や加算金が課されることがあります。これは本来、加入義務を果たしていれば支払うべき社会保険料を納めなかったペナルティであり、合同会社の経営に余計なコストが発生します。特に長期間の未加入は大きな負担につながります。
加入義務があるのに社会保険に加入しなかった場合の措置④:行政指導
社会保険への加入義務を無視した合同会社に対しては、年金事務所から行政指導が行われます。これは社会保険の適用事業所である合同会社に対して法的義務を周知し、速やかな加入を促すための措置です。行政指導を受けると、合同会社の信用やイメージにも影響が及ぶ可能性があります。
SoVa税理士ガイド編集部
合同会社の社会保険加入義務についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
まとめ

合同会社を設立した場合、社会保険への加入義務は法律で定められており、避けることはできません。健康保険や厚生年金保険を中心に、合同会社が社会保険に加入することは従業員の安心と生活を守るだけでなく、会社としての信用にも直結します。また、加入義務を無視すると、さかのぼり加入や社会保険料の追徴といった大きなリスクが発生します。
したがって、合同会社を運営する経営者は、社会保険の加入義務を正しく理解し、適切に手続きを進めることが重要です。社会保険の加入は合同会社にとって責務であり、会社と従業員双方の安心につながる大切な制度であるといえるでしょう。
合同会社の社会保険加入義務に関するおすすめ記事:合同会社で社会保険の加入は必要?手続きから保険料の計算方法まで解説

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事

会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!