一人法人の社会保険はどうなる?加入条件や一人法人のメリットを解説
カテゴリー:
公開日:2025年8月
更新日:2026年2月12日
一人で設立した法人、いわゆる一人法人においても、社会保険の加入義務は原則として発生します。「従業員がいないから不要」と思っていると、後に多額の社会保険料を遡って請求されるリスクもあります。
本記事では、一人法人の社会保険に関する基本的な考え方や、加入条件、手続き方法、加入しない場合のリスクまでをわかりやすく解説します。あわせて、一人法人として法人化するメリットについても触れていきますので、これから会社設立を検討している方はぜひ参考にしてください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
【労務手続きを自分でするのはリスク大!】
社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由
社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。
社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。
ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。
また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」
社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。
だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
一人法人でも社会保険の加入義務がある

従業員を雇わず、代表者一人で設立した法人は一人法人と呼ばれます。一人法人を立ち上げる際に特に重要なのが、社会保険への加入手続きです。役員報酬が発生している場合、従業員の有無にかかわらず、社会保険に加入する義務が発生します。
ここでいう社会保険とは、狭義には健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを指します。労災保険や雇用保険は社会保険には含まれず、労働保険として別に扱われます。本記事では狭義の社会保険にフォーカスして解説します。
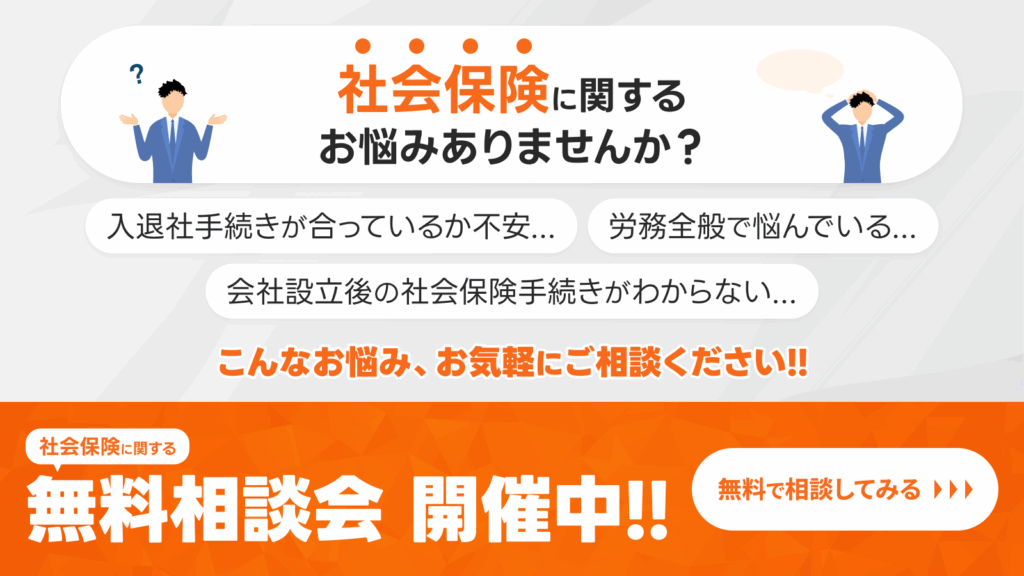
一人法人は社会保険の強制適用事業所になる
一人法人を設立すると、その法人は原則として社会保険の「強制適用事業所」に該当します。これは、法人格を持つ事業所である以上、従業員の有無にかかわらず社会保険に加入しなければならないという制度上のルールです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人の代表である一人法人の社長本人も社会保険の被保険者となり、会社から受け取る役員報酬額に応じて社会保険料を納める義務があります。社会保険料は法人・個人双方での負担となるため、設立前にしっかりと計算しておく必要があります。
一人法人でも労働保険は原則不要
社会保険とは異なり、労働保険(労災保険・雇用保険)は原則として従業員を雇用していない一人法人には適用されません。
SoVa税理士ガイド編集部
ただし、労災保険については「特別加入制度」を利用すれば、一人法人の代表者自身も任意で加入することが可能です。
一人法人を複数設立した場合も社会保険に注意
一人で複数の一人法人を設立するケースでは、それぞれの法人が独立した強制適用事業所となるため、すべての一人法人について社会保険の加入手続きが必要となります。
一人法人の社会保険に関するおすすめ記事
さらに、同一人物が複数の一人法人で代表を務めている場合は、それぞれの会社で社会保険に加入する必要があります。このとき、健康保険証は「主たる事業所」を一つ選んで届け出を行い、社会保険料は各法人の役員報酬額に応じて按分して支払う形となります。
一人法人を設立した際の社会保険の変化

一人法人を設立すると、社会保険の取り扱いも大きく変わります。法人を設立することで、健康保険法や厚生年金保険法といった法律の適用対象となり、「社会保険」への加入義務が発生します。

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介
一人法人の社長であっても、役員報酬が発生していれば、個人事業主時代のように国民健康保険や国民年金には継続加入できません。代わりに、法人として社会保険へ加入する必要があります。
なお、役員報酬がゼロ、あるいはごく少額であれば、引き続き国民健康保険・国民年金に加入し続けることも可能ですが、原則として一人法人での社会保険加入が基本ルールです。
SoVa税理士ガイド編集部
一人法人の社会保険についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
一人法人では健康保険は協会けんぽへ加入
一人法人を設立した場合、健康保険は「国民健康保険」から「全国健康保険協会(協会けんぽ)」への加入が一般的です。
協会けんぽに加入すると、個人としての負担額は一見少なくなりますが、法人(=一人法人)としても保険料を折半で負担する義務があります。そのため、最終的に一人法人全体での支出は、国民健康保険よりも高くなるケースが多くなります。
たとえば、年収500万円(月収約42万円)の一人法人社長で比較すると、一人法人では個人負担が減っても、法人としての負担が発生し、結果として社会保険料全体の支払額は増加します。
| 保険の種類 | 月額保険料(個人負担) | 法人負担額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 約30,000円(自治体により変動) | なし | 約30,000円 |
| 協会けんぽ | 約20,500円 | 約20,500円 | 約41,000円 |
一人法人では国民年金から厚生年金へ
一人法人を設立すると、年金制度も変更されます。具体的には、国民年金から脱退し、法人を通じて「厚生年金」に加入することになります。
「マイクロ法人」編集部
マイクロ法人に関連して、「 マイクロ法人のメリットとは?経費にできるものについても解説! 」の記事も是非ご覧ください。
国民年金の保険料は定額制で、2021年度の月額は約16,000円でした。一方、厚生年金は報酬比例型で、収入が多くなるほど保険料も増加します。
月収42万円の一人法人の社長であれば、厚生年金の保険料は以下の通りです。
| 年金の種類 | 月額保険料(個人負担) | 法人負担額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 約16,000円 | なし | 約16,000円 |
| 厚生年金 | 約37,500円 | 約37,500円 | 約75,000円 |
SoVa税理士お探しガイド編集部
確かに厚生年金の保険料は高額ですが、その分将来の年金受給額は国民年金よりも多くなります。
一人法人として長期的な資産形成を考える場合、厚生年金への加入はメリットも大きいといえるでしょう。
一人法人を設立するメリット

一人法人は社会保険の加入義務があるものの、それを上回る多くのメリットがあります。節税の幅が広がるだけでなく、融資や信用面、将来の雇用体制構築においても有利に働きます。
ここでは、社会保険への加入を前提とした上で、一人法人ならではの6つの代表的なメリットについてわかりやすく解説します。
1人社長の関連記事:「1人社長は儲かる?1人社長が儲かる理由やデメリットについても解説!」
一人法人のメリット①:多彩な節税が可能になる
一人法人を設立することで、個人事業主よりも幅広い節税対策が可能になります。たとえば、青色申告事業者であれば個人事業主も損失の繰越控除(3年間)が認められていますが、一人法人ではこの損失繰越が最大9年間に延長されます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
また、出張旅費規程や社宅制度などを整備すれば、実質的に生活費の一部を法人経費として処理できる可能性もあり、節税効果が大きくなります。こうした制度を活用するためには、「一人法人」としての社内規定や会計処理をきちんと整えることが重要です。

合わせて読みたい「出張旅費規程の作り方」に関するおすすめ記事

出張旅費規程の作り方は?具体的な手順や注意点についても解説!
さらに、一人法人では社会保険に加入することが義務となるため、保険料の支払いは発生しますが、これも必要経費として処理できます。
一人法人のメリットはここがポイント!

売上が年間800万円を超えてくると、法人化による節税メリットはより顕著になります。
一人法人のメリット②:融資が受けやすくなる
個人事業主と異なり、一人法人では事業用の口座と個人口座を明確に分けて管理する必要があります。このように資金管理が法人として明瞭になることで、金融機関も事業性を評価しやすくなり、融資審査の通過率が高まります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
また、一人法人として「社会保険」への加入実績があることも、事業の継続性や安定性のアピール材料になります。結果として、創業融資や運転資金の調達をよりスムーズに行える可能性が広がります。
一人法人の社会保険に関するおすすめ記事:一人社長も会社設立時には社会保険加入が必須!必要な書類や手続きをわかりやすく解説
一人法人のメリット③:責任の範囲が限定される
個人事業主の場合、万が一のトラブルや損害が発生した場合には、全責任を個人が背負うことになります。しかし一人法人を設立すれば、損失の責任は法人が負うことになり、個人の資産まですべて失うリスクは原則としてありません。
一人法人の責任範囲は、基本的には設立時に設定した資本金の範囲内に限定されます。このように「有限責任」である点も、一人法人の大きなメリットです。
一人法人のメリット④:社会保険制度を活用しやすくなる
個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入しますが、一人法人では健康保険(協会けんぽ)および厚生年金への「社会保険」加入が義務づけられます。

合わせて読みたい「社会保険の無料相談窓口」に関するおすすめ記事
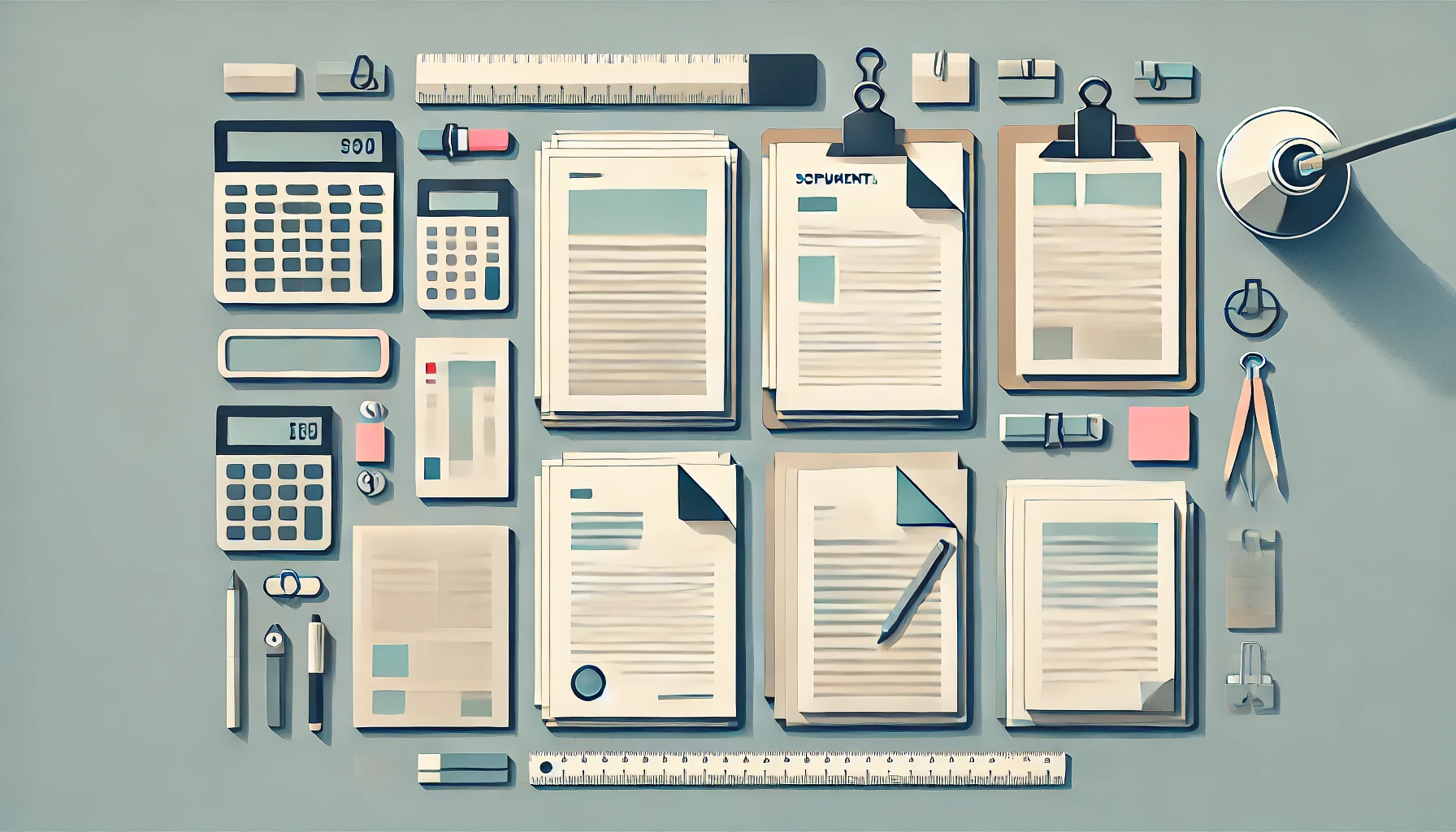
法人の社会保険の無料相談窓口はどこ?困ったときの問い合わせ先を紹介
一見、社会保険料の負担が増えるように見えますが、厚生年金は将来の年金受給額が増えるというメリットがあり、健康保険も手厚い保障内容を受けられるため、長期的にはプラスとなることが多いです。
一人法人の社会保険に関するおすすめ記事
さらに、社会保険への加入は、将来的に従業員を雇用する際の制度整備にもつながり、人材確保の観点でも好影響を与えます。
一人法人のメリット⑤:将来的な雇用や拡大がしやすくなる
一人法人を設立しておくことで、将来的に従業員を雇用しやすくなります。求職者にとって、社会保険に加入している法人で働けることは安心材料となり、求人の応募率アップにもつながります。
社会保険制度の整備は、採用面だけでなく、社内の福利厚生制度の基盤としても機能するため、事業のスケールアップを見据えるなら一人法人としての体制構築が有利です。
一人法人のメリット⑥:社会的信用が向上する
一人法人は、個人事業主よりも社会的な信用力が高まる点も見逃せません。法人登記されていることで、契約や取引の場面でも安心感を持たれやすく、パートナー企業や顧客からの信頼が得やすくなります。
また、社会保険に加入していることも、事業の「継続性」や「透明性」の証明になり、ビジネスの信頼性をさらに高める要素となります。
一人法人が社会保険に加入する方法

一人法人を設立すると、健康保険・厚生年金保険・労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きが必要になります。とくに健康保険と厚生年金保険は「社会保険」としてセットで加入義務があるため、手続きを漏れなく行いましょう。

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事

会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
一人法人の社会保険手続き:健康保険・厚生年金編
一人法人が社会保険に加入する場合、会社設立日から5日以内に「年金事務所」での手続きが必要です。健康保険・厚生年金・介護保険はまとめて手続きできます。
必要書類
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 被保険者 資格取得届(役員や従業員分)
- 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
一人法人の社会保険に関するおすすめ記事
登記簿謄本(原本)も添付が必要で、書類提出は窓口・郵送・電子申請いずれも可。一人法人で役員報酬を設定している場合、社長自身の社会保険資格取得届の提出も必須です。
一人法人で家族を扶養に入れる場合の届出
社長が一人法人で配偶者や子どもなどを扶養に入れる際は、「健康保険被扶養者(異動)届」が必要です。戸籍謄本や住民票(90日以内発行)などの添付が求められます。変更があった場合も5日以内に提出をするようにしましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
一人法人が労災保険に加入する場合
一人法人では、従業員がいなければ労災保険の加入義務はありません。
一人法人の社会保険はここがポイント!

ただし、社長自身が現場作業などを行う場合は「特別加入制度」で労災保険に加入することが可能です。
従業員を雇った場合は以下の書類を労働基準監督署へ提出します。
必要書類
- 保険関係成立届(設立日翌日から10日以内)
- 労働保険 概算保険料申告書(50日以内に保険料を納付)
労災保険料は業種別の料率に基づき計算されます。
一人法人で雇用保険に加入する際の手続き
従業員を雇った一人法人は、所定の労働条件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たす従業員に対し、雇用保険への加入義務が発生します。
必要書類
- 雇用保険適用事務所設置届
- 雇用保険 被保険者資格取得届
雇用契約書、賃金台帳、出勤記録などを添付し、設置届は雇用開始後速やかに、資格取得届は取得日の翌月10日までにハローワークへ提出します。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
一人法人が社会保険に加入しなかった場合

一人法人の税理士に依頼に関する参考記事:「資金調達を税理士に依頼するメリットやおすすめポイントについて詳細に解説!」
一人法人であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は法的義務です。
「従業員がいないから」「手続きが面倒だから」と放置していると、年金事務所からの指導や警告、最終的には立入検査・強制加入といった厳しい対応が待っています。さらに、過去に遡った保険料の支払い義務や助成金の不支給といった経営上の大きな損失にもつながりかねません。
この章では、一人法人が社会保険に加入しなかった場合に起こりうる具体的なリスクについて解説します。
一人法人が社会保険に加入しなかった場合①:年金事務所から加入要請が届く
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
一人法人であっても、法人である以上、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は法律で義務付けられています。役員報酬が発生している一人法人が社会保険に加入していない場合、まず年金事務所から加入要請が届きます。
一人法人の社会保険に関するおすすめ記事
国税庁が把握している給与支払情報などをもとに、社会保険未加入の一人法人に対して指導が行われます。電話や書面での案内が来た時点で、該当する一人法人は速やかに社会保険の手続きを行うべきです。
一人法人が社会保険に加入しなかった場合②:警告文書や訪問指導を受ける
年金事務所からの加入要請を無視し続けると、次に届くのは警告文書です。その後、担当職員による訪問指導が行われ、社会保険への加入を強く促されます。一人法人であっても、加入対象である以上、この段階での放置は大きなリスクです。
一人法人が社会保険に加入しなかった場合③:立入検査と強制加入
さらに放置を続けると、年金事務所の職員による立入検査が実施されます。検査では、賃金台帳、役員報酬の明細、労働者名簿などの提出を求められ、社会保険の加入義務があると認定されれば「強制加入」扱いとなります。
一人法人の代表者にも「受忍義務(立ち入りを拒否してはならない義務)」が課せられており、調査に協力する義務があります。
SoVa税理士ガイド編集部
さらにこの強制加入は過去に遡って最大2年分の社会保険料を請求されることがあり、法人の財務に大きな打撃を与える可能性があります。
一人法人が社会保険に加入しなかった場合④:助成金の対象外になる
一人法人が従業員を雇い、雇用保険にも加入すべき状態であるにもかかわらず、社会保険に未加入であれば、各種の雇用助成金の申請もできません。雇用調整助成金やキャリアアップ助成金などの多くは、雇用保険の適用事業所であることが前提条件です。
社会保険に加入していないことで、法人だけでなく従業員にも不利益が生じるため、一人法人であっても早めの手続きが重要です。
まとめ

一人法人であっても、社会保険への加入は法律で義務づけられており、役員報酬が発生している限りは避けられません。加入手続きを怠ると、年金事務所からの指導や強制加入、過去の保険料請求といった重大な影響を受ける可能性があります。
一方で、一人法人は節税や社会的信用、融資・採用面などで大きなメリットも得られます。適切に社会保険へ加入し、制度をうまく活用することで、将来的なリスクを回避しながら事業の安定と成長につなげることができるでしょう。
一人法人の社会保険に関するおすすめ記事:一人社長も社会保険の加入義務はある?会社設立時の手続きと必要書類
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい!