新入社員の入社手続きで必要な準備は?必要書類や具体的な手続き内容を解説!
カテゴリー:
公開日:2025年3月
更新日:2025年12月23日
新入社員を採用した際には、さまざまな入社手続きが必要です。新入社員の入社前の準備に加え、社会保険や税金に関する手続き、入社後の社内対応など、業務は多岐にわたります。
また、新入社員の入社手続きの中には、期限が定められているものも多く、漏れや不備のないように、迅速かつ正確に進めることが重要です。新入社員がスムーズに業務を開始できるよう、円滑に手続きを進めていきましょう。本記事では、新入社員の入社前後に必要な書類や手続きなどの業務について、詳しく解説します。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

目次
新入社員の入社手続きの流れ

新入社員を雇用する際に必要な手続きや届出書類について一通り説明しました。新入社員一人ひとりについて細かくて重要な手続きが多くありました。
では、今度はこれらの手続きを含め、全体的にどのような手順で新入社員の雇用手続きを進めていったら良いのかをみていきましょう。
新入社員の入社手続きに関するおすすめ記事
新入社員の入社手続きSTEP①:労働条件の明示・雇用契約の締結
新入社員の採用が決まったら、まず労働条件を明示します。前に述べた労働条件通知書または雇用契約書を示し、双方が納得したうえで署名押印し、雇用契約を結びます。
「会社設立後に税務署に提出すべき書類」編集部
会社設立をすると様々なものを経費にすることができます。会社設立で経費にできるもの一覧はこちらを参照ください。
新入社員の入社手続きSTEP②:労働保険・社会保険への加入手続き
新入社員が安心して働くために、労働保険と社会保険の手続きを行います。
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。労災保険は業務中や通勤中などに怪我や病気をした場合に給付される保険で、雇用保険は職を失った場合に給付される保険で、一人でも新入社員を雇っている事業所はすべて加入する義務があります。
新入社員の入社手続きに関するおすすめ記事
雇用保険は、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」を受け取って新入社員に渡します。労災保険に関しては、とくに手続きは必要ありません。 社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことです。

合わせて読みたい「従業員の退職手続き」に関するおすすめ記事
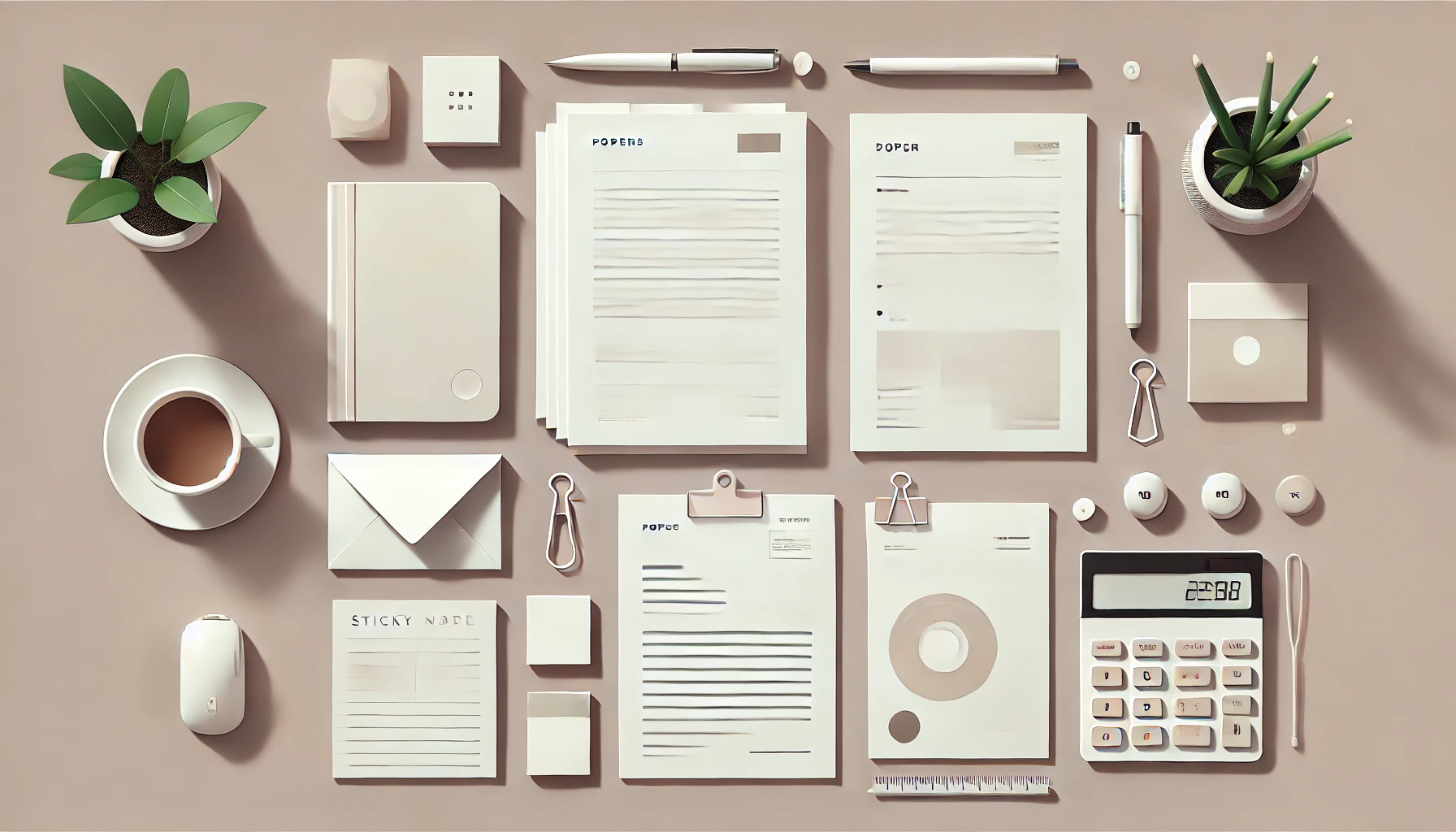
従業員の退職手続きは何をする?必要書類や会社側・従業員側でやることを解説
新入社員の入社手続きSTEP③:各種書類を提出する
新入社員に関する社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、所得税、住民税など、これまでに説明した書類を作成し、健康保険組合や年金事務所、ハローワーク、税務署、役所などに提出します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
また、新入社員に渡すべき書類も忘れずに渡すようにしましょう。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
新入社員の入社手続きに必要な書類

新入社員と会社は、入社手続きの際に必要となる入社書類を用意する必要があります。
会社が新入社員の入社前に用意する書類には、雇用契約書・労働条件通知書、扶養控除等申告書をはじめとした全5種類の書類が必要です。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」
一方で新入社員は、雇用保険被保険者証番号、基礎年金番号、給与振込先の口座情報、源泉徴収票、マイナンバーの5種類の書類を提出しなければなりません。

合わせて読みたい「新入社員の有休」に関するおすすめ記事

新入社員の有給はいつ・何日付与すべき?有給のルールや注意点を解説!
本記事では、新入社員の有給が発生する条件や付与日数、分割付与の注意点などを詳しく解説します。新入社員の有給を適切に管理し、円滑な職場環境を整えるために、ぜひ参考にしてください。
新入社員の入社手続きにおいて、どの会社でも共通して必要な書類を中心に、会社が準備すべきものと新入社員が用意すべきものに分けて解説します。
会社が入社前に用意する主な書類
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 扶養控除等申告書
- 健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
- 採用通知書(内定通知書)
- 入社誓約書
SoVa税理士お探しガイド編集部
これらの書類は、新入社員に返信用封筒を添えて郵送し、署名・捺印をして返送してもらうのが一般的です。
雇用契約書・労働条件通知書
雇用契約書・労働条件通知書は、新入社員と会社の間で労働条件の取り決めをまとめたものです。
雇用契約書は双方の署名または記名押印が必要で、発行義務はありませんが、トラブル防止のために取り交わすのが一般的です。

合わせて読みたい「雇用契約書の書き方」に関するおすすめ記事

雇用契約書の書き方とは?2024年の改正についても解説!
労働条件通知書は、労働基準法で交付が義務化されており、会社側の署名または記名押印が必要です。
扶養控除等申告書
扶養控除等申告書は、税金関係や社会保険の手続きに必要な書類で、新入社員が扶養者の有無に関わらず提出しなければなりません。
健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
健康保険被扶養者異動届と国民年金第3号被保険者届は、新入社員の社会保険加入手続きの際に必要となる書類で、扶養者がいる場合に提出が求められます。
採用通知書(内定通知書)
採用通知書(内定通知書)は、新入社員に対して正式な採用の旨を通知する書類です。
入社誓約書
入社誓約書は、就業規則や服務規律、秘密保持に関する内容を記載した書類で、新入社員の署名・捺印が必要です。
一方で、新入社員が入社前に準備すべき主な書類は以下のとおりです。
新入社員の入社手続きに関するおすすめ記事
新入社員が入社前に用意する主な書類
新入社員は、マイナンバー取得などの手続きを役所で行う必要がある場合があるため、事前に準備を促しましょう。
雇用保険被保険者証番号
雇用保険被保険者証番号とは、「4桁-6桁-1桁」で構成される11桁の番号です。新入社員に過去の雇用保険加入履歴がある場合は、提出を求めます。
基礎年金番号
基礎年金番号は、社会保険の手続きに必要な「4桁-6桁」の10桁の番号で、年金手帳や基礎年金番号通知書から確認できます。
給与振込先の口座情報
会社が用意した書類に銀行名や口座番号などを記入する方法や、通帳のコピーを提出する方法などがあります。

合わせて読みたい「キャリアアップ助成金のメリット」に関するおすすめ記事

キャリアアップ助成金とは?メリットや申請時の注意点も解説!
源泉徴収票
源泉徴収票は、新入社員が前の会社で得た収入や支払った所得税が記載された書類で、年末調整時に必要となります。

合わせて読みたい「アルバイトに有休を付与」に関するおすすめ記事

アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説!
この記事では、アルバイトやパートに対する有給付与の詳細や、有給休暇取得時の賃金計算方法、さらに有給付与に関する注意点について詳しく解説します。アルバイトの有給付与に関する正しい知識を身につけ、適切な運用を行いましょう。
マイナンバー
マイナンバーは、税金や保険手続きのために必要な個人番号で、個人番号カードや住民票から確認できます。
新入社員の入社手続きには、多くの書類が関わるため、会社と新入社員がスムーズに準備できるようにしっかりと確認を行いましょう。
新入社員の入社手続きに関するおすすめ記事:従業員の雇用手続きについて解説!必要書類や加入する保険は?
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【新入社員の入社手続き①】社会保険、雇用保険、税金関係の手続き

新入社員の入社手続きは、新入社員の生活に直結するため、速やかに完了させなければなりません。
SoVa税理士ガイド編集部
例えば、健康保険への加入が遅れると、新入社員やその家族が病院をタイミングよく受診できなかったり、受診料が高額になったりすることも考えられます。
漏れなく手続きできるよう、しっかり確認しておきましょう。

合わせて読みたい「入社 住民税 手続き」に関するおすすめ記事

入社時の住民税に関する手続きについて解説!退職時の住民税の手続きも併せて紹介!
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得手続き
新入社員が以下の条件を満たす場合は、年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を、雇用開始から5日以内に提出する必要があります。
社会保険の加入対象
正社員の場合
- 70歳未満であること
派遣社員、契約社員、パート、アルバイトの場合
- 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、派遣元の一般従業員の4分の3以上であること
- 契約期間が2ヶ月以上になること(所定の期間を超えた場合はその日から被保険者となります)
※ ただし、労働日数は4分の3以下でも、以下の条件をすべて満している場合は被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある(残業時間は除く)
- 1年以上の雇用見込がある
- 月給が88,000円以上である(残業手当、通勤手当、ボーナス等は除く)
- 学生ではない
- 法人、個人、地方公共団体、国に属する特定適用事業所に勤務している
新入社員に配偶者や子どもがいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出も必要になるため、事前に確認しておきましょう。配偶者が「国民年金の第3号被保険者※」に該当する場合は、「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を提出します。
新入社員の入社手続きに関するおすすめ記事
雇用保険の資格取得手続き
雇用保険は、「31日以上の雇用が見込め、所定労働時間が週20時間以上」であれば新入社員も加入対象となります。ただし、企業・法人の経営者や役員、日雇い労働者、4ヶ月以内の季節的事業に従事する場合などは、雇用保険被保険者の対象ではないため、手続きを行う必要はありません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
新入社員が入社した際の手続きなどはこちらの年金事務所のサイトを是非参考にしてください。
手続きには、新入社員を雇用した月の翌月10日までに、労働者名簿や出勤簿(タイムカードなど)、雇用契約書など雇用を証明できるものを添えて「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。
新入社員の入社手続きはここがポイント!

新入社員が前職で雇用保険に加入していた場合は、被保険者番号の確認のため「雇用保険被保険者証」を提出してもらいます。
税金に関する手続き
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
手続きを行う必要がある税金関係には、所得税と住民税があります。 所得税は、原則給与から天引きで源泉徴収されます。新入社員が退職した年内に再就職で入社した場合は、以前の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を提出してもらいます。
また、入社時には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も忘れずに記載・提出してもらいましょう。
新入社員の入社手続きはここがポイント!

住民税を給与からの天引きで支払う「特別徴収」にする場合、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を住民税納付先にあたる市町村へ提出する必要があります。
住民税は、前年度分を翌年6月から1年間で後払いをする方式のため、新卒の新入社員など前年の給与がない場合は、翌年の6月から住民税を給与天引きすることになります。新入社員が前職からすぐ転職している場合は、以前の勤務先で必要事項を記載した「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を送付してもらい、同届出書の記載項目にある「転勤(転職)等による特別徴収届出書」欄に記載した上で市区町村に提出することになります。

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
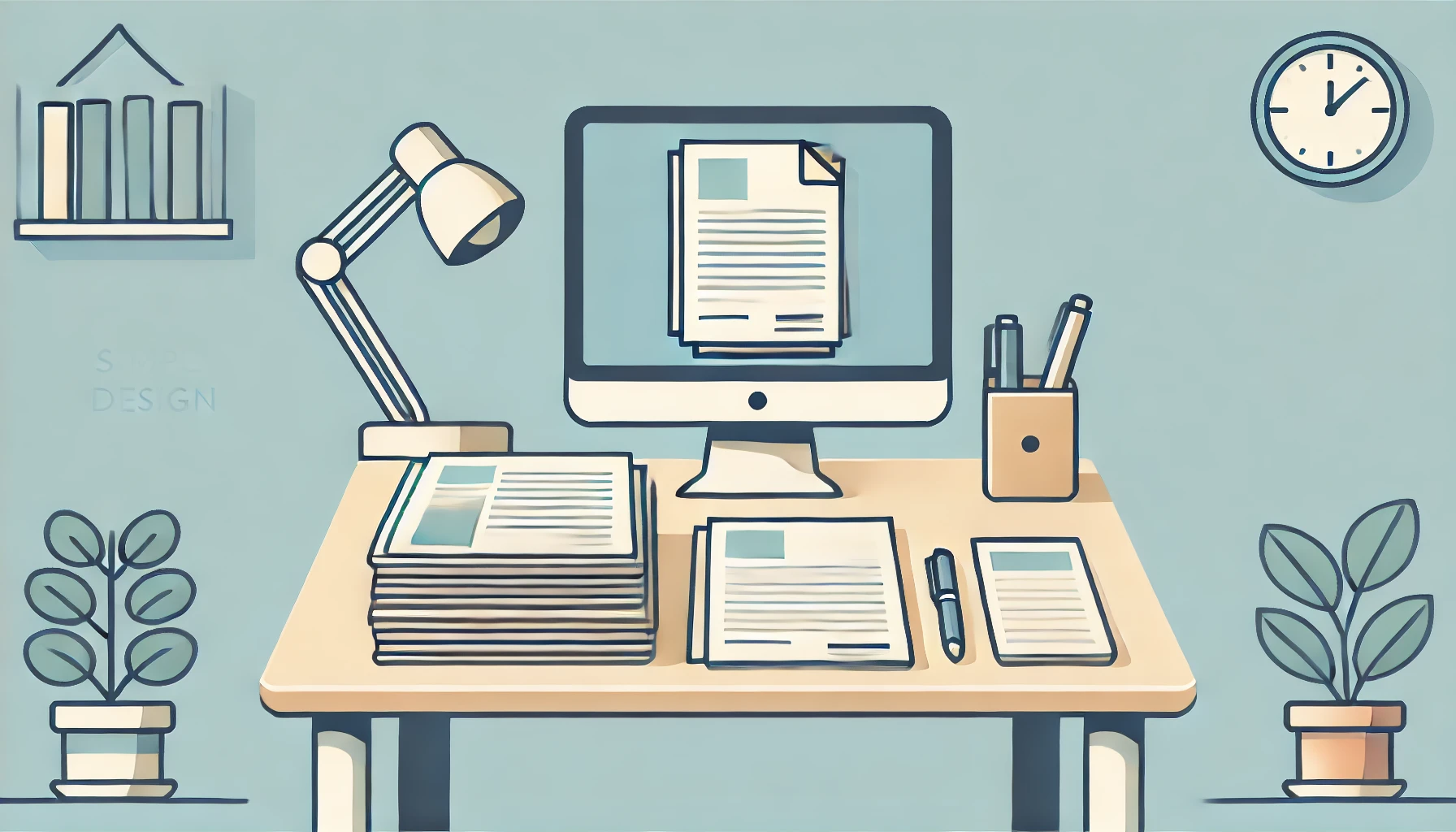
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
労災保険に関する手続き
職務遂行中に起こった事故や通勤を含む業務上の病気、怪我、失業などから新入社員を保障するために加入する「労災保険」については、すでに適用事業所である場合、新入社員ごとの手続きは必要ありません。
【新入社員の入社手続き②】社内手続き

新入社員の雇用に伴う社内手続きは、迅速かつ正確に行うことが重要です。雇用保険や社会保険などの公的な手続きには期限がありますが、それ以外の社内手続きもスムーズな業務開始のために早急に対応する必要があります。
新入社員の雇用に際し、以下のような手続きを進めていきます。
社内手続き①:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成
SoVa税理士ガイド編集部
新入社員の情報を正確に記録するため、「法定三帳簿」の作成が義務付けられています。
- 労働者名簿: 新入社員の性別、住所、業務の種類、入社年月日などを記載し、適切に管理します。
- 賃金台帳: 新入社員を含むすべての従業員の賃金情報を記録します。
- 出勤簿: 新入社員の出勤状況を正確に把握し、適切に保管します。
新入社員の入社手続きに関するおすすめ記事
社内手続き②:貸出物や備品の供給
新入社員が入社後すぐに業務に取り掛かれるよう、必要な備品を準備し、適切に手続きを進めます。
- 制服:制服着用が義務付けられている場合は、新入社員のサイズを事前に確認し、入社日に手渡せるよう準備します。
- 社員証・名刺:労働条件通知の際に取得した情報をもとに作成し、新入社員に誤りのないものを渡します。
- 机・イス・電話・パソコン・事務用品:新入社員の配属先に必要な備品を用意し、スムーズに業務を開始できるよう手続きを行います。
- メールアドレス設定・インターネット環境の準備:新入社員が業務を円滑に進められるよう、メールアドレスや社内ネットワークのID・パスワードを事前に発行しておきます。
- ICカード支給・指紋登録:入退室管理のためのICカードの作成や指紋認証の登録を新入社員の入社前に完了させます。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社内手続き③:給与計算システム・人事システムへの情報入力
新入社員の給与計算や勤怠管理を正確に行うため、必要な情報をシステムに登録します。
- 氏名・住所・扶養親族情報: 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の情報を基に入力します。
- 住民税の支払先: 市区町村ごとに住民税の支払い手続きを行います。
- 銀行口座情報: 新入社員の給与振込口座を事前に登録し、給与支払いに備えます。
新入社員の入社に関する手続きを円滑に進めることで、業務の効率化を図り、スムーズな職場環境を整えましょう。
給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
新入社員の入社手続きでよくある質問

これまで解説してきたように、新入社員の入社時には多くの手続きが必要となります。場合によっては、予定どおりに手続きが進まず、新入社員の対応に困ってしまうことがあるかもしれません。ここからは、新入社員の入社手続きでよくある疑問とその対処法を紹介します。
新入社員の入社手続きでよくある質問①:期日に間に合わなかったときはどうする?
新入社員の社会保険や雇用保険、労災保険の加入手続きには、それぞれ期限が設けられています。基本的には期限を過ぎても手続きは可能ですが、間に合わなかった場合は、できるだけ早く必要書類を提出することが重要です。なお、場合によっては追加の書類提出が求められることがあります。
新入社員の入社手続きで気をつけておきたい注意点

社会保険や雇用保険は、2年前まで遡及して加入することが可能ですが、その場合、未加入期間の保険料が一括で請求される可能性があります。この一括請求により新入社員の負担額が高額になると、新入社員とのトラブルにつながる恐れがあるため、注意が必要です。
また、正当な理由なく社会保険や雇用保険の加入手続きを行わなかった場合、罰金などのペナルティーが発生する可能性があります。同様に、労災保険の加入手続きをせずに未加入だった場合も、追徴金などのペナルティーの対象となります。
新入社員の入社手続きに関するおすすめ記事
新入社員の入社手続きでよくある質問②:新入社員が雇用保険被保険者証書を紛失したときはどうする?
新入社員が雇用保険被保険者証書を紛失してしまうと、雇用保険の手続きに必要な雇用保険被保険者番号が不明となります。その場合は、ハローワークの窓口で再発行手続きを行うことが可能です。
なお、新入社員の雇用保険加入手続きを進める際、「雇用保険被保険者資格取得届」に前職の会社名や在籍期間(雇用保険加入期間)が分かる書類を添付すれば、雇用保険被保険者番号が未記載でも手続きが可能です。
新入社員の入社手続きでよくある質問③:新入社員が年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失したときはどうする?
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
新入社員が基礎年金番号通知書を紛失した場合は、年金事務所等で再交付手続きを行うことが可能です。再交付手続きにあたっては、新入社員本人の届出意思を確認できれば、事業主が申請することもできます。なお、現在、年金手帳は廃止されています。
新入社員の入社手続きでよくある質問④:外国人新入社員の雇用に必要な手続きと書類は?
外国人の新入社員を雇用した場合は、在留カード(国内居住の場合)、パスポート、職務経歴書、卒業見込みまたは卒業証明書(留学生の場合)などの提出書類が必要です。
新入社員の入社手続きはここがポイント!

また、新入社員が外国人の場合、入社の翌月10日までに、ハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出する手続きが義務付けられています。
新入社員の手続きは企業にとって重要な業務の一つです。漏れなく迅速に進めることで、新入社員が安心して働き始める環境を整えましょう。
まとめ

新入社員を即戦力として活躍させるためには、迅速かつ適切な入社手続きが不可欠です。新入社員の入社手続きは、定期的に発生するものではなく、不定期に対応する必要があるため、スムーズに進められるよう事前の準備が重要です。
新入社員の入社手続きに必要な書類の準備や、各種手続きの流れを正確に把握することは、担当者の業務負担を軽減するだけでなく、企業の信頼向上にもつながります。また、新入社員が安心して働ける環境を整える第一歩となります。
SoVa税理士ガイド編集部
特に、法律で定められた期限がある社会保険や雇用保険の手続きは、新入社員の入社時に最優先で対応すべき項目です。
この記事を参考に、いつまでにどの手続きを完了させるべきかを明確に理解し、適切に進めるようにしましょう。
新入社員の入社手続きに関するおすすめ記事
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい!