入社時に必要な社会保険の手続きとは?期限や遅れた場合の対応についても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年3月
更新日:2026年2月24日
従業員を採用した際には、入社手続きの一環として社会保険の加入手続きを含む各種手続きを行う必要があります。
入社手続きの中には、社会保険の加入や各種届け出など、期限が設けられているものがあり、期限までに完了しないと新入社員の労働環境や生活に支障をきたす可能性があります。そのため、採用が決まったら速やかに入社手続きを進めることが重要です。
今回は、入社手続きをいつまでに完了させるべきか、社会保険の手続きを怠った場合のリスク、さらに手続きが遅れた場合の対処法について詳しく解説します。
入社手続きや社会保険に関する疑問を解決できる内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください。

合わせて読みたい「新入社員の入社手続き」に関するおすすめ記事

新入社員の入社手続きで必要な準備は?必要書類や具体的な手続き内容を解説!
目次
【労務手続きを自分でするのはリスク大!】
社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由
社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。
社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。
ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。
また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」
社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。
だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
入社時の社会保険手続きで必要な書類
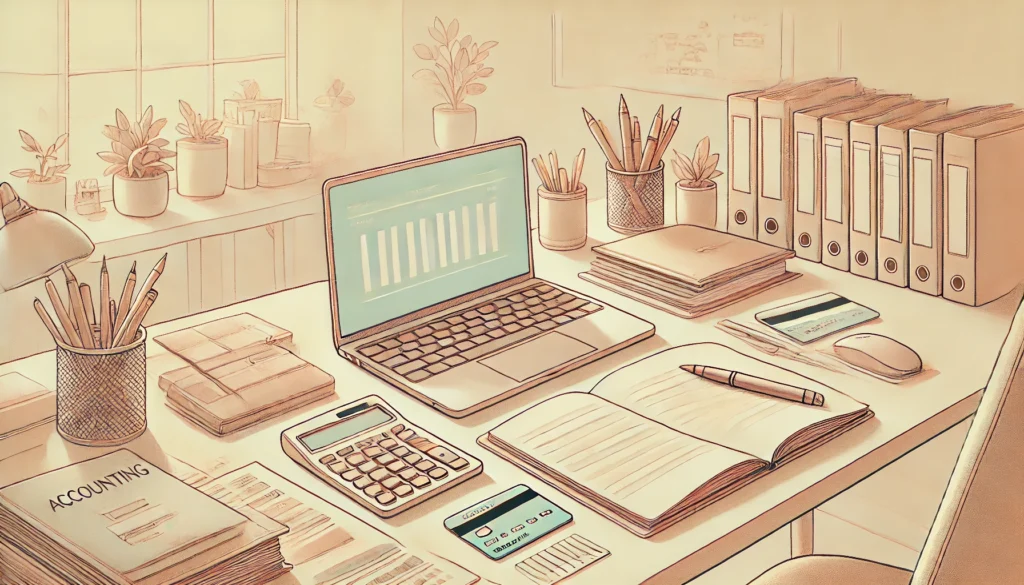
入社手続きの中で特に重要な社会保険の手続きには、以下の書類が必要になります。
社会保険の手続きでは、入社する新入社員の配偶者の有無や世帯構成によって提出すべき書類の種類や数が異なるため、注意が必要です。
入社時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事
入社時の社会保険手続きで必要な書類①:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
入社に伴い、新入社員が社会保険へ加入する際に必要な手続きです。この書類は企業側で作成・提出する必要があり、社員本人が準備する必要はありません。
SoVa税理士ガイド編集部

合わせて読みたい「アルバイトに有休を付与」に関するおすすめ記事

アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説!
この記事では、アルバイトやパートに対する有給付与の詳細や、有給休暇取得時の賃金計算方法、さらに有給付与に関する注意点について詳しく解説します。アルバイトの有給付与に関する正しい知識を身につけ、適切な運用を行いましょう。
入社時の社会保険手続きで必要な書類②:健康保険被扶養者(異動)届
入社手続きの一環として、新入社員に配偶者や子どもなどの被扶養者がいる場合、社会保険の適用を受けるために必要な書類です。
入社時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事:入社手続きの必要書類は?会社側が従業員の雇用時にすべき対応

合わせて読みたい「社会保険と国民健康保険の違い」に関するおすすめ記事

社会保険と国民健康保険の違いは?切り替え時の手続きについて解説!
本記事では、社会保険(健康保険)と国民健康保険の概要、それぞれの社会保険制度の違い、国民健康保険への切り替えが必要なタイミングや社会保険から国民健康保険への手続きを詳しく解説します。
入社時の社会保険手続きで必要な書類③:国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届
新入社員の配偶者が国民年金の第3号被保険者に該当する場合に必要な社会保険手続きです。第3号被保険者とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、主に年収130万円未満の配偶者が対象となります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
入社に際しての社会保険の手続きを適切に行うことで、新入社員が安心して勤務を開始できるようになります。入社後の手続きをスムーズに進めるためにも、必要書類を事前に確認し、迅速に対応することが大切です。
入社に伴う社会保険の加入基準と手続き
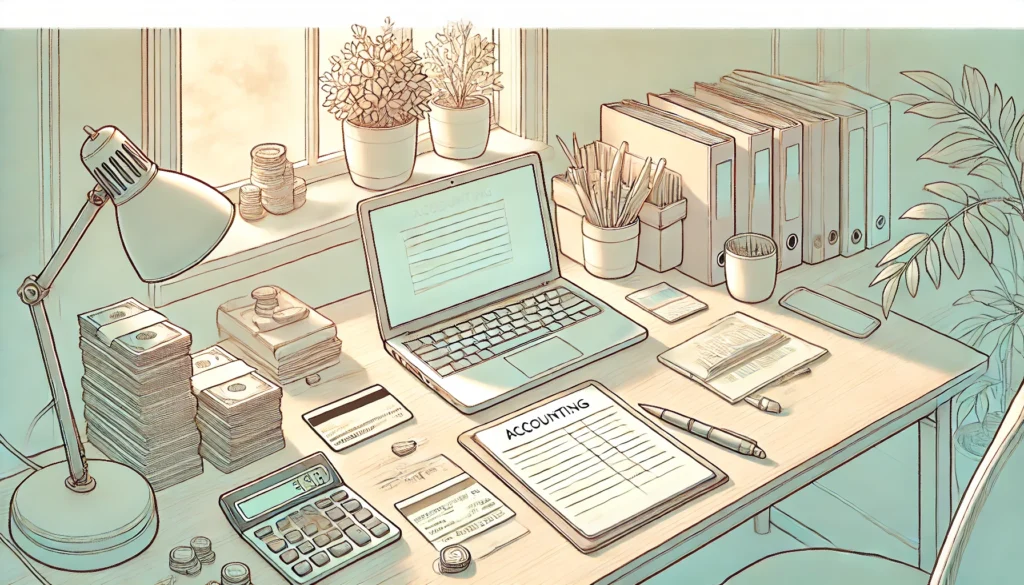

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介
入社手続きの重要なステップとして、社会保険の加入手続きを適切に進めることが求められます。社会保険には、健康保険・厚生年金・介護保険が含まれ、基本的にすべてセットで加入する必要があります。
入社時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事
ただし、厚生年金は70歳未満の従業員のみが加入対象となるため、70歳以上の新入社員については健康保険と介護保険のみの加入手続きが必要です。
会社の社会保険適用基準と入社手続き
社会保険の適用を受ける事業所は、「適用事業所」として分類され、以下の2種類に分けられます。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
「社会保険の加入条件」編集部
社会保険の適用対象が段階的に拡大され、50人以下の企業にも順次義務化されます。
令和9年から令和17年にかけて、従業員数の条件が段階的に引き下げられ、最終的には全ての企業が対象になります。
参考:厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」
1. 強制適用事業所(社会保険の加入手続きが必須)
強制適用事業所では、事業主や従業員の意向に関係なく、社会保険への加入手続きが義務付けられています。以下の事業所が該当します。
- 常時5人以上の従業員を使用する事業所(飲食業・理美容業・農林漁業などの一部業種を除く)
- 事業主を含めて従業員が1人以上いる法人の事業所
- 国や地方公共団体の事業所
「社会保険(厚生年金保険)の加入条件」編集部
社会保険、特に厚生年金保険の加入条件に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
「厚生年金の加入条件を詳しく解説!加入義務対象の従業員や企業の要件とは?」
2. 任意適用事業所(社会保険の加入手続きを申請可能)

合わせて読みたい「従業員50人以下の社会保険加入義務」に関するおすすめ記事
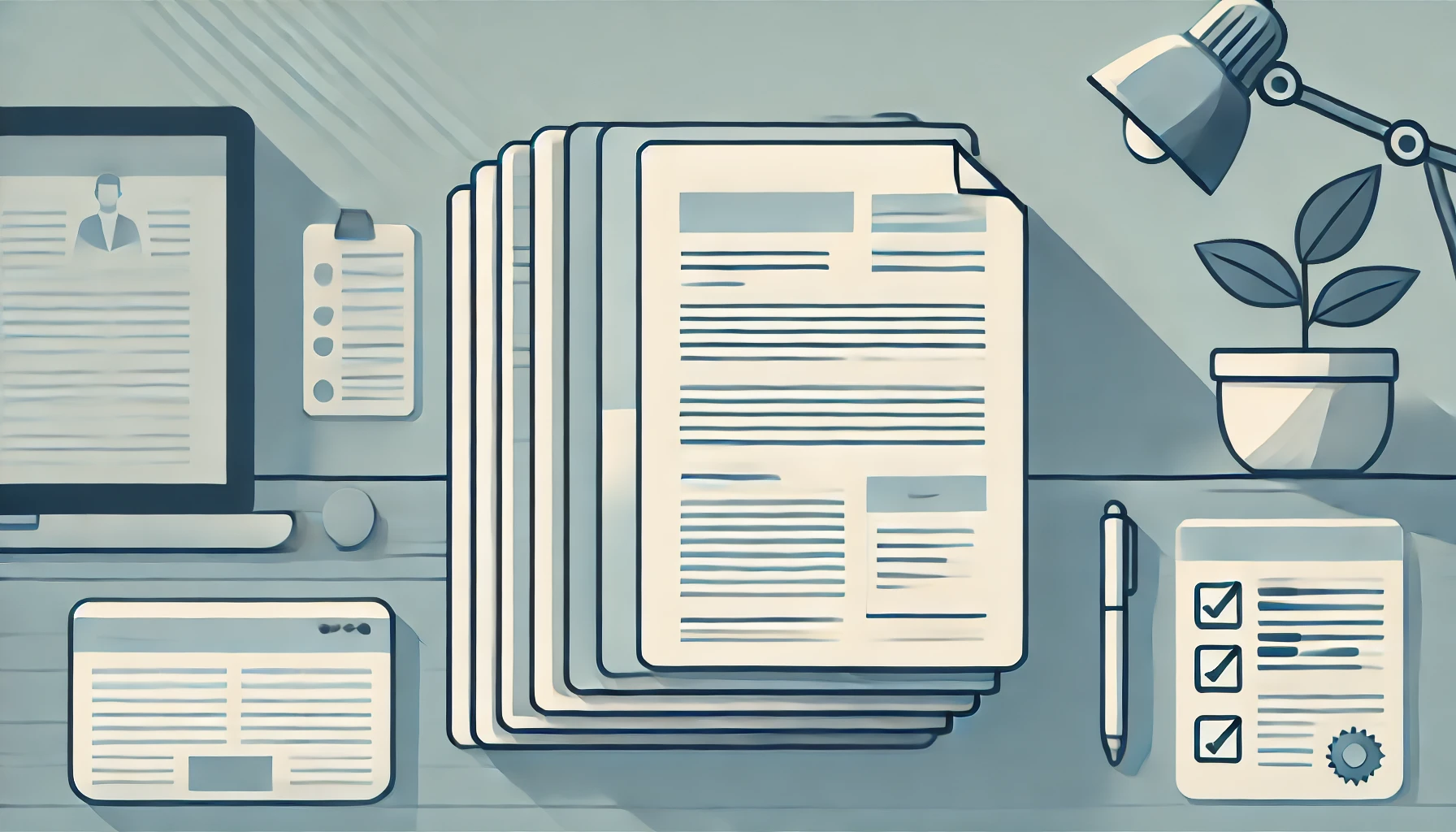
従業員50人以下の会社は社会保険の加入条件に該当する?今後の加入対象拡大についても解説!
本記事では、50人以下の企業が社会保険の加入条件に該当するかどうかの判断基準や、今後の段階的な適用スケジュールについて詳しく解説します。
任意適用事業所は、事業主が申請し、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることで、社会保険の加入手続きを行う事業所です。なお、任意適用事業所では、健康保険・厚生年金のいずれか片方のみの加入も可能です。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
従業員の社会保険加入基準と入社時の手続き
SoVa税理士お探しガイド編集部
新入社員が社会保険に加入する基準は、「一般労働者」と「短時間労働者」に分かれています。入社手続きの際には、従業員の労働条件を確認し、適切に手続きを進めましょう。
| 対象者 | 社会保険加入基準 |
|---|---|
| 一般労働者 | 正社員の4分の3以上の所定労働時間・労働日数、かつ契約期間2か月以上 |
| 短時間労働者 | 以下の全条件を満たす場合、社会保険加入が必要 |
| – 週の所定労働時間が20時間以上 | |
| – 賃金が月額8.8万円以上 | |
| – 学生以外(定時制や夜学等を除く) | |
| – 2か月以上継続して雇用が見込まれる | |
| – 従業員51人以上の事業所に勤務(2024年10月から適用範囲拡大) |
入社時の社会保険手続きを適切に進めることで、新入社員が安心して勤務を開始できる環境を整えることができます。
入社時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事

合わせて読みたい「従業員3人の社会保険」に関するおすすめ記事

従業員3人の場合に社会保険の加入義務はある?社会保険未加入のときの罰則も解説!
入社時の社会保険の加入手続き方法
新入社員を雇用した際には、入社手続きの一環として、社会保険の加入手続きを速やかに行う必要があります。具体的には、以下の手順で手続きを進めます。

合わせて読みたい「新入社員の有休」に関するおすすめ記事

新入社員の有給はいつ・何日付与すべき?有給のルールや注意点を解説!
本記事では、新入社員の有給が発生する条件や付与日数、分割付与の注意点などを詳しく解説します。新入社員の有給を適切に管理し、円滑な職場環境を整えるために、ぜひ参考にしてください。
STEP①:入社から5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を年金事務所または事務センターへ提出する。
STEP②:全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の健康保険組合に加入する場合は、各健康保険組合で別途手続きを行う。
STEP③:電子申請の場合は「e-Gov」または「e-Gov」と連携したシステムを利用して申請を行う。
入社時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事:これさえ押さえておけば大丈夫!従業員の入社手続きを徹底解説
入社時に適切な社会保険の手続きを行うことで、新入社員が円滑に社会保険の保障を受けられるようになります。事業主は、必要な手続きを早めに進め、従業員の社会保険加入を確実に完了させましょう。

合わせて読みたい「固定残業代のメリット・デメリット」に関するおすすめ記事

固定残業代とは?労働者と企業それぞれのメリットデメリットや注意点も解説!
この記事では、固定残業代の基本的な仕組みから、企業・労働者それぞれのメリット・デメリット、導入時の注意点まで、わかりやすく解説します。
入社時の社会保険手続きが遅れた場合のリスクと対応策


合わせて読みたい「雇用契約書の書き方」に関するおすすめ記事

雇用契約書の書き方とは?2024年の改正についても解説!
入社手続きの一環として行う社会保険の加入手続きが遅れると、事業主に対して、入社日から適用されるべき社会保険料をさかのぼって請求されることになります。
入社時の社会保険手続きにおける気をつけておきたい注意点

さらに、手続きの遅延に正当な理由がないと判断された場合、本来の2倍の保険料を追徴される可能性があります。
そのため、入社手続きの段階で速やかに社会保険の手続きを行うことが重要です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
新入社員が入社した際の手続きなどはこちらの年金事務所のサイトを是非参考にしてください。
社会保険の手続きが遅れた場合の対応①:社会保険加入の遅れに気づいたら、早急に手続きを行う

合わせて読みたい「社会保険料の会社負担割合」に関するおすすめ記事

社会保険料の会社負担割合は?社会保険の計算方法や会社負担の注意点を徹底解説!
入社手続きの遅れに気づいた際には、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」をすぐに年金事務所または事務センターへ提出しましょう。合わせて、手続きの遅延理由を記載した「遅延理由書」の提出も求められる場合があります。
入社時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事:従業員の入社手続きにともなう雇用保険・社会保険・税関連の届け出|必要書類や期限
社会保険の手続きが遅れた場合の対応②:社会保険証がない期間の医療費の対応

合わせて読みたい「社顔保険料は4月から6月で決まる?」に関するおすすめ記事
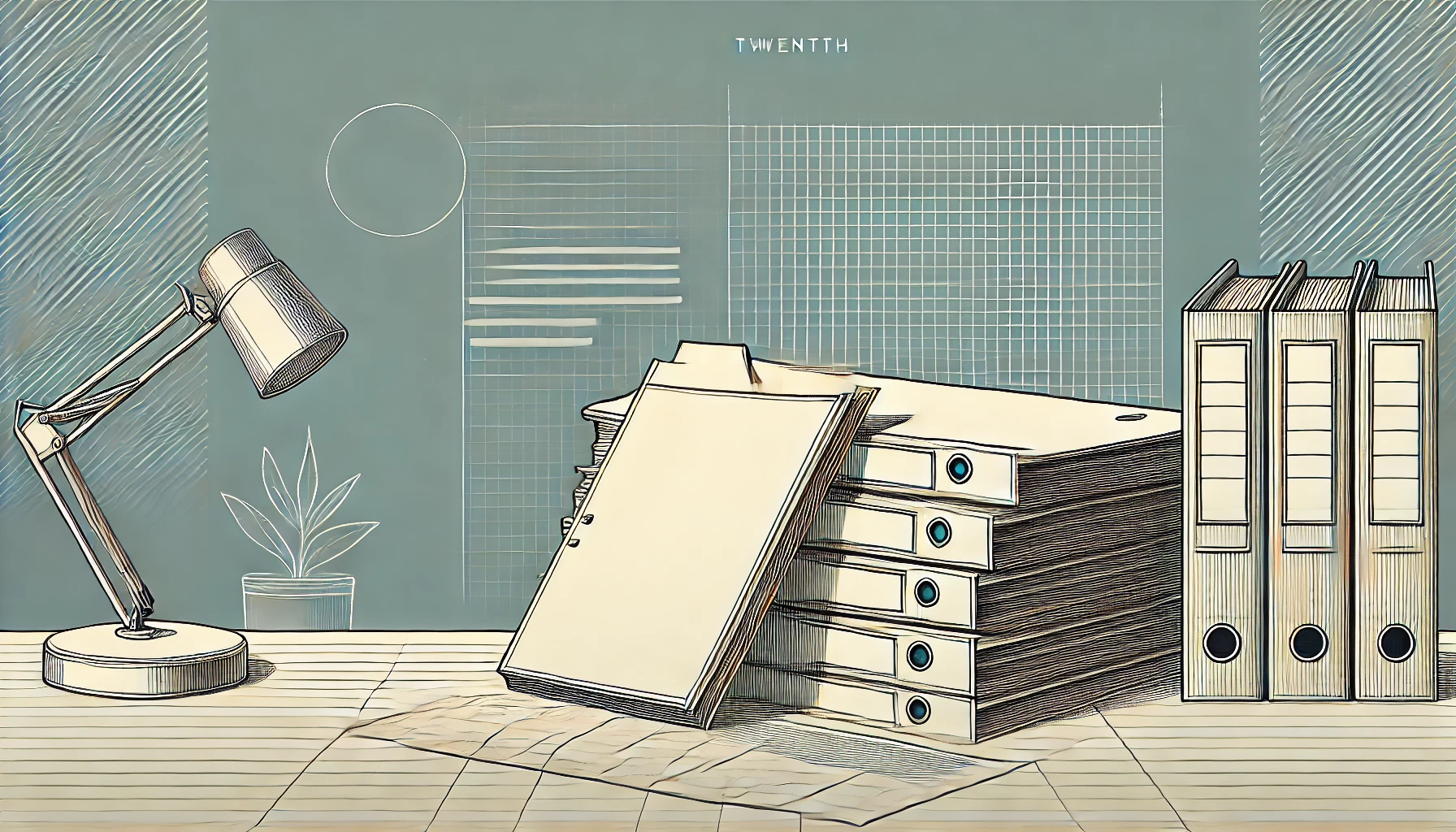
社会保険料は4月から6月で決まる!4月5月6月に残業すると手取りが減る理由を解説
入社後の手続きが完了するまでの間、健康保険証が未発行の状態で医療機関を受診すると、医療費が全額自己負担となります。しかし、後日「療養費支給申請書」を提出することで、社会保険の適用分が払い戻されるため、忘れずに手続きを行いましょう。
入社時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事
まとめ
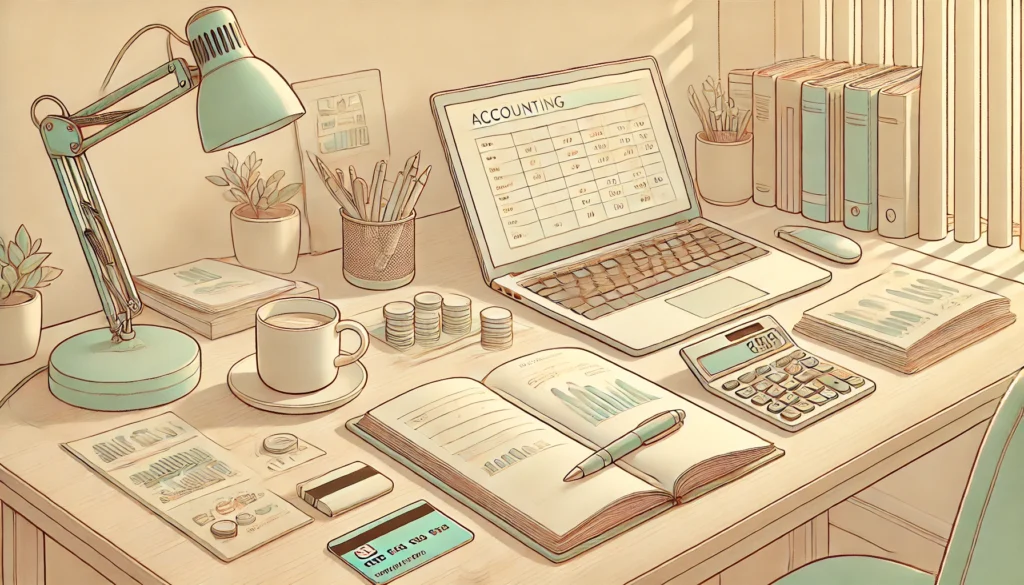
入社時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事
入社手続きでは、社会保険の加入手続きを速やかに行うことが重要です。手続きが遅れると、事業主は未納期間の保険料をさかのぼって請求されるだけでなく、正当な理由がなければ2倍の保険料を追徴される可能性があります。
入社時の社会保険手続きにおけるここがポイント!

遅れに気づいた場合は、速やかに「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」と「遅延理由書」を提出する必要があります。
また、保険証が未発行の期間に医療機関を受診すると全額自己負担となりますが、「療養費支給申請書」を提出すれば払い戻しを受けられます。こうしたリスクを避けるためにも、入社時の社会保険の手続きを確実に進めることが求められます。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」
「社会保険」編集部
社会保険の未加入や、社会保険料の滞納に科される罰則については、【社会保険未加入の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!】の記事をご覧ください
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「マイクロ法人の社会保険料」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
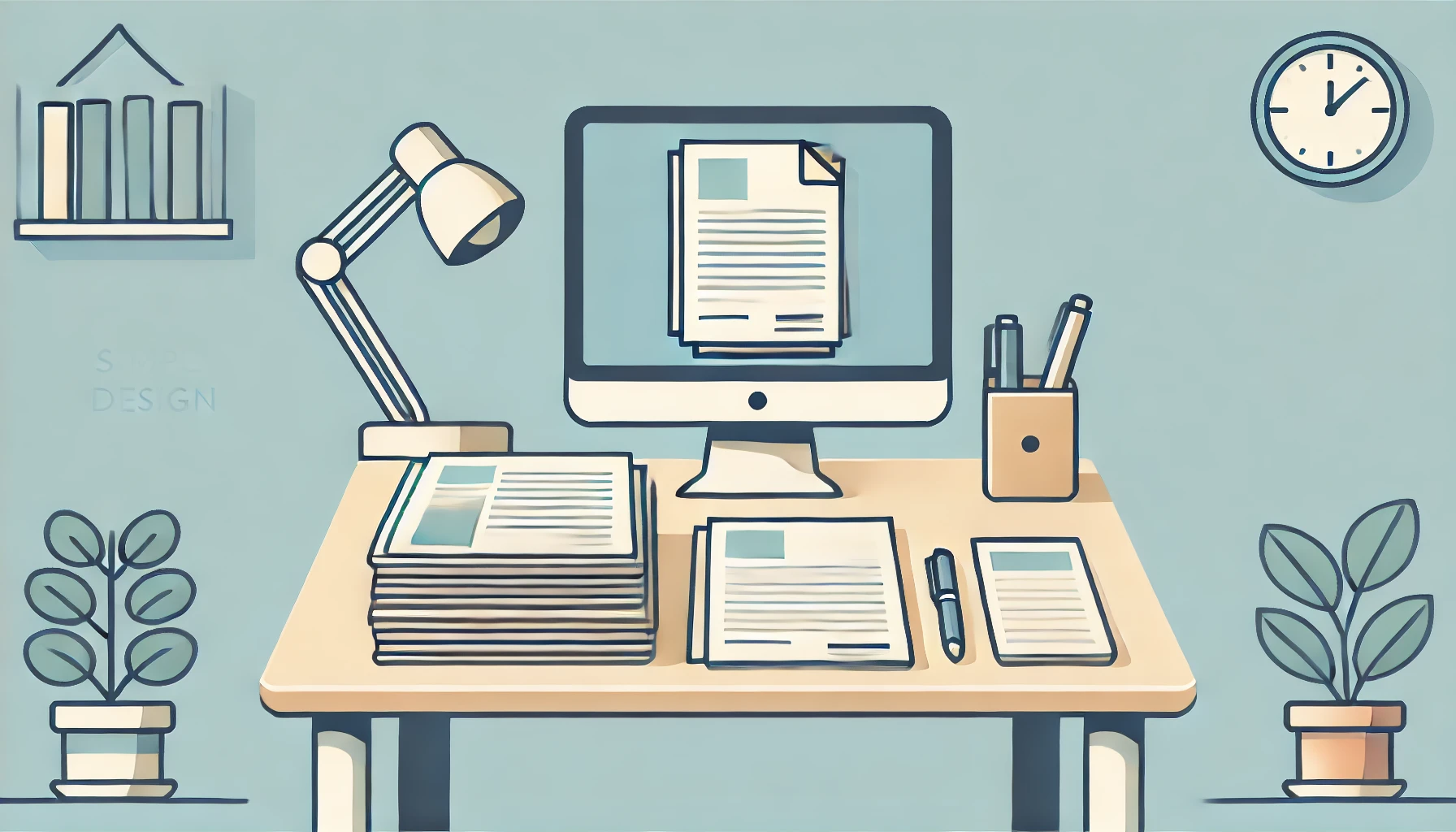
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!

合わせて読みたい「入社 住民税 手続き」に関するおすすめ記事

入社時の住民税に関する手続きについて解説!退職時の住民税の手続きも併せて紹介!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!