社会保険料の会社負担割合は?社会保険の計算方法や会社負担の注意点を徹底解説!
カテゴリー:
公開日:2024年9月
更新日:2026年1月9日
企業が従業員を雇用する際に避けて通れないのが、社会保険料の会社負担です。特に注目すべきなのが、社会保険料の会社負担割合です。会社負担割合は、保険の種類ごとに異なり、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険などそれぞれで会社がどの程度の割合で負担するのかが明確に定められています。
この社会保険料の会社負担割合は、従業員の給与や賞与に直接関係し、企業の人件費や経営計画に大きく影響を与える要素です。さらに、毎年保険料率の見直しが行われるため、常に最新の社会保険料の会社負担割合を正確に把握しておく必要があります。社会保険料を適切に計算するためには、それぞれの保険制度における会社負担割合を理解し、正しく反映させることが不可欠です。
本記事では、社会保険料とは何か、会社負担とはどういう仕組みか、そして各保険の会社負担割合はどのように計算するのかを、わかりやすく解説します。さらに、実務で注意すべきポイントや、計算時に見落としがちな会社負担割合の落とし穴についても詳しく紹介します。
「社会保険料の会社負担割合をどうやって確認すればいいの?」「どの保険にどの割合で会社が負担しているの?」といった疑問をお持ちの方にとって、本記事は必見です。ぜひ最後までご覧いただき、社会保険料の会社負担割合に関する正しい知識を身につけましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「非常勤役員の社会保険」に関するおすすめ記事

非常勤役員は社会保険の加入対象?加入条件について詳しく解説!
目次
【労務手続きを自分でするのはリスク大!】
社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由
社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。
社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。
ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。
また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」
社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。
だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険料の会社負担割合は?

社会保険料の会社負担割合は以下の通りです。
| 社会保険の種類 | 会社 | 従業員 |
| 健康保険 | 会社負担割合:50% | 従業員負担割合:50% |
| 厚生年金保険 | 会社負担割合:50% | 従業員負担割合:50% |
| 介護保険 | 会社負担割合:50% | 従業員負担割合:50% |
| 雇用保険 | 会社負担割合:業種により異なる | 従業員負担割合:業種により異なる |
| 労災保険 | 会社負担割合:100% | 従業員負担割合:0% |
健康保険、厚生年金保険、介護保険については、社会保険料の会社負担割合は原則50%となっており、従業員と会社がそれぞれ半分ずつの割合で負担する仕組みになっています。この会社負担割合は法律で定められており、企業は必ず従業員と同じ割合でこれらの社会保険料を負担しなければなりません。
一方、雇用保険については、社会保険料の会社負担割合が業種ごとに異なる点に注意が必要です。たとえば、一般の事業、農林水産業、建設業などではそれぞれ異なる割合が適用されるため、雇用保険の会社負担を正確に計算するには、自社の業種に応じた負担割合を確認することが重要です。
たとえば、4月1日に入社した従業員の場合、4月1日から4月10日までの給料が4月25日に支払われ、その際に4月分の社会保険料が控除されます。
また、労災保険については、社会保険料の会社負担割合は100%となっており、従業員の負担は一切ありません。すべての保険料を会社が全額負担するという点で、他の社会保険とは異なる特徴があります。
企業は、毎月の給与支給時に、従業員の社会保険料の負担分を給与から控除し、会社側の負担割合に応じた金額を加えたうえで、全額をまとめて納付します。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料に関しては、支払い期限が原則として翌月末となっており、支払い遅延を避けるためにも、正確な会社負担割合をもとに早めの準備が求められます。
雇用保険料については、会社が年に一度まとめて納付するケースが多いですが、従業員の分は毎月の給与から天引きし、会社負担分の割合と合わせて管理されます。
これらの社会保険料の金額は、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率と会社負担割合を掛け合わせて算出されるため、制度を正しく理解したうえで、会社の人件費計算や資金繰りに反映させることが重要です。
社会保険料の会社負担割合に関するおすすめ記事:社会保険料の会社負担割合の額は? 計算方法や金額を解説
社会保険料を決める標準報酬月額・標準賞与額とは?

標準報酬月額および標準賞与額は、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料などの各種社会保険料を算出する際の基準となる、報酬の区分を示したものです。この基準は日本年金機構によって定められており、各都道府県ごとに異なる場合があります。確認する際は、全国健康保険協会が公表している「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を参照するとよいでしょう。
標準報酬月額
標準報酬月額とは、社会保険料の計算を行うために、従業員の給与や賞与を一定の範囲で区分したものです。現在、1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの区分があります。従業員が社会保険に加入する際、その時点の給与を基に標準報酬月額が設定されます。

合わせて読みたい「社会保険と国民健康保険の違い」に関するおすすめ記事

社会保険と国民健康保険の違いは?切り替え時の手続きについて解説!
給与は変動する可能性があるため、毎年4月から6月の給与を基に、9月に標準報酬月額が再評価されます。
社会保険の会社負担割合に関する注意点

ただし、2等級以上の給与変動があった場合は、随時改定が必要です。
標準賞与額
標準賞与額は、賞与金額から1,000円未満を切り捨てた額で決定され、上限は150万円です。賞与とは、給与とは別に、年に3回以下の頻度で支給されるボーナスや手当などを指します。支給頻度が年4回以上になる場合、その支給額は賞与ではなく給与とみなされ、標準報酬月額に基づいて社会保険料が計算されるため、注意が必要です。
社会保険料の会社負担割合に関するおすすめ記事
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険料の計算方法

社会保険には、次の5つの種類があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
それぞれの社会保険料の計算方法について解説します。
社会保険料の計算方法①:健康保険
健康保険料の計算は次の通りです。
| 給与の場合 | 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率 | 会社負担割合:50% |
| 賞与の場合 | 健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率 | 会社負担割合:50% |
健康保険料率は、保険の種類や事業所の所在地によって異なります。健康保険には以下の2つの種類があります。
| 種類 | 従業員数など | 保険料率 |
| 健康保険組合 | ・常時700人以上の従業員がいる・同種・同業の事業所が集まり、3,000人以上の従業員がいる | 組合によって異なる |
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | ・人数にかかわらず、法人は加入義務がある・適用業種の個人事業主は、常時5人以上の従業員がいる場合に加入義務がある・上記以外でも条件を満たせば任意適用事業所として加入できる | 事業所がある都道府県によって異なる |
「社会保険の加入条件」編集部
社会保険の適用対象が段階的に拡大され、50人以下の企業にも順次義務化されます。
令和9年から令和17年にかけて、従業員数の条件が段階的に引き下げられ、最終的には全ての企業が対象になります。
参考:厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」
健康保険組合は主に大企業や同業の中小企業のグループで設立されますが、全国健康保険協会(協会けんぽ)は主に中小企業が対象です。協会けんぽの保険料率は協会の公式ウェブサイトで確認できます。
社会保険料の会社負担割合に関する参考記事:保険料率 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

合わせて読みたい「社会保険手続きの期限を超えた場合の対応」に関するおすすめ記事

会社設立から社会保険手続きが5日過ぎたときの対処法とは?会社設立後の社会保険手続きの期限も紹介
社会保険料の計算方法②:厚生年金保険
厚生年金保険料の計算は次の通りです。
| 給与の場合 | 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 | 会社負担割合:50% |
| 賞与の場合 | 厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率 | 会社負担割合:50% |
厚生年金保険料率は、2024年5月現在18.3%です。詳細な額は、全国健康保険協会のウェブサイトで確認できます。
「社会保険」編集部
社会保険の未加入や、社会保険料の滞納に科される罰則については、【社会保険未加入の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!】の記事をご覧ください
社会保険料の計算方法③:介護保険
介護保険料の計算は以下の通りです。
| 給与の場合 | 介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率 | 会社負担割合:50% |
| 賞与の場合 | 介護保険料 = 標準賞与額 × 介護保険料率 | 会社負担割合:50% |
介護保険料率は加入する健康保険の種類や都道府県により異なります。協会けんぽの保険料率は協会の公式ウェブサイトで確認してください。

合わせて読みたい「従業員50人以下の社会保険加入義務」に関するおすすめ記事
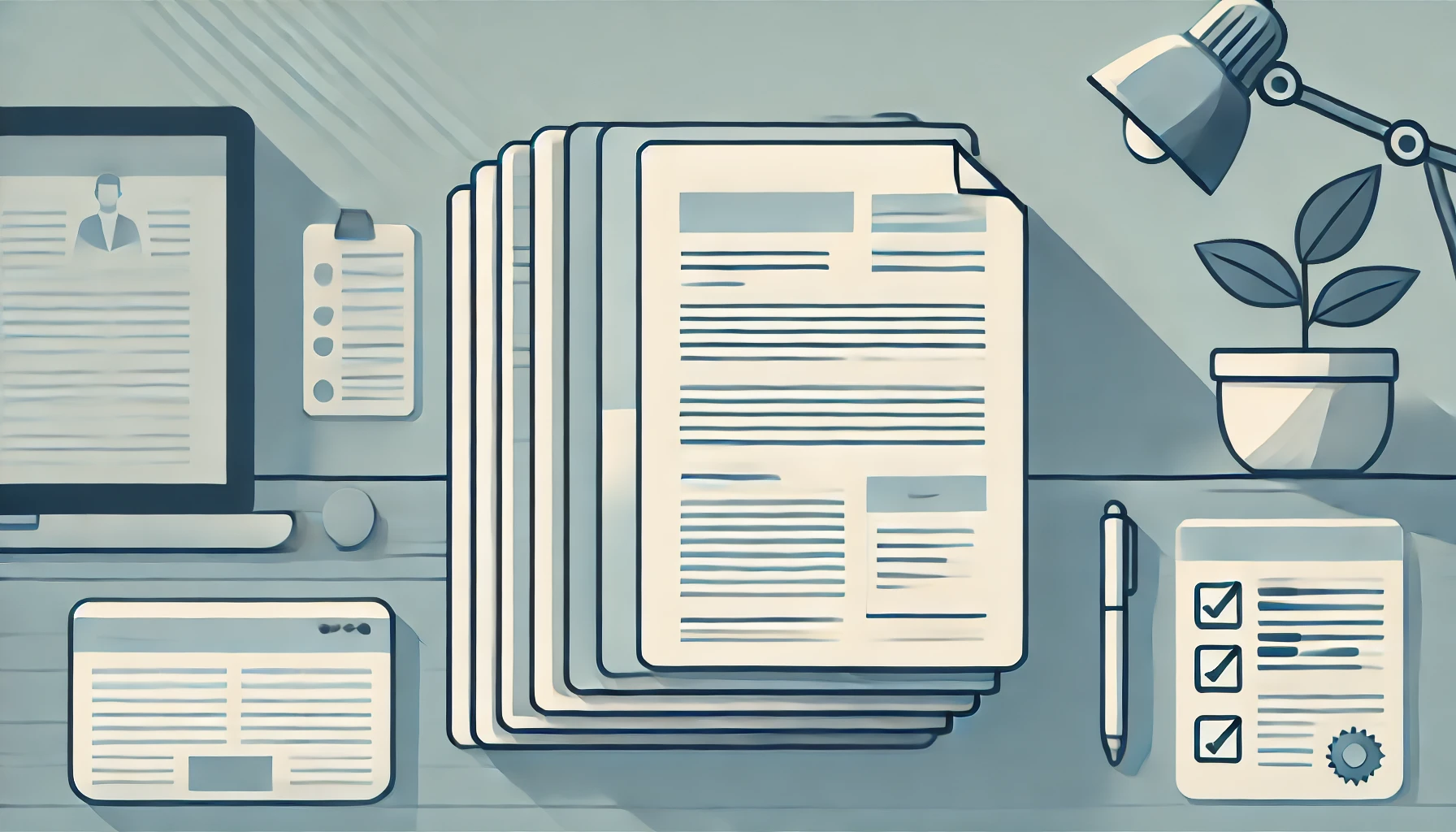
従業員50人以下の会社は社会保険の加入条件に該当する?今後の加入対象拡大についても解説!
本記事では、50人以下の企業が社会保険の加入条件に該当するかどうかの判断基準や、今後の段階的な適用スケジュールについて詳しく解説します。
社会保険料の計算方法④:雇用保険
SoVa税理士お探しガイド編集部
一人社長が会社設立をしても社会保険に加入する必要があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
「一人社長でも会社設立時には社会保険は必要?手続きや必要書類を解説!」
雇用保険料の計算方法は以下の通りです。
| 給与の場合 | 雇用保険料 = 給与額 × 雇用保険料率 | 会社負担割合:業種により異なる |
| 賞与の場合 | 雇用保険料 = 賞与額 × 雇用保険料率 | 会社負担割合:業種により異なる |
2024年度の雇用保険料率は以下の通りです。
| 業種 | 労働者負担割合 | 会社負担割合 | 雇用保険料率 |
| 一般の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造業 | 7/1,000 | 10.5/1,000 | 17.5/1,000 |
| 建設業 | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
毎年保険料率は更新されるため、厚生労働省のウェブサイトを定期的に確認しましょう。
社会保険料の会社負担割合に関する参考記事:雇用保険料率について |厚生労働省

合わせて読みたい「社顔保険料は4月から6月で決まる?」に関するおすすめ記事
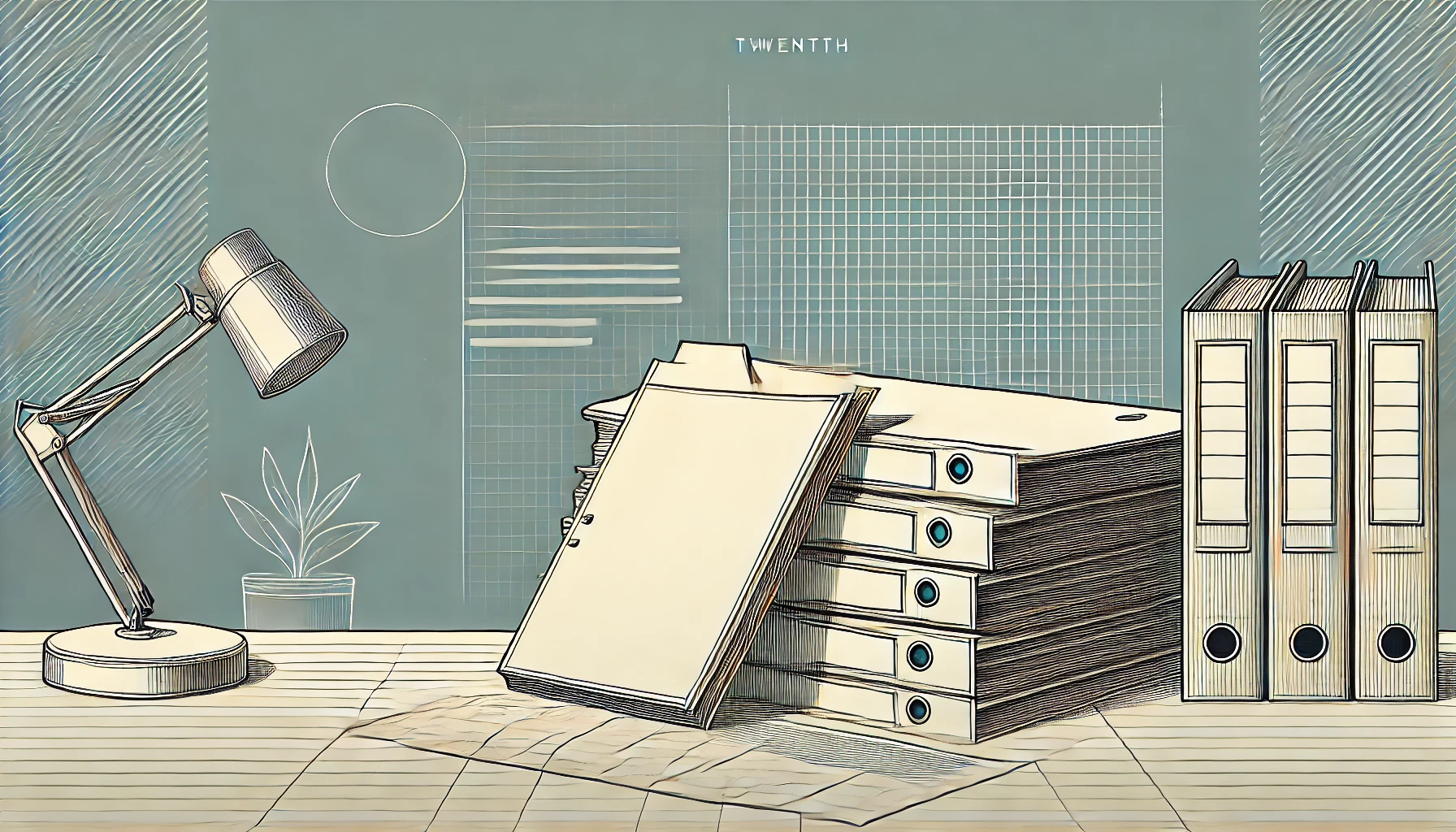
社会保険料は4月から6月で決まる!4月5月6月に残業すると手取りが減る理由を解説
社会保険料の計算方法⑤:労災保険
労災保険料の計算方法は以下の通りです。
| 給与の場合 | 労災保険料 = 給与額 × 労災保険料率 | 会社負担割合:100% |
| 賞与の場合 | 労災保険料 = 賞与額 × 労災保険料率 | 会社負担割合:100% |
労災保険については会社負担割合が100%になるのが特徴です。労災保険料率は業種により異なります。詳細は厚生労働省の公式サイトで確認しましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険料の会社負担割合に関するおすすめ記事
社会保険料の会社負担割合を計算する際の注意点

社会保険料の計算時に注意すべき点は以下の通りです。
- 社会保険料が免除される期間がある
- 介護保険の年齢に関する注意点
- ボーナス(賞与)の取り扱いについて
- 端数処理の方法について
それぞれのポイントについて詳しく説明します。

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事

会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
社会保険料の会社負担割合を計算する際の注意点①
社会保険料が免除される期間が存在する
社会保険料の会社負担割合を計算する際は、特定の期間において社会保険料が免除されるケースがあることに注意が必要です。
たとえば、産前産後休業や育児休業中の従業員に対しては、一定期間、社会保険料の会社負担と従業員負担の両方が免除されます。この免除により、社会保険料の負担割合に変動が生じることになります。

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介
産前産後休業の対象期間は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産後8週間までのうち、実際に就労していない期間が対象となります。この間は、社会保険料の会社負担割合もゼロになります。
社会保険料の会社負担割合に関するおすすめ記事

社会保険料の会社負担割合と従業員負担割合については、以下の記事も参考になるでしょう。
社会保険料の会社負担割合に関する参考記事:「副業・兼業社員の社会保険加入、会社の負担は増える?副業の種類による違いとは」
育児休業中も、子どもが3歳になるまでの間、健康保険料と厚生年金保険料の会社負担割合および従業員負担割合が免除されます。とくに育児休業を開始した月から、終了日の翌月の前月までの期間において、会社は社会保険料の会社負担割合を支払う義務がなくなります。
免除を受けるには、「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申請書」や「育児休業等取得者申出書」などの提出が必要です。これらの手続きを適切に行わないと、社会保険料の会社負担割合の免除が適用されず、誤った割合での負担が生じてしまう恐れがあります。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
社会保険料の会社負担割合を計算する際の注意点②
介護保険は従業員の年齢によって会社負担割合が異なる
介護保険料の会社負担割合を計算する際には、従業員の年齢によって社会保険料の発生有無とその割合が変わることを把握しておきましょう。
介護保険料は、原則として40歳以上の従業員が対象となり、40歳未満の従業員については社会保険料としての介護保険料が発生しないため、会社負担割合はゼロです。
40歳から64歳までの従業員は「第2号被保険者」となり、介護保険料が発生します。このとき、社会保険料としての介護保険料は労使折半となるため、会社は所定の会社負担割合に基づいて支払う必要があります。
65歳以上になると「第1号被保険者」として、介護保険料は市区町村に直接納める形式に変わります。この場合、会社負担割合は発生せず、社会保険料の負担割合においても除外されます。
つまり、介護保険に関する社会保険料の会社負担割合は、従業員の年齢によって有無や割合が変わるため、年齢確認を含めた正確な判断が求められます。

合わせて読みたい「社会保険の無料相談窓口」に関するおすすめ記事
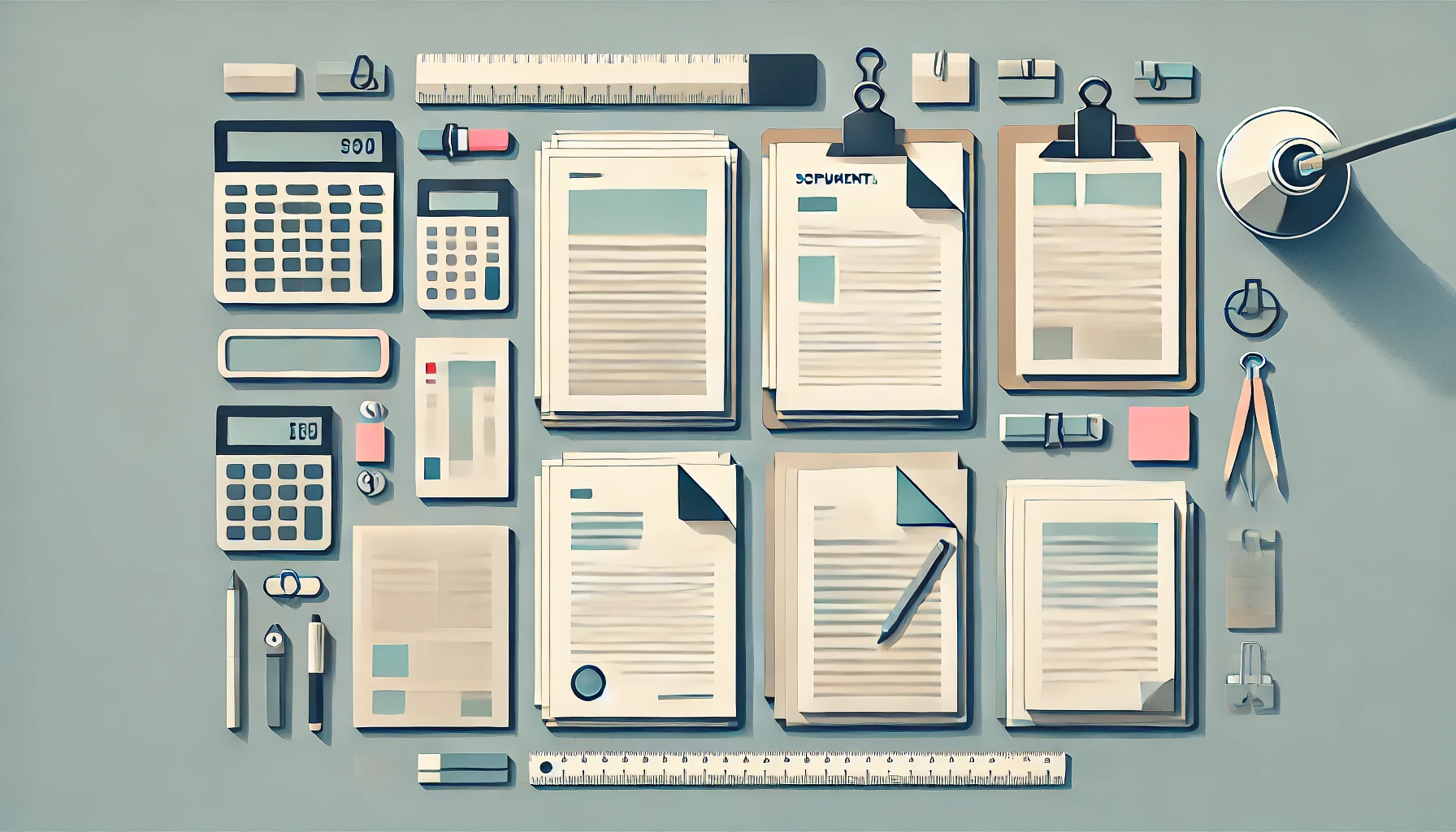
法人の社会保険の無料相談窓口はどこ?困ったときの問い合わせ先を紹介
社会保険料の会社負担割合を計算する際の注意点③
ボーナス(賞与)にかかる社会保険料の会社負担割合を忘れずに
ボーナス(賞与)にも、通常の給与と同様に社会保険料が発生します。ここでも会社負担割合の確認が重要です。
賞与に対する社会保険料は、「標準賞与額」(1,000円未満切り捨て)を基に保険料率を掛けて算出され、会社は所定の会社負担割合を支払う必要があります。
たとえば、健康保険や厚生年金保険に対する賞与分の社会保険料は、賞与支給月に応じて計算され、通常の月より高額になることがあります。その際にも正確な会社負担割合をもとに計算を行わなければなりません。
なお、賞与に該当するかどうかは「年3回以下」「労働の対価」といった条件によって判断されます。これに該当しないもの(結婚祝い金や慶弔金など)は社会保険料の対象外となり、会社負担割合にも影響しません。
また、雇用保険についても同様に、賞与に対する保険料を会社負担割合に基づいて計算する必要があります。支給額に所定の割合を掛け、正確な会社負担割合で処理を行うことが求められます。
社会保険料の会社負担割合を計算する際の注意点④
端数処理のルールに注意し、会社負担割合を正確に反映
社会保険料の会社負担割合を計算する際は、1円未満の端数処理にも注意が必要です。端数処理の違いによって、最終的な会社負担額に差が生じることもあるため、割合の計算と合わせて正確に管理しましょう。
【給与から控除する場合】
従業員負担の社会保険料については、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。これと同じように、会社負担割合に基づく社会保険料の端数処理にも一定のルールが適用されます。
社会保険料の会社負担割合に関するおすすめ記事

社会保険料の会社負担割合と従業員負担割合については、以下の記事も参考になるでしょう。
参考:「会社と社員が半分ずつ負担する、社会保険の納付額と計算方法」
【会社負担分の処理方法】
会社負担の社会保険料については、1円未満の端数を切り捨てますが、これは各従業員ごとではなく、全従業員の合算後に一括で端数処理を行います。つまり、会社負担割合を計算する際には、合算後の総額に端数処理を適用するという点に注意が必要です。
また、雇用保険についても同様に、法律に基づいて端数処理が行われますが、健康保険や厚生年金保険も社内の運用ルールに従って処理しているケースもあります。割合に関する社内基準がある場合には、そのルールに基づいて処理することも可能です。
社会保険料の会社負担割合を正確に計算するためには、このような端数処理のルールも含めて、全体の流れを理解することが不可欠です。
社会保険料の会社負担割合に関するおすすめ記事:社会保険料の会社負担割合は?計算方法と注意点を解説
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険料の支払いが難しい場合

社会保険料の支払いが困難な場合は、猶予制度や分割払い制度の利用を検討してみましょう。
社会保険料の滞納が続くと、単に督促状が送付されるだけでなく、延滞金が加算され、さらに財産調査や差し押さえといった措置が取られる可能性があります。また、会社の社会的信用が低下し、融資の確保や取引先との関係にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
「社会保険料の会社負担割合」編集部
こうした事態を避けるためにも、支払いが難しいと感じた時点で、速やかに各納付機関へ相談することが大切です。何よりも、滞納を放置しないことが重要です。
社会保険料の会社負担割合に関するおすすめ記事:「社会保険」に加入すると会社負担の額は実際いくら?
月給25万円の従業員にかかる社会保険の会社負担額と割合を解説
従業員に月給25万円を支給する場合、企業が支払う社会保険の会社負担はどのくらいになるのでしょうか?社会保険の負担は給与とは別に毎月発生するコストであり、会社経営において重要なポイントです。ここでは、社会保険の会社負担額とその割合について、東京都・協会けんぽ加入・40歳未満を前提に詳しく解説します。
月給25万円の場合の会社が負担する会社保険料に関するポイント!

月給25万円のケースでは、標準報酬月額は26万円(等級20)となります。社会保険ではこの標準報酬月額を基に、会社と従業員がそれぞれ保険料を負担します。保険料は原則として会社と従業員が半分ずつの割合で負担する仕組みです。
■ 健康保険の会社負担と割合
社会保険の中でも、健康保険は会社が毎月負担する大きな項目のひとつです。保険料率の半分を会社が負担するため、会社負担の割合は全体の50%となっています。
参考:「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
■ 厚生年金保険の会社負担と割合
厚生年金保険も社会保険の一部であり、健康保険と同様に会社負担の割合は50%です。会社負担額は健康保険よりも大きく、企業にとっての社会保険負担の中でも特に影響の大きい項目です。
■ 雇用保険の会社負担と割合
雇用保険も会社が一部を負担する社会保険の一種で、保険料率に対する会社負担の割合は約61%(0.95%/1.55%)と、他の社会保険に比べてやや高めです。
参考:「令和6年度の雇用保険料率について」
■ こども・子育て拠出金の会社負担
これは社会保険とは別の項目ですが、全額会社が負担する制度のため、実質的な会社負担の一部として見ておく必要があります。
参考:日本年金機構「子ども・子育て拠出金率が改定されました」
つまり、月給25万円の場合に会社が負担する社会保険料はいくら?
月給25万円の従業員を雇用する場合、会社が毎月負担する社会保険料の合計額は約4万円となります。これは、健康保険・厚生年金・雇用保険・子育て拠出金など、複数の保険に対する会社負担分の合計金額です。
社会保険料は、給与とは別に発生する固定コストであり、従業員1人あたりの会社負担の割合や金額を正確に把握することは、人件費管理において非常に重要です。企業経営を行う上では、この社会保険料の会社負担額を計算に含めたうえで、採用や給与設定を行うことが求められます。
Q&A|よくある質問
Q. 社会保険料の会社負担割合はどのくらいですか?
A. 社会保険料は、会社と従業員が折半で負担する仕組みです。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(対象者のみ)は基本的に会社と従業員が半分ずつ負担します。雇用保険料は事業の種類によって異なりますが、原則として会社負担の割合が高く設定されています。たとえば、一般の事業の場合、会社負担は0.6%、従業員負担は0.3%(2025年時点)などです。会社は社会保険料の会社負担分を給与とともに毎月支払い、その金額は人件費に大きく影響します。
Q. 社会保険料の会社負担で注意すべきポイントはありますか?
A. はい、社会保険料の会社負担については以下の点に注意が必要です。
- 社会保険料は賞与にも適用されるため、ボーナス支給時にも会社負担が発生する
- 4月~6月の給与が標準報酬月額の決定に影響し、年間の社会保険料に直結する
- 社会保険料の会社負担分は経費にできるが、納付遅延があると信用リスクになる
- 社会保険の適用拡大により、従業員数が一定数を超えると強制加入となる
これらを把握せずに従業員を増やすと、思わぬ負担増につながります。社会保険料の会社負担は、採用や労務戦略にも影響を及ぼす要素です。
Q. 社会保険料の計算方法はどうなっていますか?
A. 社会保険料の計算方法は、「標準報酬月額×保険料率÷2(会社負担分)」が基本です。
社会保険料の会社負担割合に関するポイント!

たとえば、東京都で月給30万円の従業員の場合、健康保険料率9.87%、厚生年金料率18.3%(2025年時点)であれば、会社は月額約4万2千円ほどの社会保険料を負担することになります。これは従業員1人あたりの固定的なコストとして把握しておくべきです。
参考:協会けんぽ「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
Q. 社会保険料の会社負担を抑える方法はありますか?
A. 法令に基づく社会保険料の会社負担割合は変更できませんが、労働時間や報酬の調整によって社会保険の加入要件に該当しないようにすることで、社会保険料の会社負担を抑える手法はあります。ただし、これは短期的なコスト削減にはなりますが、従業員満足度や採用競争力の低下、制度変更リスクなどを踏まえて慎重に判断すべきです。税理士や社会保険労務士に相談するのが安心です。
まとめ|社会保険料の会社負担割合とは

社会保険料の会社負担割合は、従業員を雇用する企業にとって重要なコスト項目です。社会保険料は原則として従業員と会社で折半する仕組みとなっており、会社負担の割合は健康保険や厚生年金保険など、それぞれの保険制度によって異なります。
社会保険料の計算を正確に行うためには、保険料率に対する会社負担の割合をしっかりと把握しておく必要があります。会社負担の割合を誤って認識していると、想定以上の人件費が発生し、経営に影響を及ぼす可能性もあります。
とくに、社会保険料の会社負担割合は毎年見直されることがあるため、常に最新の情報をチェックし、適切に対応することが求められます。社会保険料の全体額とそのうち会社負担の割合を理解しておくことで、給与設計やコスト試算もより現実的に行えます。
本記事では、社会保険料の基本構造と会社負担割合の仕組み、そして具体的な計算方法や注意点を簡単に解説しました。社会保険料の負担割合を正しく理解することは、企業のコスト意識と労務管理の質を高めるうえで非常に重要です。
社会保険料の会社負担割合をしっかり把握し、無理のない労働環境づくりと健全な企業経営に役立てていきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険料の会社負担割合に関するおすすめ記事
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日













SoVaをもっと知りたい!