会社設立時に社会保険への加入は必須?具体的な手続き方法について詳しく解説!
カテゴリー:
公開日:2025年9月
更新日:2026年2月24日
会社設立を行うと、必ず直面するのが社会保険の加入手続きです。社会保険は従業員の生活を守るだけでなく、会社にとっても人材確保や経営安定のために重要な役割を果たします。しかし、「会社設立後すぐにどの社会保険へ加入する必要があるのか」「手続きはどこで行うのか」など、具体的な流れが分からず不安に感じる方も少なくありません。
この記事では、会社設立時に必須となる社会保険の種類と、加入手続きの方法を詳しく解説します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
【労務手続きを自分でするのはリスク大!】
社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由
社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。
社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。
ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。
また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」
社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。
だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立をしたら社会保険への加入手続きは必須?

会社設立を行うと、社会保険への加入手続きが必要になります。社会保険とは、病気やケガ、失業、障害などに備えて従業員や役員の生活を保障する制度であり、会社設立後に必ず意識しておくべき重要な手続きです。社会保険には以下の5種類があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険(40歳以上が対象)
- 雇用保険
- 労災保険
会社設立時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事
特に、会社設立の際に必ず加入しなければならないのが「健康保険」と「厚生年金保険」です。健康保険法第3条および厚生年金保険法第6条に基づき、会社設立後は加入の手続きを行うことが義務付けられています。
また、雇用保険と労災保険(労働保険)については、会社設立直後に従業員を雇用しているかどうかで加入義務が変わります。今後アルバイトや正社員を採用する予定がある場合は、早めに雇用保険と労災保険の加入手続きを進める必要があります。
さらに、会社設立をして一人社長として経営を始める場合でも注意が必要です。従業員がいない場合でも、役員報酬を設定しているなら、健康保険や厚生年金保険といった社会保険への加入は必須です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立時における社会保険の手続きに関する気をつけておきたい注意点

雇用保険と労災保険は労働者向けの制度のため加入不要ですが、会社設立後に自分自身も社会保険に加入しなければならない点を忘れてはいけません。
健康保険・厚生年金への加入手続き

会社設立を行った際には、社会保険への加入手続きが必須です。特に健康保険と厚生年金保険は、会社設立直後から確実に進める必要があります。ここでは、会社設立時に必要となる社会保険の手続きと流れを解説します。
制度の概要
会社設立をすると必ず関係してくるのが健康保険と厚生年金保険です。
- 健康保険:病気やケガ、出産・死亡時の費用を保障する医療保険で、会社設立時に加入が義務づけられます。全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合健保が保険者となり、保険料は加入者と事業主が折半します。
- 厚生年金保険:会社設立時に加入する公的年金制度で、健康保険と同じく事業主と本人が保険料を折半して負担します。

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事

会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
必要書類と提出先
会社設立後に社会保険へ加入するには、以下の書類が必要です。
- 「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
- 登記簿謄本(会社設立から90日以内に交付されたもの)
- 法人番号指定通知書(事前取得がおすすめ)
SoVa税理士ガイド編集部
会社設立時に必要な社会保険の手続きについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
これらを会社本店所在地を管轄する年金事務所へ提出します。任意適用事業所の場合は「任意適用申請書」も必要で、年金事務所長の許可を受けなければなりません。
さらに、会社設立時に従業員を雇用している場合は「被保険者資格取得届」を提出し、従業員を健康保険・厚生年金保険に加入させます。家族を被扶養者にする場合は「被扶養者(異動)届」も提出する必要があります。
提出方法は、電子申請・電子媒体(CD/DVD)・郵送・窓口持参から選択可能です。
提出期限
会社設立後の社会保険手続きには期限があります。
- 「新規適用届」:会社設立の日から 5日以内
- 「被保険者資格取得届」:従業員の雇用開始日から 5日以内
なお、「被保険者資格取得届」は従業員本人が記入する必要があるため、雇用開始前に渡しておくとスムーズです。
SoVa税理士ガイド編集部
また、提出時には基礎年金番号かマイナンバーの記入も必須です。

合わせて読みたい「厚生年金の加入条件」に関するおすすめ記事

厚生年金の加入条件を詳しく解説!加入義務対象の従業員や企業の要件とは?
本記事では、厚生年金の基本的な仕組みをはじめ、厚生年金保険に加入するための条件、対象となる事業所の種類、そしてパート・アルバイトにおける最新の加入条件についても詳しく解説していきます。
雇用保険への加入手続き

会社設立を行った場合、従業員を雇用すると社会保険の一つである雇用保険への加入手続きが必要です。「1人起業」で従業員を雇わないケースでは加入義務はありませんが、1人でも雇用すれば必ず雇用保険の手続きを進めなければなりません。
定款の参考記事:「会社の定款とは?記載事項や作成方法を解説!」
制度の概要
雇用保険は、会社設立後に従業員を雇用した際に加入する社会保険の一つです。失業時の生活や雇用の安定、再就職の促進を目的としており、失業給付のほか、技能習得手当、疾病手当、就業促進手当、教育訓練給付金、育児休業給付金など多様な給付が用意されています。
会社設立時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事
労災保険が全額事業主負担であるのに対し、雇用保険料は事業主と労働者が分担して負担します。なお、雇用保険の対象となる労働者は「週20時間以上の勤務で、31日以上の雇用見込みがある人」と定義されています。

合わせて読みたい「会社設立の費用」に関するおすすめ記事

会社設立の費用はいくらかかる?株式会社と合同会社の設立相場を解説!
必要書類と提出先
会社設立後に雇用保険の加入手続きを行う際には、まず労災保険の加入手続きを完了しておく必要があります。雇用保険の申請には労働基準監督署で交付された「労働保険 保険関係成立届」の控えが必要だからです。
雇用保険の加入手続きは、会社本店所在地を管轄するハローワークにて行います。提出が必要な書類は以下の通りです。
- 「雇用保険適用事業所設置届」
- 「雇用保険被保険者資格取得届」(加入対象者ごとに提出)
- 「労働保険 保険関係成立届」の控え
- 「会社登記簿謄本」(発行3カ月以内)
- 「法人税確定申告書別表一」
- 「労働者名簿」
- 「出勤簿またはタイムカード」
- 「労働者賃金台帳」
- 「雇用契約書または雇入通知書(パート含む)」
会社設立時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事:起業したらすぐに社会保険の手続きを!加入するものや届出方法を解説
これらを揃えて、ハローワークでの社会保険手続きを完了させます。
提出期限
雇用保険の加入手続きは、従業員を雇用した日の属する月の翌月10日までに行う必要があります。手続きが完了すると「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付され、従業員の社会保険手続きが正式に完了します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「法人設立ワンストップサービス」に関するおすすめ記事

法人設立ワンストップサービスとは?メリットや注意点を解説!
SoVa税理士ガイド編集部
なお、会社設立後に雇用保険の加入手続きを怠ると、雇用保険法第83条に基づき「懲役6カ月以下または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。会社設立直後から社会保険の手続きは漏れなく実施することが重要です。
1人社長の関連記事:「1人社長は儲かる?1人社長が儲かる理由やデメリットについても解説!」
労災保険への加入手続き

会社設立を行い、1人でも従業員を雇用した場合には、社会保険の一つである労災保険への加入手続きが必須です。ここでは労災保険の制度概要や必要な手続き、提出期限について解説します。
制度の概要
会社設立時に従業員を雇用すると、労災保険の強制適用事業所となります。労災保険(労働者災害補償保険)は、従業員が仕事中や通勤途中に負ったケガ・病気・障害、または死亡した場合に保険給付を行う制度です。

合わせて読みたい「社会保険の無料相談窓口」に関するおすすめ記事
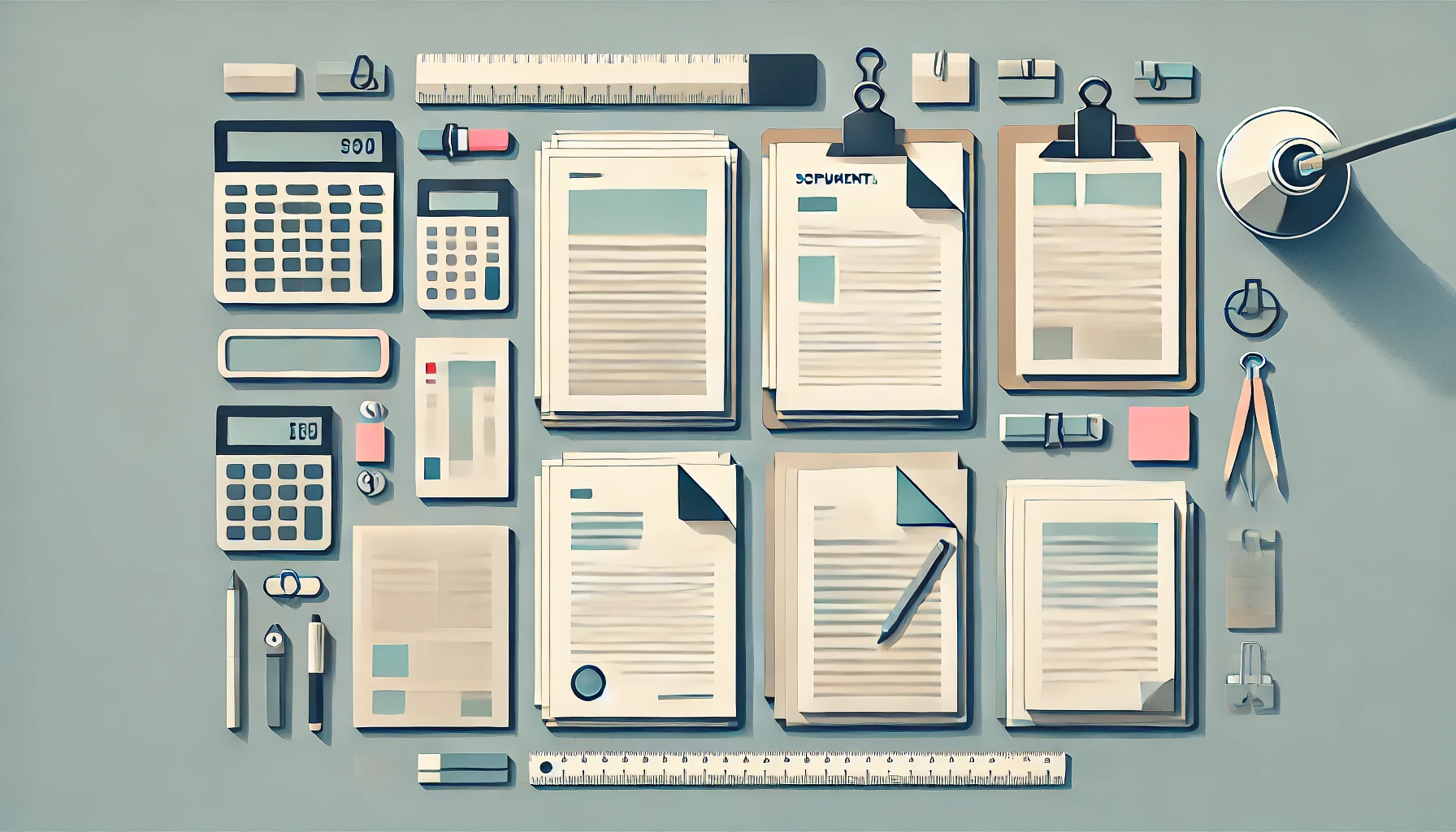
法人の社会保険の無料相談窓口はどこ?困ったときの問い合わせ先を紹介
健康保険など他の社会保険と異なり、労災保険は業務上や通勤途上に起きた事案のみを対象とします。補償対象となった場合は、健康保険のような治療費の自己負担が不要で、さらに休業時の手当も手厚く支給されます。なお、保険料は会社設立後の事業主が全額を負担します。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
必要書類と提出先
会社設立後に労災保険へ加入するには、以下の手続きが必要です。
- 「労働保険 保険関係成立届」
- 「労働保険 概算保険料申告書」
これらを会社本店所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。添付書類として「会社登記簿謄本」や「従業員の賃金台帳」が必要です。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
SoVa税理士ガイド編集部
概算保険料は、年度(4月1日〜3月31日)に支払う予定の賃金総額に保険料率を乗じて計算します。前払いで納付し、翌年度に精算する手続きを繰り返します。
提出期限
会社設立後、従業員を雇用した場合の提出期限は以下の通りです。
- 「労働保険 保険関係成立届」:雇用開始日の翌日から 10日以内
- 「労働保険 概算保険料申告書」:保険関係成立の日から 50日以内
会社設立時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事
また、労災保険の加入手続きは事業主本人でも行えますが、専門家に依頼する場合は社会保険労務士に限られる点に注意しましょう。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
会社設立して社会保険の加入手続きをするメリット

会社設立をすると社会保険への加入手続きは義務となり、保険料は会社にとって大きな負担に感じるかもしれません。しかし、社会保険は従業員を守るだけでなく、雇用主である会社にとっても大きなメリットをもたらします。
社会保険の加入手続きをするメリット①:雇用主としての備え
会社設立後に社会保険へ加入しておくことで、従業員が病気やケガをした際にも安心して医療機関を利用できる環境を整えられます。健康保険に加入していなければ、風邪の治療でも1万円以上かかる可能性がありますが、社会保険に加入していれば医療費の自己負担は軽減されます。
会社設立時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事
また、業務中に事故やケガが起きた場合、会社が治療費を全額負担するのは大きなリスクです。社会保険に加入していれば労災保険による補償があり、万が一、障害や死亡に至るケースでも、会社設立した法人が倒産に追い込まれるリスクを減らすことができます。社会保険の手続きは従業員の安心を守ると同時に、雇用主を支える仕組みでもあるのです。
社会保険の加入手続きをするメリット②:人材確保の最低条件
会社設立後に人材を確保するうえで、社会保険に加入していることは最低条件といえます。
会社設立時の社会保険加入手続きに関する気をつけておきたい注意点

求職者が仕事を選ぶ際、社会保険加入の有無は重要な判断基準です。実際、社会保険に未加入の会社はハローワークでの求人掲載もできません。
さらに、会社設立をしていながら社会保険の加入手続きを怠ると、「ブラック企業」と見られるリスクが高まります。目先の人件費を削減しようと社会保険に加入しないことは、長期的には人材不足や企業イメージの悪化につながり、結果的に大きな損失となります。

合わせて読みたい「社会保険調査」に関するおすすめ記事

社会保険調査は厳しいのか?年金事務所の調査がくる理由と流れを解説
まとめ

会社設立をすると、社会保険の加入手続きは避けて通れません。健康保険・厚生年金保険は役員1人の会社であっても必ず加入が必要であり、従業員を雇用すれば雇用保険や労災保険の手続きも行わなければなりません。社会保険に加入することで従業員に安心できる労働環境を提供でき、結果として企業の信頼性や人材採用力の向上につながります。
会社設立の際は、必要な社会保険の種類と加入手続きを正しく理解し、期限内に漏れなく対応することが重要です。
会社設立時に必要な社会保険の手続きに関するおすすめ記事:会社設立時の社会保険の必要書類、手続き方法を解説!サラリーマンの副業も加入は必要?
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!