法人成りで資産引継ぎする方法とは?個人事業主から引き継げる資産の種類や注意点も紹介!
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2026年1月10日
個人事業主がさらなる事業拡大や節税対策を見据えて法人成りを検討する際に、必ず検討すべきなのが「資産の引継ぎ」です。法人成りによって個人から法人へと事業の形を変える場合、保有している資産をどのように法人へ引継ぐかが、手続きの成否や税金への影響を大きく左右します。
しかし、法人成りの過程で行う引継ぎは単純な「所有物の移動」ではありません。自動車や備品、不動産、在庫、そして場合によっては負債まで、あらゆる対象について、税務や会計上のルールに沿った正しい引継ぎ処理が必要になります。特に、時価での譲渡・賃貸契約・現物出資など、法人成りにおける資産引継ぎの手法にはいくつかの選択肢があり、それぞれの違いを理解しておかなければなりません。
本記事では、法人成りを行う際の資産引継ぎについて、よく使われる引継ぎ方法の種類とその特徴、注意点、税務上の扱いまで詳しく解説します。これから法人成りを考えている個人事業主の方や、引継ぎ手続きに不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
法人成りに失敗しないためにも、正しい資産の引継ぎ知識が欠かせません。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
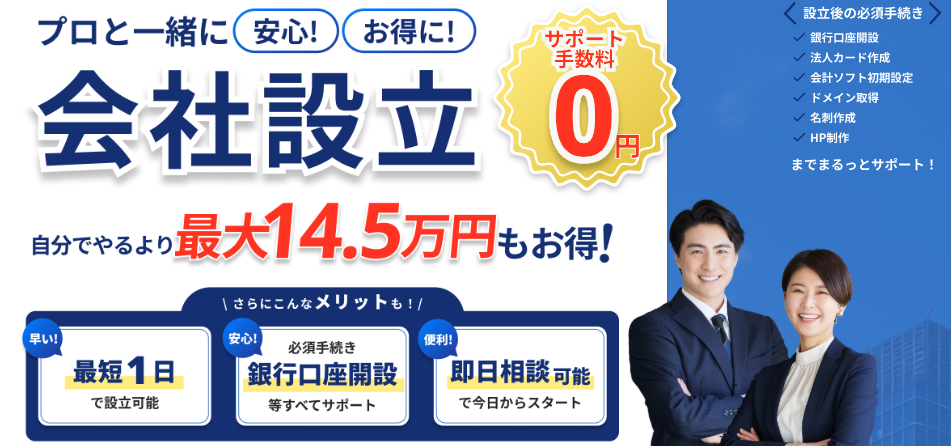
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
法人成りとは
法人成りとは、個人事業主として行っていた事業を法人として継続するために、会社を設立して事業を法人へ移行することを指します。法人成りは「法人化」とも言われますが、単なる名称変更ではなく、事業に関する資産や負債、取引先との契約、従業員の雇用関係などを法人に引継ぎ、法人としての新たなスタートを切る手続きです。
法人成りを行うことで、個人とは異なる法人格が与えられ、法的にも独立した存在として事業活動を行うことが可能になります。株式会社や合同会社をはじめとした法人形態への法人成りは、税務面や信用力の向上、資産管理の明確化といったさまざまなメリットを伴います。事業を成長させる過程で、法人成りを選択する個人事業主は少なくありません。
法人成りで資産引継ぎに関するおすすめ記事

法人成りで資産引継ぎをする場合様々な方法があります。法人成りをして資産引継ぎについて、以下の記事も参考になるでしょう。
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「【実践的】法人成りの4つの資産引継ぎ方法|事例や注意点まで解説」
法人成りでは、個人が保有していた事業用資産をどのように法人へ引継ぐかが重要なポイントになります。たとえば、車両や設備、在庫、口座などを適切な評価のもとで法人へ移転する必要があり、資産の引継ぎ方によっては税務上の影響も生じるため、事前の準備が欠かせません。こうした資産の引継ぎも含め、法人成りは計画的に進めることが大切です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人成りにおける資産引継ぎの方法4選
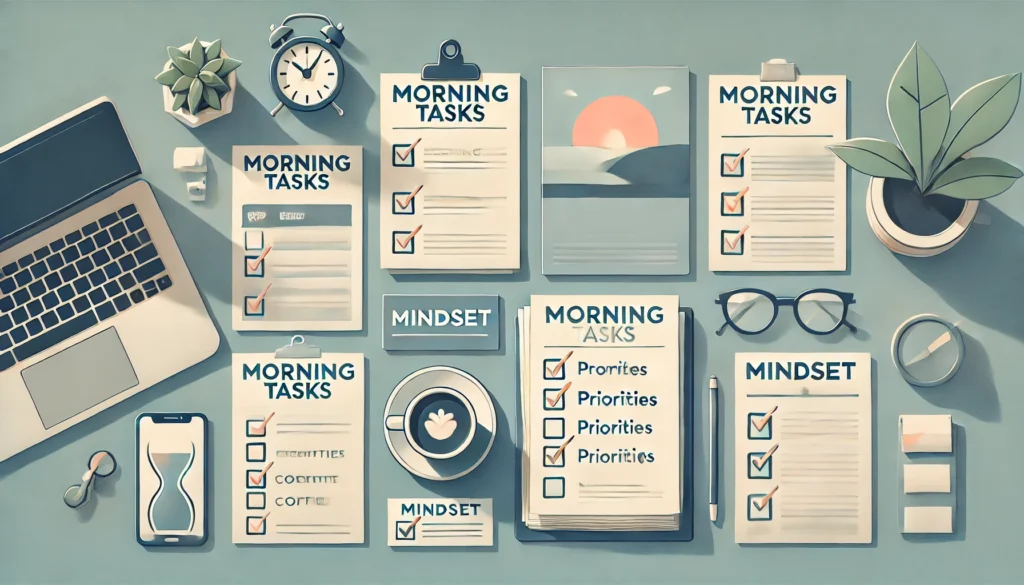
法人成りをする際には、資産引継ぎが必須のステップとなります。
個人事業主として保有していた不動産、自動車、什器備品、パソコン、在庫などの事業用資産を、新しく設立する法人に引き継いで運用を継続するには「資産引継ぎ」の手続きを適切に行う必要があります。

合わせて読みたい「 法人化を検討する売上」に関するおすすめ記事

法人化を検討すべき売上の目安は?売上以外の判断目安についても解説!
「同じ事業なのに、法人成り後も使えないの?」と疑問に思うかもしれませんが、法人成りとは、個人とは異なる法人格を持つ会社に生まれ変わる手続きであり、個人と法人は法律上まったくの別人格です。そのため、資産は法人に改めて引き継がなければ使用できないのです。
このように、法人成りには必ず資産引継ぎの対応が求められ、その手法にはいくつかの選択肢があります。
ここでは、法人成りを円滑に進めるための4つの代表的な資産引継ぎ方法についてわかりやすくご紹介します。
法人成りにおける資産引継ぎの方法①
譲渡(資産を法人に売却)
譲渡による資産引継ぎとは、個人が所有する事業用資産を、新たに設立した法人に「売却」する形で引き継ぐ方法です。
たとえば、個人事業主が事業で使っていた車両やパソコンを、法人が適正価格で購入することで資産を引継ぎ、法人成り後もそのまま活用することができます。
会社設立の関連記事:「会社の作り方を徹底解説!必要な手続きと費用について」
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
この譲渡による資産引継ぎは、法人成りの手続きにおいて最も透明性が高く、帳簿処理や税務対応もしやすい方法として多くのケースで採用されています。
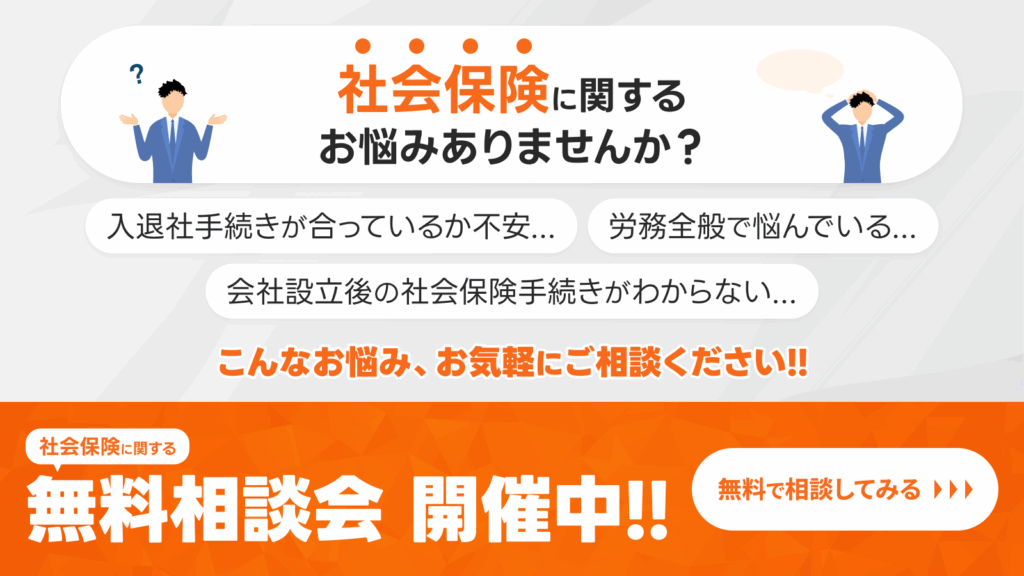
法人成りにおける資産引継ぎの方法②
賃貸(資産を法人に貸与)
一方、賃貸による資産引継ぎは、個人が所有したままの資産を法人に「貸し出す」という形で利用を継続する方法です。
たとえば、個人が所有している事務所用の建物を、法人成りによって設立された法人に賃貸契約で貸し出すことで、資産の所有権は個人に残したまま法人に使用させることが可能です。
この資産引継ぎ方法は、法人成り後の資金負担を抑えたい場合や、不動産売却による登記変更・税負担を避けたいときに有効です。
法人成りで資産引継ぎに関するおすすめ記事

法人成りで資産引継ぎをする場合様々な方法があります。法人成りをして資産引継ぎについて、以下の記事も参考になるでしょう。
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「法人成りするときの資産引継ぎはどうする?引き継げない資産や具体的な処理方法を解説」
法人成りにおける資産引継ぎの方法③
現物出資(資産を資本金として法人に出資)
現物出資による資産引継ぎは、個人が保有する資産を「現金ではなく物品として」法人に出資し、資本金の一部として資産を引継ぐ方法です。
たとえば、個人事業主が保有する高額な設備機器や不動産を、設立する法人の資本金に充てるといったケースが該当します。

合わせて読みたい「IT企業を一人で起業」に関するおすすめ記事

IT企業を一人で起業するには?おすすめのアイディアや成功のコツを解説!

ただし、資産の価額が500万円を超える場合には、裁判所の選任する検査役による調査が必要となるなど、手続きの煩雑さがネックとなるため、法人成りではあまり選択されない資産引継ぎ方法です。
法人成りにおける資産引継ぎの方法④
贈与(資産を法人に無償で譲渡)
贈与による資産引継ぎは、資産を無償で法人に引き渡す方法です。たとえば、個人が使用していた車両を、新たに設立した法人に無償で渡すケースなどが該当します。
この方法では、法人は購入資金を必要とせずに資産を得られますが、贈与された資産には「受贈益」が発生するため、法人側に課税される可能性がある点には注意が必要です。
また、贈与した個人側にも譲渡所得が課税されるケースがあり、結果的に税負担が大きくなることもあります。
そのため、法人成りにおける資産引継ぎ方法としては、贈与はリスクが高く、慎重に扱うべき手段と言えるでしょう。
法人成りで資産引継ぎに関する注意点

③と④は実務上あまり一般的ではなく、法人成りの現場では慎重な検討が求められます。
法人成り時に注意したい「みなし譲渡」
法人成りを行う際には、個人で保有していた事業用資産を、法人に引継ぎする必要があります。
この法人成りの引継ぎ作業では、思わぬ落とし穴として「みなし譲渡」という課税ルールが存在します。
とくに、無償または著しく低額での引継ぎを行った場合には、税務上で問題になることがあるため、法人成りのタイミングでの引継ぎ方法には細心の注意が必要です。

合わせて読みたい「個人事業主から法人化したときのメリットとデメリット」に関するおすすめ記事

個人事業主から法人化するメリットとデメリットとは?
そもそも「みなし譲渡」とは?
みなし譲渡とは、資産を無償や時価より大幅に安い価格で譲渡した場合に、実際にはお金が動いていなくても「時価で譲渡したとみなして課税する制度」です。
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
たとえば、法人成りによって設立した法人に対して、個人名義で所有していた不動産や車両などを引継ぎたいと考えたとします。
この際に、資産を無償、または極端に安い金額で法人に引継ぐと、税務上は「時価で譲渡した」とみなされ、個人に譲渡所得税が発生する可能性があります。

合わせて読みたい「個人事業主が法人化するタイミング」に関するおすすめ記事

個人事業主が法人化を検討すべきタイミングとは?判断基準を解説!
なぜ法人成りの引継ぎで「みなし譲渡」が問題になるのか?
法人成りとは、個人とは別の人格を持つ法人を新たに設立することです。
つまり、個人と法人は別の存在であり、たとえ自分が設立した法人であっても、資産の引継ぎは他人への譲渡と同様に扱われます。
法人成りで資産引継ぎに関するおすすめ記事

法人成りで資産引継ぎをする場合様々な方法があります。法人成りをして資産引継ぎについて、以下の記事も参考になるでしょう。
「【法人成り】資産の引き継ぎ方法でお困りの方へ【もう悩まない】」
そのため、法人成りによる引継ぎで贈与や低額譲渡を行った場合には、税務署側はそれを「実質的な利益移転」と判断し、みなし譲渡課税が行われる可能性が高まります。
法人成りで資産引継ぎに関する注意点

特に時価が高騰している資産を法人成り時に引継ぎする場合、意図せず多額の譲渡所得税が発生することもあります。
こうした課税リスクを避けるには、法人成りにおける引継ぎ方法を事前にしっかりと検討することが必要です。
【譲渡・賃貸】法人成りで行う資産引継ぎの具体例|資産ごとの引継ぎ方法
法人成りを行うときに避けて通れない手続きが「引継ぎ」です。
事業を個人から法人に切り替える以上、これまで個人名義で保有していた資産や契約などは、すべて法人に引継ぎを行わなければなりません。
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
法人成りで資産引継ぎをする場合、以下のサイトも是非ご覧ください
「法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入」
ただし、この引継ぎは単純な名義変更ではなく、資産の種類や状況によって、譲渡・賃貸・現物出資など、さまざまな方法から最適な引継ぎ手段を選ぶ必要があります。
法人成りで行う資産引継ぎの具体例1
棚卸資産の引継ぎ
法人成りを行う際には、個人事業で保有していたさまざまな資産を法人に引継ぎする必要があります。その中でも、在庫や原材料などの棚卸資産の引継ぎは、法人成りにおける最初の大きなステップといえます。
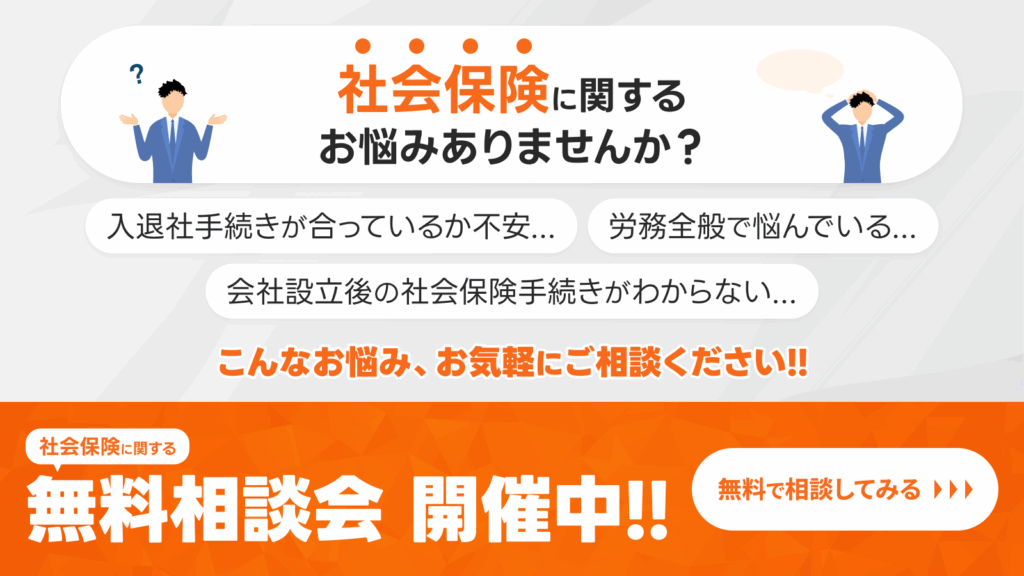
棚卸資産とは、販売や製造、業務消耗などを目的として保管している資産の総称であり、たとえば以下のようなものが該当します。
- 販売用の商品在庫
- 製造中の仕掛品
- 製品製造に必要な原材料
- 日常業務で使う消耗品(例:コピー用紙や筆記具など)
これらの棚卸資産は、法人成りを通じて設立された新しい法人に引継ぐ必要がありますが、基本的には「譲渡」という形式をとるのが一般的です。つまり、個人事業主が法人に対して資産を売却し、法人がこれを買い取る形で資産引継ぎを行うのです。
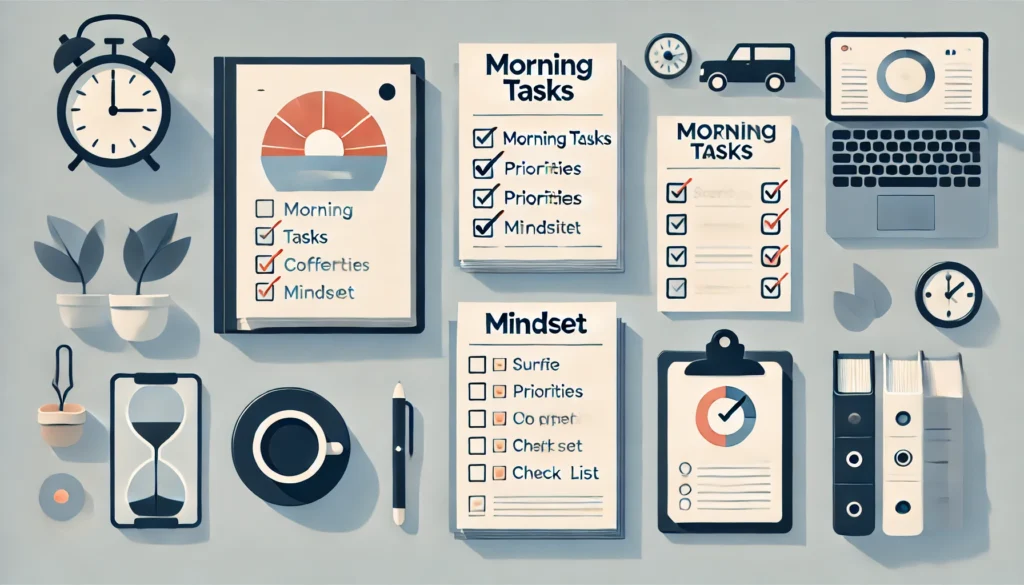
法人成り時の引継ぎ価格の考え方
法人成りにともなう棚卸資産の引継ぎ価格は、「通常の取引価格(時価)」を基準に設定します。たとえば、1つの商品が市場で5,000円で販売されている場合は、その商品を5,000円で法人に譲渡するのが原則です。

合わせて読みたい「 個人事業主と法人化はどっちが得?」に関するおすすめ記事
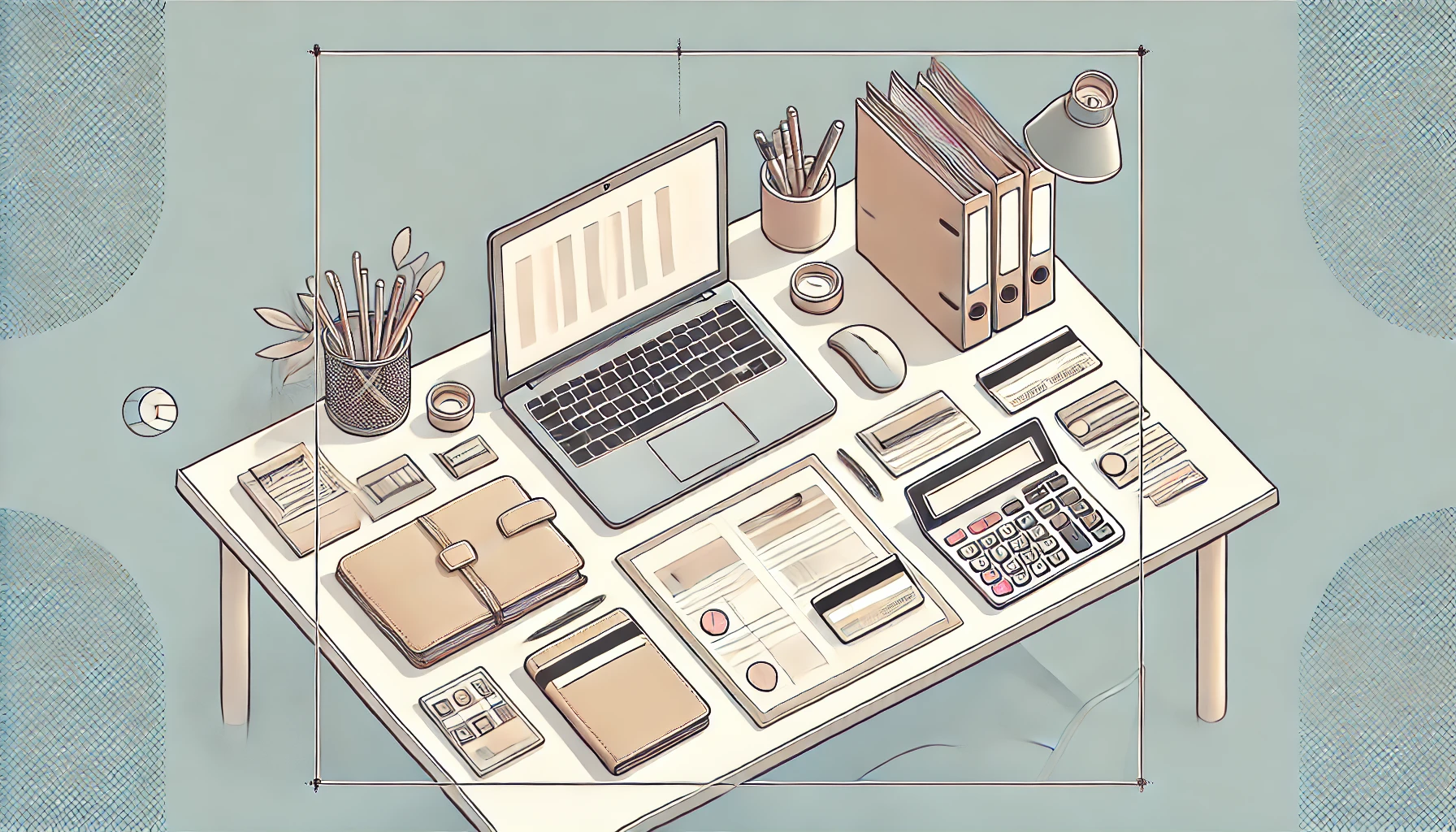
個人事業主と法人化はどっちが得?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説!
ただし、劣化・破損・陳腐化している商品であれば、実際に販売可能な価格(=時価)に応じて価格を調整し、適切に評価して法人成り時に引継ぎを行います。
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「個人事業主から法人成りしました。引き継いだ商品や固定資産などの処理がわかりません」
なお、引継ぎ価格が「通常の価格の70%未満」である場合は、税務上“低額譲渡”と判断され、贈与や譲渡所得の課税対象となるおそれがあります。これにより、法人成り時に想定外の税金が発生するリスクがあるため注意が必要です。
法人成りにおける会計処理の具体例(棚卸資産の引継ぎ)
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
法人成りによる棚卸資産の引継ぎでは、以下のような会計処理を行います。
| 区分 | 会計処理 |
|---|---|
| 個人事業主側(旧事業) | 売上として計上(事業所得) |
| 法人側(新会社) | 仕入高または在庫として資産計上 |
【事例】
個人でハンドメイド雑貨を販売していたAさんは、法人成りによって株式会社を設立。
在庫として残っていた棚卸資産を法人に50万円で譲渡による引継ぎを実施しました。法人では「仕入」、個人では「売上」として引継ぎ処理します。
なお、支払いは一部を未払金とし、分割で支払う形で引継ぎを柔軟に対応しました。
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
法人成りで資産引継ぎをする場合、以下のサイトも是非ご覧ください
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「法人成りの仕訳とは?資産・負債の引継ぎや税務処理をわかりやすく解説」
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| ケース | 雑貨販売をしていたAさんが法人成りで合同会社を設立 |
| 引継ぎ対象の資産 | 商品在庫(棚卸資産)50点・合計70万円 |
| 引継ぎ方法(譲渡) | 法人へ時価で譲渡。仕入処理:70万円 |
| 個人側の処理 | 売上として事業所得に計上 |
| 資金繰り対策 | 法人の現金が不足していたため、一部未払金で処理 |
| 備考 | 在庫評価は第三者査定で明確化、70%ルールを遵守 |
法人成りで行う資産引継ぎの具体例2
減価償却資産の引継ぎ
法人成りを行う際には、個人事業で保有していた減価償却資産を新しく設立する法人へ引継ぎすることが非常に重要です。特に、法人成り後も事業で継続して使用する予定の資産については、適切な形での資産引継ぎが求められます。
法人成りで資産引継ぎに関するおすすめ記事

法人成りで資産引継ぎをする場合様々な方法があります。法人成りをして資産引継ぎについて、以下の記事も参考になるでしょう。
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「法人成りの資産・負債の引継ぎ方法と仕訳 | 事例と注意点まで解説」
法人成りで資産引継ぎに関するポイント!

減価償却資産とは、自動車やパソコン、コピー機など、使用するごとに価値が減少していく資産を指します。
これらの資産引継ぎは、通常「譲渡」という形で処理され、法人成り時の基本的な手続きのひとつとなります。
法人成りによる減価償却資産の引継ぎは「時価」が原則
法人成りに伴って減価償却資産を引継ぎする際は、「時価」での譲渡が原則です。これは、法人が個人から資産を適正価格で取得することで、法人成りにおける税務上の問題を避けるためです。たとえば、営業用に使用していた自動車を法人成り後の法人で継続使用する場合、その自動車の時価で引継ぎ手続きを行います。

合わせて読みたい「個人事業主が0円で起業する方法」に関するおすすめ記事

0円起業の始め方は?起業アイディアや成功のコツも解説!
個人事業主に関する参考記事:「起業とは?個人事業主と法人の違いについても解説!」
時価が不明な場合は簿価で引継ぎも可能
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
法人成りで資産引継ぎをする場合、以下のサイトも是非ご覧ください
「法人成りした際の資産と負債の引き継ぎ」
法人成りの際、必ずしもすべての資産の時価を正確に把握できるとは限りません。そのような場合は、帳簿に記載されている「簿価(帳簿価額)」をもとに引継ぎを行うことが認められています。これにより、現実的な形で資産引継ぎが可能となり、スムーズな法人成りの実現にもつながります。

合わせて読みたい「個人事業主から法人化 メリット デメリット」に関するおすすめ記事

個人事業主から法人化するメリットとデメリットとは?
法人成りで減価償却資産を引継ぐ際の会計処理例
法人成りを行い、個人が保有していた減価償却資産を法人へ引継ぎした場合、以下のような会計処理が一般的です。
- 個人事業主側:譲渡所得として計上
- 法人側:固定資産として取得し、再度減価償却を開始
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
このような形で、法人成り後の法人は引継いだ資産を再評価し、適切な耐用年数を設定して償却していくことになります。
【事例】
個人で動画編集業をしていたBさんは、法人成り後に高性能PCやカメラなどの機材を譲渡で引継ぎ。
また、使用中の業務用ソフトは現物出資で法人の資本金に充当することで、柔軟な引継ぎ方法を実現しました。
一部の設備については、譲渡コストを抑えるため、法人へ賃貸で引継ぎしました。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| ケース | フリーランスの動画編集者Bさんが法人成りし法人設立 |
| 引継ぎ対象の資産 | PC(40万)、カメラ(15万)、照明機材(10万) |
| 引継ぎ方法(譲渡) | 法人へ時価65万円で譲渡し、固定資産に登録 |
| ソフトウェアの処理 | Adobeライセンスは「現物出資」で資本金に組み込み |
| 賃貸処理の併用 | 車両(残価60万円)は法人へ月3万円で賃貸し引継ぎ |
| 備考 | 減価償却は再計算、耐用年数は中古資産として再設定 |
法人成りで行う資産引継ぎの具体例3
不動産の引継ぎ

法人成りを行う際に、多くの個人事業主が直面するのが不動産の引継ぎ方法です。特に事業で使用している建物や土地といった不動産を、法人成りによって設立する法人にどう引継ぐかは、税務上も実務上も重要なポイントです。法人成りでは、不動産を「譲渡」または「賃貸」という形で法人へ引継ぎますが、それぞれに特徴と注意点があります。
まず、譲渡による不動産の引継ぎでは、個人が所有していた不動産を法人成りした法人に売却することで、所有権が法人に移転します。この場合、法人側は不動産を固定資産として計上し、建物に関しては減価償却を行うことになります。
法人成りで資産引継ぎに関する注意点

個人側には譲渡所得が発生し、法人成りに伴う所得税負担が増えることもあるため、引継ぎ価格やタイミングに注意が必要です。
次に、賃貸という方法で不動産を法人成り後の法人に引継ぐことも可能です。賃貸では所有権を個人に残したまま、法人に貸し出すことで事業利用が可能になります。法人成り直後は資金に余裕がないケースも多いため、初期費用を抑えたいときには賃貸による引継ぎが適しています。ただし、法人からの賃料収入は個人の不動産所得として申告が必要ですので、法人成り後の税務対応も計画しておきましょう。
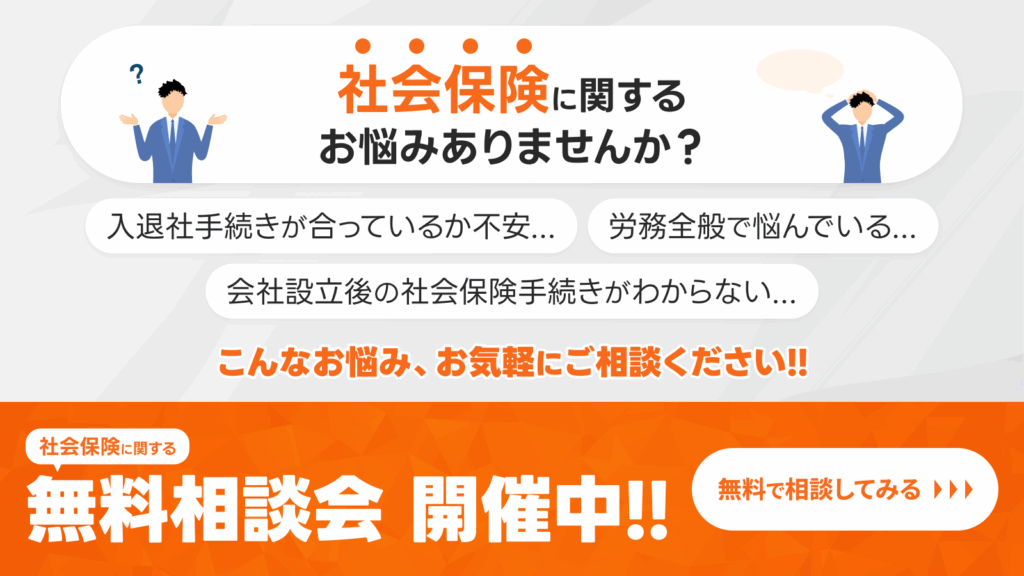
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
法人成りで資産引継ぎをする場合、以下のサイトも是非ご覧ください
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「法人成りで個人事業主の資産を引き継ぐ方法は?資産の種類、注意点も解説!」
このように、法人成りにおける不動産の引継ぎには、譲渡と賃貸の2通りの方法があり、どちらを選ぶかによってコストや税務処理が異なります。引継ぎに失敗すると、税負担が想定以上に重くなったり、法人設立後の運営に支障が出たりするため、法人成り前に十分な準備と検討が必要です。
【事例】
自宅の一部を事務所として使用していたCさんは、法人成りのタイミングで、そのスペースを法人に月額2万円で賃貸という形式で引継ぎ。
法人では賃料を経費に計上し、個人側では不動産所得として申告。引継ぎにより法人・個人双方にとって税務上有利な対応となりました。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| ケース | 自宅の一部を事務所にしていたCさんが法人成りで株式会社設立 |
| 引継ぎ対象の資産 | 自宅の一室(15㎡)を法人に使用させたい |
| 引継ぎ方法(賃貸) | 月額2万円で法人に貸し出し。不動産所得として処理 |
| 法人側の処理 | 賃料を経費計上し、引継ぎコストを最小化 |
| 所有権譲渡の回避 | 登記や税金を避け、ローン控除も継続可能 |
| 備考 | 賃貸契約書を交わし、利用割合を明記して税務上の根拠を確保 |
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「【法人成り】償却資産の引継価額は簿価?仕訳は?引継後の償却方法や耐用年数は?」
法人成りで行う資産引継ぎの具体例4
負債の引継ぎ
法人成りを進める際、資産だけでなく負債の引継ぎについても十分な検討が必要です。多くの個人事業主は、法人成りのタイミングで棚卸資産や減価償却資産の引継ぎに注力しますが、借入金や買掛金といった負債の引継ぎにもルールや注意点があるため、無視はできません。

合わせて読みたい!「税理士に相談するタイミングをお悩みの方」におすすめ記事
法人化する際に税理士への相談は必要?相談するメリットや費用を解説

原則として、法人成りをする前に、個人として抱えている負債は可能な限り完済しておくことが望ましいです。負債の引継ぎは資産のようにスムーズに行えるものではなく、煩雑な手続きや金融機関との調整が必要になるからです。つまり、法人成り前にすべての負債を処理しておけば、引継ぎの工程をひとつ減らすことができ、スムーズに法人運営へ移行できます。
しかし、事業拡大に伴い一時的な資金繰りの悪化や、法人成り前に完済できない事情がある場合は、法人設立後に新会社が金融機関から融資を受け、その資金を活用して個人名義の負債を返済するという形で負債を間接的に引継ぐことも可能です。
法人成りで資産引継ぎに関する注意点

ただし、設立間もない法人では信用力が乏しく、融資の審査が厳しくなるケースも多く見られます。
もう一つの方法として、正式に負債を引継ぐ「債務引受」という手段があります。これは、個人事業主の借入金などの負債を、法人成りによって設立された法人が引受け、法的にも正式な負債引継ぎを行う方法です。
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
債務引受には以下の2つの形態があります。
- 重畳的債務引受:法人と個人の両方が返済義務を負う方法で、法人成り時の負債引継ぎでは比較的多く採用されている形式です。万が一法人側が返済できなくなった場合でも、個人が引き続き責任を負うことになります。
- 免責的債務引受:新設法人が負債を完全に引継ぎ、個人は返済義務から解放される形です。ただし、金融機関の同意が不可欠であり、実現にはハードルがあるため、慎重な交渉と準備が必要です。
いずれの方法でも、法人成りによって負債の引継ぎを行うには、借入先の金融機関や取引先と事前にしっかりと話し合い、同意を得ることが極めて重要です。特に法人成り直後の会社は信用基盤がまだ整っていないため、交渉には計画性と戦略が求められます。
法人成りで資産引継ぎに関するおすすめ記事

法人成りで資産引継ぎをする場合様々な方法があります。法人成りをして資産引継ぎについて、以下の記事も参考になるでしょう。
「法人成りで引き継ぐ資産が不動産の場合の注意点」
また、法人成りによる負債引継ぎを行った場合の会計処理や税務処理も複雑になることがあります。たとえば、個人から法人への負債の移行については、債権者との合意文書の作成や、貸借対照表上の負債残高の適切な表示など、会計処理における整合性も欠かせません。
【事例】
創業融資を個人で受けていたDさんは、法人成り後にその借入を法人に引継ぎたいと考えましたが、金融機関からの同意が得られず断念。
結果、個人で返済を継続し、法人には負債を引継がない選択をしました。
代わりに法人の収益が安定してから、法人名義で改めて資金調達し、実質的な負債の引継ぎを後日行う形としました。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| ケース | 起業準備中のDさんが個人で300万円の創業融資を受けていた |
| 法人成り後の対応 | 金融機関からの同意が得られず、負債を個人で継続返済 |
| 資金対策 | 棚卸資産の譲渡益で150万円を繰上返済 |
| 法人借入の検討 | 法人成り後、実績をもとに法人名義で借入を申請予定 |
| 備考 | 金融機関への説明資料を準備し、法人化の信用影響を抑制 |
法人成りで資産引継ぎを行う際の注意点
法人成りを検討している個人事業主にとって、最も重要なステップのひとつが資産引継ぎです。
事業を法人化するにあたり、これまで個人として扱っていた資産・契約・事務手続きなどを、法人に正しく引継ぐことが、スムーズな法人成りのカギを握ります。
しかし、この引継ぎを誤ると、思わぬトラブルや税務リスクを抱えることになりかねません。
ここでは、法人成りを成功させるために必要な引継ぎの注意点について、徹底的に解説します。
法人成りの資産引継ぎに不安がある方も、この記事を読めば適切な準備ができるはずです。
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
法人成りで資産引継ぎをする場合、以下のサイトも是非ご覧ください
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「法人化・法人成りで車など減価償却資産の引継ぎ節税対策」
法人成りで資産引継ぎを行う際の注意点①
資産引継ぎできないもの
法人成りの際、すべての資産がそのまま法人に引継ぎできるわけではありません。
法人成りで引継ぎできない代表的な資産には、以下のようなものがあります。
- 賃貸借契約中の物件
- リース契約中の機器や車両
- 個人名義で取得した営業許可・届出書類など
たとえば、個人で借りていた事務所やリース車両を法人に引継ぐ場合、新たに法人名義で再契約が必要になることがあります。
また、飲食業などで個人として取得した営業許可証なども、法人成り後の法人に引継ぐことはできず、法人として改めて申請が必要です。

こうした引継ぎ不可の資産があることを事前に把握しておかないと、法人成り後の事業運営に支障が出る恐れがあります。
スムーズな法人成りと引継ぎのためにも、すべての資産や契約の見直しを行いましょう。
法人成りで資産引継ぎを行う際の注意点②
資産引継ぎ時には消費税が発生する場合も
法人成りにおける資産の引継ぎは、方法によっては課税対象となることがあります。
資産を売却して法人に引継ぐ場合(譲渡)、あるいは現物出資や賃貸により法人へ引継ぐ場合は、消費税が課税される可能性があります。
ただし、以下のような資産については、法人成りに伴う引継ぎにあたっても消費税が非課税です。
- 土地および土地の上に存する権利(建物は課税)
- 有価証券(株・債券・預金など)
- 現金、小切手、手形
- 商品券、図書カードなどの物品切手類
- 社会福祉用途の物品や土地の貸付
- 住宅の貸付(事業用建物を除く)
個人事業主が課税事業者である場合、法人成り時の資産引継ぎには消費税が課されるため、事前に正確な課税関係を確認する必要があります。
特に、譲渡金額が高額となると支払う消費税も多額になるため、引継ぎ方法を検討する際の重要な判断材料となります。
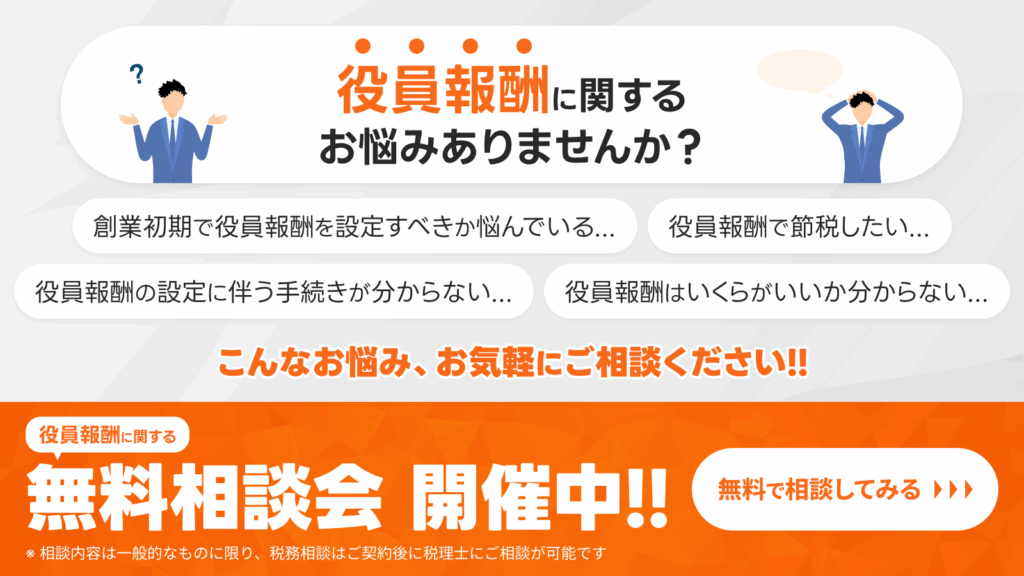
法人成りで資産引継ぎに関する参考記事:「個人事業主から法人成りをした場合の資産引継ぎと仕訳方法について」
法人成りで資産引継ぎを行う際の注意点③
時価と異なる価格で引継ぐと課税リスクがある
法人成りにおける資産引継ぎの価格設定は、税務上の大きな論点です。
実際の時価から著しく乖離した価格で引継ぎを行うと、以下のような課税問題が発生します。
たとえば、資産を時価の70%未満で法人に引継いだ場合、「低額譲渡」として差額が贈与とみなされ課税対象になることがあります。
法人成りで資産引継ぎに関するポイント!

時価よりも高い金額で資産を法人へ引継いだ場合は、法人側にとってはその差額が「寄附金」とされ、損金不算入(経費にならない)扱いとなり法人税負担が増加します。
【例】
- 時価1,000円の資産を600円で譲渡(低額譲渡) → 差額の一部が贈与扱い
- 同資産を1,200円で譲渡(高額譲渡) → 法人側で200円が寄附金扱い
このように、法人成りにおける引継ぎ価格の設定は、税務署に疑義を持たれないよう適正な時価を基準に行うことが不可欠です。
償却資産の引継ぎ処理も法人成りで重要なポイント
法人成りで引継ぐ償却資産については、取得価額や使用年数を考慮して、法人における減価償却処理を行う必要があります。
引継ぎ後の償却処理を適切に行うことで、節税や財務管理の面で大きな効果をもたらします。
「法人成りで資産引継ぎ」編集部
主な償却資産の引継ぎ処理には以下の3つがあります。
- 少額減価償却資産(10万円未満):全額即時償却が可能
- 一括償却資産(10〜20万円):3年で均等に償却
- 中小企業の特例(10〜30万円):年間300万円まで一括償却可能
これらの制度を活用することで、法人成り後の法人が引継いだ資産を早期に経費化できるため、資金繰りを安定させながら利益調整が行えます。
法人成りで資産引継ぎに関するポイント!

法人成りでの資産引継ぎには、こうした減価償却の仕組みもセットで検討すべきと言えるでしょう。
まとめ|法人成りで資産引継ぎ方法
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人成りを円滑に進めるためには、事前の引継ぎ準備が何よりも重要です。個人事業から法人へ移行する過程では、多くの資産の引継ぎが発生します。棚卸資産や減価償却資産、不動産など、どのように引継ぎを行うかによって、法人側の会計処理や税務対応が大きく異なるため、慎重な判断が必要です。
また、法人成りに際しては、資産の引継ぎだけでなく、負債の引継ぎや契約関係の再整理も発生します。中には引継ぎが認められないケースもあるため、法人成りのタイミングや引継ぎ方法を誤ると、余計な税負担や手続きの遅延を招くおそれがあります。
法人成りを成功させる最大のポイントは、「どの資産を、どのような方法で引継ぐか」という計画をしっかりと立てることです。譲渡・賃貸・現物出資・贈与といったさまざまな引継ぎ手段の中から、最も適した方法を選び、税務上のリスクを回避するためにも、専門家への相談は欠かせません。
これから法人成りを検討している方は、ぜひ今回紹介した引継ぎの知識を活用し、スムーズな法人成りを実現しましょう。正しい資産引継ぎが、法人としての安定したスタートにつながります。

合わせて読みたい「個人事業主から法人化 社会保険手続き」に関するおすすめ記事

個人事業主から法人化(法人成り)したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!