従業員の退職手続きは何をする?必要書類や会社側・従業員側でやることを解説
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2026年1月8日
従業員が退職する際には、会社側と従業員側の双方で、数多くの手続きを確実に進める必要があります。退職の際に発生する手続きには、退職届の提出や業務引き継ぎといった社内手続きだけでなく、健康保険や厚生年金、雇用保険、源泉徴収票の発行、離職票の交付など、法令に基づく各種の公的手続きも含まれます。こうした手続きを正しく理解し、期限内に完了させることは、従業員本人にとっても会社にとっても非常に重要です。
特に従業員にとっては、退職前に行う書類提出や貸与物の返却、退職後に必要となる健康保険や年金の切り替えといった手続きを見落とすと、後々トラブルになる可能性があります。一方で、会社側も、従業員の退職に伴って発生する各種喪失届や証明書類の交付など、正確で迅速な手続きが求められます。手続きの遅延や漏れがあると、従業員の生活や再就職に影響を及ぼす恐れもあるため注意が必要です。
本記事では、従業員の退職手続きに関して、従業員側が行う手続きと、会社側が対応する手続きを項目ごとに詳しく解説します。退職時に必要なすべての手続きを一つひとつ確認し、退職後の生活に支障が出ないよう、万全の準備を進めましょう。
「従業員の退職手続き」編集部
従業員も会社側も、退職に伴う手続きをスムーズに進めるための実践的なガイドとして、ぜひご活用ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社側が対応すべき従業員退職時の手続きとは?
会社側が従業員の退職に直面した際には、法令や就業規則に従い、迅速かつ確実に各種手続きを進める必要があります。従業員から退職の意思が示された時点で、会社側には数多くの対応事項が発生し、それぞれの退職手続きを正しく理解し、期限内に処理することが求められます。退職手続きに不備があると、従業員とのトラブルや法的リスクに発展する可能性があるため、会社側は責任を持って丁寧に進めることが重要です。
「従業員の退職手続き」編集部
従業員の退職時における手続きについて、以下のサイトも是非ご覧ください。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「退職手続きはいつまでに何をやるべき?従業員側・会社側それぞれの作業を解説」
| 手続き名 | 概要 | 提出期限 | 提出先 | 主な必要書類 |
|---|---|---|---|---|
| 退職届の受理 | 従業員から退職の意思表示を受け取り、 退職日などを確認 |
民法上は退職の14日前 (ただし協議が必要) |
社内 (人事・労務部門など) |
退職届 (原則書面。法的義務ではないが証拠保全のため) |
| 貸与物の回収 | 社員証・PC・健康保険証などの 会社貸与品を回収 |
退職日または最終出勤日まで | 社内管理部門 | 貸与品チェックリスト 健康保険証(本人・扶養家族分) |
| 社会保険の資格喪失手続き | 健康保険・厚生年金の資格喪失を 年金事務所へ届け出る手続き |
資格喪失日(退職翌日)から5日以内 | 管轄の年金事務所 | 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届 健康保険証(本人・扶養家族分) |
| 雇用保険の資格喪失手続き | 雇用保険の資格喪失をハローワークへ 届け出る手続き |
退職日の翌々日から10日以内 | 管轄のハローワーク | 雇用保険被保険者資格喪失届 雇用保険被保険者離職証明書 賃金台帳 出勤簿 労働者名簿 |
| 所得税(源泉徴収票の交付) | 退職した年の給与・控除情報を記載した源泉徴収票を 従業員へ交付 |
退職日から1ヶ月以内 | 従業員本人 | 源泉徴収票 |
| 住民税の異動届出 | 特別徴収の対象者が退職したことを 自治体に報告 |
退職した月の翌月10日まで | 従業員の居住地の市区町村 | 給与所得者異動届出書 |
| 離職票の交付(希望者) | 失業給付を受けるために必要な離職票を発行し、 従業員へ送付 |
雇用保険喪失手続きと同時 | 従業員本人 | 離職票-1・離職票-2、 離職証明書 賃金資料 |
| 健康保険資格喪失証明書発行 | 国保加入などに必要な証明書。 本人の希望に応じて申請・交付 |
任意 (希望があった場合) |
協会けんぽまたは健康保険組合 | 健康保険資格喪失証明書 (発行申請書) |
| 雇用保険被保険者証の返却 | 雇用保険に加入していたことを 証明する書類を従業員に返却 |
退職日または退職後速やかに | 従業員本人 | 雇用保険被保険者証 |
| 退職証明書の発行 | 従業員の希望に応じて就労状況などを 記載した退職証明書を発行 |
請求を受けた場合は遅滞なく | 従業員本人 | 退職証明書 (自由形式・厚労省モデル様式あり) |
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社側がする従業員退職時の手続き①
従業員から退職届を受け取った際の基本的な対応

まず、従業員が退職の意思を明確にした際には、会社側としてはその退職の申し出を受け入れたうえで、退職日やその後の手続きについて従業員と十分に協議を行う必要があります。退職の意思表示から14日を経過すれば、従業員は原則として退職できると民法に定められており、就業規則に「1ヶ月前に申し出ること」といった記載があっても、法律上は14日での退職が有効となります。したがって、従業員の退職申し出が就業規則より短い期間であっても、会社側はその退職を拒むことができません。
従業員の退職手続きに関するポイント!

(民法第627条第1項)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
ただし、退職の申し出から14日未満で退職したいという希望がある場合には、会社側の同意がなければその希望通りにはなりません。このようなケースでは、会社と従業員が互いに相談し、可能な退職日について合意を形成することが望まれます。
従業員の退職手続きに関する注意点

退職届は法的に義務付けられているわけではありませんが、会社側としては、従業員に退職の証拠を明確に残す意味でも書面での提出を求めるべきです。口頭のみでは、退職日や条件を巡る誤解が発生するおそれがあります。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「従業員の退職に伴う社会保険・雇用保険等の手続きと対応の注意点」
会社側がする従業員退職時の手続き②
健康保険証や会社支給物の回収
退職手続きの中でも、会社側が注意しなければならないのが、従業員に貸与していた物品や健康保険証の確実な回収です。たとえば、社員証、名刺、社用PC、社用携帯電話など、業務上使用していたすべての備品を従業員から退職日前または最終出勤日までに回収することが重要です。退職日当日に従業員が出社しないケースもあるため、最終出勤日を事前に確認しておくことで、会社側は確実な手続きが可能になります。
従業員の退職手続きに関するおすすめ記事

従業員が退職する際の会社側と従業員側の手続きについて、以下の記事も是非参考にしてください。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「従業員の退職手続き一覧~必要な書類や手続きの期限は?」
また、従業員の健康保険証は、退職日をもって資格喪失となるため、会社側はこれを回収し、年金事務所へ提出する必要があります。扶養家族がいる従業員については、家族分の健康保険証もあわせて回収することが求められます。
「従業員の退職手続き」編集部
万一、従業員から健康保険証の返却が得られない場合には、「健康保険被保険者証回収不能届」を添えて、資格喪失手続きとともに届け出を行います。
会社側がする従業員退職時の手続き③
社会保険の資格喪失に関する退職手続き
従業員が退職した場合、会社側がまず取り組まなければならない退職手続きのひとつが、社会保険に関する資格喪失の手続きです。この退職手続きは、従業員が健康保険や厚生年金の対象外となることを正式に申請する重要なプロセスであり、会社側には法定期限内に適切な処理を行う義務があります。退職後も従業員に不利益が生じないよう、会社側は一連の退職手続きを丁寧かつ迅速に進める必要があります。

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
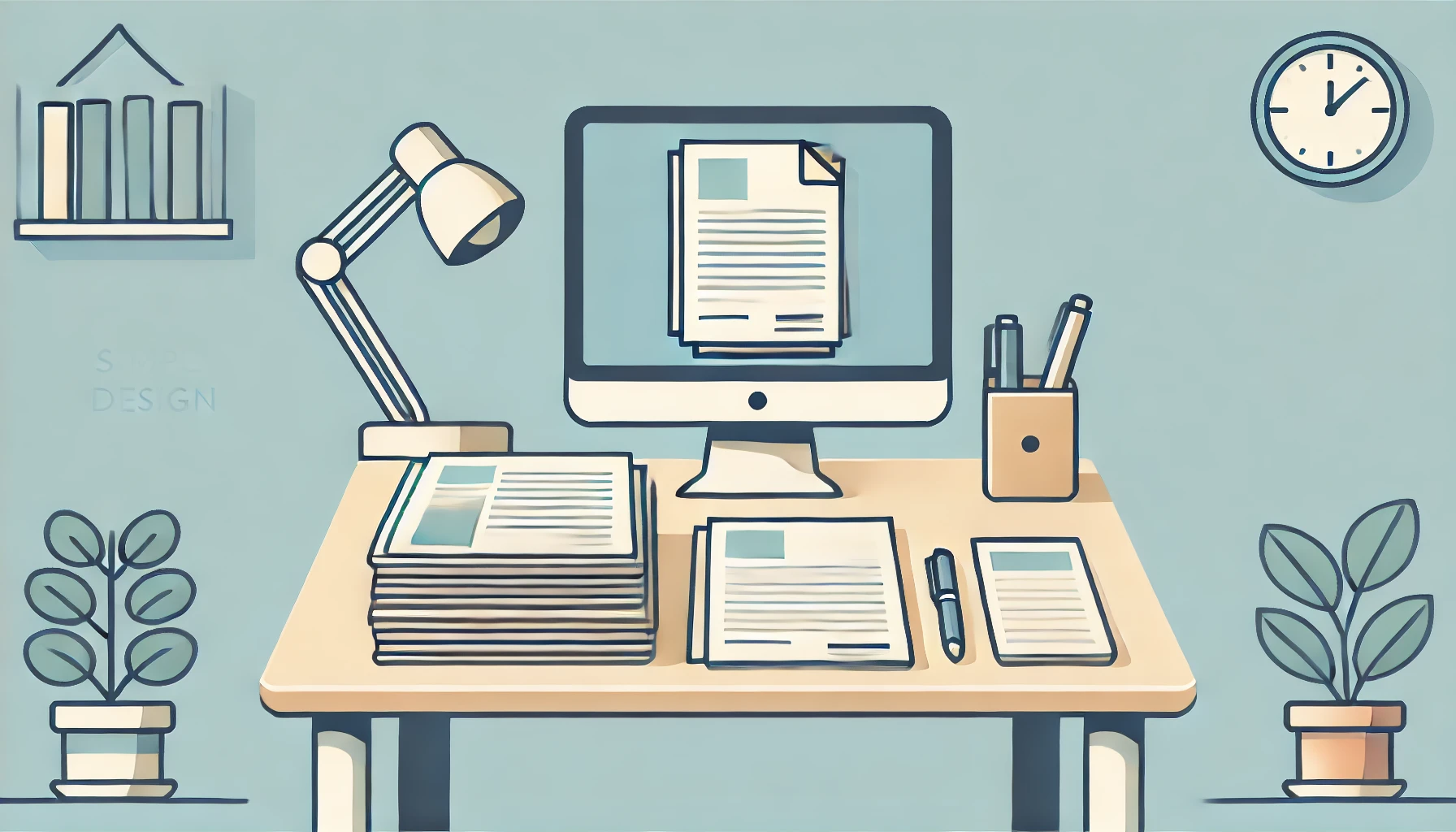
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
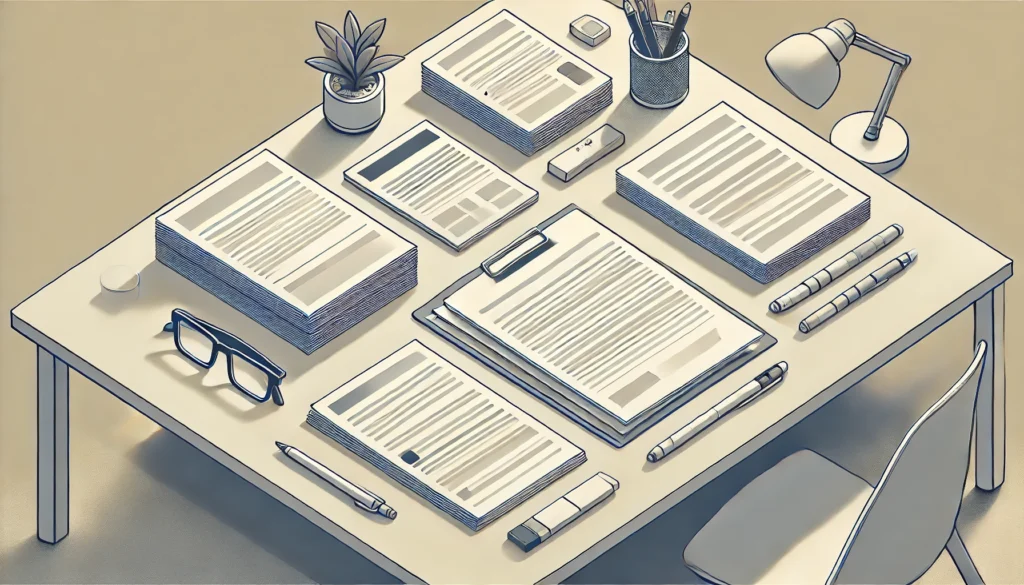
「従業員の退職手続き」編集部
従業員の退職時における手続きについて、以下のサイトも是非ご覧ください。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「従業員退職による会社の手続きチェックリスト|提出・回収が必要な書類一覧を解説」
退職した従業員の社会保険資格喪失日は、退職日の翌日となります。たとえば、従業員の退職日が3月31日であれば、資格喪失日は4月1日です。会社側は、この資格喪失日から5日以内に、健康保険および厚生年金の資格喪失手続きを完了させる必要があります。
具体的には、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」という書類を、退職した従業員を雇用していた事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。この手続きにあたっては、退職した従業員本人だけでなく、扶養に入っていた家族全員分の健康保険証を添付する必要があるため、会社側は退職前に従業員からの返却状況をしっかり確認しておくことが重要です。
従業員の退職手続きに関するおすすめ記事

従業員が退職する際の会社側と従業員側の手続きについて、以下の記事も是非参考にしてください。
「退職者への手続き一覧|必要書類のチェックリストと注意点も解説」
また、健康保険組合に加入している会社の場合は、年金事務所だけでなく、所属する健康保険組合にも別途資格喪失の手続きを行う必要があります。この場合も、退職した従業員の健康保険証が添付書類として必要になります。健康保険組合への提出も期限があるため、会社側の退職手続き担当者は年金事務所と健康保険組合の両方に対する退職処理を同時に行う体制を整えることが求められます。

合わせて読みたい「会社側の退職手続き」に関するおすすめ記事
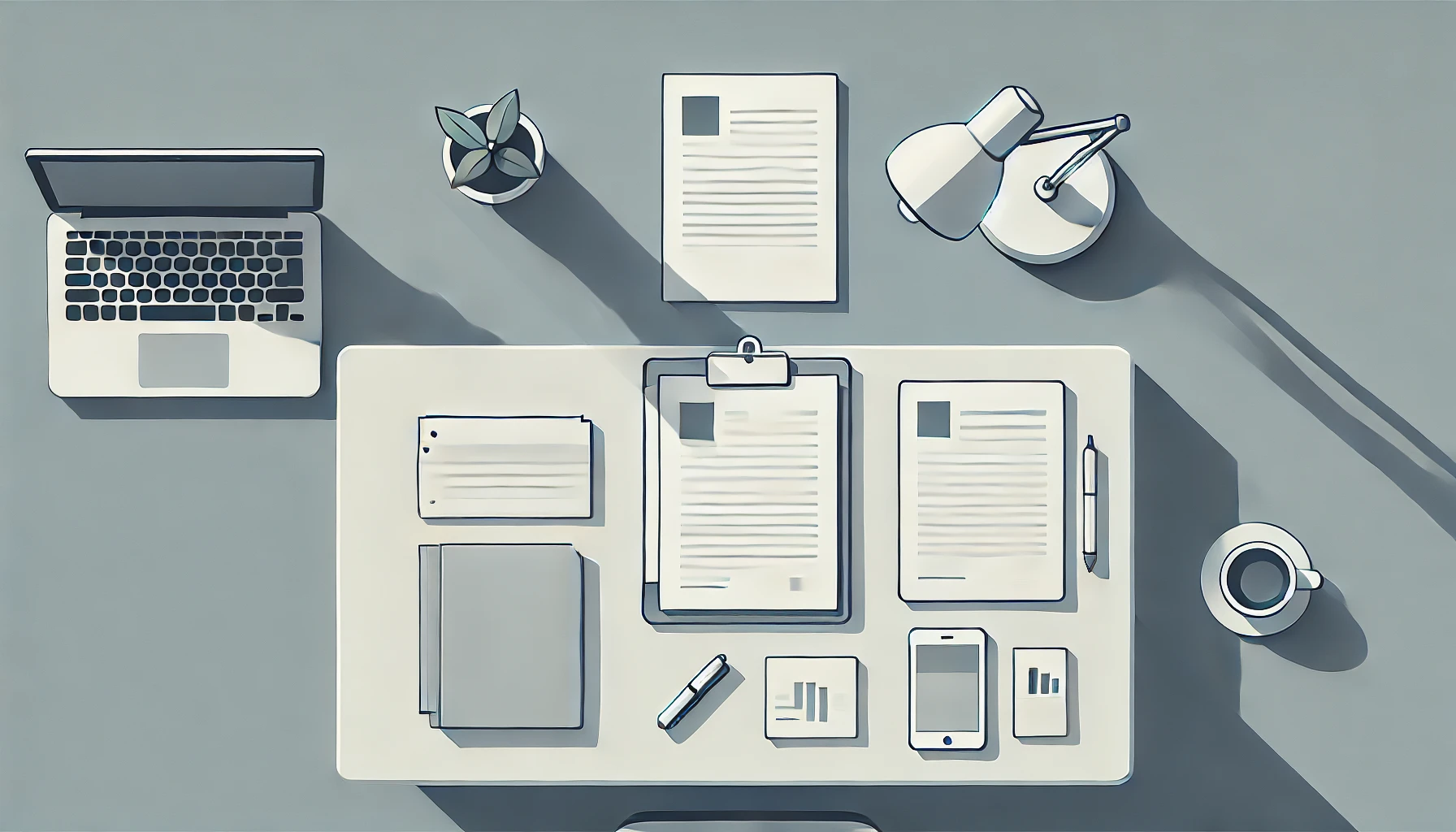
退職手続きでは会社側はいつまでに何をすべき?必要な手続きや対応の注意点を解説!
社会保険に関する退職手続きが遅れた場合、退職後の従業員が次に加入する保険への切り替えに支障が生じたり、医療費の自己負担が一時的に増加したりするリスクがあります。
「従業員の退職手続き」編集部
会社側は退職した従業員の将来の不利益を防ぐ意味でも、この手続きを確実に遂行することが不可欠です。
社会保険の資格喪失に関する退職手続きは、退職した従業員の公的保険制度からの脱退と、新たな保険制度へのスムーズな移行の起点となるため、すべての従業員の退職時に必ず発生する重要な業務です。
会社側がする従業員退職時の手続き④
雇用保険の資格喪失手続き
従業員が退職すると、会社側は雇用保険に関する退職手続きもあわせて行う必要があります。
従業員の退職手続きに関するポイント!

雇用保険は、従業員の退職後に失業給付などを受けるための制度であるため、会社側が資格喪失の手続きを適切に実施しなければ、退職した従業員が正当に給付を受けることができなくなってしまいます。そのため、この雇用保険の資格喪失も退職手続きの中でも非常に重要な位置を占めています。
会社側が行うべき雇用保険の退職手続きとして、まず「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。この資格喪失届は、退職日から2日後以降、10日以内に会社の所在地を管轄するハローワークに提出する必要があります。この手続きによって、退職した従業員が雇用保険制度から正式に除外されることになります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
「従業員の退職手続き」編集部
従業員の退職時における手続きについて、以下のサイトも是非ご覧ください。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
さらに、従業員が離職票を希望する場合には、「雇用保険被保険者離職証明書」も併せて提出する必要があります。この離職証明書には、退職理由や退職直前の賃金支払い状況などを記載しなければならず、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿など、退職前の勤務実績が確認できる資料も添付することになります。これらの退職関連書類を提出することで、退職した従業員は正式に離職票を受け取ることができ、その後の失業保険受給などの手続きに使用できます。
なお、59歳未満の退職者については、本人が離職票の発行を希望しない場合、資格喪失届だけで退職手続きは完了しますが、退職する従業員が59歳以上である場合は、本人の意思に関わらず離職票の交付が必要です。
「従業員の退職手続き」編集部
この点についても会社側はしっかりと確認し、退職手続きを適切に進めることが求められます。
離職証明書はハローワークで配布される3枚綴りの複写式となっており、会社側が記入後、原則として退職前に従業員本人に内容を確認させ、自署をもらうのが基本です。従業員が署名できない状況にある場合には、その理由を記載し、会社側が代表者名で署名することになります。こうした点も含め、雇用保険に関する退職手続きでは会社側の正確な対応が不可欠です。
退職後の従業員が公的支援を適切に受けられるかどうかは、すべて会社側の退職手続きの正確さと迅速さにかかっています。従業員の立場を十分に理解し、すべての退職手続きを漏れなく遂行する姿勢が、企業としての社会的責任にもつながります。
従業員の退職手続きに関するおすすめ記事

従業員が退職する際の会社側と従業員側の手続きについて、以下の記事も是非参考にしてください。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「会社側が行う退職手続きは?遅いと言われないためのチェックリストも紹介」
会社側がする従業員退職時の手続き⑤
所得税・住民税関連の退職後の手続き
従業員の退職後、会社側は税務関連の手続きも適切に行わなければなりません。まず、所得税については、退職する従業員に対してその年に支払った給与や賞与、社会保険料の控除額、源泉徴収税額などを記載した「源泉徴収票」を、退職後1ヶ月以内に交付する義務があります。これは、従業員が再就職先で年末調整を受ける場合や確定申告を行う際に必要不可欠な書類です。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「雇用保険の手続き【事業者向け】従業員の退職時の続きに必要なものも解説」
住民税に関しては、特別徴収を行っていた場合、会社側は「給与所得者異動届出書」を退職者が住民登録している自治体に、退職した月の翌月10日までに提出する必要があります。
従業員の退職手続きに関する注意点

この提出を怠ると、自治体からの督促や指導が会社側に届くこともあるため、退職手続きの一環として忘れずに対応しましょう。

会社側がする従業員退職時の手続き⑥
従業員への書類交付と退職後の最終対応
「従業員の退職手続き」編集部
従業員の退職時における手続きについて、以下のサイトも是非ご覧ください。
「もう悩まない!会社がやるべき従業員の退職手続きを詳しく解説」
従業員の退職後、会社側にはいくつかの重要な書類を本人へ交付する義務があります。この手続きには、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、離職票、退職証明書、そして希望があれば健康保険資格喪失証明書などが含まれます。従業員がすでに出社しない場合を考慮し、会社側は退職前に郵送先住所を確認しておく必要があります。これらの書類(手続き)は、従業員が退職後の生活や再就職活動をスムーズに行ううえで非常に重要なものとなるため、会社側は正確な情報と迅速な対応を徹底しなければなりません。

合わせて読みたい「退職手続きはいつまで」に関するおすすめ記事

退職手続きはいつまでに何をすべき?手続きの流れを解説!
従業員が退職する際に必要な手続きの流れとは
従業員が自己都合で退職を決めた場合、単に会社を去るというだけではなく、段階的かつ多岐にわたる手続きを完了させる必要があります。従業員がスムーズに退職するためには、退職を申し出る段階から最終出社日まで、会社と連携を取りながら、必要な退職手続きを順を追って進めることが不可欠です。従業員自身の負担を減らすと同時に、会社側との信頼関係を維持しながら、トラブルのない退職を実現するためには、正確な手続きへの理解が求められます。
| 時期(目安) | 従業員が行うこと | 会社側とのやり取り内容 | 手続き・書類の内容例 |
|---|---|---|---|
| 1~2か月前 | 上司に退職の意思を伝える | 退職日の相談 合意形成 |
退職の意思表示 スケジュール調整 |
| 1か月前 (または規定) |
退職届(または退職願)の提出 | 人事部または上司へ正式提出 | 退職届に氏名・退職日・理由(「一身上の都合」など)を記入 |
| 引き継ぎ期間 | 業務マニュアル作成 後任者への説明 |
業務の引き継ぎ 関係先への連絡 |
引き継ぎ表・取引先リスト・社内共有資料の整備 |
| 最終出社日 | 会社からの書類受取 備品の返却 |
健康保険証や社員証 PCなどの回収 |
健康保険証、社員証、社用機器、鍵、名刺、作成資料などの返却 |
| 退職日 (または後日) |
郵送での書類受け取り | 書類の郵送や直接交付 | 源泉徴収票 退職証明書 雇用保険被保険者証 離職票 健康保険資格喪失証明書など |
| 退職後 (再就職あり) |
新しい勤務先に必要書類を提出 | 新会社が保険・年金・税金手続き | 雇用保険被保険者証 源泉徴収票 マイナンバー提出 |
| 退職後 (再就職なし) |
各種行政手続き (自分で行う) |
特になし (本人が役所等で申請) |
国保・国民年金の切替 失業保険申請 確定申告 住民税納付手続きなど |
従業員の退職手続きに関するおすすめ記事

従業員が退職する際の会社側と従業員側の手続きについて、以下の記事も是非参考にしてください。
「会社側が行う従業員退職時の雇用保険の手続き|必要書類や流れを解説」
従業員側が行う退職手続き①
【2カ月前】退職の意思表示と退職日調整
従業員が退職を決意したら、まず行うべき手続きは、直属の上司に退職の意思を明確に伝えることです。従業員は、法律上は退職の意思を伝えてから2週間後には退職することが可能ですが、実務上は1か月前、あるいは2か月前を目安に退職を申し出るケースが一般的です。これは、従業員の退職に伴って後任者の配置や引き継ぎ業務といった会社側の社内手続きも発生するためです。
従業員の退職手続きに関するポイント!

退職日をめぐっては、従業員と会社側の双方で話し合い、業務への影響を最小限に抑える形で日程を確定します。
この意思表示も、退職手続きの第一歩として非常に重要であり、従業員にとっても会社にとっても納得のいく日取りを設定するための調整が必要です。
従業員側が行う退職手続き②
【1か月前】退職届を提出し、従業員としての引き継ぎ

合わせて読みたい「退職手続きのチェックリスト」に関するおすすめ記事

【チェックリスト付き】退職手続きの一連の流れと必要な手続きを解説!
退職日が確定した後、従業員は正式な退職届を会社へ提出します。
「従業員の退職手続き」編集部
この退職届の提出も、従業員にとって重要な退職手続きのひとつです。
退職届は就業規則で提出が定められている場合があり、会社によってはフォーマットを指定していることもあります。従業員は、氏名、提出日、退職日、退職理由(通常は「一身上の都合」)などを記入し、上司あるいは人事部門に提出することで、退職の意思を正式に表明します。

退職届を提出した後、従業員は業務の引き継ぎに入ります。引き継ぎは、業務継続性を保つために不可欠な退職手続きであり、従業員がこれまで担当していた内容をマニュアル化したり、後任者への説明を行ったりするなどして、スムーズな退職を目指します。業務の引き継ぎも従業員の退職に関する重要な内部手続きの一部といえるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
従業員側が行う退職手続き③
【最終出社日】退職書類の受け取りと備品の返却
従業員の最終出社日は、退職前に完了すべき各種手続きが集中するタイミングです。この日までに従業員は、会社から貸与されていた備品や書類などをすべて返却しなければなりません。返却すべき対象には、健康保険証(扶養分含む)、社員証、社用パソコン、業務資料、社内デバイス、制服、鍵などがあります。従業員は漏れのないよう返却リストをもとに準備を進め、会社との最終的な確認を行います。
「従業員の退職手続き」編集部
従業員の退職時における手続きについて、以下のサイトも是非ご覧ください。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「会社側の退職手続きの流れとは?チェックリストと注意点も紹介」
また、従業員が退職後に必要となる書類の受け取りも、このタイミングで進められます。会社側から従業員に交付される主な書類には、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、離職票、退職証明書、健康保険資格喪失証明書(希望者のみ)などがあります。これらの書類は、退職後の各種手続きで必要不可欠となるため、従業員は内容と発行予定日を確認しておくことが重要です。
従業員の退職手続きに関するポイント!

なかには後日郵送となる書類もあるため、従業員は退職前に受け取り方法についても明確にしておく必要があります。
退職後の手続き
従業員が退職した後も、必要な手続きは継続します。再就職先がある場合は、従業員が新たな勤務先に健康保険証やマイナンバー、雇用保険被保険者証などを提出することで、新会社が保険や年金の取得手続きを行います。また、源泉徴収票をもとに新しい会社で年末調整が行われるなど、従業員は引き続き会社を介して税務・保険手続きに関与することになります。
従業員の退職手続きに関するおすすめ記事

従業員が退職する際の会社側と従業員側の手続きについて、以下の記事も是非参考にしてください。
従業員の退職手続きに関する参考記事:「会社側の退職手続きは何日以内?13項目のチェックリスト付きガイド」
一方で、従業員が退職後にすぐ再就職しない場合は、従業員自身が直接行う手続きが多く発生します。たとえば、国民健康保険への加入、国民年金への切り替え、ハローワークでの失業給付申請、確定申告などがその代表です。これらの手続きには、各行政機関(市区町村役所・年金事務所・ハローワーク・税務署)での対応が必要となり、従業員は退職後のスケジュールに余裕をもって準備を進める必要があります。
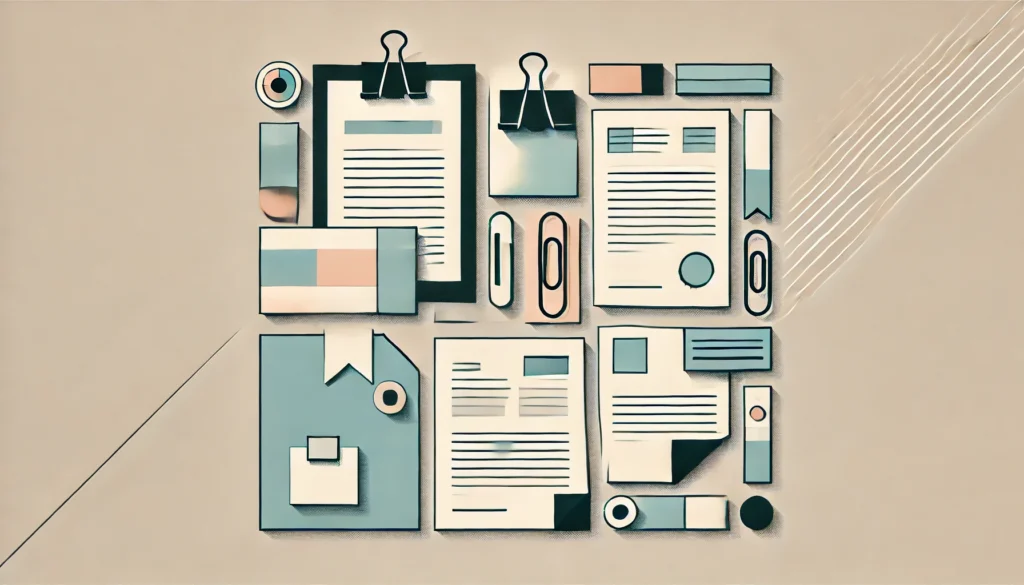
「従業員の退職手続き」編集部
従業員が退職した後にミスなく生活を再構築するためには、これらの手続きを正確かつ期限内に完了させることが非常に重要です。
退職後の生活設計に直結する各種手続きを把握し、必要書類を適切に管理することも従業員の大切な責任の一部です。
まとめ|従業員の退職手続き
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
従業員が退職する際には、従業員本人と会社側の両方において、数多くの退職手続きが発生します。退職の意思表示から始まり、退職届の提出、業務の引き継ぎ、備品の返却、書類の受け取りなど、すべてが退職手続きの一部です。さらに、社会保険や雇用保険、年金、税金に関する各種の行政手続きも加わり、従業員は退職前から退職後にかけて継続的に手続きを行う必要があります。
とくに重要なのは、従業員自身が退職手続きの流れを事前に把握し、手続きの期限や必要書類を正確に理解しておくことです。退職手続きには、健康保険の資格喪失手続きや年金の切り替え手続き、雇用保険の資格喪失手続き、離職票の申請手続き、源泉徴収票の受取手続きなど、多岐にわたる手続きが関係します。これらの手続きは、いずれも従業員の退職後の生活に直結するものであり、一つでも漏れがあるとトラブルにつながる可能性があります。
会社側も、退職に伴う手続きを正確に実行する責任があります。従業員の退職に関する各種届出や証明書の発行など、社内外の手続き業務を滞りなく処理することが、信頼される企業運営につながります。退職手続きは、単なる形式的な処理ではなく、従業員との関係性を円満に締結するための重要な手続きであるといえるでしょう。
退職に関する手続きを従業員も会社も正しく理解し、すべての退職手続きをスムーズかつ確実に完了させることが、安心して新たなステージへ進むための第一歩です。この記事を通じて、従業員の退職手続きを網羅的に把握し、抜け漏れのない万全の手続き対応を目指しましょう。
従業員の退職手続きに関するおすすめ記事

従業員が退職する際の会社側と従業員側の手続きについて、以下の記事も是非参考にしてください。
「退職までに必要な手続きは?従業員側と会社側の流れと必要書類を解説」
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドとの違いを徹底比較!ビジネスオーナーズ ゴールドを持つメリットとは
-
ビジネスカード

2026年1月29日
2
三井住友カードビジネスオーナーズ2枚持ちのメリットは?2枚持ちにおすすめの個人カードや選び方も紹介
-
ビジネスカード

2026年1月29日
3
三井住友ビジネスオーナーズのメリット・デメリットとは?ゴールドとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月29日
4
三井住友ビジネスオーナーズゴールドのメリットは?一般カードやfor Ownersとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月29日
5
即日ファクタリング来店不要おすすめ15選!選び方から注意点まで徹底解説
-
資金調達

2026年1月24日













SoVaをもっと知りたい!