有給休暇の付与条件とは?条件別の付与日数や計算方法を解説!
カテゴリー:
公開日:2025年4月
更新日:2025年11月5日
有給休暇の付与日数は、労働者の勤続年数や勤務条件によって変わります。フルタイム労働者の場合、入社から半年が経過すると「有給休暇」として10日が付与され、その後の継続勤務年数に応じて有給休暇の日数も増えていきます。パート・アルバイト労働者の場合は、継続勤務年数に加えて、所定労働日数という条件によっても有給休暇の付与日数が変動します。
また、有給休暇の付与条件や基準日が異なる従業員が多い企業では、有給休暇の管理が煩雑になりやすい傾向があります。そのため、適切に有給休暇を付与するには、有給休暇のルールや条件を正しく理解することが重要です。
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事
さらに、有給休暇は年5日の取得が義務化されており、企業は有給休暇の取得状況を正確に管理する必要があります。適切な有給休暇の付与と管理を行うために、有給休暇の付与日数やその条件について、この記事で基本的な知識をしっかり身につけましょう。
給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
有給休暇とは
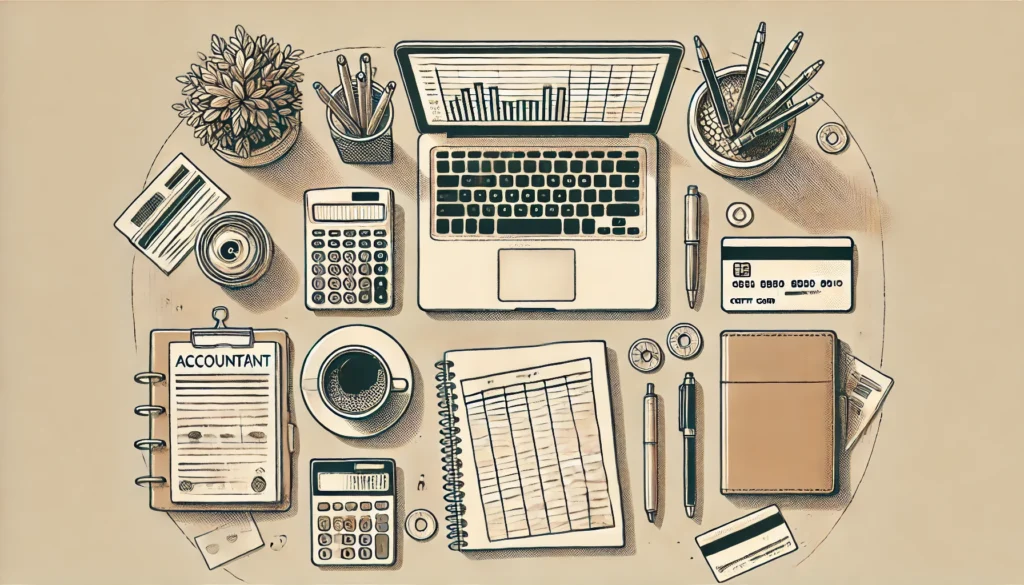
有給休暇とは、一定の条件を満たした労働者に対して、「有給」での休暇を付与する制度のことです。有給とは、すなわち「給与が支払われる」という意味であり、有給休暇を取得した労働者には、その期間の給与が支払われます。
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事
有給休暇は、1年ごとに一定の条件を満たした場合に所定の日数が付与されることから、「年次有給休暇」と呼ばれます。一般には「有給休暇」や「有休」などの略称で広く認識されています。年次有給休暇制度は労働基準法によって定められており、企業は労働者が要件を満たせば、有給休暇を付与する義務があります。
SoVa税理士ガイド編集部
通常、労働時間に応じて給与が支払われる「ノーワーク・ノーペイの原則」がありますが、有給休暇についてはこの原則が適用されず、休暇を取得しても給与が支払われる仕組みになっています。
有給休暇が付与されるための条件や具体的な要件については、次の段落で詳しく解説します。

合わせて読みたい「給与計算 方法」に関するおすすめ記事

給与計算方法まとめ!正確な給与計算方法を詳細に解説します
有給休暇の付与条件
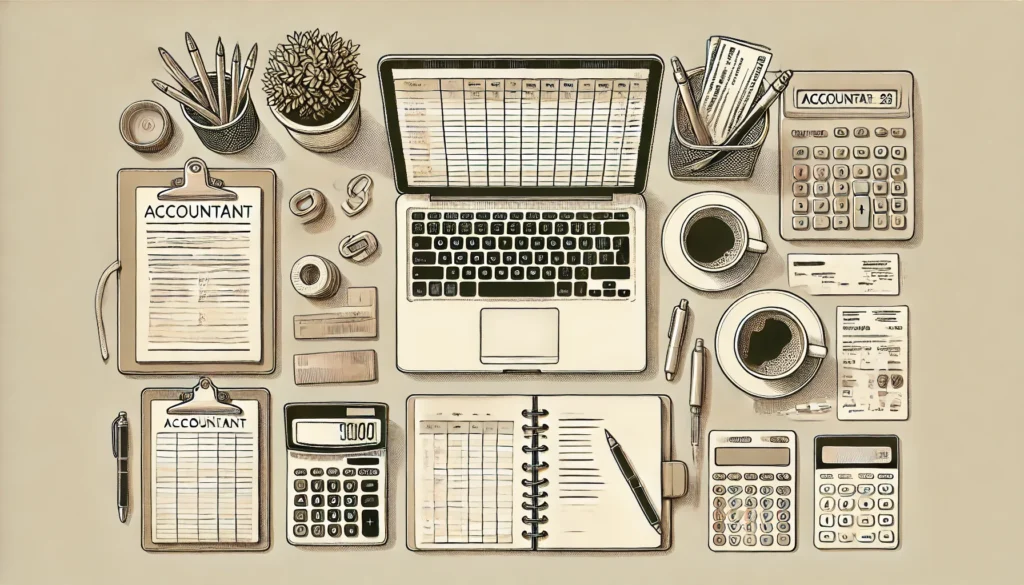
年次有給休暇は、すべての労働者に無条件で付与されるわけではなく、有給休暇を取得するためには一定の条件を満たす必要があります。労働基準法第39条に基づき、以下の条件を満たした労働者に対して年次有給休暇が付与されます。
年次有給休暇の付与条件
- 条件①:雇い入れ日から6カ月以上継続勤務していること
- 条件②:雇い入れ日から6カ月以上継続勤務し、かつ総労働日の8割以上を出勤していること
SoVa税理士お探しガイド編集部
有給休暇の付与条件についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです!
有給の付与条件に関するおすすめ記事:有給休暇とは?付与日数や計算方法、繰越保持日数の上限について解説
例えば、新卒社員の場合、入社から半年が経過し、出勤率が8割以上であれば有給休暇が付与されます。ただし、8割未満の出勤率だった場合、その期間の有給休暇は0日となるため、病気やその他の理由で長期欠勤した際は注意が必要です。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
なお、一度出勤率が8割未満になったからといって、その後ずっと有給休暇が付与されないわけではありません。有給休暇は毎年、出勤率が8割以上であるかどうかを基準に付与の判断がされる仕組みになっています。そのため、継続勤務をしている限り、翌年以降も有給休暇を取得できる可能性があります。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」
有給の付与条件に関するここがポイント!

また、有給休暇の付与条件を満たしているかどうかを判断する際、出勤としてカウントされる日とされない日があります。
労働者自身も人事労務担当者も、有給休暇の適正な処理を行うために、以下のルールを確認しておきましょう。
出勤としてカウントされる日の条件
- 有給休暇を取得した日
- 遅刻や早退をした日
- 介護休業を利用した日
- 育児休業を利用した日
- 業務上のけがや病気による休業日
- 労働基準法65条に基づき、産前・産後に休業した日
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事:年次有給休暇とは?付与日数・権利発生条件・計算方法など徹底解説
出勤としてカウントされない日の条件
- 会社(使用者)都合で休業した日
- 正当なストライキで休業した日
- 休日出勤した日
有給休暇の付与条件を正しく理解し、適切に管理することで、有給休暇をスムーズに取得できるようにしましょう。

合わせて読みたい「 給与支払事務所等の開設届出書の提出」に関するおすすめ記事

給与支払事務所等の開設届出書の提出は不要?給与支払事務所等の開設届出書の書き方や記載例も解説
【状況別】有給休暇の付与日数条件
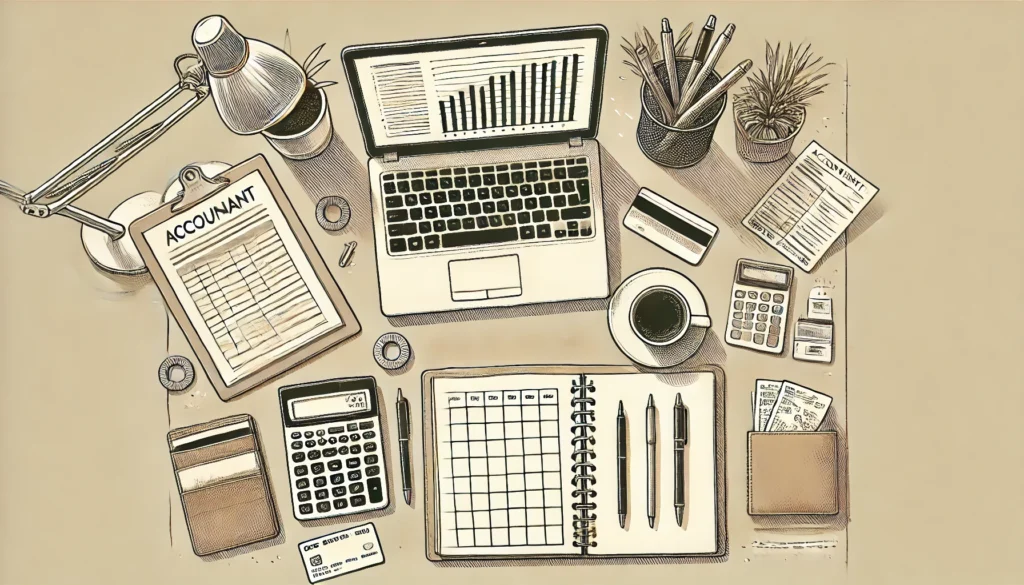
有給休暇の付与日数や制度は、労働者の立場や勤務条件によって異なります。正社員、パート・アルバイト、休業者といったそれぞれの条件ごとに、有給休暇の仕組みを詳しく見ていきましょう。
「会社設立後の役員報酬」編集部
会社設立後の役員報酬はいつから支払うべきなのかについては、以下のサイトも是非ご覧ください!
「 会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説 」

合わせて読みたい「36協定の残業時間の上限」に関するおすすめ記事

36協定の残業時間の上限は月45時間?80時間?規制や罰則について解説
正社員の有給休暇の条件
週5日以上フルタイムで働く正社員には、有給休暇が一定の条件のもとで付与されます。入社から半年後に10日、その後、1年ごとに11日、12日と増えていき、6年6ヵ月以上の勤務で年間20日の有給休暇が付与されます。
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事
なお、派遣社員や契約社員、準社員などの雇用形態であっても、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じ条件で有給休暇が付与されます。
有給付与の条件に関する気をつけておきたい注意点

ただし、派遣社員の場合は、派遣先企業ではなく、派遣元の派遣会社が有給休暇の管理や付与を行うため、制度の違いに注意が必要です。
パート・アルバイトの有給休暇の条件
パート・アルバイトなどの短時間勤務の労働者も、週の所定労働時間や年間の所定労働日数に応じた有給休暇が付与されます。有給休暇が付与される条件は正社員と同様で、以下のように勤務日数に応じた有給休暇の日数が決まります。
役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
- 週1日勤務:半年後に1日
- 週2日勤務:半年後に3日
- 週3日勤務:半年後に5日
- 週4日勤務:半年後に7日
- 週5日勤務:半年後に10日
また、週の所定労働日数が3日の場合は5年6ヵ月以上、4日の場合は3年6ヵ月以上勤務すると、有給休暇の付与日数が10日になります。これは「年間10日以上の有給休暇が付与される」条件を満たすため、企業側には「年間5日の有給休暇を取得させる義務」が発生します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
パート・アルバイトの労働者も、自身の有給休暇が適切に消化されているかをしっかり確認しましょう。
育児・介護休業中の労働者の有給休暇の条件
育児休業や産前産後休業、介護休業中の労働者は、実際には出勤していませんが、有給休暇の判定上は出勤したものとみなされます。
有給付与の条件におけるここがポイント!

そのため、育児休業から復帰した労働者に有給休暇を付与する際、休業期間中に一切出勤していなかったとしても、全日出勤したとみなして有給休暇を付与しなければなりません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
勤怠管理に関連してフレックスタイム制については、【 アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説! 】の記事も是非ご覧ください。
例えば、勤続年数7年の社員が育児休業から復帰する場合、20日間の有給休暇が付与されます。なお、病気やケガによる休職の場合、業務上の病気やケガ(労災)での休業であれば、出勤扱いとして有給休暇の付与が行われます。一方、業務外の病気やケガによる休職の場合は、本人の都合や会社の規定によって有給休暇の付与対象となるかどうかが判断されるため、会社の規則を確認しておくことが重要です。

合わせて読みたい「新入社員の有休」に関するおすすめ記事

新入社員の有給はいつ・何日付与すべき?有給のルールや注意点を解説!
本記事では、新入社員の有給が発生する条件や付与日数、分割付与の注意点などを詳しく解説します。新入社員の有給を適切に管理し、円滑な職場環境を整えるために、ぜひ参考にしてください。
有給休暇の付与条件をしっかり理解し、適切に管理することで、正社員・パート・アルバイト・休業者問わず、有給休暇を正しく取得できるようにしましょう。
給与計算に関する参考記事:「寡婦控除とは?適用条件や申告方法、ひとり親控除との違いについても解説!」
【条件別】有給休暇の給与計算方法
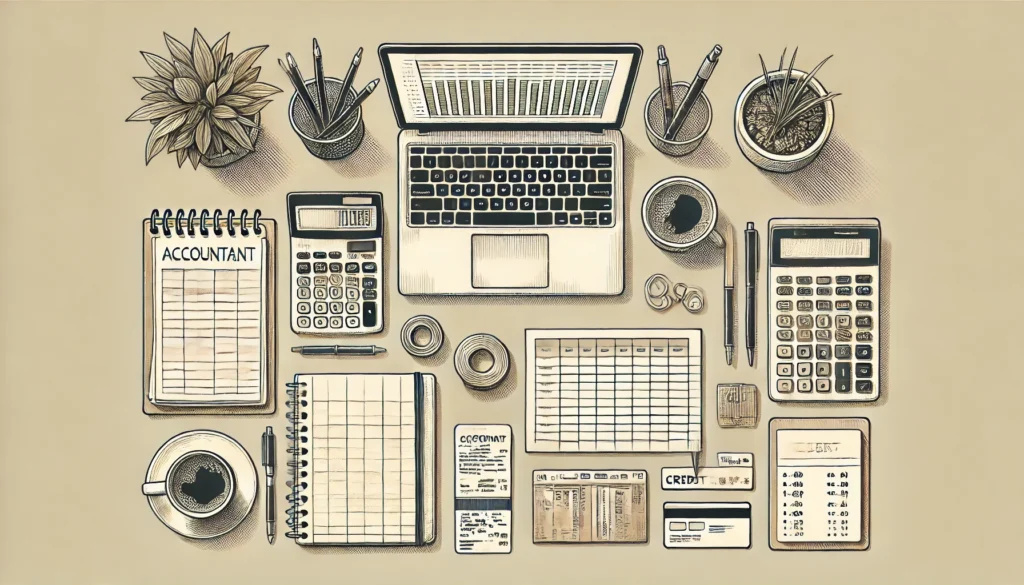
年次有給休暇を取得する際に気になるのが、有給休暇取得日における賃金の計算方法です。有給休暇を取得した場合、どのような条件で賃金が支払われるのかを確認しておきましょう。
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事
有給休暇中の賃金計算方法は、基本的に以下の3つの方法で対応されます。どの計算方法が適用されるかは、企業の就業規則や労働契約の条件によって異なります。
有給休暇取得時の賃金計算の条件①:通常勤務分で計算する
この計算方法では、有給休暇を取得した場合でも通常の勤務と同様の賃金が支払われます。特に月給制の正社員であれば、有給休暇を取得しても固定給が変わらないため、給与計算がシンプルです。

合わせて読みたい「新入社員の入社手続き」に関するおすすめ記事

新入社員の入社手続きで必要な準備は?必要書類や具体的な手続き内容を解説!
パート・アルバイトの場合は、「時給 × 所定労働時間」 の計算式で有給休暇取得日の賃金が決まります。有給休暇を取得しても、その日の所定労働時間分の給与が支払われるのが特徴です。
有給休暇取得時の賃金計算の条件②:通常勤務分で計算する平均賃金で計算する
有給休暇取得日の賃金を平均賃金 で計算する方法もあります。労働基準法第12条では、平均賃金の算出方法として以下の2つの条件を定めており、どちらか高い方の金額が適用されます。

合わせて読みたい「アルバイトに有休を付与」に関するおすすめ記事

アルバイトの有給付与の条件は?賃金の計算方法についても解説!
この記事では、アルバイトやパートに対する有給付与の詳細や、有給休暇取得時の賃金計算方法、さらに有給付与に関する注意点について詳しく解説します。アルバイトの有給付与に関する正しい知識を身につけ、適切な運用を行いましょう。
平均賃金の計算方法
直近3カ月の賃金総額 ÷ その期間の歴日数(カレンダーの日数)
直近3カ月の賃金総額 ÷ その期間の労働日数 × 0.6
算出された平均賃金に、有給休暇の日数を掛けた金額がその月の賃金として支払われます。この方法は、時給制や日給制の労働者にも適用できるため、さまざまな雇用条件の労働者に対応できる計算方法といえます。
有給休暇取得時の賃金計算の条件③:通常勤務分で計算する標準月額報酬で計算する
標準月額報酬を基準にして、有給休暇取得時の賃金を計算する方法もあります。標準月額報酬 とは、健康保険料や厚生年金保険料の計算に用いられる基準で、給与の月額を一定の区分ごとに分けたものです。この標準月額報酬を日割りした標準日額報酬 を、有給休暇取得日の賃金として支払います。
給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
SoVa税理士ガイド編集部
有給休暇の賃金計算方法は、企業ごとのルールや労働契約の条件によって異なるため、事前に自身の労働契約や就業規則を確認し、どの計算方法が適用されるのかを把握しておくことが重要です。
有給休暇の付与条件ついてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もすすめです。
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事:有給休暇のルールとは?福利厚生や人材確保につながるメリットを解説
有給付与条件に関する注意点
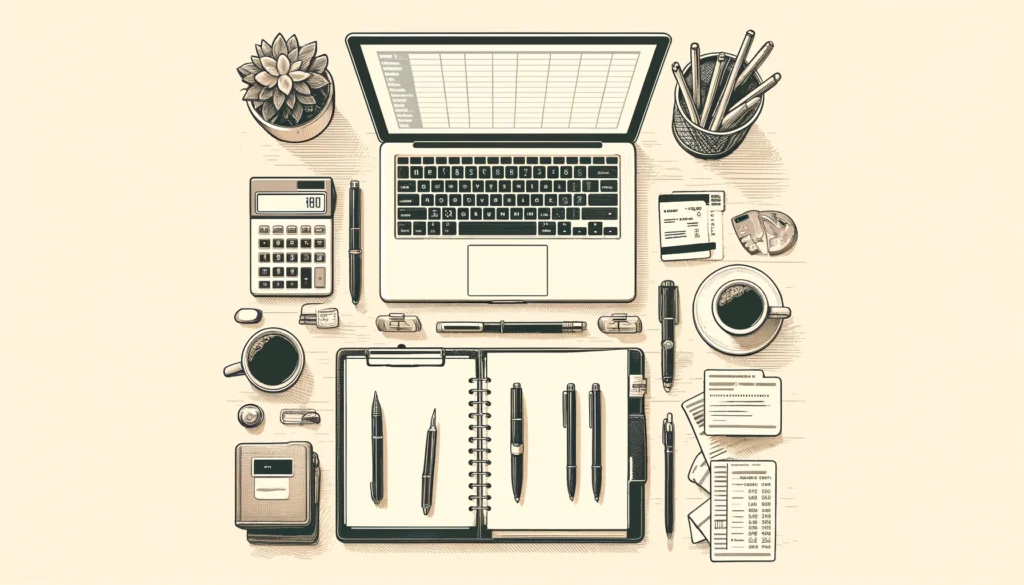
労働者の有給休暇取得に関しては、さまざまな条件や注意点があります。ここでは、有給休暇を翌年以降に繰り越す際のルールや、半休・時間単位の有給休暇の条件、さらに有給休暇の規定に違反した場合の罰則について詳しく解説します。

合わせて読みたい「固定残業代のメリット・デメリット」に関するおすすめ記事

固定残業代とは?労働者と企業それぞれのメリットデメリットや注意点も解説!
この記事では、固定残業代の基本的な仕組みから、企業・労働者それぞれのメリット・デメリット、導入時の注意点まで、わかりやすく解説します。
有給付与条件に関する注意点①:有給休暇の繰り越しと有効期限の条件
週5日以上勤務する労働者には、毎年10日から20日の有給休暇が付与されます。
SoVa税理士ガイド編集部
未消化の有給休暇がある場合でも、条件を満たせば、付与日から2年間は繰り越して使用することが可能です。
企業側が一方的に繰り越しを認めず、有給休暇を無効にすることはできません。
<有給休暇の繰り越し例>
- 2021年10月1日:12日分の有給休暇を付与 → 5日間の有給休暇を使用(残日数7日)
- 2022年10月1日:14日分の有給休暇を付与 → 5日間の有給休暇を使用(残日数7日+14日-5日=16日)
- 2023年10月1日:16日分の有給休暇を付与(残日数32日。ただし、2021年10月付与分の残り2日は有効期限切れで失効)
なお、就業規則によって有給休暇の有効期限を2年以上に延長することも可能です。
有給付与条件に関する注意点②:半休・時間単位の有給休暇の条件
有給休暇は通常1日単位で取得しますが、就業規則に規定があれば、半日単位や時間単位で取得することも可能です。ただし、半日・時間単位の有給休暇の運用は企業ごとに異なり、導入していない企業では取得できません。
半休については法律上の規定はなく、企業の就業規則によって自由に定めることができます。一方、時間単位の有給休暇には以下のような条件があります。
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事:有給休暇の労働基準法における定義|付与日数や取得義務化など法律を解説
<時間単位の有給休暇の条件>
- 導入には労使協定を結ぶ必要がある
- 有給休暇を時間単位で取得できる対象者、取得可能日数、1日分が何時間に相当するか、1時間単位以外の扱いなどを就業規則に明記する
- 年間5日間の有給休暇取得義務には含まれず、時間単位の取得とは別に5日以上の有給休暇を取得させる必要がある
- 時間単位の有給休暇として取得できるのは年間5日分以内
有給付与条件に関する注意点③:有給休暇付与・取得義務違反の罰則
労働基準法第39条では、有給休暇に関する条件や規定が明確に定められています。以下のような有給休暇に関する義務は、すべて法律で決まっているため、企業はこれに違反しないよう注意が必要です。
- 労働者に対して有給休暇を付与しなければならない
- 有給休暇の付与日数は労働条件に応じて決められている
- 年間10日以上の有給休暇が付与された労働者には、最低5日以上の有給休暇取得を企業が確実に実施しなければならない
これらの規定に違反すると、以下の罰則が適用されます。
- 5日以上の有給休暇を取得させなかった場合:30万円以下の罰金
- その他の労働基準法第39条違反:使用者に対して最大6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事
さらに、理論上は「1人の労働者に対する違反が1つの違反」となるため、複数の労働者に対して違反があった場合、その分だけ罰則が科される可能性があるため注意が必要です。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
まとめ

今回は、有給休暇の付与条件や仕組みについて詳しく解説しました。
有給休暇は労働基準法により定められており、有給休暇を付与する条件として「雇い入れ日から6ヵ月継続勤務し、出勤率が8割以上」という基準が設けられています。この条件を満たした労働者には有給休暇が付与され、最初の有給休暇の付与は入社から半年後に行われます。その後は、最初の付与日(基準日)を起点として1年ごとに付与日数が増えていきます。
有給休暇の付与条件に関するおすすめ記事
また、有給休暇を付与するタイミングについては、労働者の不利益にならない範囲で前倒しすることも可能です。
有給付与の条件に関する気をつけておきたい注意点

ただし、前倒しで有給休暇を付与した場合、その基準日が変更されるため、今後の有給休暇の付与条件に影響が出る点に注意が必要です。
適切な有給休暇の付与が行われない場合、企業は違法とみなされ、罰則が科される可能性があります。有給休暇の付与日数や基準日を正しく把握し、適切に管理することが重要です。

合わせて読みたい「給与計算 注意点 (税理士)」に関するおすすめ記事

給与計算の注意点は?税理士に丸投げするメリットについても紹介
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!