経営セーフティ共済で節税できる?デメリットやメリットも解説!
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2026年1月23日
経営セーフティ共済は、中小企業や個人事業主が倒産リスクに備えるための制度ですが、同時に強力な節税効果が得られる節税対策ツールとしても注目を集めています。実際に、経営セーフティ共済の掛金は全額を損金または必要経費に算入できるため、節税目的で経営セーフティ共済に加入するケースが増加しています。
しかし、節税だけを目的に経営セーフティ共済を活用すると、思わぬデメリットに直面することも。たとえば、短期解約による掛け捨てや元本割れ、解約手当金への課税など、節税効果が帳消しになるデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
この記事では、経営セーフティ共済でどれだけ節税ができるのか、節税効果を最大化する方法は何か、さらに節税に潜むリスクやデメリットについても詳しく解説します。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
節税のために経営セーフティ共済を検討している方、すでに加入しているけれど運用に迷っている方は必見です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
創業融資が受けられるか、今すぐチェック!
簡単シミュレーションで融資額を診断

画像引用:「創業融資額診断シミュレーション」
「創業融資を受けたいけど、自分は通るの?」
「どれくらいの金額を借りられるか知りたい!」
そんな疑問をお持ちの方は、「創業融資シミュレーション」がおすすめです!
✔ アンケートに答えるだけで、融資額&審査通過率がすぐに分かる!
✔ 無料で何度でも気軽にシミュレーション可能
✔ 創業期に融資を検討している方に最適
「申し込む前に、どれくらい借りられるのか知りたい…」そんな方は、まずはシミュレーションで融資の可能性をチェックしましょう!
※シミュレーション結果をもとに専門家への無料相談も可能です

経営セーフティ共済とは?節税効果も期待できる中小企業の倒産リスク対策制度
「経営セーフティ共済」とは、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といい、万が一、取引先企業が倒産した場合の資金繰り悪化を防ぐために、中小企業向けに設計された共済制度です。「経営セーフティ共済」という名称は通称で、制度は独立行政法人中小企業基盤整備機構によって運営されています。
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「経営セーフティ共済とは?節税効果やメリット・デメリットを紹介」
中小企業は大企業と異なり、限られた取引先に依存しているケースが多く、一社の倒産によって連鎖的に自社が経営危機に陥るリスクが高いのが実情です。経営セーフティ共済は、こうしたリスクに備えるための仕組みとして設けられており、加入企業間で支え合う「相互扶助」の考え方に基づいています。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
経営セーフティ共済の具体的な内容

経営セーフティ共済に加入すると、取引先の倒産時に無担保・無保証人での貸付制度が利用可能になります。これにより、突然の売掛金回収不能などによる資金ショートを回避し、連鎖倒産のリスクから会社を守ることができます。
そして、経営セーフティ共済の大きな魅力は、節税効果が非常に高い点です。掛金は月額5,000円から20万円まで設定でき、支払った掛金は全額が損金算入可能となっています。つまり、利益が出た年度に掛金を拠出することで、法人税の節税対策として大いに活用できるのです。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
この節税メリットは、事業規模にかかわらず、多くの中小企業にとって有効であり、「節税しながら倒産リスクにも備えられる」という一石二鳥の制度として注目されています。
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?掛金や、加入資格、メリット・デメリット」
経営セーフティ共済の加入状況と他制度との違い
経営セーフティ共済は、令和5年(2023年)3月末時点で、全国で約62万件の中小企業が加入している信頼性の高い制度です。経営リスク管理と節税対策の両面から、年々加入者数が増加しています。
また、「小規模企業共済」という類似名称の制度もありますが、こちらは経営者個人の退職金準備を目的としたもので、目的が異なります。経営セーフティ共済と小規模企業共済は、併用も可能であり、双方の加入要件を満たすことで、企業経営と経営者個人の将来の両方に備えることができます。
経営セーフティ共済の節税効果
経営セーフティ共済は、万が一の取引先倒産に備える共済制度であると同時に、非常に高い節税効果を発揮する節税対策制度でもあります。最大のポイントは、支払った掛金が全額、経費として処理できる点にあります。
法人が経営セーフティ共済に加入した場合、掛金は全額が損金算入可能となり、法人税の節税につながります。個人事業主であれば、掛金は必要経費として扱われるため、所得税や住民税、さらには事業税の節税にもなります。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
つまり、経営セーフティ共済に加入すること自体が、直接的な節税手段になるというわけです。
例えば、毎月10万円の掛金を設定した場合、年間で120万円を損金または経費にでき、それにより大幅な節税効果が期待できます。黒字が多く出た年ほど税負担が大きくなるため、利益が大きい年度に掛金を増額することで、節税効果を最大化できるのです。
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「経営セーフティ共済の節税効果と手続きを税理士が解説!」
経営セーフティ共済の節税効果①
節税を意識した経営者にこそ、経営セーフティ共済が選ばれる理由
節税を強く意識する中小企業経営者や個人事業主にとって、経営セーフティ共済は非常に効果的な節税ツールです。従来のように現金を手元に残しておく、あるいは定期預金で資金を保管しておく方法では、税金対策にはなりません。現金を保有していても節税にはつながらず、資金効率も悪くなります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
無借金経営のデメリットについては、【無借金経営のデメリットとは?無借金経営のメリット・実質無借金経営についても解説!】 の記事も是非参考にしてください。
それに対して、経営セーフティ共済は、掛金を支払うことで資金の保全と節税の両立が可能です。支払った掛金は、即時に経費として認められるため、現金を寝かせるよりも圧倒的に節税メリットが高いのです。
経営セーフティ共済の節税効果に関するポイント!

たとえば、月10万円の掛金を支払えば、年間で120万円もの支出が節税対象となり、高額な税負担を直接的に軽減できます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
この節税メリットは、資金をただ貯めるだけでは得られないものです。現金を手元に置いておくだけでは税金は減りませんが、経営セーフティ共済なら、資金を動かしながら節税を実現できます。つまり、「資金活用+節税」の両立が可能なのです。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて以下のサイトも是非ご覧ください。
「経営セーフティ共済の8つのデメリットとメリットを解説!」
さらに、万が一のときには掛金の10倍まで無担保・無保証での貸付が受けられ、資金繰りを支える制度にもなっています。つまり、節税効果と経営リスク対策を同時に実現できるのが、経営セーフティ共済最大の特徴です。
経営セーフティ共済の節税効果②
前納による節税効果の強化も!賢く使えば節税インパクトはさらに大きく
節税をさらに高めたい方には、掛金の前納制度もおすすめです。経営セーフティ共済では将来の掛金を前もって支払うことができ、特にそのうち1年以内分は当期の経費として処理可能。この制度を使えば、利益が多く出た年度にまとめて前納して一気に節税、という高度な節税戦略も実行できます。
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「経営セーフティ共済、2024年10月改正へ 「裏ワザ」の節税にメス」
節税を意識するなら、資金に余裕のあるタイミングでの前納は非常に有効です。節税によるキャッシュフローの最適化を狙う経営者にとって、経営セーフティ共済は節税を計画的に行うための戦略的制度といえるでしょう。
このように、経営セーフティ共済の掛金の扱い方次第で、節税効果の大きさを柔軟に調整できる点も、経営者から高く評価される理由の一つです。

経営セーフティ共済の節税効果③
節税額の試算例|数字で見る経営セーフティ共済の節税メリット
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
では、実際にどれくらいの節税効果があるのか、具体的に見てみましょう。
たとえば、課税所得が500万円の個人事業主が年間60万円を経営セーフティ共済に支払った場合、次のような節税効果が見込まれます。
- 所得税・復興特別所得税:20.42%
- 住民税:10%
- 個人事業税:5%(業種により異なる)
合計で約35.42%の税率軽減となり、節税額はおよそ21万円にものぼります。これは、資金を預金しているだけでは得られない、非常に大きな節税メリットといえるでしょう。

合わせて読みたい「法人税・法人事業税・法人住民税の違い」に関するおすすめ記事

法人税・法人事業税・法人住民税の違いとは?計算方法や課税対象、納付先まで詳細解説!
経営セーフティ共済の節税効果④
解約時の注意点と節税との関係
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
「倒産防止共済とは?メリット・デメリットを徹底解説(経営セーフティ共済)」
節税目的で経営セーフティ共済を利用する際には、解約時に返戻金が発生し、それが課税対象になることにも注意が必要です。これは、節税の繰延べ(タイミング調整)という考え方に近く、その時期を調整することで、トータルで見れば節税効果を維持することが可能です。
経営セーフティ共済の節税効果に関するポイント!

解約のタイミングを業績の悪い年にずらすなどの工夫をすれば、節税効果を損なわずに返戻金を受け取ることができます。
節税だけでなく、その後の税務戦略も見据えることで、経営セーフティ共済の恩恵を最大限に引き出せます。
節税を真剣に考える経営者・個人事業主にとって、経営セーフティ共済は欠かせない節税ツールです。掛金を経費にして節税、前納で節税、貸付制度でリスク回避、返戻金を活用して長期的な節税――あらゆる場面で節税という観点から有利に働く制度なのです。

合わせて読みたい「信用保証協会」に関するおすすめ記事

信用保証協会とは?わかりやすく解説!信用保証協会のすべて
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
節税対策を検討中なら、まずはこの制度の活用から始めてみてはいかがでしょうか?経営セーフティ共済で節税、そして安定した経営の未来を築きましょう。
2024年10月からの制度改正|経営セーフティ共済の節税利用に制限
経営セーフティ共済は、取引先倒産への備えと同時に、高い節税効果が得られる制度として、多くの中小企業・個人事業主に活用されてきました。経営セーフティ共済の掛金は、法人であれば損金、個人であれば必要経費に算入できるため、非常に強力な節税ツールとされてきたのです。

合わせて読みたい「日本政策金融公庫の信用情報」に関するおすすめ記事
日本政策金融公庫は信用情報を見ない?信用情報はどこまで調べるのかまで徹底解説!

日本政策金融公庫に関するおすすめ記事

日本政策金融公庫の面談で聞かれる質問については以下の記事がおすすめです。
参考記事:「 日本政策金融公庫の面談でよく聞かれる質問は?回答のポイントを解説! 」
しかし、2024年10月以降、経営セーフティ共済の節税利用に関して大きな変更が加えられます。具体的には、2024年10月1日以降に一度共済を解約し、その後すぐに再加入した場合、再加入から2年間の掛金は損金・必要経費にできなくなるという制限が導入されるのです。
この変更は、短期での解約と再加入を繰り返し、節税目的で掛金を一気に支出していたケースが増えたことへの対応策です。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて以下のサイトも是非ご覧ください。
「中小企業倒産防止共済 解約のタイミングと手続き方法や注意点(経営セーフティ共済)」
経営セーフティ共済を節税目的で使っていた場合は要注意!
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
これまで、経営セーフティ共済を節税目的で活用していた企業の中には、3~4年で解約し、100%の解約手当金を受け取り、さらにすぐに再加入するという方法で節税効果を最大化していた事例が多く見られました。

「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
実際、2011年に経営セーフティ共済の積立限度額が320万円から800万円に引き上げられて以降、節税メリットを重視した加入が急増しています。
このような動きに対し、中小企業庁は「制度本来の趣旨を逸脱している」とし、経営セーフティ共済の節税目的だけの利用に歯止めをかける改正を行うに至ったのです。

合わせて読みたい「日本政策金融公庫」に関するおすすめ記事

日本政策金融公庫からの運転資金融資の目安は?ポイントや注意点を解説!
経営セーフティ共済の節税効果は今後も有効?改正後の活用ポイント
今回の改正により、短期での節税目的の再加入は難しくなりますが、経営セーフティ共済の節税効果自体が失われるわけではありません。
現行制度では、経営セーフティ共済の掛金を支払うだけで、即座に損金や必要経費として処理できる節税効果があり、これは通常の貯蓄や資金確保では得られない節税メリットです。
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「経営セーフティ共済(倒産防止共済)を利用した駆け込み節税とは?決算期に加入する注意点、制度の概要も紹介」
今後は、経営セーフティ共済を「本来の目的」である倒産リスクへの備えとして活用しつつ、結果的に節税にもなるという“自然な活用”が推奨されるようになります。

合わせて読みたい「スタートアップの資金調達」に関するおすすめ記事

スタートアップの資金調達方法とは?シリーズAやシード期などの投資ラウンドも紹介
なぜ改正された?経営セーフティ共済の節税スキームへの警鐘
中小企業庁が発表した資料によれば、経営セーフティ共済を節税目的で利用することを推奨するWebサイトやYouTube、書籍が急増しており、それらが解約→再加入→節税というスキームを指南していたことが、制度改正の背景にあります。
経営セーフティ共済の節税効果に関する注意点

「節税だけを目的とした経営セーフティ共済の利用」は、制度の信頼性を損なうとして、今後は制限される流れが加速しています。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて以下のサイトも是非ご覧ください。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「経営セーフティ共済で節税できる!加入方法から注意点まで徹底解説します」
節税だけでなく、経営の安定を考える時代へ
節税効果が高いという理由で経営セーフティ共済に加入する事業者は今も非常に多く、掛金を活用した節税戦略は依然有効です。
経営セーフティ共済の節税効果に関するポイント!

ただし、今後は制度を純粋な節税対策としてだけ見るのではなく、「節税+資金繰り+リスク管理」をトータルで考えた戦略的な活用が求められます。
経営セーフティ共済は、節税面で大きなメリットがある制度であると同時に、万が一の取引先倒産時には掛金総額の最大10倍までの貸付が受けられる安心のセーフティネットでもあります。つまり、節税効果を活かしつつ、経営リスクも軽減できるというハイブリッド型の制度なのです。
改正後も節税効果を失わないためには、2024年9月30日までに再加入しておくことがひとつの選択肢です。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
経営セーフティ共済の改正前に手続きを済ませておけば、従来通り掛金が節税対象として認められます。
また、今後は長期的に継続利用する形での節税を意識することが大切です。解約・再加入による短期節税が封じられる以上、経営セーフティ共済の節税メリットを最大限に活かすには「継続的な掛金支払い」による節税対策が最も効果的といえるでしょう。

合わせて読みたい「日本政策金融公庫の返済免除」に関するおすすめ記事

日本政策金融公庫は返済免除ができる?返済が困難になった時の対処法を解説!
経営セーフティ共済のメリット
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、中小企業や個人事業主が経営リスクに備えるための共済制度であり、さらに高い節税効果が得られる制度としても注目されています。
ここでは、経営セーフティ共済のメリットを徹底的に紹介し、制度の活用方法やポイントをわかりやすく解説します。
経営セーフティ共済のメリット①:掛金を損金・経費として計上できる
経営セーフティ共済の最大のメリットは、なんといっても掛金が全額損金または必要経費として計上できることです。法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費となるため、経営セーフティ共済の加入だけで即時に節税効果が発生します。
経営セーフティ共済の節税効果に関するポイント!

特に利益が大きく出た年度には、経営セーフティ共済の掛金を一時的に増額することで、法人税や所得税を大きく軽減することが可能です。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「最新)賢い会社の節税術!倒産防止共済で最大の効果を出す方法を税理士が解説!」
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
まさに、節税のために活用できる経営セーフティ共済の代表的な特長といえます。

合わせて読みたい「税理士に依頼できる記帳代行と丸投げサービスの違いについて」に関するおすすめ記事
税理士に依頼できる「記帳代行」と「丸投げ」の違いとは?

経営セーフティ共済のメリット②:取引先倒産時に迅速な資金借入が可能
経営セーフティ共済は、取引先が倒産した際に即座に借入ができる共済制度です。連鎖倒産の危機があるとき、経営セーフティ共済に加入していれば、共済金として資金をスムーズに確保できます。
金融機関からの融資が難しい非常事態でも、経営セーフティ共済による貸付制度が経営を支える強力なバックアップになります。経営セーフティ共済の安心感は、経営者にとって心強い存在となるはずです。
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
「経営セーフティ共済(倒産防止共済)のメリットとデメリットを解説」
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
経営セーフティ共済のメリット③:倒産がなくても借入が可能
経営セーフティ共済では、取引先が倒産していなくても借入が可能です。掛金を12ヵ月以上納付していれば、事業資金(運転資金や設備投資)として、無担保・無保証で借入できるのも経営セーフティ共済の大きな特徴です。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
急な資金ニーズが発生した場合でも、経営セーフティ共済を活用することで、資金調達の選択肢を広げることができます。
どのような状況下でも、経営セーフティ共済は経営を守るための重要な制度となっています。

合わせて読みたい「税理士への資金調達の依頼」に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済のメリット④:掛金の増額・減額が柔軟にできる
経営セーフティ共済の掛金は、5,000円〜20万円の範囲内で自由に調整可能です。経営状況に合わせて掛金を増額すれば節税効果が高まり、減額すればキャッシュフローを維持できます。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「経営セーフティ共済vs.小規模企業共済どっちが有利?」
こうした柔軟性は、経営セーフティ共済ならではの強みです。定期的な見直しを行うことで、経営セーフティ共済を長期的に効果的に活用することができます。

経営セーフティ共済のメリット⑤:解約時に解約手当金が受け取れる
経営セーフティ共済では、解約時に掛金総額や納付期間に応じて解約手当金が支給されます。これは、万が一制度を終了する場合でも、一定の返戻があるという安心材料になります。
また、経営セーフティ共済に長期間加入していれば、解約手当金の支給率も高くなり、将来の資金にもつながります。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
ただし、解約時には返戻金が課税対象になるため、経営セーフティ共済の解約タイミングには注意が必要です。
経営セーフティ共済の節税効果に関するポイント!

2024年10月からは、経営セーフティ共済の解約後に再加入した場合、2年間は掛金が損金や必要経費として計上できなくなる改正が実施されます。これは、節税だけを目的とした短期間の解約・再加入を防ぐための措置です。
今後は、経営セーフティ共済の節税効果を継続的に得るには、長期的な視点での活用が求められます。
経営セーフティ共済のデメリットとは?加入前に知っておきたい注意点
節税対策として注目されている経営セーフティ共済ですが、どんなに節税効果が高くても、見落としてはいけないデメリットがあります。
節税ばかりに目がいくと、将来的に思わぬデメリットが発生し、結果として節税どころか損失を招く可能性もあるのです。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて以下のサイトも是非ご覧ください。
「経営セーフティ共済とは?制度の概要と2024年の改正内容まとめ」
ここでは、経営セーフティ共済を節税目的で検討する際に注意すべき主要なデメリットをわかりやすく解説します。
節税のメリットとデメリットを正しく理解することが、最も効果的な節税戦略につながります。
デメリット① 起業から1年未満では経営セーフティ共済に加入できない
まず、経営セーフティ共済は起業してから1年以上経過していないと加入できません。
節税のために早く共済に加入したくても、起業初年度の経営者には利用できないというのは大きなデメリットです。

合わせて読みたい「日本政策金融公庫の審査期間」に関するおすすめ記事
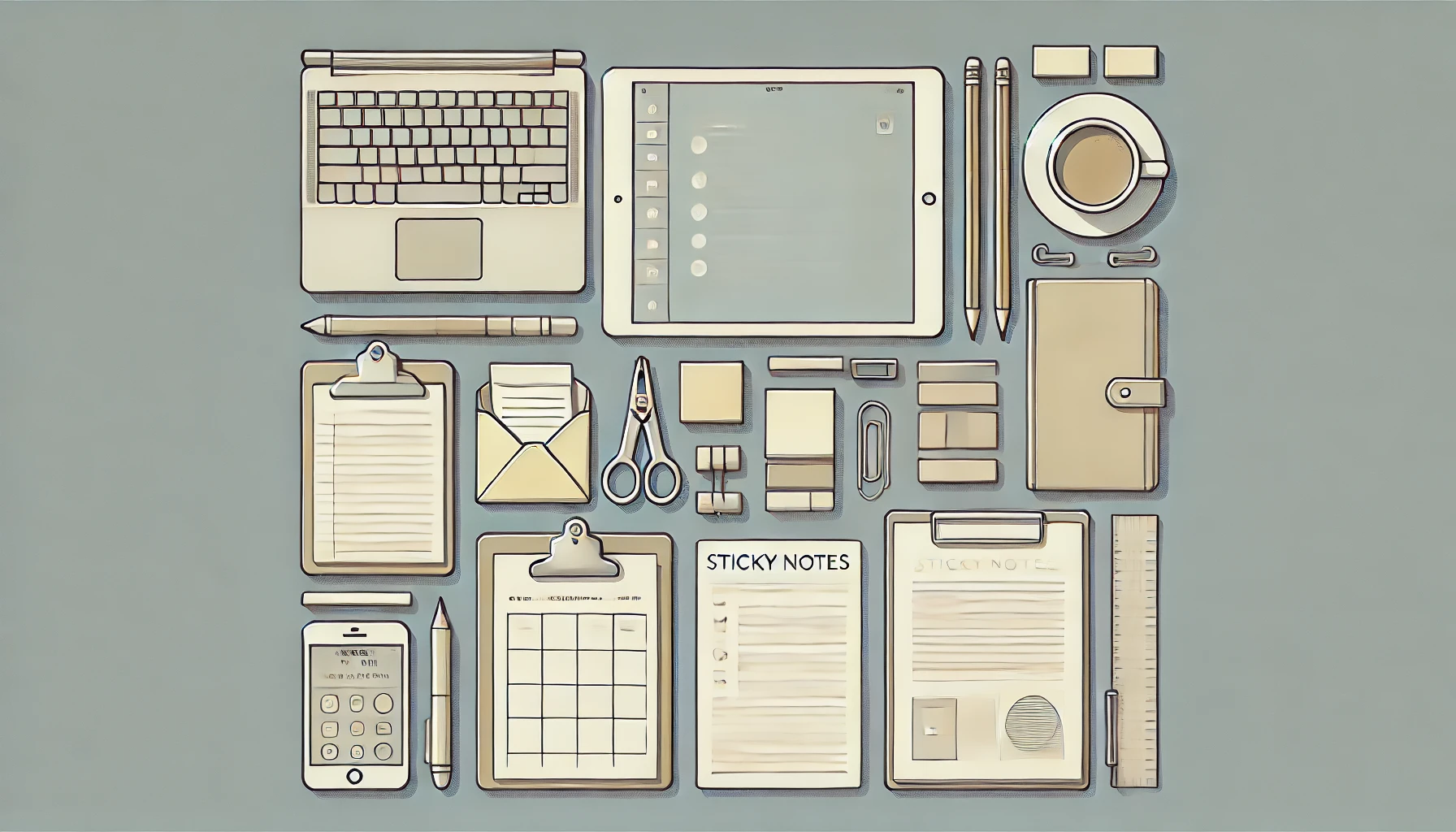
日本政策金融公庫の審査期間はどれくらい?融資までの期間を解説!
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
節税計画を立てる際には、事業開始のタイミングと共済の加入要件をよく確認する必要があります。
これは節税を焦るあまり、制度を誤解してしまう典型的なデメリットパターンです。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて以下のサイトも是非ご覧ください。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「多くの個人事業主の倒産防止共済は節税にならない|むしろキャッシュフローの悪化につながる理由を解説」
デメリット② 掛金納付が12ヵ月未満だと掛け捨て|経営セーフティ共済の返金なし
節税目的で掛金を支払っても、納付期間が12ヶ月未満の場合、解約しても手当金は一切出ません。
つまり、節税できたつもりでも掛金は丸ごと掛け捨て。これは非常に大きな節税面でのデメリットです。
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は節税になる ?それともならない?詳しく解説」
また、強制解約やみなし解約でも同様に返戻はゼロ。節税を目的にするなら、最低でも1年間継続しないと節税の意味をなさないという点は、しっかり把握しておく必要があります。
デメリット③ 経営セーフティ共済は40ヵ月未満の解約で元本割れのリスク
節税目的で経営セーフティ共済を利用しても、40ヶ月未満で解約すると元本割れになります。
支給される解約手当金の率は掛金納付月数に応じて決まるため、節税で得た金額よりも返戻率が低ければ、トータルではマイナスになる可能性もあるというデメリットです。
経営セーフティ共済の節税効果に関する注意点

節税効果だけを見て短期解約を考えると、「節税したはずなのに損した」という典型的なデメリットパターンに陥る可能性があります。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは? メリット/デメリットについても解説」
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
節税効果と返戻率のバランスは必ずチェックしましょう。
掛金納付月数に応じた解約手当金の支給率
経営セーフティ共済の解約手当金は、掛金を納めた月数と解約の理由によって支給率が異なります。以下に、納付期間ごとの支給率の目安を紹介します。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて以下のサイトも是非ご覧ください。
経営セーフティ共済の節税効果に関する参考記事:「経営セーフティ共済とは? 加入条件やメリット・デメリットをわかりやすく解説」
- 1か月〜11か月の間に解約した場合
任意解約・みなし解約・機構解約のいずれであっても、解約手当金の支給はありません(0%)。この期間の解約は、すべて掛け捨てとなるため、節税目的であっても注意が必要です。 - 12か月〜23か月の解約
任意解約であれば80%、みなし解約は85%、機構解約では**75%**が支給されます。
この段階では、元本割れが生じるものの、一定の返戻が発生します。 - 24か月〜29か月の解約
任意解約で85%、みなし解約で90%、機構解約で**80%**の支給率となります。
返戻率はやや改善しますが、節税効果と返戻金のバランスを見ながら解約判断が必要です。 - 30か月〜35か月の解約
任意解約は90%、みなし解約は95%、機構解約は**85%**と、支給率はさらに上昇します。
このタイミングから、節税効果とあわせて現金回収面でも安定性が出始めます。 - 36か月〜39か月の解約
任意解約では95%、みなし解約では100%、機構解約では90%。
特にみなし解約では、掛金が満額返戻される水準に達しますが、みなし解約は法人解散や個人事業主の死亡等、狙ってできるものではありません。 - 40か月以上継続してからの解約
任意・みなし解約のどちらも100%支給。機構解約の場合も95%の高水準です。
この水準まで掛金を納めることで、節税をしながら元本もしっかり回収できる理想的な状態となります。
デメリット④ 経営セーフティ共済の解約手当金は課税対象
経営セーフティ共済で節税できたとしても、解約手当金は「雑収入」として課税されます。
つまり、節税効果は一時的なものであり、将来的には税負担が戻ってくる可能性があるというデメリットがあるのです。

合わせて読みたい「税理士への資金調達の依頼」に関するおすすめ記事

このように、節税の効果は「恒久的な減税」ではなく、「課税の繰延べ」に過ぎないことを理解しておくことが重要です。
経営セーフティ共済の節税効果に関する注意点

無計画に解約してしまえば、節税どころか翌年の納税負担が増えるという逆効果のデメリットもあります。
デメリット⑤ 経営セーフティ共済の借入は実質的に有利子

経営セーフティ共済の貸付制度は、表向き「無利子」とされていますが、実際には借入額の10%が掛金総額から控除されます。
「経営セーフティ共済の節税効果」編集部
これにより、実質的には利息を払っているのと同じ構造であり、節税目的で借入するには不向きというデメリットもあります。
1,000万円を借りたら100万円分の掛金が失われると考えると、節税効果よりも資金の損失が大きい可能性もあります。
節税と資金繰りの両立を図る場合、この借入控除のデメリットをしっかりと認識しておくことが大切です。
経営セーフティ共済の節税効果に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済の節税効果や、経営セーフティ共済のメリット・デメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。
「中小企業倒産防止共済制度とは?加入条件やメリット・デメリットを解説」
Q&A|よくある質問
Q: なぜ「経営セーフティ共済は節税にならない」と言われるのですか?
A: 「経営セーフティ共済は節税にならない」とされる理由は、解約や貸付返済時に受け取る資金が益金として計上され、課税されるためです。短期間で解約すると、節税効果よりも税負担が先送りされるだけになるケースがあります。したがって、経営セーフティ共済の節税効果を最大限に活かすには、長期加入や解約時期の計画が重要です。
Q: 経営セーフティ共済のデメリットは何ですか?
A: 経営セーフティ共済のデメリットとして、解約時に課税される点や、短期解約の場合に掛金の全額が戻らない可能性があります。また、掛金の前納や増額を行った年は大きな節税効果が得られますが、将来的な税負担も増えるため、資金繰り計画とセットで考える必要があります。このため、「節税目的だけ」で加入すると、将来の負担に後悔するケースがあります。
Q: 節税効果を最大化するにはどうすれば良いですか?
A: 経営セーフティ共済の節税効果を最大化するには、黒字決算の年に掛金を増額し、資金に余裕がある場合は前納する方法が有効です。一方で、解約時期を利益が少ない年度に設定すれば、課税負担を抑えられます。税理士と連携して、中長期の利益予測に基づいた掛金設定を行うことが、経営セーフティ共済を節税戦略として成功させる鍵です。
まとめ|経営セーフティ共済で節税するなら、デメリットも理解した上で活用
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
経営セーフティ共済は、倒産リスクに備える共済制度としてだけでなく、節税対策としても非常に有効な制度です。掛金を全額損金や必要経費にできることから、経営セーフティ共済による節税効果は即効性が高く、多くの中小企業・個人事業主が節税目的で加入しています。
しかし、経営セーフティ共済を節税だけのために利用すると、短期解約による掛け捨てや元本割れ、解約手当金への課税など、思わぬデメリットが発生する可能性もあります。
こうした節税に関するデメリットを把握せずに経営セーフティ共済を活用すると、かえって節税効果が相殺されるリスクがあるため注意が必要です。
本記事で紹介したように、経営セーフティ共済は節税に直結するメリットが大きい一方で、継続年数や解約のタイミング次第で節税効果が変動する制度でもあります。
節税目的で経営セーフティ共済を活用するなら、デメリットを理解したうえで、40ヶ月以上の継続や出口戦略をしっかりと設計することが、節税の成功に不可欠です。
今後、経営セーフティ共済を導入して節税をしたいと考えている方は、単なる節税だけでなく、制度の特性・リスク・将来の資金計画までも含めて戦略的に考えることが大切です。
正しい知識と運用で、経営セーフティ共済を最大限に活用した節税対策を実現しましょう。

合わせて読みたい「税理士への資金調達の依頼」に関するおすすめ記事

税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!