新入社員の有給はいつ・何日付与すべき?有給のルールや注意点を解説!
カテゴリー:
公開日:2025年4月
更新日:2025年12月23日
新入社員の有給は、いつ・何日付与すればよいのか、適切に管理できていますか? 新入社員には、入社後一定期間が経過すると法律に基づいて有給が付与されますが、そのルールを正しく理解していないと、付与日や有給の管理が煩雑になったり、新入社員からの問い合わせが増えたりすることもあります。
また、新入社員に対して入社後すぐに有給を付与するケースや、有給を分割して付与するケースなど、企業によって対応が異なることもあり、注意が必要です。特に、新入社員の有給に関するルールを適切に運用しないと、トラブルにつながる可能性もあります。
本記事では、新入社員の有給が発生する条件や付与日数、分割付与の注意点などを詳しく解説します。新入社員の有給を適切に管理し、円滑な職場環境を整えるために、ぜひ参考にしてください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
有給が発生する条件

新入社員が年次有給休暇を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。
<新入社員の1年目の有給取得条件>
- 新入社員が入社日から6ヵ月間継続して勤務している
- 新入社員が入社日から6ヵ月間の全労働日のうち、8割以上出勤している
新入社員の有給付与ルールに関するおすすめ記事
<新入社員の2年目以降の有給取得条件>
- 新入社員が前回の有給付与日から1年間継続して勤務している
- 新入社員が有給付与日から直近1年間、全労働日の8割以上出勤している
SoVa税理士ガイド編集部
全労働日とは、新入社員が出勤しなければならない日数を指し、労働の義務がある所定労働日とも言えます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
新入社員に対して最初に企業が年次有給休暇を付与するのは、入社6ヵ月後です。2年目以降は、新入社員の6ヵ月経過日を基準にして、1年ごとに年次有給休暇を付与しなければなりません。
「入社直後に有休付与」編集部
有給休暇は原則として入社後6ヶ月で付与されますが、早期付与も可能です。たとえば、入社直後に5日を与え、6ヶ月後に残りを付与する分割も認められています。
【4月1日に入社した新入社員の場合】
- 最初の年次有給休暇付与日:10月1日
- 以降の有給付与日:毎年10月1日に1年分の年次有給休暇を付与
新入社員の有給取得には、所定労働日に対する出勤率が重要になります。出勤率を計算する際には、「出勤したものとして取り扱う必要がある日」と「全労働日から除いて計算しなければならない日」があるため、注意が必要です。
新入社員の有給付与ルールに関するおすすめ記事:有給休暇の前借りは違法になる?従業員から依頼された場合の対応方法を解説
<新入社員が出勤したものとして取り扱う必要がある日数>
- 業務上の負傷・疾病によって療養のために休業した日
- 労働基準法第65条による産前産後休業日
- 育児・介護休業法による育児休業や介護休業を取得した日
- 新入社員が有給を取得した日
<全労働日から除く日数>
- 使用者の責に帰すべき事由で休業した日
- ストライキなど正当な争議行為によって労働の提供がまったくなかった日
- 休日労働があった日(週1日または4週を通じて4日必要となる法定休日)
- 公休、所定休日など法定外の休日、就業規則や雇用契約書で定める休日に労働があった日(法定外休日)
新入社員の有給取得のルールを正しく理解し、適切に管理することで、新入社員がスムーズに有給を取得できる環境を整えることが重要です。

合わせて読みたい「固定残業代のメリット・デメリット」に関するおすすめ記事

固定残業代とは?労働者と企業それぞれのメリットデメリットや注意点も解説!
この記事では、固定残業代の基本的な仕組みから、企業・労働者それぞれのメリット・デメリット、導入時の注意点まで、わかりやすく解説します。
新入社員の有給付与日数

年次有給休暇は、新入社員を含むすべての労働者に対して、一定の要件を満たせば付与されるのが原則です。新入社員だけでなく、パート・アルバイトや契約社員といった非正規雇用の従業員にも有給が付与されます。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」
<新入社員として正社員・フルタイムで勤務する場合の有給付与日数(週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上)>
| 勤続期間 | 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
SoVa税理士お探しガイド編集部
新入社員の有給付与ルールついてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
新入社員を含め、勤続期間が長くなるほど年次有給休暇の付与日数は増え、勤続期間6年6ヵ月以上で最大の20日となります。
新入社員の有給付与におけるここがポイント!

新入社員が入社後に8割以上の出勤率を満たせず、有給が付与されない年があったとしても、勤続期間自体は継続して加算されるため、次回の付与日数が適切に計算されているか確認することが重要です。
たとえば、新入社員が入社して1年6ヵ月経過した時点で、病気やケガによる欠勤が多く、有給が付与されなかった場合でも、2年6ヵ月経過時に直近1年間の出勤率が8割以上になっていれば、付与される有給日数は1年6ヵ月時点の「11日」ではなく、2年6ヵ月経過時の「12日」となります。
「新入社員の有休」編集部
新入社員の有給管理は、適切に行わなければ付与日数の計算ミスやトラブルにつながる可能性があります。新入社員の有給付与ルールを正しく理解し、適切な管理を行うことが重要です。

合わせて読みたい「従業員の退職手続き」に関するおすすめ記事
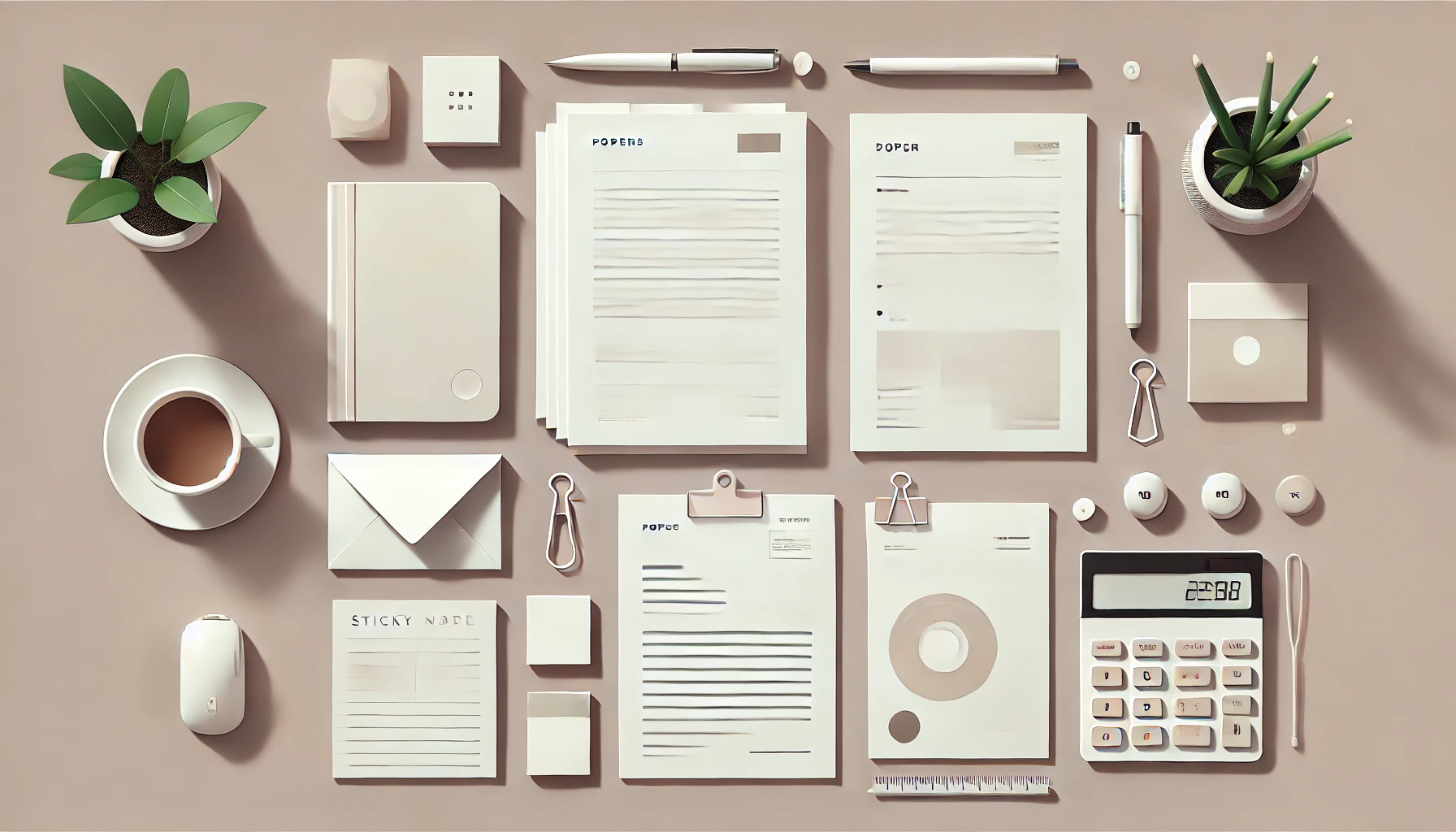
従業員の退職手続きは何をする?必要書類や会社側・従業員側でやることを解説
新入社員に入社後すぐに有給を付与したい場合

新入社員の有給休暇は、入社後6ヵ月が経過した時点で付与されるのが原則です。しかし、これは最低基準を定めるものであり、新入社員に対してより早く有給を付与することは法律上問題ありません。そのため、新入社員の働きやすさを考慮し、前倒しで有給を付与する企業も増えています。

合わせて読みたい「36協定の残業時間の上限」に関するおすすめ記事

36協定の残業時間の上限は月45時間?80時間?規制や罰則について解説
たとえば、新入社員に対して入社後すぐに5日間の有給を付与し、6ヵ月経過後に残りの5日間を付与するというような分割付与を行うことも可能です。新入社員が入社してから6ヵ月経過するまでの間に、自分や家族の体調不良などで急に休みが必要になることも考えられます。そうした場合に配慮し、新入社員が安心して働ける環境を整えることが、入社後すぐに有給を付与する主な目的です。
新入社員の有給付与ルールに関するおすすめ記事
実際に、新入社員に対して入社後すぐに有給を付与している企業も少なくありません。新入社員が有給をすぐに取得できることで、仕事への不安が軽減され、より安心して働くことができます。また、新入社員にとって柔軟で働きやすい職場環境を作ることができ、従業員満足度の向上にもつながります。
SoVa税理士ガイド編集部
新入社員が安心して有給を取得できる環境を整えることで、仕事のパフォーマンスが向上し、生産性の向上にも寄与するでしょう。

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
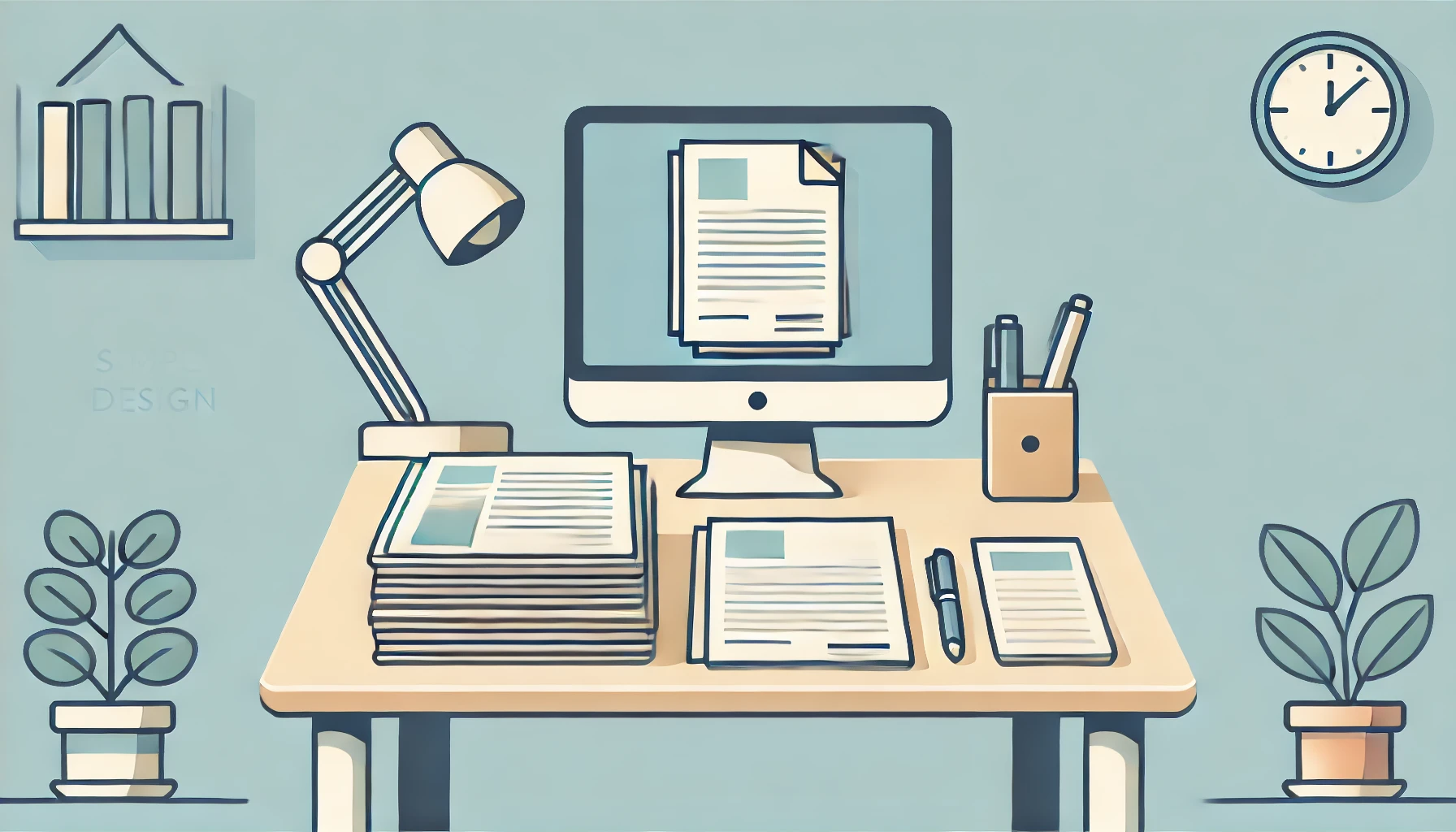
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
新入社員に有給の分割付与をする際の注意点

新入社員に有給を分割付与する際は、労務管理が複雑になる点に注意が必要です。特に、新入社員の有給の基準日や出勤率の計算が変わるため、適切な管理が求められます。
新入社員に有給の分割付与をする際の注意点①:新入社員の有給付与の基準日が異なる
新入社員に有給を分割付与する場合、基準日が通常とは異なる形になります。法律通りに新入社員の有給を付与する場合と、分割付与する場合の違いを以下の事例で見てみましょう。

合わせて読みたい「入社 住民税 手続き」に関するおすすめ記事

入社時の住民税に関する手続きについて解説!退職時の住民税の手続きも併せて紹介!
通常の有給付与(法律通りのケース)
- 2024年9月1日入社の新入社員
- 入社から6ヵ月後の2025年3月1日(基準日)に有給10日付与
- 基準日から1年後の2026年3月1日に有給11日付与
分割付与する場合
- 2024年9月1日に入社した新入社員に対し、入社後すぐに有給6日を付与
- 入社から6ヵ月後の2025年3月1日に残りの有給4日を付与
- 最初に有給を付与した2024年9月1日から1年後の2025年9月1日に有給11日付与
新入社員の有給付与で気をつけておきたい注意点

通常の有給付与では、新入社員の2年目の基準日は2025年3月1日ですが、分割付与の場合は2025年9月1日になる点に注意が必要です。
新入社員の有給付与ルールに関するおすすめ記事
新入社員に有給の分割付与をする際の注意点②:新入社員の有給における出勤率の計算が煩雑化する
新入社員が有給を取得するためには、全労働日の8割以上の出勤が必要です。しかし、有給を分割付与する場合、本来の基準日から繰り上げられた期間の出勤率は、すべて出勤したものとみなされます。そのため、新入社員の有給に関する出勤率の算定は、以下のように計算する必要があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
(実際の出勤日数+短縮された期間のすべての労働日数) ÷ 1年間の労働日数(短縮された期間を含む)
新入社員の有給に関する3回目の基準日以降は、次の基準日までの期間が通常どおり1年になるため、その1年間の出勤実績で出勤率を計算してください。
新入社員に有給を分割付与することは、柔軟な働き方を支援する一方で、管理の負担が増えるため、正確な計算とルールの理解が必要です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
新入社員が入社した際の手続きなどはこちらの年金事務所のサイトを是非参考にしてください。
新入社員に有給の分割付与した際によくあるトラブル

新入社員の有給は基本的に前借りできませんが、特別有給や分割付与の制度を活用することで、新入社員の希望に沿う形で有給を付与することは可能です。
しかし、新入社員の有給の前借り制度を安易に導入するのはおすすめできません。なぜなら、新入社員の有給を前借りできるようにすると、トラブルが発生しやすくなるためです。ここでは、新入社員の有給の前借りに関する主なトラブルとその対策について解説します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
新入社員の有給付与ルールについてもっと知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:新入社員の有給取得はいつから?条件や使い方を紹介
新入社員の有給前借りトラブル①:前借りした有給を消化後に退職してしまう
最も懸念されるのは、新入社員が有給を前借りした後、付与基準日前に退職してしまうケースです。
例えば、4月1日に入社した新入社員の有給の正式な付与基準日が10月1日だとします。しかし、新入社員の希望に応じて、有給を前借りし、5月1日に有給5日を付与したとしましょう。
この新入社員が8月1日に退職してしまった場合、本来の基準日(10月1日)を迎える前に退職することになり、未発生の有給を使用したまま会社を去ることになります。企業側としては、前借りした有給に対する給与の返還を求めたいところですが、法律上、給与の返還手続きを行うことは難しく、好ましくないとされています。そのため、企業としては「本来は欠勤になるはずだった日に特別有給を付与した」という形で処理しなければなりません。
SoVa税理士ガイド編集部
このようなケースは企業にとって損失となるため、新入社員の有給前借りには慎重な対応が必要です。
新入社員の有給前借りトラブル②:希望者が殺到して管理が煩雑化
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
新入社員の有給前借りを一度認めてしまうと、多くの新入社員が前借りを希望する可能性があります。
例えば、「この新入社員は何日有給を前借りしたか」「この新入社員の付与基準日はいつに変更されたのか」といった情報を正確に管理しなければならず、企業の負担が大幅に増加します。
さらに、新入社員の有給管理が複雑化すると、「本来取得できるはずの有給が付与されていない」「有給の残日数が不明確」といった問題が発生し、企業への信頼が低下する恐れもあります。
新入社員の有給付与はここがポイント!

どうしても新入社員の有給前借りを制度として導入する場合は、勤怠管理システムを活用し、適切に管理できる環境を整えることが重要です。
新入社員の有給前借りは、慎重に運用しなければ企業にとって大きなリスクとなるため、適切なルール設定と管理体制の整備が欠かせません。
まとめ

新入社員の有給は、適切に管理しないと付与日や取得状況の把握が難しくなり、労務管理の負担が増えてしまいます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
特に、新入社員に対して有給を入社後すぐに付与する場合や分割付与する場合は、法律のルールを理解した上で慎重に運用することが重要です。
また、新入社員が有給を適切に取得できるよう、制度をわかりやすく説明し、取得を促す環境を整えることも大切です。新入社員の有給をスムーズに管理し、トラブルを防ぐために、本記事で紹介したポイントを参考にしてください。
新入社員の有給付与ルールに関するおすすめ記事
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「給与計算 注意点 (税理士)」に関するおすすめ記事

給与計算の注意点は?税理士に丸投げするメリットについても紹介
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!