【チェックリスト付き】退職手続きの一連の流れと必要な手続きを解説!
カテゴリー:
公開日:2025年4月
更新日:2026年1月8日
退職時には、本人だけでなく会社側にもさまざまな退職手続きが発生します。
スムーズな退職を実現するためには、必要な手続きを漏れなく進めることが不可欠です。とはいえ、実際には「どのタイミングで何をすればいいのか」「渡すべき書類や回収すべき物品は何か」など、悩むことも多いもの。
そこで本記事では、会社側が対応すべき退職手続きをチェックリスト形式でわかりやすく整理しました。退職日まで、そして退職後にやるべきことを網羅したチェックリストを活用し、抜け漏れのない対応を目指しましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
会社側の退職手続き

社員の退職手続きを進める際には、必要な対応を正確に把握しておくことが欠かせません。
以下に、会社側で行うべき退職手続きをチェックリストにまとめました。
SoVa税理士お探しガイド編集部
それぞれの退職手続きには定められた期限がありますので、チェックリストを活用しながら、確実に対応を進めてください。
【会社側で行う退職手続きチェックリスト13】
| No | 項目名称 | 退職手続き期限 |
|---|---|---|
| 1 | 退職届の受理 | 退職日の14日前まで |
| 2 | 退職手続きの説明 | 退職日まで |
| 3 | 健康保険証の回収 | 退職日まで |
| 4 | 貸与品(パソコン、社員証、名刺、入館証)の回収 | 退職日まで |
| 5 | 年金手帳の返却 | 退職日まで |
| 6 | 社会保険脱退手続き | 退職日から5日以内 |
| 7 | 雇用保険脱退手続き | 退職日から10日以内 |
| 8 | 住民税の退職手続き | 退職月の翌月10日まで |
| 9 | 健康保険資格喪失証明書の送付 | 退職日から約5日後~ |
| 10 | 離職票の送付 | 退職日から約10日後~ |
| 11 | 雇用保険被保険者証の送付 | 退職日から約10日後~ |
| 12 | 退職証明書の送付 | 退職日から約10日後~ |
| 13 | 源泉徴収票の送付 | 退職日から1か月以内 |
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリスト関するおすすめ記事
この退職手続きチェックリストを活用することで、退職に伴う各種手続きを漏れなくスムーズに進めることができます。社員の円満な退職をサポートするためにも、各手続きの期限管理を徹底しましょう。
退職日までにやるべき退職手続きチェックリスト

退職手続きでは、期限や内容を正確に押さえることが非常に重要です。
ここでは、退職日までに会社側が進めるべき退職手続きをチェックリスト付きでまとめました。各項目を一つずつ確認しながら進めましょう。
「退職手続き」編集部
法律上は退職の申し出から退職手続きは2週間ですが、実際には引き継ぎや有給消化などを考慮して1ヶ月から2ヶ月程度退職手続きがかかるケースが多数になっています。
退職日までにやるべき退職手続き①:退職届の受理
退職手続きの最初のステップは、退職届の受理です。
SoVa税理士ガイド編集部
民法627条では原則2週間前までとされていますが、多くの企業では就業規則で「1カ月前提出」を定めています。
退職届を受理したら、退職日を確定し、次の退職手続きへと進めます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
チェックリスト
- 退職届を正式に受理したか
- 退職日を確定し、社内共有したか
退職日までにやるべき退職手続き②:退職手続きの説明と意思確認
退職者に対して、必要な退職手続きを丁寧に説明し、各種意思確認を行います。
漏れを防ぐため、以下の項目ごとに確認しましょう。
チェックリスト
- 健康保険の任意継続希望の有無を確認したか
- 住民税の納付方法(普通徴収/特別徴収)を確認したか
- 退職証明書・離職票の発行希望を確認したか
- 退職所得の受給に関する申告書の記入案内をしたか
退職日までにやるべき退職手続き③:健康保険証の回収
退職日までに健康保険証を回収します。
本人分はもちろん、扶養家族分も忘れずに回収し、社会保険の喪失手続きに備えます。
SoVa税理士ガイド編集部
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリストについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
チェックリスト
- 退職者本人の健康保険証を回収したか
- 扶養家族分の健康保険証も回収したか
- 回収した保険証を資格喪失届に添付できるよう準備したか
退職日までにやるべき退職手続き④:貸与品(パソコン・社員証など)の回収
貸与していた機材や備品も、退職手続きの重要なチェックポイントです。
貸与品リストに基づき、漏れなく回収しましょう。
チェックリスト
- パソコン、タブレット等IT機器を回収したか
- 社員証、入館証、名刺等を回収したか
- クラウドサービスや社内システムのアクセス権を削除したか
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリスト関するおすすめ記事:会社側が行う退職手続きは?遅いと言われないためのチェックリストも紹介
退職日までにやるべき退職手続き⑤:年金手帳の返却
会社で保管している年金手帳があれば、必ず退職者へ返却します。
次の職場や国民年金加入手続きで必要になるため、確実な引き渡しが必要です。

合わせて読みたい「新入社員の有休」に関するおすすめ記事

新入社員の有給はいつ・何日付与すべき?有給のルールや注意点を解説!
本記事では、新入社員の有給が発生する条件や付与日数、分割付与の注意点などを詳しく解説します。新入社員の有給を適切に管理し、円滑な職場環境を整えるために、ぜひ参考にしてください。
チェックリスト
- 会社預かり分の年金手帳を退職者へ返却したか
退職者から回収すべき物チェックリスト

退職手続きを進める際は、まず会社に返却すべきものを整理することが重要です。
以下のチェックリストを活用し、漏れなく準備を進めましょう。

合わせて読みたい「会社側の退職手続き」に関するおすすめ記事
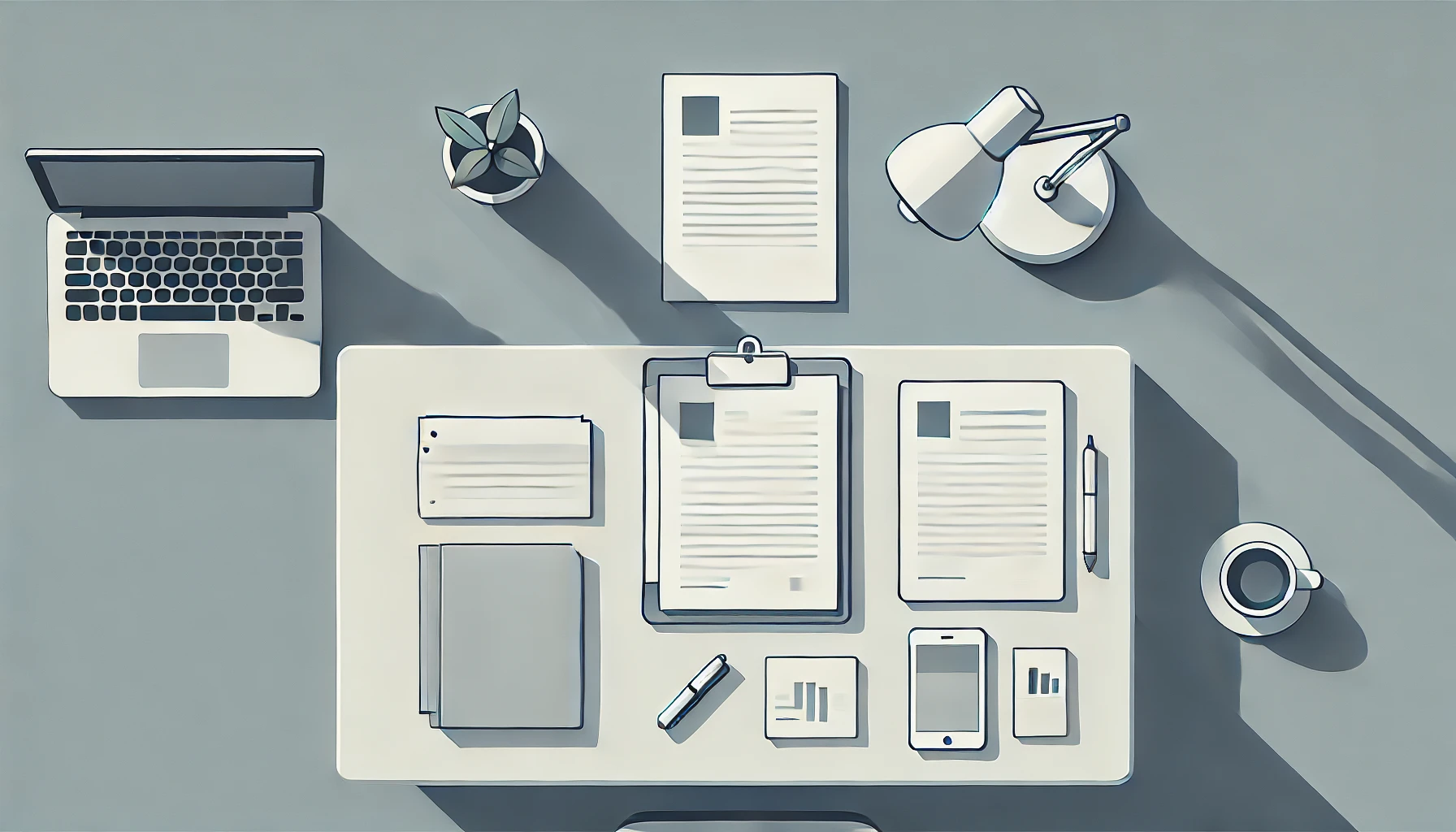
退職手続きでは会社側はいつまでに何をすべき?必要な手続きや対応の注意点を解説!
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
チェックリスト
- 健康保険被保険者証(本人・扶養者分含む)
- 身分証明書(社員証・IDカード・社章など)
- 鍵・セキュリティカード(カードキー・入館証)
- 通勤定期券
- 名刺(自分用・取引先用すべて)
- 書籍・参考資料・事務用品
- 制服・作業着(必要に応じてクリーニング済みで)
- 業務用書類・データ
- パソコン・携帯電話などのデジタルツール
- クラウドツール・SNSアカウントの権限整理
- 返却に迷うその他の物品
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリスト関するおすすめ記事
以下では各項目の退職手続きについて詳しく解説していきます。
1.健康保険被保険者証の返却
退職時には、会社を通じて加入していた健康保険を脱退するため、健康保険被保険者証を回収する必要があります。
本人分はもちろん、扶養家族分の保険証も含めて、退職手続きチェックリストに従い確実に返却しましょう。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」
2.身分証明書(社員証・IDカード・社章など)
会社の一員であることを示す社員証や社章なども、退職手続きで必ず返却します。
退職後の不正利用防止のため、忘れずに回収しましょう。
3.鍵・セキュリティカード(カードキー・入館証)
会社施設への入館に必要なカードキーや鍵も、退職日までに返却する退職手続き項目の一つです。
不要になったタイミングで速やかに返却を進めてください。

合わせて読みたい「従業員の退職手続き」に関するおすすめ記事
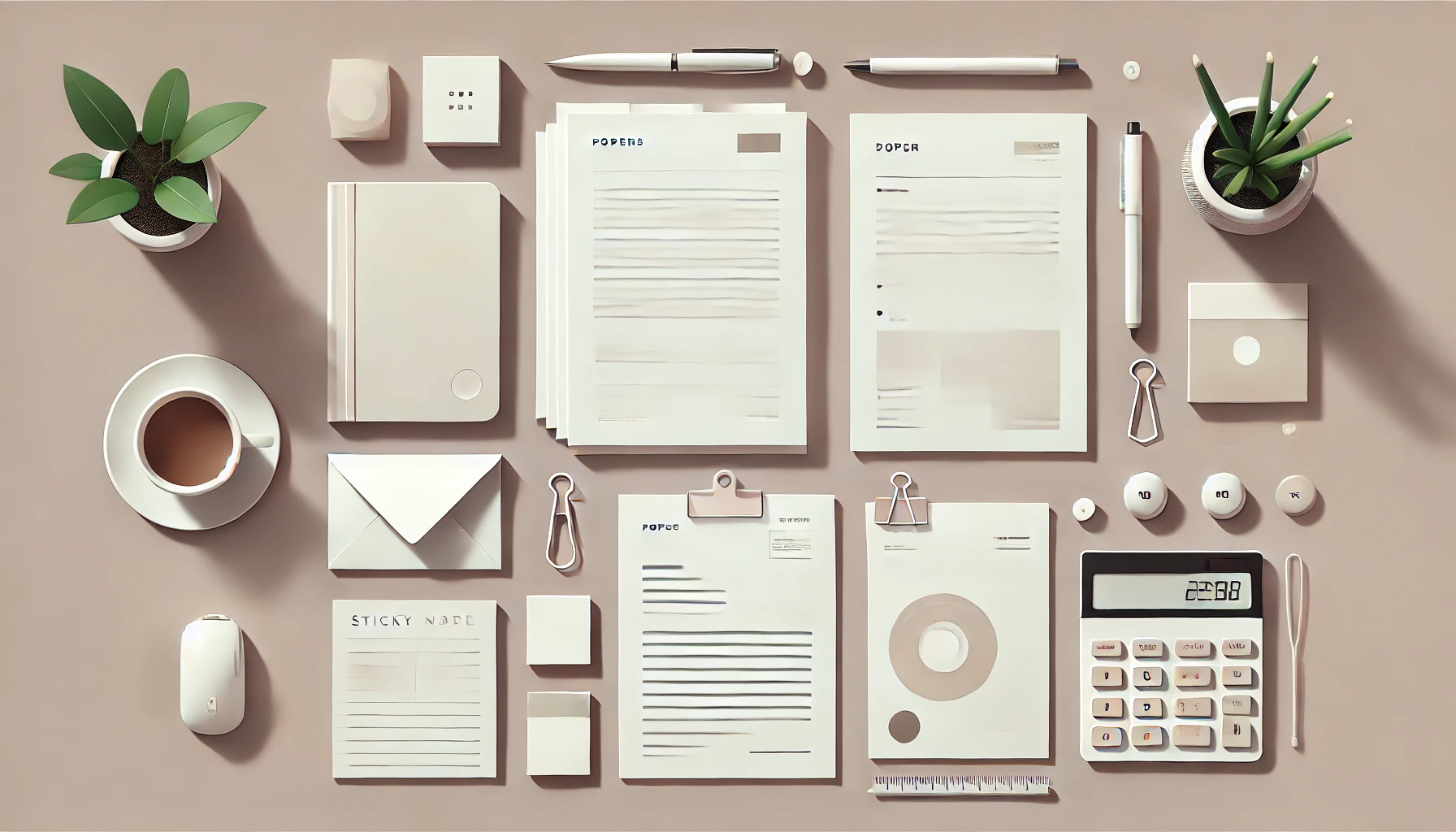
従業員の退職手続きは何をする?必要書類や会社側・従業員側でやることを解説
4.通勤定期券
通勤定期券は会社支給の場合、退職に合わせて精算・返却が求められます。
会社のルールに従い、退職手続きの中で忘れずに対応しましょう。
5.名刺(自分用・取引先用)
配布された自分の名刺、取引先から受領した名刺は、すべて会社の資産です。
SoVa税理士ガイド編集部
退職時には持ち出さず、会社へ返却することが退職手続き上のルールとなっています。
6.書籍・参考資料・事務用品・制服・作業着
会社購入の書籍や資料、事務用品、制服・作業着も返却対象です。
クリーニングが必要な場合や、自費購入分がある場合は会社と確認し、適切に退職手続きを行いましょう。
7.業務用の書類・データ
業務に関連する書類やデータも、退職手続きで重要な回収項目です。
自分が作成したものであっても、持ち出しは厳禁です。必ず会社に返却し、情報漏洩を防ぎましょう。
8.パソコン・携帯電話などのデジタルツール
貸与されたパソコンや携帯電話も、退職手続きの一環として必ず返却します。
データのコピーや私的利用は禁止されていますので、適切に対応してください。
9.クラウドツール・SNSアカウント
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
退職前には、業務用クラウドツールのアカウント削除や、SNSアカウント情報の更新・引き継ぎを行います。
特に会社名をプロフィールに記載している場合は、忘れずに変更することが退職手続き上必要です。
10.その他、返却に迷うもの
返却するか迷う物品があれば、必ず会社に相談して指示を仰ぎましょう。
自己判断による持ち出しは、後のトラブルにつながるリスクがあります。
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリスト関するおすすめ記事
退職後に渡すべき書類チェックリスト

退職手続きにおいて、会社側が退職者に確実に渡さなければならない書類がいくつか存在します。これらは退職後の生活や転職先での入社手続きに必要不可欠なものです。
本記事では、会社側が対応すべき退職手続きチェックリストをもとに、渡すべき書類と注意点を整理しました。
退職手続きでは、以下の書類を退職者に必ず交付してください。
各書類の役割を理解し、チェックリストを活用しながら、渡し漏れがないよう徹底しましょう。
SoVa税理士ガイド編集部
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリストについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
チェックリスト
- 雇用保険被保険者証(会社保管分がある場合)
- 源泉徴収票
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(会社保管分がある場合)
- 離職票(退職者から請求があった場合)
- 退職証明書(退職者から請求があった場合)
以下で、各項目の退職手続きと渡すべきポイントを解説します。
1.雇用保険被保険者証(会社が保管している場合)
雇用保険被保険者証は、転職先での雇用保険手続きや、失業手当(失業保険・失業給付金)の申請に必要な重要書類です。
退職手続きの一環として、会社側で保管している場合は必ず退職者へ返却してください。紛失している場合は、退職前に再発行手続きの案内も行いましょう。
2.源泉徴収票
源泉徴収票は、所得税の年末調整や確定申告に必要です。退職後に新しい職場に提出するか、自身で確定申告を行う際に使用されます。
退職手続きの締めくくりとして、必ず発行・交付し、受領確認を取りましょう。
3.年金手帳または基礎年金番号通知書(会社が保管している場合)
退職者が厚生年金に引き続き加入する際に必要となる書類です。2022年3月31日以降は年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書が主流となっています。
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリスト関するおすすめ記事
会社側が保管している場合は、退職手続き完了時に返却を行ってください。もし退職者側が紛失していた場合は、再発行手続き方法も案内できると親切です。
4.離職票(退職者から請求があった場合)
離職票は、失業手当(失業保険・失業給付金)受給の申請に必要な書類です。退職者から発行の希望があった場合、会社は速やかに退職手続きに沿って作成・交付しなければなりません。
発行に時間がかかるため、退職後に郵送対応するケースもありますが、必ず事前に渡し方についても案内しておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
5.退職証明書(退職者から請求があった場合)
退職証明書は、労働基準法第22条に基づき、退職者から請求があった場合に会社が発行義務を負う書類です。
国民健康保険や国民年金の加入手続き時の添付書類としても利用できるため、退職手続きチェックリストに含め、迅速に対応しましょう。
SoVa税理士ガイド編集部
発行は比較的早くできるため、希望者には退職日当日または直後に交付するのが理想です。
退職後にやるべき退職手続きチェックリスト

従業員が退職した後、会社側は速やかに各種の退職手続きを進めなければなりません。
必要な手続きには期限が定められており、対応が遅れると行政手続き上のトラブルにもつながりかねません。退職後に会社側が対応すべき手続きのチェックリストは以下の通りです。
- 健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続き
- 雇用保険の資格喪失手続き・離職票の作成
- 住民税の徴収・切替手続き
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリスト関するおすすめ記事
それぞれの退職手続きのポイントを確認しましょう。
1.健康保険・厚生年金保険に関する退職手続き
退職者の健康保険および厚生年金保険については、退職手続きチェックリストに基づき以下の手続きを進めます。
手続き内容
- 資格喪失日から5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出
- 本人および扶養家族分の健康保険証を回収し、提出
- 提出先は事務センターまたは管轄年金事務所
退職手続きで気をつけておきたい注意点

資格喪失日は退職日の翌日となるため、例えば1月31日退職なら、2月1日が資格喪失日となり、2月5日までに手続きを完了させる必要があります。提出方法は、電子申請・郵送・窓口持参の3通りから選べます。
2.雇用保険に関する退職手続き
雇用保険に関する手続きも、退職手続きチェックリストに沿って進めます。
手続き内容
- 「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出
- 「雇用保険被保険者離職証明書」の作成・提出
- 提出先は事業所を管轄するハローワーク
退職手続きで気をつけておきたい注意点

資格喪失の翌日から10日以内に手続きを完了する必要があります。
例えば1月31日に退職した場合、2月1日が資格喪失日となり、2月2日から起算して10日以内に提出しなければなりません。
あわせて、出勤簿、退職辞令、賃金台帳、離職理由が確認できる書類も併せて提出し、ハローワークから離職票を交付してもらいます。
3.住民税に関する退職手続き
住民税も、退職手続きチェックリストに記載しておくべき重要項目です。
給与から住民税を特別徴収している従業員が退職した場合、会社は以下の手続きを行います。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
手続き内容
退職時期に応じて対応を選択します。
- 【1月~5月に退職した場合】
最後の給与または退職金から住民税の残額を一括天引きして納付する。 - 【6月以降に退職した場合】
以下のいずれかを選択する必要があります。
- 最後の給与または退職金から残額を一括天引きして会社経由で納付する
- 普通徴収へ切り替え、退職者本人に納付させる
- 新しい就職先で特別徴収を再開してもらう
- 最後の給与または退職金から残額を一括天引きして会社経由で納付する
SoVa税理士ガイド編集部
退職者本人とよく相談し、普通徴収へ切り替える場合は市区町村への届け出も忘れずに行いましょう。
Q&A|よくある質問
Q: 退職前にやることは何ですか?
A: 退職手続きの前には、まず退職前にやることを整理しておくことが重要です。退職前にやることとしては、退職届や退職願の提出日程を確認し、上司や人事部に正式に退職意思を伝えること、業務の引き継ぎスケジュールを作成すること、会社から借りている備品(社員証、パソコン、制服など)の返却準備をすることが挙げられます。また、退職前にやることとして社会保険や税金の切り替え手続き、残っている有給休暇の消化計画も欠かせません。
Q: 退職前にやることを効率的に進める方法はありますか?
A: 退職前にやることを効率的に進めるには、チェックリストを活用するのが効果的です。退職手続きの全工程を「やることリスト」として書き出し、完了した項目にチェックを付けることで、手続き漏れを防げます。特に社会保険や年金の退職手続き、有給休暇の消化、引き継ぎ資料の作成などは優先順位を付けて行いましょう。
まとめ

退職手続きをスムーズに行うためのチェックリスト関するおすすめ記事
退職手続きは、タイミングや内容を間違えるとトラブルにつながる可能性もある重要な業務です。
本記事で紹介した退職手続きチェックリストを活用すれば、退職日までに行うべきこと、貸与品の返却、退職後に必要な書類対応など、すべてを整理しながら確実に進めることができます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
退職手続きの一連の流れを把握し、チェックリストをもとに対応を進めることで、従業員・会社双方にとって円満な退職を実現しましょう。
退職手続きをスムーズに行うためのチェックリスト関するおすすめ記事:チェックリストつき!退職手続きの流れと必要な書類を解説
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドとの違いを徹底比較!ビジネスオーナーズ ゴールドを持つメリットとは
-
ビジネスカード

2026年1月29日
2
三井住友カードビジネスオーナーズ2枚持ちのメリットは?2枚持ちにおすすめの個人カードや選び方も紹介
-
ビジネスカード

2026年1月29日
3
三井住友ビジネスオーナーズのメリット・デメリットとは?ゴールドとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月29日
4
三井住友ビジネスオーナーズゴールドのメリットは?一般カードやfor Ownersとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月29日
5
即日ファクタリング来店不要おすすめ15選!選び方から注意点まで徹底解説
-
資金調達

2026年1月24日














SoVaをもっと知りたい!