退職手続きでは会社側はいつまでに何をすべき?必要な手続きや対応の注意点を解説!
カテゴリー:
公開日:2025年4月
更新日:2026年1月8日
退職手続きは、従業員だけでなく会社側にとっても重要な業務です。適切な対応を怠ると、思わぬトラブルや法的リスクにつながることもあるため、会社側は退職手続きの流れや注意点をしっかりと把握しておく必要があります。
本記事では、退職前から退職後にかけて会社側が行うべき退職手続きの内容を時系列で解説するとともに、スムーズに進めるためのポイントや、税金・社会保険料の精算方法、会社側が特に注意すべき点まで詳しく紹介します。会社側の人事担当者や管理部門の方は必見です。
目次
【退職前】会社側が退職手続きで行う手続き
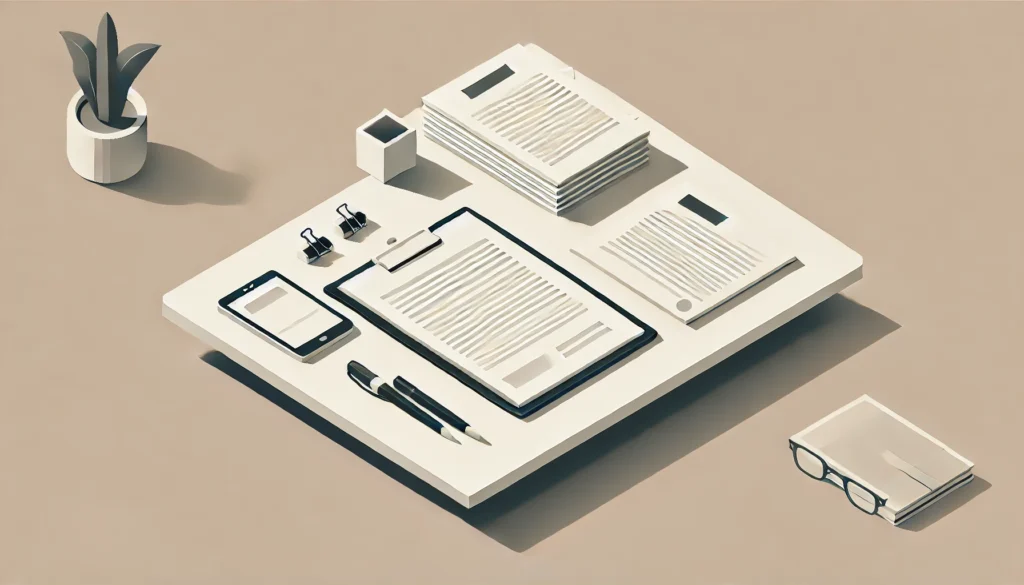
退職手続きの中には期限が明確に定められているものもあるため、会社側としては確実かつ漏れのない対応が求められます。以下では、退職手続きにおいて会社側が実施すべき基本的な対応を順を追って解説します。
退職手続き①:退職日の決定
退職手続きの第一歩として、会社側は従業員と話し合い、退職日を確定させる必要があります。従業員が退職を申し出てから14日後以降の日付を設定することが基本です。
SoVa税理士ガイド編集部
民法第627条では、「期間の定めのない雇用契約の場合、解約の申入れから2週間経過後に雇用契約が終了する」と定められています。
仮に就業規則で「退職は3ヶ月前の申し出が必要」としていても、従業員が2週間以上前に申し出ていれば、法律上は有効です。会社側はこの点を理解したうえで、円満な退職手続きを進めるために従業員と調整を行いましょう。なお、会社側が認める場合には、申し出から14日未満でも退職を承認することが可能です。
退職手続き②:退職届の受理
会社側は、退職日が確定した時点で、従業員に退職届を提出してもらい、正式に受理します。法的には口頭のみでも効力はありますが、会社側が後々のトラブルを避けるためには、書面での提出を求めることが望ましいです。
また、会社側は退職届の提出期限や、有給休暇の消化についても明確に伝え、スムーズな退職手続きの進行を図ることが重要です。
「退職手続き」編集部
法律上は退職の申し出から退職手続きは2週間ですが、実際には引き継ぎや有給消化などを考慮して1ヶ月から2ヶ月程度退職手続きがかかるケースが多数になっています。
退職手続き③:退職者への手続き説明
退職手続きにおいて、会社側が従業員へ行うべきもう一つの重要なステップが、退職後に必要となる手続きの説明です。必要書類や公的手続きについて分かりやすくまとめ、チェックリストなどを用いて説明すると、会社側として丁寧な対応と受け取られやすくなります。
退職手続きで会社側がやるべき手続きに関するおすすめ記事
特に健康保険については、退職後すぐに次の職場が決まっていない場合、国民健康保険への切り替えなどの案内が必要です。これらの説明を漏れなく行うことは、会社側にとって大切な信頼構築の一環でもあります。
退職手続き④:必要書類の準備
退職手続きにおいて、会社側が準備すべき書類は以下の通りです。
- 給与所得の源泉徴収票
- 健康保険の資格喪失証明書
- 離職票
- 退職証明書
特に、会社側が発行する退職証明書については、従業員の求めに応じて速やかに交付しなければなりません。労働基準法第22条により、会社側にはこの義務が課されています。
退職手続きで会社側がやるべき手続きに関するおすすめ記事:退職手続きはいつまでに何をやるべき?従業員側・会社側それぞれの作業を解説
退職手続き⑤:貸与品の回収
退職手続きの一環として、会社側は健康保険証や社員証、制服、業務用パソコンなどの貸与品を適切に回収する必要があります。回収漏れを防ぐために、事前にリストを作成して従業員に提示しておくとスムーズです。
特に健康保険証の返却は、退職翌日から5日以内に保険者へ提出する必要があるため、会社側は確実に管理・対応する必要があります。有給休暇消化後の郵送対応なども考慮し、退職手続きの最後まで丁寧に対応しましょう。

合わせて読みたい「従業員の退職手続き」に関するおすすめ記事
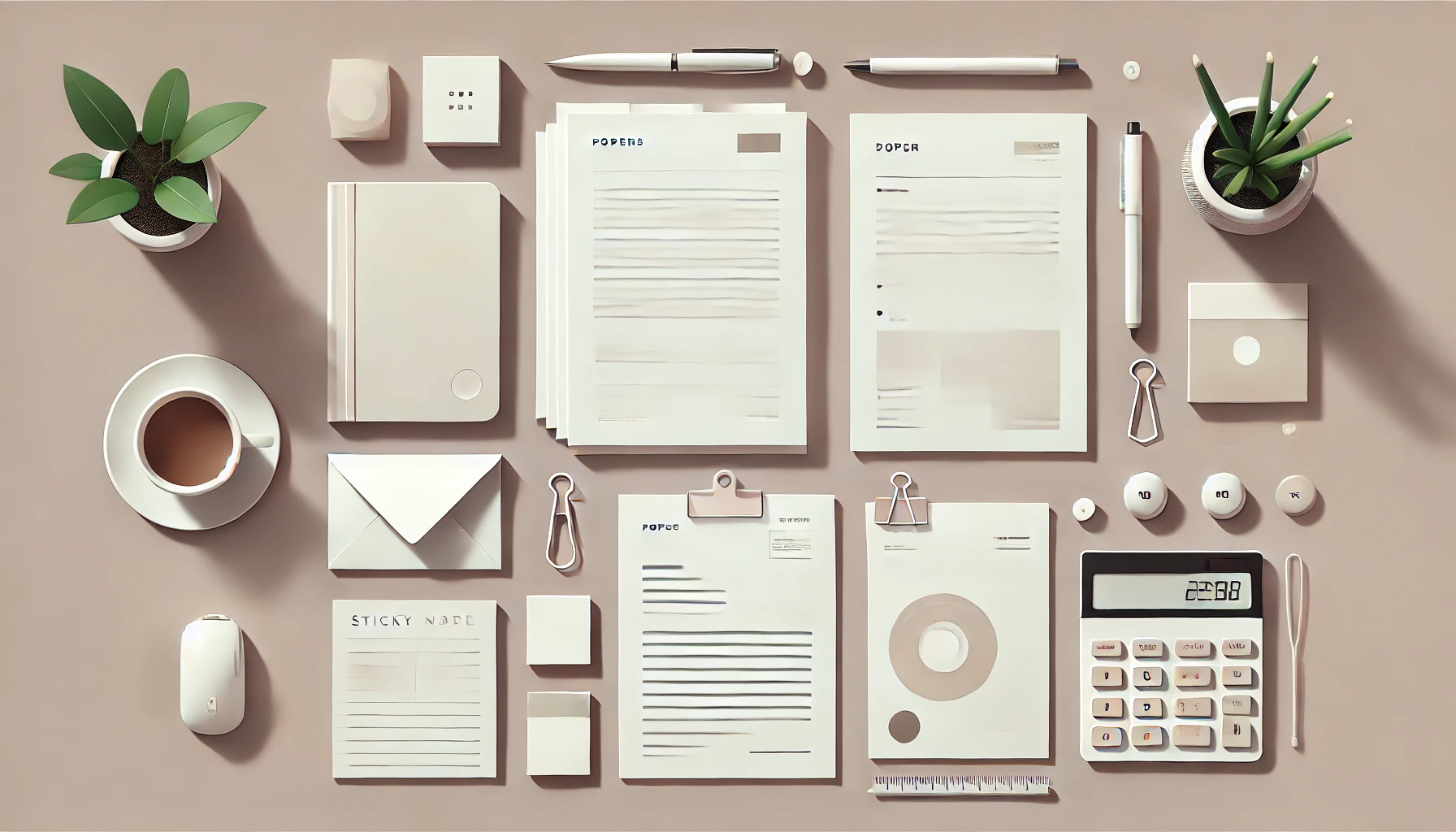
従業員の退職手続きは何をする?必要書類や会社側・従業員側でやることを解説
【退職後】会社側が退職手続きで行う手続き

従業員が退職した場合、会社側は速やかに必要な退職手続きを進める必要があります。これには、以下の退職手続きが含まれます。会社側が行うべき退職手続きをそれぞれ詳しく解説します。
健康保険・厚生年金保険に関する退職手続き
会社側は、退職した従業員に対して、健康保険および厚生年金保険の資格喪失手続きを速やかに行う必要があります。資格喪失手続きは、資格喪失日から5日以内に行う必要があり、会社側は「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」と「本人および扶養家族分の健康保険証」を所管の年金事務所または事務センターに提出します。退職日が1月31日の場合、資格喪失日は2月1日となり、会社側は2月5日までに手続きを完了させなければなりません。
提出方法には、電子申請、郵送、窓口持参の3つの方法があります。
雇用保険に関する退職手続き
会社側は、退職した従業員が雇用保険の被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」および「雇用保険被保険者離職証明書」を提出しなければなりません。例えば、退職日が1月31日の場合、2月1日が資格喪失日となり、2月2日から10日以内に手続きを完了させる必要があります。
この手続きには、出勤簿や退職辞令、賃金台帳、離職理由を確認できる書類を併せて提出し、ハローワークから離職票を受け取ります。
退職手続きで会社側がやるべき手続きについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
所得税に関する退職手続き
退職した従業員に対して、会社側は退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。この源泉徴収票は、退職者が新しい就業先に就職した場合、年末調整に使用されます。会社側は、所得税法に基づき、源泉徴収票の交付を怠らないように注意する必要があります。

合わせて読みたい「みなし残業代(固定残業代)」に関するおすすめ記事

みなし残業(固定残業)制度とは?企業側のメリットと注意点を解説!
本記事では、みなし残業(固定残業)制度の基本的な仕組みから、企業が導入するメリット・デメリット、注意点までをわかりやすく解説します。これから制度の導入を検討している企業の方や、仕組みを正しく理解したい人事担当者にとって、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
また、源泉徴収票は、退職後に就業しない場合でも確定申告で必要となるため、退職者に対して適切に交付することが求められます。交付を怠った場合、会社側には罰則が科されることがあります。
住民税に関する退職手続き
会社側は、給与から住民税を特別徴収していた退職者に対して、住民税に関する退職手続きを実施しなければなりません。住民税は、前年の所得に対して翌年の6月から1年間で支払われる仕組みです。
会社側が対応すべき退社手続きに関するここがポイント!

退職時期によって手続きが異なるため、会社側はその点に留意する必要があります。
1月から5月に退職した場合、会社側は最後に支払う給与や退職金から住民税を天引きします。6月以降に退職した場合は、以下のいずれかの方法で手続きを行います。
- 最後に支払う給与または退職金から天引きし、会社経由で納付
- 普通徴収に切り替え、退職者自身が納付
- 新しい就業先で特別徴収
このように、会社側は退職手続きにおいて多くの重要な手続きを迅速に実行することが求められます。
退職手続きを会社側がスムーズに進めるポイント

退職手続きには多くの必要書類や手続きがあり、手作業で進める場合、記入漏れやミスが発生する可能性が高くなります。そのため、会社側は退職手続きを滞りなく進めるための方法やポイントを事前に把握し、効率的に管理することが求められます。以下に、退職手続きを円滑に進めるための方法を紹介します。
退職手続きを会社側がスムーズに進めるポイント①:労務管理システムを導入する
労務管理システムとは、退職手続きに必要な書類作成や申請作業、勤怠管理、給与計算、社会保険手続きなどを効率的に行うことができるシステムです。会社側がこのシステムを導入することで、従業員の退職手続きに関連する作業の負荷を軽減し、記入漏れやミスを防ぐことができます。
このシステムでは、退職した従業員に必要な社会保険や雇用保険の資格喪失届、源泉徴収票の作成が簡単に行えます。
SoVa税理士ガイド編集部
また、法改正に伴う税率や保険料の変更にも対応しており、会社側にとって非常に効率的です。
労務管理システムを活用することで、退職手続きがスムーズに進み、ミスや遅延を最小限に抑えることができます。
退職手続きを会社側がスムーズに進めるポイント②:電子申請を利用する
労務管理システムを導入しない場合でも、政府が提供する「e-Gov(イーガブ)」を利用すれば、退職手続きに関する書類の電子申請を行うことができます。会社側は、退職手続きに関する書類作成から申請までの一連の流れを全てWeb上で処理できるため、時間の短縮や生産性の向上が期待できます。
退職手続きで会社側がやるべき手続きに関するおすすめ記事
手作業で退職手続きを進める場合、期間や金額の計算などで複雑な部分が多く、ミスが起きやすいですが、電子申請を利用すれば、入力データをチェックしながら作業を進めることができ、ミスを防止することができます。このように、電子申請を活用することで、会社側は退職手続きにおけるミスを減らし、円滑に進めることができます。
退職手続きを会社側がスムーズに進めるポイント③:チェックリストを作成する
退職手続きには多くの書類や作業が必要なため、手続きの漏れが生じやすくなります。会社側は、退職手続きに必要な書類や手続きを事前にリストアップし、チェックリストを作成しておくことが重要です。これにより、退職手続きが滞りなく進められ、漏れを防ぐことができます。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
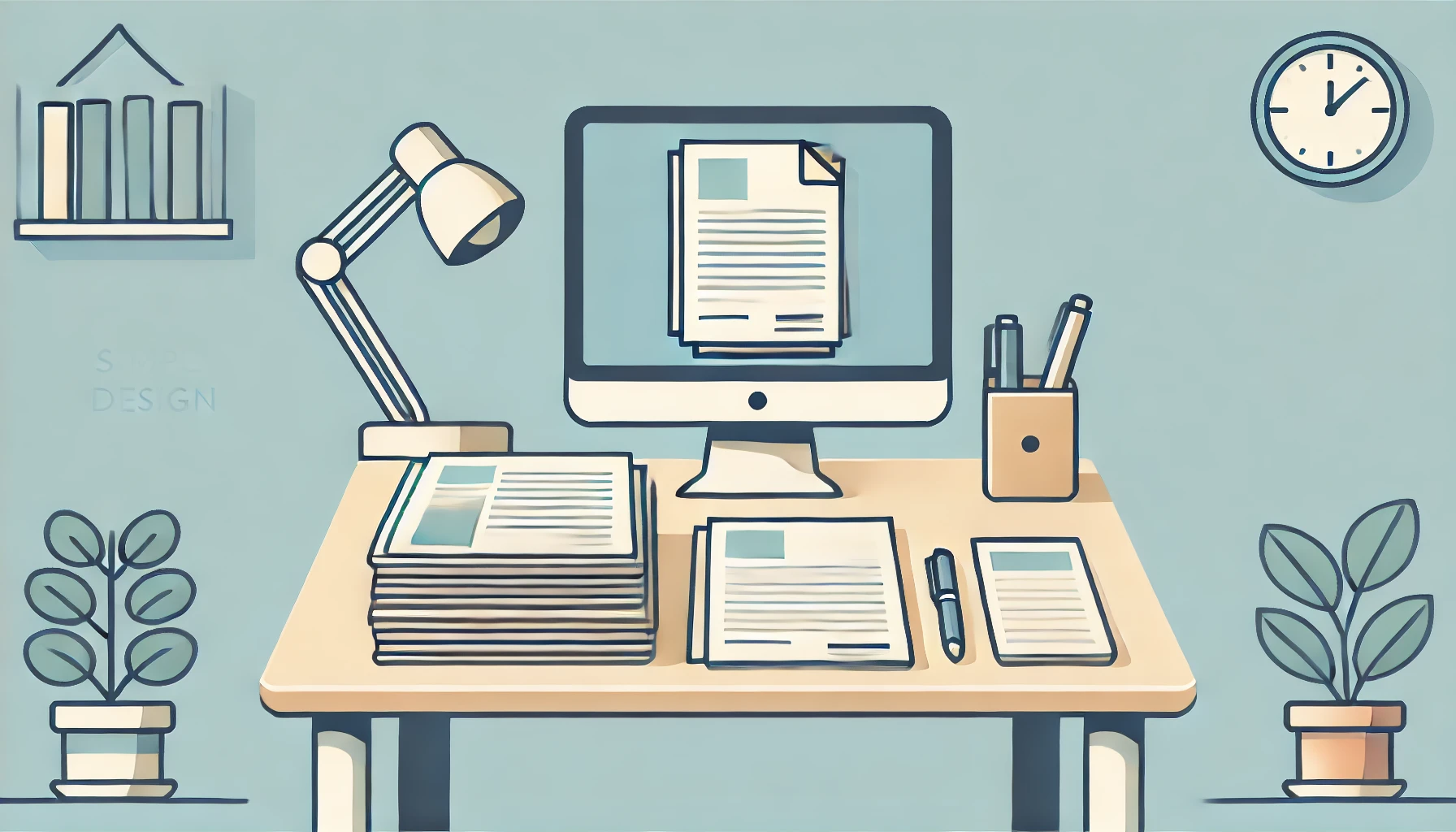
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
チェックリストは、会社側だけでなく、従業員側に提出をお願いする必要がある書類や手続きについてもリスト化することが推奨されます。会社側と従業員側がチェックリストを共有し、双方で確認しながら進めることで、退職手続きの漏れやミスを防ぐことができます。
退職手続きにおける税金・社会保険料の計算方法

退職手続きの一環として、会社側は社会保険料や住民税の取り扱いについても正確に管理する必要があります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
これらの手続きは退職日に基づいて計算されるため、会社側は従業員の退職日を確認した上で適切に対応しなければなりません。
以下に、退職後の社会保険料および住民税について、会社側が注意すべき点をまとめました。
社会保険料
退職日の翌日が社会保険の資格喪失日となるため、会社側はその日を基準に社会保険料を計算する必要があります。具体的には、厚生年金保険や健康保険などの社会保険料は、資格喪失日の前月分まで発生します。
たとえば、3月31日に退職した場合、資格喪失日は4月1日となり、3月分までが社会保険料の対象となります。会社側は、退職日に基づいて社会保険料を適切に処理することが求められます。
退職手続きで会社側がやるべき手続きに関するおすすめ記事
住民税
住民税は前年の所得を基に決まるため、退職後でも前年に収入があれば住民税の支払い義務が発生します。会社側は、従業員の住民税を給与から天引きするかたちで通常徴収しますが、退職時には残りの住民税を一括で徴収する必要があります。この徴収方法は退職した月によって異なるため、会社側は適切に処理を行うことが重要です。
退職時期別の住民税の取り扱い
- 1月から4月に退職:残りの住民税(5月までの分)を一括して天引きして徴収します。
- 5月に退職:5月分の住民税を最後の給与または退職金から天引きして徴収します。
- 6月から12月に退職:
- 残額(翌年5月までの分)を一括徴収する方法
- 普通徴収へ切り替えて、従業員本人が支払う方法
- 転職先で特別徴収を継続する方法
「特別徴収」は、会社が給与から天引きして代わりに住民税を納付する方法であり、「普通徴収」は従業員本人が直接住民税を支払う方法です。退職時には、これらの方法のいずれかを選択することになります。
会社側が対応すべき退職手続きはここがポイント!

特に、1月から5月に退職した場合、住民税は通常通り給与から天引きされますが、6月から12月に退職した場合は上記の3つの方法から選択されることが一般的です。
退職手続きにおいて、これらの税金関連の手続きを適切に行うことは、会社側の重要な責務です。
退職手続きにおける会社側の注意点
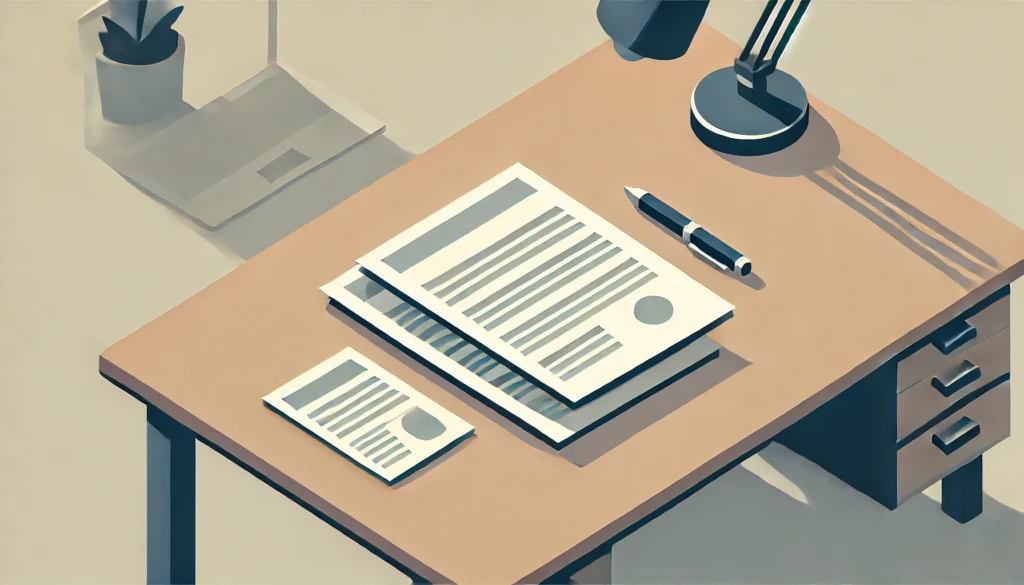
退職手続きにおいて、会社側が特に注意しなければならない重要な点がいくつかあります。ここでは、実務上トラブルになりやすく、見落とされがちな注意点を3つに絞ってご紹介します。これらをしっかりと把握し、退職手続きにおけるリスクを未然に防ぎましょう。
退職手続きにおける会社側の注意点①:有給休暇の取得・買い取りに関する明確な対応
退職直前にまとめて有給休暇を取得する従業員は少なくありませんが、会社側は業務引き継ぎとのバランスを考慮する必要があります。退職日を迎える前に、従業員に対して有給の取得・買い取りに関する明確な方針を示し、手続きを進めましょう。
- 引き継ぎが不十分なまま退職日を迎えるリスク: 会社側は、従業員が有給を取得する前に業務の引き継ぎ計画を立て、円滑に退職できるように配慮します。
- 有給の買い取り義務への対応: 会社都合で退職する場合、有給休暇の買い取り義務が発生するため、これを適切に処理する必要があります。
退職手続きで会社側がやるべき手続きに関するおすすめ記事
あらかじめ退職希望日と有給残日数を把握し、引き継ぎ計画を立てたうえで、有給の取得・買い取りの方針を従業員と明確にすり合わせることが、会社側にとって重要なポイントです。
退職手続きにおける会社側の注意点②:貸与物・情報資産の確実な回収とアクセス遮断
退職後のセキュリティリスクを避けるため、会社側は情報資産の管理に特に注意を払う必要があります。退職手続きを進める中で、従業員が持ち帰ったり、アクセスしたりすることがないよう、適切な回収と遮断措置を取ることが求められます。
- 会社貸与物の返却: パソコンやスマートフォン、IDカードなどの貸与物は、退職日までに必ず回収し、管理を徹底しましょう。
- 社内システムやアカウントの停止: 退職後に従業員がアクセスできないよう、社内システムやメール、チャットアカウントを停止します。
- 個人デバイスへのデータ保存・転送の禁止徹底: 特にリモートワークをしている場合、退職後もデータの保存や転送が行われるリスクがあるため、これを防ぐための措置を取ることが重要です。
これらの手続きを退職日までに確実に行い、情報漏洩のリスクを回避するため、会社側は徹底的に管理を行う必要があります。
退職手続きで会社側がやるべき手続きに関するおすすめ記事:退職手続きで会社側に必要な対応とは?流れや書類、各種保険の計算方法を紹介
退職手続きにおける会社側の注意点③:退職理由と合意内容の「証拠化」
退職が自主的なものであるか、会社都合であるかによって、失業給付や社会保険の手続きが変わります。会社側は、退職理由や合意内容について書面で確認・記録を残すことが重要です。
- 退職届・退職願の提出を促す: 退職手続きが正式に進む前に、従業員に退職届または退職願を提出させることが必要です。
- 退職理由と合意した退職日を文書化する: 退職理由や退職日については、口頭だけでなく、メールなどで証拠として残しておくことが重要です。
会社側が対応すべき退職手続きのここがポイント!

後日、退職に関するトラブルや「退職は強制だった」との主張を防ぐためにも、退職の経緯を文書で証明できる状態にしておくことが、会社側のリスク管理において不可欠です。
これらのポイントをしっかりと抑え、退職手続きを円滑に進めることが、会社側の責務となります。
まとめ

固定残業代は、企業・労働者双方にとってメリットの多い制度ですが、その一方で導入や運用には明確なルールと注意点が伴います。
SoVa税理士ガイド編集部
企業にとっては給与計算の簡素化や採用時の給与競争力アップといった利点がある一方で、制度設計を誤ると法的リスクを伴います。
また、労働者にとっても収入の安定や評価の見える化といったメリットがある一方で、実際の労働時間と賃金が見合わない可能性も否定できません。
固定残業代を正しく活用するには、「透明性」と「適切な運用」がカギ。導入前には制度の趣旨と運用方法をしっかり確認し、労使双方が納得できる形で進めることが大切です。
退職手続きで会社側がやるべき手続きに関するおすすめ記事
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい!