退職手続きはいつまでに何をすべき?手続きの流れを解説!
カテゴリー:
公開日:2025年4月
更新日:2026年1月8日
退職時には、会社側・退職者側の双方にとって重要な「退職手続き」が発生します。
しかし、「退職手続きはいつまでに何をすべき?」「手続きの流れがわからない」と不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
退職手続きには明確な期限が定められているものも多く、いつまでに対応するかによって、その後のトラブル防止やスムーズな転職・生活準備にも大きな影響を与えます。
本記事では、退職手続きにおいて会社側がいつまでに対応すべきこと、退職者側がいつまでに進めるべきことをチェックリスト形式で整理し、退職日以降に必要な手続きもあわせてわかりやすく解説します。
「退職手続きはいつまで?」と迷わないために、ぜひ参考にしてください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、退職手続きを含む役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社側は退職手続きでいつまでに何をすべき?

社員の退職が決定したら、会社側は迅速に「退職手続き」を進めなければなりません。それぞれの退職手続きには「いつまでに」対応すべき期限があるため、漏れなく対応することが重要です。
以下では、退職手続きごとに「いつまでに」何をすべきかを詳しく解説します。
「退職手続き」編集部
法律上は退職の申し出から退職手続きは2週間ですが、実際には引き継ぎや有給消化などを考慮して1ヶ月から2ヶ月程度退職手続きがかかるケースが多数になっています。
①雇用保険に関する退職手続き|退職後10日以内に提出
雇用保険に関する退職手続きでは、以下2つの書類をハローワークに提出する必要があります。
必要な退職手続き
- 「雇用保険被保険者資格喪失届」
- 「雇用保険被保険者離職証明書」(※必要な場合)
いつまでに?
- 退職日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出することが義務付けられています。
注意点
雇用保険被保険者離職証明書は、退職者が失業給付金を申請するために必要ですが、転職先が決まっている場合や本人から求めがない場合は提出不要です。
退職手続きにおける気をつけておきたい注意点

ただし、退職者が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず必ず発行し、提出しなければなりません。
10日以内に退職手続きを完了しないと、退職者に不利益が生じる可能性があり、トラブルの原因にもなるため注意しましょう。
②社会保険に関する退職手続き|退職後5日以内に届け出
社会保険(健康保険・厚生年金)の退職手続きも速やかに対応する必要があります。
必要な退職手続き
- 「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」の提出
- 健康保険証(本人・扶養家族分)の回収と返却
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、退職手続きを含む役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
いつまでに?
- 退職日の翌日から起算して5日以内に年金事務所または事務センターへ届け出る必要があります。
注意点
健康保険と厚生年金は退職日の翌日に資格を喪失します。
たとえば、1月31日が退職日の場合、2月1日が資格喪失日となり、2月5日までに退職手続きを完了させる必要があります。
退職手続きで気をつけておきたい注意点

保険料は、資格を喪失する前月分まで発生するため、給与計算時にも注意が必要です。
③住民税・所得税に関する退職手続き|住民税は退職翌月10日まで/所得税は退職後1か月以内
住民税・所得税についても、退職に伴い必要な手続きを進めます。

合わせて読みたい「従業員の退職手続き」に関するおすすめ記事
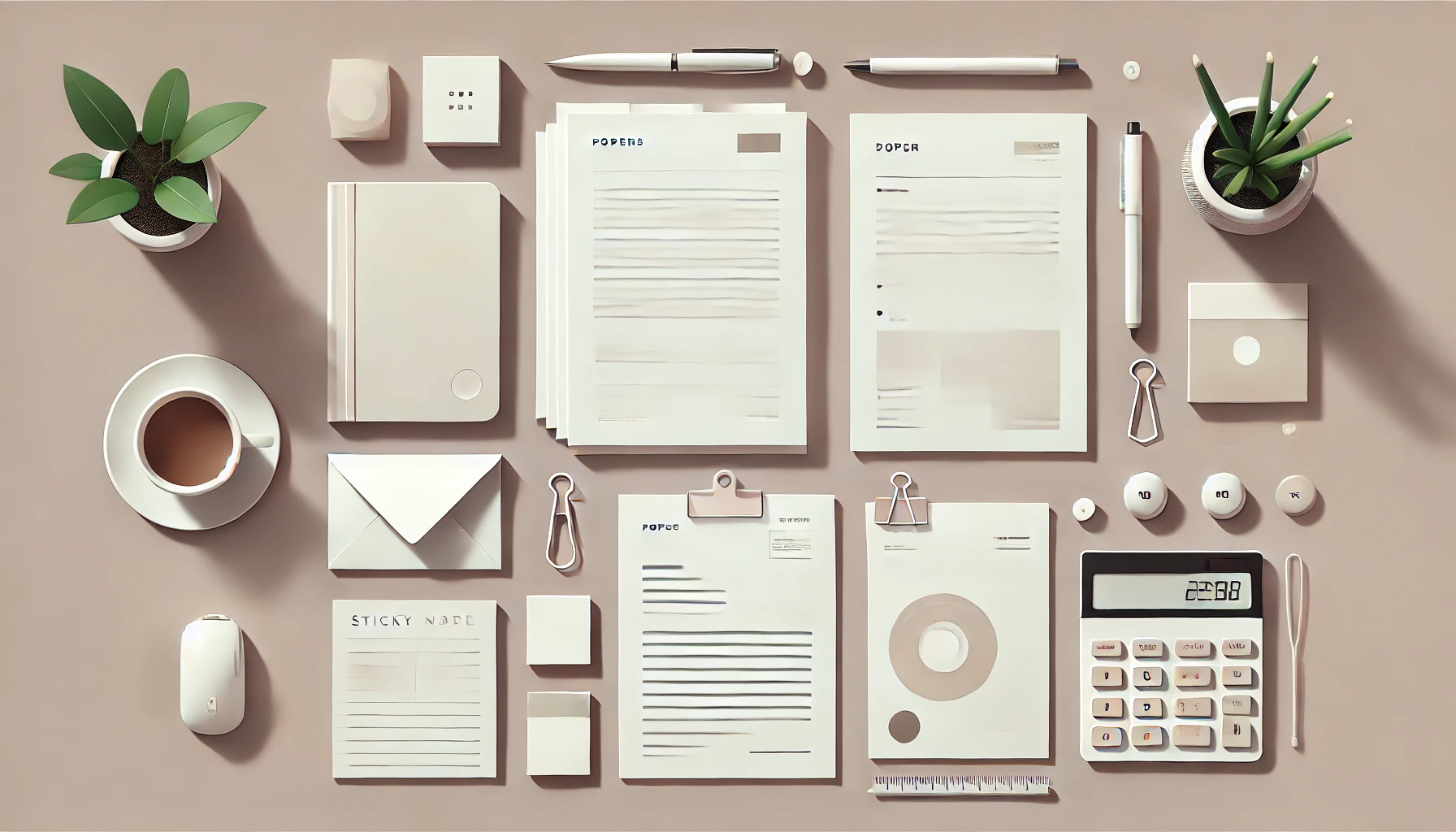
従業員の退職手続きは何をする?必要書類や会社側・従業員側でやることを解説
必要な退職手続き
- 【住民税】「給与支払い報告に係る給与所得異動届」の提出
- 【所得税】源泉徴収票の発行と送付
いつまでに?
- 【住民税】退職翌月10日までに役所へ異動届を提出
- 【所得税】退職日から1か月以内に源泉徴収票を本人に送付
注意点
住民税は特別徴収から普通徴収へ切り替える必要があり、提出期限を過ぎると役所との調整が複雑になります。
所得税に関しては、源泉徴収票を期日までに発行し、退職金が支給される場合は別途「退職所得の源泉徴収票」を発行する必要があります。
退職手続きではいつまでに何をすべきかに関するおすすめ記事:退職手続きの流れややるべきこととは? 退職後の対応についても解説
④退職者から回収すべきもの|退職日までに必ず回収
退職手続きの一環として、退職者から貸与物や重要書類を確実に回収します。
回収すべきもの
- 健康保険証
- パソコン・スマホ・キーカード・制服などの貸与品
- 社員証
- 名刺
- 業務データ・書類
- 退職届(雇用保険手続きで必要になる場合あり)
いつまでに?
- 退職日当日までに回収を完了させておきましょう。
注意点
退職手続きが遅れると、貸与物の未返却や情報漏洩リスクが高まるため、退職日までに必ずチェックリストで管理しながら回収しましょう。
⑤退職者に発行・郵送すべき書類|退職後できるだけ速やかに
退職者に対しては、必要な書類を発行・郵送する手続きも欠かせません。
発行・送付すべき書類
- 離職票(必要な場合)
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
いつまでに?
- 【離職票】発行後、できるだけ速やかに本人に郵送
- 【源泉徴収票】退職日から1か月以内に送付
退職手続きではいつまでに何をすべきかに関するおすすめ記事

退職手続きは複雑でいつまでに何をすべきなのかなど分かりにくい部分もあります。退職手続きの概要や流れについては以下の記事が参考になるでしょう。
退職手続きで会社側はいつまでに何をする?手続き一覧と流れをくわしく解説
注意点
離職票は本人の希望に関係なく発行が必要なケースもあり(59歳未満)、また、退職後の住所変更がないかも事前に確認しておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、退職手続きを含む役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
退職者側は退職手続きでいつまでに何をすべき?

ここでは、一般的な退職手続きの流れとスケジュールについて紹介します。
退職手続きや業務引き継ぎに追われ、周囲に迷惑をかけたり、自分自身が大変になったりしないためにも、退職までにいつまでに何をすべきかを正しく把握し、計画的に進めましょう。
有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」

合わせて読みたい「会社側の退職手続き」に関するおすすめ記事
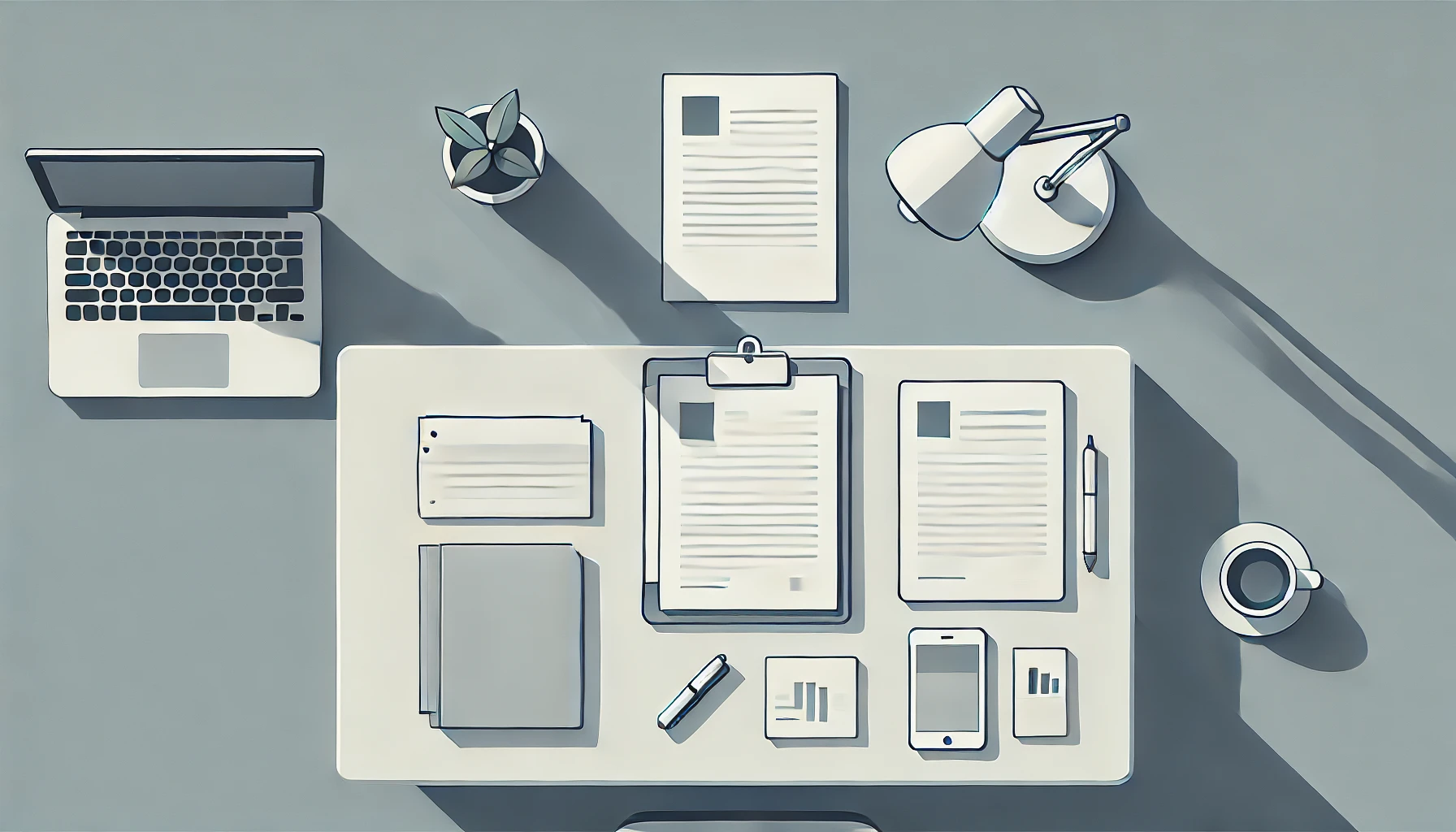
退職手続きでは会社側はいつまでに何をすべき?必要な手続きや対応の注意点を解説!
①退職の意思表示|退職希望日の1〜3カ月前までに
退職手続きのスタートは、退職の意思をいつまでに伝えるかが重要です。
一般的には、退職希望日の1〜3カ月前までに直属の上司に退職の意思を伝えます。
SoVa税理士ガイド編集部
退職手続きではいつまでに何をすべきかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
ポイント
- 民法上では2週間前でも退職可能ですが、会社の就業規則で「1カ月以上前に退職の意思を伝えること」と定められている場合は、そちらを優先しましょう。
- 退職希望日の2〜3カ月前までに伝えることで、引き継ぎや後任者対応に十分な時間を確保できます。
②退職願の提出|退職日の1カ月前までに提出
次に、退職手続きの一環として退職願をいつまでに提出するかを考えます。
就業規則で提出が定められている場合、退職日の1カ月前までに退職願を提出しましょう。
ポイント
- 会社都合退職の場合も、会社から求められた場合は、指定された期日までに提出が必要です。
- 民法上は、遅くとも退職希望日の2週間前までに退職の申し出があれば有効です。
→ つまり、退職願も最遅で2週間前までには提出する必要があります。
③業務の引き継ぎ|退職日の3日前までに完了

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
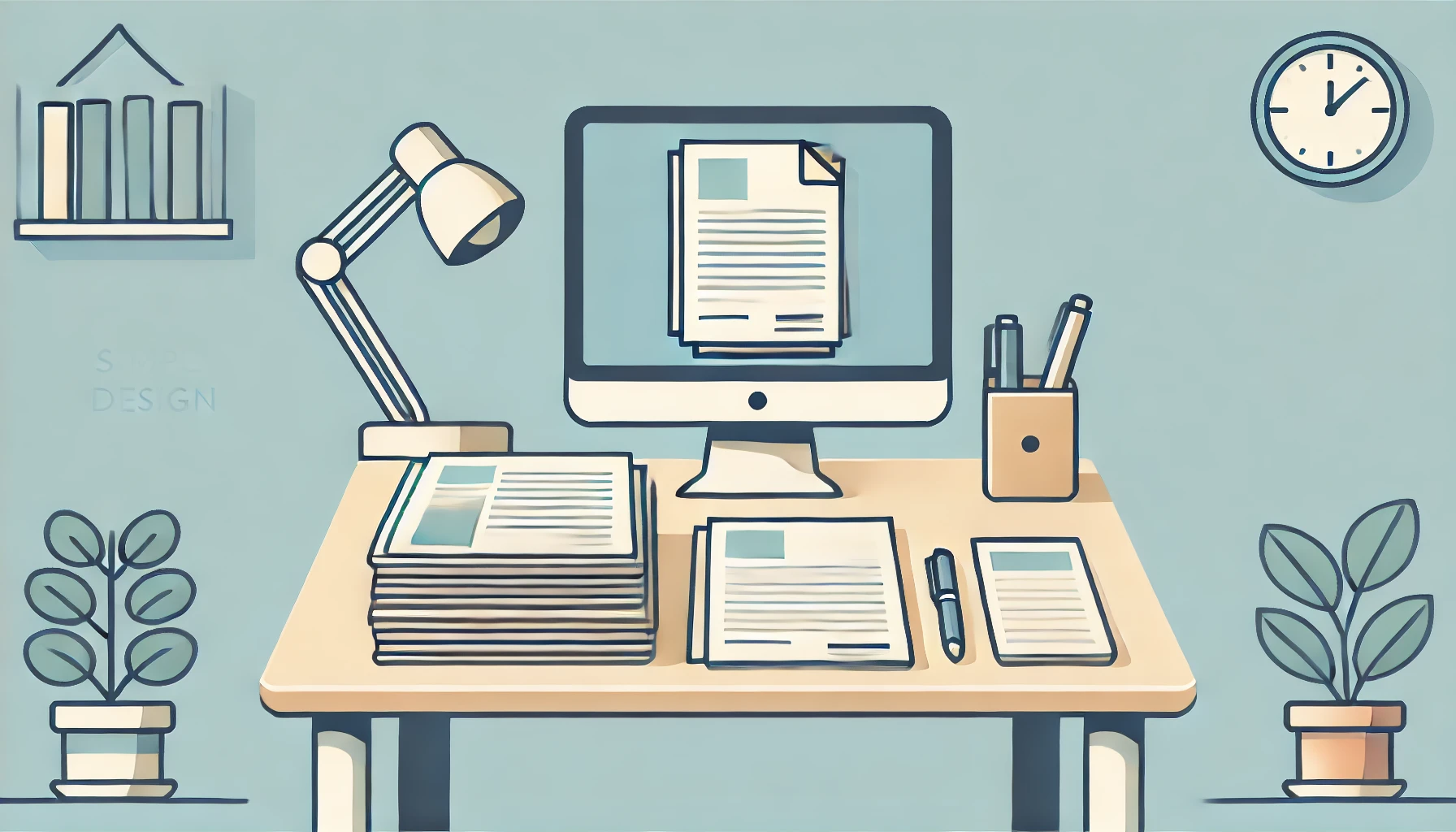
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
業務の引き継ぎは、退職手続きの中でも特に重要です。
業務引き継ぎをいつまでに終わらせるかを逆算して考え、退職日の3日前までに引き継ぎ完了を目指しましょう。
ポイント
- 引き継ぎが間に合わないとトラブルになるため、必ずスケジュールを組み、「いつまでに何を引き継ぐか」を具体的に設定して進めます。
- 業務経緯や注意点をまとめた資料も引き継ぎ完了予定日の前日までに作成しておくと安心です。
④取引先へのあいさつ|退職日の2~3週間前までに完了
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、退職手続きを含む役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
取引先へのあいさつは、いつまでに行うかがマナーとして重要です。
一般的には、退職日の2~3週間前までにあいさつを済ませるのが適切です。
ポイント
- 会社によっては「退職日まで口外禁止」というルールがあるので、いつまでに伝えて良いかは必ず上司に事前確認しましょう。
- あいさつが遅れると先方に不信感を与えるため、できれば2週間前には完了しておくことをおすすめします。
退職手続きではいつまでに何をすべきかに関するおすすめ記事

退職手続きは複雑でいつまでに何をすべきなのかなど分かりにくい部分もあります。退職手続きの概要や流れについては以下の記事が参考になるでしょう。
会社側が行う退職手続きは?期間や順番・方法を解説<チェックリスト付>
⑤有休消化・整理整頓・返却物確認|退職日前日までに完了
有休が残っている場合、いつまでに有休を消化するかを引き継ぎや業務整理と合わせて計画します。
また、備品や貸与物の返却も、退職日前日までに完了しておく必要があります。
ポイント
- 有休消化を希望する場合は、最終出社日の1カ月以上前までに希望を申告するとスムーズです。
- デスクやロッカーの整理整頓、貸与物(PC・IDカード等)は退職日前日までにすべて回収・返却できるよう準備します。
- 「いつまでに何を返却するか」もリスト化して管理すると安心です
退職手続きではいつまでに何をすべきかに関するおすすめ記事

退職手続きは複雑でいつまでに何をすべきなのかなど分かりにくい部分もあります。退職手続きの概要や流れについては以下の記事が参考になるでしょう。
退職手続きはいつまでに何をすべきなのか流れに関する参考記事:「退職手続きで会社側に必要な対応とは?流れや書類、各種保険の計算方法を紹介」
⑥退職(最終出社)当日の退職手続き
退職日当日は、最後の「退職手続き」を行う大事な日です。
この日に行うべきことをいつまでに終わらせるか、しっかり把握しておきましょう。
ポイント
- 健康保険証・社員証・社用機器などの返却は当日の午前中までに完了しておくのが理想です。
- 退職証明書や離職票の受領予定がある場合、いつまでに受け取るか(郵送か直接か)を確認しておきましょう。
- 社内外へのあいさつは、できる限り午前中から昼過ぎまでに済ませましょう。
⑦公的な退職手続き|退職後すぐに開始、14日以内に完了
退職後も公的な退職手続きが必要です。これらもいつまでに手続きするかを意識して進めましょう。
ポイント
- 国民健康保険や国民年金の切り替え手続きは、退職後14日以内に完了させることが法律で定められています。
- 離職票を受け取った後、失業保険の申請もできるだけ早めに行うのが望ましいです。
- 税金(住民税・所得税)の支払い方法変更手続きも、退職後1カ月以内を目安に対応しましょう。
退職日以降に必要な手続きはいつまでにすべき?

従業員の退職日以降も、会社側にはさまざまな退職手続きが発生します。
ここでは、退職手続きが「いつまで」に必要か、発生順に整理して詳しく解説します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、退職手続きを含む役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【退職の翌日から5日以内】社会保険(健康保険・厚生年金)の退職手続き
退職手続きのうち、まず対応が必要なのが社会保険の資格喪失手続きです。
従業員の退職後、翌日から起算して5日以内に、「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出しましょう。
退職手続きではいつまでに何をすべきかに関するおすすめ記事

退職手続きは複雑でいつまでに何をすべきなのかなど分かりにくい部分もあります。退職手続きの概要や流れについては以下の記事が参考になるでしょう。
会社側の退職手続きは何日以内?13項目のチェックリスト付きガイド
必須対応
- 「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出【退職後5日以内】
- 本人および扶養親族分の健康保険証を回収し添付
※回収できなかった場合は「被保険者証回収不能届」を添付
提出方法
- 郵送、窓口持参、または電子申請で手続き可能
注意点
在職中に70歳到達者がいる場合は、専用様式が必要です。
退職手続きで「いつまで」に回収すべきもの(健康保険証など)も、あわせて整理しましょう。
【退職の翌々日から10日以内】雇用保険の退職手続き
次に進めるべき退職手続きは、雇用保険の資格喪失手続きです。
退職の翌々日から数えて10日以内に、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。
必須対応
- 「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出【退職後10日以内】
- 「雇用保険被保険者離職証明書」を提出(必要な場合)
添付すべき書類
- 出勤簿、賃金台帳、退職届など
注意点
離職票の発行は、会社が提出した証明書を基にハローワークが行います。いつまでに必要書類を揃えるかも事前に確認しておきましょう。
【退職翌月10日まで】住民税に関する退職手続き
住民税に関しても、退職手続き上、迅速な対応が求められます。
住民税の手続きは、退職月の翌月10日までに完了させる必要があります。
必須対応
- 【転職先が決まっている場合】
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、転職先に引き渡し、転職先が提出 - 【再就職まで期間がある場合】
退職者本人が居住地の市区町村へ「異動届出書」を提出【退職翌月10日まで】
注意点
SoVa税理士お探しガイド編集部
退職月や再就職有無により、普通徴収・特別徴収・一括徴収が異なります。
いつまでに本人に説明・書類準備するかも明確にしておきましょう。
【退職から15日以内】健康保険被保険者資格喪失確認通知書の送付
社会保険の資格喪失手続きを完了すると、健康保険被保険者資格喪失確認通知書が会社に届きます。
この通知書も、退職から15日以内を目安に、退職者へ速やかに送付する必要があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、退職手続きを含む役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
必須対応
- 健康保険被保険者資格喪失確認通知書を受領後できるだけ早く退職者に郵送
注意点
退職者は、保険の切り替え手続きにこの通知書を使用します。退職手続きでいつまでに送るか、社内フローを整備しておきましょう。
【退職から1カ月以内】離職票の送付
離職票は、雇用保険の失業給付申請に不可欠な書類です。
ハローワークから交付されたら、退職から1カ月以内を目安に、速やかに退職者へ郵送しましょう。
必須対応
- 離職票の受領後、すぐに退職者へ郵送
注意点
遅延すると失業手当の受給手続きに支障が出ます。
いつまでに離職票を送付するかを意識して、対応漏れを防ぎましょう。
【退職から1カ月以内】源泉徴収票の発行・送付
源泉徴収票の発行も退職手続きの必須対応です。
退職者には、退職日から1カ月以内に、源泉徴収票を送付しなければなりません。
必須対応
- 退職源泉を記載した源泉徴収票を作成
- 退職後1カ月以内に本人へ送付
注意点
同年中に再就職する場合、転職先で年末調整に使います。
再就職しない場合は、本人に確定申告が必要となる旨も退職手続き時にいつまでに説明するかを計画しておきましょう。
退職手続きではいつまでに何をすべきかに関するおすすめ記事:退職届はいつまでに出すべき?提出するまでの手続きも解説!
退職手続きにおける注意点

退職手続きは、すべての従業員に対して同じパターンで進められるわけではありません。
場合によっては、「この場合の退職手続きはいつまでにどう進めればいいのか」と悩むこともあるでしょう。
ここでは、特に注意が必要なケース別に、退職手続きでいつまでに何をすべきかをわかりやすく解説します。
注意点①:財形貯蓄制度を利用している場合|退職手続きでいつまでに解約するか
財形貯蓄制度を利用している従業員は、退職日以降この制度を利用できなくなります。
SoVa税理士ガイド編集部
そのため、退職手続きの一環として退職日までに財形貯蓄の解約手続きを完了させなければなりません。
ポイント
- 解約手続きは退職日までに必ず完了させること
- もし転職先で財形貯蓄を継続する場合は、「勤務先異動申告書」を退職日までに提出する必要があるため、本人に説明しておきましょう。
注意点②:従業員貸付制度を利用している場合|退職手続きでいつまでに返済を完了するか
従業員貸付制度を利用していた場合も、退職手続きに注意が必要です。貸付金の返済は、退職日までに完済することが原則となっています。
ポイント
- 退職手続きの中で、いつまでに返済を終える必要があるかを明確に伝える
- 残高や返済計画を事前に確認し、必要があれば繰り上げ返済の案内も行う
注意点③:外国人従業員が退職する場合|退職手続きでいつまでに書類を提出するか
外国人従業員も基本的な退職手続きは日本人と同様ですが、追加で対応すべき手続きもあります。
特に、「在留カード番号記載様式」は、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出しなければなりません。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、退職手続きを含む役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
ポイント
- 「在留カード番号記載様式」の提出は、退職後10日以内に必須
- 退職証明書も、外国人従業員には退職手続き時に必ず交付する必要あり(転職時に入国管理局へ提出するため)
注意点
- 外国人従業員には、退職手続きの「いつまでに」行う各種説明(就業規則・手続き期限)も丁寧に行うことが求められます。
注意点④:従業員から有給休暇消化の申し出があった場合|退職手続きでいつまでに調整するか
退職前に「有給休暇を全て消化したい」という申し出があった場合、基本的に会社側はこれを拒否できません。
したがって、退職手続きの中で、いつまでに有給休暇を消化するかを明確にスケジュールに落とし込む必要があります。
退職手続きではいつまでに何をすべきかに関するおすすめ記事

退職手続きは複雑でいつまでに何をすべきなのかなど分かりにくい部分もあります。退職手続きの概要や流れについては以下の記事が参考になるでしょう。
退職したらすること【基本の5つ】必要な書類や手続きを期限順に分かりやすく解説
ポイント
- 有給休暇の取得完了は退職日までに確実に終わらせるよう調整
- もし業務都合で消化できない場合は、有給の買い取りを検討。ただし、就業規則に買い取りルールが明記されている場合に限る。
注意点
- 有給買い取りも、「いつまでにどの方法で処理するか」事前に社内確認を取っておくとスムーズです。
注意点⑤:退職者の個人情報管理|退職後いつまで保管すべきか
退職後も、退職手続きの一環として個人情報の適切な管理が求められます。
退職手続きのここがポイント!

労働基準法109条により、退職後3年間(当分の間)個人情報を保管しなければなりません。
ポイント
- 退職手続きで収集した書類・データは最低3年間保管
- 保管期限を知らずに早期廃棄したり、逆に不要に長期間保存することのないよう注意
- 3年経過後は、適切な方法で速やかに破棄する
注意点
- いつまでに破棄できるか(保管満了日)も、管理表などに記録しておくとよいでしょう。
まとめ

専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、退職手続きを含む役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
退職手続きではいつまでに何をすべきかに関するおすすめ記事

退職手続きは複雑でいつまでに何をすべきなのかなど分かりにくい部分もあります。退職手続きの概要や流れについては以下の記事が参考になるでしょう。
会社を辞めたら何をする? 退職後にすべき手続きの順番をわかりやすく説明!
退職手続きは、いつまでに何をすべきかを正しく把握しておくことが、円満な退職のために不可欠です。会社側も退職者側も、それぞれが担う退職手続きを期限内に進めることで、トラブルや無用な手間を防ぐことができます。
本記事で紹介した「退職手続きはいつまでに何をすべきか」の流れや注意点を押さえ、チェックリストを活用しながら、一つひとつ確実に対応していきましょう。
適切なタイミングで退職手続きを完了させ、新しいステージに向けてスムーズなスタートを切ってください。
SoVa税理士ガイド編集部
退職手続きではいつまでに何をすべきかについてさらに詳しく知りたい人は以下の記事もご参照ください。
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!