決算賞与の平均相場はいくら?決算賞与の支給要件や支給時期も解説!
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2025年11月14日
決算賞与は、企業の業績が良好だった期末に、従業員へ感謝の気持ちを込めて支給される特別なボーナスです。しかし、「決算賞与の平均額はいくらなのか?」「他社の決算賞与の平均相場と比べて適正かどうかがわからない」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実際、決算賞与の平均は企業規模や業種によってばらつきがあり、一律に語ることはできません。それでも、決算賞与の平均支給額や決算賞与の平均的な支給時期、さらには決算賞与を平均的にどの程度の利益から支給しているのかといった実務的な目安を知ることは、非常に重要です。
本記事では、決算賞与の平均金額を徹底的に調査・解説しつつ、決算賞与の平均的な支給スケジュールや、損金算入を可能にするための支給要件、税務上の注意点についても丁寧にまとめました。「自社の決算賞与が平均的な水準かどうかを知りたい」「これから決算賞与の導入を検討しているが、平均的な運用方法が知りたい」という方にとって、本記事は具体的かつ実践的な情報源となるはずです。
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均支給額を知ることで、企業はより納得感のある報酬制度を構築でき、従業員のモチベーション向上や定着率アップにもつながります。ぜひ最後までご覧ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
決算賞与とは
決算賞与とは、企業が事業年度末の決算において利益を確定させた後、その利益の一部を従業員に還元する目的で支給する臨時の賞与のことです。通常の夏季賞与や年末賞与とは異なり、決算賞与は業績に大きく連動し、支給の有無や金額も会社の経営判断によって大きく異なります。そのため、決算賞与の平均額や平均的な支給タイミングには幅があり、明確な相場があるわけではありません。
ただし、一般的な傾向として、決算賞与の支給額の平均は従業員1人あたり数万円~数十万円程度となっており、平均的には本給の1か月分前後が支給されるケースも多く見られます。
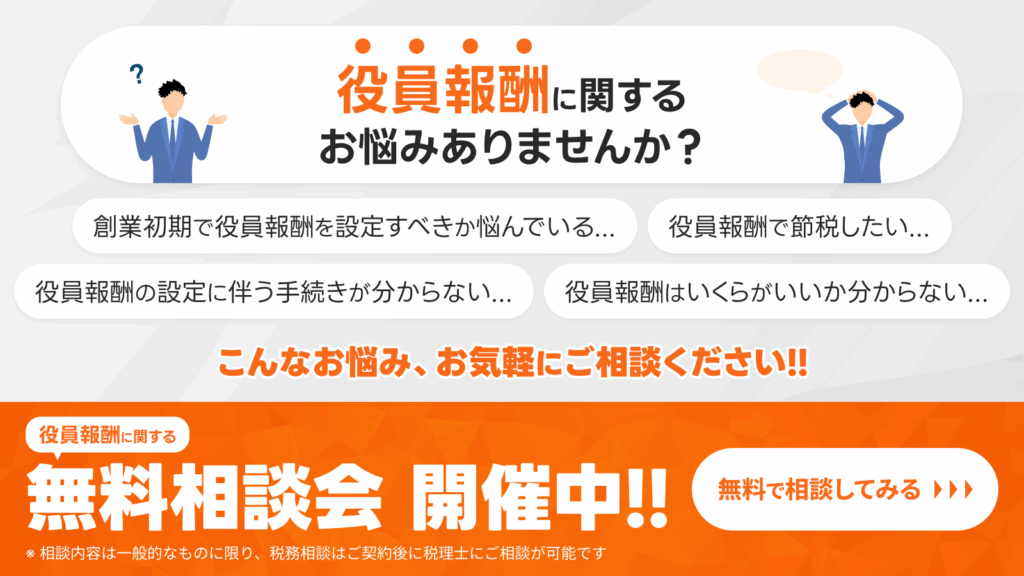
決算賞与の平均に関する注意点

決算賞与の平均は業種、規模、利益水準によって大きく異なり、同業他社と比較して決算賞与の平均額が高いか低いかを判断するには注意が必要です。
企業側にとっては、決算賞与を適切に支給することで、節税対策や損金算入による法人税の圧縮にもつながります。税務上、決算賞与を当期の損金に計上するためにはいくつかの要件があり、正しく手続きを踏むことが重要です。また、決算賞与の平均的な支給率や、社会保険料・所得税の影響を踏まえた決算賞与の平均的な手取り額を把握しておくことも、経営判断のうえで欠かせません。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
決算賞与の平均に関するおすすめ記事

決算賞与やボーナスの平均や支給時期などについては、以下の記事も是非参考にしてください。
決算賞与の平均に関する参考記事:「中小企業の賞与の平均額はいくら?決算賞与の平均額や賞与の特徴も」
決算賞与の平均額はいくら?

「決算賞与の平均はどれくらいなのか?」という疑問を持つ方は非常に多いですが、実は決算賞与の平均額は、他の賞与と比べて把握が難しいのが実情です。なぜなら、決算賞与の平均的な支給額は企業ごとに大きく異なり、業績や支給基準、従業員の役割などによって支給額にばらつきがあるため、正確な平均金額を一律に示すことができません。
「決算賞与の平均額」編集部
一般的な賞与と違って、決算賞与の平均水準は企業の利益に直結して決定されます。
ある企業では、決算期の利益の一部を従業員に還元する形で平均数万円程度の決算賞与を支給しているケースもあれば、特に業績に大きく貢献した従業員に対して平均より高額な決算賞与が支払われることもあります。実際には、決算賞与の平均額が10万円未満の企業もあれば、平均で30万円以上支給している企業も存在するなど、決算賞与の平均的な相場には大きな幅があるのが現状です。
また、全社員一律に一定額を支給する企業と、部門別・役職別に異なる基準で支給する企業とでは、決算賞与の平均額の考え方も異なります。同じ「平均」という言葉でも、「全社員を対象にした平均」、「役職ごとの平均」、「貢献度ごとの平均」など、どの軸で捉えるかによって数値の印象も大きく変わってきます。そのため、「他社の平均を参考にしたい」と考える場合でも、平均の定義を明確にしないと、かえって実態とのズレが生じることがあります。
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均や、支給時期、支給要件は以下のサイトも是非ご覧ください。
決算賞与の平均に関する参考記事:「決算賞与とは業績に連動した賞与!ボーナスとの違いは「金額・時期」!」
さらに、決算賞与の平均額を考える際には、従業員の手取り額にも注目すべきです。支給額が同じでも、社会保険料や所得税の源泉徴収によって、実際に受け取る金額、つまり手取りの平均額は異なります。企業が支給する総額と、従業員が受け取る実質的な手取りの平均には差が生じるため、「支給額ベースの平均」と「手取りベースの平均」は分けて考える必要があります。

合わせて読みたい「役員賞与の社会保険料」に関するおすすめ記事

決算賞与にかかる社会保険料の計算方法は?支給する際の注意点も解説!
このように、決算賞与の平均金額や平均的な支給傾向を把握するには、業種・規模・支給方針などを踏まえたうえで、自社に合った「基準」を明確にすることが大切です。世間一般の平均値だけを鵜呑みにするのではなく、「利益に応じて柔軟に支給する」「社内ルールに基づいて決定する」といった経営判断が、適正で納得感のある決算賞与の平均的運用につながります。
決算賞与の平均的な算出条件と損金算入のための重要なポイント
企業が従業員に決算賞与を支給する場合、その決算賞与が税務上の損金算入として認められるかどうかは非常に重要なポイントです。特に、決算賞与の平均額や平均的な支給額を参考に支給計画を立てる場合でも、税法上の要件を満たさなければ、決算賞与の平均的な支給方針があっても、損金扱いはされません。
「決算賞与の平均額」編集部
まず理解しておくべきなのは、決算賞与の平均額に関係なく、損金として認められるためには厳密な条件があるという点です。
平均的な決算賞与の支給基準を設定していたとしても、下記の要件を満たしていなければ、たとえ支給総額が平均より高額な決算賞与であっても損金として処理することはできません。
決算賞与の平均に関するおすすめ記事

決算賞与やボーナスの平均や支給時期などについては、以下の記事も是非参考にしてください。
「中小企業のボーナス平均額は?何ヶ月分?支給なしの割合や大企業との差も解説」
決算賞与の損金算入には平均的対応だけでなく明確な3要件が必須
1つ目の要件は、決算日までに、支給対象となる従業員すべてに対して個別の決算賞与額を通知することです。ここでは平均支給額だけでなく、各人への具体的な金額の通知が必要です。
2つ目の要件は、通知を受けた全従業員に対して、決算日の翌日から1か月以内に通知どおりの金額を支給することです。これは平均支給時期が1か月以内という基準に該当している必要があり、1人でも通知通りに支給されなかった場合、全体の決算賞与の平均額に関係なく損金算入が認められないことになります。

合わせて読みたい「決算賞与 経費」に関するおすすめ記事

決算賞与を経費にするには?損金算入の条件や支給するメリットを解説!

「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均や、支給時期、支給要件は以下のサイトも是非ご覧ください。
決算賞与の平均に関する参考記事:「決算賞与とは?ボーナスと違う?支給時期や平均額、算出要件などを解説」
3つ目の要件は、通知した決算賞与の平均支給額や個別金額を含めた支給予定分を、当期の帳簿上にきちんと損金経理していることです。平均的な処理時期に沿って記帳し、経理処理を完了させておくことが条件です。
決算賞与の平均額を決める際にも税務手続きに注意
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
企業が決算賞与の平均額を設定する際には、支給総額に見合った税務対応が必要です。仮に業界平均水準の決算賞与を参考にしていたとしても、通知ミスや支給遅延があれば、税務署はその決算賞与の平均的妥当性にかかわらず、損金算入を否認する可能性があります。

合わせて読みたい「役員賞与とボーナスの違い」に関するおすすめ記事

決算賞与とは?ボーナスとの違いや支給する際の注意点について解説!
また、決算賞与にかかる社会保険料の処理も注意すべき点です。社会保険料の算出時期と損金算入のタイミングがずれることがあるため、決算賞与の平均額に基づく負担見積もりとは別に、経理処理上のスケジュール管理も不可欠です。
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均や、支給時期、支給要件は以下のサイトも是非ご覧ください。
決算賞与の平均に関する参考記事:「決算賞与は利益の何パーセントにすれば良い?決算賞与の決め方の基準も」
決算賞与の平均支給スケジュールと実務上の留意点
たとえば3月決算の企業であれば、決算賞与の平均支給日は4月末までに設定されることが多くなります。これは、1か月以内に支給という要件に合致する平均的な支給タイミングとされており、従業員全員に確実に支給されることで、ようやくその決算賞与の平均額が損金算入対象として認められます。
決算賞与の平均に関するポイント!

通知書の控え、支払証明、経理帳簿などの決算賞与関連書類の平均的な保存期間や記録方法にも注意が必要です。これらを整備しておくことで、将来的な税務調査にも対応しやすくなります。
「決算前にできる節税方法」編集部
決算前にできる節税方法に関しては、【決算前に経費を使う理由とは?利益調整や節税対策について解説】の記事も是非ご覧ください。
決算賞与の平均額を検討する際には、見た目の金額だけでなく、その平均支給額が損金として処理可能かどうかという視点を持つことが不可欠です。平均的なルールに沿いつつ、企業ごとの実態に応じた正しい処理を行いましょう。
決算賞与にかかる税金と社会保険料
決算賞与とは、企業がその年度の業績や利益に応じて、従業員へ支給する特別な賞与です。通常の賞与とは異なり、決算期にあわせて支給されるものであり、決算賞与の平均支給額や決算賞与の平均的な手取り額がいくらになるのかは、多くの経営者や従業員にとって重要な関心事項となっています。
「合同会社の決算申告」編集部
決算や平時に合同会社にかかる税金については、【合同会社が売上なしでも払う税金とは?赤字(利益ゼロ)の場合の納税について解説】の記事も是非ご覧ください。
この決算賞与は税務上「損金」として処理できるメリットがある一方で、実際に支給される際には税金や社会保険料が差し引かれます。
決算賞与の平均に関するおすすめ記事

決算賞与やボーナスの平均や支給時期などについては、以下の記事も是非参考にしてください。
決算賞与の平均に関する参考記事:「決算賞与とは? 転職前に知りたい決算賞与の概要を解説」
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均額を把握するだけでなく、控除後の決算賞与の平均手取り金額を正しく見積もることが非常に重要です。
決算賞与の平均手取り額の目安とは?
一般的に、決算賞与の額面金額に対して約80%程度が手取りとして受け取れるとされており、これは決算賞与の平均的な手取り率として広く認識されています。たとえば、決算賞与の平均支給額が30万円の企業であれば、控除後の平均的な手取り額は24万円前後となります。
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均や、支給時期、支給要件は以下のサイトも是非ご覧ください。
「決算賞与とは?業績に応じて支給する?ボーナスとの違いや損金算入の要件を解説」
以下の計算式は、決算賞与の平均的な手取り額を算出するための基本的な方法です。
決算賞与の額面 ✕ 80% = 決算賞与の平均的な手取り額
もちろん、社会保険料や扶養の有無などによって変動はありますが、多くのケースでこの計算が決算賞与の平均的手取り水準の目安になります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
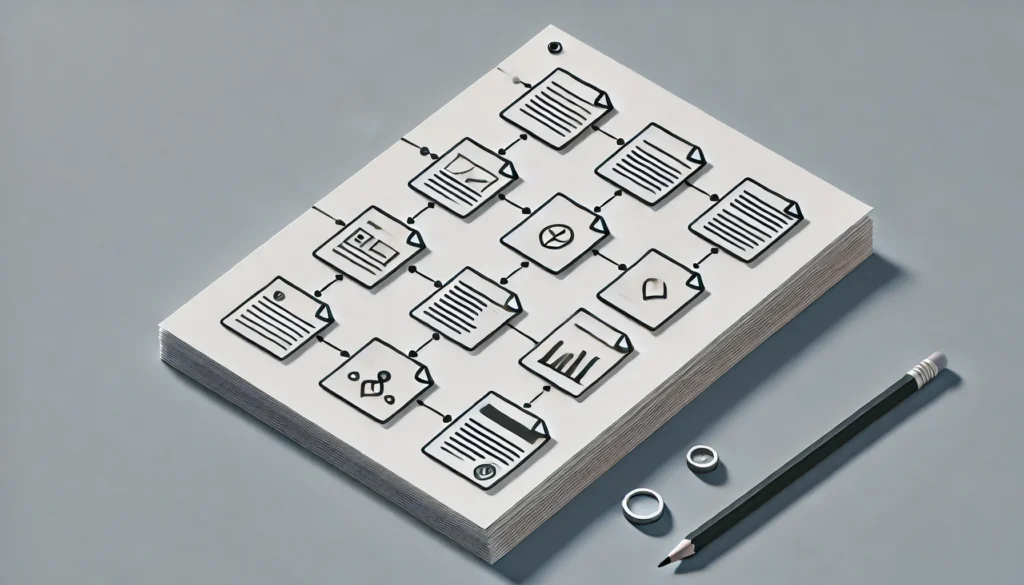
決算賞与に課される税金の計算方法
決算賞与に課税される税金は「所得税」です。これは通常の給与と同様、源泉徴収の対象となります。
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均的な税率や控除の計算方法は、以下のようなプロセスで導かれます。
- 前月の給与から社会保険料等を控除して課税対象額を算出
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」を用いて、該当する税率を確認
- 決算賞与の支給額から社会保険料を差し引いた額に、税率を乗じて所得税額を計算
このような流れで算出される税額は、決算賞与の平均的な所得税額として取り扱われます。
決算に関する参考記事:「法人の決算月は税理士に相談すべき?決め方と変更方法について解説!」
特殊なケース(決算賞与が前月給与の10倍以上など)では別の計算方法が必要ですが、それらは決算賞与の平均的な支給状況からは外れるため、ここでは省略します。

合わせて読みたい「賞与(役員賞与)の計算方法シミュレーション」に関するおすすめ記事

賞与(役員賞与)の計算方法をシミュレーション!手取りや・税金・社会保険料はいくらになる?
決算賞与にかかる社会保険料の平均的な計算方法
「合同会社の決算申告」編集部
決算や平時に合同会社にかかる税金については、【合同会社が売上なしでも払う税金とは?赤字(利益ゼロ)の場合の納税について解説】の記事も是非ご覧ください。
決算賞与からは、以下の3つの社会保険料が控除されます。これらの合計が、決算賞与の手取り額を大きく左右するため、平均的な控除率を把握することが重要です。
- 健康保険料:賞与額(1,000円未満切り捨て)× 保険料率 × 1/2
- 厚生年金保険料:賞与額 × 年金保険料率(例:18.3%)× 1/2
- 雇用保険料:賞与額 × 雇用保険料率(例:0.3%)
たとえば、賞与額が30万円だった場合の決算賞与の平均的社会保険料控除額はおおよそ4〜5万円程度が想定され、これに加えて所得税が差し引かれることで、最終的な決算賞与の平均的手取り金額が決定します。
「賞与を使った節税方法」編集部
役員賞与を使った節税方法については、【役員賞与を活用した節税方法とは?具体的な手続き方法や注意点についても解説!】のサイトも是非ご覧ください。

合わせて読みたい「役員賞与の決め方」に関するおすすめ記事

決算賞与の決め方とは?支給するメリット・デメリットや注意点も解説!
決算賞与の正確な手取り額を算出する計算式
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均手取り額を具体的に把握するためには、以下の式を利用するのが有効です。
決算賞与の額面 -(所得税 + 社会保険料)= 決算賞与の正確な手取り額
この計算式は、どの企業にも適用できる決算賞与の平均的計算方法として広く活用されています。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
決算賞与のメリット・デメリットとは?
決算賞与は、企業が事業年度の業績に応じて従業員に支給する特別な賞与であり、決算賞与の導入によるメリットとデメリットを正しく理解することが、効果的な制度運用につながります。ここでは、決算賞与の活用方法や損金算入要件、平均的な実態、税務上の注意点まで網羅的に解説します。
決算賞与の主なメリット
決算賞与のメリット①
決算賞与を損金算入すれば法人税の節税効果がある
決算賞与の平均に関するおすすめ記事

決算賞与やボーナスの平均や支給時期などについては、以下の記事も是非参考にしてください。
「【2025年最新版】中小企業のボーナス平均額は何ヶ月分?気になる中央値まで解説」
決算賞与は、税務上の一定条件を満たすことで当期の損金に算入でき、結果として法人税の負担を軽減できるという点で、企業にとって非常に大きな節税メリットをもたらします。決算賞与を損金算入するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 決算日までに、すべての従業員に対して決算賞与の金額を個別に通知
- 決算日の翌日から1か月以内に、通知内容通りに決算賞与を全員に支給
- 決算賞与の支給金額を当期に経理処理し、損金として計上
このように、決算賞与の損金算入は節税と利益調整の手段として有効であり、多くの企業で導入されています。
決算賞与の平均に関するポイント!

業績が好調な年度に決算賞与を活用することで法人税の支払額を抑えることができ、税務戦略の一環としても有用です。
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均や、支給時期、支給要件は以下のサイトも是非ご覧ください。
決算賞与の平均に関する参考記事:「決算賞与とは? 支給時期、もらえる人、メリット・デメリット」
決算賞与のメリット②
決算賞与によって従業員のモチベーションが向上
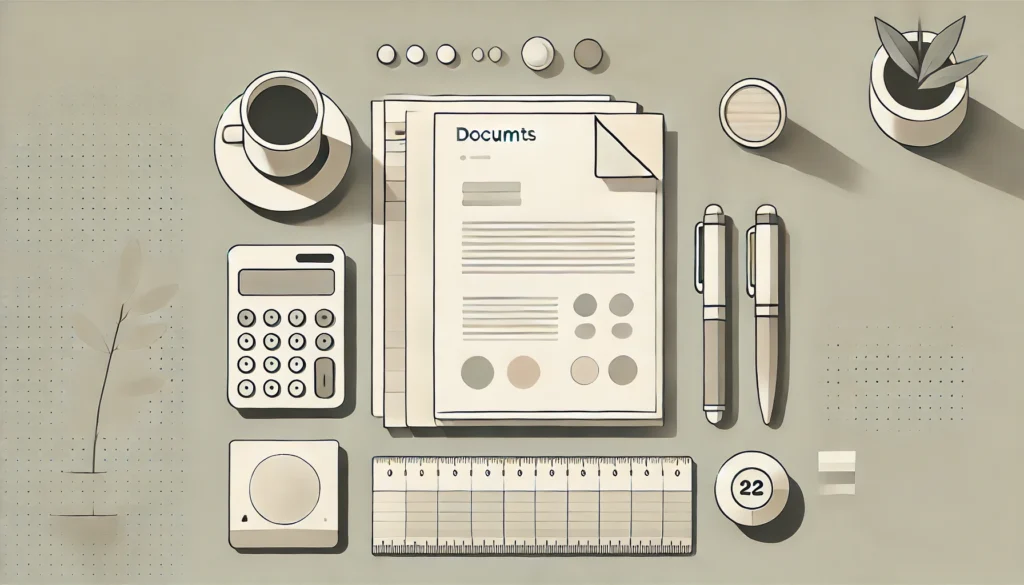
決算賞与は、業績に貢献した従業員に対する還元の意味合いが強く、従業員のモチベーションアップに直結するインセンティブです。企業が決算賞与を通じて利益を還元する姿勢を示すことで、従業員のやる気や会社への信頼感が高まり、組織のパフォーマンス向上にもつながります。
「決算賞与の平均額」編集部
決算賞与の平均や、支給時期、支給要件は以下のサイトも是非ご覧ください。
決算賞与の平均に関する参考記事:「ボーナス平均支給額の実態調査【最新版】(冬・夏、年代別、職種別の賞与)」
実際に、決算賞与の支給平均額は企業ごとに差があるものの、支給されることで従業員の満足度が上がるという点は共通しています。平均的な決算賞与の支給額を参考にしながら、自社に合ったバランスを模索することが重要です。
決算賞与の注意点とデメリット
決算賞与のデメリット①
決算賞与の支給によりキャッシュが減る
決算賞与を支給すること自体はプラスの要素ですが、その反面、企業にとっては現金流出を伴うため、キャッシュフロー管理が不可欠です。
「決算賞与の平均額」編集部
特に、決算賞与の支給額が高額になると、納税資金や仕入資金に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、決算賞与には事業主負担の社会保険料も発生するため、税務上の損金効果はあるものの、支出としてのインパクトも無視できません。
決算賞与の平均に関するポイント!

支給時期が法人税の納付時期と重なることもあるため、決算賞与を支給する際は資金繰りをしっかりと管理しましょう。
SoVa税理士お探しガイド編集部
役員賞与などにかかる所得税については以下の記事も是非参考にしてください。
「 役員賞与に所得税はかかる?役員賞与を支給する際の注意点や、損金算入し節税する方法も紹介!」
決算賞与のデメリット②
決算賞与の支給が恒常化すると逆効果になることも
一度決算賞与を支給した企業では、従業員が「来年ももらえるもの」と期待するケースが少なくありません。仮に翌年、業績が悪化して決算賞与の支給を見送った場合、従業員のモチベーションが下がるリスクが高まります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
決算賞与の平均に関するおすすめ記事

決算賞与やボーナスの平均や支給時期などについては、以下の記事も是非参考にしてください。
決算賞与の平均に関する参考記事:「決算賞与の支給要件や平均額は? 支給する時期やメリットも紹介」
こうした事態を避けるためには、決算賞与の支給基準をあらかじめ明示し、「業績連動であること」を従業員に周知しておく必要があります。制度の透明性を保つことで、納得感のある報酬設計が実現します。
【参考】中小企業の賞与の平均額はどれくらい?
中小企業における賞与の平均額を知ることは、自社の給与水準を客観的に把握するうえで非常に重要です。ここでは、厚生労働省の「毎月勤労統計調査(2022年年末)」をもとに、従業員数ごとの平均賞与額や平均的な支給割合を詳しく紹介します。
「決算賞与の平均額」編集部
企業の従業員数別に見た賞与の平均支給額と、所定内給与に対する平均支給月数は下表のとおりです。
| 従業員数 | 賞与の平均支給額 | 賞与の平均支給割合(所定内給与) |
|---|---|---|
| 5~29人 | 274,651円 | 平均1.07カ月分 |
| 30~99人 | 354,645円 | 平均1.23カ月分 |
| 100~499人 | 452,892円 | 平均1.36カ月分 |
| 500~999人 | 543,114円 | 平均1.57カ月分 |
| 1,000人以上 | 747,054円 | 平均1.92カ月分 |
このように、平均賞与は従業員数の増加とともに上昇する傾向があり、企業規模が大きいほど賞与の平均額は高くなる傾向があります。特に、1,000人以上の企業では、賞与の平均支給額が70万円を超え、給与の約2カ月分に相当するという水準です。
一方、中小企業に分類されるのは、製造業で300人以下、サービス業・卸売業では100人以下、小売業では50人以下とされています。これらの基準に基づくと、上記表における「5~29人」や「30~99人」区分が、中小企業の平均賞与として参考になるゾーンといえます。平均支給額を見ると、30人未満の企業では約27万円、30~99人の企業では35万円程度と、賞与の平均水準に大きな差があることも分かります。

決算賞与の平均に関するおすすめ記事

決算賞与やボーナスの平均や支給時期などについては、以下の記事も是非参考にしてください。
「ボーナス(賞与)の平均はいくら?年代別の支給額など基礎知識を解説」
このようなデータを活用することで、「自社の賞与は業界平均と比較してどうか?」「従業員の満足度向上にはどの程度の賞与が妥当か?」といった視点での判断がしやすくなります。平均値はあくまで目安ですが、企業の人事戦略や予算編成の参考として、賞与の平均的傾向を知ることは大きな意味を持ちます。
Q&A|よくある質問
Q: 決算賞与の平均相場はいくら?中小企業の実態は?
決算賞与の平均は業種や会社の規模によって大きく異なりますが、中小企業の場合、従業員1人あたり10万円~30万円程度が一般的とされています。実際の支給額は利益の何パーセントを決算賞与に充てるかによって決まることが多く、目安としては「当期純利益の5〜20%程度」を想定する企業が多い傾向です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
特に中小企業では、業績が良かった年度にのみ決算賞与を支給するケースが目立ちます。つまり、決算賞与の平均はあってないようなもので、あくまで利益状況とキャッシュフローが大きく影響します。
Q: 決算賞与を支給する際の「利益の何パーセント」が適正?
中小企業が決算賞与の支給を検討する場合、「利益の何パーセントまでを賞与に回すべきか」が悩みどころです。実務上では、利益の10%前後を目安とする企業が多く、これを超えると資金繰りへの影響が出る可能性があるため慎重に検討する必要があります。
仮に当期純利益が500万円であれば、決算賞与として50万円程度を配分するケースが平均的です。中小企業の場合は、設備投資や内部留保とのバランスも考慮しなければなりません。
Q: 決算賞与の支給時期はいつがベスト?
決算賞与はその名の通り「決算後」に支給されるもので、税務上は「決算確定日から1か月以内」に支払う必要があります。例えば、3月末決算の中小企業であれば、賞与の支払いは4月末までに完了している必要があります。
役員報酬として支給する場合にここで遅れてしまうと、損金として認められず、せっかくの節税効果がなくなってしまいます。支給のタイミングも重要な税務ポイントになるため、会計処理とあわせてスケジュールを管理しましょう。
まとめ|決算賞与の平均額
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
決算賞与は、業績によって支給される特別な報酬制度であり、従業員へのインセンティブとしても経営戦略としても非常に重要です。企業ごとに決算賞与の支給金額や決算賞与の支給基準は異なりますが、他社との比較を行うには決算賞与の平均額や決算賞与の平均的な支給時期といったデータが参考になります。
特に、中小企業においては、決算賞与の平均支給額や決算賞与の平均支給割合を把握することで、無理のない範囲での支給設計が可能になります。さらに、決算賞与を損金算入するための要件を正しく理解し、制度として有効活用することが、節税と従業員満足度の両立につながります。
業績に応じた柔軟な支給を行うには、毎年の決算賞与の平均動向や、他社の決算賞与の平均相場と自社の支給実績を照らし合わせることが大切です。こうした決算賞与の平均データを積極的に活用することで、従業員にとっても納得感があり、企業にとっても無理のない決算賞与の支給体制を整えることができます。
このように、決算賞与の平均に関する情報を活かすことで、企業経営と従業員満足の両面で大きな成果が期待できるでしょう。

合わせて読みたい「役員 決算賞与」に関するおすすめ記事

役員の決算賞与は損金算入できる?支給するメリット・デメリットや注意点も解説!
本記事では、決算賞与とは何かについて詳しく解説します。決算賞与の支給時期や平均相場・支給額、通常賞与(ボーナス)との違い、さらに企業が決算賞与を支給するメリットやデメリットについても紹介します。
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!