従業員50人以下の会社は社会保険の加入条件に該当する?今後の加入対象拡大についても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2026年1月9日
これまで「従業員が50人以下の会社だから、社会保険の加入義務は関係ない」と考えていた企業も、今後は注意が必要です。法改正により、社会保険の適用範囲が拡大され、50人以下の企業であっても、段階的に社会保険の加入条件に該当する可能性が高まっています。
従来、社会保険の加入義務は、常時51人以上の従業員を抱える事業所に限定されていました。しかし、改正によりこの「企業規模要件」は段階的に撤廃され、最終的にはすべての50人以下の会社にも社会保険の加入義務が及ぶようになります。
特に、パート・アルバイトなどの短時間労働者を多く雇用している50人以下の事業所では、今後、雇用形態を問わず社会保険の適用対象が広がっていきます。小規模な会社であっても、50人以下だからといって油断は禁物です。
本記事では、50人以下の企業が社会保険の加入条件に該当するかどうかの判断基準や、今後の段階的な適用スケジュールについて詳しく解説します。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
従業員50人以下の会社の経営者・総務・人事担当者が今すぐ確認すべき情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
【労務手続きを自分でするのはリスク大!】
社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由
社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。
社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。
ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。
また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」
社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。
だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【2024年10月改正】社会保険の加入条件
2024年10月から、社会保険の加入条件が大幅に見直されました。改正厚生年金保険法により、これまで対象外だった50人以下の企業も、状況によっては社会保険の適用対象となる可能性が出てきています。
これまで、特定適用事業所とは「被保険者が常時101人以上」の企業に限られていましたが、改正後は「常時51人以上の被保険者を抱える事業所」にまで範囲が拡大されました。つまり、被保険者が50人以下の企業は対象外のままですが、今後の従業員増加によって社会保険加入義務が発生するリスクは高まっています。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。
今回の改正で、社会保険に新たに加入義務が発生する従業員の条件は次の4つ。これらすべてを満たす場合、短時間労働者であっても社会保険の加入対象になります。
この加入条件は、「正社員ではないから社会保険に入らなくてよい」という認識が通用しなくなることを意味します。特に従業員50人以下の事業所でも将来的に対象になり得るため、早めの社内確認が必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険の加入条件①
週の所定労働時間が20時間以上
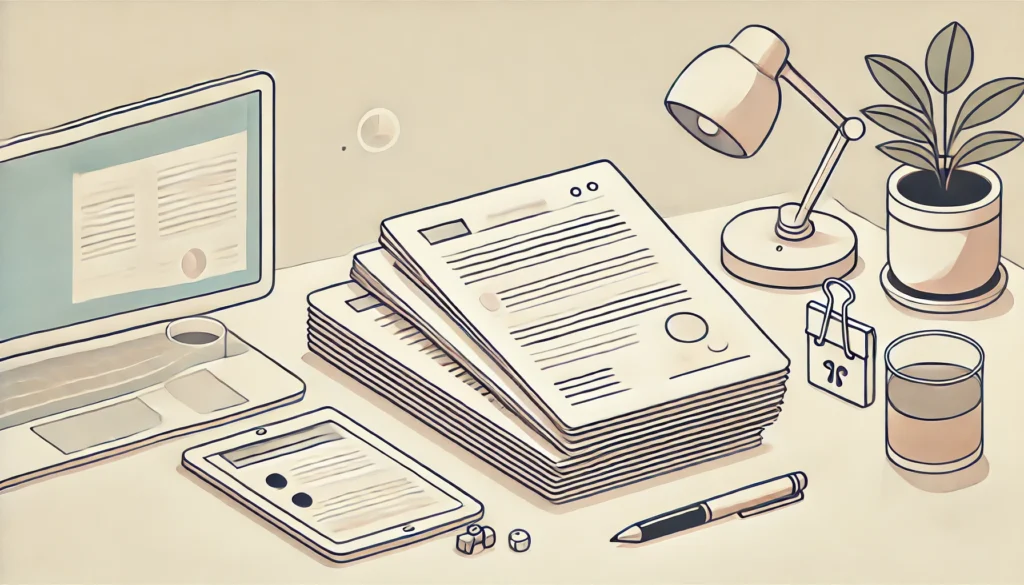
まず1つ目の社会保険の加入条件は、「週の所定労働時間が20時間以上」であることです。
ここでの「所定労働時間」とは、実際の勤務実績ではなく、雇用契約書や就業規則で定められた時間を指します。例えば、1週間に5日勤務で1日4時間、合計週20時間の勤務が雇用契約で定められていれば、社会保険の加入条件を満たすことになります。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するポイント!

一方で、普段は週16時間勤務でも、繁忙期など一時的に20時間を超える勤務があった場合は、それだけでは社会保険の加入対象とはなりません。あくまで「所定の」労働時間に注目する点が重要です。

合わせて読みたい「社会保険 加入条件」に関するおすすめ記事

社会保険の加入条件とは?手続き方法や提出書類を解説!
この要件は、従業員50人以下の企業でも将来的に加入義務が生じる可能性があるため、パート・アルバイトの契約内容を定期的に確認することが望まれます。
社会保険の加入条件②
月額賃金が8.8万円以上
次の加入条件は、「月額賃金が8.8万円以上」であることです。
この「月額賃金」は、時給や日給で働いている場合でも、1ヶ月あたりの賃金に換算して計算されます。例えば、時給1,100円で1日4時間・週5日働いている場合、月収は約8.8万円となり、社会保険の加入条件を満たすことになります。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
「2024年10月開始の社会保険適用拡大!対象とならない企業が知っておくべき「任意特定適用事業所」の申し出とは?」
ただし、月額賃金に含まれるのは基本給と職務手当などの恒常的な賃金のみであり、次のような項目は含まれません。
- 賞与(ボーナス)
- 通勤手当、家族手当
- 時間外手当(残業代)
- 結婚祝金などの一時的な手当
これらは社会保険の算定対象外となるため、金額の判断には注意が必要です。
特に、50人以下の企業では、給与構成を見直すことで将来的な社会保険の適用リスクをコントロールできる場合もあります。制度への対応だけでなく、給与設計も重要なポイントとなります。

合わせて読みたい「従業員3人の社会保険」に関するおすすめ記事

従業員3人の場合に社会保険の加入義務はある?社会保険未加入のときの罰則も解説!
社会保険の加入条件③
雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
3つ目の加入条件は、「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」ことです。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。
「人事・労務管理者の皆様~令和6年10月から社会保険の加入対象が拡大されました~」
これは「無期雇用」や「契約期間が2ヶ月超」のケースだけでなく、雇用契約が2ヶ月以内でも、更新される可能性がある場合も含まれます。つまり、形式的に2ヶ月間の契約を繰り返している場合でも、実質的に長期雇用とみなされれば、社会保険の加入対象となるのです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
具体的には、以下のようなケースで「2ヶ月超の見込みあり」と判断されます。
- 雇用契約書や就業規則に「契約更新の可能性あり」と記載されている
- 同様の契約で雇用されている従業員に、実際に契約更新の実績がある

合わせて読みたい「会社 社会保険 未加入」に関するおすすめ記事

会社設立後は社会保険に未加入のままでもいい?社会保険未加入での罰則も解説
一方で、雇い入れの時点で「更新しない」と明示され、双方が合意している場合は、加入義務は発生しません。
このように、契約内容だけでなく実態や社内の慣行も判断基準となるため、50人以下の企業においても、契約管理・雇用管理の透明性を高めておくことが将来的なトラブル防止につながります。
社会保険の加入条件④
学生でないこと
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
「【2024年10月施行】社会保険の適用拡大とは? メリットと必要な準備」
最後の加入条件は、「学生ではない」ことです。
一般的に、大学生や専門学校生、高校生など、在学中の学生は社会保険の適用拡大の対象外です。ただし、例外もあります。
- 卒業予定であり、卒業後も継続して勤務予定の学生(卒業見込証明書がある場合)
- 夜間部に通う学生
- 現在休学中の学生
これらのケースでは、学生であっても社会保険に加入する必要がある可能性があります。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する注意点

50人以下の事業所であっても、学生アルバイトを多数雇用している場合は注意が必要です。
「社会保険」編集部
社会保険の未加入や、社会保険料の滞納に科される罰則については、【社会保険未加入の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!】の記事をご覧ください
加入条件を再確認し、50人以下の企業も早めの対応を
今回の改正により、社会保険の加入条件はより具体的かつ広範囲になりました。51人以上の企業は当然として、現在50人以下の事業所でも、従業員の増加や契約内容の変化によって対象となるリスクがあります。

合わせて読みたい「一人法人の社会保険」に関するおすすめ記事

一人法人の社会保険はどうなる?加入条件や一人法人のメリットを解説

企業としては、以下の点を早めに見直すことが重要です。
- 雇用契約書の所定労働時間・更新条件
- 時給・月給の金額と手当の内訳
- 学生アルバイトやパートの実態と将来の採用計画
社会保険の適用義務違反は、事業所にとって重い負担となりかねません。 50人以下の企業であっても、今からしっかり加入条件を理解しておくことが、将来のトラブル回避と健全な企業運営につながります。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「社会保険の適用拡大とは?従業員50人以下はどうなる?2024年10月の変更点を解説」
【将来的に全企業対象】50人以下の企業も社会保険の加入義務が拡大へ
2024年に行われた社会保険制度の見直しは、50人以下の企業にとっても他人事では済まされない重大な変化をもたらしています。従来は、一定の規模以上の企業にのみ適用されていた短時間労働者に対する社会保険の加入義務が、段階的にすべての企業に拡大されていく見通しです。
これまで、「自社は従業員が50人以下だから社会保険の加入義務は関係ない」と考えていた経営者や総務担当者も、今後は明確に対応が求められるようになります。社会保険の適用範囲が広がることにより、50人以下の企業も計画的な準備と体制整備が不可欠です。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」

合わせて読みたい「社会保険の無料相談窓口」に関するおすすめ記事
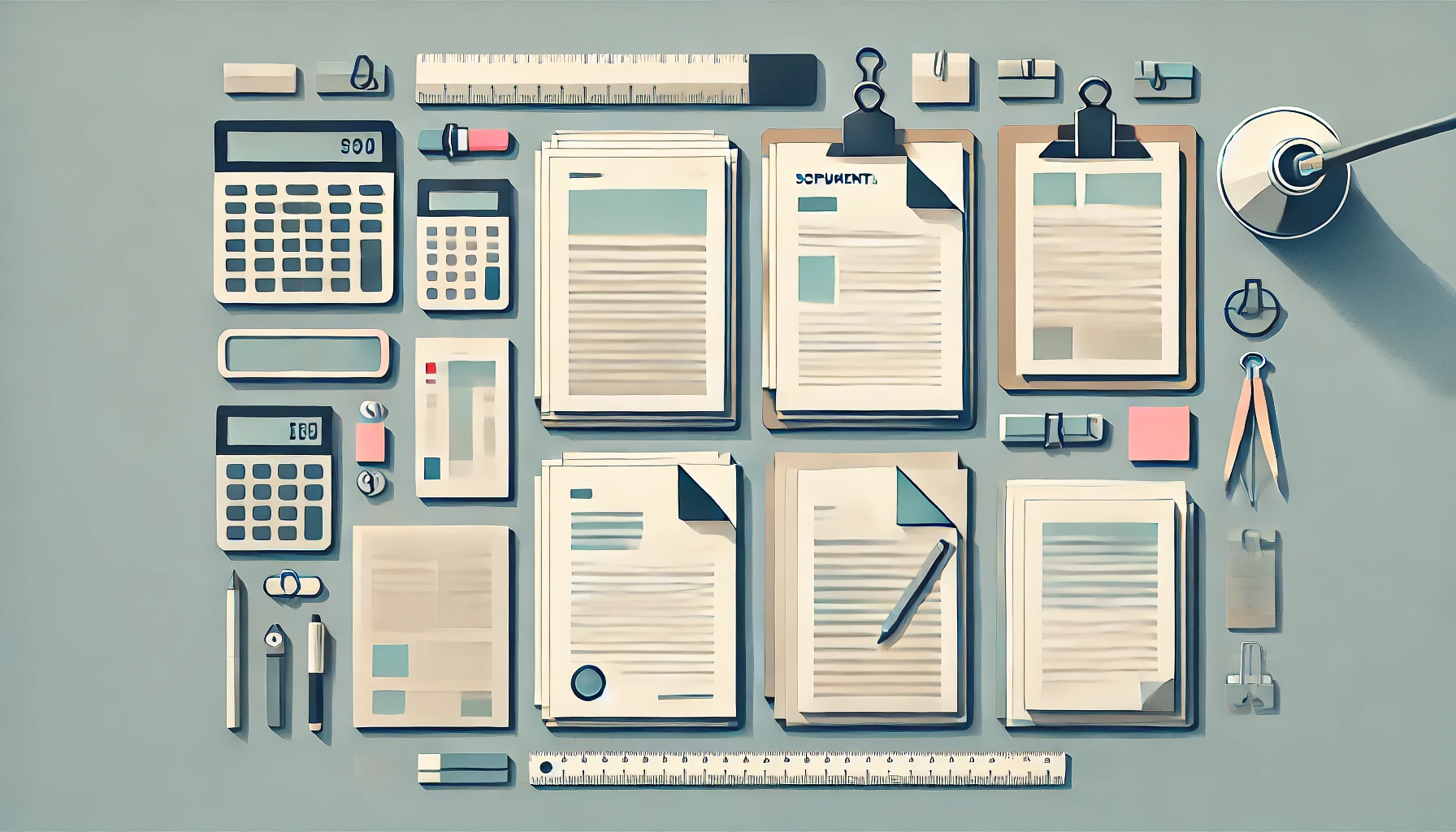
法人の社会保険の無料相談窓口はどこ?困ったときの問い合わせ先を紹介
【参考】社会保険加入に関する法改正の趣旨
今回の社会保険加入対象拡大の法改正の趣旨は、すべての働く人に社会保険の保障を行き届かせることにあります。
これまで社会保険は主に正社員などの一部の従業員を対象としていましたが、パートやアルバイトなど短時間勤務の人にも社会保険を適用し、社会保険の不公平を是正することが目的です。社会保険の加入が広がることで、働く人は将来の年金や医療保障をより安定的に受けられるようになります。
従業員50人以下の社会保険加入に関するポイント!

社会保険の法改正は単に企業に負担を求めるものではなく、社会全体で社会保険制度を支え、安心して働ける仕組みをつくるための重要な取り組みです。
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
今後は中小企業でも社会保険の加入義務が拡大する見込みがあり、経営者は社会保険の仕組みや変更内容を正しく理解し、早めの準備を進めることが求められます。
社会保険の現行加入条件とその見直し
まず、現行の制度では、以下の4つの要件をすべて満たす短時間労働者のみが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となっています。
- 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない
- 従業員数が51人以上の企業に勤務していること
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「従業員50人以下だと社会保険加入はどうなる?条件をわかりやすく解説」
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
このうち、特に「1. 賃金要件」と「4. 企業規模要件」は、社会保険の適用範囲を狭めていた要因であり、今回の見直しではこの2つが段階的に撤廃されることになりました。
これにより、将来的には賃金が少ない短時間勤務の従業員でも、また50人以下の小規模な企業に勤務している従業員であっても、社会保険の加入が必要になります。
従業員50人以下の企業にも順次拡大|段階的スケジュールの詳細
今回の社会保険制度改正のなかでも、特に注目すべき大きなポイントは、企業規模による制限が段階的に撤廃されていくことです。これまでの制度では、50人以下の企業は短時間労働者に対する社会保険の加入義務が原則としてなかったため、多くの小規模事業者が制度の適用外とされてきました。

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介
しかし今後は、社会保険の加入対象を段階的に50人以下の企業へと拡大していくスケジュールが明確に示されており、いよいよ50人以下の中小企業や零細企業にとっても本格的な社会保険対応が求められる時代が到来します。
厚生労働省が公表した方針によれば、社会保険の加入義務は企業規模に応じて段階的に50人以下の企業に拡大されていきます。以下がその具体的なスケジュールです。
| 適用開始時期 | 対象企業の従業員数 | 対象となる企業の範囲 |
|---|---|---|
| 令和9年10月~令和11年9月末 | 36人以上 | 50人以下の一部企業が社会保険対象に |
| 令和11年10月~令和14年9月末 | 21人以上 | 50人以下の企業の大部分が対象 |
| 令和14年10月~令和17年9月末 | 11人以上 | さらに多くの50人以下の企業が対象 |
| 令和17年10月以降 | 制限なし(すべての企業) | すべての50人以下の企業が社会保険の対象に |
今後の社会保険加入条件拡大のスケジュール①
令和9年(2027年)10月 ~ 令和11年(2029年)9月末
従業員36人以上の企業が社会保険の適用対象に追加されます。
この段階では、50人以下の企業のうち、比較的規模が大きい中小企業が社会保険の加入義務を新たに負うことになります。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「令和9年から社会保険加入条件が変更、50人以下の場合も加入対象に」
すでに社会保険制度への意識が高い企業もある一方で、「まだ適用外だと思っていた」50人以下の企業も多数存在しており、準備の遅れが懸念されます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
今後の社会保険加入条件拡大のスケジュール②
令和11年(2029年)10月 ~ 令和14年(2032年)9月末
従業員21人以上の企業が対象に拡大されます。
この時点で、50人以下の企業の中でも中小・小規模クラスが一気に適用対象となるフェーズに突入します。
特に、個人事業主が法人化して立ち上げたばかりの法人や、地域密着型の小規模な商店、サービス業なども、社会保険の加入義務が発生する状況になるため、より現実的な影響が広がります。


合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
今後の社会保険加入条件拡大のスケジュール③
令和14年(2032年)10月 ~ 令和17年(2035年)9月末
従業員11人以上の企業が新たに対象となります。
この段階では、いわゆる超小規模な企業でも社会保険への対応が必要となり、50人以下の企業の大半が加入義務を持つことになります。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
これまで「社員数が少ないから関係ない」と考えていた事業者も、社会保険制度に真正面から向き合うことが求められる時代に突入します。
今後の社会保険加入条件拡大のスケジュール④
令和17年(2035年)10月 ~

合わせて読みたい「合同会社 社会保険 設立」に関するおすすめ記事

合同会社を設立したときの社会保険への加入義務は?必要な書類や手続きをわかりやすく解説
企業規模にかかわらず、社会保険の加入義務が完全適用されます。
このタイミングで、従業員数が10人以下の極小規模事業者や個人経営の法人など、すべての50人以下の企業が例外なく社会保険制度の適用対象となることになります。
つまり、社会保険の企業規模要件が完全に撤廃され、50人以下というラインが意味を持たなくなるのです。
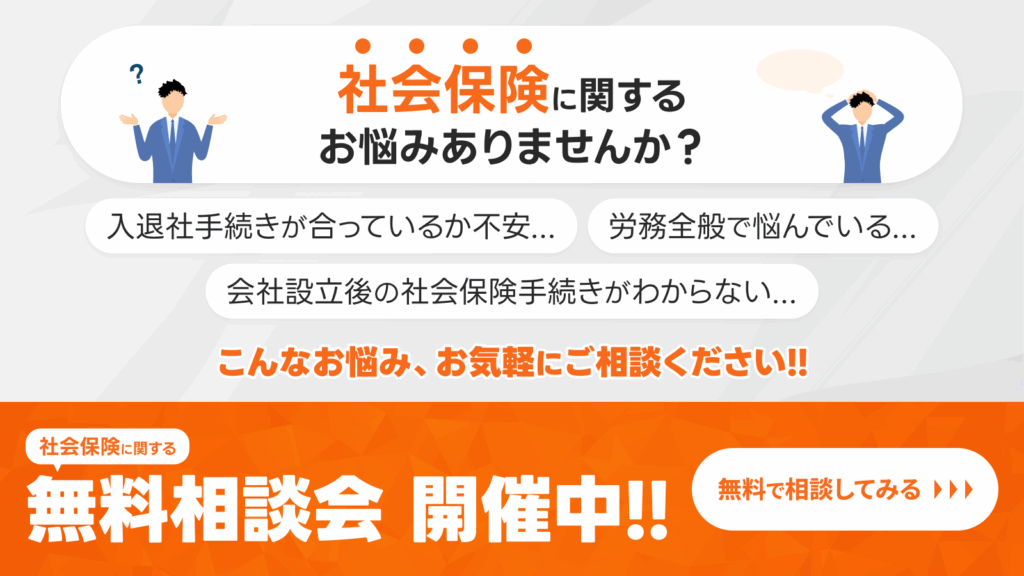
この段階的な制度移行により、最終的には全国のすべての企業、つまり50人以下の全ての事業所において、パート・アルバイトを含む短時間労働者にも社会保険の加入義務が発生することになります。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「106万円の壁を気にせず働く方法:50人以下の企業で手取りを守る理由とは?税理士社労士が解説」
これにより、これまで制度の枠外にいた50人以下の企業でも、従業員数や就労時間をもとに加入対象者を正しく把握し、社会保険手続きや保険料の事業主負担への対応が求められます。

合わせて読みたい「厚生年金の加入条件」に関するおすすめ記事

厚生年金の加入条件を詳しく解説!加入義務対象の従業員や企業の要件とは?
本記事では、厚生年金の基本的な仕組みをはじめ、厚生年金保険に加入するための条件、対象となる事業所の種類、そしてパート・アルバイトにおける最新の加入条件についても詳しく解説していきます。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する注意点

特に、50人以下の企業では人事・労務担当者が不在または兼任であることも多く、社会保険の事務処理にかかる負担は想像以上です。 しかし、社会保険の適用は法的義務であるため、違反すれば行政指導や保険料の遡及徴収のリスクもある点に注意が必要です。
「従業員50人以下の社会保険加入」編集部
近年増加している労務リスクを抑えるために会社設立直後から税理士だけではなく社労士とも顧問契約を結ぶ会社が増えています。会社設立後に役員報酬を含む給与計算や、従業員50人以下の社会保険加入義務の判断などは社労士への相談がおすすめです。
賃金要件も撤廃予定|50人以下の企業にも大きな影響
社会保険の加入条件として、これまで一定の「賃金水準(月額8.8万円以上)」が定められていました。しかし、この賃金要件も3年以内に撤廃される予定であることが発表されています。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
最低賃金が全国的に上昇している背景を受けて、週20時間程度の勤務であっても年収106万円を上回るケースが増えており、賃金による制限が実質的な意味をなさなくなってきているのです。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。
「社会保険の加入条件とは?従業員側、事業所側の視点でわかりやすく解説【2025年最新】」
この社会保険の加入条件変更は、50人以下の企業にとって特に重大です。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するポイント!

これまで賃金が低いために社会保険加入の義務がなかったパート・アルバイトについても、今後は所得に関係なく加入対象となる可能性が高いため、50人以下の企業の負担はこれまで以上に大きくなることが予想されます。
従業員50人以下の企業が社会保険加入条件拡大で受ける影響とは
今後の社会保険制度の改正により、従業員50人以下の企業が受ける影響は非常に大きなものになると予想されています。これまで従業員50人以下の企業は、社会保険の適用対象外であるケースが多く、特に短時間労働者に対する加入義務を負わない場合もありました。しかし、今後は社会保険の対象が従業員50人以下の企業にも段階的に広がっていくため、事前の対応が不可欠です。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
「バイトやパート先の社会保険に入りたくない。年収はいくらまでに抑えればいい?」
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
従業員50人以下の企業には、限られた人員で事務や経理・労務を兼務しているところも多く、社会保険の適用拡大に伴い、対応すべき業務が一気に増加します。ここでは、特に従業員50人以下の企業が直面する可能性の高い課題や準備すべきポイントを詳しく整理してみましょう。
従業員50人以下の企業が受ける影響①
社会保険料の負担が増える可能性
まず、従業員50人以下の企業にとって最も直接的な影響が「社会保険料の負担増加」です。社会保険料は企業と従業員が折半で支払う仕組みですが、従業員50人以下の企業では、これまで加入対象外だったパート・アルバイトなどが新たに加入対象となることで、企業側の支出が確実に増加します。

合わせて読みたい「会社設立時の社会保険」に関するおすすめ記事

会社設立時の社会保険手続きについて徹底解説!
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する注意点

特に利益率が低い従業員50人以下の小規模企業にとっては、コスト上昇が経営に直結する懸念もあります。
従業員50人以下の企業が受ける影響②
社会保険関連の事務手続きが複雑化
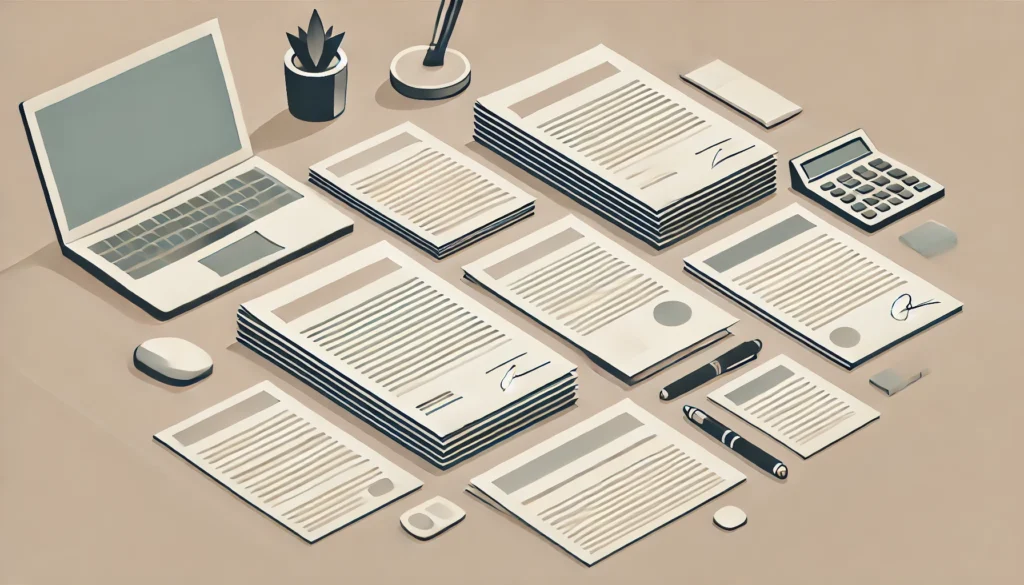
従業員50人以下の企業では、経理・人事の専任スタッフがいないケースも多く、社会保険の加入・脱退・月額変更などの事務処理が非常に負担になります。社会保険の対象者が増えることで、従業員50人以下の企業であっても年中発生する手続きを正確にこなす体制が求められます。事務ミスによるペナルティや、行政からの指導を回避するためにも、従業員50人以下の事業所でも早期のシステム導入や外部委託の検討が重要です。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「従業員50人以下の企業でパートが社会保険に加入する条件は?【人事労務FAQ】」
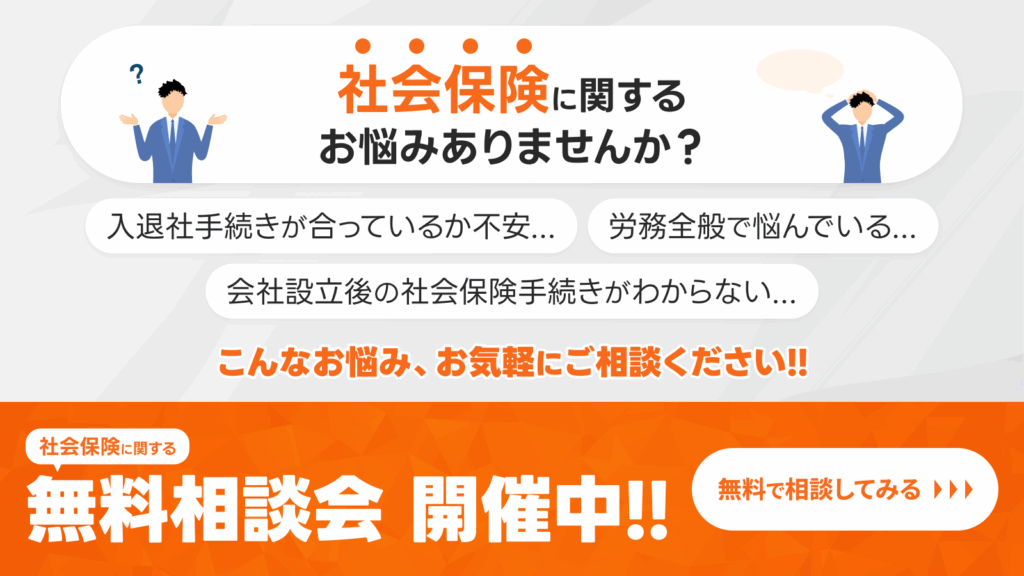
従業員50人以下の企業が受ける影響③
50人以下の企業でも契約形態の見直しが必要
制度の改正により、今後は従業員50人以下の企業でも、従業員の労働時間や賃金額をもとに社会保険の加入対象者を正確に判断しなければなりません。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するポイント!

これまで週20時間未満の契約で働いていた従業員についても、変更・更新のタイミングで社会保険の加入対象となる可能性があるため、従業員50人以下の企業でも雇用契約書の記載内容や実働状況をしっかり確認する必要があります。
従業員50人以下の企業が受ける影響④
就業規則・雇用契約の整備が求められる
社会保険の加入対象が拡大することで、従業員50人以下の企業であっても就業規則や雇用契約書の整備が避けられません。
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
特に、短時間労働者への適用や契約更新時の取り扱いについては、制度に沿った明文化が求められます。
従業員50人以下の会社だから簡素でよいという時代ではなくなりつつあり、社会保険対応のための社内ルールの再構築が必須になります。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「2024年10月~パートの働き方が大きく変わる!」
従業員50人以下の企業が受ける影響⑤
50人以下の企業こそ、従業員対応の丁寧さが求められる
「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部
従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「106万円の壁と130万円の壁の違いとは?企業の実務対応と注意点を解説」
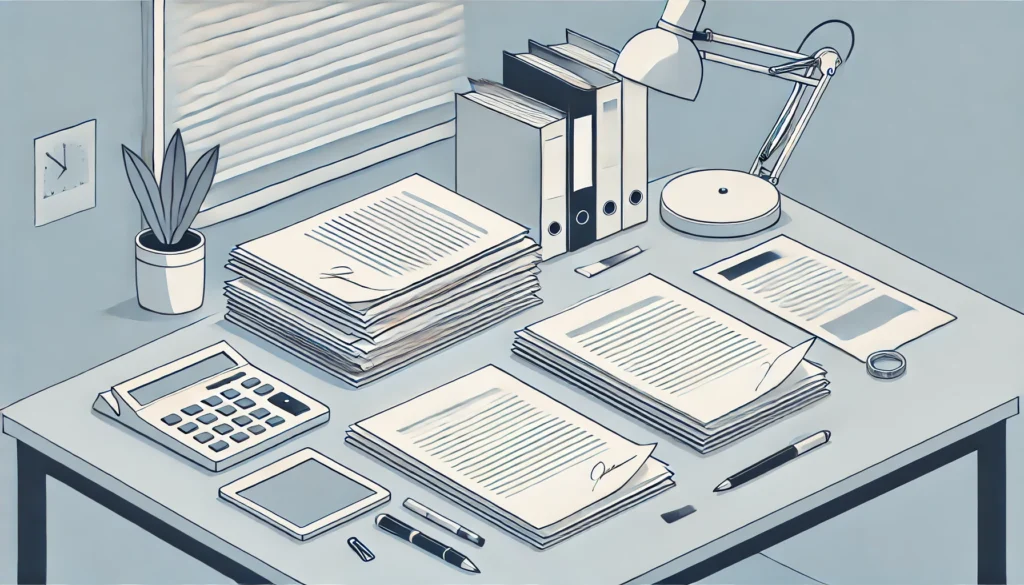
従業員50人以下の社会保険加入義務に関するポイント!

社会保険に加入することは、従業員の安心感や福利厚生の充実につながります。特に、50人以下の企業では、従業員との距離が近く、少人数だからこそ制度への不安や不明点がダイレクトに伝わってくるものです。
経営者として、従業員に対して社会保険の仕組みや対応方針を丁寧に説明することは、職場環境の安定と定着率の向上にも直結します。また、これらの社会保険手続きを各自に行うことは離職率の低下にも繋がります。
従業員50人以下の企業にとって、社会保険対応は信頼経営の土台ともいえるでしょう。
まとめ|社会保険の加入義務は50人以下の企業にも今後拡大
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
今回の法改正によって、社会保険の加入義務は50人以下の企業にも確実に広がっていくことが明らかになりました。これまで「50人以下の会社は社会保険の対象外」とされていた常識が変わり、今後は50人以下の企業であっても社会保険への加入対応が求められる時代が訪れます。
制度変更は段階的に進められますが、最終的にはすべての50人以下の企業が社会保険の適用対象となる予定です。つまり、従業員数が50人以下であるかどうかに関係なく、社会保険の加入条件を満たす従業員がいれば、企業側は確実に社会保険の手続きや保険料負担の義務を負うことになります。
特に、50人以下の企業は人手不足や労務管理の体制が整っていないケースも多く、社会保険の実務対応に時間と手間がかかることが想定されます。そのため、50人以下の企業こそ、制度改正のスケジュールを正しく把握し、今のうちから備えておくことが不可欠です。
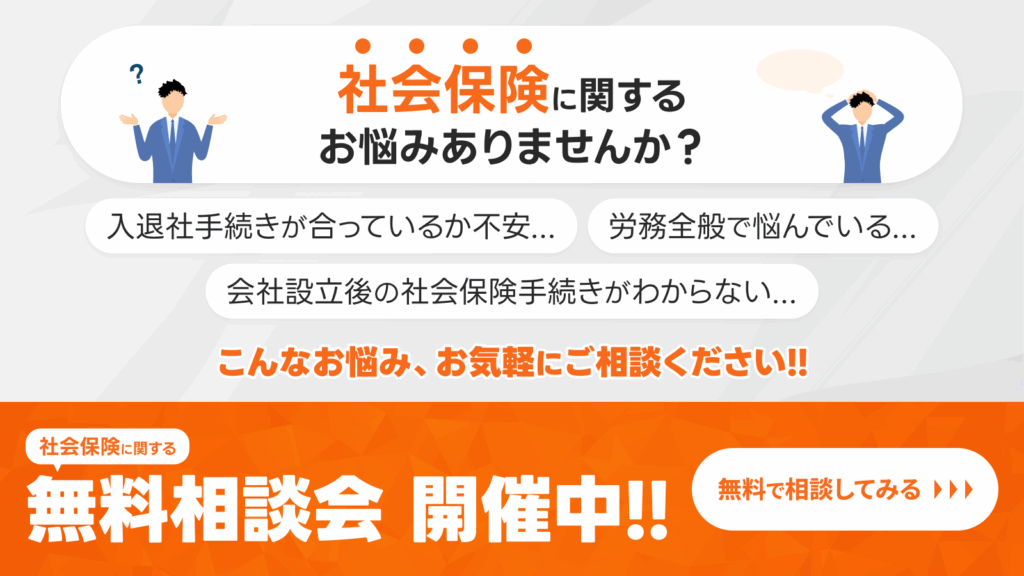
今後、50人以下の企業が社会保険に対応できるかどうかは、企業の信頼性や人材の確保にも直結します。「まだ50人以下だから大丈夫」と油断せず、すべての50人以下の企業が社会保険対応に向けて一歩を踏み出すタイミングにきています。
社会保険の義務化は、50人以下の企業にとっても例外ではありません。早めの準備が、安定した経営と労働環境の整備につながります。

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事

会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!