社労士顧問料の相場は?顧問契約のメリットや依頼内容別の相場も解説!
カテゴリー:
公開日:2025年5月
更新日:2026年1月8日
企業運営において、労務管理や社会保険手続きは欠かせない業務ですが、社内で対応するには専門知識や時間が必要です。こうした課題を解決する手段として注目されているのが、社労士との顧問契約です。とはいえ、「社労士に顧問料を支払うといくらかかるのか」「相場はどれくらいなのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、社労士顧問料の相場について、従業員数別や依頼内容別の具体的な費用感を詳しく解説します。また、社労士と顧問契約を結ぶことで得られるメリットや、顧問料を抑えるためのポイントについても紹介します。コストと効果のバランスを見極めるために、社労士顧問料の相場をしっかり押さえておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
社労士に依頼できることは?

社労士は、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令、さらに健康保険・厚生年金保険・雇用保険といった社会保険関係法令に精通した、労働と社会保険のプロフェッショナルです。こうした専門性を活かして、社労士は「労働分野」と「社会保険分野」の2軸にわたり、企業の人事労務を支援します。
そのため、社労士との顧問契約を検討する際には、企業の課題に即した分野に強い社労士を選ぶことがポイントになります。特に、労働条件の整備や労務トラブルの防止を目的とする場合には、労働分野に強い社労士との顧問契約が効果的です。
社労士顧問料の相場に関するおすすめ記事
社労士と顧問契約を結び、顧問料を支払って定期的なサポートを受けることで、以下のようなメリットが得られます。顧問料の相場は、依頼する業務範囲や従業員数によって異なりますが、月額2万〜7万円程度が一般的です。
- 労働時間管理や賃金体系が法令に準拠しているかを確認し、社労士から適切なアドバイスを受けられる
- 雇用契約書や就業規則の内容について、社労士に確認・作成を依頼できる
- 入退社時の社会保険・雇用保険の各種手続きを、社労士に代行してもらえる
- 給与計算や賃金台帳の作成業務を、顧問契約の範囲内で社労士に依頼できる
- 助成金申請について、社労士が最新の制度情報をもとにサポートしてくれる
SoVa税理士ガイド編集部
このように、社労士との顧問契約は、法令遵守の確保や労務リスクの回避、業務の効率化など、顧問料の相場以上の価値をもたらす投資といえるでしょう。
企業規模や課題に合わせて、適切な顧問契約を結ぶことが重要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【従業員数別】社労士顧問料の相場

社労士の顧問料は、「いくらが適正なのか?」「自社の規模なら相場はどれくらい?」といった疑問を抱える企業担当者も多いのではないでしょうか。実際、社労士の顧問料は従業員数や業種、依頼内容によって大きく異なり、それぞれの相場を理解しておくことは、適切な顧問契約を結ぶうえで非常に重要です。
ここでは、社労士顧問料の相場について、従業員数別・企業タイプ別に詳しく解説し、中小企業と大企業の違いや実際の事例も紹介します。社労士顧問契約を検討する際の参考にしてください。
SoVa税理士ガイド編集部
社労士顧問料の相場についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:社労士顧問料の相場はいくら?業務内容で見る具体的な価格例
従業員数別の顧問料相場:5人未満から50人以上まで
社労士顧問料の相場は、企業の従業員数によって明確な差があります。一般的に、従業員数が少ない企業ほど顧問料は低く、業務負担の増加に伴って顧問料も上昇する傾向があります。
たとえば、5人未満の小規模企業では社労士顧問料の相場は月額2万円〜3万円程度、10人未満の場合は2万円〜4万円が一般的です。従業員が10〜19人の中小企業では、社労士顧問料の相場は月額4万円〜6万円前後となり、さらに20〜49人規模の企業では6万円〜8万円程度が目安となります。従業員が50人を超える企業では、顧問料の相場は月額8万円〜10万円以上となることも珍しくありません。これは、従業員数が増えるほど労務管理や社会保険手続きなど社労士が対応すべき業務が多岐にわたるためです。

合わせて読みたい「税理士にスポット相談する際の相談」に関するおすすめ記事

税理士にスポット相談する際の相場は?顧問契約との違いについても解説!
中小企業と大企業で異なる顧問料の相場
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
中小企業と大企業では、社労士の顧問料設定に大きな違いがあります。中小企業向けの社労士顧問料は、一般的に低めに設定されており、月額2万円〜5万円程度が相場です。これは、基本的な労務相談や保険手続きが中心の業務となるためです。一方、大企業の場合は対応範囲が広がり、労務トラブル対応、人事制度設計、社内研修などが加わることで、顧問料の相場は月額8万円〜15万円と高額になる傾向があります。さらに、特定のプロジェクトやコンサルティング業務が含まれる場合は、別途追加費用が発生するケースもあります。企業の規模や業務の複雑性が、社労士の顧問料相場に直結していることを理解しておきましょう。
社労士顧問料の相場に関するおすすめ記事
実例で見る:企業タイプ別の社労士顧問料相場
社労士の顧問料は、企業の業種や特性によっても相場が異なります。たとえば、スタートアップ企業や飲食業など少人数体制の企業では、シンプルな労務管理が主な業務となるため、顧問料は月額2万円〜3万円程度に設定されることが多いです。一方、製造業や建設業、農業関連など、従業員数が多く法令対応が厳格に求められる業種では、月額8万円〜10万円以上の顧問料が相場となる傾向があります。
社労士顧問料のここがポイント!

また、外資系企業の場合は英語での対応や国際的な労務知識が必要となるため、社労士顧問料も高めに設定されるのが一般的です。
こうした企業タイプ別の相場を把握しておくことで、より自社に合った社労士選びが可能になります。
【依頼内容別】社労士費用の相場
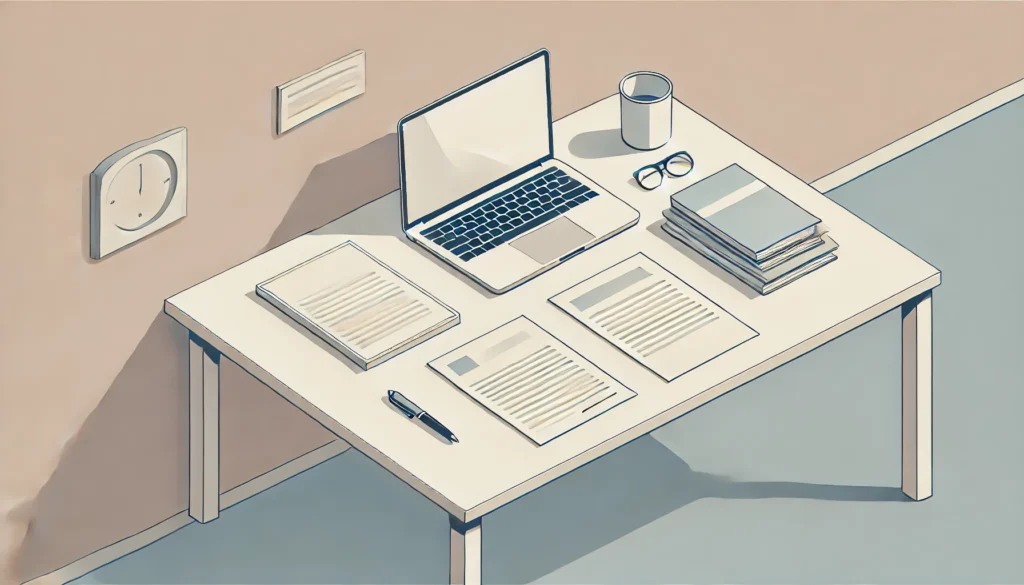
社労士と顧問契約を結ばずに業務を依頼する場合、スポット契約として単発の業務を社労士に依頼することになります。
SoVa税理士ガイド編集部
スポット契約では、依頼内容ごとに社労士の顧問料とは異なる個別の費用が発生し、一般的に顧問契約に比べて割高になるのが特徴です。
社労士にスポットで依頼する際の顧問料の相場を把握しておくことで、無駄な出費を避け、費用対効果の高い活用が可能になります。以下では、社労士に依頼できる主な業務ごとの顧問料・費用相場について詳しく解説します。
依頼業務別の社労士報酬相場一覧
| 依頼業務内容 | 顧問料・費用相場 |
|---|---|
| 労働社会保険の手続き代行 | 5万円〜8万円(従業員5人未満) |
| 就業規則の作成 | 20万円程度 |
| 給与計算 | 月額2万円〜3万円(従業員5人未満) |
| 助成金の申請 | 助成金額の20〜30%程度 |
| 労務コンサルティング | 相談料5万円〜/企画・運用:50万円〜 |
| 個別労働紛争対応(ADR) | 着手金2万円〜5万円+成功報酬20%前後 |
労働社会保険の手続き代行の相場
社労士に労働保険や社会保険の手続きをスポットで依頼する場合、顧問料の相場は従業員5人未満で5万円〜8万円程度です。算定基礎届や月額変更届など、複雑な計算や書類作成が求められる業務が含まれるため、従業員数が増えるにつれて費用も上がる傾向があります。社内リソースで行うには負担が大きく、社労士に依頼することで手続きのミス防止にもつながります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
就業規則作成の相場
就業規則の作成は、従業員が常時10人以上いる企業で義務付けられており、社労士に依頼するケースが多く見られます。費用相場は約20万円で、退職金規程や賃金規程など追加項目ごとに5万円〜10万円が加算されるのが一般的です。法的整合性に欠ける規則は重大なトラブルの原因にもなるため、就業規則の作成は経験豊富な社労士への依頼が安心です。
社労士顧問料の相場に関するおすすめ記事

合わせて読みたい「会社側の退職手続き」に関するおすすめ記事
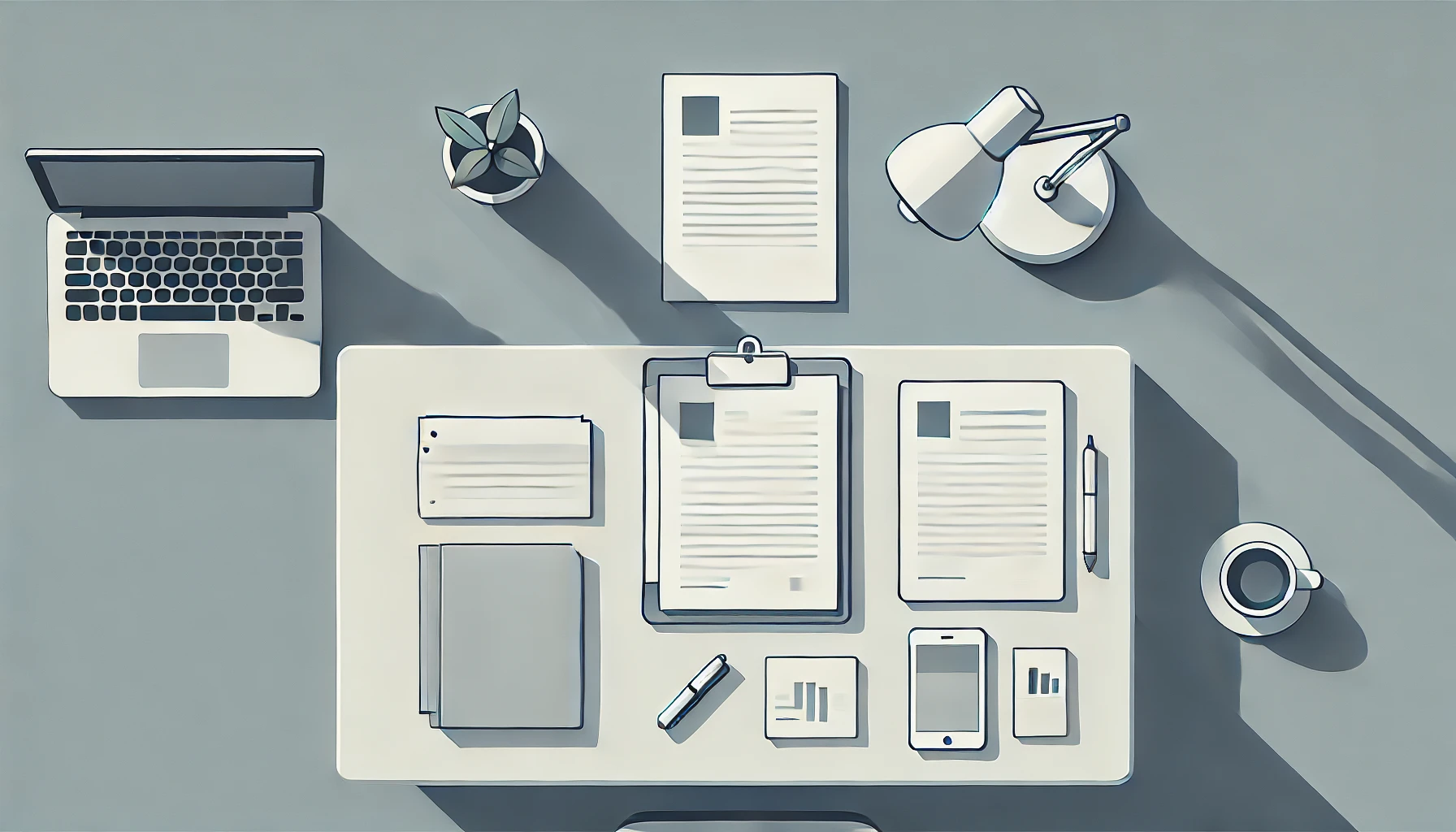
退職手続きでは会社側はいつまでに何をすべき?必要な手続きや対応の注意点を解説!
給与計算の相場
給与計算業務には、保険料や税金、残業代の正確な計算などが含まれ、ミスが許されない作業が多く発生します。社労士に給与計算をスポットで依頼する場合の顧問料相場は、従業員5人未満で月額2万円〜3万円程度です。従業員が増えるほど若干の加算がありますが、大きく跳ね上がることは少ないため、業務効率化を図るうえで有効な手段となります。

合わせて読みたい「給与計算 方法」に関するおすすめ記事

給与計算方法まとめ!正確な給与計算方法を詳細に解説します
助成金申請の相場
助成金の申請を社労士に依頼する際の費用相場は、受給額の20〜30%が一般的です。スポット契約では着手金が発生する場合もあり、顧問契約を結んでいると割引や着手金免除などのメリットを受けられるケースがあります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
助成金は制度変更が頻繁なため、最新情報に詳しい社労士に依頼することで、確実な受給に近づくことができます。
労務に関するコンサルティングの相場
労務に関するコンサルティングは、労働環境の整備や制度改善を目的として社労士に依頼されることが多く、相談料の相場は5万円前後です。企画立案や制度導入の支援など、より踏み込んだ内容を依頼する場合は50万円〜100万円以上の費用がかかることもあります。労務管理を強化したい企業にとっては、社労士の知見を活かしたコンサルティングが有効です。
社労士顧問料の相場に関するおすすめ記事:社労士顧問料、知らないと損する!? 相場の秘密に迫る!
個別労働関係紛争に関する業務の相場
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
個別の労使トラブルに対応する際、社労士の中でも「特定社労士」に限りADR(裁判外紛争解決手続)を行うことができます。ADR対応を社労士に依頼する際の費用相場は、着手金が2万円〜5万円、成功報酬が解決金額の20%前後となります。費用設定は事務所によって異なるため、事前に確認し、自社の状況に合った社労士を選ぶことが重要です。
社労士顧問料を払うことで得られるメリット
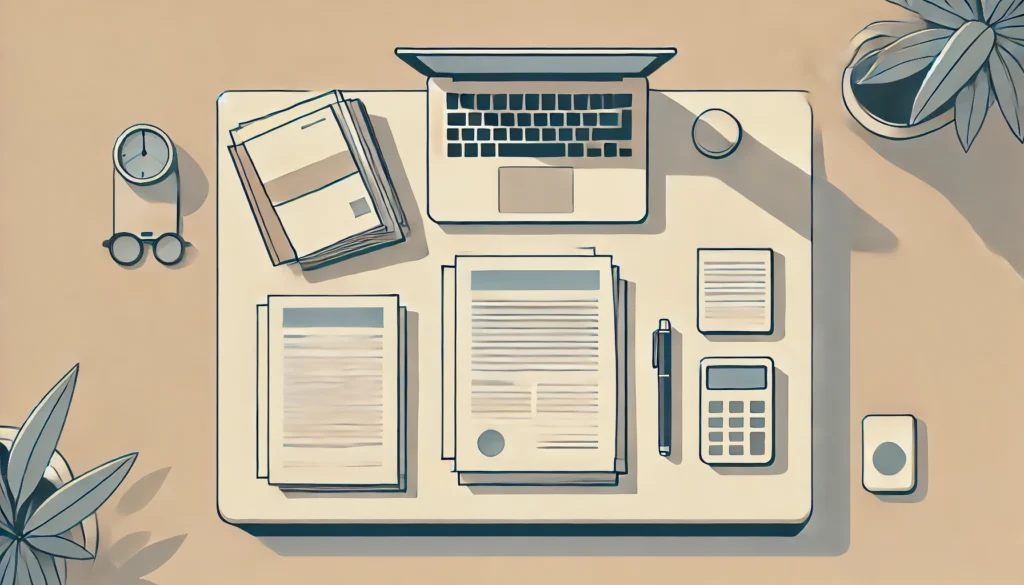
スポットで社労士に依頼する選択肢もある中で、社労士顧問料を払うことで得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
社労士顧問料を払うメリット①:法改正や労務問題対応の安心感
社労士に顧問料を支払って契約を結ぶ大きなメリットのひとつが、頻繁に行われる法改正への対応です。
SoVa税理士ガイド編集部
労働基準法や社会保険制度は毎年のように変更されており、内容を正確に把握し運用することは多くの中小企業にとって非常に負担の大きい業務です。
しかし、社労士と顧問契約を結ぶことで、常に最新の法改正情報を提供してもらえるだけでなく、企業に合わせた実務的な対応方法までアドバイスを受けられます。このようなサポートが、経営上のリスク回避やトラブル防止に繋がり、社労士の顧問料以上の安心感と安定経営をもたらします。
社労士顧問料を払うメリット②:経営者の負担軽減と業務効率化
社労士の顧問料を支払って継続的なサポートを受けることは、労務管理や社会保険関連業務の負担軽減に直結します。給与計算や入退社時の保険手続きなどは、企業の成長に比例して煩雑さが増すため、社労士に業務をアウトソースすることで、経営者や人事担当者の時間と労力を大幅に節約できます。
社労士顧問料の相場に関するおすすめ記事
また、専門家である社労士が業務を遂行するため、手続きの正確性が向上し、ヒューマンエラーのリスクも低減します。顧問料の相場は月額2万〜7万円程度が一般的ですが、それ以上の業務効率化と経営集中の価値が見込めます。
社労士顧問料を払うメリット③:専門家のサポートによりリスクを回避
人事・労務の分野では、法的なミスや管理不足が企業の信用問題や訴訟に発展するケースもあります。適切な労働時間の管理や就業規則の整備を怠ることで、重大な労務トラブルを招く可能性も否めません。こうしたリスクに備えるためにも、社労士との顧問契約は有効です。社労士に定期的に相談できる体制を整えておくことで、問題を未然に防ぎ、必要なときに迅速な対応を受けることが可能となります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
顧問料という月額費用を支払うことは、リスク回避という観点でも極めて費用対効果が高い選択です。
社労士顧問料を払うメリット④:顧問契約で受けられるアフターケア
社労士に支払う顧問料には、単に日常業務の代行だけでなく、アフターケアまで含まれている場合が多くあります。たとえば、労働局や年金事務所からの調査対応、行政指導が入った際の書類準備や立会い、トラブル発生時の解決サポートまで、幅広い対応を受けられます。さらに、問題解決後には、再発防止策の提案など継続的な支援も期待できます。こうした一連の流れを通じて、社労士の顧問料は単なる「コスト」ではなく、「経営を守る保険」のような役割を果たすと言えるでしょう。
社労士顧問料を抑えるためのポイント

社労士との顧問契約を検討する際、「顧問料を少しでも抑えたい」「相場より高い契約にならないか不安」という方も多いはずです。ここでは、社労士顧問料を適正な相場で抑えるための具体的な交渉ポイントや、契約の工夫について紹介します。
SoVa税理士ガイド編集部
社労士顧問料の相場についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社労士顧問料を抑えるポイント①:依頼したい内容を整理する
社労士と顧問契約を結ぶ際、顧問料を相場よりも抑えるためには、契約前の交渉が重要です。まず、自社にとって本当に必要な社労士業務を明確にすることが第一歩となります。たとえば、「相談対応のみ」の顧問契約にするのか、「社会保険手続き」「給与計算」などの実務を含めるのかによって、社労士顧問料の相場は大きく変動します。また、手続きの回数を制限したり、労務相談の対応時間を限定することで顧問料を下げられるケースもあります。必要な範囲を見極めて依頼することで、無駄のない契約内容と適正な顧問料に抑えることが可能です。
社労士顧問料を抑えるポイント②:複数の社労士事務所を比較する
社労士顧問料を相場内で抑えるためには、複数の社労士事務所の料金やサービス内容を比較検討することが不可欠です。同じような業務内容でも、社労士ごとに顧問料の相場感には差があります。都市部の社労士事務所ではオフィス維持費などにより顧問料が高めに設定されていることもあり、地方の社労士やオンライン専門の社労士事務所と比較すると料金差が明確です。複数の見積もりを取ることで、相場を把握しやすくなり、納得感のある価格で契約を結ぶことができます。
社労士顧問料を抑えるポイント③:オンライン対応の社労士でコストを削減
顧問料を抑えたい企業にとって、オンライン対応の社労士事務所を活用することは非常に効果的です。近年では、社労士業務の多くがオンラインで完結できるようになり、訪問や対面の必要がない分、事務所側のコストも抑えられています。その結果、オンライン型の社労士サービスは、顧問料の相場よりも安く提供されているケースが増加中です。
社労士顧問料の相場に関するおすすめ記事
書類のやりとりや相談もすべてデジタル化されているため、地方在住でも都市部の専門家に低価格で依頼できるなど、コスト削減と専門性を両立できます。
社労士との顧問契約でよくあるトラブルとは?
社労士との顧問契約は、労務管理や社会保険手続きの負担を減らすうえで大きなメリットがありますが、契約内容を十分に理解していない場合、トラブルに発展することもあります。特に社労士の顧問契約の範囲や報酬の相場を把握していないと、「ここまで対応してもらえると思っていたのに追加料金が発生した」というケースが少なくありません。顧問契約を結ぶ前に、対応範囲・社労士報酬の相場・緊急時の対応などを明確にしておくことが大切です。
社労士の顧問契約で発生しやすいトラブル例
- 顧問契約の範囲があいまい
社労士の顧問契約では、月額顧問料の範囲に含まれる業務(社会保険手続き・給与計算・労務相談など)が明確でないまま契約してしまい、後から「それは別料金です」と言われるトラブルがよくあります。社労士に依頼する際は、契約書で対応範囲を細かく確認することが重要です。 - 社労士報酬の相場を理解せずに契約してしまう
社労士の顧問契約の相場は会社の規模や従業員数によって変わります。小規模企業であれば月額2〜3万円前後が一般的ですが、助成金申請や給与計算が含まれると相場は高くなります。相場を調べずに契約すると、他社より高い顧問料を支払っていることに後で気づくケースも。 - 社労士とのコミュニケーション不足
社労士と顧問契約をしていても、日常的な報告や相談が不足すると、労務トラブルが発生してから気づくこともあります。社労士は継続的な関係を築くことで本領を発揮するため、定期的な打ち合わせや報告体制を整えておくことが望ましいです。
社労士との顧問契約トラブルを防ぐために
社労士との顧問契約トラブルを防ぐには、契約前に相場を確認し、業務範囲と料金体系を明確にすることが基本です。また、社労士との信頼関係を築くためには、定期的に労務の課題を共有し、問題が起きる前に相談する姿勢が欠かせません。社労士の顧問契約は単なる外注ではなく、企業の成長を支えるパートナー契約であるという意識を持つことが、長期的な成功につながります。
社労士の顧問契約相場に関するおすすめ記事

社労士との顧問契約に関するトラブルについては以下のサイトも是非ご覧ください。
「社労士とのトラブル解決の手引き ~信頼できる相談先を探す~」
Q&A|よくある質問
Q: 社労士顧問料の相場は依頼内容によって変わりますか?
A: はい、依頼内容によって社労士顧問料の相場は変わります。例えば、社会保険・労働保険の手続き代行だけであれば相場は低めですが、給与計算や労務コンサルティング、就業規則の作成・改定などを含めると顧問料の相場は高くなります。また、緊急対応やスポット業務が多い場合は、通常の顧問料に加えて追加料金が発生することもあります。
Q: 社労士顧問料を安く抑える方法はありますか?
A: 社労士顧問料を抑えるには、依頼内容を必要最低限に絞り込む方法があります。例えば、給与計算は社内で行い、社会保険・労働保険の手続きだけを社労士に依頼するなど、業務範囲を限定すると顧問料の相場を下げられます。また、オンライン対応が可能な社労士事務所を選ぶと、移動時間や打ち合わせコストが削減され、顧問料相場が比較的安くなる傾向があります。
Q: 社労士顧問契約の相場感はどのように把握すべきですか?
A: 社労士顧問料の相場感を把握するには、複数の社労士事務所から見積もりを取り、依頼内容と料金を比較することが重要です。顧問料の金額だけでなく、対応範囲や追加費用の有無、緊急時の対応スピードなども確認することで、自社に最適な社労士顧問契約を選びやすくなります。
まとめ

社労士顧問料の相場に関するおすすめ記事
社労士の顧問料は、従業員数や依頼内容によって相場が異なりますが、毎月1万円〜5万円程度が一般的です。
SoVa税理士ガイド編集部
社労士と顧問契約を結ぶことで、法改正への迅速な対応や労務トラブルの予防といった多くのメリットが得られ、結果的に企業経営の安定につながります。
また、社労士顧問料を抑えるには、自社に合った契約内容を見極めることが大切です。今回紹介した社労士顧問料の相場や選び方のポイントを参考に、信頼できる社労士との関係構築を目指しましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!