社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
カテゴリー:
公開日:2025年9月
更新日:2025年11月26日
※PR ※本記事はプロモーションを含みます。
社会保険料は、会社を経営するうえで必ず発生する重要な義務であり、毎月の社会保険料を正しく納付することは企業にとって欠かせません。社会保険料は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料などで構成され、社会保険料は必ず定められた納付方法で支払う必要があります。社会保険料を納付せずに放置すれば延滞金などのペナルティが発生するため、社会保険料は期限までに適切な納付方法を選んで確実に納付することが求められます。
この記事では、社会保険料の納付方法を徹底的に解説し、社会保険料を金融機関窓口で納付する場合、口座振替で納付する場合、電子納付で納付する場合の違いやメリットを詳しく紹介します。さらに、社会保険料の納付期限の基本や、社会保険料の納付をスムーズに進める工夫についても説明し、社会保険料の納付にかかる手間を軽減するための実践的なポイントをまとめました。
社会保険料は毎月必ず納付するものだからこそ、社会保険料の納付方法を正しく理解し、効率よく社会保険料を納付することが経営安定のために重要です。社会保険料の納付に悩んでいる方や、最適な納付方法を探している方は、ぜひ参考にしてください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
社会保険料の納付方法
会社が負担する社会保険料は、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料などで構成されており、必ず決められた納付方法に従って納付しなければなりません。社会保険料の納付は、期限を守り、適切な納付方法を選んで実施することが大切です。ここでは、社会保険料の納付方法について詳しく解説していきます。
社会保険料の納付方法に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法や、三井住友銀行Trunkを利用した口座振替については以下の記事も是非参考にしてください。
社会保険料の納付方法に関する参考記事:「社会保険料の納付方法は?納付の仕組みや支払い期限を解説!」

三井住友銀行 Trunk [PR]
国税や社会保険料の口座振替にも対応。社会保険料等の支払いが楽になるおすすめの法人口座です。
金融機関窓口での社会保険料納付方法
社会保険料の基本的な納付方法は、金融機関の窓口で手続きを行う納付方法です。納付書を持参して直接窓口で納付することで、確実に社会保険料を納付することができます。金融機関窓口での納付方法は、昔から利用されているオーソドックスな納付方法で、確実性を重視する会社に向いています。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
口座振替による社会保険料の納付方法
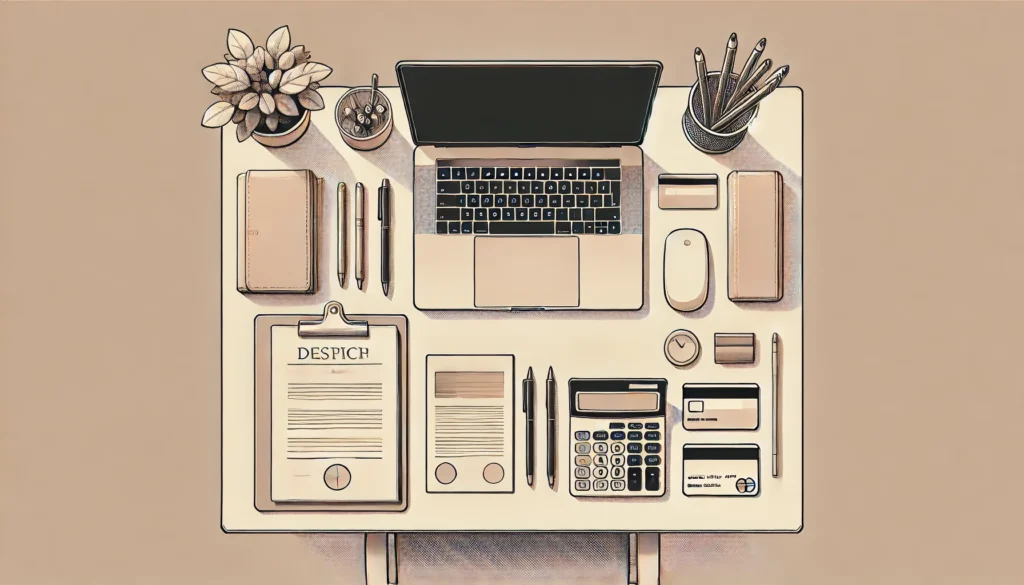
次に便利なのが口座振替による納付方法です。あらかじめ口座振替の手続きを行っておけば、毎月自動的に社会保険料が納付されます。この納付方法では「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出する必要があります。
社会保険料の納付方法に関するポイント!

口座振替を利用する納付方法なら、担当者が毎月納付のたびに金融機関に行く手間を省け、納付漏れのリスクも低くなります。
電子納付(Pay-easy)による社会保険料納付方法
社会保険料の納付方法としては、電子納付(Pay-easy)も利用できます。電子納付は複数の手段から選べる柔軟な納付方法で、以下のような形態があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
インターネットバンキングによる電子納付方法
銀行のWebサイトを利用し、社会保険料をオンラインで納付する納付方法です。契約さえあれば、社内からでも簡単に社会保険料の納付が可能です。
モバイルバンキングによる電子納付方法
携帯電話やスマートフォンを使って納付する方法です。外出先からでも社会保険料を納付できる利便性の高い納付方法です。
「社会保険料の納付方法」編集部
社会保険料の納付方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
社会保険料の納付方法に関する参考記事:「保険料の納付」
ATMによる電子納付方法
「Pay-easy」マーク付きATMを利用して社会保険料を納付する方法です。納付書に記載された収納機関番号(0500)、納付番号(16桁)、確認番号(6桁)を入力して納付を完了させる納付方法です。
テレフォンバンキングによる電子納付方法
電話の音声案内に従って納付を行う方法です。インターネット環境がなくても利用できる納付方法で、幅広い会社に対応できます。
社会保険料の納付方法に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法や、三井住友銀行Trunkを利用した口座振替については以下の記事も是非参考にしてください。
「法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」を2025年5月より提供開始」
社会保険料納付方法でクレジットカードは使える?
社会保険料の納付方法は、金融機関窓口での納付方法、口座振替による納付方法、電子納付方法の3種類に限られています。法人が納付する社会保険料については、クレジットカードでの納付は認められていません。最近では国民年金保険料の納付方法としてクレジットカードが利用可能になっていますが、社会保険料の納付方法はあくまで3種類に限定されています。
社会保険料の納付は会社にとって大きな義務であり、納付期限を守って適切な納付方法で行う必要があります。金融機関窓口での納付方法は確実性が高く、口座振替による納付方法は利便性が高く、電子納付方法は柔軟性が高いという特徴があります。クレジットカードによる納付はできないため、必ず認められた納付方法を選び、計画的に社会保険料を納付しましょう。

合わせて読みたい「社会保険料」に関するおすすめ記事

社会保険料の勘定科目は?仕訳方法や注意点を解説!
Trunkなら社会保険料の納付がもっと簡単に
会社を経営する上で避けて通れないのが、毎月の社会保険料の納付です。社会保険料は、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料といった複数の保険料をまとめて納付する必要があり、納付方法をどう選ぶかが会社の事務負担に直結します。
従来の社会保険料の納付方法は、金融機関窓口で納付書を使って納付するか、電子納付を利用するしかありませんでした。しかし、Trunkを利用して三井住友銀行の法人ネット口座を開設すれば、社会保険料の納付方法を「口座振替」に切り替えることができます。
社会保険料の納付方法に関するポイント!

Trunkを使うことで、社会保険料の納付を自動化でき、納付業務が格段に楽になります。

三井住友銀行 Trunk [PR]
国税や社会保険料の口座振替にも対応。社会保険料等の支払いが楽になるおすすめの法人口座です。
三井住友銀行の法人ネット口座とTrunkの強み
各種手数料が安いから納付コストも削減
三井住友銀行の法人ネット口座は、振込手数料が業界最安値水準の145円。さらに三井住友銀行同士の振込は無料なので、従業員への給与振込や取引先への支払いなど、毎月繰り返す納付や振込コストを大幅に削減できます。
社会保険料の納付に関しても、Trunkを利用することで、納付方法を効率化しつつコスト面でも安心できる仕組みを整えることが可能です。
「社会保険料の納付方法」編集部
社会保険料の納付方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
「三井住友銀行の新サービス「Trunk」を徹底解説!法人向け総合金融サービス・事業用口座の特徴とは」
社会保険料の口座振替に対応できるのはTrunkならでは
最大の特徴は、Trunkを通じて三井住友銀行の法人ネット口座を開設すると、社会保険料の納付方法として「口座振替」が使えるようになることです。これは多くの法人にとって珍しい大きなメリットであり、Trunkならではの強みといえます。
社会保険料の納付方法に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法や、三井住友銀行Trunkを利用した口座振替については以下の記事も是非参考にしてください。
社会保険料の納付方法に関する参考記事:「社会保険料の納付の処理をする(毎月末)」
毎月の社会保険料納付を、窓口納付や電子納付で対応していた場合、納付期限を意識したり、納付書を管理したりする手間が発生します。しかし、Trunkなら社会保険料を自動で納付できるため、納付漏れや納付遅延のリスクを防ぎ、事務負担を劇的に軽減できます。
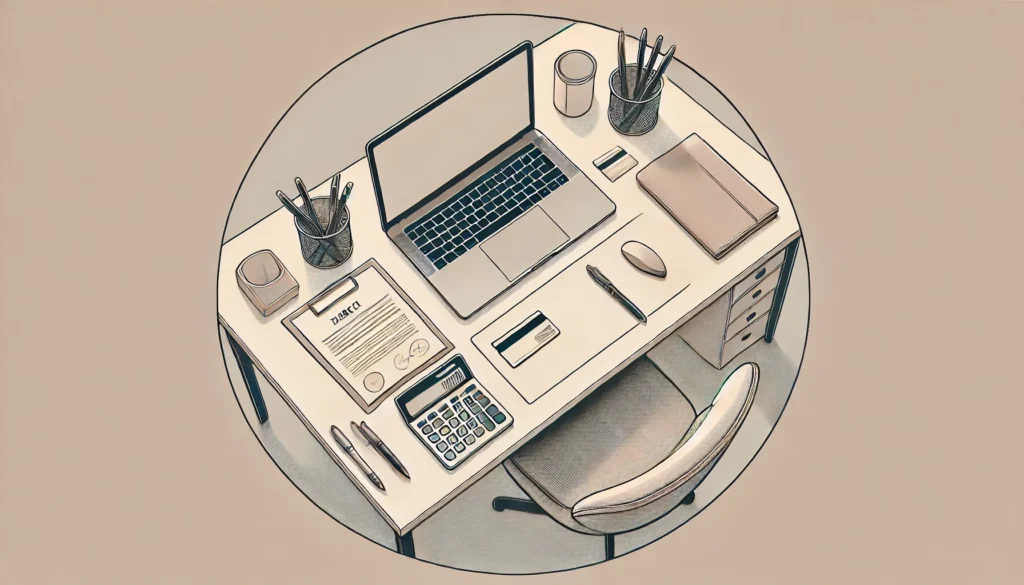
最短翌営業日で口座開設、納付体制もすぐ整う
三井住友銀行の法人ネット口座は、最短翌営業日で開設が可能。Trunkを通じて口座開設を行えば、創業直後の法人でもスピーディーに納付体制を整えられます。必要書類も少なく、オンラインで完結するので、社会保険料の納付方法を早い段階から確実に準備できるのが魅力です。
「社会保険料の納付方法」編集部
Trunkを利用することで、これまで煩雑だった社会保険料の納付が「自動化された納付方法」に変わります。毎月の社会保険料納付にかかる手間が減り、納付書の管理や納付期限の確認に追われる必要もなくなります。
さらに、三井住友銀行の法人ネット口座を利用すれば、社会保険料の納付以外にも税金や公庫返済の納付にも対応でき、会社全体の支払い業務を効率化できます。納付方法をTrunkで一本化することで、経理担当者や経営者の負担を大きく軽減できるのです。

合わせて読みたい「会社設立後に社会保険料の支払開始日」に関するおすすめ記事

会社設立後の社会保険料はいつから支払いが始まる?いつから社会保険に加入するのかについても詳細解説!
社会保険料納付の仕組みとタイミング
社会保険料は、法人が必ず支払わなければならない重要な保険料であり、納付の仕組みや納付方法、納付期限を正しく理解することが大切です。社会保険料は、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料といった制度に基づいて計算され、毎月必ず納付する義務が生じます。ここでは、社会保険料の納付に関する仕組みを詳しく見ていきましょう。

社会保険料の納付先と基本の仕組み
社会保険料は、日本年金機構に納付する決まりになっています。法人は毎月20日前後に送付される「保険料納入告知書(納付書)」をもとに、期日までに社会保険料を納付しなければなりません。社会保険料の納付は、金融機関窓口での納付、口座振替による納付、電子納付の3つの納付方法が認められており、これ以外の納付方法で社会保険料を支払うことはできません。
社会保険料の納付方法に関する注意点

国民年金保険料のようにクレジットカードで納付できるケースもありますが、法人が支払う社会保険料についてはクレジットカード納付は不可です。必ず正式な社会保険料の納付方法を選ぶ必要があります。
社会保険料の納入告知書(納付書)について
社会保険料を納付する際に欠かせないのが、毎月年金事務所から届く納入告知書(納付書)です。社会保険料の納付書は、1枚目が「領収済通知書」、2枚目が「領収控」、3枚目が「納入告知書・領収証書」という3枚つづりで構成され、社会保険料の納付時に必ず使用します。
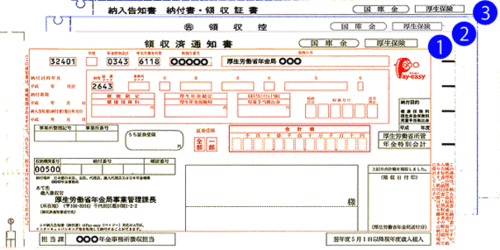
画像引用:日本年金機構「社会保険料の納入告知書(納付書)について」
郵便事情で納付書が届かない場合もあり、その場合は必ず年金事務所に連絡して再発行を依頼しなければ、社会保険料を納付できません。社会保険料の納付業務を滞りなく進めるためには、この納付書の管理が非常に重要です。

三井住友銀行 Trunk [PR]
国税や社会保険料の口座振替にも対応。社会保険料等の支払いが楽になるおすすめの法人口座です。
「社会保険料の納付方法」編集部
社会保険料の納付方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
社会保険料の納付方法に関する参考記事:「社会保険料とは?標準報酬月額の決め方や内訳をわかりやすく解説」
社会保険料の納付方法に関する注意点

納入告知書(納付書)は、毎月20日頃に送付されますが、郵便事情により届くまでに時間がかかる場合があります。
社会保険料の計算方法
社会保険料は、従業員の標準報酬月額に保険料率を掛け合わせて算出されます。標準報酬月額とは、給与を区分ごとに分けた基準額で、健康保険は1級から50級、厚生年金は32級に分かれています。

合わせて読みたい「社会保険 会社負担」に関するおすすめ記事

社会保険料の会社負担割合は?社会保険の計算方法や会社負担の注意点を徹底解説!
たとえば東京都内で協会けんぽに加入し、従業員の標準報酬月額が30万円の場合、社会保険料の計算は次のようになります。
- 健康保険料:30万円 × 9.91% = 29,730円
- 健康保険料(介護保険料込み):30万円 × 11.50% = 34,500円
- 厚生年金保険料:30万円 × 18.30% = 54,900円
このように計算された金額が会社と従業員で折半され、会社は従業員負担分を含めた社会保険料を納付することになります。社会保険料の計算方法を理解しておくことは、毎月の社会保険料の納付額を確認するうえで欠かせません。
社会保険料の納付方法に関する参考記事:「社会保険料の納付方法は?仕組みや納付期限・滞納時のリスクもまとめて解説」
社会保険料の納付期限とスケジュール
社会保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日と定められています。たとえば3月分の社会保険料を納付する場合、4月10日前後に社会保険料の金額が確定し、4月20日ごろに納入告知書が届きます。そして4月30日が納付期限となり、この日までに社会保険料を納付する必要があります。
社会保険料の納付方法に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法や、三井住友銀行Trunkを利用した口座振替については以下の記事も是非参考にしてください。
「社会保険料の納付方法および支払期限と、滞納した場合のリスク」
社会保険料は「支払う月の前月分を納付する」仕組みで動いています。納付期限を守らないと延滞金が発生する可能性があるため、社会保険料の納付はスケジュール管理が重要です。納付方法が口座振替であれば自動的に社会保険料が納付されるため、納付忘れのリスクを防げます。
「社会保険料の納付方法」編集部
社会保険料の納付は、日本年金機構へ納付する仕組みに基づき、納入告知書をもとに行います。
社会保険料の納付方法に関する注意点

社会保険料は、金融機関窓口・口座振替・電子納付という正しい納付方法でのみ納付でき、法人の社会保険料はクレジットカードによる納付は認められていません。
毎月必ず発生する社会保険料の納付を効率的に進めるためには、納付方法の選択と納付期限の管理が不可欠です。社会保険料の納付を確実に行うことが、会社の信頼を守る第一歩といえるでしょう。
社会保険料の納付と支払先
社会保険料の納付は、社会保険料の種類ごとに支払先が異なる点をしっかり理解しておくことがとても重要です。社会保険料は健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料と複数に分かれており、それぞれの社会保険料にはそれぞれ別の支払先が存在します。
会社は給与から社会保険料を控除したうえで、正しい支払先へ社会保険料を納付する必要があり、支払先の把握が不十分だと納付遅延や手続きミスにつながる可能性があります。
社会保険料の納付と支払先に関する参考記事:「社会保険料の支払い方法や納付期限、滞納するリスクをわかりやすく解説」
具体的には、健康保険料と厚生年金保険料の支払先は日本年金機構、雇用保険料と労災保険料の支払先は労働局やハローワークです。
「社会保険料の納付と支払先」編集部
社会保険料の納付と支払先の対応関係を理解しておくことで、毎月の社会保険料の納付業務をスムーズかつ正確に進められます。
| 社会保険の種類 | 社会保険料の支払先 | 納付の管轄 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 日本年金機構(支払先) | 協会けんぽ等 |
| 厚生年金保険料 | 日本年金機構(支払先) | 厚生年金制度 |
| 雇用保険料 | 労働局・ハローワーク(支払先) | 労働保険料管理 |
| 労災保険料 | 労働局(支払先) | 労働保険料として納付 |
社会保険料を滞納した場合の罰則とは?
社会保険料は会社にとって必ず納付しなければならない法的義務です。社会保険料を納付しない、あるいは納付が遅れると、それは重大な違反行為とみなされ、厳しい罰則が適用されます。社会保険料は従業員の生活や将来の年金にも直結する重要な保険料であるため、納付を怠れば企業としての信頼を失うことにもつながります。ここでは、社会保険料の納付を滞納した場合にどのような罰則が科されるのかを詳しく解説します。
社会保険料の納付方法に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法や、三井住友銀行Trunkを利用した口座振替については以下の記事も是非参考にしてください。
「初めての方向け!社会保険料の納付はどんな流れ?」
社会保険料滞納の罰則①
社会保険料滞納による遅滞金の発生
社会保険料の納付期限を過ぎてしまうと、すぐに「遅滞金(延滞金)」という罰則が課されます。社会保険料は必ず納付期限までに納付しなければならず、1日でも遅れると納付額に遅滞金が上乗せされます。
遅滞金は滞納期間が長引くほど重くなります。3か月以内の滞納であれば年2.4%の利率ですが、3か月を超えて社会保険料を納付しない場合は年8.7%という高い割合が課されます。社会保険料を納付せずに放置するほど、社会保険料の納付総額は膨らみ、企業の財務負担は大きくなっていきます。
「社会保険料の納付方法」編集部
社会保険料の納付方法については以下のサイトも是非ご覧ください。
社会保険料の納付方法に関する参考記事:「保険料の納付方法について」

合わせて読みたい「社会保険の罰則」に関するおすすめ記事

社会保険の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!
社会保険料滞納の罰則②
社会保険料未納による納付処分・強制執行
社会保険料を納付せず、督促を無視した場合は、さらに重い罰則が適用されます。行政による「納付処分」に移行し、社会保険料の未納分を強制的に納付させる措置が取られます。
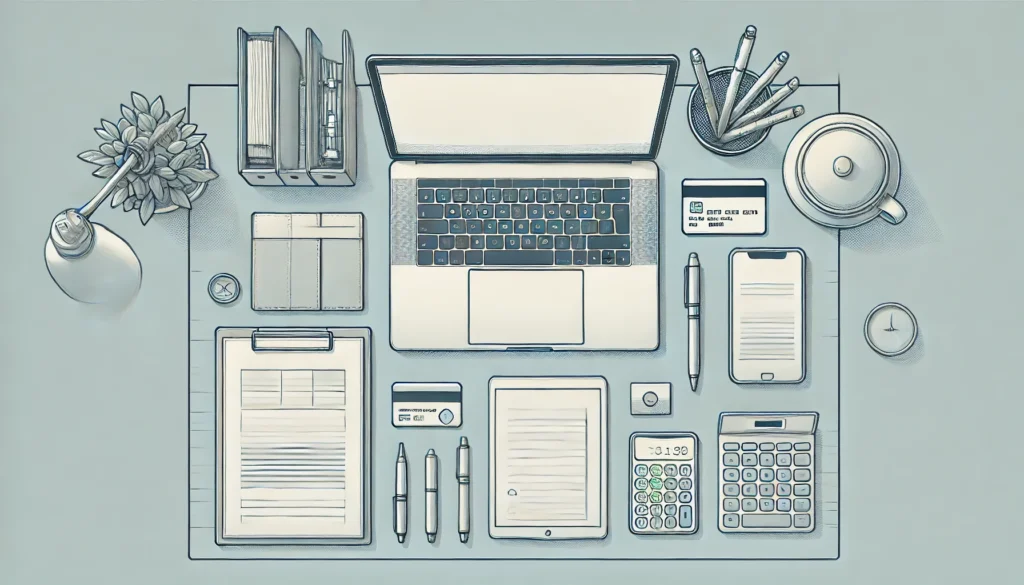
社会保険料の納付方法に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法や、三井住友銀行Trunkを利用した口座振替については以下の記事も是非参考にしてください。
社会保険料の納付方法に関する参考記事:「厚生年金保険料とは?計算方法や納付方法を企業向けに解説」
「社会保険料の納付方法」編集部
納付処分の流れは次のとおりです。
- 納付指導(最終的な納付の警告)
- 財産調査(納付資力の確認)
- 差押え(銀行口座や売掛金に対する強制的な納付)
- 財産換価(差押え資産を現金化し、社会保険料に充当)
- 国税庁への委任による滞納整理(社会保険料の最終的な強制納付)
このように、社会保険料を納付しなければ、差押えなどの強制的な罰則に発展し、会社経営そのものに深刻な影響を及ぼします。

合わせて読みたい「社会保険 加入条件」に関するおすすめ記事

社会保険の加入条件とは?手続き方法や提出書類を解説!
社会保険料滞納の罰則③
社会的信用の低下と経営リスク
社会保険料の納付を怠ると、金銭的罰則だけでなく、企業の信用を大きく失うという二次的リスクも発生します。
- 社会保険料を滞納した事実は金融機関の融資審査に悪影響を与え、資金調達が難しくなる
- 悪質な場合は社会保険料滞納事業者として官報に掲載される可能性があり、社会的に「納付義務を果たさない企業」という烙印を押される
- 社会保険料が納付されていないことで従業員が損害を受け、訴訟や労務トラブルに発展する
社会保険料を納付しなければ、会社のイメージ悪化だけでなく、従業員からの信頼喪失という深刻な問題にもつながります。
社会保険料の納付方法に関する参考記事:「国民年金保険料のかんたんな納付方法」
【まとめると…】社会保険料の納付方法と仕組みを理解しよう
社会保険料の納付は、企業や個人事業主にとって毎月欠かせない義務です。社会保険料の仕組みは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などを、事業主と従業員が一定の割合で負担し合う制度になっています。給与から天引きされた社会保険料を会社がまとめて納付するのが一般的な流れです。
社会保険料の納付方法には、金融機関での納付、SMBC Trunkなどの口座振替による自動引き落とし、電子納付(e-Gov・e-Taxなど)といった複数の選択肢があり、特に電子納付は手間を減らしやすい方法として注目されています。正しい社会保険料の納付方法と仕組みを理解し、期限内に納付を行うことで、行政手続きの遅延や延滞金のリスクを防ぐことができます。
| 納付方法 | 特徴 | メリット | 向いている事業者 |
|---|---|---|---|
| 金融機関窓口での納付 | 納付書を使って銀行や郵便局で支払い | 現金・振込で確実に納付可能 | 小規模事業者や初めて納付する会社 |
| 口座振替(自動引き落とし) | 登録した口座から自動で引き落とし | 納付忘れ防止・手続き簡単 | 継続的に社会保険料を納付する企業 |
| 電子納付(e-Gov・e-Taxなど) | オンラインで社会保険料を納付 | 24時間手続き可能・ペーパーレス化 | 効率化を重視する中小企業・法人 |

三井住友銀行 Trunk [PR]
国税や社会保険料の口座振替にも対応。社会保険料等の支払いが楽になるおすすめの法人口座です。
社会保険料の納付は一見複雑に感じますが、納付方法と仕組みを正しく把握しておくことで、日々の労務管理をスムーズに進められます。近年は電子納付の普及により、社会保険料の手続きもデジタル化が進んでおり、今後はより効率的な運用が求められています。
まとめ:社会保険料の納付方法とは
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険料は、法人が従業員を雇用する以上、必ず納付しなければならない大切な義務です。社会保険料は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料などから構成されており、毎月の社会保険料を正しく納付することが会社の信用を守る基本となります。
社会保険料の納付方法には、金融機関窓口での社会保険料納付、口座振替による社会保険料納付、電子納付による社会保険料納付といった複数の納付方法があります。どの納付方法を選ぶかによって、社会保険料の納付の効率性や手間は大きく変わります。特に口座振替など自動化された納付方法を活用すれば、社会保険料の納付忘れを防ぎ、毎月の納付業務の負担を大きく減らすことができます。
一方で、社会保険料を納付期限までに納付しなければ、遅滞金や強制的な納付処分といった罰則が課されるリスクもあります。だからこそ、社会保険料の納付は計画的に行い、常に正しい納付方法で確実に納付することが欠かせません。
社会保険料は毎月必ず納付するものだからこそ、納付方法を正しく理解し、効率的に社会保険料を納付する仕組みを整えておきましょう。社会保険料の納付をスムーズに進めることが、企業経営の安定につながるのです。

合わせて読みたい「社長の社会保険」に関するおすすめ記事

社長は社会保険に入れない?社会保険に入れる場合と、入れない場合や注意点を解説します!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドとの違いを徹底比較!ビジネスオーナーズ ゴールドを持つメリットとは
-
ビジネスカード

2026年1月27日
2
三井住友カードビジネスオーナーズ2枚持ちのメリットは?2枚持ちにおすすめの個人カードや選び方も紹介
-
ビジネスカード

2026年1月27日
3
三井住友ビジネスオーナーズのメリット・デメリットとは?ゴールドとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月27日
4
三井住友ビジネスオーナーズゴールドのメリットは?一般カードやfor Ownersとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月27日
5
即日ファクタリング来店不要おすすめ15選!選び方から注意点まで徹底解説
-
資金調達

2026年1月24日













SoVaをもっと知りたい!