税務調査の流れとは?調査対象となる確率や時期についても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年6月
更新日:2025年12月6日
税務調査という言葉を聞いて、何を準備すればいいのか、どんな流れで調査が進むのか不安に感じる方は多いのではないでしょうか。税務調査の流れを事前に知っておくことは、突然の調査にも冷静に対応するための大きな武器になります。
この記事では、税務調査の流れを初動から完了まで順を追って詳しく解説するとともに、実際に税務調査の対象となる確率や、税務署が税務調査を行いやすい時期の傾向についてもわかりやすく紹介します。
「うちの事業は税務調査の対象になる可能性があるのか?」「税務調査が入ったらどういう流れで進むのか?」「税務調査はいつ頃行われやすいのか?」といった疑問をお持ちの方にとって、この記事は最適な情報源です。
税務調査の流れをしっかりと理解し、調査に向けた心構えと準備を整えることで、万が一税務調査の通知が届いたとしても慌てず対応できます。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査の基本、税務調査の流れ、そして税務調査の確率と時期まで、このページで一気にチェックしておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
税務調査とは
税務調査とは、税務署や国税局が行う調査のことで、納税者の申告内容が正確であるかどうかを確認するために実施されます。法人税や所得税などの税金は、申告納税制度に基づいて納税者が自分で申告・納付を行いますが、誤りや不正を未然に防ぐために税務調査が必要になります。
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査の流れ|チェックされるポイントや注意点も解説」
税務調査は、法人や個人事業主はもちろん、確定申告をしているすべての納税者が対象となり得ます。税務調査によって、過少申告や無申告、仮装・隠蔽といった問題が見つかるケースもあるため、税務調査は税制の公正性を保つために欠かせない仕組みといえるでしょう。
税務調査には大きく分けて2つの種類があります。税務調査の流れを理解するには、まず「任意調査」と「強制調査(犯則調査)」の違いを把握することが大切です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
近年、税務署でもAIを活用しているため税務調査リスクは増大しているため、顧問税理士と相談しながら正確な日々の記帳がもとめられます。2024年には追徴課税額が過去最高を更新しています。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
任意調査の税務調査の流れ
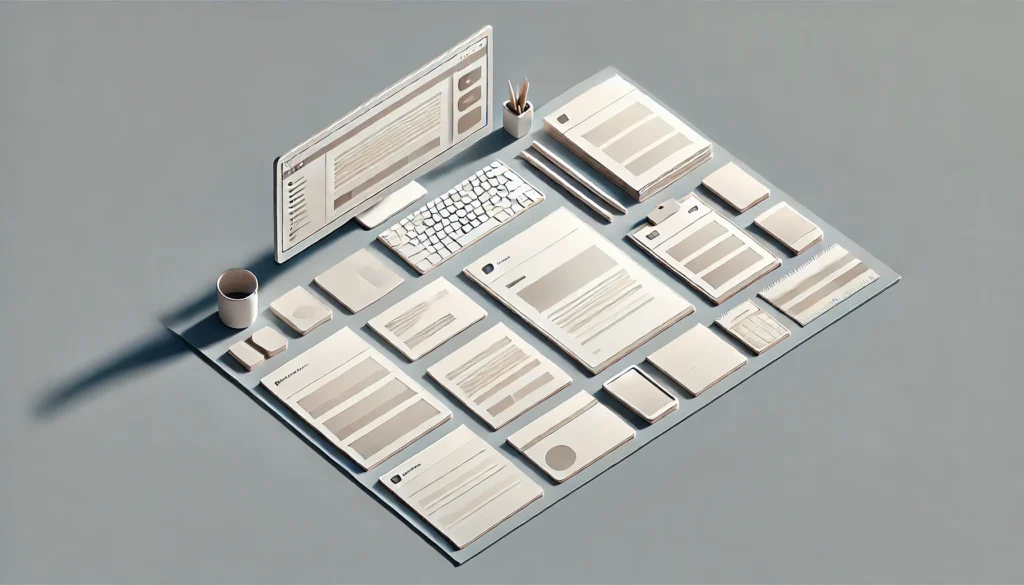
任意調査は、税務署が納税者に事前連絡を行い、協力を得ながら進める税務調査です。税務調査の大半はこの任意調査に該当し、通常は電話や書面での通知を経て日程を調整し、2日程度にわたって税務調査が行われます。
税務調査の流れに関する注意点

税務調査という言葉には「任意」とありますが、納税者には調査を受け入れる義務(受忍義務)があるため、税務調査を拒否したり、帳簿を見せないといった行為は罰則の対象になることがあります。
また、任意調査でも「無予告」で突然始まる税務調査も存在します。帳簿の改ざんや隠蔽が疑われる場合、税務署は税務通則法に基づき無予告の税務調査を行うことがあります。このような税務調査では、事前通知がない代わりに、調査理由を後から確認することも可能です。
強制調査(犯則調査)の税務調査の流れ
「税務調査の流れ」編集部
強制調査は、いわゆる「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が実施する税務調査です。
裁判所の令状に基づいて行われ、納税者の意思に関係なく強制的に行われる税務調査であり、脱税の立件を目的とするケースが多くなります。
このタイプの税務調査は、事前の通知や調整がなく、調査官が突然現れて帳簿や関係書類の押収を行います。通常の税務調査とは異なり、調査そのものが刑事手続きの一環であり、悪質な脱税事案などで用いられます。
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
「税務調査される個人事業主の特徴は?3つの対策と対象になったときに取るべき対応を解説」
税務調査の流れを完全網羅|準備・実地・通知・結果・その後の対応まで詳細解説
税務調査とは、納税者の申告内容に誤りや不正がないかを確認するために、税務署または国税局が行う公式な調査です。法人・個人を問わず、事業を行っているすべての納税者が税務調査の対象となる可能性があり、調査の内容は申告書類の確認から帳簿、契約書、領収書、さらには経営者個人の資金の動きにまで及ぶことがあります。
ここでは、税務調査の目的をふまえたうえで、実際にどのような流れで進んでいくのかを、「準備」「通知」「実施」「結果通知」「事後対応」までの流れごとに詳細に解説します。
税務調査の全体像を把握し、その一連の流れを理解しておくことが、適切な事前準備と冷静な対応につながります。
税務調査の全体の流れ|準備調査から実地調査へ
税務調査は、大きく「準備調査」と「実地調査」に分けられ、段階的な流れで進行します。

合わせて読みたい「税務調査の税理士費用」に関するおすすめ記事

税務調査の税理士費用の相場はいくら?税理士立合いのメリットも解説!
準備調査の流れ
税務調査の流れの出発点は、「準備調査」と呼ばれる非公開の内部調査です。この段階では、税務署職員が納税者に通知することなく、申告書の内容と各種法定調書・支払調書・外部情報などを突き合わせ、異常値や不審な動きがないかを確認します。
「税務調査の流れ」編集部
この水面下の税務調査の流れは、納税者側が気づかないまま進行します。もしも不明点や不整合が確認された場合、次のステージとして実地調査へ移行する流れとなります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
実地調査の種類と流れ|税務調査の手法は4パターン
準備調査を経て、調査の必要性が高いと判断された場合、税務調査の流れは「実地調査」に進みます。実地での税務調査は、状況に応じて4つの調査形式に分類され、それぞれ異なる流れで実施されます。

合わせて読みたい「税務調査で税理士に依頼するかどうか」に関するおすすめ記事
税務調査に税理士は必要?税理士に依頼するメリット・デメリットまで紹介

一般調査の流れ
税務調査のなかでも最も標準的なのが「一般調査」です。税務署から事前に電話や文書で連絡があり、調査の日程、対象税目、対象期間などの調整を経て、税務調査官が会社や事務所に出向きます。
帳簿や証憑書類、契約関係書類などを用いて申告内容の妥当性を確認するのが一般調査の基本的な流れです。一般的には1~3日程度の調査日程で完了する流れですが、内容や規模によっては延長されることもあります。
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
「税務調査はいつ来る?事前準備に必要な書類や調査の流れを解説」
現況調査の流れ
現況調査は、税務調査官が事前通知なしで現場を訪れる無予告型の調査です。
「税務調査の流れ」編集部
主に飲食業や小売業など、現金取引が中心の業種が対象となります。
帳簿の隠蔽や改ざんといった不正の疑いがある場合に選ばれる税務調査で、突然始まる流れに驚く方も少なくありません。ただし、現況調査も任意調査の範囲であるため、調査の流れの中で日程の再調整を求めることも可能です。
特別調査の流れ
特別調査は、一般調査よりも調査期間が長く、複雑な取引や多数の関係会社を持つ大企業などに行われます。調査の流れとしては、数回にわたって実地調査が行われ、通常よりも詳細で時間を要するのが特徴です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
税務調査以外に、社会保険調査については以下の記事も是非参考にしてください。
「 社会保険調査は厳しいのか?年金事務所の調査がくる理由と流れを解説 」

合わせて読みたい「国税局からの電話」に関するおすすめ記事

国税局から電話が来る理由を解説!注意点と対応方法も紹介
企業グループ全体の構造を把握し、連結取引や税務リスクの分析を行うため、調査の流れは複雑かつ広範囲にわたります。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査とは?流れと対応のポイントを弁護士がわかりやすく解説」
反面調査の流れ
反面調査は、調査対象の納税者本人ではなく、その取引先や金融機関など第三者に対して行われる税務調査です。納税者の主張が事実かどうかを裏付けるために実施されるもので、間接的に調査の正確性を高めるための流れに組み込まれています。

合わせて読みたい「税務調査で追徴課税はいくら?」に関するおすすめ記事

税務調査で追徴課税はいくら取られる?いくらから調査対象になるのかも詳しく解説!
税務調査の進行の流れ(時系列)
次に、税務調査が実際にどのような流れで展開されていくのか、ステップバイステップで整理します。
① 税務調査の通知と連絡の流れ
税務調査の第一報は、通常、税務署からの電話連絡で始まります。1~2週間前に通知され、調査の対象税目・期間・調査官の人数・実施予定日などが伝えられる流れです。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
「税務調査の流れ」
税務代理権限証書を提出している場合には、税理士に直接通知されるのが基本的な流れとなります。
② 日程調整と準備の流れ
調査日程は通知後に調整され、納税者や税理士のスケジュールに応じて決定される流れです。やむを得ない理由があれば日程変更も可能です。
調査日が決まったら、帳簿や契約書、証憑資料などの準備に入る流れとなり、税務調査の質問に備えて、経営の実態や数字の根拠を説明できるよう整理しておくことが重要です。
税務調査当日の流れ
税務調査の当日は、調査官の来社から始まり、社長や担当者との会話、帳簿や証憑類の確認、現場の状況確認など、一連の流れで進行していきます。
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査とは?対象となる法人・個人、確率・時期・流れなどを解説」
この税務調査の当日の流れをあらかじめ理解しておくことで、慌てずに対応し、余計な誤解や疑念を招かずに調査を終えることが可能になります。
ここでは、税務調査の流れを「初日の午前」「初日の午後」「2日目以降」の3段階に分けて、具体的かつ詳細にご紹介します。税務調査の全体の流れを知ることが、スムーズな対応の鍵となります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【初日午前】税務調査の流れは会話から始まる
税務調査の当日の流れは、通常、朝10時頃に税務調査官が来社することから始まります。来訪直後、まずは身分証明書の提示が行われ、ここで正式に税務調査の実施が開始される流れになります。
税務調査の流れにおいて、初めの段階では帳簿を開いて数字の確認をするのではなく、調査官との雑談を交えた会話が中心となります。調査官は、天気や経済状況などの軽い話題から入り、徐々に会社の実態や経営の方向性に関する聞き取りへと話題を移すという流れで進行します。
この「会話中心の流れ」には、調査官が会社の雰囲気や経営者の姿勢を見極めるという意図が含まれており、税務調査の重要なファーストステップとなります。

「税務調査の流れ」編集部
雑談から本題へと話題が移る流れの中で、以下のような質問が出てくることが一般的です。
- 自社の業務内容とその特徴について
- 現在の経営方針や将来の見通し
- 役員構成とその役割
- 従業員の雇用条件や勤務実態
- 取引金融機関や資金繰りの方法
- 主要な取引先とその背景関係
これらのやり取りは、今後の調査をどのような流れで進めていくかを判断するための材料となります。つまり、税務調査の午前中の流れは、「事前情報の整理」と「現場感覚の確認」を目的とした情報収集フェーズと言えるでしょう。
【初日午後~2日目以降】税務調査の流れは帳簿精査と現場確認へ
午前中のヒアリングが終了すると、税務調査の流れは帳簿・証憑類の確認や現場の確認へと本格化していきます。ここからは、税務調査の流れが「数字に基づいた実証フェーズ」へと移行します。
■ 現金監査の流れ
まず行われるのは、当日の現金残高と帳簿上の金額が一致しているかを確認する現金監査です。この流れでは、現金出納帳と実際の現金残高が一致しているかをチェックすることで、資金管理の正確性を判断されます。
税務調査における現金監査の流れは、調査官が不正流用や資金移動の痕跡を確認するための重要なポイントです。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査の流れを全解説!調査時の注意点5選も併せて紹介」
■ 金庫・書庫・事務所内の調査の流れ
次に、税務調査の流れの一環として、金庫や事務室内の書類、未処理資料、メモ、手書きの記録など「原始記録」が確認されます。
この流れの目的は、表に出てこない情報や隠された取引の有無を見つけ出すことであり、必要に応じて業務用メールの内容まで調査の対象になる場合があります。
■ 棚卸資産の確認の流れ
商品や原材料などの棚卸資産の実在確認も、税務調査の流れに含まれます。特に、積送品・預け品・返品在庫・無償支給品などの管理状況が適正かをチェックし、在庫の過少申告がないかを確認する流れです。
在庫関連の調査は、売上や仕入と密接に関係するため、税務調査の流れの中でも非常に重要なパートになります。
■ 経営概況の聴取の流れ
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査とは?調査の流れや時期、必要書類について解説」
調査官は、会社の経営状況や資金繰り、借入状況、役員報酬、さらには経営者の生活状況や趣味にまで踏み込んだ質問をしてくることがあります。これは、税務調査の流れの中で、事業と個人の金銭的関係や生活レベルに矛盾がないかを見極めるためです。
■ 帳簿・証憑の確認の流れ

経費(特に交際費・特別損失・外注費など)に関する帳簿・領収書・請求書などの確認が、税務調査の流れの中でも最も時間を要する部分です。
税務調査の流れに関するポイント!

税務調査官は金額の妥当性や取引の経緯を尋ねてくるため、即答できるよう準備しておくことで流れをスムーズに進めることが可能です。
【よくある質問とその流れ】税務調査で問われやすい項目
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査の流れは?指摘を受けやすい法人の特徴や注意点の解説」
税務調査の流れの中で、調査官からは以下のような具体的な質問がなされます。これらの質問は、調査の焦点を絞るための確認事項であり、全体の流れを左右することもあります。
- 納品書の作成タイミングは?
- 請求書の金額の根拠や決定プロセスは?
- 発注書や契約書はどこに保管してあるか?
- 特別取引や高額支出の理由と説明の妥当性
- 経費の妥当性と社内ルールの有無
このような質問に曖昧な回答をしてしまうと、税務調査の流れが長引くリスクが高まります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
「税務調査の流れ」編集部
経理担当者や経営者は、会社の資金の流れについて詳細に説明できる準備をしておくことが重要です。
税務調査終了後の流れ|結果通知とその後の対応
税務調査が終了したあとは、通常、1カ月以内に調査結果が通知される流れになります。税務調査の結果に基づき、次のような対応が求められます。

合わせて読みたい「税理士変更による税務調査」に関するおすすめ記事
法人税務調査で指摘事項への対応は?税務調査の基礎から対策まで解説!

申告是認(流れの終了)
調査の結果、申告内容に問題がないと認められた場合は「申告是認」となり、税務調査の流れはここで完結します。
修正申告(流れの修正)
申告内容に一部誤りが認められた場合、税務署から修正申告を促される流れとなります。納税者が指摘に同意すれば、自主的に修正申告を行い、調査の流れは是正措置へと進みます。
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
更正通知(強制的な流れ)
指摘内容に納得できず修正申告を行わない場合、税務署は「更正処分」を通じて強制的に課税額を変更する流れになります。不服があれば審査請求や訴訟も可能ですが、専門家との相談が重要です。
個人事業主に税務調査が入る確率とは?税務調査の流れや対象となる傾向を徹底解説
「個人事業主にも税務調査は来るの?」「税務調査の確率ってどれくらい?」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。実際、税務調査は法人だけでなく、個人事業主に対しても行われるものであり、毎年一定数の個人が税務調査の対象となっています。ここでは、個人事業主が税務調査を受ける確率や、税務調査の選定基準、税務調査の流れについて詳しく解説します。
個人事業主が税務調査を受ける確率はどれくらい?
国税庁が公表した令和3年度(2021年度)の統計によると、個人に対して実施された実地による税務調査の件数は約28万3,000件にのぼります。一方で、同年度に確定申告を行った個人事業主(事業所得・不動産所得のみ)は約657万人でした。
これらの数字から算出すると、個人事業主が税務調査を受ける確率は約0.5%、つまり200人に1人程度の割合で税務調査が実施されているという計算になります。
税務調査の流れに関する注意点

これは「100年に1回程度税務調査が入る」という感覚に近く、表面的には非常に低い確率に見えるかもしれません。しかし、税務調査は無作為に行われるものではなく、一定の傾向や基準に基づいて選定されるため、条件によっては税務調査の確率が一気に高まることもあります。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が行われる流れには、明確な判断基準が存在するのです。
税務調査が個人事業主に行われる流れと判断要因
税務調査は、ただ確率の問題ではありません。税務調査には「税務署が調査の必要性ありと判断したときに実施される」という基本原則があり、そこには次のような税務調査の流れを決定づける要素があります。
- 毎年の確定申告で赤字計上が続いている
- 所得が大きく増減している
- 経費の計上が著しく多く、不自然である
- 現金商売や売上計上時期に曖昧さがある
- 税務署への通報や指摘が入った
- 過去に税務調査を受け、指摘事項があった
このような項目に該当する場合、税務署は「調査対象として適正かどうかを検討する」という税務調査の初期流れ(準備調査)を行い、その結果によって実地調査へと進む税務調査の本格的な流れが開始されることになります。
法人や会社が受ける税務調査の確率と税務調査の流れ

税務調査は個人事業主だけでなく、法人や会社にも実施されます。むしろ、法人のほうが税務調査の対象となる確率は高いとされています。
令和4年度(2022年度)の統計では、法人税の申告件数は約313万件、実施された法人への税務調査は約6万2,000件と発表されています。これらの数値をもとに計算すると、法人が税務調査を受ける確率は約1.98%。つまり、法人は50社に1社の割合で税務調査の対象となっているということになります。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
「税務調査の流れ」
税務調査の流れに乗るかどうかは、法人の業種・規模・利益率・急成長の有無・過去の税務調査歴などによって大きく左右されます。たとえば、現金商売の多い業種や、新規設立から急成長している企業、過去に税務調査で指摘を受けた会社などは、税務調査の流れに入りやすいとされています。
税務調査に進む流れを防ぐ方法
税務調査は、ある日突然に通知されるように見えて、実は準備調査→実地調査→結果通知という一連の税務調査の流れを経て進行します。
税務調査の流れに関する参考記事:「社長も経理担当者も知っておきたい、法人企業の税務調査の流れ」
「税務調査の流れ」編集部
税務調査の対象に選ばれないためには、まずこの税務調査の流れを理解し、どの段階で何が判断材料になっているのかを知ることが重要です。
税務調査の流れを防ぐためには以下のような取り組みが有効です。
- 帳簿・領収書を日々正確に記録・保管する
- 不明確な経費や売上は控え、裏付けを整える
- 税理士に定期的に相談し、整合性をチェックする
- 不自然な取引や架空経費の計上を避ける
- 事業と私的な支出を明確に分離する
これらを意識することで、税務署から見て「税務調査を行う必要性がない」と判断されやすくなり、税務調査の流れ自体に入らない確率を高めることができます。
税務調査が行われやすい時期とは?流れとスケジュールの傾向を解説
税務調査は、ある日突然通知が届くことが多いため、「いつ税務調査が来るのか?」「どの時期に税務調査が集中しやすいのか?」と不安に思っている方も少なくないでしょう。
実は、税務調査には法律で定められた実施時期があるわけではありませんが、過去の実績や運用上の事情から、税務調査が行われやすい時期やその流れには一定の傾向があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税務調査の流れを把握するには、調査が開始されやすい時期を知ることも重要です。以下では、税務調査が実施される可能性が高い時期とその背景、そしてその後の流れについて詳しく解説します。
税務調査の実施時期に決まりはないが、実は集中しやすい時期がある
税務調査には「この月に必ず実施される」といった決まった時期はありません。しかし、国税庁や税務署の運用上、税務調査が行われる時期には偏りがあるのが現実です。
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
「税務調査の流れを解説!スムーズに税務調査を乗り切るポイントとは?」
特に税務調査が集中しやすいのは、以下の2つの時期です。
■ 4月〜5月:確定申告明けの税務調査の動きが始まる時期
3月に確定申告業務が終了すると、税務署の職員に一定の余裕が生まれ、税務調査の準備や実施が本格化する時期に入ります。
このタイミングで、税務署は「準備調査」と呼ばれる税務調査の事前段階に着手し、申告内容の確認や情報収集を進め、必要に応じて実地調査の税務調査に移行する流れとなります。

合わせて読みたい「税理士に依頼する時の費用」に関するおすすめ記事
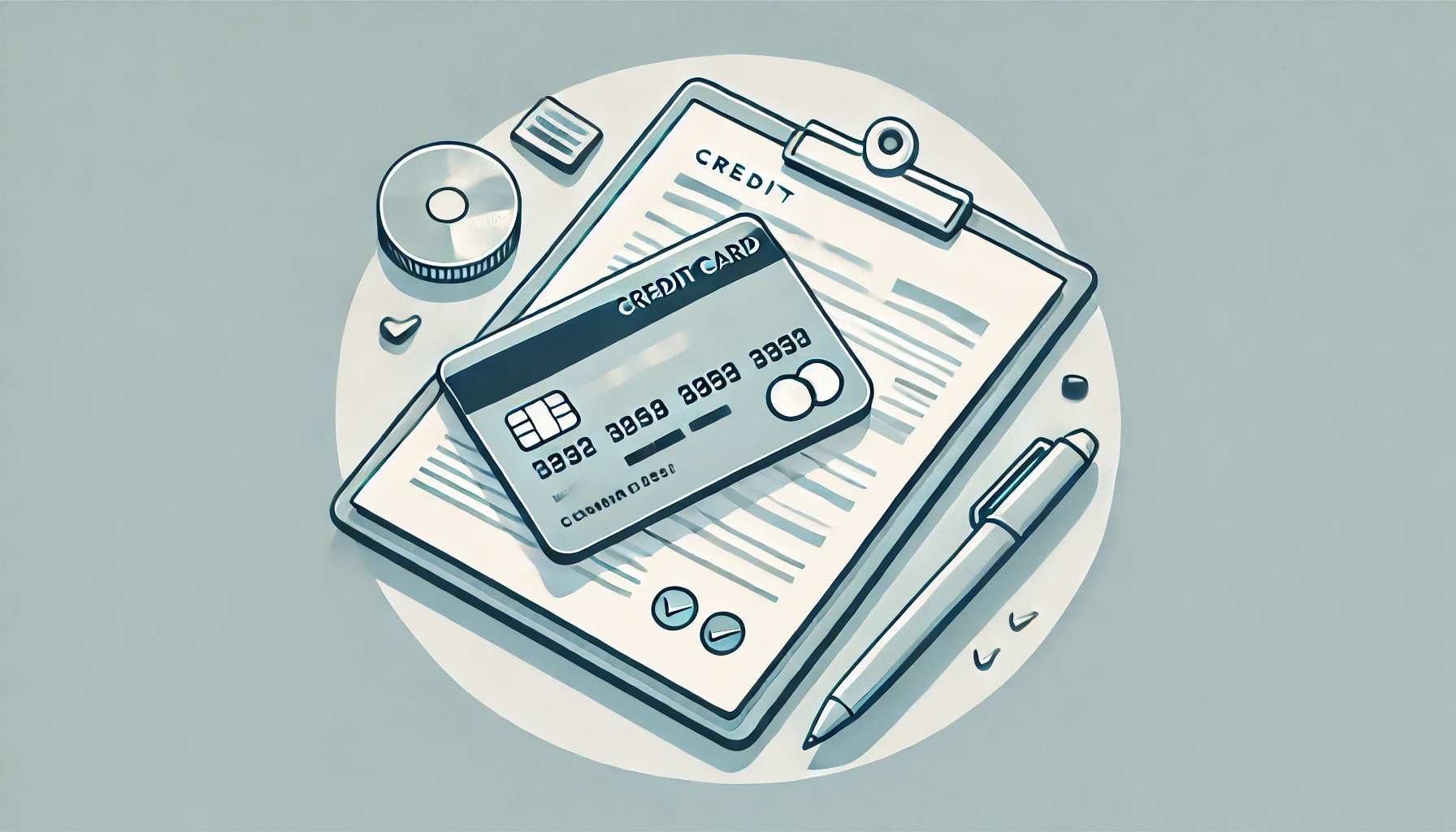
税務調査はいつ来るのか?税務調査の対象となる法人や個人、時期と流れなどについて解説!
■ 7月〜11月:人事異動後に税務調査が一気に活発化
毎年6月末前後に行われる税務署や国税局の人事異動が落ち着くと、新体制が整った税務署では税務調査の計画と実施が急ピッチで進められるようになります。
この時期は、税務調査の通知が届きやすく、実地調査が多く行われる時期としても知られているため、事前に準備しておくことが重要です。
税務調査の通知が届いた場合、その後の流れとしては1〜2週間以内に税務調査が実施され、帳簿確認や現場視察といった一連の税務調査の流れが始まるのが一般的です。
税務調査が行われにくい時期も存在する?
「税務調査の流れ」編集部
一方で、税務調査がほとんど行われない時期もあることをご存じでしょうか?
それが1月〜3月です。この期間は、税務署にとって確定申告業務が最も忙しくなる「繁忙期」にあたります。
このため、税務調査のための人員が不足しがちであり、税務調査の実施件数も他の時期に比べて明らかに少ない傾向があります。
ただし、税務調査が完全に行われないわけではありません。特に緊急性の高い案件や、重大な申告漏れ・脱税の疑いがある場合には、例外的にこの時期にも税務調査が行われる流れとなることがあります。
決算月ごとに異なる税務調査の流れ
税務調査は、会社や個人事業主の決算月・申告月に応じて実施時期がずれるという特徴もあります。
たとえば、3月決算の法人であれば、法人税の申告は通常5月末。その後、税務署側で準備調査が行われ、秋口(9月〜11月)に税務調査の通知が届くという流れになることが多いです。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査の流れに関する参考記事:「個人への税務調査の種類と実地調査の流れ」
税務調査のこのような流れは、「申告後しばらく時間が経ってから実施される」というのが一般的です。これは、税務署が申告書類や外部情報をもとに調査対象を選定するために一定の時間を要するからです。
税務調査の流れを予測することで、先手の対策が可能に
税務調査がいつ行われるかを100%予測することはできませんが、税務調査の実施時期の傾向や税務調査の流れを知っておくことで、先手を打って準備することが可能になります。

税務調査の流れに関するポイント!

税務調査は突然通知が届き、数日後には調査官が来社するという流れが一般的です。そのため、税務調査の実施が増える春や秋に向けて、帳簿の整理や証憑の準備を整えておくことが重要です。
また、税務調査の流れに沿って、「初日午前のヒアリング」「午後以降の帳簿精査」「2日目の現場確認」といった実施内容にも備えておくと、実際に税務調査が行われた場合にも冷静に対応できます。
税務調査の流れとチェックポイント|どのような点が調査対象になる?
税務調査では、どのような流れで調査が行われ、どのポイントが重点的に確認されるのかを知っておくことで、万が一の際に慌てずに対応できます。税務調査の流れをあらかじめ把握し、想定される質問や確認内容に備えておくことは、スムーズな対応とトラブル回避に直結します。
「税務調査の流れ」編集部
ここでは、税務調査の流れに沿って「売上」「経費」「在庫」「増減の大きい項目」といったチェックポイントについて、詳しく解説していきます。
売上の期ズレは税務調査の流れで必ず確認される要注意ポイント
税務調査の流れにおいて、まず注目されるのが「売上の計上時期」です。いわゆる期ズレ(売上の繰延べや費用の前倒し)は、利益を操作しようとする意図があるとみなされる可能性があり、税務調査の中でも特に厳しく確認されるポイントです。

合わせて読みたい「税務調査の流れ」に関するおすすめ記事

税務調査の流れは? 法人の税務調査での指摘ポイントや税理士の役割まで解説!
税務調査の流れとしては、帳簿や請求書、契約書などをもとに「この売上はどの期に属するべきか」という観点で整合性を確認されます。
税務調査の流れに関する注意点

たとえ故意でなくとも、税務調査の流れの中で期ズレが発見されれば、修正申告や追徴課税の対象になる恐れもあります。
増減の大きい項目も税務調査の流れで着目される
税務調査の流れでは、前年との比較や異常値に着目するのが一般的です。例えば「交際費が前年より急増している」「売上が不自然に減少している」といったケースでは、税務調査の流れにおいて調査官から詳細な説明を求められます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
こうした項目は、税務調査の初期段階から重点的に確認されることが多く、取引先とのやり取り、契約書、請求書などを用意しておくことで、税務調査の流れが円滑に進みます。
税務調査の流れに関するポイント!

変動の理由が正当であり、それを示す証拠があれば、税務調査の後半での指摘を回避できる可能性が高まります。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査とは?流れや必要書類、対応方法の解説」
経費の計上内容も税務調査の流れの中で確認される
税務調査の流れでは、経費の妥当性も徹底的にチェックされます。税務調査官は、事業に関係ない私的な支出が混在していないか、架空経費が計上されていないかという点を、証憑書類や帳簿と照合しながら確認します。
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
税務調査の流れに関する参考記事:「相続税の税務調査!質問内容集や当日の流れ、調査時期を紹介」
特に、税務調査の流れの中では飲食代・交通費などの曖昧な支出が注目されやすく、利用頻度の高い店や、領収書のない支出は、私的流用を疑われるリスクがあります。税務調査の後半でトラブルにならないよう、事業関連性の説明や証拠の準備が重要です。
在庫の確認も税務調査の流れの中で重要な工程
税務調査の流れにおいて、製造業や卸売業、小売業など在庫を抱える業種では、「棚卸資産の計上状況」も欠かせない確認事項です。税務調査の流れの中で在庫の計上漏れや過大計上が見つかると、納税額に直接影響を与えるため、調査官も慎重に確認します。
税務調査の中盤以降には、以下のような項目が流れに沿って調べられます。
- 未着品:発注済だが未納品のもの
- トラック品:出荷済だが売上未計上の商品
- 仕掛品:製造中の製品
- 消耗品:期末時点で未使用の在庫品
「税務調査の流れ」編集部
これらの在庫が適切に管理・計上されているかを確認し、税務調査の流れの中で齟齬がないようにしておく必要があります。
税務調査の流れを正しく理解し、想定される質問にも備えよう
税務調査は「通知→準備→実地調査→結果報告」という一連の税務調査の流れに沿って進みます。この税務調査の流れの中で、帳簿の整備、証憑の準備、説明資料の用意が的確にできていれば、調査がスムーズに終わる可能性が高くなります。
特に以下のような質問が、税務調査の流れの中で頻繁に投げかけられます。
- 納品書や請求書の発行タイミング
- 経費支出の背景
- 特別損失や交際費の妥当性
- 売上の計上基準と対応する取引の記録
これらの内容に即答できる体制を整えておくことで、税務調査の後半でのトラブルを防げます。税務調査の流れの理解と準備は、事業運営における重要なリスク管理の一環です。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査が入るとどうなる?当日までの流れや対応方法を解説」
税務調査の流れに関する注意点

税務調査は突然通知が来るケースもあり、準備不足だと調査の流れが複雑化し、対応が長期化するリスクがあります。
だからこそ、税務調査の流れを平時から意識して、帳簿や資料の整理をルーティン化しておくことが重要です。
税務調査の流れを意識した日常の経理処理と、想定質問への備えができていれば、たとえ調査が入ったとしても慌てる必要はありません。今後の税務調査の流れをスムーズに乗り越えるためにも、ぜひ本記事を参考に準備を進めてください。

合わせて読みたい「税理士変更による税務調査」に関するおすすめ記事
税理士変更で税務調査の対象になる?税務調査の注意点について解説

税務調査の対象となった際の注意点と対応の流れ
税務調査の対象となった場合、どのような対応の流れで進めるのが適切なのか、また注意すべき点はどこにあるのかを事前に理解しておくことが大切です。税務調査は突然通知されることもあるため、冷静に調査の流れに対応できるよう準備しておきましょう。
税務調査の注意点と対応の流れ①
税務調査が入っても過度に恐れないことが大切
「税務調査」と聞くと、「脱税を疑われているのでは…?」と不安になる方も多いかもしれません。しかし、税務調査は不正の摘発を目的としたものばかりではなく、申告内容に確認が必要な場合に定期的に実施されるものであり、調査の流れの中で誤りが見つかったとしても、悪質でない限りは修正申告で済むことが一般的です。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査の流れに関する参考記事:「法人の税務調査の流れと対象になりやすい傾向とは?」
税務調査の通知を受けた後の対応の流れとしては、まず落ち着いて必要書類を準備し、想定される質問のシミュレーションを行いましょう。税務調査の流れがスムーズに進むよう、信頼できる税理士に立ち会ってもらうことも非常に有効です。
税務調査の注意点と対応の流れ②
誠実な態度が税務調査の流れを左右する

合わせて読みたい「税務署から電話」に関するおすすめ記事

税務署から電話がきた理由とは?対応方法や相談する際のポイントも解説!
税務調査では、経理や税務処理だけでなく、経営者の態度や受け答えの姿勢も調査官の印象に影響します。税務調査の流れの中で、敵対的・高圧的な対応をとると、調査官に悪印象を与え、税務調査の内容が厳しくなる場合もあるため注意が必要です。
税務調査においては、へりくだる必要もありませんが、誠実で丁寧な対応を心がけることで、調査官との信頼関係が築かれ、調査の流れもスムーズになります。
税務調査の注意点と対応の流れ③
質問には正確かつ落ち着いて答えることが重要
「税務調査の流れ」編集部
税務調査の実地調査の流れでは、様々な質問を受けることになります。
税務調査の流れに関するポイント!

ここで大切なのは、事実に基づいて正確に答えることです。わからないことがあればその場で曖昧な返答をするのではなく、「確認して後日回答します」と伝えるのが得策です。
税務調査の進行の流れでは、一つの回答が次の質問に影響することもあるため、誤解を生まないよう慎重に対応しましょう。
税務調査の注意点と対応の流れ④
質問は簡潔に、必要以上の情報は避けるのが税務調査の基本
税務調査では、聞かれてもいないことまで話すことで、不要な疑いを招く恐れがあります。調査官が質問する内容は、税務調査の流れに基づいて整理された調査項目です。ですので、質問には簡潔に、的確に答えることが税務調査の流れを乱さずに済ませるポイントです。
税務調査の流れに関するおすすめ記事

税務調査が入るまでの流れや、税務調査当日の流れは以下の記事が参考になるでしょう。
税務調査の流れに関する参考記事:「個人に対する税務調査の流れと調査対応の注意点」
税務調査の注意点と対応の流れ⑤
税理士との事前打ち合わせで税務調査の流れを想定する
税務調査の通知を受けたら、まず最初に行うべきは税理士との事前打ち合わせです。税務調査の全体的な流れを把握しておくことで、どのような書類を準備すべきか、どんな質問が来るかといった対策が可能になります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

特に初めて税務調査を経験する方にとっては、税理士の存在は非常に心強いもの。税務調査の流れの各段階で、税理士が税法に基づいて回答してくれることで、調査のトラブルを回避しやすくなります。
税務調査の注意点と対応の流れ⑥
留置きへの備えも税務調査の流れで忘れてはならない点
税務調査の中では、書類の「留置き(預かり)」が発生することもあります。この場合、帳簿や契約書など業務に必要な書類が一時的に手元からなくなってしまうため、業務への影響が出る恐れもあります。
「税務調査の流れ」編集部
税務調査が来るまでの流れや、税務調査当日の流れに関して以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査の流れに関する参考記事:「税務調査とは?どこまで・何を調べる?流れや個人・法人の対応方法などについて詳しく解説」
税務調査の実地調査の流れに備えて、業務に必要な書類はあらかじめコピーを取っておく、クラウドや外部ストレージに保存しておくなどの対策が重要です。調査の流れを意識したこうした事前準備は、税務調査をスムーズに乗り切るための大きな助けになります。
税務調査の流れに関するポイント!

税務調査は、突然やってくることが多いため、事前に流れを理解しておくことが非常に重要です。税務調査の流れに沿って、書類の準備、税理士との連携、質問への対応方法などを整理しておけば、過度に不安になる必要はありません。
また、税務調査の流れの中で適切な対応を取ることが、調査官との信頼関係を築き、調査を円滑に終える鍵となります。誠実な態度と冷静な受け答えを心がけながら、税務調査の流れに応じた対応を徹底しましょう。
Q&A|よくある質問
Q: 税務調査の確率はどのくらいですか?
A: 税務調査の確率は、業種や規模、過去の申告状況によって異なります。一般的に法人の場合、税務調査が入る確率は数%〜10%程度といわれますが、売上規模が大きい企業や現金取引が多い業種は確率が高くなる傾向があります。税務調査の確率を下げるためには、帳簿の正確な記帳や証憑の保存など、日常的な税務管理が重要です。
Q: 税務調査はどの時期に行われることが多いですか?
A: 税務調査が行われる時期は、法人の場合は決算申告後の数カ月〜1年以内が多いです。特に、9月〜11月や2月〜3月といった税務署の繁忙期を避けた時期に集中する傾向があります。税務調査の流れとして、繁忙期の直後に調査準備が行われることもあるため、年間を通して確率を意識した準備が必要です。
Q: 税務調査の確率が上がる要因は何ですか?
A: 税務調査の確率が上がる要因としては、過去に申告漏れや修正申告の履歴がある場合、経費計上に不自然な点がある場合、売上や利益が急変している場合などが挙げられます。また、業種特有のリスクや、同業他社と比べた数値の乖離も税務調査の確率を高める要因になります。
まとめ|税務調査の流れを理解して正しく対応を
税務調査は、法人・個人事業主を問わず、申告内容の確認や不備の指摘を目的として実施されるものです。実際に税務調査の対象となった際に慌てないためには、税務調査の流れをあらかじめ把握しておくことが非常に重要です。
今回の記事では、税務調査の種類や対象となる確率、実施されやすい時期、そして当日の対応方法まで、税務調査の流れに沿って具体的に解説しました。特に、税務調査がどのような流れで進行するのか、どこで何をチェックされるのかを理解しておけば、余計な不安に振り回されることなく落ち着いて対応できます。
税務調査の流れにおいては、事前通知、日程調整、帳簿確認、実地調査、結果通知まで段階的な手順があります。この流れを押さえておくことで、事前準備や税理士との連携、書類の整理など、具体的にやるべき行動が明確になります。
税務調査は、突然やってくることもありますが、流れを把握しておけば対策が可能です。特に、税務調査に備えて経理業務を見直すことや、税務調査の流れに沿った書類管理を徹底しておくことは、企業や事業主にとって大きなリスクヘッジになります。
「税務調査の流れが不安」「税務調査に備えたい」「税務調査が入りそうで心配」——そう感じている方は、早めの準備が肝心です。税務調査の流れを理解した今こそ、信頼できる税理士に相談し、税務調査対策を万全に整えておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「税務調査が10年以上来ない」に関するおすすめ記事

税務調査が10年以上来ない法人と個人事業主の特徴とは?業種や税務調査が入る確率も紹介!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!