税務調査で追徴課税はいくら取られる?いくらから調査対象になるのかも詳しく解説!
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2025年12月6日
税務調査が入ると、実際にいくら取られるのかが気になって不安になる方は多いものです。税務調査は、申告された所得や経費、納税額が正確かどうかを税務署が確認するための制度であり、申告内容に誤りがあると、税務調査を通じて追徴課税が発生することがあります。そうなると、最終的にいくら取られるのか、追徴課税がいくらになるのかが問題となります。
特に、税務調査では売上や利益がいくらか、経費がいくら計上されているか、申告額と実態にいくらの差があるのかといったポイントが徹底的に確認されます。調査の結果、申告ミスや漏れが見つかれば、追徴課税というかたちで本来納めるべき税金に加えて、いくらかの加算税や延滞税を支払う必要が出てきます。
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
税務調査が入ることでいくら取られるかは、その内容によって大きく変動するのです。
また、そもそも税務調査はどのような基準で実施されるのか、いくらの売上や所得があると税務調査の対象になりやすいのかも、事前に知っておきたい情報です。税務署がどのような会社や個人を税務調査の候補とするのか、その判断にはいくらかの目安や傾向が存在します。そして、税務調査が行われる頻度やタイミング、さらには税務調査後にいくらの税金を追加で納めることになるのかという金額面のリスクも、無視できません。
この記事では、税務調査でいくら取られるのか、追徴課税の金額はどれほどかかるのか、また税務調査は実際いくらから対象となるのかといった疑問に対して、税務調査の実情や仕組みを踏まえて詳しく解説していきます。税務調査について正しく理解しておくことで、いくら取られるのかという不安を減らし、日々の申告や記帳をより慎重に行えるようになるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
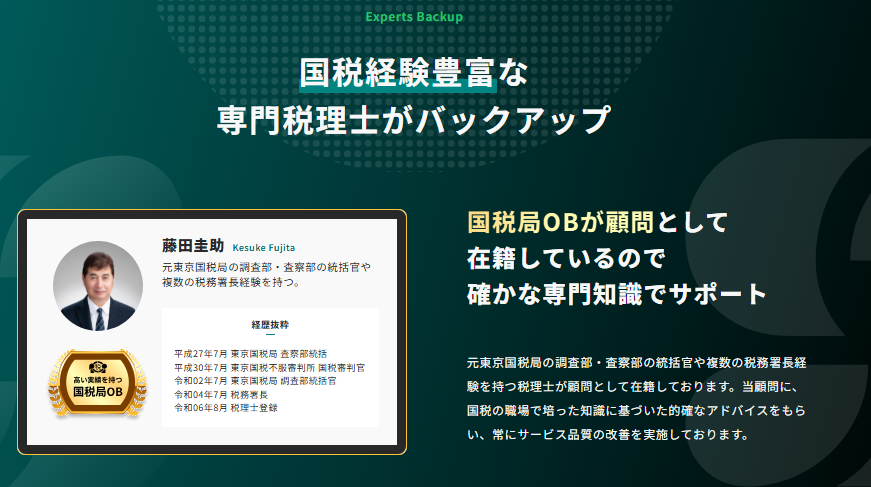
目次
税務調査とは?税務調査の対象・目的・種類
税務調査とは、納税者が申告した所得や経費、納税額が正しいかを確認し、いくら納めるべきかを判断するために、税務署または国税局が実施する調査です。日本の税制度は「申告納税方式」を採っており、納税者が自分で税額を計算し、いくら納めるかを決めて申告する仕組みとなっています。しかし、すべての人が正確に申告し、正確にいくら納めているとは限らないため、いくらの申告が妥当かを調べるために税務調査が行われるのです。

合わせて読みたい「国税局からの電話」に関するおすすめ記事

国税局から電話が来る理由を解説!注意点と対応方法も紹介
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するおすすめ記事

税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下の記事も参考になるでしょう。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「税務調査は個人でいくらから?対象になりやすい人の特徴や対策を解説」
税務調査では、収入はいくらだったのか、経費はいくら計上されているのか、利益はいくらなのか、申告された金額と実際の取引にいくらの差があるのかといった、さまざまな「いくら」がチェックされます。そして、もしミスや過少申告が見つかれば、追徴課税としていくらかの税金を追加で納める必要が生じます。
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
日本の税制度は申告納税方式を採用しており、納税者自身が税額を計算し、自主的に申告・納付を行う仕組みになっています。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「税理士変更による税務調査」に関するおすすめ記事
法人税務調査で指摘事項への対応は?税務調査の基礎から対策まで解説!

すべての納税者が完全に正しく申告しているとは限らず、うっかりミスや計算誤り、意図的な所得隠しなどが発生することもあるため、税務調査が実施されることで正確な納税の実現を目指すのです。
税務調査の対象となるのは法人だけでなく、個人事業主やフリーランス、確定申告義務のある一般の個人も含まれます。つまり、税務調査は誰にとっても他人事ではなく、すべての納税者が税務調査の対象になる可能性を持っているのです。
SoVa税理士お探しガイド編集部
近年、税務署でもAIを活用しているため税務調査リスクは増大しているため、顧問税理士と相談しながら正確な日々の記帳がもとめられます。2024年には追徴課税額が過去最高を更新しています。
税務調査の種類とは?任意調査と強制調査の違いを解説

税務調査には大きく分けて二つの種類があります。それが「任意調査」と「強制調査(犯則調査)」です。どちらの税務調査が行われるかによって、調査の進め方や納税者の対応方法が異なります。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するおすすめ記事

税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下の記事も参考になるでしょう。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「個人事業主はいくらから税務調査の対象?」
任意調査とは?
任意調査とは、納税者の協力のもとで行われる一般的な税務調査のことです。現在行われている税務調査の大多数がこの任意調査に該当し、税務署職員が事前連絡をしたうえで、税務調査の日程や調査内容を納税者と調整しながら実施されます。税務調査では、帳簿書類・領収書・契約書などが対象となり、税務調査担当者が数日にわたって細かく内容を確認します。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する注意点

「任意」とは言っても、税務調査に協力する義務(受忍義務)が法律で定められており、正当な理由なく税務調査を拒否した場合には罰則の対象となることもあります。
また、事前連絡がない「無予告」で行われる税務調査もあります。これは、証拠の隠滅や帳簿改ざんが疑われるような場合に実施され、通常の任意調査と比べても厳格に進められる税務調査の一種です。
強制調査(犯則調査)とは?
強制調査は、通常の税務調査とは異なり、裁判所の令状を得て強制的に行われる非常に厳しい税務調査です。強制調査は、国税局の査察部が主導し、脱税などの重大な犯罪行為が疑われる場合に限って実施されます。事前通知はなく、調査対象者は税務調査を拒否することはできません。
このような強制的な税務調査は、立件を目的とした刑事調査の一環でもあり、脱税額が巨額である場合や悪質性が高いと判断されたときに行われます。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するポイント!

税務調査の中でも最も重い対応が取られるケースであり、実際の摘発・起訴へとつながる可能性もあるため、税務調査の中でも例外的な位置づけにあります。
税務調査でいくら取られる?追徴課税の金額とその実態を徹底解説!
「税務調査が入ったら、いくら取られるのか?」
「追徴課税はいくら取られるのか?」
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
そんな不安を感じている法人経営者や個人事業主の方は少なくないでしょう。
税務署の調査が入ると、どのくらいの金額が追徴課税として課されるのか、具体的な数値とともに、その背景を解説します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人の税務調査ではいくら取られる?追徴課税の平均は570万円!
まず、法人に対する税務調査でいくら取られるかという点について、国税庁の統計データ(令和3事務年度)をもとに見てみましょう。

合わせて読みたい「法人税・法人事業税・法人住民税の違い」に関するおすすめ記事

法人税・法人事業税・法人住民税の違いとは?計算方法や課税対象、納付先まで詳細解説!
法人税の調査は全国で約4万1千件実施され、そのうち約3万1千件で申告内容に問題がありました。つまり、否認率は76%と非常に高く、4社中3社が何らかの追徴課税を受けていることになります。
そして、実際に税務調査でいくら取られるのかというと、1件あたりの追徴課税額は平均で約570万円(法人税+消費税+加算税を含む)にも上ります。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するおすすめ記事

税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下の記事も参考になるでしょう。
「個人の場合の税務調査はいくらからと決まっているの?どのような人が目を付けられやすい?」
この570万円という数字だけを見ると、「税務調査が入ったら一体いくら取られるんだ…」と恐ろしく感じる方も多いでしょう。実際、税務調査でいくら取られるのかはケースによって異なりますが、想定以上の高額になることも珍しくありません。
個人の場合はいくら取られる?平均追徴課税額は399万円
続いて、個人事業主に対する税務調査ではいくら取られるのかを見てみましょう。
令和3年度には、個人への税務調査が約31,400件行われ、そのうち約26,700件で否認が発生しました。否認率はなんと85%に達しており、法人よりもさらに高い割合で何らかの修正を求められています。

合わせて読みたい「税務調査で税理士に依頼するかどうか」に関するおすすめ記事
税務調査に税理士は必要?税理士に依頼するメリット・デメリットまで紹介

そして、個人の場合の追徴課税はいくら取られるかというと、平均約399万円(所得税+消費税+加算税)です。法人と比較すれば若干低めではあるものの、個人にとっては非常に大きな金額であり、場合によっては経営を圧迫するレベルの負担になり得ます。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「税務調査が個人に入る確率は?いくらから?対象になりやすい業種や特徴、対策まで解説します。」
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
ここまで見て、「税務調査って、結局いくら取られるんだ…?」と不安になった方もいるかもしれません。しかし、この高額な追徴課税の平均額には、ある理由があります。
税務署が税務調査を行う対象は、不自然な申告や不正の疑いがあるケースに絞られていることが多いのです。つまり、最初から目をつけられていた企業や個人のデータがベースになっているため、結果として「税務調査=いくら取られるのか怖い」と思わせるような金額になってしまっているわけです。
個人の税務調査はいくらから来る?いくら取られる?
「税務調査っていくらから来るの?」「税務調査に入られたら、いくら取られるのか不安…」
そんな疑問をお持ちの個人事業主やフリーランスの方は少なくありません。
税務署が行う税務調査では、申告にミスがあれば追徴課税としていくら取られるのかが大きなポイントです。正しく申告していても、いくらかの修正が入る可能性はありますし、誤りや漏れがあればいくら取られるか分からない事態にもなり得ます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「個人事業主で税務調査の目をつけられる金額はいくらから?」
税務調査はいくらから来る?金額の目安はある?
「税務調査はいくらの収入から対象になるのか?」という質問に対し、明確な基準は公開されていません。しかし、一般的には課税対象額が1,000万円を超えると税務調査が来やすくなると言われています。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するポイント!

いくらから必ず税務調査が入るというラインはないものの、収入がいくら以上なのか、経費がいくら計上されているのか、還付金がいくらになっているのかなど、さまざまな「いくら」に税務署は注目しているのです。

合わせて読みたい「税理士に依頼できる記帳代行と丸投げサービスの違いについて」に関するおすすめ記事
税理士に依頼できる「記帳代行」と「丸投げ」の違いとは?

個人に税務調査が来る確率は?いくらの割合で対象になる?
国税庁のデータによると、確定申告を行っている個人約640万人のうち、年間で税務調査が行われるのは約7万人程度。つまり、100人に1人、いくらで言えば“約1%”の確率で税務調査の対象になっているというわけです。
SoVa税理士お探しガイド編集部
税務調査以外に、社会保険調査については以下の記事も是非参考にしてください。
「 社会保険調査は厳しいのか?年金事務所の調査がくる理由と流れを解説 」
この「いくらの確率で税務調査が来るのか」という視点も重要です。いくら高額な納税者でなくても、ランダムに選ばれて調査が入ることもあるため、「自分はいくらの売上だから大丈夫」とは言い切れません。
税務調査でいくら取られる?平均追徴課税額は◯◯万円!
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
最も気になるのが、「税務調査でいくら取られるのか?」という部分ではないでしょうか。
国税庁の公表によれば、個人に対する税務調査の平均追徴課税額は約399万円。つまり、一度税務調査に入られると、いくら取られるのかは数百万円単位になる可能性があるということです。
もちろんこれは平均額なので、実際にいくら取られるかはケースバイケース。軽微なミスであれば数万円〜十数万円で済むこともありますが、故意や重大なミスがあれば、いくら取られるか分からない金額に膨れ上がることもあります。
税務調査の対象になりやすいケース
売上が急増した場合、いくらの増加かによって税務署が注目します。たとえば前年の倍以上の売上になっていたら、「この急増はいくらの根拠があるのか?」と調査対象になる可能性があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
消費税の還付を受けている方は、「いくらの還付額か? いくらの仕入があったのか?」という視点で見られ、帳簿に不備があればいくら取られるか分かりません。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する注意点

複数事業を並行して行っている場合、それぞれの売上がいくら、経費がいくら、利益がいくらという管理が甘いと、申告ミスにつながり税務調査でいくら取られるか分からない状況になる可能性もあります。
法人が税務調査を受ける確率は?いくら取られる?
国税庁の統計によれば、法人に対する税務調査の実施率は約1.3%。
つまり、「法人が税務調査を受ける確率はいくらか?」と聞かれれば、おおよそ75年に1回、いくらの確率で1社が対象になるという計算です。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するおすすめ記事

税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下の記事も参考になるでしょう。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「税務調査が来るのはいくらから?開業3年以上1,000万円以上の人は気をつけて!」
しかし、この「1.3%」という数字はあくまでも平均値です。法人の規模や業種によって、「いくらの売上がある会社か」「いくらの納税をしているか」などの条件により、いくら確率が高くなるかはケースバイケースです。

合わせて読みたい「税務調査の流れ」に関するおすすめ記事

税務調査の流れとは?調査対象となる確率や時期についても解説!
国税庁によると、法人1件あたりの平均追徴課税額は約570万円です。つまり、税務調査に入られた場合、最終的にいくら取られるかというと平均値は570万円にもなります。これだけの金額を「いくらかの申告ミス」で支払うことになるのです。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する注意点

もちろん、「自社はいくら取られる可能性があるのか?」は状況によって異なります。
数十万円で済むケースもあれば、数千万円単位でいくらも取られることもあります。
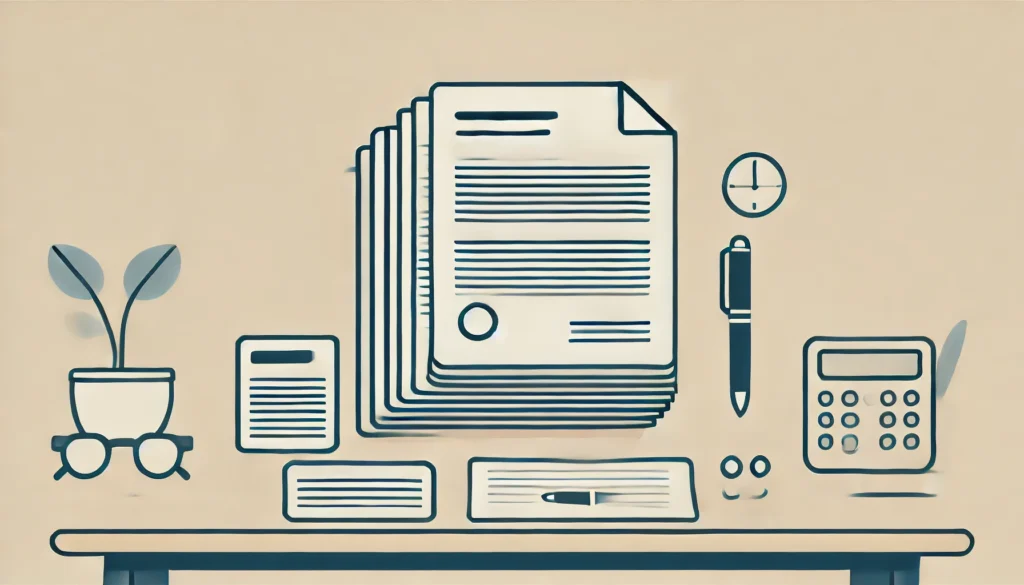
税務調査は法人のいくらから始まる?いくらが狙われる?
税務調査が法人に入るかどうかは、「いくらから」という明確な基準があるわけではありません。ただし、一般的には次のようなものが調査の引き金になることがあります。

合わせて読みたい「税理士に依頼する時の費用」に関するおすすめ記事
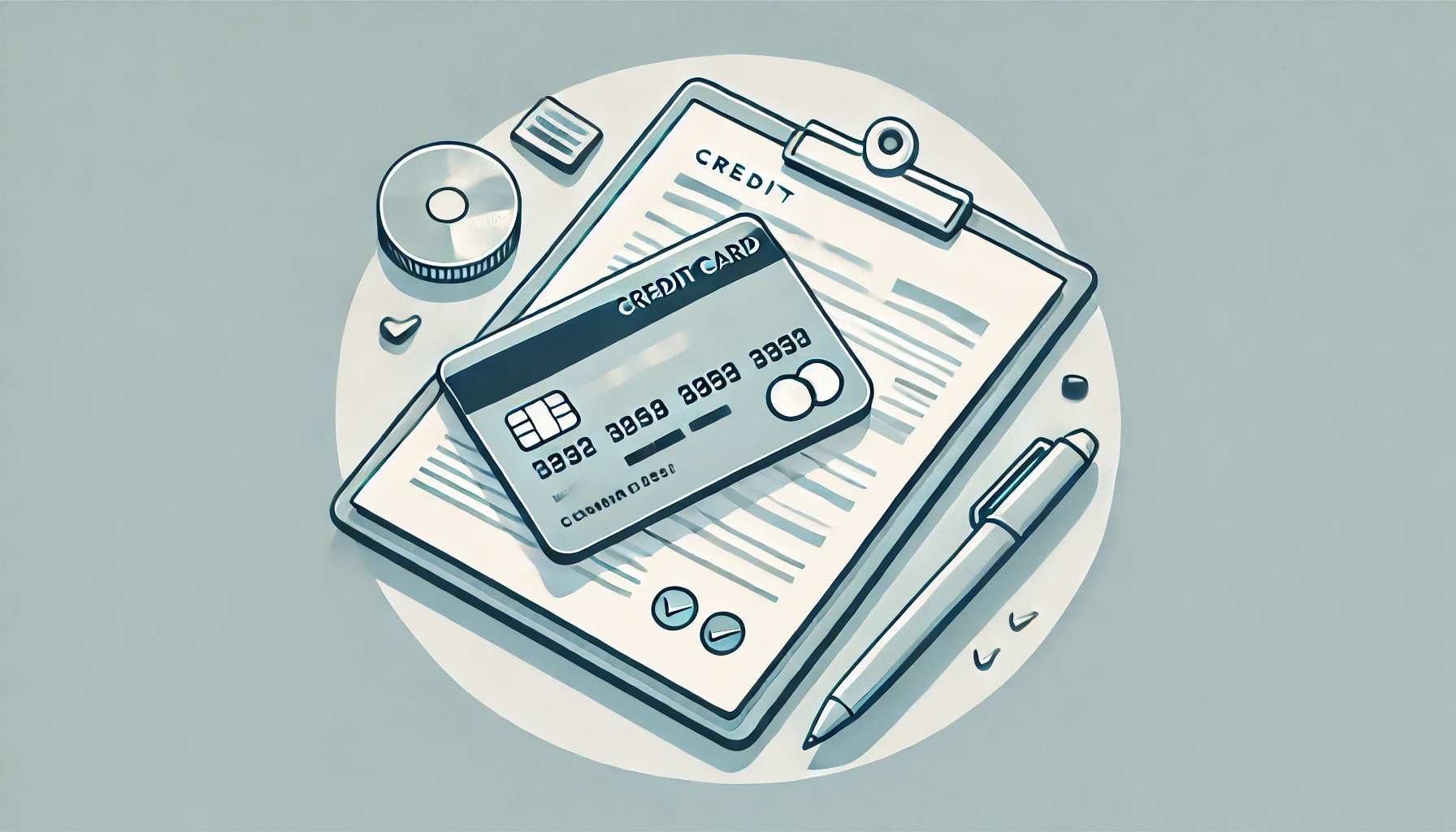
税務調査はいつ来るのか?税務調査の対象となる法人や個人、時期と流れなどについて解説!
1. 売上がいくら増えたか
前年と比べて売上がいくら増加しているかは、税務署が強く注目するポイントです。たとえば前年よりいくらも売上が増えたのに、それに見合った納税額が増えていないと、「この法人はいくらかおかしい」と判断されやすくなります。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「個人は税務調査でいくら税金を払ってる?」
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
2. 経費がいくら膨らんでいるか
経費としていくら計上しているのか、その金額が常識的かどうかも調査対象になります。たとえば交際費がいくらにも達している、あるいは減価償却費がいくらにも及んでいるような場合、調査のきっかけになります。
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下のサイトも是非ご覧ください。
「脱税で逮捕されるのはいくらから?調べられる期間や税務調査の流れを解説」
3. 利益の落差がいくらあるか
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するおすすめ記事

税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下の記事も参考になるでしょう。
「税務調査が入る確率は?個人事業主(一人親方)も対象?入りやすい特徴や対策」
前年は黒字で今年は赤字、あるいは利益がいくらも減っているなど、極端な変動がある場合も要注意です。「その落差はいくら?」「その理由に正当性はあるか?」という視点から税務署は動きます。
税務調査後の追徴課税や修正申告の影響
「税務調査を受けたあと、いったい何が起こるのか?」「税金はいくら増えるのか?」「追徴課税ってどのくらい取られるのか?」
そんな不安を抱えている方に向けて、税務調査後に起こることと、税金や追徴課税がいくらになる可能性があるかをわかりやすく解説します。
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
税務調査後の追徴課税で取られる加算税の種類なども紹介します!
基本的には修正申告|税務調査で指摘されるといくら税金を追加で支払う?
税務調査が行われた場合、申告内容に誤りがあれば修正申告が求められるのが一般的です。
この修正により、もともと支払っていた税金にプラスしていくらかを追加で納める必要が出てきます。
ただし、正しく申告していた場合は特に問題視されることはなく、「税務調査=いくら取られる」というわけではありません。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するポイント!

税務調査はあくまで申告内容の確認が目的であり、多くのケースで刑事罰に発展することはなく、いくらもの罰金が課されるわけではないという点は安心材料と言えます。
加算税の種類と金額の目安
ここでは、税務調査で課される可能性のある「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」「延滞税」について詳しく解説します。
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
「いくら加算されるのか?」「いくらから対象になるのか?」といった視点も交えてご紹介します。
| 加算税の種類 | 主な課税要件 | 原則税率 | 重加算税率(仮装・隠蔽等) | 適用除外の例 |
|---|---|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内申告後、修正申告や更正により追加納税が発生 | 基本10% ※50万円超部分は15% |
35% | ・税務調査前に自主修正をした場合 ・正当な理由がある場合(通法67①) |
| 無申告加算税 | 期限内に申告せず、期限後に申告した場合 | 15%(原則) ※50万円超部分は20% |
40% | ・正当な理由がある場合(通法66①ただし書) ・1か月以内の申告(通法66⑨) |
| 不納付加算税 | 源泉徴収した税金を期限内に納付しなかった場合 | 10%(原則) | 35% | ・正当な理由がある場合(通法65⑤) ・1か月以内の納付(通法65①・②) |
| 重加算税(共通) | 仮装・隠蔽によって申告漏れや無申告が発生した場合 | 上記加算税に代えて適用 | 上記のとおり | ・納税者の責めに帰すべき事由がない場合など一部免除可能 |
無申告加算税|税務調査で申告していないことが判明した場合、いくら取られる?
無申告加算税は、確定申告すべき収入があるにもかかわらず、申告をしなかった場合に税務調査で発覚すると課される追徴課税です。税務調査では「いくら申告されていないのか」「いくら納税すべきだったのか」を重点的に確認されます。
仮に、税務調査前に自発的に期限後申告を行った場合は、無申告加算税としていくらの税額に対して5%が課されることになります。
しかし、税務調査の事前通知や税務署からの連絡を受けた後に申告した場合は、いくらの税額に対して10%が加算されます。

税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「税務調査が個人事業主に来るのはいくらから?入られやすい人の特徴や対策方法も紹介」
このように、税務調査が入る前にいくら早く対応できるかで、いくらのペナルティを回避できるかが変わってくるのです。
過少申告加算税|税務調査で金額のミスが見つかったらいくら課される?
過少申告加算税は、税務調査で「申告額が実際より少なかった」と指摘されたときに課される追徴課税です。税務調査では、「本来いくら申告すべきだったか」「いくら差額が出たのか」を精査されます。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する注意点

税務署から指摘を受ける前に、自主的に修正申告をすれば加算税は発生しません。しかし、税務調査で指摘された後に修正した場合、元の納税額に対して10%の加算税が課されます。
さらに、追加で納めるべき税金がいくらかに応じて、その金額が50万円超であれば15%に引き上げられる可能性もあります。つまり、いくらのミスがあったかによって、いくら取られるかが大きく変動するのです。

合わせて読みたい「税務調査が10年以上来ない」に関するおすすめ記事

税務調査が10年以上来ない法人と個人事業主の特徴とは?業種や税務調査が入る確率も紹介!
重加算税|税務調査で不正が判明したときは、いくら取られる?
重加算税は、税務調査で意図的な隠ぺいや仮装が見つかった場合に課される最も重い追徴課税です。
この加算税は、「いくらを故意に隠したか」「いくらを偽ったか」によって課税額が決まり、税務署の調査官も最も厳しくチェックします。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関するおすすめ記事

税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下の記事も参考になるでしょう。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「税務調査の追徴課税の平均額は?個人の場合はいくらになる?」
過少申告加算税の代替で課される場合は35%、無申告加算税の代替であれば40%の重加算税が発生します。
たとえば100万円を故意に隠していた場合いくら取られるかというと、最大140万円以上の納付義務が発生するケースもあります。
しかも、過去に税務調査で重加算税を受けた履歴があると、さらに10%上乗せされ、いくら取られるか分からないほど高額の追徴課税になることもあるのです。
延滞税|納付が遅れた場合は、いくらずつ増えていく?
延滞税は、期限までに税金を納付しなかった場合に発生する税金で、税務調査が入る前・後に関わらず発生します。
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
「いくら遅れたか」「いくらの税額が未納か」によって、発生する額が変動します。
- 2カ月以内の延滞:年率7.3%(または延滞税特例割合+1%のいずれか低い方)
- 2カ月超の延滞:年率14.6%(または特例割合+7.3%のいずれか低い方)

たとえば、50万円を3カ月遅れて支払った場合、いくら取られるかというと、数万円以上の延滞税が追加で発生する可能性があります。
つまり、「いつ納めたか」「いくら納めていないか」でいくらの延滞税が取られるかが変わるというわけです。
「税務調査で追徴課税はいくら取られる?」編集部
税務調査で追徴課税は平均でいくら取られるのか、税務調査対象になりやすいのはいくらからなのかについては以下のサイトも是非ご覧ください。
税務調査で追徴課税はいくら取られるのかに関する参考記事:「個人の税務調査はいくらから?どこまで調べる?追徴課税の平均や流れについて解説」
Q&A|よくある質問
Q. 税務調査で追徴課税はいくらくらいになるのですか?
税務調査での追徴課税の金額(いくら取られるか)は、調査によって判明した申告漏れや不正の規模によって大きく異なります。過去の国税庁の統計によると、法人の場合は1件あたり約700万円前後の追徴課税が発生することが多く、個人事業主でも数十万円〜数百万円に及ぶことも珍しくありません。
税務調査での追徴課税額は、以下のような構成で決まります。
- 本税(申告漏れや過少申告の差額)
- 加算税(無申告加算税・過少申告加算税など)
- 延滞税(納期限からの遅延分)
ここがポイント!

つまり、追徴課税は「いくら申告していなかったか」だけでなく、「いくらの期間放置していたか」にも左右されます。
Q. 税務調査は、いくらの売上や利益があれば対象になるのですか?
税務調査は、必ずしも「いくら売上があるから対象になる」というわけではありません。しかし、実際には年商1,000万円以上の法人や個人事業主が調査対象になるケースが増える傾向にあります。
特に次のような条件があると、税務署が「いくら申告されているか」「いくらの経費が計上されているか」に注目して、税務調査の候補とする可能性が高まります。
- 売上と利益のバランスが不自然(売上が高いのに利益が少ない)
- 経費の金額が大きく、内容が曖昧
- 赤字決算が複数年続いている
- 同業他社と比べて申告額が著しく少ない
つまり「いくら売上があるか」だけでなく、「いくら納税しているか」「いくら節税しているか」が総合的にチェックされていると考えてください。
Q. 税務調査で追徴課税を減らすためにはどうしたらよいですか?
税務調査での追徴課税を少しでも減らしたい場合には、事前に自主的に修正申告を行う方法が効果的です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
税務署に指摘される前に修正すれば、加算税の軽減や延滞税の抑制につながることがあります。
また、税務調査では「いくらが事業に関連した正当な経費か」を明確に説明することが極めて重要です。領収書や契約書などの証憑書類をしっかり保管し、いつでも提示できる体制を整えておくことが、税務調査対策としては非常に有効です。
まとめ|税務調査の追徴課税でいくら取られる?
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税務調査は、すべての納税者にとって現実的なリスクであり、どのような規模の事業であっても、税務署の目に留まれば税務調査の対象となる可能性があります。税務調査が行われた場合、最も気になるのがいくら取られるのかという点です。税務調査では、申告内容の整合性や帳簿の正確性が厳しく確認され、もし申告漏れや計算ミスが発見された場合には、追徴課税としていくら取られるかがその場で問題となります。税務調査によっていくらの追徴課税が発生するのかは、違反の内容や過去の申告履歴によって大きく異なり、軽微なミスでもいくらかの金額を追加で納める必要が生じることは少なくありません。
また、税務調査が入るきっかけとなるのは、売上や利益がいくらあるのか、経費がいくら計上されているのか、帳簿上の誤差がいくら生じているのかなど、「いくら」に関わる情報が判断材料になります。税務調査で実際にいくら取られるかは、税額の過少申告や所得の隠ぺいがあった場合には特に高額になり、追徴課税としていくらもの金額を追加納税する事態に発展することもあります。いくらのミスがいくらの負担につながるのか、それを把握しておくことが税務リスクの最小化につながります。
このように、税務調査とは、単なる形式的な確認ではなく、いくらの申告が正しいか、いくら取られるべき税額かを厳密に見られる調査です。税務調査でいくら取られるのか不安に感じる方こそ、日々の申告と記帳を丁寧に行い、いくらが正しく処理されているかを常に意識することが重要です。税務調査でいくら取られるのかを事前に想定し、いくらからが調査対象となるのかを理解しておくことで、追徴課税による経営上のダメージを最小限に抑えることができます。

合わせて読みたい「税務調査の税理士費用」に関するおすすめ記事

税務調査の税理士費用の相場はいくら?税理士立合いのメリットも解説!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!