税金に時効はあるのか解説!税務調査や脱税は5年?7年?
「税金に時効はあるのか?」という疑問は、確定申告や納税を忘れてしまった方、または税務署から通知を受けた方にとって非常に気になるテーマではないでしょうか。実は、税金にも時効が存在すると法律で定められています。ただし、この税金の時効制度は非常に複雑で、税務調査が入った場合や脱税が発覚した場合には、税金の時効が中断・延長されるという仕組みがあります。
通常、税金の時効は3年とされていますが、税務調査の結果や申告内容によっては5年、さらに悪質な脱税行為が認定されれば最大で7年まで税金の時効が延びるケースもあります。つまり、税務署が税務調査を開始することで、過去の税金に対する調査・追徴が可能になる時効期間が大幅に広がるというわけです。
また、税務調査によって税金の未納や申告漏れが発覚すると、時効内であれば追徴課税や加算税、延滞税などのペナルティが科されるため、金額面でも非常に大きなリスクを抱えることになります。税金の時効をあてにして放置していると、税務調査の通知1つで時効が振り出しに戻り、多額の税金を支払う羽目になる可能性もあるのです。
この記事では、税金に関する時効の仕組みと、税務調査による時効の中断・延長、さらに脱税や無申告の場合の調査対象年数やリスクについて、分かりやすく詳しく解説します。
「税金や税務調査の時効」編集部
税金の時効制度を正しく理解し、税務調査に備えて今から何をすべきかを確認しておきましょう。
税金のリスクを軽視せず、正しい知識で対応することが何より重要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
脱税・無申告でも時効はある?
「脱税や無申告でも、税金には時効があるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。実は、税金にも時効が存在し、一定期間が経過すると税務署が税金を徴収できなくなる場合があります。これを「税金の時効制度」と呼びます。
税務調査と税金の時効に関するおすすめ記事

税務調査や税金に時効、税金の時効が停止したりリセットされるケースについては以下の記事も参考になるでしょう。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「脱税による税務調査の時効は5年?7年?罰金やペナルティについても解説」
しかし、税金の時効には条件があり、時効の年数は3年・5年・7年のいずれかに分類されます。また、税務署による税務調査や督促、処分が行われた時点で税金の時効は中断またはリセットされるため、理論上の時効が成立することは非常にまれです。
「税金や税務調査の時効」編集部
ここでは、税金の時効制度の詳細と、時効が延長されるケース、税務調査の遡及期間、重加算税との関係まで、徹底的に解説します。
税金の時効とは?税金にも時効が存在する理由と基本制度

まず大前提として、税金に時効があるのは、行政処分の期限を定めることで納税者の法的安定性を確保するためです。すべての税金には、税務署が更正や追徴処分を行える「時効期間」が法律で設定されています。
税金や税務調査の時効に関するポイント!

具体的には、国税通則法第70条に基づき、税金の時効は原則3年、特例として5年・7年に延長されることがあります。
「税金や税務調査の時効」編集部
これを「更正決定等の期間制限」といい、税金の種類や行為の悪質性に応じて、時効の年数が異なります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【3年】税金の時効:軽微な過少申告などの場合
税金の時効が3年になるのは、以下のようなケースです。
このような場合、税金の時効は法定申告期限から3年間とされ、3年を過ぎると税務署は原則としてその税金について追徴や更正を行えません。ただし、時効が成立する前に税務署から何らかの通知や調査が入った場合、税金の時効は中断します。
税務調査と税金の時効に関するおすすめ記事

税務調査や税金に時効、税金の時効が停止したりリセットされるケースについては以下の記事も参考になるでしょう。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「税務調査の時効はどのくらい?無申告や脱税の場合の対象年数やペナルティを解説」
【5年】税金の時効:無申告・重大な申告ミスの場合
次に、税金の時効が5年に延長されるケースを見てみましょう。
「税金や税務調査の時効」編集部
以下に該当する場合、税務署は5年以内であれば追徴課税や更正処分が可能です。
税金の時効が5年になる代表的な例として、年間100万円の納税義務がある人が5年間無申告だった場合、未納の税金は500万円。これに加えて無申告加算税(最大25%)が課されると117万5,000円、合計617万5,000円の税金を支払う義務が生じます。時効が成立しなければ、これだけの税金を一括で納める必要があるのです。
税金に関する参考記事:「寡婦控除とは?適用条件や申告方法、ひとり親控除との違いについても解説!」
【7年】税金の時効:悪質な脱税・不正行為があった場合
SoVa税理士お探しガイド編集部
近年、税務署でもAIを活用しているため税務調査リスクは増大しているため、顧問税理士と相談しながら正確な日々の記帳がもとめられます。2024年には追徴課税額が過去最高を更新しています。
税金の時効がさらに7年に延びるのは、脱税などの悪質な不正が認定された場合です。これは、国税通則法第70条第5項に明記されており、次のような行為が対象です。
税務調査と税金の時効に関するおすすめ記事

税務調査や税金に時効、税金の時効が停止したりリセットされるケースについては以下の記事も参考になるでしょう。
「「確定申告をしていない(無申告)」のペナルティは5年で時効になる|ペナルティの中身や時効になる可能性、過少申告についても解説」
こうした場合、税金の時効は7年とされ、税務署は7年以内であれば税金の更正、加算税の賦課、延滞税の請求を行うことができます。さらに、重加算税(35~40%)が課されることも多く、税金の負担が1000万円以上に膨れ上がることもあります。
税金の時効は本当に成立する?時効中断とリセットの仕組み
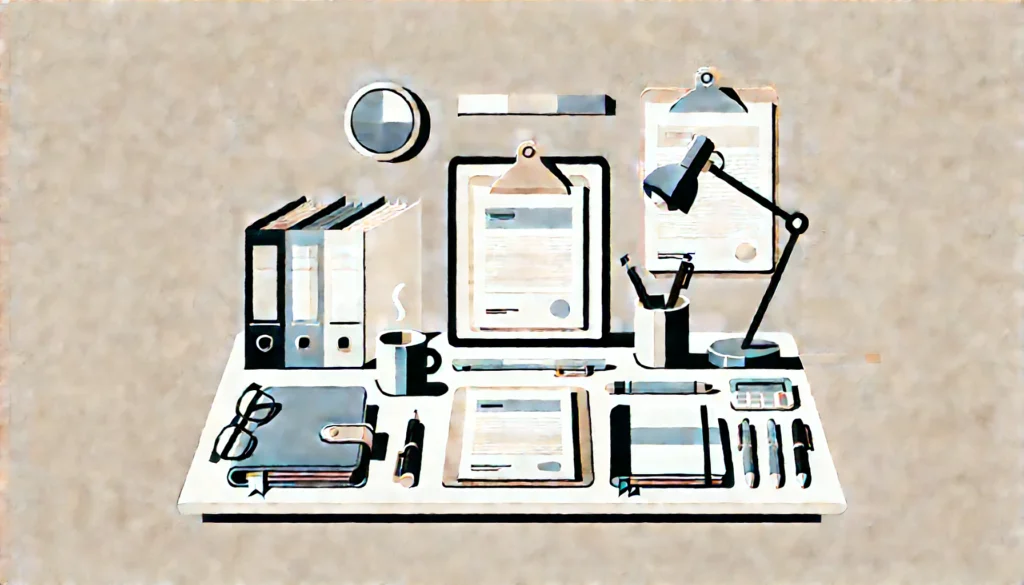
SoVa税理士お探しガイド編集部
税務調査以外に、社会保険調査については以下の記事も是非参考にしてください。
「 社会保険調査は厳しいのか?年金事務所の調査がくる理由と流れを解説 」
理論上、税金には時効が存在し、一定期間が経過すれば税務署はその税金に対して更正や追徴課税などの処分を行えなくなるとされています。これを「税金の時効制度」といい、確かに法律上は認められているものです。しかし、実務の世界では、この税金の時効が実際に成立するケースは極めて稀であるのが現実です。
その大きな理由は、税務署には税金の時効を中断・停止・リセットするためのさまざまな制度的手段が用意されているからです。
税金や税務調査の時効に関するポイント!

納税者が「あと少しで時効だから大丈夫」と油断している間に、税務署のアクションによって時効の進行が止まり、税務調査や督促の対象となることが非常に多くあります。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「税金に時効はあるのか?」
そのため、「あと数ヶ月で時効だから安心」と思っていても、税務署からの1通の書類で税金の時効は振り出しに戻ることになります。
「税金や税務調査の時効」編集部
税金の時効はあるが、あってないようなものと認識しておくのが現実的です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【1】税務署からの督促状・催告書で税金の時効は即リセット
税金の時効が中断される最も代表的なケースが、税務署から納税者に送付される「督促状」や「催告書」です。このような文書が一通でも届いた時点で、それまで進行していた税金の時効は完全にリセットされます。
「税金や税務調査の時効」編集部
税金や税務調査の時効や、時効が停止するケースなどは以下のサイトも是非ご覧ください。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「税金に時効はあるの?」
たとえば、税務署が税金の未納に気づき、「納税義務があります」と通知した場合、その通知が届いた日から再び時効がカウントされ直します。これにより、本来あと数ヶ月で時効が成立するはずだった税金についても、再び3年・5年・7年の時効期間が最初からスタートすることになるのです。
このように、税金の時効は非常に簡単に中断・延長される仕組みになっており、税務署側が動き出せば、時効の成立は事実上ほぼ不可能となります。

合わせて読みたい「税務調査で追徴課税はいくら?」に関するおすすめ記事

税務調査で追徴課税はいくら取られる?いくらから調査対象になるのかも詳しく解説!
【2】税務調査の開始や通知でも税金の時効は中断・停止
次に注意すべきなのが、税務調査の開始や、税務署からの事前通知です。税務署は、調査に入る前に「○月○日から税務調査を行います」という通知書(事前通知書)を送付することが一般的ですが、この通知が届いた時点で、税金の時効は自動的に停止または中断されます。
税務調査と税金の時効に関するおすすめ記事

税務調査や税金に時効、税金の時効が停止したりリセットされるケースについては以下の記事も参考になるでしょう。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「税金にも「時効」があるならば「逃げ切れる」のか?」
また、実地調査が行われた場合や、税務調査の結果として修正申告を求められた場合にも、税金の時効は進行しなくなるか、新たにカウントし直しになります。
「税金や税務調査の時効」編集部
税務署が税務調査に着手した瞬間から、納税者にとっては「時効は振り出しに戻った」と同じ状態になるのです。
税務調査は、数年分の税金に対してさかのぼって行われるため、「あと1年で時効だった税金」が調査によって再カウントとなり、結果的に7年分の税務調査が行われるリスクも十分にあります。
【3】更正処分・修正申告が行われた場合も時効は無効化

合わせて読みたい「法人が支払う税金の種類について」に関するおすすめ記事
法人が支払う税金、種類と納付タイミングを税理士が解説!

さらに、税務署による更正処分(税額の修正決定)や、納税者自身が提出する修正申告も、税金の時効を無効化する代表的なトリガーとなります。
たとえば、税務調査の結果、税務署が過去の申告に誤りを見つけ、「本来納付すべき税金が不足している」と判断した場合、更正処分が行われます。この時点で、その税金に関する時効の進行は中断され、場合によっては加算税や延滞税も追加で課されることになります。
また、納税者が自主的に過去のミスを見つけて修正申告を提出した場合でも、同様に税金の時効はリセットされ、再度ゼロからスタートすることになります。
税金の時効は「あるようで、ないもの」と考えるべき
こうした実態を踏まえると、法律上は確かに税金に時効が存在していても、税務署のちょっとした動きや通知で簡単に時効が中断・リセットされてしまうのが現実です。督促状や税務調査の通知、更正処分などは、納税者が知らないうちに進行していることもあり、気づいたときには時効の成立が遠のいていたという事例も多々あります。

合わせて読みたい「法人が納める消費税」に関するおすすめ記事
法人が納める消費税について解説! 税理士のサポートを受けるメリットも紹介

そのため、「税金の時効で逃げ切れるかもしれない」と考えるのは極めて危険な選択です。時効を待つよりも、早期に専門家へ相談し、適切に修正申告や納税対応を行った方が、税務調査での追徴リスクや加算税の負担を軽減できる可能性が高いです。
税金や税務調査の時効に関するポイント!

税金に関するトラブルを避けるためにも、「税金の時効があるから大丈夫」と油断せず、常に正しい申告と納税を心がけることが重要です。
脱税による税務調査と税金の時効|時効はあるが成立は極めて困難?
日本の税制は、納税者が自ら申告し、納税額を確定させる「申告納税制度」を基本としています。これは、法人税や所得税といった主要な税金すべてに適用される制度です。納税者の自己申告に依存するこの仕組みにおいて、税務署は税金の申告内容が正しく、かつ過不足なく納付されているかを確認するため、定期的に税務調査を実施しています。

合わせて読みたい「法人税・法人事業税・法人住民税の違い」に関するおすすめ記事

法人税・法人事業税・法人住民税の違いとは?計算方法や課税対象、納付先まで詳細解説!
この税務調査には、過去の税金の申告内容を遡って確認する権限がありますが、その調査対象となる期間には「時効」という法的な制限が設けられています。
「税金や税務調査の時効」編集部
一定期間を超えてしまえば、原則として税務署はその過去の税金に対して調査・更正を行えなくなるというのが、税金の時効制度です。
しかしながら、この税金の時効制度には多くの例外が存在し、特に脱税や無申告といった行為があった場合には、時効の年数が5年・7年と延長され、税務調査の対象も大幅に広がる可能性があります。また、税務署の通知や調査開始によって、税金の時効が中断またはリセットされる仕組みがあるため、実務上、時効が成立することは非常に稀であると言えるのです。
税務調査と税金の時効に関するおすすめ記事

税務調査や税金に時効、税金の時効が停止したりリセットされるケースについては以下の記事も参考になるでしょう。
「税金の時効は何年?経営者が知りたい所得税の時効に関する3つの知識」

合わせて読みたい「税務調査の流れ」に関するおすすめ記事

税務調査の流れとは?調査対象となる確率や時期についても解説!
時効3年|税務調査の基本的な調査対象期間と税金の取り扱い
「税金や税務調査の時効」編集部
税金や税務調査の時効や、時効が停止するケースなどは以下のサイトも是非ご覧ください。
「脱税とは?申告漏れとの違い・具体例・リスク・時効・脱税を防ぐための注意点などを分かりやすく解説!」
原則として、税務調査における調査対象期間は過去3年分の税金とされています。これは、税金の申告内容に大きな誤りがなく、故意や悪質な脱税行為が見られない、いわゆる「通常の申告」であると税務署が判断した場合に適用される時効3年の原則です。
こうしたケースでは、税務署による税務調査も、時効である3年の範囲に限定されるのが一般的です。
税金や税務調査の時効に関するポイント!

この「3年の時効」が成立するには、税務署がそれまでに調査や通知などを行っていないことが前提となります。
時効5年|繰り返される誤りや無申告があった場合の税金への対応
次に、税金の時効が5年に延長されるのは、中程度の申告義務違反や継続的なミスが確認された場合です。
「税金や税務調査の時効」編集部
特に次のような状況が該当します。
このような場合、税務署は「軽微なミスでは済まされない」と判断し、税金の時効を5年に延長することで、5年間分の申告内容と納税状況を詳細に調査することが可能となります。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「相続税の時効は5年か7年|逃れる方法はある?ペナルティも解説!」

専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
また、無申告は特に重く見られやすく、税務調査でも優先的に5年分が対象とされる傾向があります。仮に年間100万円の納税義務がある場合、5年間無申告であれば、本税500万円に加えて無申告加算税・延滞税が課されるため、合計納税額は600万円を超えるケースも少なくありません。
時効7年|脱税や虚偽申告など悪質性が高い場合の税金リスク
税金の時効が7年に延長されるケースは、税務署が明確な脱税行為や虚偽の申告があったと認定した場合です。
国税通則法第70条では、「偽りその他不正の行為」により税額を免れた場合、税金の時効は7年まで延びることが明記されています。
【具体的な脱税例】
これらの行為は、いずれも税務署から「悪質」と判断される可能性が高く、時効が7年に引き延ばされるだけでなく、重加算税(35〜40%)や延滞税の賦課対象ともなります。税務調査では7年間分の資料提出を求められることもあり、調査が長期化するケースもあります。
税金の時効年数は固定ではない?判断は税務署次第
重要な点として、税金の時効年数(3年・5年・7年)は機械的に決まるものではなく、税務署が個別に判断するという特徴があります。たとえ納税者に悪意がなかったとしても、結果として税金の過少申告が何年も続いていた場合、税務署の裁量で「5年または7年の時効が妥当」と判断され、調査対象年数が延長されることは十分に起こり得ます。

合わせて読みたい「税理士変更による税務調査」に関するおすすめ記事
法人税務調査で指摘事項への対応は?税務調査の基礎から対策まで解説!

したがって、「今年で時効だから安心」と思い込むのは危険であり、税金の時効制度は極めて柔軟かつ厳格に運用されているという点を理解しておく必要があります。
税金の時効制度は、納税者を過剰な追及から守るために存在する仕組みです。しかし、現実には税務調査や通知によって容易に中断・再スタートが可能な制度設計となっており、時効が実際に成立する例はごく一部に限られます。
「税金や税務調査の時効」編集部
税金や税務調査の時効や、時効が停止するケースなどは以下のサイトも是非ご覧ください。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「贈与税の時効は6年(隠したら7年)時効成立を判断する上での注意点」
特に、脱税や無申告が疑われるケースでは、税金の時効が7年まで延び、税務調査の範囲も大幅に広がるため、早い段階での是正や専門家への相談が極めて重要です。「時効まで逃げ切れる」と考えるのではなく、税金の申告に不安があるなら、時効が成立する前に自ら修正申告することが、結果として負担を軽減する最善の方法です。
現実的に時効はほぼ成立しない理由
ここまでご説明してきたとおり、税金には時効が存在するというのは事実です。所得税や法人税などの国税では、税金の時効期間が3年・5年・7年と状況に応じて定められており、税務署がその期間内に税務調査を行わなければ、税金の徴収権が消滅するという仕組みになっています。
また、地方税(住民税や固定資産税など)についても、「賦課権の除斥期間」や「徴収権の消滅時効」という税金の時効に関する制度が存在し、こちらでは各地方自治体が徴税権を持つことになります。つまり、国税であれ地方税であれ、税金には時効という法的な期限が設けられているのです。
税務調査と税金の時効に関するおすすめ記事

税務調査や税金に時効、税金の時効が停止したりリセットされるケースについては以下の記事も参考になるでしょう。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「相続税申告の時効成立は7年。でも簡単に逃げ切れない理由 元国税専門官が解説」
とはいえ、「税金の時効をうまく使って納税義務を回避できるのでは?」という発想は、現実には極めて実現性が低く、非常に危険です。というのも、税金の時効は一度成立すれば税金の支払い義務が消える仕組みである一方で、税務署や自治体による税務調査や督促、通知があった時点でその時効は簡単にリセット・中断されてしまうからです。
たった1通の税務署からの督促状や、税務調査開始の通知が届くだけで、税金の時効はゼロから再スタートします。
「税金や税務調査の時効」編集部
つまり、税金の時効を成立させるには、3年・5年・7年という長期にわたり、一切税務調査を受けず、税務署や自治体からの接触もなく過ごす必要があるという極めて非現実的な状況を維持しなければなりません。
しかし、税務署は税金の回収におけるプロフェッショナルです。税金の公平性を守るため、無申告や過少申告、脱税といった行為は税務調査で徹底的に調査され、適正に税金を徴収する体制が整っているのです。税金の申告義務を逃れて時効成立を狙うという行為は、税務署の目を欺けるようなものではないという点をしっかり理解しておく必要があります。
加えて、税金の時効がリセットされた場合、過去の税金が再び徴収の対象となるだけでなく、税務調査の結果に応じて延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、さらには重加算税など、複数の税金ペナルティが一気に加算されます。その金額は、本来の税金の何倍にも膨れ上がることもあり、経済的なダメージは非常に大きなものになります。
税金や税務調査の時効に関する気をつけておきたい注意点

さらに深刻なのは、税務調査で悪質な脱税が発覚した場合には、税金の追徴に加えて、不動産や給与、預金などの資産が差し押さえられるリスクもあるという点です。
こうした強制的な徴収措置は、税金の時効を狙って逃げ切ろうとした結果として最悪の展開を招くことになりかねません。
結論として、「税金の時効で逃げ切る」という考え方は、現実的ではなく、極めてリスクの高い選択肢です。税務調査によって税金の未申告や脱税が発覚した場合、時効が延び、負担が増し、信頼も失われます。

無申告や脱税に対する税金のペナルティ|税務調査で発覚した場合のリスクとは?
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
無申告や脱税があった場合、税金の納付義務だけでなく、税務調査の対象期間が通常よりも延長され、さらに重いペナルティが課されるリスクがあります。税金の時効制度は、一定期間が過ぎると追徴課税ができなくなる仕組みですが、税務調査が入ると時効が中断・延長されるため、実際には税金の時効が成立することは極めてまれです。
「税金や税務調査の時効」編集部
税金や税務調査の時効や、時効が停止するケースなどは以下のサイトも是非ご覧ください。
「裁判例にみる時効をめぐる課税上の争点等」

合わせて読みたい「消費税の申告義務」に関するおすすめ記事
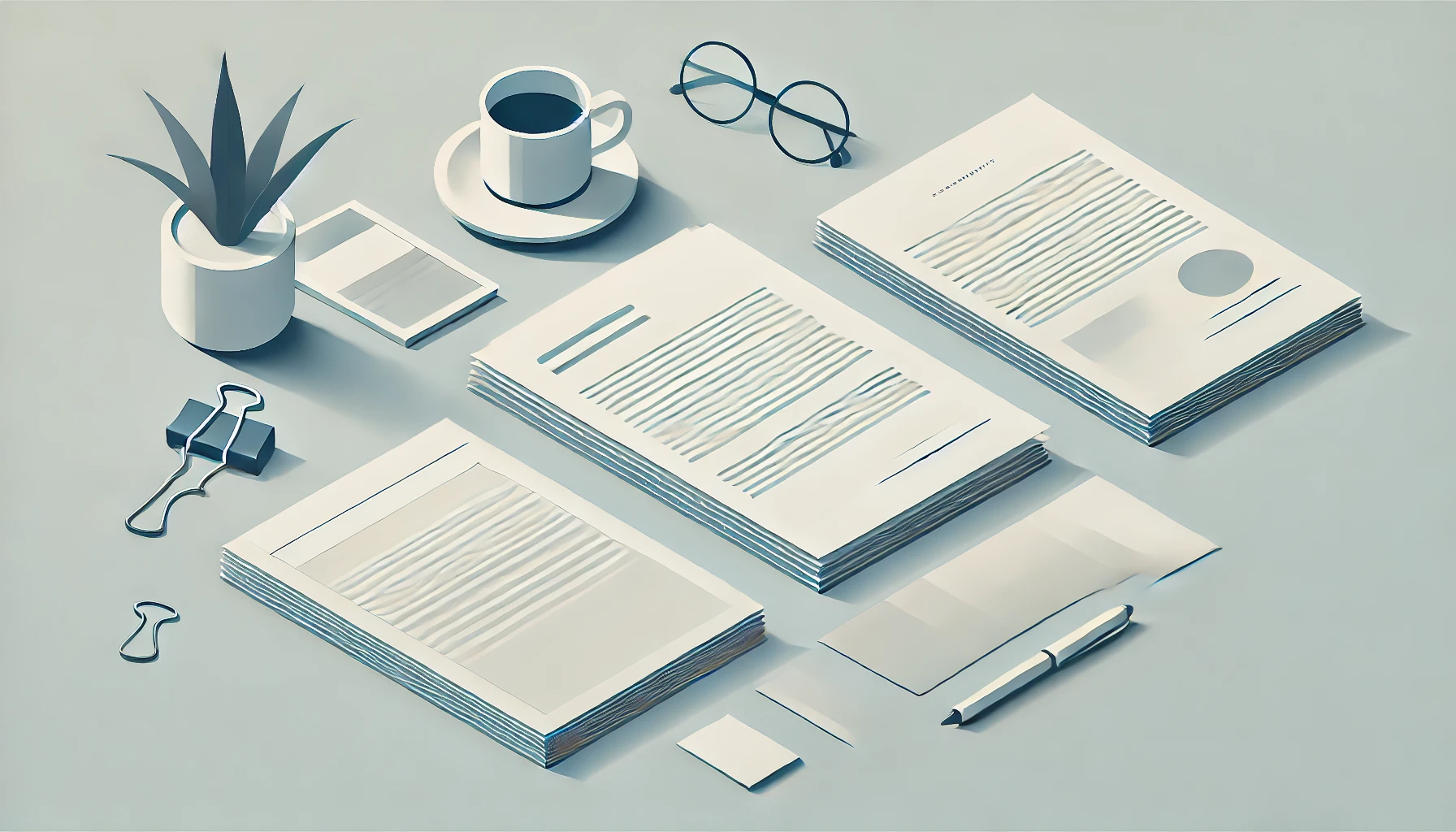
消費税申告義務の対象となる条件とは?計算方法や課税事業者と免税事業者の違いも解説!
また、税務調査の結果、無申告や過少申告、意図的な隠蔽が確認されると、各種の加算税や延滞税、重加算税といったペナルティが税金に上乗せされて課されます。ここでは、税務調査で見つかりやすい無申告・脱税に対する税金のペナルティを具体的に解説し、それぞれの税金に課される加算税の計算方法や時効との関係性についても詳しくご紹介します。
| 加算税の種類 | 主な課税要件 | 原則税率 | 重加算税率(仮装・隠蔽等) | 適用除外の例 |
|---|---|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内申告後、修正申告や更正により追加納税が発生 | 基本10% ※50万円超部分は15% |
35% | ・税務調査前に自主修正をした場合 ・正当な理由がある場合(通法67①) |
| 無申告加算税 | 期限内に申告せず、期限後に申告した場合 | 15%(原則) ※50万円超部分は20% |
40% | ・正当な理由がある場合(通法66①ただし書) ・1か月以内の申告(通法66⑨) |
| 不納付加算税 | 源泉徴収した税金を期限内に納付しなかった場合 | 10%(原則) | 35% | ・正当な理由がある場合(通法65⑤) ・1か月以内の納付(通法65①・②) |
| 重加算税(共通) | 仮装・隠蔽によって申告漏れや無申告が発生した場合 | 上記加算税に代えて適用 | 上記のとおり | ・納税者の責めに帰すべき事由がない場合など一部免除可能 |

合わせて読みたい「税務調査が10年以上来ない」に関するおすすめ記事

税務調査が10年以上来ない法人と個人事業主の特徴とは?業種や税務調査が入る確率も紹介!
無申告加算税|税金を期限までに申告しなかったペナルティ
無申告加算税は、納税者が税金の確定申告を期限内に行わなかった場合に、税務調査によって発覚すると課される加算税です。税金を期限までに申告しないこと自体が税法違反と見なされるため、税務署は厳正に対応します。
たとえば、税金100万円を無申告だった場合、税務調査により次のような無申告加算税が発生します。
無申告加算税:50万円×15%+50万円×20%=25万円
ただし、税務調査の通知を受ける前に自主的に税金を申告・納付すれば、無申告加算税は5%に軽減されます。つまり、税務調査が始まる前に自ら税金を正しく申告することで、ペナルティを最小限に抑えることが可能です。
「税金や税務調査の時効」編集部
税金や税務調査の時効や、時効が停止するケースなどは以下のサイトも是非ご覧ください。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「脱税に時効はあるの?ペナルティや脱税を防ぐポイントなど解説」
延滞税|税金の納付遅れに対する金利的ペナルティ
税金の納付が遅れた場合には、延滞税という形で追加の税金が発生します。延滞税は、税金の納付が法定期限を過ぎた日から発生し、税務調査によって過去の未納が発覚した場合にも必ず課される税金です。
税務調査と税金の時効に関するおすすめ記事

税務調査や税金に時効、税金の時効が停止したりリセットされるケースについては以下の記事も参考になるでしょう。
「【贈与税時効は原則6年】時効が成立しない理由と申告漏れリスクは?」
たとえば、税金100万円を30日遅れて納付した場合、税務調査で指摘されると、以下のような延滞税が加算されます。
延滞税:100万円×7.3%×30日÷365日 ≒ 6,000円
「税金や税務調査の時効」編集部
税務調査が入る前に納税を完了していれば、この延滞税という追加税金の負担を軽減することができます。
過少申告加算税|税金を少なく申告した際に課される罰則
過少申告加算税は、期限内に税金を申告したものの、実際よりも少ない金額で申告していた場合に、税務調査によって過少が発覚すると課される税金です。
たとえば、本来納付すべき税金が200万円だったにもかかわらず、100万円だけを申告していた場合、税務調査によって次のような過少申告加算税が発生します。
過少申告加算税:100万円×10%+100万円×15%=25万円
税金や税務調査の時効に関するポイント!

税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税が免除される可能性があるため、時効成立を待つよりも早期の是正が重要です。
重加算税|悪質な脱税行為に対する最も重い税金の罰則
重加算税は、税務調査によって仮装や隠ぺいなどの故意的な不正行為が発覚した場合に、非常に高い税率で課される税金です。この重加算税は、いわば脱税への「制裁」として機能しており、通常の加算税とは別枠で扱われます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
たとえば、税金100万円をまったく申告していなかった場合、税務調査で脱税が認定されれば、40万円の重加算税が上乗せされます。

合わせて読みたい「還付金」に関するおすすめ記事

還付金とは?還付が発生しうる税金の種類と還付条件についても解説!
また、過去5年以内に重加算税や無申告加算税を課された履歴がある場合、税率にさらに10%が加算される「加重措置」もあるため、繰り返しの不正行為は特に厳しく処罰されます。これらは税務調査の過程で明らかになると、税金の時効も7年に延長される可能性があります。
「税金や税務調査の時効」編集部
税金や税務調査の時効や、時効が停止するケースなどは以下のサイトも是非ご覧ください。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「税金の滞納に時効はある?差し押さえ回避のために知っておくべきこと」
税金には罰則や加算税が存在し、税務調査によってそれが明るみに出た場合には、想像以上の負担がのしかかります。
税金や税務調査の時効に関する気をつけておきたい注意点

無申告や虚偽申告といった税金の重大な違反行為は、税務調査によって時効が延長され、最大で過去7年分の税金を遡って調査・追徴される可能性が高くなります。
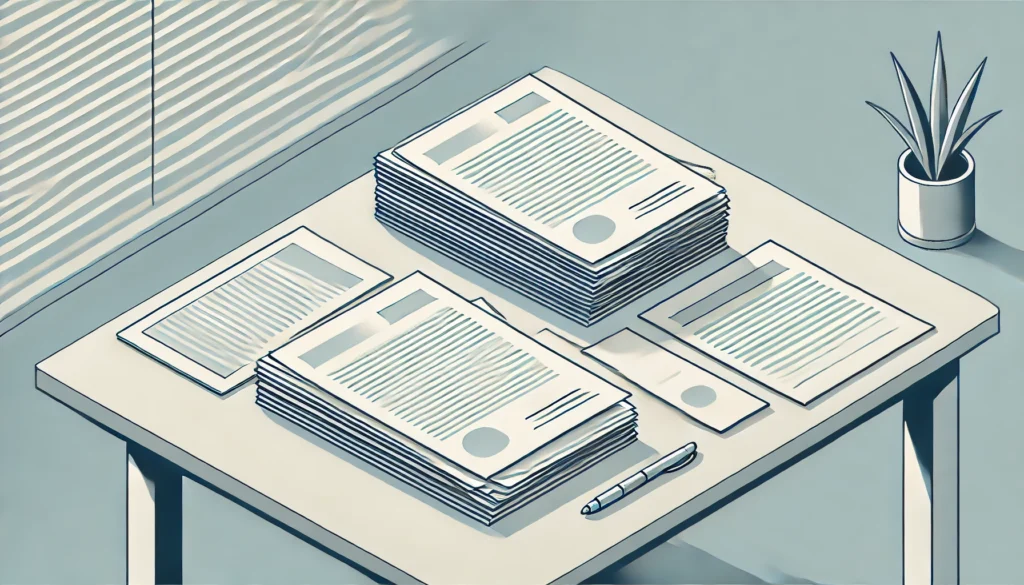
さらに、税務調査では税金の不備だけでなく、申告の意図や過去の行動パターンも詳細にチェックされ、一度悪質と認定されれば、加算税や重加算税など多額の追加税金が課される結果となるのです。
税務署には「賦課権」と「徴収権」もあることに注意
税金の納付を怠った場合、税務署は強力な権限をもって対応します。特に重要なのが、税金に関する「賦課権」と「徴収権」です。税務署は、税務調査の結果、無申告や過少申告が確認されれば、税金の額を再計算・決定できる「賦課権(課税権)」を行使し、本来納めるべき税金を確定させます。
税務調査と税金の時効に関するおすすめ記事

税務調査や税金に時効、税金の時効が停止したりリセットされるケースについては以下の記事も参考になるでしょう。
税金と税務調査の時効に関する参考記事:「個人で無申告!時効はいつ?払わずにいたら、どのような追徴課税がかかるのか?」
さらに、確定した税金について支払いがない場合には、差し押さえなどの強制執行を行える「徴収権」も有しており、これは非常に強力な権限です。
「税金や税務調査の時効」編集部
税務調査によって税金の不備が見つかれば、時効内であれば税務署は賦課権・徴収権を使って徹底的に対応してきます。
これらの税金に関する権限には一応「時効(期間制限)」がありますが、税務調査の開始や督促状の送付によって時効は簡単に中断・リセットされるため、「税金は時効で逃げ切れる」という考え方は極めて危険です。
税金や税務調査の時効に関する気をつけておきたい注意点

税金の時効を狙って放置することは、むしろ税務調査によるペナルティや追徴リスクを高める要因となるため注意が必要です。
Q&A|よくある質問
Q. 税金にも時効はあるのですか?
A. はい、税金にも時効があります。納税義務や徴収権は無期限ではなく、原則として5年の時効期間が定められています。ただし、納税者が脱税行為を行っていた場合や申告漏れが悪質と判断された場合は、税金の時効は7年に延長されることがあります。これは国税通則法によって規定されており、税務署が時効完成前に調査や督促を行えば、時効が中断または延長されるケースもあります。
Q. 税務調査は時効を過ぎたら行われないのですか?
A. 一般的に、税務調査は税金の時効期間内であれば実施されます。原則は5年ですが、脱税などの不正行為が疑われる場合は7年間さかのぼって税務調査が行われることがあります。
気をつけておきたい注意点

たとえ5年以上前の取引でも、内容によっては税務調査の対象になる可能性があるため注意が必要です。
Q. 脱税が発覚した場合、税金の時効はどうなりますか?
A. 脱税が発覚した場合、税金の時効期間は5年ではなく7年に延長されます。さらに、重加算税や延滞税といった追加の税金やペナルティが課されることもあります。特に、意図的な申告漏れや仮装・隠蔽などが行われていた場合には、通常の課税だけでなく、刑事罰に発展することもあります。
Q. 税務調査や税金の時効に備えてできる対策は?
A. 税金の時効を正しく理解し、帳簿や領収書を7年間保存しておくことが基本的な対策です。また、専門知識のある税理士に相談することで、税務調査や税金の時効に関連するトラブルを未然に防げます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
特に法人や個人事業主は、税務リスクを軽減するためにも、日頃から正確な会計処理と申告を行うことが重要です。
まとめ|税金の時効は存在し、税務調査によって延長・中断される可能性大
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税金に時効はあるのか?という疑問に対する答えは「Yes」ですが、現実には税金の時効が実際に成立するケースはごくわずかです。確かに、税金の種類や状況によって、税金の時効期間は3年・5年・7年と定められています。しかし、その時効は税務調査の開始や税務署からの通知・督促状の送付によって、簡単に中断またはリセットされる仕組みになっています。
特に、無申告や過少申告、脱税などの不正が疑われる場合は、税務調査によって税金の時効が最大7年まで延長されるリスクがあります。しかも、税務調査によって税金の不備が発覚すると、本税だけでなく、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税・重加算税といった高額の税金が追加で課されることになり、納税者の負担は大きく膨らみます。
さらに、税務調査は一度開始されると過去数年分の税金を徹底的にチェックされるため、税金に関する不備があれば見逃されることはほとんどありません。税金の時効を期待して放置するよりも、税務調査が始まる前に自主的に修正申告や納付を行うほうが、税金リスクを大きく減らすことができるのです。
税金の時効制度は、あくまでも「理論上の期限」に過ぎず、税務署の調査権限や税務調査の実務と組み合わせて理解する必要があります。もし過去の申告や納税に不安がある場合は、時効を待つのではなく、税金と税務調査の専門知識を持つ税理士などの専門家に相談することが、最も安全で確実な選択肢となるでしょう。

合わせて読みたい「税務調査で税理士に依頼するかどうか」に関するおすすめ記事
税務調査に税理士は必要?税理士に依頼するメリット・デメリットまで紹介

税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!