会社設立の費用はいくらかかる?株式会社と合同会社の設立相場を解説!
カテゴリー:
公開日:2025年10月
更新日:2026年1月10日
会社を立ち上げようと考えたとき、最初に気になるのが「会社設立の費用」です。会社設立の費用は、登記や定款認証、資本金の払い込み、印鑑の作成など多岐にわたり、株式会社か合同会社かによっても大きく異なります。会社設立の費用は最低でも数十万円単位で必要になるため、起業準備において重要な検討項目です。
特に株式会社を設立する場合は、定款認証費用や登録免許税などがかかり、会社設立の費用は20万円以上が一般的です。一方で、合同会社であれば会社設立の費用を10万円前後に抑えることも可能です。
「会社設立の費用」編集部
この差は起業時の資金計画に大きな影響を与えるため、会社設立の費用を正しく把握しておくことが成功の第一歩となります。
本記事では、株式会社と合同会社の会社設立の費用を比較し、それぞれの費用の内訳や相場をわかりやすく解説します。会社設立の費用を少しでも抑えたい方や、最適な会社形態を選びたい方はぜひ参考にしてください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
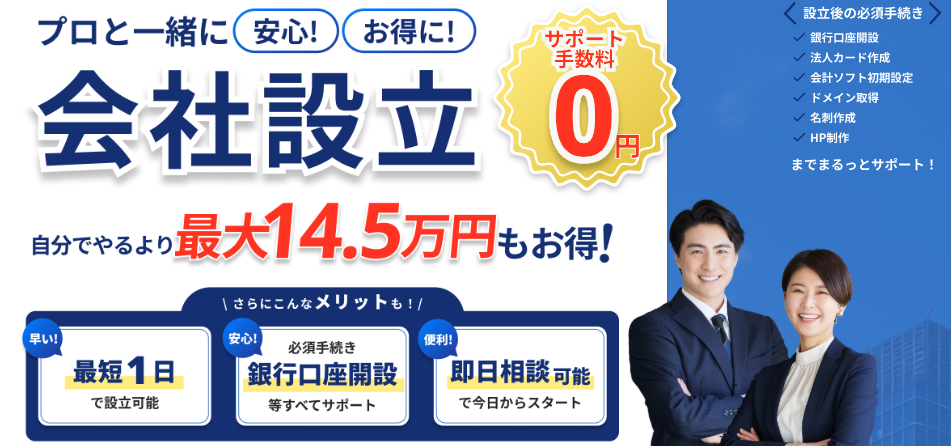
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
会社設立の費用に含まれるもの
会社設立の費用は、主に次のような内容で構成されています。
- 会社の設立登記にかかる費用
- 定款作成・認証にかかる費用
- 資本金として用意する金額
- 会社印鑑や印鑑証明書などに必要な費用
- 専門家に手続きを代行依頼する際の費用
これらはいずれも会社設立の費用として必須であり、株式会社か合同会社かに関わらず必要になります。
会社設立の費用に含まれるもの①
会社の設立登記費用
会社設立の費用の中でも大きな割合を占めるのが設立登記です。
会社設立の費用に関するポイント!

登記は法務局に会社の存在を登録する手続きで、この際に登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は会社形態によって異なり、株式会社では最低15万円、合同会社では最低6万円です。さらに「資本金額×0.7%」の金額が最低額を上回る場合は、その金額が会社設立の費用として必要になります。資本金を多く設定すればするほど、会社設立の費用も増える点に注意しましょう。
会社設立の費用に含まれるもの②
定款にかかる費用
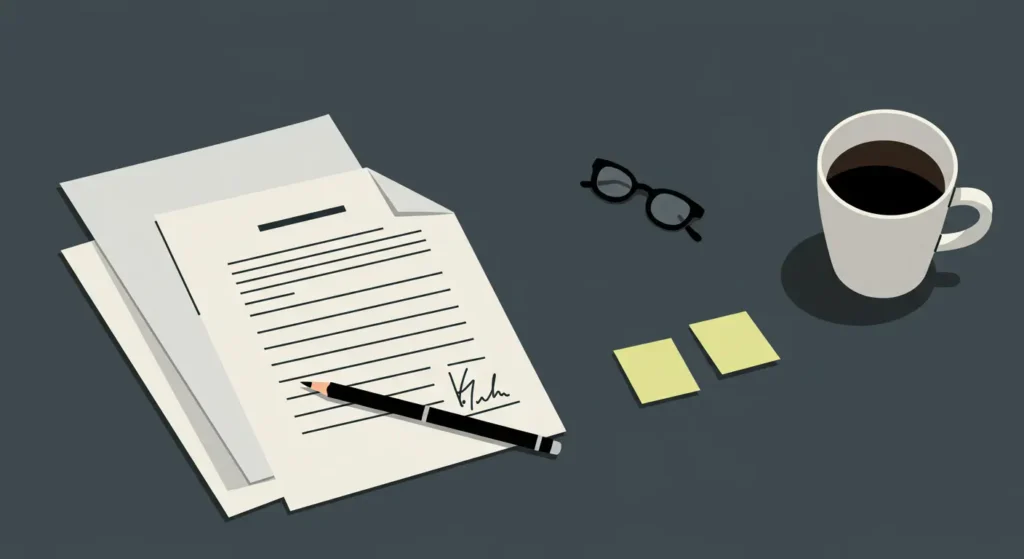
会社設立には必ず定款が必要で、これにも会社設立の費用がかかります。紙の定款を作成すると4万円の収入印紙代が発生しますが、電子定款にすれば印紙代は不要です。
会社設立の費用と維持費に関するおすすめ記事

合同会社と株式会社の会社設立の費用違い、会社設立後の維持費については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立の費用と維持費に関する記事:「会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説」
定款の認証手数料(株式会社の場合のみ)
株式会社を設立する場合、会社設立の費用のひとつとして「定款認証手数料」が発生します。これは作成した定款が正しく記載されているか、公証人に確認してもらうことで改ざんや紛失などのトラブルを防ぐための仕組みであり、会社設立の費用の中でも避けられない出費です。
定款認証は公証役場で行われ、公証人に証明してもらう必要があります。この会社設立の費用である認証手数料は、設立時の資本金の金額によって変動します。
会社設立の費用に関するポイント!

資本金が少ない場合と多い場合で会社設立の費用が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
「会社設立の費用」編集部
具体的には以下のように、資本金の額に応じて会社設立の費用である定款認証手数料が決まります。
- 資本金100万円未満:3万円
- 資本金100万円以上300万円未満:4万円
- 資本金300万円以上:5万円
このように、株式会社を設立する際には会社設立の費用として必ず定款認証手数料を見込んでおかなければなりません。一方で、合同会社の場合は定款認証が不要なため、この会社設立の費用は発生しない点が大きな違いとなります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立の費用に含まれるもの③
資本金
会社設立の費用には、資本金も含まれます。法律上は1円から株式会社や合同会社を設立できますが、実際には信用や事業規模を考慮して資本金を設定する必要があります。
多くの会社は資本金を300万〜500万円程度に設定しており、これも会社設立の費用の一部として計上されます。
会社設立の費用と維持費に関する記事:「会社設立の費用はいくらかかる?会社形態や手続きごとの金額の違いとあわせて解説」
会社設立の費用に関するポイント!

資本金は単なる出資金ではなく、金融機関や取引先からの信用にも直結するため、会社設立の費用の中でも特に重要なポイントです。
会社設立の費用に含まれるもの④
会社印鑑や印鑑証明書にかかる費用
会社設立の費用には会社印鑑の購入費用や印鑑証明書の発行費用も含まれます。会社印鑑は契約や登記に不可欠で、材質やサイズによって数百円〜1万円程度の費用がかかります。
また、印鑑証明書は1通あたり100円〜1,000円程度で、会社設立の費用の中でも細かな出費として積み重なります。必要な手続きをスムーズに行うためにも、会社設立の費用としてあらかじめ準備しておきましょう。
会社設立の費用に含まれるもの⑤
専門家に依頼した場合の費用
会社設立の費用は、自分で手続きを行う場合よりも、司法書士や税理士などの専門家に依頼した場合に増えます。特に登記手続きは司法書士しか代行できないため、依頼するケースが多く見られます。
会社設立の費用と維持費に関するおすすめ記事

合同会社と株式会社の会社設立の費用違い、会社設立後の維持費については以下の記事も是非参考にしてください。
「会社設立に必要な費用とは?法定費用や運営費用など項目別に解説」
専門家に依頼する会社設立の費用はおおよそ5万円〜20万円が相場です。
「会社設立の費用」編集部
確かに会社設立の費用は上がりますが、ミスを減らせるうえ、設立後のフォローも受けられるという大きなメリットがあります。

合わせて読みたい!「会社設立時の費用」に関するおすすめ記事
会社設立時に税理士に依頼した時にかかる費用とメリットを解説

株式会社と合同会社の会社設立の費用を比較
会社を立ち上げる際に必ず発生するのが「会社設立の費用」です。同じ会社設立であっても、株式会社を選ぶか合同会社を選ぶかによって会社設立の費用は大きく変わります。ここでは、株式会社と合同会社の会社設立の費用を比較し、それぞれの相場について詳しく解説します。
株式会社と合同会社の会社設立の費用一覧
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円(電子定款なら不要) | 40,000円(電子定款なら不要) |
| 定款謄本手数料 | 約2,000円(1ページあたり250円) | 0円 |
| 定款認証手数料(公証人に支払う費用) | 15,000円〜50,000円(資本金や条件によって変動) | 0円 |
| 登録免許税 | 150,000円 または 資本金×0.7%(いずれか高い方) | 60,000円 または 資本金×0.7%(いずれか高い方) |
| 合計 | 約222,000円〜 | 約100,000円〜 |
この表からも分かるように、会社設立の費用は株式会社の方が高額になります。株式会社の場合は最低でも約22万2,000円が必要で、さらに資本金や専門家に依頼する報酬を含めると、会社設立の費用は30万円〜50万円に達するケースもあります。一方、合同会社は最低で約10万円から設立が可能であり、会社設立の費用をできる限り抑えたい人にとって魅力的な選択肢です。

合わせて読みたい!「株式会社と合同会社の設立費用に関する違い」におすすめ記事
株式会社と合同会社の設立費用の違いから会社設立後の費用まで徹底解説!


株式会社の会社設立の費用相場
株式会社を設立する場合、会社設立の費用は定款関連費用と登記費用が中心となります。具体的には、定款用の収入印紙代、定款謄本の手数料、定款認証料、そして登録免許税が必要です。
会社設立の費用に関する注意点

会社の規模を大きくすることを目指す場合には、役員報酬や株式譲渡契約書の作成、場合によっては監査報酬なども発生します。さらに将来的に株式上場を目指す場合は、証券取引所への上場費用も追加されます。
このように、会社設立の費用は高額ですが、株式会社は社会的な信用度が高く、資金調達の幅が広がる点が大きなメリットです。大規模な事業展開や外部投資家からの出資を想定している場合は、会社設立の費用がかかっても株式会社を選ぶ価値があります。
合同会社の会社設立の費用相場
合同会社の会社設立の費用は株式会社に比べて大幅に低く抑えられます。必要となるのは定款の収入印紙代と登録免許税であり、電子定款を導入すれば収入印紙代4万円を削減できるため、会社設立の費用をさらに抑えることが可能です。
会社設立の費用に関するポイント!

合同会社には定款認証費用が不要であり、登記の登録免許税も株式会社より安い60,000円からです。
結果として、会社設立の費用は6万円〜30万円程度に収まるケースが多く、小規模事業や家族経営などに適した選択肢となります。
株式会社と合同会社の比較から分かるように、会社設立の費用は選ぶ会社形態によって大きく変動します。信用力や資金調達を重視するなら会社設立の費用が高くても株式会社を、コストを抑えてスピーディーに立ち上げたいなら合同会社を選ぶのが一般的です。

合わせて読みたい「株式会社 合同会社 変更」に関するおすすめ記事

株式会社から合同会社への変更手続きは?組織変更のメリット・デメリットまで解説!
「会社設立の費用」編集部
いずれにしても、会社設立の費用は初期投資の大部分を占めるため、事業計画や将来の方向性に合わせて慎重に検討することが重要です。
会社設立の費用には補助金や助成制度の活用も可能
会社設立の費用は、登記や定款認証、資本金、印鑑作成など多岐にわたり、まとまった金額が必要になるのが一般的です。特に株式会社を設立する場合は、合同会社と比べても会社設立の費用が大きくなるケースが多く、起業家にとって大きな負担となります。そこで注目したいのが、会社設立の費用を抑えるために利用できる補助金や助成制度です。
会社設立の費用と維持費に関するおすすめ記事

合同会社と株式会社の会社設立の費用違い、会社設立後の維持費については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立の費用と維持費に関する記事:「会社設立の費用・維持費ってどれくらい?個人事業主とどっちがお得?」
補助金・助成金で会社設立の費用を軽減する
会社設立の費用を準備する際に、すべてを自己資金だけで賄うのは負担が大きいものです。その点、補助金や助成金を活用すれば、会社設立の費用の一部を外部資金でまかなうことができます。これらは返済の必要がない資金であり、会社設立の費用を抑えつつ事業のスタートダッシュを切るための心強いサポートになります。
会社設立の費用を支援する主な補助金・助成制度
会社設立の費用を支援する補助金や助成制度は、以下のような団体によって提供されています。
- 経済産業省:創業促進や中小企業支援のための補助金を実施
- 厚生労働省:雇用や働き方改革に関連した助成金を提供
- 地方自治体:地域の起業家を対象に、会社設立の費用を補助する独自制度を用意
- 民間団体:ベンチャー企業やスタートアップ支援を目的に、多様な助成制度を実施
このように、さまざまな機関が会社設立の費用を支援しており、自分の事業内容や条件に合う制度を選ぶことで、大きな金銭的負担を軽減することができます。
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例
会社設立の費用は、登記費用や定款認証費用、資本金の払い込みなどを含めると決して小さな金額ではありません。株式会社を設立すれば20万円以上、場合によってはさらに高額になることもあります。
「会社設立の費用」編集部
こうした会社設立の費用を少しでも抑えるために活用できるのが、国や自治体、民間団体が提供する「補助金」や「助成金」です。
返済の必要がなく、条件を満たせば会社設立の費用を大幅に軽減できるため、起業準備段階から検討する価値があります。
ここでは、創業時に利用できる代表的な補助金・助成金の例を紹介します。
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例①
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路拡大や新たな顧客開拓に取り組む際に使える制度で、会社設立の費用を補う強力な支援策です。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
「会社設立の費用」編集部
会社設立の費用や維持費については以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立の費用と維持費に関する記事:「一人で会社を作るときに必要な費用は? 会社設立や事業開始にかかる費用」

補助対象経費の3分の2以内、最大50万円まで補助を受けられるため、広告費や販売促進にかかる会社設立後の初期費用を大きく削減できます。従業員5名以下の小売業やサービス業など幅広い業種が対象となり、会社設立の費用を抑えつつ成長投資につなげられる点が魅力です。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例②
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用を正社員へ転換する企業を支援する助成金です。創業直後にパートやアルバイトを雇い、後に正社員化する場合に申請でき、1人当たり最大72万円の支給が受けられます。人件費は会社設立の費用には含まれませんが、創業時の人材確保にかかるコストを実質的に補填できるため、会社設立の費用負担を総合的に軽減する効果があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例③
地域中小企業応援ファンド(スタートアップ応援型)
地域資源を活用した新商品開発や観光関連事業などに挑戦する企業を支援するのが、地域中小企業応援ファンドです。
会社設立の費用に関するポイント!

各自治体が独自に運営しており、設備投資や研究開発などに幅広く利用できます。
会社設立の費用に直結するわけではないものの、創業直後にかかる運転資金や拡大コストを補助金でまかなえるため、会社設立の費用の総合的な負担を減らすことにつながります。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例④
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、就職が難しい人材を試行的に雇用する際に利用できる制度です。原則3ヶ月間、月額4万円が支給され、最大12万円を受け取ることが可能です。
会社設立の費用と維持費に関するおすすめ記事

合同会社と株式会社の会社設立の費用違い、会社設立後の維持費については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立の費用と維持費に関する記事:「会社設立する時にかかる費用はどのくらい?株式会社と合同会社の違いも紹介」
創業時の人材雇用コストを抑えることは、結果的に会社設立の費用を圧縮することにつながります。
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例⑤
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
通称「ものづくり補助金」と呼ばれるこの制度は、設備投資や新規サービスの開発に利用でき、補助額は数百万円から最大8,000万円まで拡大する場合もあります。創業期に設備を導入する際、会社設立の費用に匹敵する大規模なコストを補助してもらえる可能性がある点は見逃せません。

合わせて読みたい「会社の設立費用は経費にできるのか」に関するおすすめ記事

会社設立の費用は経費?経費の基礎から会社設立に税理士が必要な理由まで解説!
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例⑥
IT導入補助金
会社設立の費用を抑えるうえで、ITツール導入をサポートするIT導入補助金も効果的です。会計ソフトや労務管理システムなど、バックオフィス業務を効率化するツール導入費用の一部を補助してもらえるため、設立直後から経理・労務の負担を軽減しつつ会社設立の費用を削減できます。
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例⑦
事業承継・引継ぎ補助金
「会社設立の費用」編集部
会社設立の費用や維持費については以下のサイトも是非ご覧ください。
「会社設立とは?必要な手続と費用、設立までの流れを詳しく解説」
事業承継を機に新たな挑戦を行う企業が対象で、最大800万円が補助されます。経営資源の引き継ぎや新事業への投資に活用でき、会社設立の費用と合わせて創業期の資金繰りを改善する効果があります。
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例⑧
研究開発型スタートアップ支援事業
技術シーズの事業化を目指すスタートアップ向けの助成制度です。研究開発に伴う初期費用を補助することで、会社設立の費用を技術投資に集中させやすくします。
会社設立の費用を軽減できる補助金・助成金例⑨
地域雇用開発助成金
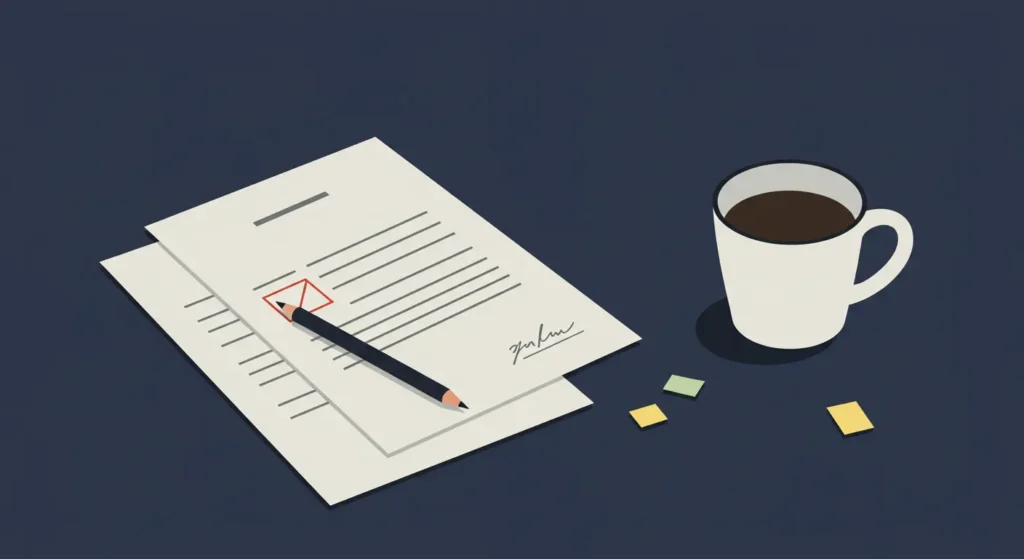
雇用機会が不足している地域で事業所を設立し、人材を雇用する場合に助成される制度です。
「会社設立の費用」編集部
人件費や整備費用の一部を補助してくれるため、地方で起業する際に会社設立の費用を軽減する大きな支えとなります。
会社設立の費用と補助金の注意点
会社設立の費用を補助金や助成金でまかなう際には注意点もあります。各補助金・助成制度には対象条件や申請期限、使途の制限などがあり、要件を満たさないと受け取れません。また、会社設立の費用として受給できるのは一部に限られることもあるため、詳細を必ず確認する必要があります。
会社設立の費用に関する注意点

民間団体の助成金や補助金は種類が豊富で、金額や条件もバラバラです。会社設立の費用を最も効率よくカバーできる制度を選ぶためには、複数の情報を比較検討することが欠かせません。
会社設立の費用は決して小さな金額ではありませんが、国や自治体、民間団体が提供する補助金・助成制度をうまく活用すれば、必要な費用を大幅に抑えることが可能です。会社設立の費用を少しでも減らすことで、設立後の運転資金に余裕が生まれ、経営を安定させやすくなります。

合わせて読みたい「開業費と創立費」に関するおすすめ記事

会社設立費用の勘定科目は?開業費と創立費と記帳のポイントについて詳細解説!
これから起業を考えている方は、会社設立の費用を自己資金だけで負担するのではなく、補助金や助成金といった制度を積極的に調べて利用し、計画的に会社設立を進めていきましょう。
会社設立の費用を節約する方法
起業を検討する際、多くの人が気になるのが「会社設立の費用」です。株式会社を設立しようとすると、定款認証や法人設立登記にかかる登録免許税などを合わせて、20万円〜25万円程度の会社設立の費用が必要になります。決して小さな金額ではないため、少しでも会社設立の費用を抑えたいと考える人は少なくありません。
会社設立の費用と維持費に関する記事:「株式会社の設立費用の目安と内訳は?資本金1円でも節約にならない理由と節約する方法を解説」
かつては「有限会社」という形態があり、株式会社よりも会社設立の費用が安く済む方法として選ばれていました。しかし2005年の会社法改正によって有限会社は新設できなくなり、現在は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」のいずれかを選ぶことになります。
では、現行の制度で会社設立の費用を安くする方法とはどのようなものなのでしょうか。
会社設立の費用を節約する方法①
株式会社にこだわらずに合同会社を選択する
会社設立の費用を節約したい場合、最大のポイントは「株式会社に限定しない」という考え方です。株式会社を設立すると、定款認証費用や最低15万円の登録免許税が必要となり、会社設立の費用はどうしても高額になります。
一方で、「合同会社」「合名会社」「合資会社」であれば、会社設立の費用はおおよそ10万円程度に抑えられます。特に合同会社は、株式会社と比較して会社設立の費用が半額程度で済み、登記や設立後のランニングコストも抑えられるため人気があります。
合同会社を選ぶメリットと会社設立の費用の差
合同会社は、会社設立の費用を抑えたい起業家に特におすすめです。
「会社設立の費用」編集部
合同会社の会社設立の費用は以下の通りです。
- 定款に貼る収入印紙代:4万円(電子定款を導入すれば不要)
- 登録免許税:6万円または資本金の0.7%の高い方
つまり、会社設立の費用は最低6万円で可能となります。株式会社の会社設立の費用が最低20万円かかるのと比較すると、その差は非常に大きく、初期費用を抑えたい人にとって大きなメリットです。
さらに、合同会社には決算公告義務や役員任期の制約がなく、会社設立の費用だけでなく維持費も安くなる点が魅力です。
会社設立の費用と維持費に関するおすすめ記事

合同会社と株式会社の会社設立の費用違い、会社設立後の維持費については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立の費用と維持費に関する記事:「会社設立に最低限必要な費用」
会社設立の費用を節約する方法②
電子定款で会社設立の費用を節約
会社設立の費用を減らす方法としては、電子定款の活用も有効です。紙の定款であれば4万円の収入印紙代が必要ですが、電子定款を利用すればこの費用を丸ごと節約できます。
電子定款を導入するためには、PDFソフトやICカードリーダー、マイナンバーカードなどの初期準備が必要ですが、一度環境を整えてしまえば、会社設立後もさまざまな場面で活用できるため、長期的に見ても会社設立の費用を削減できます。
また、株式会社の場合は毎年必要となる決算公告についても、電子公告を選択すれば官報公告に比べて年間6万円程度の維持費削減につながります。

合わせて読みたい「株式会社の最低設立費用」に関するおすすめ記事

株式会社の最低設立費用はいくら?株式会社の設立費用が最低いくらかかるのかについて解説!
会社設立の費用を節約する方法③
資本金を工夫する
会社設立の費用を考えるとき、資本金も重要な要素です。法律上は1円からでも会社設立は可能ですが、実際には運転資金を考慮するとある程度の金額を設定する必要があります。
ここでポイントとなるのが資本金1,000万円のラインです。資本金が1,000万円未満であれば、会社設立から最初の2年間は消費税の納税が免除されます。つまり、資本金を調整することで会社設立の費用だけでなく、設立後の税負担を軽減することも可能になります。
会社設立の費用は、株式会社を選ぶか合同会社を選ぶか、紙の定款か電子定款か、資本金の設定をどうするかといった選択によって大きく変わります。
会社設立の費用に関するポイント!

「株式会社にこだわらない」「電子定款を導入する」「資本金を1,000万円未満に抑える」といった工夫をすれば、会社設立の費用を大幅に節約することができます。
起業時の会社設立の費用を節約できれば、設立後の運転資金に余裕を持たせることができ、事業を安定させやすくなります。会社設立の費用をただの出費と考えるのではなく、戦略的に抑える方法を選ぶことが、成功する経営への第一歩です。
会社設立の費用だけでなく維持費も重要
会社を立ち上げる際には、まず会社設立の費用を準備しなければなりません。しかし、会社設立の費用を支払った後も、会社運営には継続的に「維持費(ランニングコスト)」が発生します。会社設立の費用だけに目を向けるのではなく、会社の存続に不可欠な維持費をしっかり理解し、設立後1年程度は安心して運営できるだけの資金を確保しておくことが大切です。
会社設立後に共通して発生する維持費
会社設立の費用をクリアした後、どの会社形態でも共通して発生する維持費があります。これらは会社設立の費用とは別に、毎年かかる固定的な維持費です。
会社設立後に共通して発生する維持費①
税金(住民税均等割)
会社運営を行う以上、必ず税金が発生します。黒字なら法人税や住民税が課され、赤字であっても「住民税均等割」という税金は必ず支払わなければなりません。
会社設立の費用に関する注意点

資本金1,000万円以下の会社では7万円、1,000万円を超える会社では18万円が毎年の維持費として必要です。これは会社設立の費用には含まれないため、別途準備が必要です。
会社設立後に共通して発生する維持費②
社会保険料
会社設立の費用を負担した後に必ず直面するのが社会保険料という維持費です。健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険への加入は義務であり、会社が従業員と折半して負担します。会社側の負担額は給与総額の約14.6%程度となり、会社設立の費用と同じくらい大きな支出となるケースも少なくありません。
会社設立後に共通して発生する維持費③
税理士など専門家への報酬
会社設立の費用を節約して自分で設立手続きを行う人もいますが、設立後は税務や会計業務が発生するため、多くの会社が税理士と顧問契約を結びます。税理士報酬は年間30万〜50万円程度が相場であり、会社設立の費用とは別に発生する維持費として考えておかなければなりません。

会社設立の費用と維持費に関する記事:「会社設立の費用はいくら?株式会社・合同会社立ち上げ時の違いも解説」
株式会社だけに必要な維持費
会社設立の費用は株式会社と合同会社で異なりますが、設立後に発生する維持費も会社形態によって違いがあります。株式会社のみで発生する維持費は次のとおりです。
株式会社だけに必要な維持費①
決算公告費用
株式会社は毎年の決算内容を公告する義務があり、これにかかる維持費が発生します。官報公告なら約6万円、新聞に掲載すると10万〜100万円の費用がかかる場合もあります。電子公告を選べば無料ですが、準備が必要です。
「会社設立の費用」編集部
会社設立の費用を節約しても、この維持費を負担しなければならない点は押さえておきましょう。
株式会社だけに必要な維持費②
役員変更登記費用
株式会社では役員の任期が決まっており、就任・退任・重任の際に登記手続きが必要です。この登記には司法書士への依頼費用も含めて3万〜6万円程度の維持費がかかります。合同会社には任期の定めがないため、この維持費は不要です。
株式会社だけに必要な維持費③
株主総会の開催費用
会社設立の費用と維持費に関するおすすめ記事

合同会社と株式会社の会社設立の費用違い、会社設立後の維持費については以下の記事も是非参考にしてください。
「会社設立の費用相場はいくら?株式会社と合同会社の違いを徹底比較」
株式会社は原則として年に1度、株主総会を開かなければなりません。会場費や飲食代、資料準備などに費用がかかり、これも維持費の一部です。規模によって費用は異なりますが、会社設立の費用には含まれない追加的な出費である点に注意が必要です。
会社形態ごとの維持費比較
会社設立の費用だけでなく、設立後の維持費を比較すると、株式会社は合同会社に比べて高くなる傾向があります。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社・合名会社・合資会社 |
|---|---|---|
| 住民税均等割 | 7万円~(資本金・従業員数により変動) | 7万円~(資本金・従業員数により変動) |
| 社会保険料 | 給与支払額の一定割合 | 給与支払額の一定割合 |
| 税理士報酬 | 年間30万~100万円 | 年間30万~100万円 |
| 決算公告費用 | 官報公告:約6万円 新聞掲載:10万~100万円 電子公告:無料 |
不要 |
| 役員変更登記費用 | 3万~6万円 | 不要 |
| 株主総会開催費用 | 会場費・飲食代・手土産代など(規模により変動) | 不要 |
会社設立の費用は登記費用や定款認証、資本金など初期費用に目が向きがちですが、実際には設立後にかかる維持費が経営に大きな影響を与えます。会社設立の費用だけを準備しても、維持費を考慮していなければ資金が不足し、事業が続けられなくなる可能性があります。
「会社設立の費用」編集部
会社設立の費用や維持費については以下のサイトも是非ご覧ください。
「株式会社の設立費用」
したがって、会社設立の費用と維持費の両方を見据えて資金計画を立てることが、安定した経営の第一歩となります。
まとめ:会社設立の費用相場
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社を立ち上げるときに避けて通れないのが「会社設立の費用」です。会社設立の費用は、株式会社を選ぶか合同会社を選ぶかによって大きく変わり、最低でも数十万円単位の金額が必要になります。株式会社の会社設立の費用は定款認証料や登録免許税を含めて約22万円以上が一般的で、資本金や専門家に依頼する費用を加えると30万~50万円に達することもあります。一方で、合同会社の会社設立の費用は10万円程度から始められ、株式会社に比べて大幅にコストを抑えることができます。
ただし、会社設立の費用は初期の登記や定款作成だけではありません。会社印鑑の作成や印鑑証明書の取得、資本金の払い込み、さらには会社設立後に発生する維持費も含めてトータルで考えることが大切です。会社設立の費用を安く抑えたとしても、設立後に発生する税金や社会保険料、専門家への顧問料などが重なれば、経営を圧迫する可能性もあります。したがって、会社設立の費用は「初期費用」と「ランニングコスト」の両方を意識して資金計画を立てる必要があります。
さらに、会社設立の費用を軽減するためには、補助金や助成金の活用も有効です。小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金、キャリアアップ助成金などを上手に利用すれば、会社設立の費用の一部を補填でき、設立後の事業運営にもプラスになります。返済義務のない補助金や助成金は、会社設立の費用を自己資金だけでまかなうよりも、起業を安定させる大きな助けになるでしょう。
会社設立の費用を正しく理解し、会社形態の違いによるメリット・デメリットを比較検討することは、これから起業する人にとって不可欠な準備です。株式会社で社会的信用度を重視するのか、合同会社で会社設立の費用を最小限に抑えるのか、自分の事業規模や将来の展望に合わせて判断することが重要です。
起業はゴールではなくスタートです。会社設立の費用を単なる出費として捉えるのではなく、将来の事業を安定させるための投資と考え、資金計画をしっかりと立てましょう。会社設立の費用を計画的に準備することで、事業運営に余裕を持ち、スムーズにスタートを切ることができます。

合わせて読みたい「freee会社設立の費用」に関するおすすめ記事

freee会社設立の費用は無料?会社設立で実際にかかる費用を紹介
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!