会社設立1年目に発生する税金とは?起業後に注意しておきたい税金についても解説!
カテゴリー:
公開日:2025年4月
更新日:2026年1月16日
会社設立1年目には、事業の立ち上げや売上確保に目を向ける一方で、税金に関する正確な知識と準備が不可欠です。多くの起業家が見落としがちですが、会社設立1年目から発生する税金には注意が必要です。税務署や自治体からの通知が届く前に、どの税金がいつ発生するのか、どのように支払うべきかを理解しておくことで、スムーズな経営スタートを切ることができます。
たとえば、法人税や地方法人税、法人住民税、法人事業税など、会社設立1年目から支払いが求められる税金は複数存在します。さらに、事業規模によっては消費税や印紙税といった初年度でも対象となる税金があるため、資本金や売上見込みに応じた税金対策が求められます。
また、会社設立1年目の税金には、資本金の金額や設立時期によって免除や軽減が受けられる税金もあります。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
税金制度を正しく理解し、税金負担を最小限に抑えることが、会社経営の安定に直結します。
この記事では、会社設立1年目に発生する主な税金の種類や、それぞれの納付期限、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。初年度に必要な税金の知識を整理し、税金トラブルを未然に防ぐために、ぜひ最後までご覧ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「会社設立時の借入方法」に関するおすすめ記事

会社設立時の借入方法を紹介!開業資金でおすすめの融資とは?
目次
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
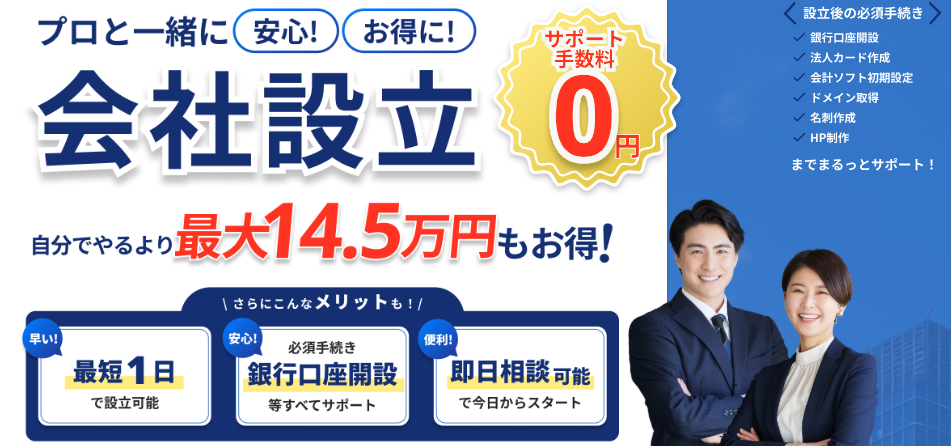
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
会社設立1年目に発生する税金の種類・納付先・時期とは

「会社設立1年目の税金」編集部
基本的に法人が支払う税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・消費税の5種類です。詳しい法人が支払う税金の種類についてはこちらの記事を参照ください。
会社設立1年目は、事業運営や顧客開拓に注力する時期ですが、それと同時に避けて通れないのが税金の支払いです。法人として活動を開始した瞬間から、さまざまな税金の対象となるため、会社設立1年目だからといって「税金はまだ関係ない」と油断していると、後から思わぬ負担やトラブルが生じてしまうこともあります。
会社設立1年目に支払う税金に関するおすすめ記事

会社設立1年目に支払う税金に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立1年目に支払う税金に関する参考記事:「法人1年目に支払うべき税金と注意点」
とくに、消費税や固定資産税以外の多くの税金は、会社設立1年目から納付義務が発生する可能性が高いため、早い段階での把握と準備が重要です。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
ここでは、会社設立1年目において企業が納付すべき主な税金の種類と納付スケジュールについて詳しく整理します。
会社設立1年目にかかる主な税金一覧
| 税金の種類 | 管轄・納付先 | 納付期限(原則) |
|---|---|---|
| 法人税 | 税務署 | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 地方法人税 | 税務署 | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 消費税 | 税務署 | 決算日の翌日から2ヶ月以内(課税業者の場合) |
| 印紙税 | 税務署(収入印紙で支払い) | 文書作成時に都度納付 |
| 法人住民税 | 都道府県・市区町村 | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 法人事業税 | 都道府県税事務所 | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 固定資産税 | 市区町村 | 年4回:4月末、7月末、12月末、翌年2月末 |
会社設立1年目に発生する税金①
法人税:利益が出れば会社設立1年目でも課税対象に
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人税は、会社の「所得(利益)」に対して課せられる基本的な税金です。利益が出た場合、たとえ会社設立1年目であっても納税義務が生じます。毎年の決算終了後2ヶ月以内に、税務署へ申告・納付する必要があります。赤字決算の場合は発生しませんが、黒字化した際には確実に対象となるため、準備は早めに行っておきましょう。
会社設立1年目に支払う税金に関するおすすめ記事

会社設立1年目に支払う税金に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立1年目に支払う税金に関する参考記事:「起業後に発生する税金」
会社設立1年目に発生する税金②
地方法人税:法人税に連動して発生する税金
地方法人税も、法人の所得をもとに算出される会社設立1年目から関係する税金の一つです。法人税の金額をベースに計算され、税務署へまとめて申告・納付します。実質的には法人税と一体で扱われるため、法人税の申告準備と同時に進めることが一般的です。
「会社設立後の役員報酬」編集部
会社設立後の役員報酬はいつから支払うべきなのかについては、以下のサイトも是非ご覧ください!
「 会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説 」
会社設立1年目に支払う税金に関する参考記事:「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
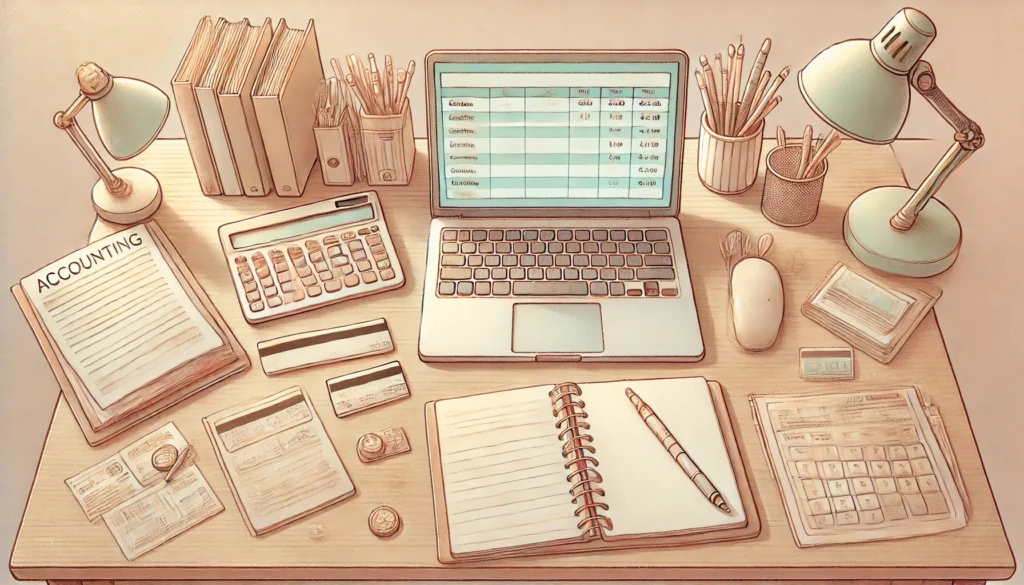
会社設立1年目に発生する税金③
消費税:1年目でも課税対象になるケースがある
「会社設立」編集部
会社設立(法人化)のメリットとデメリットに関しては、【法人化のメリット・デメリットとは?法人化の適切なタイミングについても解説!】の記事も是非ご覧ください。
原則として、課税売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。
会社設立1年目に支払う税金に関するポイント!

会社設立1年目では、前年度の売上がないため免税事業者となるケースが多いですが、インボイス制度の影響で、取引先から課税業者としての登録を求められるケースも増えています。
1年目から自発的に課税業者を選択する場合は、消費税の申告・納付が必要になります。

合わせて読みたい「会社設立で税金対策」に関するおすすめ記事

会社設立で税金対策をしよう!会社設立で節税する方法を紹介
会社設立1年目に発生する税金④
印紙税:契約書を作成した時点で必要になる税金
会社設立1年目に支払う税金に関するおすすめ記事

会社設立1年目に支払う税金に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
「法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較」
印紙税は、契約書や領収書、請負契約など、法律で定められた文書を作成した場合に課税される税金です。会社設立1年目でも、業務委託契約書や賃貸借契約書を交わす場面が多く発生するため、その都度、収入印紙を購入して支払う必要があります。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
印紙の金額は文書の内容や金額によって異なるため、事前の確認が不可欠です。
会社設立1年目に発生する税金⑤
法人住民税:赤字でも支払う必要がある税金

合わせて読みたい「会社設立時の登録免許税」に関するおすすめ記事
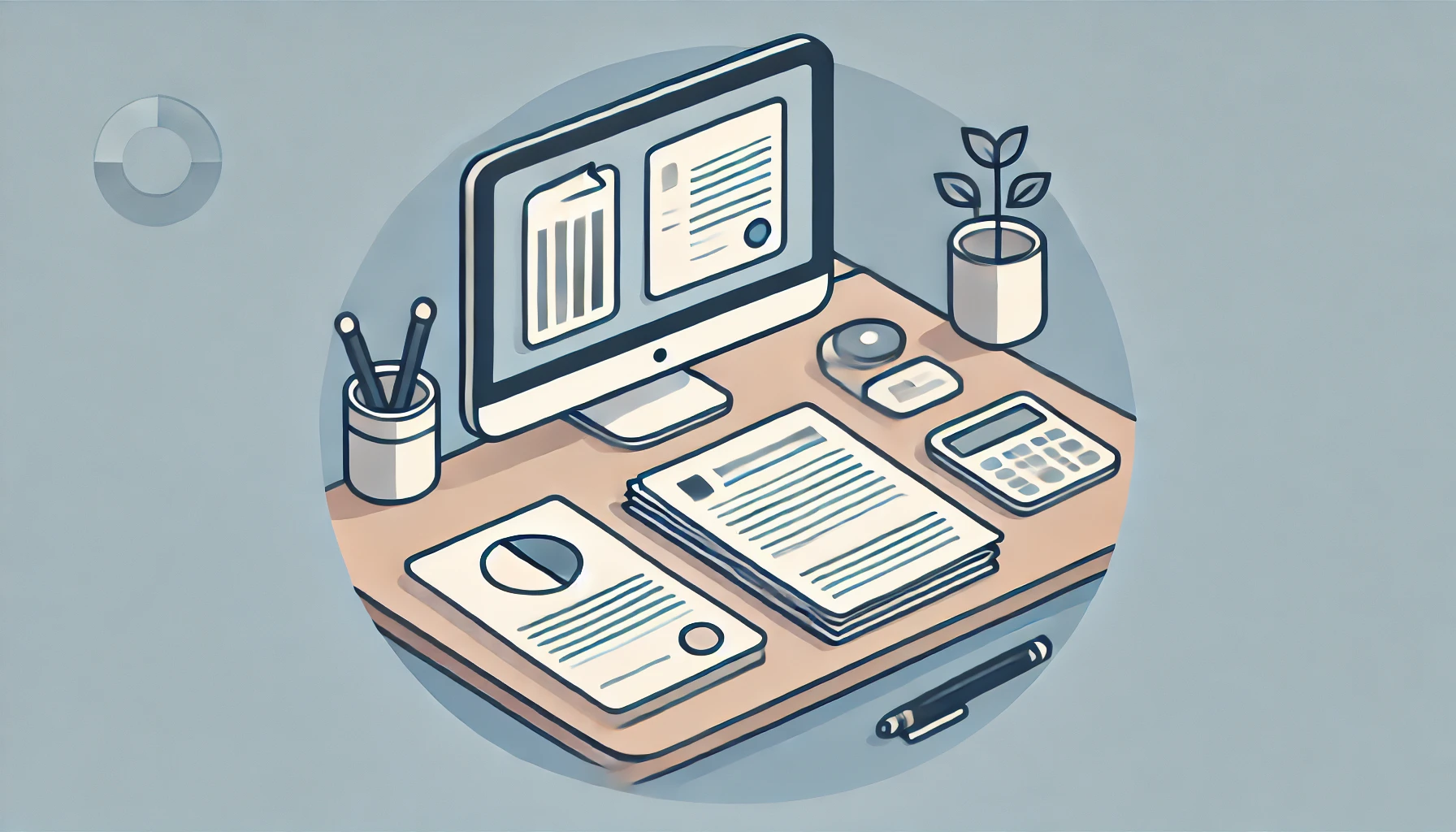
会社設立時の登録免許税とは?登録免許税の納付方法や半額になる方法も紹介!
法人住民税は、法人が本店所在地の自治体に支払う税金(地方税)です。所得に応じて課税される「法人税割」と、赤字でも発生する「均等割」の2種類で構成されており、会社設立1年目で利益が出ていなくても、最低限の均等割は必ず納付しなければなりません。自治体によって税金の税率や最低税金額が異なる点も押さえておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立1年目に発生する税金⑤-1
法人税割とは
法人税割は、国に納める法人税額をもとに計算される税金(地方税)です。会社設立1年目でも利益が出て法人税が発生すれば、その金額に応じて法人税割も支払う必要があります。たとえば、東京都の場合は、資本金の金額や法人税額に応じて、適用される税率(標準税率または超過税率)が変わります。

合わせて読みたい「 起業の成功率」に関するおすすめ記事

起業の成功率はどれくらい?5年後10年後の確率と成功する秘訣を紹介!
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
会社設立1年目に支払う税金に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
会社設立1年目に支払う税金に関する参考記事:「法人にかかる税金とは?法人設立1期目の税金の注意点について解説!」
会社設立1年目に支払う税金に関するポイント!

どの税率が適用されるかは、まず資本金の額を確認したうえで、事業規模や収益によって判断されるため、会社設立1年目の段階から税金のシミュレーションしておくことが大切です。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
法人税割の基本的な計算方法は以下の通りです。
法人税額(税額控除前) × 地方税率(例:標準税率や超過税率)
法人税が発生する=法人税割も発生する構造になっているため、会社設立1年目から黒字を見込んでいる法人は、法人税割の納税も念頭に置いておくべきです。
税金に関する参考記事:「寡婦控除とは?適用条件や申告方法、ひとり親控除との違いについても解説!」

会社設立1年目に発生する税金⑤-2
均等割とは
一方、均等割は法人の利益とは関係なく発生する税金です。会社設立1年目で赤字決算となった場合でも、事務所の所在自治体や資本金の額、従業員数などによって一定額を納付しなければなりません。
会社設立1年目に支払う税金に関する気をつけておきたい注意点

たとえば、東京都では主たる事務所がある区市町村によって、均等割の金額が異なります。また、資本金が1,000万円を超えるかどうか、従業員が50人を超えるかどうかなども、税額に影響します。

合わせて読みたい「インボイス 2割特例 いつまで」に関するおすすめ記事
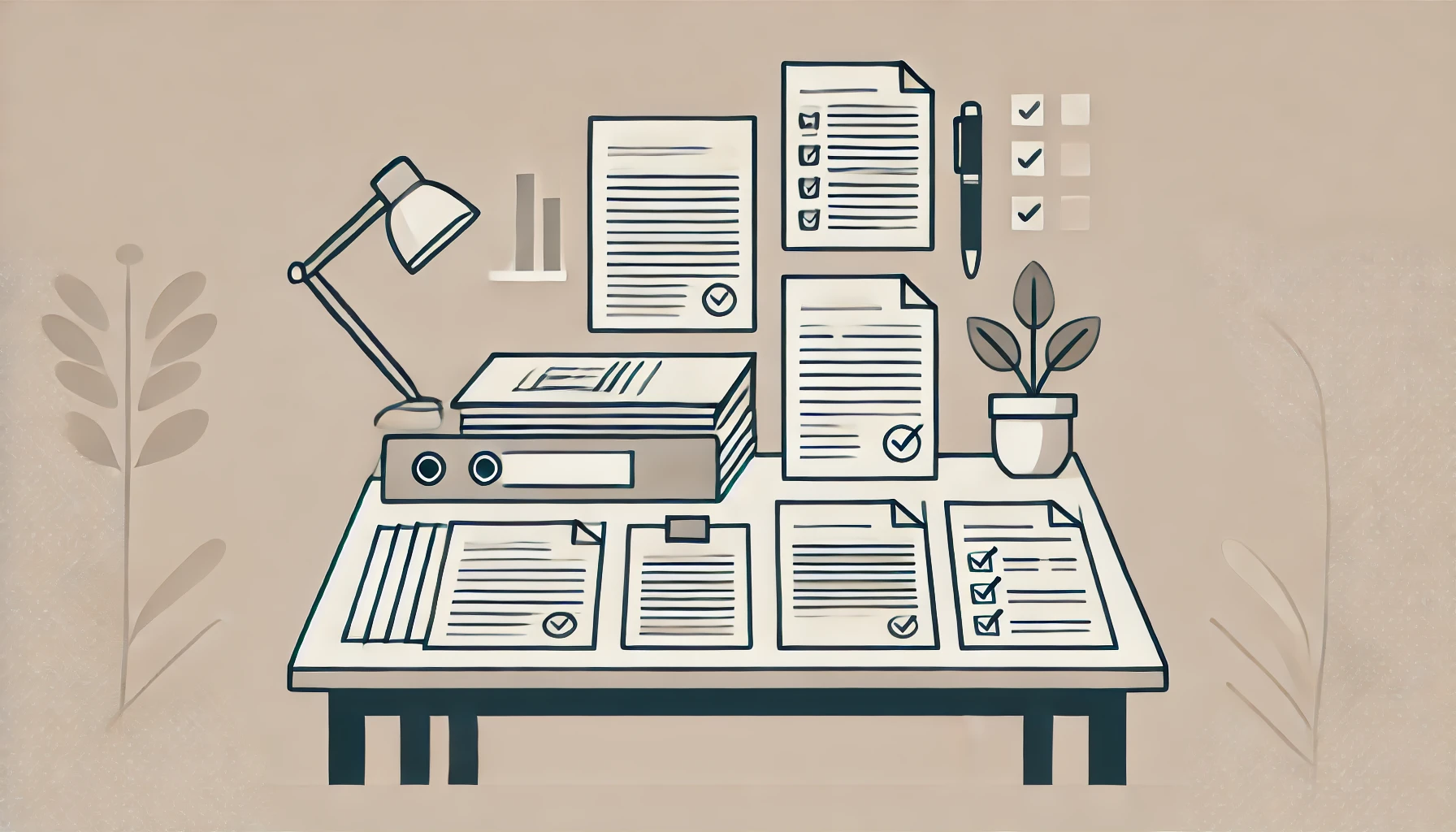
インボイスの2割特例はいつまで?2割特例の計算方法も解説!
このように、法人住民税は会社設立1年目から必ず関係してくる税金であり、法人税割は利益が出た場合、均等割は赤字でも発生するという点をしっかり把握しておくことが、初年度の資金計画において重要です。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
会社設立1年目に支払う税金に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
「【税理士監修】起業1年目で消費税の還付は受けられる?分かりやすく解説」
会社設立1年目に発生する税金⑥
法人事業税:利益に応じて負担が生じる
法人事業税は、法人の所得に応じて都道府県に支払う地方税であり、法人税と似ていますが別物です。会社設立1年目でも、利益が出れば法人事業税の納税対象となります。こちらも、決算後2ヶ月以内に申告・納付する必要があります。
会社設立の関連記事:「会社の作り方を徹底解説!必要な手続きと費用について」
【参考】法人税・法人住民税・法人事業税の違いまとめ
| 種類 | 納付先 | 納付手続き時期 | 主な違いと特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人税 | 国税 | 税務署(国) | 決算後2か月以内 | 国税として税務署に申告 予定納税あり e-Tax対応 |
| 法人事業税 | 地方税 | 都道府県 | 決算後2か月以内 | 地方税 申告様式は第六号 課税方式に種類あり eLTAX対応 |
| 法人住民税 | 地方税 | 都道府県および市町村の双方 | 決算後2か月以内 | 二重納付先 均等割が発生し赤字でも納付義務あり eLTAX対応 |

合わせて読みたい「会社設立に必要な届出」に関するおすすめ記事

会社設立に必要な届出を詳細解説!会社設立後の手続きと届出書を紹介
会社設立1年目に発生する税金⑦
固定資産税:資産を保有している法人に課税
土地や建物、設備などの固定資産を所有している場合は、固定資産税の支払いが必要です。市区町村が課税主体となり、年4回の納期(4月、7月、12月、翌年2月)で納付します。
たとえ会社設立1年目でも、資産を保有していれば課税対象となるため、物件取得時には税負担も計算に入れておくことが重要です。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
会社設立1年目に支払う税金に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
会社設立1年目に支払う税金に関するおすすめ記事
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント
会社設立1年目は、事業の立ち上げや営業活動に集中したい時期ですが、同時に最も多くの税金の基礎知識と対応が求められるタイミングでもあります。
法人を設立した初年度から、避けて通れない税金や会計処理が多く発生するため、あらかじめ税金の種類や処理方法を把握しておくことが、無駄な支出やペナルティを防ぐ第一歩です。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
ここでは、会社設立1年目に必ず押さえておくべき代表的な税金とその注意点について、詳しく解説します。

合わせて読みたい「合同会社の設立に必要な書類」に関するおすすめ記事

合同会社設立の必要書類とは?合同会社設立の必要書類を詳しく解説!
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント①
創立費とその税務処理
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイントの1つ目は創立費とその税務処理です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

会社設立前に発生する費用は「創立費」として分類され、会社設立1年目の税金処理でも重要な位置を占めます。具体的には、以下のような支出が創立費として計上可能です。
- 定款認証手数料
- 登録免許税(登記に必要な税金)
- 司法書士や行政書士に依頼した報酬
- 法人印(実印、角印、銀行印など)の作成費
会社設立1年目に支払う税金に関するポイント!

これらは繰延資産として処理し、会社設立1年目から任意のタイミングで償却することができ、税金対策にも有効です。
「会社設立日」編集部
間違えやすい会社設立日と登記日の違いについては以下の記事も是非ご覧ください。
会社設立日と登記日の違いに関する参考記事:「会社の設立日は登記日と同じ?設立に関する日付の違いや注意点を解説!」
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント②
開業費も繰延資産として処理可能
「税金を滞納したらどうなる?」編集部
法人税、所得税や消費税を滞納した場合どうなるのかに関しては「 税金を滞納したらどうなる?リスクと対処法も解説! 」の記事が参考になるでしょう。
会社設立後、事業開始までに発生する費用は「開業費」として取り扱われます。こちらも税金上は繰延資産に該当し、会社設立1年目から任意に償却処理が可能です。

合わせて読みたい「法人設立ワンストップサービス」に関するおすすめ記事

法人設立ワンストップサービスとは?メリットや注意点を解説!
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
例としては以下のような費用が開業費になります。
- 許認可取得の手続き費用
- 開業準備中の打ち合わせや挨拶回りの交際費
- 広告宣伝費やウェブサイト制作費
- 名刺、パソコン、什器備品などの購入費
- 勉強会、起業セミナーへの参加費
- 各種消耗品費
会社設立1年目に支払う税金に関するおすすめ記事

会社設立1年目に支払う税金に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
「会社を設立すると消費税が免税される!?免税の条件とは?」
こうした費用は会社設立1年目のスタートアップ期に集中しやすいため、税金の観点からも正確な仕訳と管理が求められます。
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント③
中小法人向けの軽減税率の適用
「会社設立(法人化)を検討する売上の目安」編集部
会社設立(法人化)を検討すべき売り上げの目安に関しては、以下のサイトも是非ご覧ください。
「法人化を検討すべき売上の目安は?売上以外の判断目安についても解説!」
会社設立1年目の中小企業で、資本金が1億円以下である場合には、「法人税の軽減税率制度」が利用できます。通常23.2%の法人税率が、所得800万円以下の部分に限り15%へと軽減される制度です。


合わせて読みたい「法人番号と会社法人等番号の違い」に関するおすすめ記事
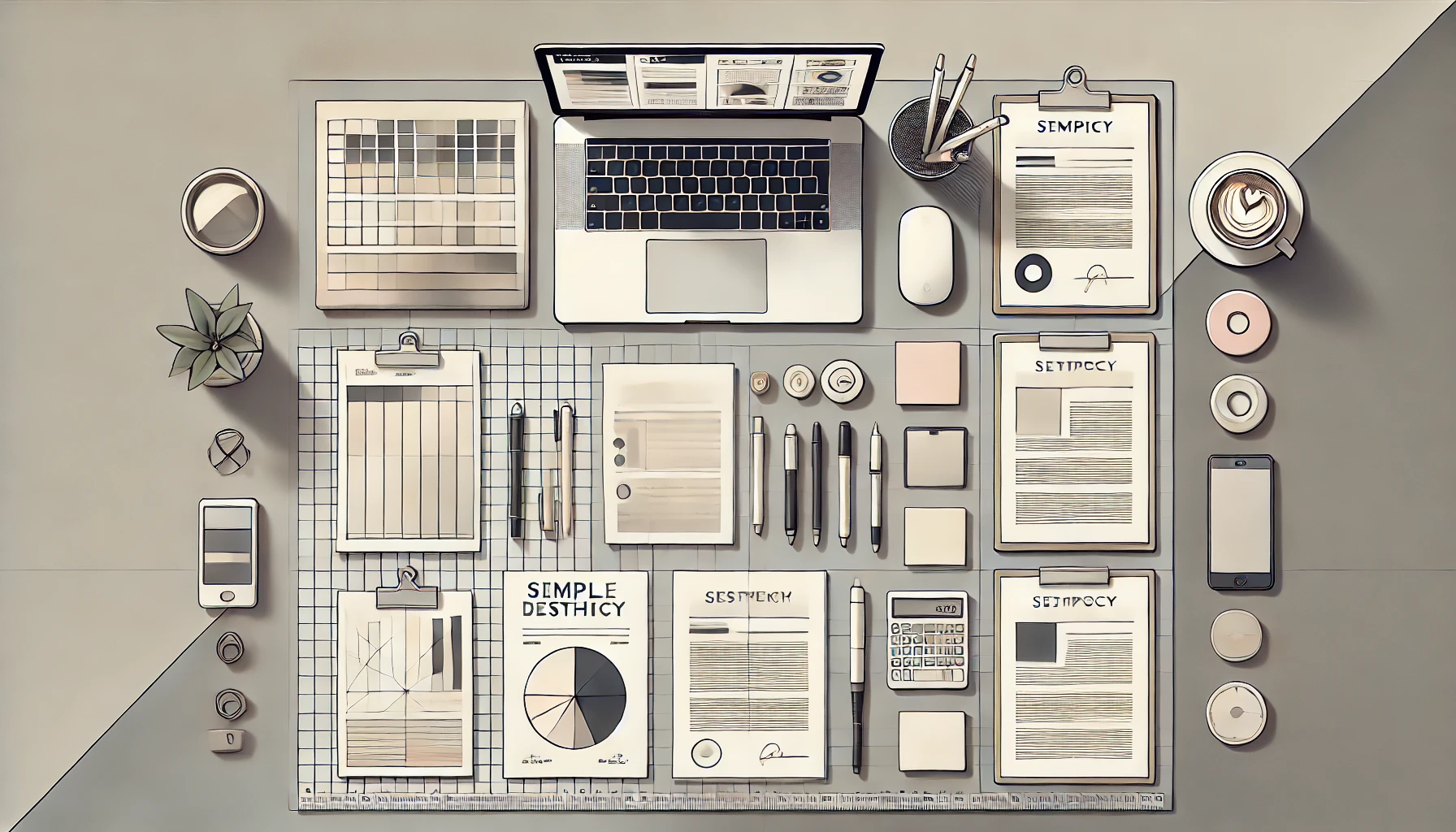
法人番号と会社法人等番号の違いとは?調べ方や使い道も紹介!
会社設立1年目に支払う税金に関する参考記事:「会社を作ると支払うことになる税金一覧」
ただし、会社設立1年目で会計期間が1年未満の場合は、この800万円の枠を月割で按分する必要があります(※1か月未満は切り上げ)。この軽減制度は会社設立1年目から適用可能であり、節税の大きなチャンスとなります。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント④
交際費の損金算入限度額にも注意
会社設立1年目から発生する可能性がある「接待交際費」も、税金処理に影響する項目です。
会社設立1年目に支払う税金に関するポイント!

中小法人の場合は、交際費として年間800万円までを損金(税務上の経費)として計上することができます。

合わせて読みたい「税理士に依頼する時の費用」に関するおすすめ記事

会社設立後に必要な税務署の届出とは?税務署での手続きも詳しく解説!
ただし、会社設立1年目で事業年度が12ヶ月に満たない場合は、この800万円の枠も月数に応じて按分が必要です。これにより、法人税の課税所得を抑える効果が得られるため、適切に管理すべき税金処理のひとつです。
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント⑤
少額減価償却資産の特例制度
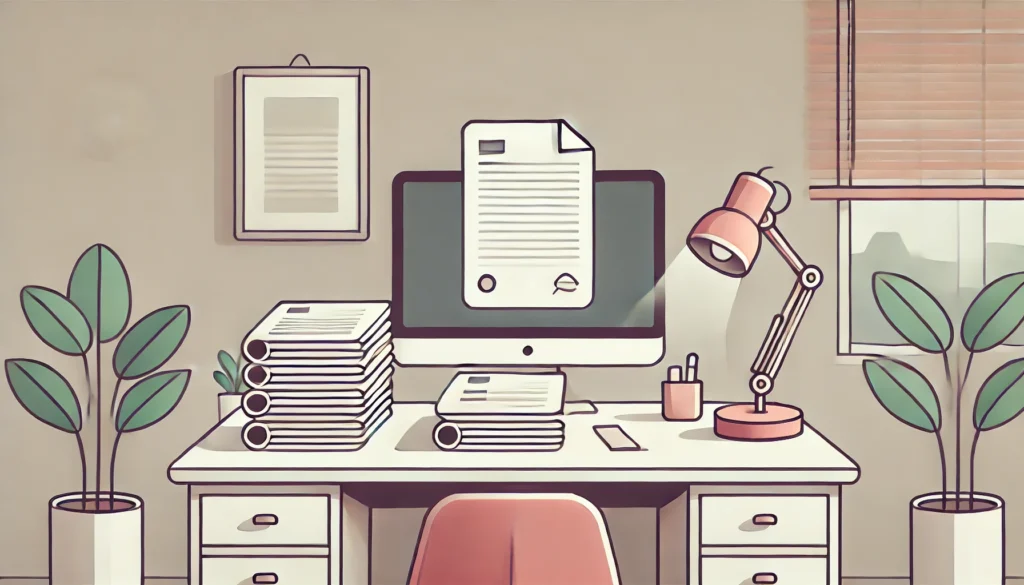
中小法人が30万円未満の固定資産を購入した場合は、減価償却せずにその年に全額損金算入できる特例制度があります。会社設立1年目からこの制度の利用は可能ですが、年間の合計額が300万円までという上限があります。これも会計期間が12ヶ月未満の場合、税金上は月割で計算します。

合わせて読みたい「税務署から電話がくる理由」に関するおすすめ記事

税務署から電話がきた理由とは?対応方法や相談する際のポイントも解説!
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント⑥
寄付金の損金扱いとその制限
会社設立1年目に、社会貢献活動の一環として寄付金を支出した場合でも、全額が損金になるわけではありません。国や地方公共団体への寄付は全額損金にできますが、一般寄付金は、資本金や所得に基づいて算出される損金算入限度額までしか経費化できません。これも税金計算の大切なポイントです。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
会社設立1年目に支払う税金に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
「会社設立1年目の税金の盲点とは」
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント⑦
個人事業から引き継いだ資産の処理
個人事業から法人成りをした場合、取得済みの減価償却資産を法人に引き継ぐことがあります。この場合、法人側で「中古資産」として計上し、耐用年数を見積もるか「簡便法」で償却期間を算出して減価償却費を計上します。
会社設立1年目に支払う税金に関する気をつけておきたい注意点

この処理方法は会社設立1年目における税金処理のミスが起きやすい箇所であり、資産価値と使用可能期間を明確にし、税務署からの指摘を避ける工夫が必要です。
会社設立1年目に支払う税金に関するおすすめ記事

会社設立1年目に支払う税金に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
「起業1年目でかかる税金とその対策方法とは?」
会社設立1年目に特に注意したい税金のポイント⑦-1
減価償却費の月割計算も重要
会社設立1年目が12ヶ月未満となる場合は、資産の減価償却費も月割計算をする必要があります。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
定率法であれ定額法であれ、償却費は以下の式で算出されます。
償却費 = 資産価格 × 償却率 ×(事業年度の月数 ÷ 12)
これにより、会社設立1年目の事業年度が10ヶ月であれば、全体の10/12分だけ減価償却費が計上されることになります。税金に直結する部分のため、正確な月数の把握と計算が重要です。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
会社設立1年目における消費税免除の条件と税金対策のポイント
会社設立1年目には、様々な手続きや準備に加え、多くの税金に関する判断が求められます。なかでも、消費税の納税義務が発生するかどうかは、会社設立直後の資金繰りや経営に大きな影響を与える重要なテーマです。
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
会社設立1年目に支払う税金に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
会社設立1年目に支払う税金に関する参考記事:「起業家必見!起業前から会社設立後、経営を続けるうえで知っておくべき税金の種類と納税時期を徹底解説!」
通常、会社設立1年目の法人が消費税の納税義務を免除される条件としては、「資本金が1,000万円未満であること」が挙げられます。つまり、資本金を1,000万円未満に設定していれば、会社設立1年目は消費税の税金負担が発生しない、いわゆる「免税事業者」として扱われます。

合わせて読みたい「法人が納める消費税」に関するおすすめ記事
法人が納める消費税について解説! 税理士のサポートを受けるメリットも紹介

会社設立1年目に支払う税金に関するポイント!

会社設立1年目の税金の中でも消費税は特に重要な項目であり、設立時点での資本金の額によって、税金の負担が大きく異なります。
会社設立1年目における消費税免除の条件と税金対策①
資本金が1,000万円以上だと会社設立1年目でも消費税の納税義務あり
会社設立1年目であっても、資本金が1,000万円以上となる場合は、初年度から消費税の納税義務が発生します。売上の大小に関係なく、「資本金が1,000万円以上である」という事実だけで、会社設立1年目に消費税という税金を支払う必要があるのです。

合わせて読みたい「消費税の申告義務」に関するおすすめ記事
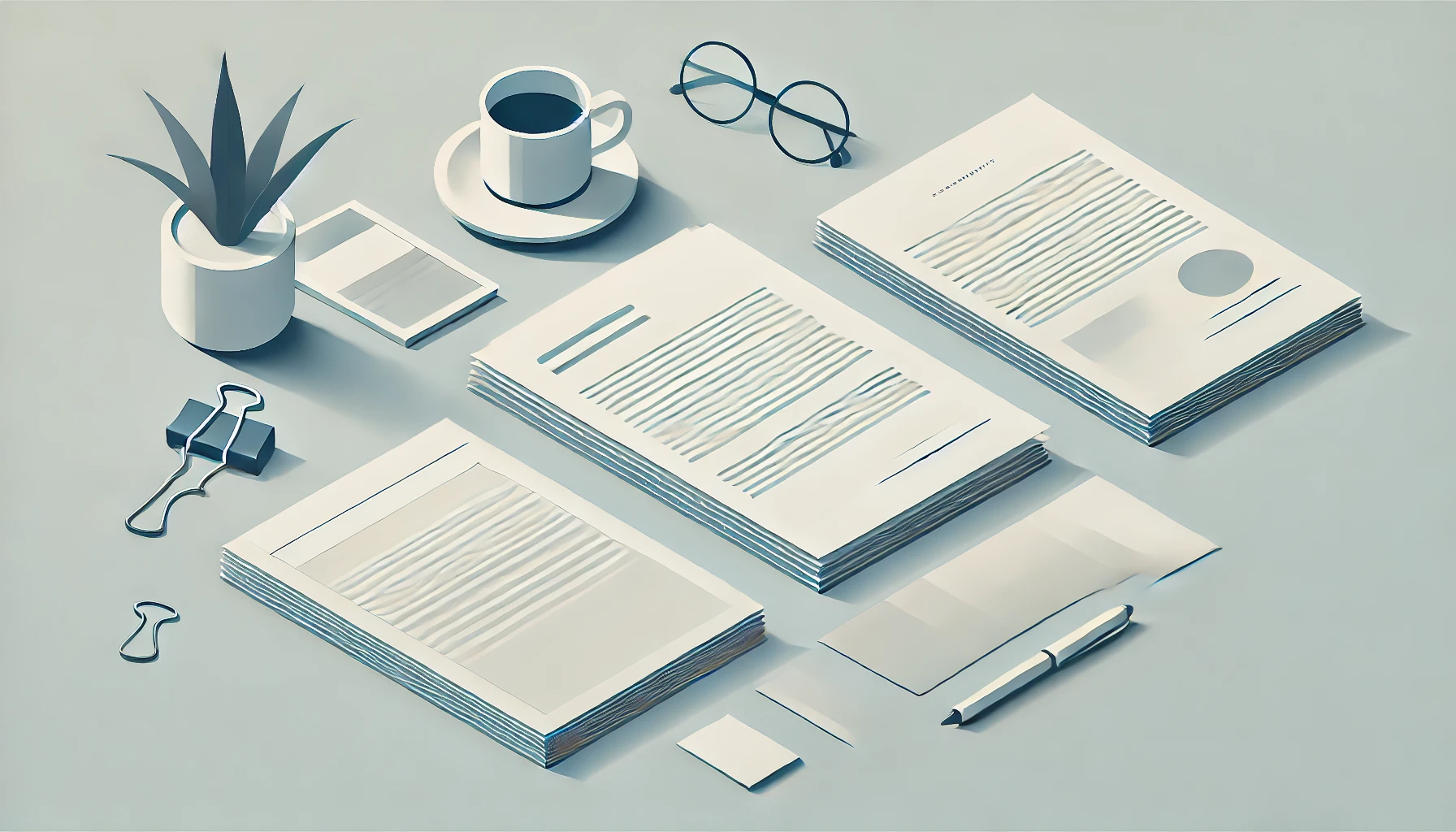
消費税申告義務の対象となる条件とは?計算方法や課税事業者と免税事業者の違いも解説!
「会社設立1年目に支払う税金」編集部
消費税申告の対象者や消費税の計算方法は非常に複雑なので早めに専門家に相談することをおすすめします。
会社設立1年目に支払う税金に関する参考記事:「売上高が1000万円超えたり超えなかったりする事業者の消費税はどうなる?納税義務のポイントを徹底解説!」


合わせて読みたい「株式会社を自分で設立する方法」に関するおすすめ記事

株式会社の設立は自分でできる?自分で株式会社を設立する際のポイントや設立手続きを解説!
設立後すぐに大きな資金調達を予定している場合や、最初から高額な資本金を設定しようと考えている場合には、この税金上のルールを事前に理解しておくことが、無駄な税金支出を防ぐカギとなります。
会社設立1年目における消費税免除の条件と税金対策②
資本準備金を活用して税金の負担を回避
会社設立1年目の税金対策として有効なのが、「資本準備金」の制度を利用する方法です。会社法では、出資金のうち2分の1までは資本金に計上せず、「資本準備金」として処理することが認められています。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
たとえば、1,500万円の資金を用意して会社を設立する場合、その全額を資本金にしてしまうと、会社設立1年目から消費税という税金の納付が必須になります。しかし、750万円を資本金、残りの750万円を資本準備金として処理すれば、資本金が1,000万円未満となり、消費税の納税義務が免除される可能性が高くなります。
会社設立1年目に支払う税金に関するおすすめ記事

会社設立1年目に支払う税金に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立1年目に支払う税金に関する参考記事:「会社設立の際に気にかけておきたい、会社にかかる税金のまとめ」
このように、資本金と資本準備金の配分を調整することで、会社設立1年目にかかる税金の負担を大きく抑えることが可能です。
会社設立1年目における消費税免除の条件と税金対策③
役員借入金を活用して資本金を調整する方法
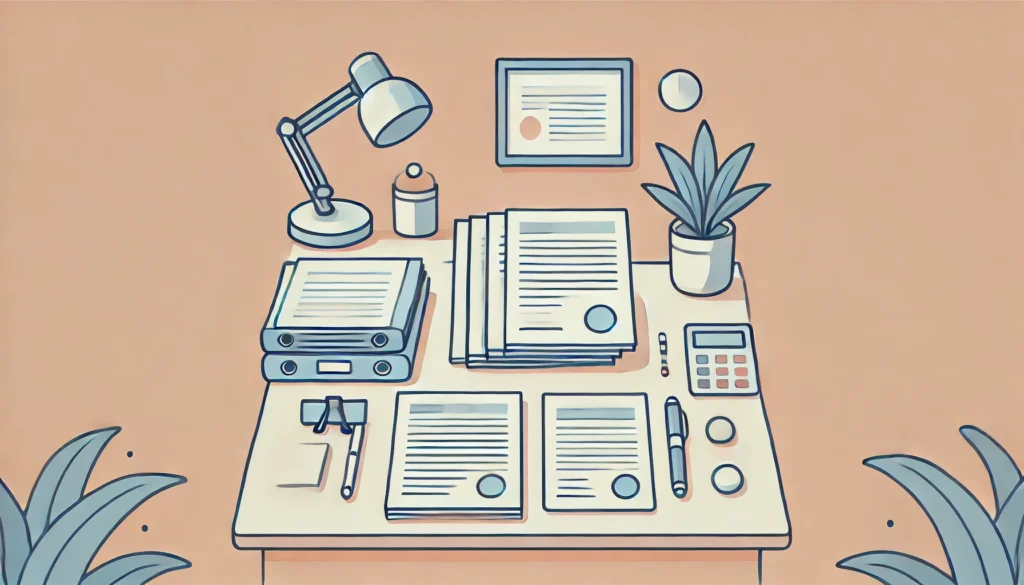
さらに、会社設立1年目の消費税対策として「役員借入金」の活用も有効です。たとえば、起業時に1,200万円の自己資金がある場合、そのうち800万円を資本金、残りを会社への「役員借入金」として処理することで、資本金を1,000万円未満に抑えることができ、会社設立1年目の税金(消費税)を免除される可能性が出てきます。
会社設立1年目に支払う税金に関するポイント!

役員借入金は会社の負債として扱われるため、将来的に返済が必要ではありますが、初年度の資金繰りや税金の負担軽減という意味では非常に効果的な手段です。
個人事業主が起業1年目で活用できる税金の控除制度
起業して1年目の個人事業主にとって、税金負担を少しでも抑えることは経営を安定させるための重要なポイントです。そこで活用したいのが、個人事業主が使える各種控除制度。適用できる制度を正しく理解し、確実に申告すれば、所得税の節税にもつながります。
「起業1年目に発生する税金の種類」編集部
特に1年目は見落としがちな項目も多いため、しっかりとチェックしておきましょう。
起業1年目の税金に関する参考記事:「起業や事業開始後に発生する税金は?使える控除制度も解説」
個人事業主が起業1年目で活用できる税金の控除制度①
青色申告特別控除
起業後に青色申告を選択し、帳簿を複式簿記で正しく記帳するなど、一定の要件を満たすことで、最大65万円または55万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
この控除は所得から直接差し引くことができるため、課税対象の金額が減り、1年目から税金の負担を軽減できます。なお、この制度を利用するには、「青色申告承認申請書」を、適用を希望する年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
青色申告はメリットが多いため、会社設立をしたら必ず提出するようにしておきましょう!

合わせて読みたい「一人で起業できる仕事」に関するおすすめ記事

1人で起業できる仕事とは?おすすめのビジネスモデルや一人で起業する方法を解説
個人事業主が起業1年目で活用できる税金の控除制度②
事業主控除
個人事業税の対象となる業種でも、年間の事業所得が290万円以下であれば税金はかかりません。これは一律290万円の事業主控除が認められているからです。
起業1年目は売上がまだ安定していないケースも多いため、この事業主控除により個人事業税がゼロになる可能性もあります。該当する業種に該当している場合でも、課税の判断にはこの控除が大きく影響します。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
まとめ|会社設立1年目に発生する税金とは
会社設立1年目は、ビジネスの基盤を築く大切な時期であると同時に、税金に関する重要な知識と対応が求められる時期でもあります。会社設立1年目には、法人税や法人住民税、法人事業税、印紙税、地方法人税、消費税、固定資産税など、さまざまな税金の支払い義務が発生する可能性があります。これらの税金を正しく理解せずに放置すると、支払い遅延や追徴課税といったリスクを招くこともあるため、注意が必要です。
特に、会社設立1年目の税金対策で重要なのが消費税です。資本金が1,000万円未満であれば原則として1年目の消費税は免除されますが、条件によっては1年目から消費税の納税が必要となるケースもあります。また、創立費・開業費などの処理、減価償却、交際費の損金算入、税金の特例措置など、会社設立1年目には特有の税金処理ルールが複数存在します。
このように、会社設立1年目は事業運営だけでなく税金面でも非常に多くの判断と対応が求められるフェーズです。会社設立後すぐの段階で、どの税金がいつ、どこへ、どのように支払う必要があるかを明確にし、計画的に対応することが、資金繰りや経営安定につながります。
少しでも税金に不安がある場合は、会社設立1年目の段階で、早めに税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。会社設立1年目の税金対策を万全にしておくことが、今後の事業の成長と健全な経営を支える礎となるのです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「青色申告の承認申請書の書き方」に関するおすすめ記事
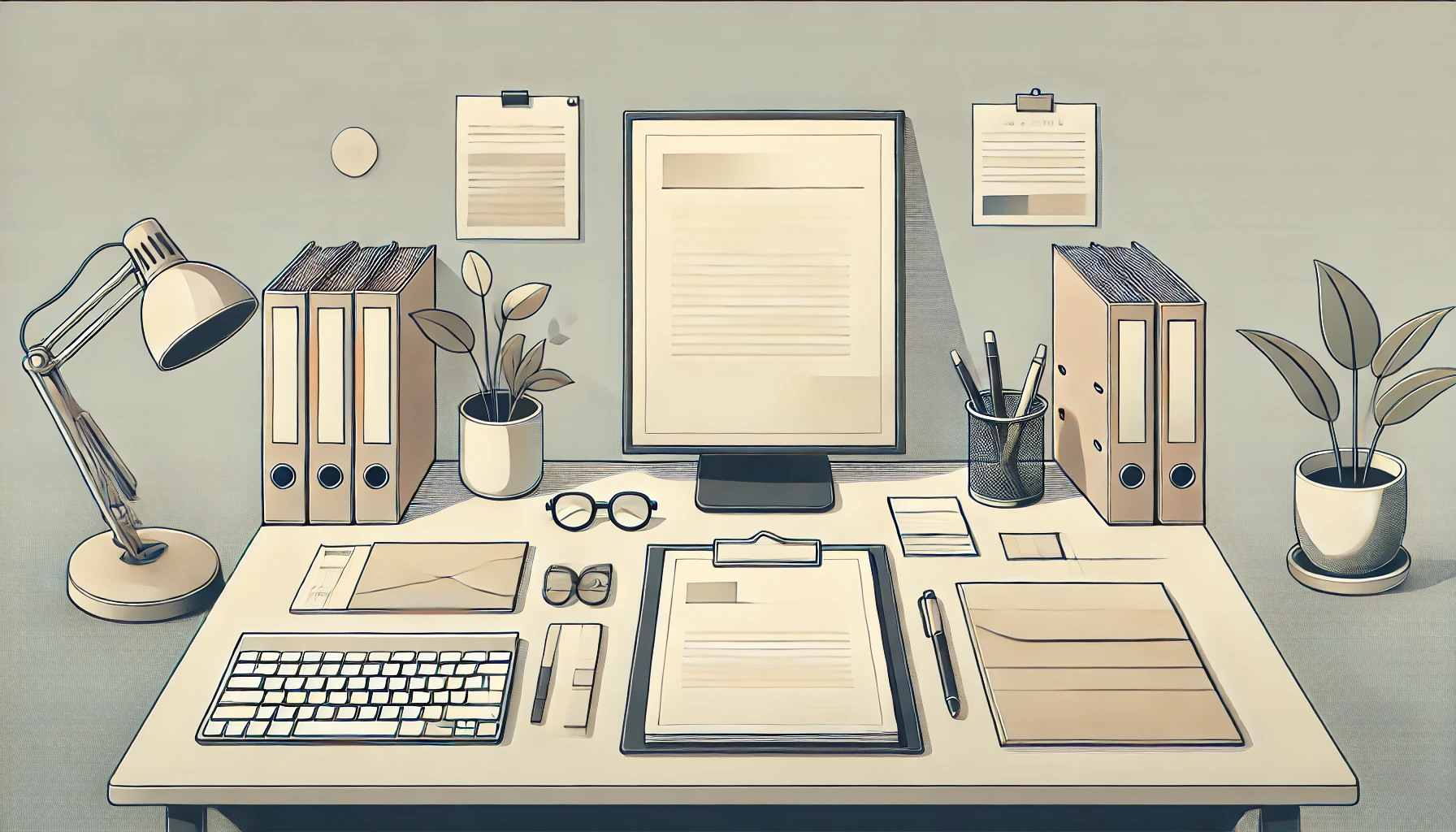
法人の青色申告の承認申請書とは?青色申告の承認申請書の書き方や記載例を詳しく解説!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日













SoVaをもっと知りたい!