法人保険で節税できる?メリット・デメリットや損金算入について解説
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2025年11月4日
法人保険で節税できるのか?という疑問は、多くの経営者や財務担当者が一度は抱えるテーマです。法人保険を導入すれば節税につながるという話を耳にしても、「本当に節税効果があるの?」「法人保険のどこまでが損金になるの?」「今の税制でも法人保険による節税は通用するのか?」など、不明点が多いのが実情ではないでしょうか。
実際に、法人保険は法人税の節税対策として利用されることの多い制度ですが、2019年の税制改正以降、法人保険による節税スキームの制限が厳しくなったこともあり、節税効果を得るには制度への深い理解が必要です。節税目的で法人保険に加入するには、保険料の損金算入割合や解約返戻率の仕組み、保険金の益金算入のルールなどを正確に把握することが重要となります。
本記事では、法人保険を活用した節税の基本的な仕組みから、法人保険による節税の具体的なメリット、法人保険が節税にならないケース、法人保険における損金算入のルール、そして節税目的で法人保険を導入する際のデメリットや注意点まで、徹底的に詳しく解説します。法人保険で節税したいと考えている方や、法人保険の節税効果を最大化したいと考えている経営者の方にとって必見の内容です。
「法人保険の節税効果」編集部
節税の手段として法人保険を正しく活用するために、この記事を通じて「節税できる法人保険」の本質を理解し、自社に最適な法人保険の選び方と節税戦略を明確にしていきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
創業融資が受けられるか、今すぐチェック!
簡単シミュレーションで融資額を診断

画像引用:「創業融資額診断シミュレーション」
「創業融資を受けたいけど、自分は通るの?」
「どれくらいの金額を借りられるか知りたい!」
そんな疑問をお持ちの方は、「創業融資シミュレーション」がおすすめです!
✔ アンケートに答えるだけで、融資額&審査通過率がすぐに分かる!
✔ 無料で何度でも気軽にシミュレーション可能
✔ 創業期に融資を検討している方に最適
「申し込む前に、どれくらい借りられるのか知りたい…」そんな方は、まずはシミュレーションで融資の可能性をチェックしましょう!
※シミュレーション結果をもとに専門家への無料相談も可能です

法人保険とは?
法人保険とは、会社が契約者となって加入する保険のことで、経営上のリスク管理や従業員の福利厚生、そして節税対策としても活用される重要な手段です。個人の保険とは異なり、法人の資金を活用して保険契約を行うため、保険料の一部または全部を経費(損金)として処理できることが大きな魅力です。
法人保険は、保険法上の分類により以下の3つのカテゴリーに分けられます。
【法人保険の主な3種類とその活用目的】
| 法人保険の分類 | 主な目的・特徴 | 代表的な保険商品 |
|---|---|---|
| 生命保険 (第一分野) |
経営者や役員、従業員の万一の死亡や退職に備える法人保険。 事業承継対策や退職金準備、福利厚生の充実にも利用可能。 契約形態や受取人の設定次第では、節税効果も期待できる。 |
養老保険 定期保険 収入保障保険 |
| 損害保険 (第二分野) |
事業活動に伴う物的損害や賠償リスクに備える法人保険。 建物・設備の火災や事故、情報漏洩、顧客への損害賠償など幅広いリスクをカバー。 |
火災保険 企業財産保険 PL保険 個人情報漏洩保険 施設賠償責任保険 |
| 第三分野の保険 | 病気やケガなど、就業不能状態への備えに特化した法人保険。 経営者や従業員の医療リスクをカバーし、企業の安心経営を支える。 |
医療保険 がん保険 介護保険 所得補償保険 |
これらの法人向け保険は、保険料を単なる経費として処理するだけでなく、キャッシュフロー調整や長期的な資金準備、さらには節税の手段としても有効です。
法人保険の節税効果に関するおすすめ記事

法人保険の節税効果や、法人保険のメリットとデメリットについては以下の記事も是非参考にしてください。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「法人保険は節税にならない?損金算入のルールや加入するメリット・デメリットについて紹介」
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人保険のタイプ別の違い|掛け捨て型と積立型、節税効果にも差が出る?

法人保険には「掛け捨てタイプ」と「積立タイプ」の2つが存在します。それぞれ保険の機能と節税の効果に違いがあるため、導入前にしっかりと理解しておくことが大切です。
| タイプ | 貯蓄性 | 解約返戻金 | 節税の視点 |
|---|---|---|---|
| 掛け捨て型 | なし | 基本的にゼロ | 保険料全額を損金にできるケースがあり、 短期的な節税に向いている |
| 積立型 | あり | 一定期間後に受け取り可 | 長期的な資産形成と節税を両立。 退職金準備や事業承継資金の形成にも有用。 |
たとえば、養老保険や長期定期保険の一部プランは、保険期間満了時や中途解約時に解約返戻金を受け取れるため、将来の資金準備として活用可能です。また、一定の保険設計を行えば、法人税の軽減にもつながる仕組みになっています。
法人保険の節税効果に関するおすすめ記事

法人保険の節税効果や、法人保険のメリットとデメリットについては以下の記事も是非参考にしてください。
「法人保険の節税効果─正しい税務メリットと損金シミュレーション」
法人保険を導入することで、経営リスクの備えと同時に節税効果が得られるのは、企業にとって非常に大きなメリットです。万一の際に会社の資金繰りを守る役割を果たすだけでなく、保険の設計次第では退職金や事業承継資金の積立にも活用できます。
法人保険の節税効果に関する注意点

法人保険による節税は、税務上の取り扱いルールや改正にも影響を受けやすいため、導入にあたっては税理士や保険の専門家のアドバイスを受けることが欠かせません。
法人保険は単なる保険ではなく、節税戦略の一環として企業経営に活かせる有力な手段です。自社に最適なプランを見極めて、税負担を抑えながらリスクマネジメントを強化していきましょう。
法人保険に節税効果|2019年の税制改正以降の実態
「法人保険=節税」というイメージを持っている経営者の方は今も少なくありません。実際、かつては法人が加入する保険を活用することで、大きな節税効果が得られる時代がありました。しかし、現在ではその仕組みに大きな変化が生じています。
特に2019年の税制改正により、法人保険を利用した節税スキームは大幅に制限され、今では安易に節税目的だけで法人保険に加入することがリスクとなるケースもあります。
「法人保険の節税効果」編集部
ここでは、法人保険における節税の実態を、現在の制度に即して詳しく解説します。
税制改正以前の法人保険には高い節税効果があった
2019年の改正が行われる前は、法人保険の保険料を全額または一部を損金扱いとして計上することが認められていました。法人が契約者となり、解約返戻金付きの高返戻率商品に加入することで、保険料の損金算入を利用した節税が可能でした。
さらに、契約から数年後に保険を解約すれば、多くの場合で払い込んだ保険料と同等、もしくはそれ以上の解約返戻金を受け取ることができ、実質的な節税を実現できるように設計された商品も数多く存在していました。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「法人保険とは?節税効果の真意や会社で入るメリットを解説」
そのため、節税を重視する中小企業経営者の間では、法人保険を活用した節税対策が常套手段のひとつとされてきたのです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
2019年の税制改正で法人保険の節税効果は激減
ところが、2019年の税制改正によって、このような法人保険を活用した節税対策は大きな転機を迎えました。保険料の損金算入の可否について、新たな要件と分類が導入され、これまでのようなシンプルな節税スキームは事実上難しくなっています。
「法人保険の節税効果」編集部
たとえば、以下のようなポイントが新たに明確化されました。
- 解約返戻率が高い保険ほど、損金算入の制限が強化
- 保険期間3年以上かつ、第三分野保険を除いた法人保険に対して適用
- 最高解約返戻率が50%を超える保険商品においては、特定の計算式により損金にできる保険料が大幅に制限
その結果、節税目的での法人保険加入はもはや難しい状況となっています。
解約返戻率と損金算入の関係|節税効果はほぼ期待できない
税制改正後は、「節税を狙うほど損金計上が制限される」という逆転現象が起きています。
以下は、具体的な損金算入の考え方の例です。
- 年間保険料が100万円
- 最高解約返戻率が90%
- 契約から10年未満の場合
→ 損金にできる保険料:100万円-(100万円×90%×90/100)=19万円(19%)
同様に、返戻率100%の保険では損金算入できるのはわずか10%=10万円。このように、高い解約返戻率を持つ法人保険ほど節税効果が限定的になる仕組みに変更されたのです。
法人保険の節税効果に関するおすすめ記事

法人保険の節税効果や、法人保険のメリットとデメリットについては以下の記事も是非参考にしてください。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「騙されないで!法人契約の生命保険に節税の効果は一切ない」
実は節税にはならない「課税繰り延べ」という誤解
法人保険の保険料を一部損金として処理できたとしても、それは課税のタイミングをずらしているだけにすぎません。

合わせて読みたい「税理士 法人 節税 対策 中小企業」に関するおすすめ記事

【中小企業必見】法人の節税対策は税理士に相談すべき?知っておくと得する節税対策まとめ
将来、保険金や解約返戻金を受け取る際、それらは益金(売上と同じ扱い)として課税対象になります。つまり、法人税が免除されたわけではなく、単に納税を後ろ倒しにしただけであり、本質的な節税ではないのです。
法人保険の節税効果に関する注意点

このような仕組みを「課税繰り延べ」と呼びますが、節税対策として考えるには限界があります。税金そのものが減るわけではないため、資金計画を誤ると、逆に税負担が重くなるリスクもあります。

節税目的で法人保険に入るなら「出口戦略」が重要
ただし、法人保険をすべて否定するわけではありません。適切な目的とタイミングで活用すれば、節税につながるケースもあります。
たとえば、
- 解約返戻金を役員退職金として支給する
- 返戻金を福利厚生費として社員に還元する
- 保険金を使って経費の増加タイミングと利益圧縮を調整する
このように、将来的な資金活用まで見据えた「出口設計」を行えば、法人保険でも一定の節税効果が得られることがあります。重要なのは、「節税になるから入る」のではなく、「何のために使うのか」を明確にしたうえで契約することです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
現在の税制下では、法人保険の節税効果は大幅に制限されており、以前のような節税メリットはほとんど期待できません。高い解約返戻率の商品は損金処理が厳しく制限され、解約後に受け取る返戻金は益金として課税対象となるため、単純な節税にはなりません。
「法人保険の節税効果」編集部
法人保険の使い方次第で税負担を抑えるチャンスは残されています。
節税を目的とするなら、法人保険の出口戦略や受け取り方、そしてタイミングの最適化が非常に重要です。
法人保険に加入する4つのメリットとは?
法人保険は、経営の安定やリスク対策だけでなく、節税の観点からも注目されている保険制度です。経営者や役員の退職金準備、事業承継資金の確保、従業員向けの福利厚生など、法人保険の活用方法は多岐にわたります。さらに、保険料の一部を損金として処理できるケースもあり、法人税の節税効果を期待できる点も魅力のひとつです。
「法人保険の節税効果」編集部
法人保険の節税効果や、法人保険のメリット・デメリットについては以下のサイトも是非ご覧ください。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「法人保険とは?メリット・デメリットや節税にならないのか解説」
ここでは、法人保険に加入することで得られる4つの主なメリットを紹介しながら、各メリットにおける具体的な節税効果や節税対策の活用法について詳しく解説していきます。
法人保険に加入するメリット1
経営上のリスクに備えられる|法人保険によるリスク回避と節税効果
企業活動を続ける中で、経営者の急な死亡や病気、また資金繰りの悪化といった事態は、会社の存続を脅かす深刻なリスクです。特に中小企業では、経営者の信用に依存した経営体制が多いため、万一が起これば取引停止や資金調達困難といった事態に直面する可能性があります。
法人保険に加入することで、死亡保険金や入院給付金などを受け取り、リスク時の資金補填が可能になります。
法人保険の節税効果に関するポイント!

契約内容によっては保険料の一定割合を損金計上できるため、保険料支出による節税効果も同時に期待できます。
また、貯蓄性のある法人保険に加入していれば、契約者貸付制度を活用して、解約返戻金の範囲内で資金調達が可能となります。この制度も、一時的な資金不足に対応しながら節税効果を維持するという観点で非常に有効です。保険料を損金処理することで、法人税の課税所得を圧縮し、節税メリットを享受できます。
法人保険の節税効果に関するおすすめ記事

法人保険の節税効果や、法人保険のメリットとデメリットについては以下の記事も是非参考にしてください。
「法人の生命保険で節税はできない?法人保険のメリット・デメリット」
法人保険に加入するメリット2
経営者や役員の退職金準備ができる|法人保険と節税対策の好相性
節税対策として法人保険が活用される代表例が、経営者や役員の退職金準備です。養老保険や長期平準定期保険などの法人向け生命保険は、解約返戻金や満期保険金が支払われる貯蓄型保険であり、将来の退職金の原資として活用できます。
「法人保険の節税効果」編集部
退職金を現金で積み立てる場合と異なり、法人保険で積み立てれば、目的外に資金を流用することなく、計画的に節税しながら資金を確保できます。
法人保険の保険料の一部を損金処理できる設計にしておけば、積立中の法人税を抑えることが可能です。また、支給時には退職金として経費化されるため、二重の節税効果を得られる場合もあります。このように、退職金準備と節税を両立できるのが法人保険の大きなメリットです。
法人保険に加入するメリット3
円滑な事業承継を実現できる|納税資金対策と節税戦略

合わせて読みたい「節税 税理士 選び方」に関するおすすめ記事

節税に強い税理士の選び方は?選び方のポイントや必要な準備を解説!
事業承継時の節税対策としても、法人保険は非常に有効な手段です。経営者が亡くなった際には、後継者が相続税や贈与税を支払う必要があり、まとまった現金が求められます。法人保険で支払われる死亡保険金を納税資金や自社株買い取り資金に充てることで、承継の障害を軽減できます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人保険の節税効果に関するポイント!

このとき、保険料の一部が損金算入できるように設計されていれば、支払い中の節税効果も同時に得られるという大きな利点があります。
特に自社株の評価額が高く、相続税負担が重い企業ほど、保険を通じた事前準備と節税戦略が不可欠です。法人保険を活用すれば、遺族や後継者が資金不足により経営権を失うリスクも回避でき、資産承継と節税の両立が実現できます。
法人保険に加入するメリット4
福利厚生の一環として活用できる|従業員満足と節税のバランス
福利厚生制度の充実と節税対策を同時に実現できるのも、法人保険を導入する大きな理由のひとつです。従業員の死亡時や入院・就業不能に備える保険に法人が加入することで、従業員の安心を確保し、会社のイメージアップや人材の定着率向上にも貢献します。
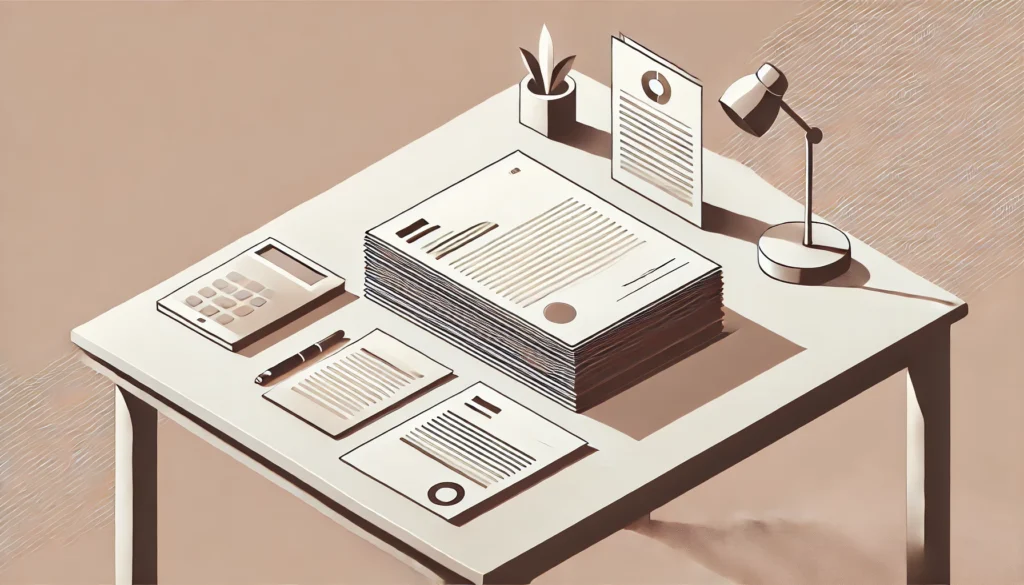
法人保険の節税効果に関するおすすめ記事

法人保険の節税効果や、法人保険のメリットとデメリットについては以下の記事も是非参考にしてください。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「法人保険は節税にならない!?2024年最新の状況や加入のメリットを紹」
さらに、一定の条件を満たせば、これらの保険料は福利厚生費として損金処理が認められ、法人税の節税にもつながります。
「法人保険の節税効果」編集部
つまり、従業員満足度の向上と、会社の税負担軽減を両立できる制度設計が可能です。
従業員にとっても、福利厚生が手厚い企業は信頼性が高く、長期的な雇用安定にもつながるため、結果的に企業側の人材確保コストの削減と節税効果という二重のメリットが得られます。

合わせて読みたい「マイクロ法人 節税 (税理士)」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は節税できる?個人事業主から法人化するおすすめタイミングも解説!
法人保険は、企業が抱える経営課題に対して多面的に活用できるツールであり、節税効果を狙った戦略的活用が可能です。特に、退職金準備や事業承継、福利厚生といった場面では、税負担の圧縮と資金計画の最適化を同時に実現できるのが法人保険の魅力です。
もちろん、節税を目的とした保険加入には注意が必要であり、節税効果を最大化するには契約内容の精査と専門家のアドバイスが欠かせません。
法人保険の節税効果に関するポイント!

税制改正の影響を受けやすい制度であるため、節税目的での導入を検討する際は、保険の設計と出口戦略を一体で考えることが重要です。
法人保険は、リスク管理と節税の両方に貢献する経営資源として、計画的に活用すれば大きな武器となります。「法人保険=節税」と短絡的に考えるのではなく、節税効果を得られるように活かす工夫こそが求められる時代です。
法人保険を活用するデメリットとは?
法人保険は、経営リスクへの備えや、資金計画、さらには節税対策として導入されることが多く、中小企業やスタートアップの経営層にとって非常に魅力的な制度のひとつです。しかし、法人保険を活用することで必ずしも無条件に節税効果が得られるとは限らず、慎重な設計や戦略が求められます。
「法人保険の節税効果」編集部
法人保険の節税効果や、法人保険のメリット・デメリットについては以下のサイトも是非ご覧ください。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「法人保険のメリットは?保険の種類や節税効果について解説」
とくに節税目的で法人保険に加入する場合には、保険料の継続負担や返戻金の受取タイミングなど、見落としがちなデメリットを把握しておくことが重要です。ここでは、節税狙いの法人保険活用で起こりやすい代表的な2つのデメリットについて詳しく解説します。
法人保険に加入するデメリット1
キャッシュフロー悪化のリスク|法人保険による節税効果と資金負担の両立に注意
節税目的で法人保険を活用する場合、保険料の一部または全額を損金算入できるため、一時的に課税所得を圧縮し法人税の節税効果を得ることが可能です。しかし、節税効果を期待して加入する保険商品ほど、保険料の額が高くなる傾向があるため、月々の支出が経営を圧迫するリスクも否めません。
法人保険の節税効果に関する注意点

法人保険による節税メリットは確かに魅力的ですが、同時に高額な保険料負担によってキャッシュフローが悪化し、資金繰りが逼迫してしまうこともあります。
節税に注力するあまり、事業資金を削ってしまうようでは本末転倒です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【キャッシュフロー悪化がもたらす影響と節税対策の盲点】
- 高額な保険料が資金を圧迫し、節税以上の損失が出る
- 資金ショートを避けるために借入が必要になる
- 保険料を支払うために他の経費を削る羽目になる
- 結果的に節税どころか財務悪化を招く可能性もある
法人保険は節税のためだけに加入するのではなく、経営資金とのバランスを見て導入することが不可欠です。節税効果を最大化しつつ、健全なキャッシュフローを保てる保険設計を意識しましょう。
法人保険に加入するデメリット2
解約タイミングを誤ると返戻金が減少|節税効果を無駄にしないための注意点
法人保険の節税効果に関するおすすめ記事

法人保険の節税効果や、法人保険のメリットとデメリットについては以下の記事も是非参考にしてください。
「法人が加入する掛け捨て型生命保険の節税効果は?メリットやデメリットについても解説」
法人保険を使った節税対策では、保険料を損金にできる間は節税効果が得られるように見えますが、その後の解約タイミングによって受け取れる解約返戻金が大幅に減少するリスクがあります。

法人保険の中には、解約返戻率のピーク時期が設計上あらかじめ決まっている保険商品が多く存在します。ピークを迎える前や過ぎたタイミングで解約してしまうと、返戻金が予想よりも少なくなり、結果的に節税効果が相殺される可能性が高まります。

合わせて読みたい「法人が経費にできるもの一覧」に関するおすすめ記事

法人で経費にできるもの一覧まとめ!経費にできるものとできないものを紹介
【解約返戻金と節税効果の逆転現象に注意】
- 節税効果を期待して契約したのに、解約時に損失が発生
- 解約時に返戻金が少なすぎて、納税資金に充てられない
- 節税どころか、返戻金を益金として課税されることで逆に法人税負担が増す
法人保険の節税効果に関する注意点

法人保険で節税を狙う場合には、返戻金の受取タイミングを綿密に計画しないと、節税の恩恵を失うだけでなく損失につながる可能性もあるのです。
法人保険を節税目的で導入する際の落とし穴とは?
近年の税制改正により、法人保険の節税効果は一律ではなくなり、保険の種類や契約形態、解約返戻率によって損金処理できる割合が大きく異なるようになっています。かつては、法人保険の保険料の全額や2分の1を損金算入できる商品が存在しましたが、現在はそうした商品は厳しく制限されており、「法人保険=節税できる」と単純に捉えるのは危険です。
「法人保険の節税効果」編集部
法人保険の節税効果や、法人保険のメリット・デメリットについては以下のサイトも是非ご覧ください。
「法人保険は節税対策にならない?仕組みから税理士が徹底解説」
さらに、法人保険に加入して保険料を損金にすることで一時的に節税が実現しても、返戻金や保険金を受け取ったタイミングでその金額が益金となり課税対象になります。これはいわゆる課税繰り延べであり、本質的な節税ではなく納税のタイミングを後ろにずらしているだけとも言えます。
「法人保険の節税効果」編集部
節税のために加入した法人保険が、逆に税負担を増やす結果にならないよう、出口戦略を事前に設計することが重要です。
法人保険はどんな会社に向いている?節税対策としての有効性と導入判断
法人保険は、企業のリスクマネジメントや資金確保、そして何より節税対策として活用できる有力な手段です。ただし、法人保険による節税効果は、会社の財務状況や経営体制、加入タイミングによって大きく左右されます。節税を目的として法人保険に加入する場合には、まず自社が本当に法人保険に適した状態であるかを見極めることが不可欠です。
ここでは、節税を効果的に実現できる法人保険の活用が向いている企業の特徴と、逆に節税目的でも導入を控えるべき会社の条件について、詳しく解説していきます。

合わせて読みたい「経営セーフティ共済で節税」に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済で節税できる?デメリットやメリットも解説!
法人保険による節税効果が期待できる会社の特徴とは?
法人保険を通じた節税対策が特に効果を発揮しやすいのは、経営資源が限定されており、特定の人材に依存している中小企業や家族経営の会社です。これらの企業では、経営者やキーパーソンに万が一があった場合に即座に事業継続が困難になることが多く、法人保険による保障と節税の両立が必要とされます。
【節税目的で法人保険の加入がおすすめな会社の例】
- 家族経営や少人数体制の企業で、経営者の役割が大きい会社
- 事業停止が即座に収益減に直結するような資金的余裕が少ない中小企業
- 借入金がある会社で、死亡時に返済リスクを減らしつつ節税を図りたい企業
- 退職金や事業承継を節税しながら資金計画として進めたい会社
このような会社では、法人保険の死亡保険金や解約返戻金を活用することで、資金準備と法人税の節税効果を同時に実現できます。保険料の一部または全部を損金として計上できれば、法人税の節税につながるのはもちろん、返戻金を有効活用すれば長期的な財務改善も期待できます。
「法人保険の節税効果」編集部
法人保険の節税効果や、法人保険のメリット・デメリットについては以下のサイトも是非ご覧ください。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「法人保険は節税になるの?法人保険の経理・税務処理についてわかりやすく解説」
節税を狙っても法人保険に向かない会社とは?
法人保険で節税効果を狙いたい気持ちはわかりますが、すべての企業が法人保険に適しているわけではありません。
法人保険の節税効果に関するポイント!

特に資金繰りが厳しい企業や赤字続きの企業にとっては、法人保険がむしろ経営リスクとなることもあります。
【法人保険の導入を慎重にすべき、節税効果が期待できない会社の例】
- 赤字決算が続いており、法人税の発生がない会社(節税効果がゼロ)
- 保険料の支払いによってキャッシュフローが逼迫する恐れがある企業
- 長期契約による固定支出が重く、一時的な節税のために財務を圧迫してしまう会社
- 保険料を損金処理しても、将来的に返戻金に対して課税され、節税にならない結果になる可能性がある企業
「法人保険の節税効果」編集部
このような企業では、法人保険を使って節税しようとしても、法人税が発生していなければ節税の意味がありません。
また、契約途中で解約せざるを得なくなった場合、返戻金が少なくなるだけでなく、節税効果も帳消しになるリスクがあるため、無理な加入は避けるべきです。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「「法人向け損害保険を活用する」という節税術」
節税を前提とした法人保険はタイミングが重要|導入すべき時期とは?
節税目的で法人保険を導入するなら、会社の経営が安定し、一定の利益が出ていて法人税が発生しているタイミングが理想です。法人保険の保険料を損金として処理することで、実際に法人税の負担が減る=節税効果が生まれるのは、黒字企業でこそ可能になる話です。

また、長期契約の商品であれば、毎年一定額の保険料を支払い続ける中で損金計上が継続できるため、安定した節税対策が構築できるようになります。さらに、将来的な解約返戻金の受取タイミングを適切に設計すれば、節税の効果を維持したまま退職金や事業承継資金として活用することも可能です。
「法人保険の節税効果」編集部
法人保険の節税効果や、法人保険のメリット・デメリットについては以下のサイトも是非ご覧ください。
法人保険の節税効果に関する参考記事:「法人保険に節税効果はない?課税の仕組みや法人保険の4つのメリットを解説」
節税を成功させる法人保険の導入タイミングは、「利益が出ているとき」「資金に余裕があるとき」「中長期的な活用目的が明確なとき」です。
まとめ|法人保険の節税効果
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人保険を活用した節税対策は、企業経営において重要な役割を果たす方法のひとつです。法人保険に加入することで、保険料を損金として計上できる可能性があり、法人税の節税効果が期待できる点は、多くの企業にとって大きな魅力です。特に中小企業や家族経営の法人では、経営者の万一への備えと同時に、節税メリットを享受できる法人保険は資金戦略上非常に有効な選択肢となります。
ただし、法人保険による節税はすべての会社にとって無条件で有利というわけではありません。2019年の税制改正により、法人保険の保険料を損金にできる条件が厳格に定められており、解約返戻率や契約形態によって節税効果に大きな差が出るようになりました。節税目的で法人保険を導入する場合には、損金算入の可否、返戻金の益金算入、保険金受取時の課税タイミングなど、多角的な視点からの検討が不可欠です。
また、法人保険で得た解約返戻金や保険金は、そのまま益金として法人税の課税対象になるため、短期的な節税ではなく「課税の繰り延べ」にすぎないケースもある点に注意が必要です。本当に節税効果を実感するには、退職金準備や事業承継、福利厚生など、法人保険の目的を明確にし、経営戦略の中に組み込むことが不可欠です。
つまり、法人保険による節税効果を最大限に活かすためには、契約前の制度理解、税制改正への対応、長期的な資金活用計画、そして税理士などの専門家との連携が必要不可欠です。
節税だけを目的に法人保険を選ぶのではなく、節税を含めた経営全体の最適化を図る手段として、法人保険を戦略的に導入することが成功への近道となるでしょう。節税効果の高い法人保険の選び方、法人保険に関する税務上の最新ルール、損金処理のポイントなどをしっかり押さえ、自社にとって最適な節税型法人保険プランを選定しましょう。
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!