会社設立時の事業年度の決め方は?ポイントや税理士に依頼する場合のメリット・デメリットを解説
カテゴリー:
公開日:2024年5月
更新日:2026年1月24日
会社設立を進める際に、事前にしっかりと考えておくべき重要な項目の一つが「事業年度」の決め方です。会社設立後の経営や税務申告にも大きな影響を与えるため、最適な事業年度の決め方を知っておくことが重要になります。
会社設立時に適切な事業年度を設定することで、資金繰りや決算時期の調整がしやすくなり、節税対策を効果的に行うことができます。しかし、どのような決め方がベストなのか分からない方も多いのではないでしょうか。会社設立後にスムーズに経営を進めるためにも、慎重な検討が必要です。
また、会社設立時の事業年度の決め方について、税理士に相談することで得られるメリットもありますが、一方で費用面のデメリットも考慮しなければなりません。そこで、本記事では、会社設立における事業年度の決め方のポイントを詳しく解説するとともに、税理士に依頼する際のメリット・デメリットについても分かりやすくご紹介します。

合わせて読みたい「税理士に依頼する時の費用」に関するおすすめ記事

会社設立後に必要な税務署の届出とは?税務署での手続きも詳しく解説!
これから会社設立を考えている方や、最適な事業年度の決め方に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
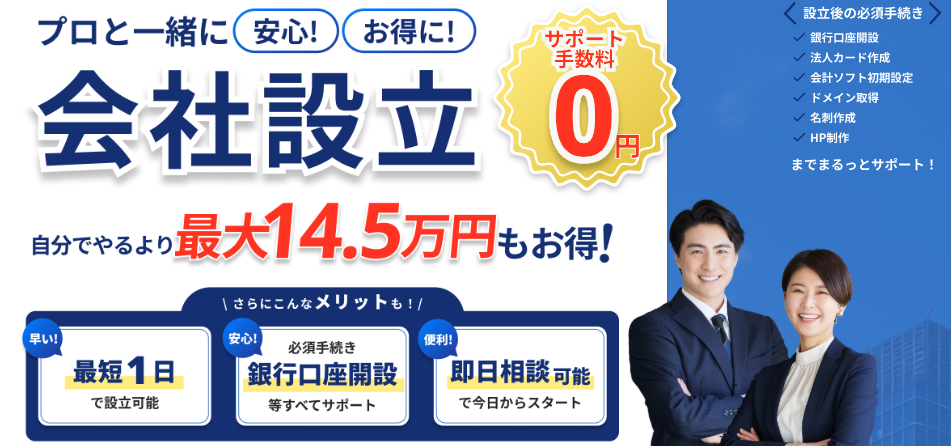
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
事業年度とは

事業年度とは、決算書類を作成するための一定期間を指します。法人においては、会社設立登記を行った日が事業年度の開始日となり、その日から1年以内の期間を事業年度として設定します。ただし、事業年度を変更する場合に限り、例外として1年6ヶ月以内の期間を設定することが可能です。
また、事業年度の最後の月を「決算月」と呼び、決算月の最終日を「決算日」と言います。
事業年度に関するおすすめ記事:会社設立時における事業年度の決め方とポイント
事業年度のルール

事業年度のルール①:原則として期間は1年
会社設立時に設定される事業年度は、基本的に1年間とされます。例えば、「1月1日から12月31日までの1年間」や「4月1日から3月31日までの1年間」といった形で事業年度を設定します。事業年度が1年を超えない限り、数カ月単位で設定することも可能です。
-

SoVa税理士お探しガイド編集部
多くの会社は3月や12月を決算月としていますが、会社設立時に事業年度を会社の都合に合わせて自由に設定することができます。
おすすめ参考記事:事業年度を自由に設定できる

合わせて読みたい!「税理士に相談するタイミングをお悩みの方」におすすめ記事
法人化する際に税理士への相談は必要?相談するメリットや費用を解説

事業年度のルール②:定款に定めなくても可
会社設立の際には、「定款」と呼ばれる会社の基本規則を記載した書類を作成する必要があります。事業年度は定款の任意記載事項であり、記載しなくても問題ありません。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
しかし、定款に事業年度を記載しない場合は、会社設立後2カ月以内に法人設立届出書に事業年度を記載して、税務署に届け出る必要があります。
事業年度・決算日のルールに関するおすすめ記事
会社設立時の事業年度の決め方

会社設立時に設定する事業年度は任意で決められるため、どのように設定するか迷うこともあるかと思います。事業年度を決める際には、まず決算期をいつにするかが重要です。決算期を設定すれば、そこから逆算して事業年度を決めることができます。
-

SoVa税理士お探しガイド編集部
ここでは、会社設立時の事業年度の決め方のポイントを5つご紹介します。
事業年度の決め方①:繁忙期は決算期から外す
会社設立時の事業年度の設定において、決算期が繁忙期と重なると、以下のような様々な弊害が発生する可能性があります。

合わせて読みたい「会社設立 法人 種類 税理士」に関するおすすめ記事

【会社設立】法人の種類や設立方法は?会社設立に税理士が必要な理由まで解説!
手が回らなくなる
決算作業には、これまでの取引のまとめや棚卸しなど、多くの業務が含まれます。繁忙期と決算期が重なると、担当者や税理士の作業量が膨大になり、処理しきれなくなるリスクがあります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
一人会社を設立するメリットについては以下の記事がおすすめです。
「一人会社を作るメリットは?個人事業主との違いや一人会社の作り方を解説!」
納税額を見通しにくい
繁忙期は通常、利益が増える時期ですが、この時期は利益に変動が出やすいものです。繁忙期を決算期に設定すると、利益の予測が難しくなり、予想外の納税額の増減が生じる可能性があります。
「会社設立日」編集部
間違えやすい会社設立日と登記日の違いについては以下の記事も是非ご覧ください。
会社設立日と登記日の違いに関する参考記事:「会社の設立日は登記日と同じ?設立に関する日付の違いや注意点を解説!」
節税対策が行いにくい
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
決算に向けて税金を少しでも圧縮するためには、事前の準備が必要です。しかし、繁忙期と決算期が重なると、節税対策を立てるのが難しくなるリスクがあります。
おすすめ記事:【4step】会社設立時の決算月の決め方を税理士が解説!
事業年度の決め方②:資金繰りのサイクルから計算する
会社設立後、事業年度が終了すると、その後2カ月以内に確定申告を行う必要があります。そして、速やかに法人税などを納付しなければなりません。この納税の月に、会社のキャッシュが不足していると、資金繰りに苦しむことになるかもしれません。会社設立時には、以下のポイントを考慮して事業年度を決定しましょう。

合わせて読みたい「 起業の成功率」に関するおすすめ記事

起業の成功率はどれくらい?5年後10年後の確率と成功する秘訣を紹介!
入金が多く、支出が少ない月を選ぶ
会社設立時に事業年度を設定する際は、決算期を売上げ入金が多く、借入金の返済がないキャッシュが潤沢にある月にするのがよいでしょう。
SoVa税理士お探しガイド編集部
一人会社を設立するメリットについては以下の記事がおすすめです。
「一人会社を作るメリットは?個人事業主との違いや一人会社の作り方を解説!」
繁忙期前や取引先の事情を考慮する
特に、繁忙期の前で支出が多くなる月は避ける方が無難です。また、取引先に公的機関がある場合、それらの機関は3月に予算編成を行い、売上げを3月に入金するケースが見られます。このような場合、3月直前にはキャッシュが不足することが考えられるため、その月も避けるのが賢明です。
会社設立の関連記事:「会社の作り方を徹底解説!必要な手続きと費用について」
事業年度の決め方③:消費税の免税を考慮する

合わせて読みたい「株式会社の設立の流れ」に関するおすすめ記事

株式会社の設立の流れとは?株式会社設立のポイントや注意点も紹介!
基本的に、会社設立後において、当期の売上高が1,000万円を超える会社は、その2期先から消費税の納税が必要となります。
会社設立後の最初の2期までは、消費税の課税対象となる売上高が存在しないため、この期間は免税期間となります。会社設立から1年後を事業年度の決算期とし、消費税の納税が発生する期をまるまる2年後に設定すれば、納税義務が生じない期間が長くなります。なお、会社設立から6カ月以内に1,000万円の売上を達成した場合は、上記の免税期間にかかわらず2期目から消費税の納税義務が発生します。ただし、会社設立から決算期までが7カ月以下であれば、免税される取り決めもあります。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
これらの点を考慮し、売上高の予測も含めて、会社設立時に節税のために最適な事業年度の決算期を設定することが重要です。
「マイクロ法人の税理士」編集部
マイクロ法人の税理士は本当にいるのか、【 マイクロ法人の決算は税理士なしでやる方法とは?メリット・デメリットについても解説! 】の記事を参考に顧問税理士との契約を検討しましょう。
事業年度の決め方④:法人税の納付時期から計算する
会社設立後、法人税の納付時期は決算期から2カ月以内です。この時にキャッシュが不足している場合、資金繰りが厳しくなります。
事業年度の決算期を設定する際には、繁忙期を避ける方法だけでなく、最も利益が期待できる繁忙期に納税月を合わせる方法もあります。繁忙期前には支出が多くなりますが、繁忙期を過ぎた時期に法人税の納付を行えば、キャッシュフローに与える影響を軽減できます。

合わせて読みたい「税理士にスポット相談する際の相談」に関するおすすめ記事

税理士にスポット相談する際の相場は?顧問契約との違いについても解説!
売上の増減が予測しやすい業種の場合、キャッシュが十分に用意できる時期を見定め、その時期に法人税の納付時期を合わせるように、会社設立時に事業年度の決算期を逆算して設定するのも有効です。
事業年度の決め方⑤:役員報酬の支払い時期から決める
会社設立後、役員報酬は事業年度の開始日から3カ月以内に金額を決定します。役員報酬には、毎月定額を支払う定期同額給与、事前に支払う時期を決める事前確定届出給与、業績に応じて給与額を変更する業績連動給与があります。基本的に、これらの役員報酬の金額は一度決定すると変更できないため、支払い金額や時期が事前に決まっているはずです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
そこで、法人税の納付時期を、役員報酬の支出が増える時期から外す方法を検討するのもおすすめです。役員報酬を決定する際には、前期の決算の結果から利益予想を立て、損金計上できる金額と役員個人の所得税が過度に膨らまない金額を十分に考慮することが重要です。
会社設立時の事業年度の決め方のポイントに関するおすすめ記事:事業年度はどのようにして決める?決め方のポイントや法人税との関係も解説

合わせて読みたい「役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

役員報酬の決め方とは?決めるときの注意点も詳細解説!

合わせて読みたい「役員報酬の株主総会議事録の作成方法」に関するおすすめ記事

役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!
会社設立後に事業年度を変更する方法

事業年度や決算期は、会社設立後に変更することも可能です。以下に事業年度の変更方法をご紹介します。
事業年度の変更手続きSTEP①:株主総会の開催
会社設立後に事業年度や決算月を変更するには、まず株主総会を開催し、事業年度の変更について3分の2以上の賛成を得る必要があります。通常、事業年度は定款で規定されており、定款を変更するには特別決議が必要です。
変更の決議後は、株主総会議事録に変更内容を記載します。規模の小さい会社では、株主総会を開催せずに議事録を作成することもあります。
事業年度の変更手続きSTEP②:定款を変更する
株主総会での特別決議の後、定款の事業年度を変更します。定款に事業年度を記載することは任意ですが、通常は記載されているため、変更が必要です。

合わせて読みたい「マネーフォワードクラウド会社設立で会社設立」に関するおすすめ記事

マネーフォワードクラウド会社設立を使って会社設立する方法とは?マネーフォワードで会社設立するメリットも紹介!
事業年度は任意の項目であり、そのため公証役場での定款の認証や法務局での登記は不要です。手続きには費用がかかりません。
事業年度の変更手続きSTEP③:税務署等へ異動届と議事録を提出する
公的機関への通知は、所轄税務署や都道府県税事務所、市区町村の役所に「異動届出書」を提出することで行います。事業年度の変更を決議した「株主総会議事録」のコピーを添付して提出しましょう。届出書と議事録の提出により、事業年度の変更手続きは完了します。

合わせて読みたい「スタートアップ企業において税理士に依頼できる業務とメリット」に関するおすすめ記事

スタートアップに税理士は必要?依頼できる業務とメリットを徹底解説
さらに、主要取引先や金融機関などにも、事業年度の変更を連絡する必要があります。
会社設立後に事業年度を変更する方法に関するおすすめ記事:決算期は変更できる?メリット・デメリットや手続きを解説
会社設立を税理士に依頼するメリット

ここまで、会社設立時の事業年度の決め方や会社設立後に事業年度を変更する方法について解説してきましたが、自分だけで事業年度を決めるのは難しいと思っている方もいるのではないでしょうか。
もっと早く相談したらよかったと後悔する前に、必要に応じて税理士などの専門家に相談することも重要です。ここでは、会社設立を行う際に税理士に依頼することのメリットについて解説します。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立を税理士に依頼するメリット①:税務に関する情報提供を受けながら意思決定ができる

合わせて読みたい「freee 税理士 会計士」に関するおすすめ記事

freeeがあれば税理士・会計士はいらない?メリットとデメリットを解説
たとえば、株式会社を設立する際には、次のような要素が税金に影響を与える可能性があります。
- 資本金の額や株主構成
- 事業年度や決算月の選定方法
- 役員報酬などの支払額
- 支店の登録などの手続き
- 会社設立するタイミング
「会社設立と事業年度」編集部
資本金は1円からでも会社設立できますが、融資や取引先からの信用を考えると、ある程度の金額を設定したほうが安心です。適正な資本金額の目安については、【 会社設立費用1円!?資本金1円で会社を設立する方法を解説 】も参考になります。
会社設立において、これらの要素は今後の税金に大きな影響を与えます。税理士との事前相談によって、会社設立前に必要な情報を得て、経営者として最適な選択や判断を行うことができます。
会社設立を税理士に依頼するメリット②:創業融資や助成金・補助金のサポートが受けられる
税理士事務所や会計事務所によって異なりますが、創業融資や助成金・補助金のサポートを提供している場合があります。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
特に、創業融資などは事業計画書が必要になるため、税理士が事業計画書の作成支援も行っていることがあります。また、助成金や補助金などは日々変更されるため、最新の情報を税理士から提供してもらうこともできます。
おすすめ参考記事:事業年度とは?会計期間との違いや決算期の決め方を解説
会社設立を税理士に依頼するメリット③:経費等の相談ができる
会社設立前には、さまざまな経費がかかります。例えば、本店を設けるためのオフィスの賃貸料、自宅を事務所として使用する場合の家賃の経費配分、必要な設備や備品の購入費用など、会社設立時は検討すべき事項が多岐にわたります。これらの経費は適切に処理しないと、後々の経理や税務処理に問題が生じる可能性があります。

合わせて読みたい「法人の住所変更登記」に関するおすすめ記事

法人の住所変更登記をする方法とは?本店移転登記の手続き方法を解説!
税理士に相談することで、これらの経費がどのように処理されるべきか、どのような経費が控除対象となるかを事前に理解することができます。たとえば、オフィスの賃貸料や自宅事務所の家賃の経費配分については、税法上の規定に従って正確に計算する必要があります。税理士はその専門知識を持っているため、適切なアドバイスを受けることができ、税務調査などのリスクを軽減することができます。
-

SoVa税理士ガイド編集部
事前にこれらの情報を把握しておくことで、会社設立後の経営をスムーズに進めることができます。税理士のサポートを受けることで、経費処理に関する煩雑な作業から解放され、本来の業務に集中できる環境を整えることができます。
会社設立を税理士に依頼するメリットに関するおすすめ記事:会社設立前や設立後に税理士は必要なのか?メリット・デメリットをご紹介
会社設立を税理士に依頼するデメリット
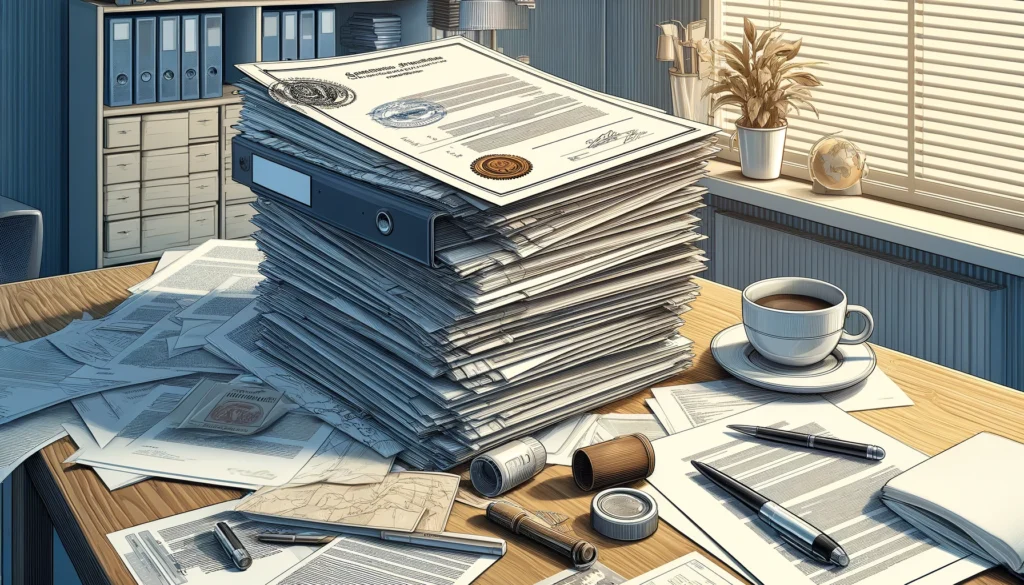
会社設立時に税理士に依頼することのメリットが多くある一方で、税理士に依頼するかどうかは状況に応じて慎重に判断する必要があります。
以下の会社設立時に税理士に依頼することのデメリットを参考に、会社設立時から税理士に依頼すべきかどうかを検討することをおすすめします。
会社設立を税理士に依頼するデメリット①:税理士報酬の費用負担が発生する
税理士に依頼することで、報酬費用が発生するというのが最も大きなデメリットです。
そのため、作業を代行してもらうことで手間が軽減される利点や、有益な提案を受けることで得られる利益、税理士費用に伴う税負担の軽減などのメリットと比較して、会社設立時から税理士が必要かどうかを検討することが重要です。
ただし、顧問税理士との契約を検討している場合、会社設立のサポートの費用を無償、または比較的安価に設定している税理士事務所もあります。顧問税理士との契約を前提としている場合には、税理士から会社設立のサポートを受けることを積極的に検討してみてもいいでしょう。
会社設立を税理士に依頼するデメリット②:税理士を探す手間がかかる
通常、会社設立後に税理士を途中で変更すると、かなり手間がかかる場合があります。そのため、可能であれば最初に選ぶ税理士を慎重に選択したいと考える方も多いでしょう。ただし、選択基準や報酬相場などが分からないこともあり、税理士を選ぶのに多くの手間がかかることがあります。
会社設立を税理士に依頼するデメリットに関するおすすめ記事:会社設立に税理士は必要?依頼するメリット・タイミングを解説
まとめ
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
事業年度を決める際には、消費税の免税期間や会社の繁忙期、資金繰りなど、留意すべき要素があります。自社の状況や業種、業務の進行状況を考慮し、最適な事業年度を設定するようにしましょう。
また、会社設立には多くの専門知識と労力が必要です。会社設立時に税理士に依頼することのメリット・デメリットも参考にしながら、状況に応じて税理士などの専門家に会社設立をサポートしてもらうことを検討するのもおすすめです。
おすすめ参考記事:STEP1‐⑧ 事業年度を決める
税理士に関するおすすめ記事

税理士に関して以下の記事も是非参考にしてください。
「渋谷区で安いおすすめ顧問税理士事務所|東京都【2025年最新】」
SoVa会社設立編集部
会社設立の際に必要な印鑑については以下の記事をご覧ください。
「 合同会社を設立するのに必要な印鑑の種類は?印鑑を準備する際の注意点も解説! 」
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!