マイクロ法人での資産運用はいくらからがおすすめ?メリットや注意点を解説!
カテゴリー:
公開日:2025年3月
更新日:2025年6月11日
個人の不動産投資や株式投資の資産運用成績が好調で年収が増えると、一般的にマイクロ法人を活用した資産運用を検討すべきだといわれています。これは、富裕層だけでなく、資産運用を行うサラリーマンにとっても重要な選択肢の一つです。特にいくらからマイクロ法人を設立するのが得策なのかは、多くの人が気になるポイントでしょう。
そこで本記事では、サラリーマンが資産運用を効率化するためにマイクロ法人の設立を検討すべき年収はいくらからかの目安や、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

合わせて読みたい「マイクロ法人は売上なしでも大丈夫」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は売上なしでも大丈夫?メリットやデメリットについても解説!
本記事では、売上なしの状態でマイクロ法人を運営する際の重要なポイントを解説し、法人を維持するためのコストやリスク、さらには売上がなくても活用できるメリットについて詳しく紹介します。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
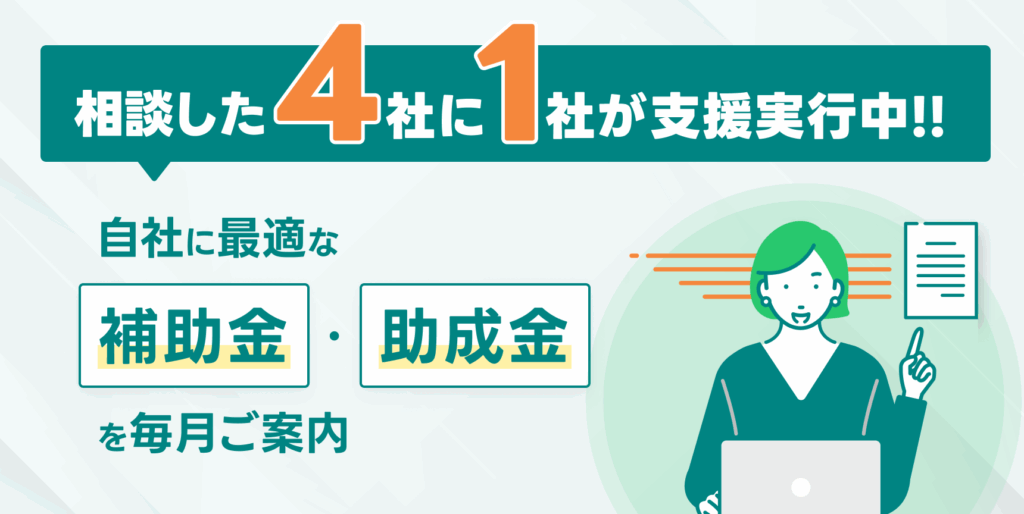
目次
マイクロ法人での資産運用に関する基礎知識

マイクロ法人での資産運用はいくらからがおすすめかについて解説する前に、まずはマイクロ法人での資産運用に関する基礎知識について解説をしていきます。
SoVa税理士ガイド編集部
マイクロ法人に適した業種はいくつかありますが、資産運用会社もその代表的な選択肢の一つです。マイクロ法人を活用して資産運用を行うことで、節税や資産の効率的な管理が可能になります!
そもそもマイクロ法人とは
マイクロ法人とは、一般的に経営者一人で事業を行い、従業員を雇わない小規模な法人形態を指します。株式を公開していない非公開会社の場合、役員や株主の人数に制限はなく、マイクロ法人も法律上は一般的な法人と同等に扱われます。ただし、マイクロ法人という言葉自体やその定義について、法律上の明確な規定はありません。
一般の企業が収益向上や事業拡大を目指すのに対し、マイクロ法人は主に節税や資産運用の最適化を目的とする点が特徴的です。特に、不動産投資や株式投資などの資産運用を行う際、個人で運用するよりも法人を活用したほうが有利になるケースが多いため、いくらからマイクロ法人を設立すべきかを考えることが重要です。
マイクロ法人での資産運用はいくらからがいいかに関するおすすめ記事:マイクロ法人での資産運用はいくらから?目安や今注目の「FIRE」を解説
そもそも資産運用会社とは
資産運用会社とは、その名の通り、クライアントの資産を適切に運用し、報酬を得る事業を指します。しかし、マイクロ法人のような小規模な会社形態では、資産運用会社の役割がやや異なります。
マイクロ法人を活用した資産運用では、経営者自身の資産を法人名義で運用することが主な目的となり、クライアントの資産を運用するものではありません。そのため、多くの場合、外部からの依頼を受けるのではなく、いくらからだとメリットが大きいかを見極め、自身の資産管理や節税のために活用されます。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
SoVa税理士お探しガイド編集部
このように、マイクロ法人を通じた資産運用には多くのメリットがありますが、いくらから設立すべきか、またどのような資産運用方法が適しているのかを理解することが重要です。
マイクロ法人での資産運用はいくらから検討すべき?

一定の年収がないと、マイクロ法人を設立しても手間が増えるだけでなく、かえって税負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。マイクロ法人を活用した資産運用において、設立のメリットがある年収の目安はいくらからなのかを把握することが重要です。
SoVa税理士ガイド編集部
一般的にメリットが大きくなる年収の目安がいくらからかというと、年収700万円超が1つの目安とされています。
ただし、単年の収入がいくらからかだけでなく、将来的な資産運用の計画も含めて判断する必要があります。節税の観点からみるマイクロ法人の設立基準はいくらからかは以下の通りです。
マイクロ法人での資産運用はいくらからがいいかに関するおすすめ記事
いくらから?資産運用を検討すべき基準①:給与所得と副業を合わせて700万円超の場合
サラリーマンが資産運用や副業を行う場合、所得税は給与所得と合算されて計算されます。所得税率は以下の通りです。
<所得税の速算表>
- 6,950,000円~8,999,000円:税率23%(控除額636,000円)
- 9,000,000円~17,999,000円:税率33%(控除額1,536,000円)
一方で、マイクロ法人を設立した場合の法人税率は以下の通りです。
<マイクロ法人の法人税率>
- 年800万円以下の部分:15%
- 年800万円超の部分:23.2%
例えば、年収700万円で個人と法人の税率を比較すると、所得税は23%、法人税は15%となり、マイクロ法人を設立することで税率を抑えられる可能性があります。このことから、資産運用や副業による年収がいくらからならマイクロ法人を活用すべきかを考える際、700万円が1つのボーダーラインとなります。
いくらから?資産運用を検討すべき基準②:副業所得が900万円超または年商1,000万円超の場合
マイクロ法人を活用した資産運用はいくらから検討すべきかのもう一つの基準として、所得が900万円を超えた場合も設立を検討するべきタイミングです。課税所得900万円超の個人の税率は、所得税・住民税を合わせて最低43%になるため、法人実効税率の約35%よりも高くなります。
さらに、年商1,000万円を超えると消費税の課税事業者となりますが、マイクロ法人を設立すると一定の条件下で2年間は消費税が免除されるため、資産運用の観点からも節税メリットがあります。
マイクロ法人での資産運用はいくらからがいいかに関するおすすめ記事
このように、資産運用を効率化し節税を実現するためには、いくらからマイクロ法人を設立すべきかを見極めることが大切です。
マイクロ法人で資産運用会社の設立が得するケース

マイクロ法人を活用した資産運用は、サラリーマン、個人投資家、資産家、オーナー社長にとって、節税や資産の効率的な管理に役立つ手段です。いくらからマイクロ法人を設立すべきかと合わせて確認することで、ご自身がマイクロ法人で資産運用会社を設立すべきか判断もしやすくなるでしょう。
マイクロ法人での資産運用はいくらからがいいかに関するおすすめ記事
マイクロ法人で資産運用会社の設立が得するケース①:資産運用や副業を行うサラリーマン
近年、多くのサラリーマンが本業の安定収入に加えて、資産運用や副業を通じて収益を増やすことを目指しています。しかし、個人で資産運用や副業を行う場合、税負担が大きくなり、収益の最大化が難しくなることがあります。
そこで、いくらからがメリットが大きくなるかを理解した上でマイクロ法人を設立することで、節税効果を得ることが可能になります。例えば、個人では経費として認められない支出(自宅の一部をオフィスとして使用する際の家賃の一部など)も、法人を通じて計上することで節税が可能です。加えて、資産運用で得た利益や副業の収益をマイクロ法人に移すことで、個人の所得税や住民税の負担を軽減することができます。
いくらからマイクロ法人を設立すべきかという点については、一般的に年収700万円を超えると法人税率の方が有利になる可能性が高まります。また、副業の所得が900万円を超えたり、年商が1,000万円を超えたりした場合も、マイクロ法人の設立をいくらから検討すべきかのよいタイミングといえるでしょう。
マイクロ法人での資産運用はいくらからがいいかに関するおすすめ記事
マイクロ法人で資産運用会社の設立が得するケース②:資産運用を行う個人投資家
個人投資家にとっても、いくらからがお得かを見極めて設立することで、マイクロ法人を活用した資産運用を効率的に進めることができます。株式投資、不動産投資、暗号資産などで高額な利益を得た場合、個人の所得税率は累進課税により高くなりがちです。

合わせて読みたい「マイクロ法人 決算 自分で」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の決算は自分でできる?税理士なしで自分でやる手順を解説!
本記事では、マイクロ法人の決算を自分で行う際に知っておくべき基本知識から、具体的な手順、注意点までを解説します。大きなミスを防ぎ、安全にマイクロ法人の決算を乗り越えられるよう、しっかりと知識を身につけていきましょう。
一方、マイクロ法人を通じて投資を行えば、法人税率が適用され、所得税よりも低い税率で課税されることが多く、結果的に税負担を軽減できます。また、法人を活用することで、投資関連の経費を広く認められるため、さらなる節税が可能になります。いくらから設立すべきかは、年間の投資利益が一定額を超え、個人の税負担が増加してきたタイミングで検討するとよいでしょう。
マイクロ法人で資産運用会社の設立が得するケース③:相続税の発生が見込まれる資産家
相続税の発生が見込まれる資産家にとって、マイクロ法人を活用することで、資産の引き継ぎをスムーズに行い、税負担を軽減することが可能です。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
例えば、個人で資産を相続する場合、遺産の総額に応じて高額な相続税が発生し、相続人に大きな財政負担を強いることがあります。しかし、マイクロ法人に資産を移転し、法人の株式を相続する形にすれば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
マイクロ法人で資産運用を行うにはいくらからに関してここがポイント!

特に、不動産や事業資産を保有している場合、法人化することで相続時の資産分割がしやすくなり、家族間のトラブルを防ぐことにもつながります。
マイクロ法人で資産運用会社の設立が得するケース④:事業承継を考えるオーナー社長
オーナー社長にとって、自社株の相続や事業承継は重要な課題です。マイクロ法人を活用することで、経営権の引き継ぎを円滑にし、税務上の負担を軽減することができます。
例えば、マイクロ法人を設立して自社株を管理することで、後継者には経営権を伴う普通株式を、その他の相続人には無議決権株式を割り当てることが可能になります。これにより、経営権を後継者に集中させつつ、他の相続人にも資産としての株式を分配することができ、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
マイクロ法人での資産運用におけるメリット

マイクロ法人を活用した資産運用は、税制のメリットを最大限に活かし、効率的に資産を増やす手段の一つです。その際、いくらからマイクロ法人を設立すべきか、その判断基準を明確にすることが重要です。
マイクロ法人での資産運用におけるメリット①:経費計上の幅が広がる
個人で資産運用を行う場合、経費として認められる範囲は限られています。しかし、マイクロ法人を設立することで、役員報酬・退職金・法人保険・福利厚生費・社宅費など、幅広い経費を計上できるようになります。
例えば、個人では控除できない自宅家賃の一部をマイクロ法人の社宅として計上したり、不動産を法人名義で購入して減価償却費として計上したりすることが可能です。これにより、資産運用を行う際の税負担を大幅に軽減できます。
マイクロ法人で資産運用を行うにはいくらからに関して
マイクロ法人で資産運用を行うにはいくらからに関して気をつけておきたい注意点

また、役員報酬を設定することで、個人所得を適切に分散でき、所得税の負担を抑えることができます。ただし、報酬額が高すぎると税制上のメリットが減少するため、いくらから役員報酬を設定するべきか慎重に考える必要があります。
マイクロ法人での資産運用におけるメリット②:損失を最長10年間にわたって繰り越せる
資産運用を行っていると、株式や投資信託、不動産などの売却時に損失が発生することがあります。個人で損失を繰り越せる期間は最長3年ですが、マイクロ法人を活用すれば、損失を最長10年間繰り越せるため、将来の利益と相殺しやすくなります。

合わせて読みたい「マイクロ法人の社会保険料」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!
この仕組みを活用することで、資産運用による損益をコントロールし、税金の負担を軽減できます。いくらから法人化を検討すべきかは、年間の投資損益や所得税率を考慮して決めるとよいでしょう。
マイクロ法人での資産運用はいくらからがいいかに関するおすすめ記事:マイクロ法人設立とは?作り方・年収はいくらから?個人事業主の場合は確定申告をどうする?
マイクロ法人での資産運用におけるメリット③:所得税・住民税・社会保険料の負担を軽減
法人税率は、個人の所得税率よりも上限が低いため、一定額以上の所得がある場合は、法人化したほうが有利になることが多いです。具体的にいくらからだとメリットが大きいかで言うと、年収700万円以上のサラリーマンや副業収入が900万円以上の人は、マイクロ法人を設立することで節税メリットを享受しやすくなります。
また、いくらからがお得かを踏まえてマイクロ法人を設立すれば、経営者自身が役員となることで給与所得控除を適用できるため、所得税や住民税の負担が軽減されます。例えば、給与所得控除の上限は195万円であり、適用されることで課税対象所得を大幅に削減できます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
さらに、法人では健康保険や厚生年金に加入することで、個人事業主が負担する国民健康保険や国民年金よりも支払額を抑えられるケースが多く、社会保険料の負担も軽減できます。
マイクロ法人での資産運用における注意点

マイクロ法人を活用した資産運用は、多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。いくらから法人化を検討するべきかを判断するには、注意点も十分に理解した上で決断することが重要です。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
マイクロ法人で資産運用を行う際の注意点①:会社の資産を個人で自由に使えない
いくらからがお得かを見極めた上でマイクロ法人を設立した場合でも、資産運用を法人名義で行う場合、個人と法人の資産を明確に分ける必要があります。
マイクロ法人で資産運用を行うにはいくらからに関して気をつけておきたい注意点

法人が保有する資産は、たとえ経営者であっても、自由に私的利用することはできません。
個人事業主であれば、事業で得た収益をそのまま個人資産として自由に使えますが、マイクロ法人の場合は違います。法人が得た収益を個人で利用するには、役員報酬や配当という形で受け取る必要があります。
マイクロ法人の資産運用はいくらからに関する参考記事:「マイクロ法人と個人事業主の二刀流をするとき、業種はどうする?」
さらに、役員報酬の変更は原則として年1回、事業年度開始後3か月以内と決められており、一度決定すると簡単には変更できません。例えば、「資産運用で想定以上の利益が出たので、役員報酬を増やしたい」と思っても、すぐに調整できないため、慎重に設定する必要があります。
マイクロ法人で資産運用を行う際の注意点②:赤字でも法人住民税が発生する
いくらからマイクロ法人を設立するかを考える際、法人住民税の負担を理解しておくことも大切です。
個人事業主の場合、所得が赤字であれば、所得税や住民税は発生しません。しかし、マイクロ法人では、たとえ資産運用による利益がなく赤字になったとしても、法人住民税(均等割)を支払わなければなりません。
法人住民税には以下の2つの種類があります。
- 法人税割(所得金額に応じて課税される)
- 赤字の場合、法人税割は発生しません。
- 均等割(損益に関係なく一定額を支払う必要がある)
- 資本金1,000万円以下の法人の場合、年間7万円程度の負担が発生します。
このため、いくらから法人化すると税負担のメリットが出るのかを見極めることが重要です。
マイクロ法人での資産運用はいくらからがいいかに関するおすすめ記事
マイクロ法人の設立でよくある疑問|Q&A
Q.マイクロ法人設立に伴うマイクロ法人の維持費は年間いくら?
A.マイクロ法人の年間維持費は税理士と顧問契約をするかどうかで変わってきます。顧問税理士をつける場合、マイクロ法人の年間維持費は約38万円~、マイクロ法人に顧問税理士をつけない場合は約28万円~が相場です。
Q.マイクロ法人の設立費用はいくら?
A.マイクロ法人の設立費用は、株式会社の場合は約20万円~24万円、合同会社の場合は約6万円~10万円が相場です。
Q.マイクロ法人設立後は会計ソフトを導入した方が良いのか
A.マイクロ法人を設立後は年度終了後に必ず決算申告を行う必要があります。つまり、マイクロ法人の記帳は単式簿記ではなく、必ず複式簿記で行います。
単式簿記の場合は、会計ソフトを導入しなくても日々の記帳か可能ですが、複式簿記の場合は会計ソフトを導入なしではマイクロ法人での記帳が困難になると言えます。また、マイクロ法人が税理士と顧問契約する場合でも、税理士の記帳方法が会計ソフト導入を前提としていることも多いため会計ソフトは必要です。
「マイクロ法人の設立」編集部
会計ソフトのなかには、無料で会社設立をサポートするソフトを提供しているものもあるため、会社設立の段階からソフトを導入するのもおすすめです。
まとめ

この記事では、マイクロ法人を活用した資産運用はいくらから検討すべきかについて解説しました。従来、資産運用会社は資産家が節税や相続、事業承継を目的に設立するケースが一般的でしたが、最近ではいくらからマイクロ法人を設立すればメリットを得られるかを検討する個人投資家や副業サラリーマンが増え、より広く注目されるようになっています。
マイクロ法人での資産運用はいくらからがいいかに関するおすすめ記事
いくらからがお得かを理解した上で資産運用を目的としたマイクロ法人を設立することで、税制上のさまざまなメリットを享受できるだけでなく、資産の相続や事業承継の対策としても有効です。特に、資産運用の利益を法人に移すことで所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
SoVa税理士ガイド編集部
ただし、いくらからマイクロ法人を設立するとメリットが出るのかを見極めることが重要であり、法人運営にかかるコストや事務負担の増加といったデメリットも考慮する必要があります。
この記事で紹介したマイクロ法人を活用した資産運用のメリット・デメリットやいくらからマイクロ法人の設立を検討すべきかを踏まえ、自身の状況に応じてマイクロ法人化を検討すべきか判断してみてください。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します















SoVaをもっと知りたい方