マイクロ法人でも厚生年金に加入する義務はある?加入するメリットとデメリットを解説!
カテゴリー:
公開日:2025年3月
更新日:2026年2月12日
マイクロ法人とは、フリーランスなどの個人事業主が税金対策や厚生年金の加入を目的に設立・経営する法人のことです。マイクロ法人では、役員報酬を適切に設定することで厚生年金に加入でき、国民年金よりも手厚い年金制度を活用できる可能性があります。通常、マイクロ法人は個人事業主が単独で運営し、従業員や他の株主がほとんど存在しない「個人事業主のための法人」として機能します。
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事:フリーランス・個人事業主は知っておきたい新たな選択肢「マイクロ法人」とは?
近年、フリーランスを中心にマイクロ法人の設立が増えており、厚生年金を利用した社会保険料の最適化が注目されています。しかし、マイクロ法人と厚生年金の関係にはメリットだけでなくデメリットもあるため、その実態をしっかり理解することが重要です。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「マイクロ法人の社会保険料」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!
目次
マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、従業員を雇わず、代表者自身が1人で事業活動を行いながら、税金対策や厚生年金の加入を考慮して設立される法人のことを指します。特に個人事業主やフリーランスが、社会保険料の負担を最適化し、厚生年金を活用するためにマイクロ法人を設立するケースが増えています。
マイクロ法人と一般的な法人との違い
| 項目 | マイクロ法人 | 一般的な法人 |
|---|---|---|
| 外部株主や従業員の有無 | なし(代表者1人) | あり |
| 登記の有無 | あり | あり |
| 設立の目的 | 節税や厚生年金の加入を目的とすることが多い | 事業経営・拡大や社会貢献 |
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事
マイクロ法人には、外部の株主や複数の従業員が存在せず、代表者1人がすべてを管理します。一般的な法人は株主を募り、役員や従業員を抱えて事業を拡大するのに対し、マイクロ法人は厚生年金の活用や税負担の軽減を目的に運営されることが多いのが特徴です。
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事:個人の法人の二刀流で大幅節税!?マイクロ法人ってなに!?
会社法では、非公開会社の役員や株主の人数に決まりはないため、法律上はマイクロ法人も一般的な法人と同じ扱いになります。ただし、マイクロ法人を設立するには会社法に則った手続きが必要で、法人登記を行う必要があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
マイクロ法人と個人事業主との違い
「マイクロ法人」編集部
「マイクロ法人とは?」とマイクロ法人の定義を考える際に個人事業主とマイクロ法人の違いを把握しておくことも重要です。
マイクロ法人と個人事業主の大きな違いは、法人化の有無ですが、それにより厚生年金への加入可否や税務上のメリットに差が出ます。
マイクロ法人を設立すると、一定の役員報酬を設定することで厚生年金に加入することが可能となり、老後の年金額を増やせるメリットがあります。個人事業主の場合、国民年金のみの加入となるため、将来的な年金受給額が低くなる可能性があります。このため、厚生年金を活用したいと考えるフリーランスの間で、マイクロ法人の設立が注目されています。
また、個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで事業を始められるのに対し、マイクロ法人は定款を作成し、法務局で法人登記を行う必要があります。そのため、マイクロ法人の設立には一定の手間とコストがかかりますが、厚生年金の恩恵や節税メリットを考慮すると、長期的には有利になるケースもあります。
ここがポイント!

個人事業主のままでいるか、マイクロ法人を設立するかは、厚生年金の活用や税制面のメリットを総合的に考え、中長期的な視点で判断することが重要です!
厚生年金とは?国民年金との違い

公的年金制度には、国民年金制度と厚生年金制度があり、どちらの年金制度に加入するかは、個人の働き方やマイクロ法人の活用有無によって決まります。特に、マイクロ法人を設立することで厚生年金への加入が可能となり、個人事業主やフリーランスにとって重要な選択肢となっています。ここでは、国民年金と厚生年金の特徴や違いについて説明します。
国民年金とは
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する基本的な年金制度です。これは「基礎年金」とも呼ばれ、「2階建て」と言われる年金制度の1階部分にあたります。
SoVa税理士ガイド編集部
個人事業主やフリーランスは原則として国民年金のみの加入となるため、将来の年金受給額が比較的低くなる傾向があります。
そのため、マイクロ法人を設立し、厚生年金に加入することで、老後の年金額を増やす方法が注目されています。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
厚生年金とは
厚生年金は、会社員や公務員が加入できる年金制度で、給与に応じた保険料を支払い、将来の受給額が国民年金よりも高くなる仕組みです。
また、一定の条件を満たしたアルバイトやパートタイマーも厚生年金に加入することができます。マイクロ法人の代表者も、自らに役員報酬を設定することで厚生年金に加入でき、国民年金のみの場合に比べて手厚い年金制度を利用することが可能になります。

合わせて読みたい「マイクロ法人での資産運用はいくらから?」に関するおすすめ記事

マイクロ法人での資産運用はいくらからがおすすめ?メリットや注意点を解説!
本記事では、サラリーマンが資産運用を効率化するためにマイクロ法人の設立を検討すべき年収はいくらからかの目安や、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
厚生年金は、「2階建て」の年金制度の2階部分にあたるため、国民年金のみの場合よりも将来の受給額が増え、障害年金や遺族年金の給付も手厚くなるメリットがあります。
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事
厚生年金と国民年金の違いとは
厚生年金と国民年金の違いについて、マイクロ法人の活用も視野に入れながら、以下の表で確認してみましょう。
| 項目 | 厚生年金 | 国民年金 |
|---|---|---|
| 対象者 | 会社員、公務員、マイクロ法人の代表(役員報酬を受ける場合) | 個人事業主、学生、無職の人(第1号被保険者、第3号被保険者) |
| 保険料 | 収入に応じて変動 | 一律 |
| 保険料負担 | 会社と折半(マイクロ法人の場合は会社負担分も自己負担) | 全額自己負担 |
| 最低被保険者期間 | 1か月 | 10年 |
| 支給開始年齢 | 65歳(生年月日によっては60歳) | 65歳 |
| 将来の受給額 | 収入と加入期間に応じて変動(マイクロ法人を活用すれば増額可能) | 加入期間に応じて一律 |
| 障害年金 | 障害等級1~3級の場合に支給(3級未満でも支給される場合あり) | 障害等級1~2級の場合に支給 |
| 遺族年金 | 生計を維持されていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母に支給 | 生計を維持されていた要件を満たした子供に支給 |
マイクロ法人の社長でも社会保険への加入義務はある?

「マイクロ法人」編集部
マイクロ法人に関連して、「 マイクロ法人のメリットとは?経費にできるものについても解説! 」の記事も是非ご覧ください。
そもそも社会保険とは、厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険など、公的保険の総称です。特に「健康保険+厚生年金」のみを指す場合もあり、狭義にはこの2つを指すことがあります。
企業は設立後、健康保険法第3条・厚生年金保険法第9条などの法律により、以下の社会保険への加入が義務付けられています。
- 健康保険
- 厚生年金
SoVa税理士お探しガイド編集部
マイクロ法人を設立した場合でも、役員(代表者)が一定以上の報酬(給与)を設定すると、厚生年金と健康保険の加入が必須になります。
従業員を雇用していない一人社長のマイクロ法人でも、法人化と同時に厚生年金への加入義務が発生するため、国民年金のみの個人事業主とは異なり、老後の年金受給額を増やすことが可能です。
一方で、労災保険や雇用保険については、従業員をひとりでも雇用している場合に加入が義務付けられるため、マイクロ法人の運営方針によって加入すべき社会保険が異なります。
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事
マイクロ法人の設立で社会保険料が削減できる仕組み

個人事業主がマイクロ法人を設立し、自ら役員報酬を受け取ることで厚生年金に加入することが可能になります。この際、役員報酬を低く設定することで、厚生年金や健康保険の社会保険料負担を抑えることができる点が大きなメリットです。
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事
例えば、年収500万円の個人事業主がマイクロ法人を設立し、役員報酬を月額20万円に設定した場合、厚生年金や健康保険の保険料負担が大幅に軽減されます。一方で、国民健康保険や国民年金に加入したままの場合、所得に応じた高額な保険料を支払う必要があります。
ここがポイント!

特に、厚生年金は国民年金に比べて将来の受給額が高くなるため、マイクロ法人を活用して厚生年金に加入することで、老後の年金額を増やす効果も期待できます!
このため、所得が高くなるにつれ、国民健康保険や国民年金の負担が大きくなる個人事業主にとって、マイクロ法人を設立し厚生年金に加入する方法は、節税と将来の年金対策の両方を兼ね備えた魅力的な選択肢となります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
マイクロ法人を設立して厚生年金に加入するメリット

SoVa税理士ガイド編集部
このマイクロ法人を活用した厚生年金加入スキームには、いくつかの大きなメリットがあります。
主にマイクロ法人で厚生年金に加入するメリットは以下の3つがあります。
厚生年金に加入するメリット①:厚生年金と健康保険の保険料削減
マイクロ法人を設立し、役員報酬額を調整することで、厚生年金や健康保険の負担を大幅に軽減できます。特に、年収が高い個人事業主にとって、国民健康保険や国民年金よりも厚生年金に加入するほうが保険料負担を抑えやすいケースが多く、この手法は有効な選択肢となります。

合わせて読みたい「マイクロ法人 決算 自分で」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の決算は自分でできる?税理士なしで自分でやる手順を解説!
本記事では、マイクロ法人の決算を自分で行う際に知っておくべき基本知識から、具体的な手順、注意点までを解説します。大きなミスを防ぎ、安全にマイクロ法人の決算を乗り越えられるよう、しっかりと知識を身につけていきましょう。
厚生年金に加入するメリット②:信用力の向上
マイクロ法人として法人化することで、個人事業主に比べて社会的信用度が向上します。これにより、取引先からの信頼を得やすくなり、金融機関からの融資の審査も通りやすくなることが期待できます。また、法人名義で契約ができるため、事業用のクレジットカードや銀行口座の開設もしやすくなる点もメリットです。
マイクロ法人の関連記事:「マイクロ法人は家賃も経費にできる?経費計上する方法や注意点を解説!」
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事
厚生年金に加入するメリット③:税制面で有利
マイクロ法人として法人化することで、法人税の適用を受けることが可能です。法人税率は個人事業主の所得税率よりも低くなる場合が多く、利益の分配方法を工夫することで節税効果を高めることができます。さらに、厚生年金に加入することで将来の年金受給額が増加するため、老後の備えとしても有利です。
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事:マイクロ法人設立とは?作り方・年収はいくらから?個人事業主の場合は確定申告をどうする?
このように、マイクロ法人を設立し、厚生年金に加入することで、社会保険料の最適化、信用力の向上、税制メリットを同時に享受できる可能性があります。
「会社設立後の役員報酬」編集部
会社設立後の役員報酬はいつから支払うべきなのかについては、以下のサイトも是非ご覧ください!
「 会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説 」
マイクロ法人を設立して厚生年金に加入するデメリット


合わせて読みたい「マイクロ法人の格安税理士」に関するおすすめ記事

マイクロ法人が格安で税理士に依頼する際の注意点
しかし、マイクロ法人を活用した厚生年金加入スキームには、いくつかの大きな落とし穴やリスクも存在します。適切に運用しなければ、厚生年金や社会保険料の負担増加につながる可能性があるため注意が必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
マイクロ法人を設立して厚生年金に加入するデメリットは以下の4つが挙げられます。
厚生年金に加入するデメリット①:厚生年金・社会保険料の増加リスク
厚生年金は国民年金よりも手厚い制度ですが、その分、保険料の負担も大きくなります。役員報酬を高く設定しすぎると、厚生年金や健康保険の支払額が想定以上に膨らんでしまう可能性があります。逆に、役員報酬を極端に低く設定すると、税務署から「不自然な所得分配」とみなされ、税務調査の対象となるリスクもあります。
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事
厚生年金に加入するデメリット②:マイクロ法人の設立・維持コスト
マイクロ法人を設立するには、法人登記費用や専門家への相談料が発生します。また、法人維持には会計処理や税務申告のための費用、法人住民税の均等割(赤字でも発生)などのコストがかかります。これらの費用を考慮せずに「厚生年金の保険料削減」だけを目的にマイクロ法人を設立すると、かえってコストが増えるリスクがあります。
厚生年金に加入するデメリット③:税務上のリスク

合わせて読みたい「マイクロ法人は売上なしでも大丈夫」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は売上なしでも大丈夫?メリットやデメリットについても解説!
本記事では、売上なしの状態でマイクロ法人を運営する際の重要なポイントを解説し、法人を維持するためのコストやリスク、さらには売上がなくても活用できるメリットについて詳しく紹介します。
マイクロ法人と個人事業を併用する場合、事業の切り分けが曖昧だと税務署から問題視される可能性があります。特に、法人と個人事業の間で不自然な利益分配や取引が行われていると、税務調査の対象になるリスクが高まります。また、役員報酬の設定が適正でないと、法人税や所得税の面でも問題が生じるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に対応する必要があります。
厚生年金に加入するデメリット④:将来的な影響(厚生年金の受給額)
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
厚生年金に加入することで将来の年金受給額は増えますが、役員報酬を極端に低く設定すると、厚生年金の受給額が少なくなる可能性があります。短期的には社会保険料の負担を抑えられるものの、長期的には老後の年金額が大きく減るリスクがあるため、将来の年金受給額を考慮した上で役員報酬を決定することが重要です。
SoVa税理士ガイド編集部
このように、マイクロ法人を活用した厚生年金の加入スキームは、適切に運用すれば大きなメリットがあるものの、設計を誤ると税務・社会保険料・法人維持費用の面でデメリットが発生する可能性があります。リスクを十分に理解した上で、適切な報酬設定や法人運営を行うことが重要です。
マイクロ法人の設立でよくある疑問|Q&A
Q.マイクロ法人設立に伴うマイクロ法人の維持費は年間いくら?
A.マイクロ法人の年間維持費は税理士と顧問契約をするかどうかで変わってきます。顧問税理士をつける場合、マイクロ法人の年間維持費は約38万円~、マイクロ法人に顧問税理士をつけない場合は約28万円~が相場です。
「マイクロ法人」編集部
マイクロ法人で税理士と顧問契約をしようか迷う場合、自計する場合の時間や税理士に依頼するコストなどを基準に判断するのがおすすめです。【税理士は必要?マイクロ法人の設立と運営のリアルを徹底解説!】の記事も是非参考にして税理士に依頼するかを決めましょう。
Q.マイクロ法人の設立費用はいくら?
A.マイクロ法人の設立費用は、株式会社の場合は約20万円~24万円、合同会社の場合は約6万円~10万円が相場です。
Q.マイクロ法人設立後は会計ソフトを導入した方が良いのか
A.マイクロ法人を設立後は年度終了後に必ず決算申告を行う必要があります。つまり、マイクロ法人の記帳は単式簿記ではなく、必ず複式簿記で行います。
単式簿記の場合は、会計ソフトを導入しなくても日々の記帳か可能ですが、複式簿記の場合は会計ソフトを導入なしではマイクロ法人での記帳が困難になると言えます。また、マイクロ法人が税理士と顧問契約する場合でも、税理士の記帳方法が会計ソフト導入を前提としていることも多いため会計ソフトは必要です。
「マイクロ法人の設立」編集部
会計ソフトのなかには、無料で会社設立をサポートするソフトを提供しているものもあるため、会社設立の段階からソフトを導入するのもおすすめです。

合わせて読みたい「従業員50人以下の社会保険加入条件」に関するおすすめ記事
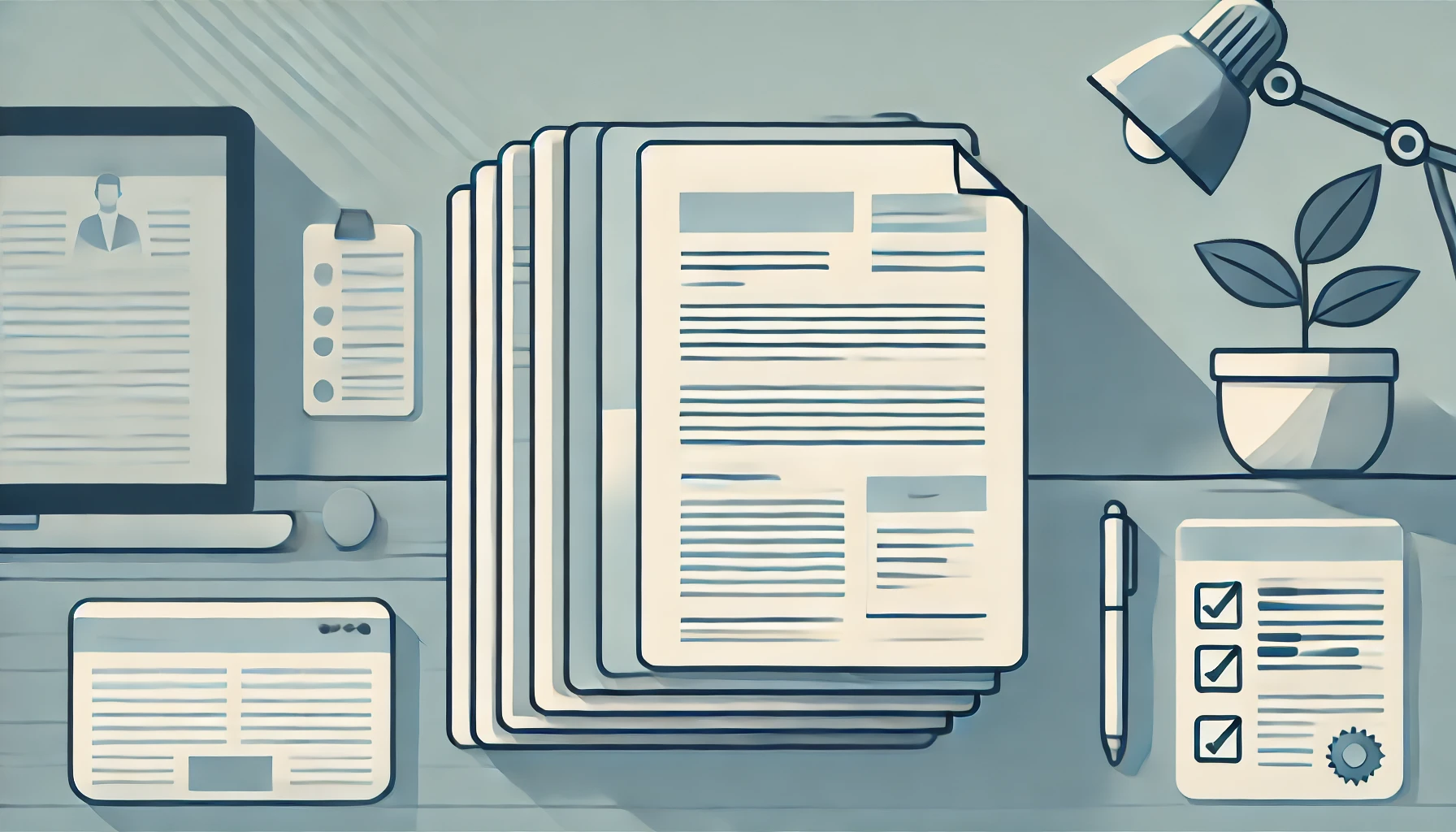
従業員50人以下の会社は社会保険の加入条件に該当する?今後の加入対象拡大についても解説!
Q: マイクロ法人が厚生年金に加入する場合の社会保険料はいくらになる?
マイクロ法人が厚生年金に加入した場合の社会保険料は、役員報酬額によって決まります。例えば役員報酬が月20万円の場合、厚生年金保険料と健康保険料を合わせた社会保険料は会社と個人で折半し、それぞれ約3万円前後の負担となります。報酬額が高くなれば保険料も比例して増える仕組みです。
「マイクロ法人の設立」編集部
社会保険料は経費として計上でき、法人税の節税効果も得られますが、毎月の固定的な支出になるため、マイクロ法人の資金繰り計画に組み込む必要があります。
Q: マイクロ法人で厚生年金に加入しないリスクとは?
マイクロ法人が厚生年金や健康保険などの社会保険料を支払わず未加入のままにしておくと、年金事務所から加入勧奨や指導が入ります。強制的に遡って保険料を徴収されることもあり、その場合は数年分の保険料と延滞金をまとめて支払わなければなりません。

合わせて読みたい「マイクロ法人 赤字」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の赤字経営は大丈夫?赤字になったときの注意点や対処法を解説
さらに、未加入期間は将来の年金受給額に反映されず、老後の生活資金が不足する可能性もあります。短期的な負担軽減よりも、長期的なリスク回避を優先することが重要です。
マイクロ法人の社会保険料に関する参考記事:「社会保険の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!」
Q: マイクロ法人の厚生年金加入手続きの流れは?
マイクロ法人が厚生年金に加入するには、まず年金事務所に新規適用届を提出します。その際、登記簿謄本や役員報酬の決定通知書など、必要書類を揃えることが求められます。
マイクロ法人の税理士に依頼に関する参考記事:「資金調達を税理士に依頼するメリットやおすすめポイントについて詳細に解説!」
申請後、社会保険料の算定基礎届や資格取得届を提出し、翌月以降に保険料の納付が始まります。マイクロ法人の場合、手続きは比較的シンプルですが、書類の不備や提出漏れがあると加入が遅れるため、税理士や社労士に依頼してスムーズに進めるケースも多く見られます。
まとめ

マイクロ法人を活用した厚生年金・社会保険料の削減スキームは、特に国民健康保険や国民年金の負担が重い個人事業主にとって、大幅なコスト削減が期待できる手法です。厚生年金に加入することで、老後の年金受給額が増えるメリットもあるため、社会保険料の最適化と将来の年金対策を両立できる可能性があります。
しかし、役員報酬の設定による厚生年金の影響、法人維持コスト、税務リスク、将来的な年金受給額の減少など、慎重に検討すべきポイントも多く存在します。
気をつけておきたい注意点

特に、マイクロ法人の役員報酬を極端に低く設定すると、将来的な厚生年金の受給額が減少するリスクもあるため、長期的な視点での計画が不可欠です。
このスキームを成功させるためには、厚生年金や社会保険の制度を正しく理解し、税務や法人運営のリスクを考慮した上で、適切な設計を行うことが重要です。そのためには、社会保険や税務に詳しい専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが推奨されます。
マイクロ法人でも厚生年金に加入できるかに関するおすすめ記事
マイクロ法人を活用した厚生年金加入戦略は、短期的な社会保険料削減だけでなく、長期的な年金受給額や法人経営の安定性を考慮して総合的に判断することが重要です。事業規模や個人の状況に応じて最適な方法を選択し、リスクを十分に認識しながら活用することで、マイクロ法人のメリットを最大限に引き出すことが可能となります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!