住民税の特別徴収・普通徴収の違いとは?退職後の住民税の手続きについて解説!
カテゴリー:
公開日:2025年5月
更新日:2026年1月8日
住民税の支払い方法には、「特別徴収」と「普通徴収」という2つの方法があります。どちらも住民税を納める制度である点は同じですが、支払いのタイミングや手続き、誰が納税を行うかといった点で大きな違いがあります。
この記事では、住民税の特別徴収と普通徴収の違いをわかりやすく解説するとともに、それぞれのメリット・デメリットや切り替え方、注意点まで詳しく紹介します。会社員や個人事業主、退職者など立場によって適した徴収方法が異なるため、自分にとって最適な住民税の納付方法を見つける参考にしてください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
住民税の特別徴収と普通徴収の違い

SoVa税理士お探しガイド編集部
住民税の特別徴収と普通徴収の違いは主に3点あります。
納付方法の違い
特別徴収では住民税が給与から自動的に差し引かれ、普通徴収では住民税を自身で納付します。
納付回数の違い
特別徴収は年12回、普通徴収は年4回の納付です。この納付回数の違いも、住民税の管理方法に影響を与えます。
「住民税の特別徴収と普通徴収」編集部
住民税の特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。
手続きの違い
特別徴収は事業主が住民税の申告・納付を行い、普通徴収では本人が住民税のすべてを対応します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
これらの違いにより、住民税の徴収方法は生活スタイルや職業に応じて選ぶ必要があります。
住民税の特別徴収と普通徴収の違いに関するおすすめ記事
普通徴収のメリット・デメリット

普通徴収とは、住民税を納税者本人が自ら納付書などを用いて支払う方法です。この普通徴収の特徴的なメリットの一つは、支払い方法の違いにあります。市区町村によっては、普通徴収ではクレジットカード払いやスマホアプリ決済などが可能であり、この支払い手段の違いが利便性やポイント還元といったメリットをもたらします。
住民税の特別徴収と普通徴収の違いに関する気をつけておきたい注意点

ただし、このような支払い方法には決済手数料がかかる場合もあり、特別徴収との費用面での違いに注意が必要です。
一方で、普通徴収のデメリットにも注目すべき違いがあります。住民税の納付回数が年4回と限定されており、特別徴収の年12回と比べると、1回あたりの負担額が大きくなるという回数の違いが心理的・経済的負担につながる場合があります。
SoVa税理士ガイド編集部
また、普通徴収では住民税の納付手続きを自分で管理する必要があり、この管理方法の違いが納付忘れや滞納リスクという形で現れる点にも留意が必要です。
万が一滞納した場合には、督促状の送付や財産差し押さえといった厳しい措置を受けることもあり、対応への違いが明確です。
住民税の特別徴収と普通徴収の違いに関するおすすめ記事:住民税の普通徴収と特別徴収の違いとは?手続きの流れも解説

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
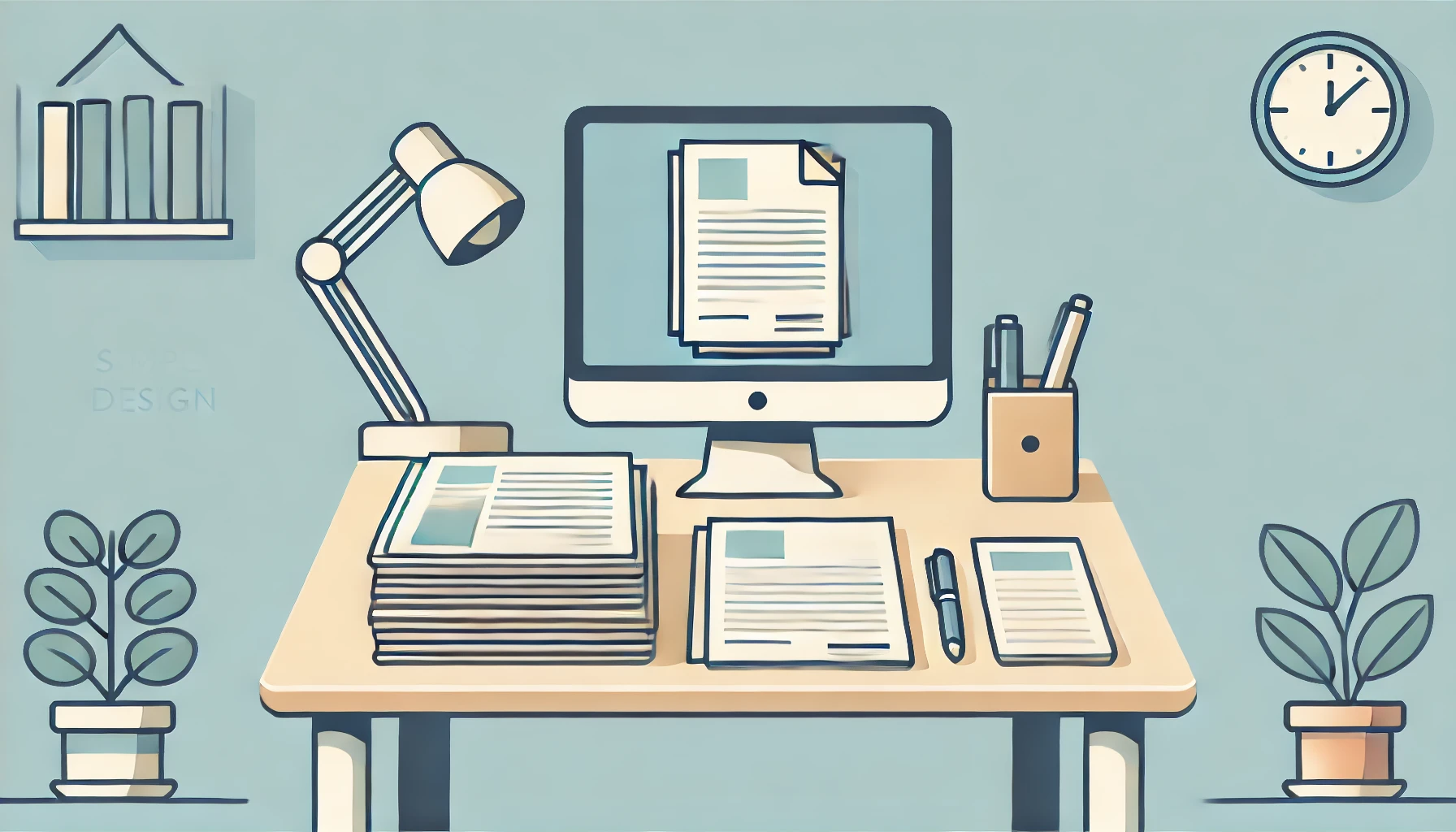
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
特別徴収のメリット・デメリット

住民税の特別徴収は、会社などの事業主が従業員の給与から住民税を天引きし、代わりに自治体へ納付する仕組みです。この方法の最大のメリットは、納税者本人が支払い手続きを行わずに済むという手間の違いにあります。給与から自動的に住民税が引かれ、年12回の分割払いになるため、1回あたりの負担が少なくなるという支払い頻度の違いも利点の一つです。
SoVa税理士ガイド編集部
住民税の特別徴収と普通徴収の違いについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
しかし、特別徴収にもデメリットがあります。たとえば、全従業員分の住民税を計算し、各自治体に納付するという事務負担の違いが、事業主にとって大きな手間となる場合があります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
SoVa税理士ガイド編集部
また、住民税が自動的に引き落とされることで、納税者自身が税額を意識しにくくなるという意識の違いも見逃せません。
特別徴収では、住民税の金額や仕組みを自分で確認しづらくなるという情報把握の違いが生じやすいのです。
住民税の特別徴収・普通徴収の切り替えができるケース
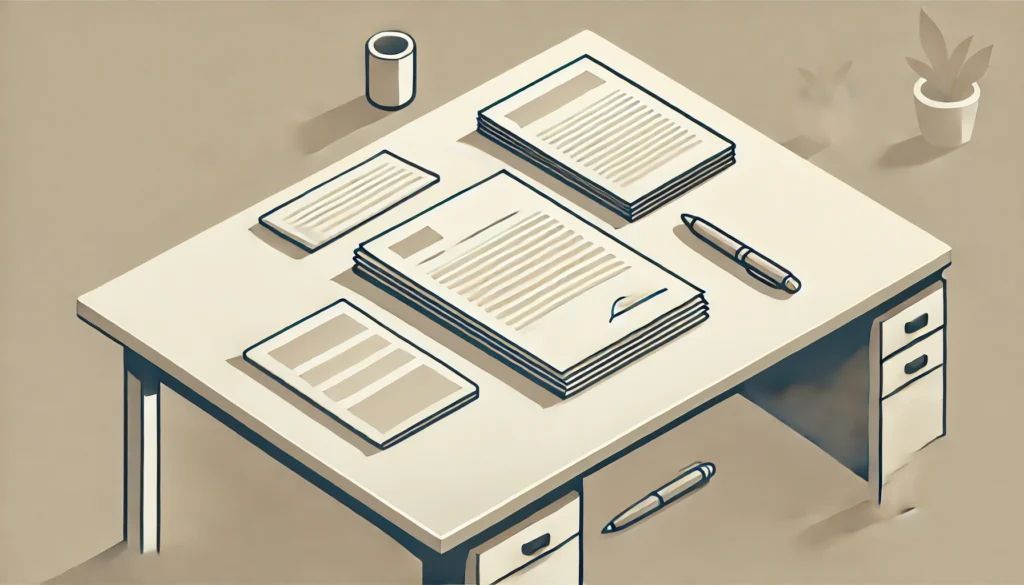
ここでは、住民税における特別徴収と普通徴収の違いを踏まえたうえで、どのような場合に切り替えができるのか、またその方法やタイミングについて詳しく解説します。
住民税の特別徴収と普通徴収の違いに関するおすすめ記事
住民税の特別徴収から普通徴収に切り替えられる主なケースは以下の通りです。
転職した場合
転職により勤務先が変わると、新たな事業所で住民税の特別徴収がすぐに開始されないことがあります。その場合、住民税は一時的に普通徴収へと切り替わることがあります。また、前職で特別徴収の停止手続きが行われなかった場合も、普通徴収による納付が必要になります。このように、転職をきっかけに住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収へと切り替わるケースは少なくありません。

合わせて読みたい「会社側の退職手続き」に関するおすすめ記事
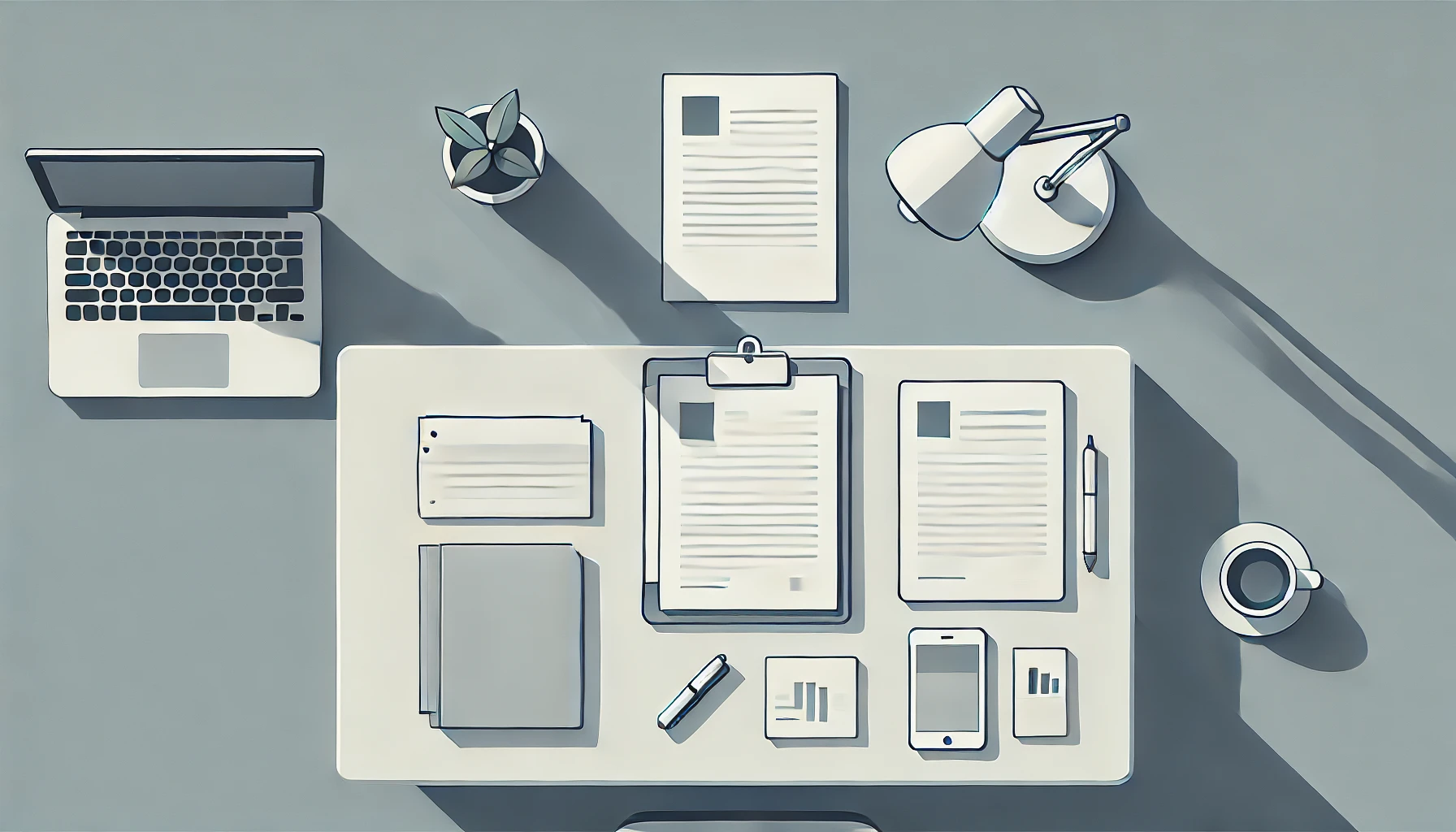
退職手続きでは会社側はいつまでに何をすべき?必要な手続きや対応の注意点を解説!
退職・失業した場合
退職後、一定期間収入がなくなると、住民税を給与から天引きする特別徴収ができなくなるため、普通徴収へ切り替えられるのが一般的です。
住民税の特別徴収と普通徴収の違いに関するここがポイント!

住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、無職の期間でも支払い義務が残りますが、この場合は納付書による普通徴収で対応することになります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
収入が大幅に減少した場合
住民税は前年の所得に基づいて算出されるため、当年に収入が大幅に減少した場合、特別徴収のままだと支払いが困難になることがあります。このような状況では、住民税の特別徴収から普通徴収へ切り替えることで、分納などの相談がしやすくなる場合があります。税額が高額で負担が大きいと感じた際には、普通徴収への切り替えを検討するのも一つの方法です。

合わせて読みたい「法人が納める消費税」に関するおすすめ記事
法人が納める消費税について解説! 税理士のサポートを受けるメリットも紹介

このように、住民税の特別徴収と普通徴収の違いを理解し、状況に応じて適切に切り替えることで、納税の負担を軽減できる可能性があります。どちらの徴収方法にもメリットとデメリットがあるため、自身のライフスタイルや収入状況に合わせて判断することが大切です。
住民税の特別徴収と普通徴収の違いに関するおすすめ記事:住民税の普通徴収・特別徴収の違いは?手続きや節税について解説
住民税の特別徴収を行う際の注意点

住民税の特別徴収を実施する際には、普通徴収との違いを正確に理解した上で対応することが極めて重要です。特別徴収は、住民税を従業員本人に代わって事業者が納付するという仕組みであり、この点において普通徴収との仕組みの違いが明確です。事業者は、住民税の基本的な制度構造と特別徴収と普通徴収の制度的な違いを正しく把握し、担当者がそれぞれの役割の違いを認識しておく必要があります。
住民税の特別徴収対象は全従業員:範囲の違いに注意
住民税の特別徴収は、正社員のみならず、パート・アルバイト・役員といったあらゆる給与所得者が対象となる点が特徴です。これは、対象者の範囲における普通徴収との適用範囲の違いと言えるでしょう。また、住民税の納付先は会社の所在地ではなく、従業員の住民票所在地となる市区町村であるという点も、手続き上の納付先の違いとして押さえておくべきです。

合わせて読みたい「従業員の退職手続き」に関するおすすめ記事
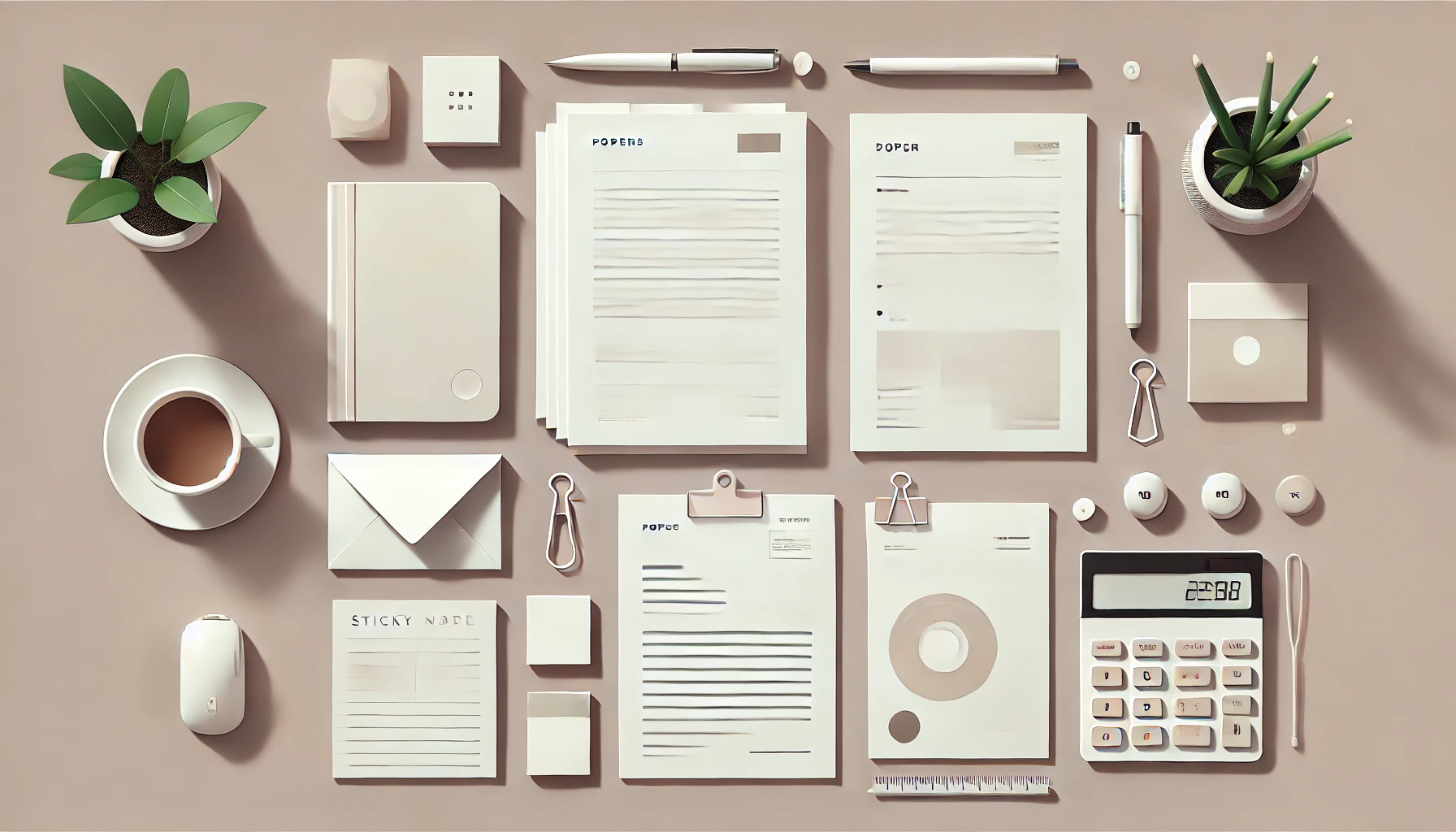
従業員の退職手続きは何をする?必要書類や会社側・従業員側でやることを解説
特別徴収の住民税は納付期限を厳守:期限対応の違いにも注意
特別徴収によって天引きされた住民税は、翌月10日までに各自治体へ納付する必要があります。納付期限を過ぎた場合には、延滞金が発生することになり、この納付管理の違いにも注意が必要です。普通徴収の場合と比べて、事業者が延滞の責任を負うという責任構造の違いがあるため、特別徴収を行う企業は納期限を特に意識しなければなりません。
住民税の特別徴収と普通徴収の違いに関するおすすめ記事
たとえば、延滞1か月以内は年2.4%、1か月を超えると年8.7%といった利率が課されることになり、これは特別徴収を選択した場合に発生する金利負担の違いとも言えるでしょう。
特別徴収と普通徴収の切り替え:変更の自由度における違い
住民税の特別徴収と普通徴収の違いのひとつとして、切り替えの自由度があります。特別徴収は原則として強制適用となっており、普通徴収と違って、会社や従業員の都合だけでは変更できないという変更可否の違いが存在します。
SoVa税理士ガイド編集部
ただし、自治体によっては一定の条件を満たすことで、特別徴収から普通徴収への切り替えが認められる例外的な違いもあります。

合わせて読みたい「入社 住民税 手続き」に関するおすすめ記事

入社時の住民税に関する手続きについて解説!退職時の住民税の手続きも併せて紹介!
たとえば、以下のような場合に、東京都では普通徴収への切り替えが可能とされています(いわゆる東京都統一基準)。これは自治体による適用判断の違いの一例です。
- 総従業員数が2人以下である
- 他の勤務先で特別徴収がすでに行われている
- 給与額が少なく住民税の天引きが難しい
- 給与の支払いが不定期である
- 個人事業主の専従者である
- 退職済、または5月末までに退職予定である(4月1日時点で給与がないなど)
まとめ

専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
住民税の特別徴収と普通徴収の違いに関するおすすめ記事
住民税の特別徴収と普通徴収には、それぞれに違いがあり、メリット・デメリットも異なります。会社が給与から自動的に天引きする特別徴収は納め忘れがなく手間がかかりませんが、収入の変動に気づきにくいという側面もあります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
一方、普通徴収は自分で納付する分、管理の手間はありますが、資金繰りを自分で調整できる自由度があります。
特別徴収と普通徴収の違いを正しく理解し、必要に応じて切り替えの手続きを行うことで、より自分のライフスタイルに合った住民税の納付が可能になります。

合わせて読みたい「住民税の特別徴収と普通徴収」に関するおすすめ記事

住民税の特別徴収とは?普通徴収との違いや手続き方法についても解説!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドとの違いを徹底比較!ビジネスオーナーズ ゴールドを持つメリットとは
-
ビジネスカード

2026年1月29日
2
三井住友カードビジネスオーナーズ2枚持ちのメリットは?2枚持ちにおすすめの個人カードや選び方も紹介
-
ビジネスカード

2026年1月29日
3
三井住友ビジネスオーナーズのメリット・デメリットとは?ゴールドとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月29日
4
三井住友ビジネスオーナーズゴールドのメリットは?一般カードやfor Ownersとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月29日
5
即日ファクタリング来店不要おすすめ15選!選び方から注意点まで徹底解説
-
資金調達

2026年1月24日














SoVaをもっと知りたい!