社会保険の扶養加入条件は?メリット・デメリットや具体的な手続き方法について解説!
カテゴリー:
公開日:2025年2月
更新日:2026年2月24日
雇用者から家族を社会保険の扶養に入れたいといわれた場合、社会保険の扶養に追加する人の収入だけでなく、続柄や生活実態(同居・別居)の確認が必要となるケースもあります。
この記事では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養に入れる条件、社会保険の扶養に入るメリット、そして社会保険の扶養に関する具体的な手続き方法について詳しく解説します。
目次
【労務手続きを自分でするのはリスク大!】
社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由
社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。
社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。
ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。
また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」
社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。
だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
そもそも社会保険の扶養とは

社会保険の扶養とは、社会保険に加入している会社員や公務員の配偶者が、自分自身で健康保険や厚生年金に加入しなくても済む仕組みのことを指します。
会社員や公務員は、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し、社会保険料として健康保険料・厚生年金保険料を支払います。社会保険料の負担は、被保険者である会社員・公務員と勤務先が折半し、それぞれ1/2ずつ負担します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
勤務先が負担する1/2と、被保険者の給料から天引きされた社会保険料を合わせて、最終的に保険料の納付が行われます。
このように社会保険に加入している会社員や公務員が配偶者を扶養している場合、その配偶者は社会保険の扶養に入ることができます。社会保険の扶養となった配偶者は、自分で健康保険に加入しなくても、社会保険の健康保険を利用することが可能です。また、年金に関しても不利な扱いを受けることはなく、社会保険の扶養に入っている限り、健康保険料や厚生年金保険料の支払いは不要となります。
社会保険の扶養加入に関するおすすめ記事
社会保険の被扶養者になるための条件

社会保険の中でも健康保険においては、被保険者との関係性や収入といった一定の条件を満たしていれば親族を扶養に入れることが出来ます。
今回は、加入者の多い全国健康保険協会(協会健保)の扶養親族追加の条件を元に解説します。
「社会保険の加入条件」編集部
社会保険の適用対象が段階的に拡大され、50人以下の企業にも順次義務化されます。
令和9年から令和17年にかけて、従業員数の条件が段階的に引き下げられ、最終的には全ての企業が対象になります。
参考:厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」
被保険者の条件①:社会保険の扶養対象になる範囲
社会保険の扶養対象となるのは、被保険者およびその配偶者の三親等以内の親族、または事実婚関係にある同一生計の人です。具体的には、被保険者の父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、配偶者、子、孫などが社会保険の扶養対象者として含まれます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
被保険者と同居していなくても社会保険の扶養に入れられるケース
親族を社会保険の扶養に入れる際、同居が必要な場合と不要な場合があります。別居でも問題なく扶養に入れられる対象者は、以下の通りです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 直系尊属(被保険者の父母、祖父母、養父母など)
社会保険の扶養加入に関する注意点

ただし、社会保険の扶養に入れるには、生計維持要件を満たす必要があります。例えば、別居している親を社会保険の扶養に入れる場合、被保険者からの仕送りがあり、生活費の大部分を負担していることが条件となります。
被保険者と同居が必須のケース
社会保険の扶養に入るために同居が必要となる対象者は、以下の通りです。
- 被保険者の三親等以内の親族(甥、姪、伯父、伯母など)
- 事実婚の配偶者の父母または子
- 事実婚の配偶者が亡くなった後も同居を続ける父母または子
これらのケースでは、収入条件を満たすことに加えて、同居していることが社会保険の扶養要件となります。さらに、2020年4月1日以降は、日本国内に住所を有していることも条件として追加されました。
被保険者の条件②:社会保険の扶養対象になる家族の収入条件
社会保険の扶養に入るためには、収入要件を満たす必要があります。社会保険の扶養にできる家族の収入条件は、原則として 年間収入130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満 であることです。

合わせて読みたい「マイクロ法人の社会保険料」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!
この「年間収入130万円未満」という基準は、社会保険の扶養に入ることで健康保険や年金の適用を受けるための重要な要件となります。そのため、扶養内で働きたいパートやアルバイトの従業員を雇用している場合、月収が10万8,333円以下になるように調整することで、社会保険の扶養に入る資格を維持しやすくなります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
また、社会保険の扶養に入るためには、年間収入だけでなく、生計維持関係も確認されます。
生計維持の基準
- 同居している場合:扶養される人の収入が、被保険者の年間収入の1/2未満であること(世帯の状況による判断もあり)
- 別居している場合:扶養される人の収入が、被保険者からの仕送り額より少ないこと
また、60歳以上または一定の障がい者の場合、社会保険の扶養に入るための収入基準は「年間収入180万円未満」となります。

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介
社会保険の扶養における「収入」の定義
社会保険の扶養における年間収入には、以下のような収入が含まれます。
- 給与収入(賞与・各種手当を含む)
- 厚生年金・国民年金などの年金収入
- 事業収入(農業・営業など)
- 不動産収入(賃貸収入など)
- 利子・投資収入(預貯金利子・株式配当など)
- 親族からの仕送り
SoVa税理士お探しガイド編集部
これらの収入は、前年の所得および直近3ヶ月の収入を基に判断されます。
一方で、遺産相続や退職金、宝くじの賞金など、一時的な収入は社会保険の扶養に関する収入要件には含まれません。

合わせて読みたい「マイクロ法人 社会保険」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減!役員報酬と社会保険の関係を解説
被保険者の条件③:厚生年金保険の第3号被保険者は配偶者のみが対象
社会保険の中でも、厚生年金保険における第3号被保険者の制度では、扶養対象となるのは配偶者のみです。
具体的な条件は以下の通りです。
- 被保険者(第2号被保険者)の 扶養配偶者(妻または夫)のみが対象
- 配偶者の年齢が20歳以上60歳未満であること
- 扶養配偶者の年間収入が130万円未満であること
また、配偶者が厚生年金保険の適用事業所で働いており、厚生年金の加入条件(月収8.8万円以上など)を満たす場合は、社会保険の扶養に入ることができず、自身で社会保険に加入することになります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
このように、社会保険の扶養制度にはさまざまな条件があり、健康保険や厚生年金の制度ごとに扶養の範囲や要件が異なるため、注意が必要です。
社会保険の扶養加入に関するおすすめ記事
社会保険の被扶養者になるメリット・デメリット

社会保険の扶養に入ることで、配偶者や子どもにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
「社会保険」編集部
社会保険の未加入や、社会保険料の滞納に科される罰則については、【社会保険未加入の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!】の記事をご覧ください
社会保険の扶養に入る配偶者や子どものメリット
社会保険の扶養に入るメリット①:税金の負担が軽減される
一般的に、所得税は年収103万円、住民税は96.5万円を超えると税金が発生します。しかし、社会保険の扶養に入るために年収を一定額以下に抑えれば、所得税や住民税の負担を回避できます。

合わせて読みたい「雇用契約書の書き方」に関するおすすめ記事

雇用契約書の書き方とは?2024年の改正についても解説!
SoVa税理士お探しガイド編集部
扶養される側の所得が少なければ、扶養者の税負担も軽減されるため、家計全体の負担が抑えられるメリットがあります。
社会保険の扶養に入るメリット②:社会保険料を支払う必要がなくなる
社会保険は強制加入の制度であり、会社などの健康保険に加入できない場合、通常は国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。しかし、社会保険の扶養に入ることで、被保険者の健康保険に加入でき、自分で保険料を支払う必要がなくなります。

合わせて読みたい「社会保険と国民健康保険の違い」に関するおすすめ記事

社会保険と国民健康保険の違いは?切り替え時の手続きについて解説!
本記事では、社会保険(健康保険)と国民健康保険の概要、それぞれの社会保険制度の違い、国民健康保険への切り替えが必要なタイミングや社会保険から国民健康保険への手続きを詳しく解説します。
「社会保険(厚生年金保険)の加入条件」編集部
社会保険、特に厚生年金保険の加入条件に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
「厚生年金の加入条件を詳しく解説!加入義務対象の従業員や企業の要件とは?」
さらに、配偶者の社会保険の扶養に入ることで、国民年金保険料の支払いも不要になります。
社会保険の扶養加入に関するポイント!

第3号被保険者として扱われ、将来的に基礎年金を受給できるため、社会保険料を負担せずに年金制度の恩恵を受けられる点は大きなメリットです。
社会保険の扶養に入るメリット③:企業の社会保険制度による付加給付を受けられる
勤務先の健康保険組合によっては、独自の給付制度を提供している場合があります。例えば、医療費の自己負担額の補助や、高額療養費制度に加えての追加給付など、国民健康保険よりも手厚い保障を受けられることがあります。
社会保険の扶養に入ることで、これらの恩恵を受けられるため、医療費負担の軽減につながります。

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事
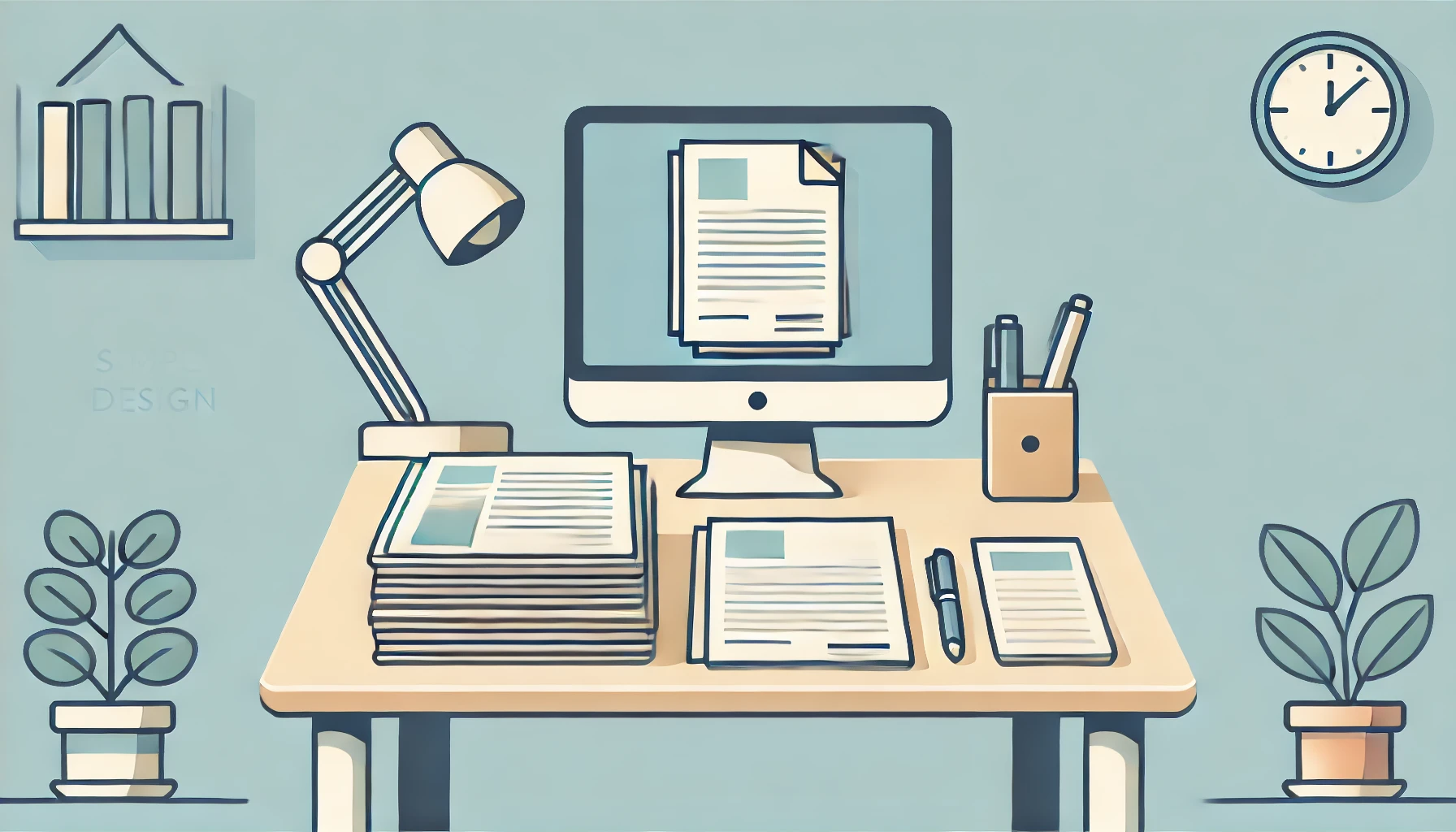
中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!
社会保険の扶養に入る配偶者や子どものデメリット
社会保険の扶養に入ることで、一定のメリットがある一方で、デメリットも存在します。

合わせて読みたい「従業員50人以下の社会保険加入義務」に関するおすすめ記事
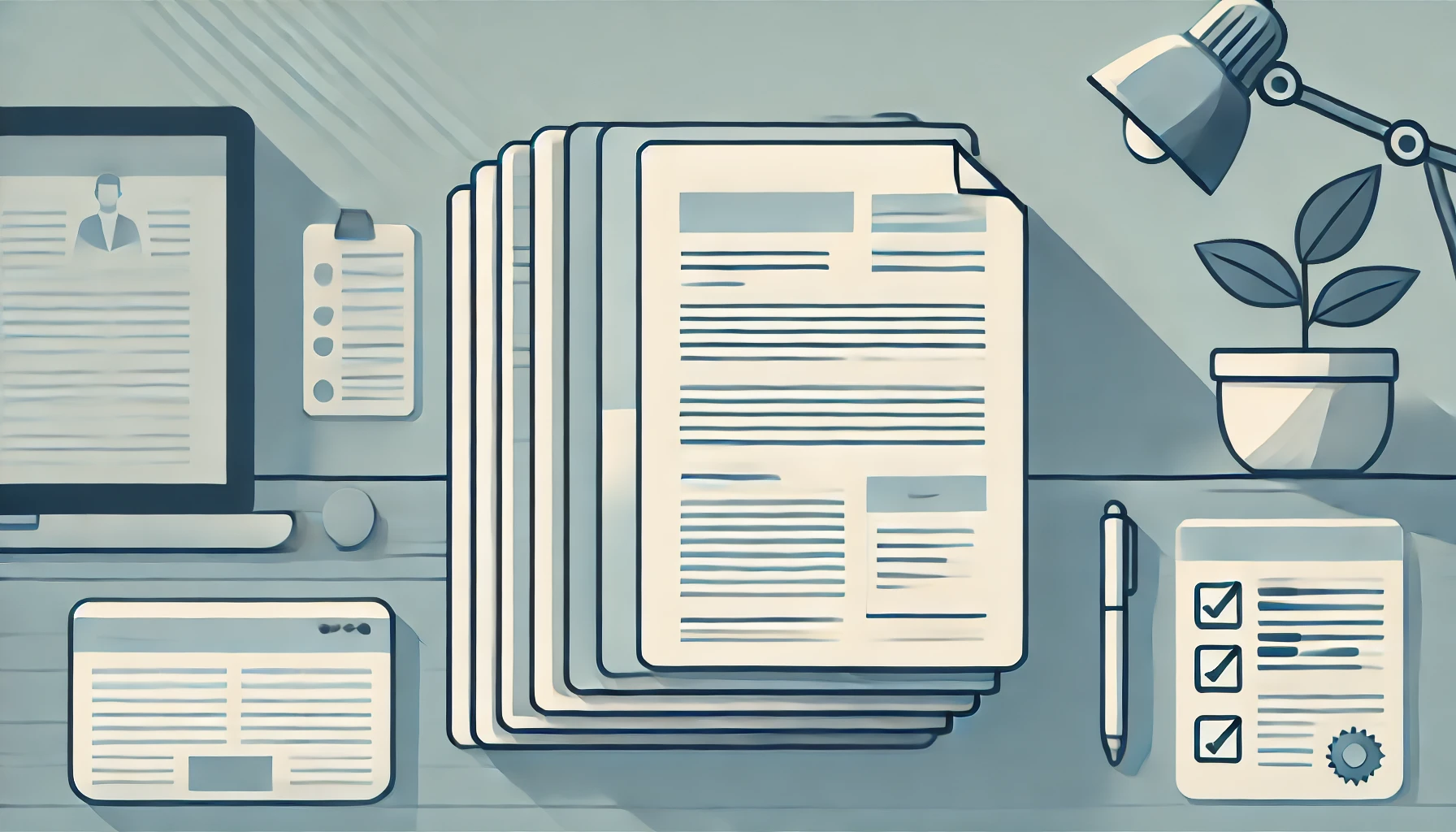
従業員50人以下の会社は社会保険の加入条件に該当する?今後の加入対象拡大についても解説!
本記事では、50人以下の企業が社会保険の加入条件に該当するかどうかの判断基準や、今後の段階的な適用スケジュールについて詳しく解説します。
社会保険の扶養に入るデメリット①:厚生年金に加入できず、将来の年金額が少なくなる
パートやアルバイトで働く配偶者が社会保険の扶養に入り、勤務先の厚生年金に加入しない場合、将来受け取れる年金額が少なくなる可能性があります。
厚生年金に加入すれば、老後の年金額を増やせるメリットがありますが、社会保険の扶養内にとどまることで、国民年金(基礎年金)のみとなり、受給額が限られてしまいます。国民年金の満額は月額約6.6万円程度であり、老後の生活資金としては不十分と感じるケースもあります。
社会保険の扶養に入るデメリット②:傷病手当金を受け取れない

合わせて読みたい「社顔保険料は4月から6月で決まる?」に関するおすすめ記事
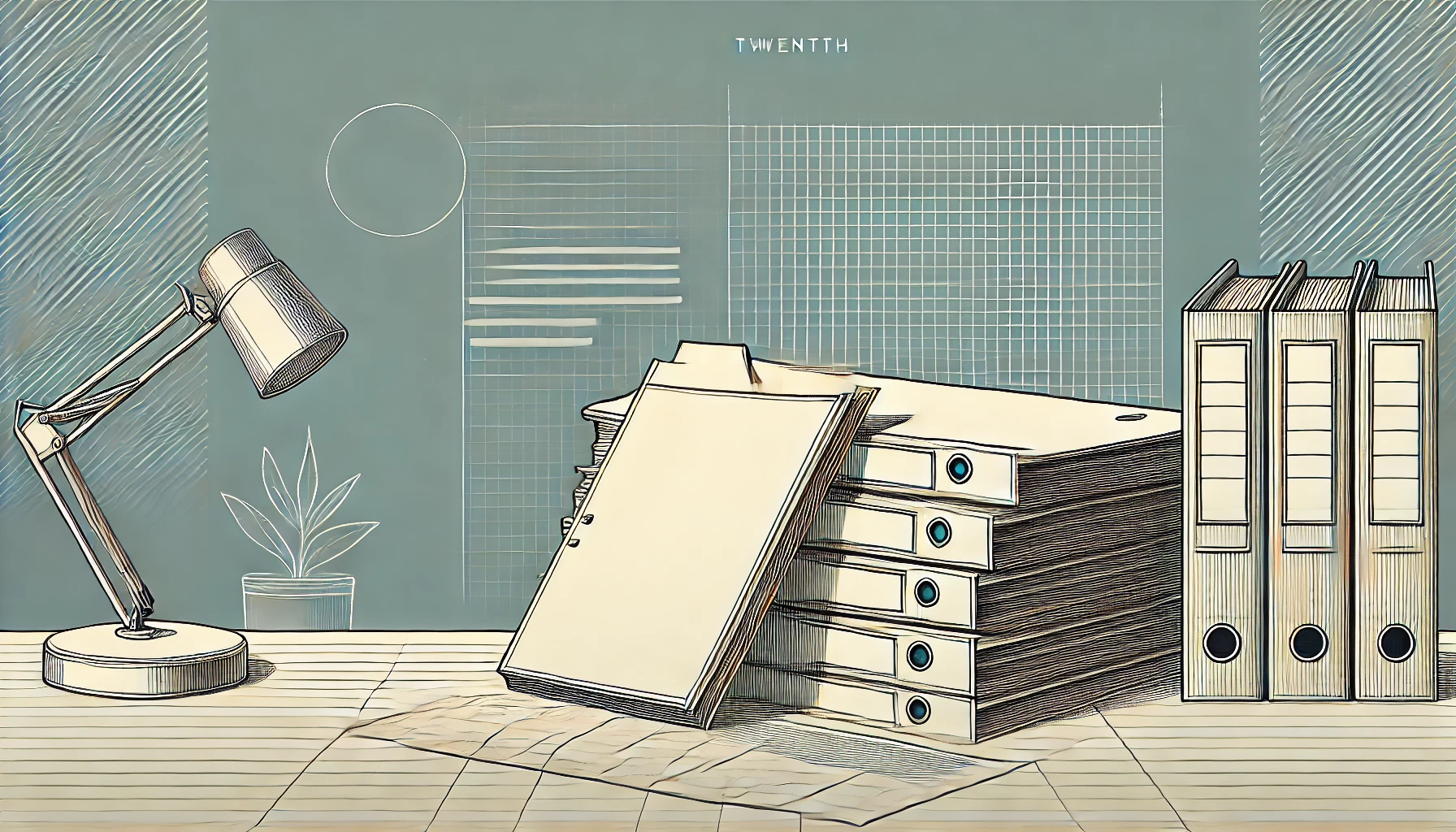
社会保険料は4月から6月で決まる!4月5月6月に残業すると手取りが減る理由を解説
会社員が健康保険に加入している場合、病気やケガで仕事を休んだ際には、傷病手当金を受け取ることができます。しかし、社会保険の扶養に入っている被扶養者は、こうした手当の対象外となります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
そのため、扶養内で働く場合に長期間の病気やケガで働けなくなると、収入が途絶えてしまうリスクがあります。
社会保険の扶養に入るデメリット③:働く時間を制限され、キャリア形成に影響が出る
社会保険の扶養に入るためには、一定の年収制限(例:130万円未満)があり、収入を抑える必要があります。このため、フルタイムで働くことを避けたり、勤務時間を調整したりすることで、キャリア形成の機会を制限される可能性があります。
短期的には社会保険の扶養内にとどまることで税金や社会保険料の負担を抑えられるものの、長期的には昇給の機会を逃したり、スキルアップの機会を失うことで、将来の収入に影響を与える可能性があります。
社会保険の扶養加入に関するおすすめ記事
社会保険の扶養者になるデメリット・デメリット

家族を社会保険の扶養に入れることで得られるメリットとデメリットについて解説します。社会保険の扶養制度を利用する際は、これらのポイントを理解しておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
家族を社会保険の扶養に入れるメリット
ここでは、被保険者が家族を社会保険の扶養に入れることで得られる主なメリットを3つ紹介します。社会保険の扶養制度を活用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。
家族を社会保険の扶養に入れるメリット①:税負担が軽減する
家族を社会保険の扶養に入れることで、扶養者の税金負担が軽減されるメリットがあります。配偶者を社会保険の扶養に入れた場合、配偶者控除や配偶者特別控除が適用され、税負担を抑えられます。

合わせて読みたい「従業員3人の社会保険」に関するおすすめ記事

従業員3人の場合に社会保険の加入義務はある?社会保険未加入のときの罰則も解説!
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険の扶養に入るためには、扶養される人の年間所得が一定額以下である必要がありますが、その条件を満たせば、扶養する側と扶養される側の双方に税制上のメリットが生じます。
家族を社会保険の扶養に入れるメリット②:扶養する人の社会保険料が増えない
社会保険では、健康保険の被保険者が扶養する家族(被扶養者)を増やしても、被保険者の社会保険料が増えることはありません。
特に、全国健康保険協会(協会けんぽ)などの社会保険では、扶養する配偶者を追加しても、厚生年金保険料が増えることはなく、社会保険料の負担は個人単位ではなく世帯全体で抑えられます。
社会保険の扶養に関するここがポイント!

これにより、配偶者や親を社会保険の扶養に入れることで、家計全体の負担を軽減できる可能性があります。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
家族を社会保険の扶養に入れるメリット③:扶養手当を受けられることがある
勤務先によっては、社会保険の扶養家族がいることで扶養手当が支給される場合があります。
企業によって支給額や支給対象は異なりますが、扶養手当がある職場に勤めている場合、社会保険の扶養制度を活用するメリットはさらに大きくなります。扶養手当は、配偶者・子ども・親など、社会保険の扶養に入れている家族が対象となることが多いため、勤務先の制度を確認しておきましょう。
家族を社会保険の扶養に入れるデメリット
社会保険の扶養に家族を入れることで得られるメリットがある一方で、デメリットもあります。扶養することで発生する可能性のある負担について理解しておきましょう。
① 医療費や介護サービス使用料の負担が増える可能性がある
特に高齢の親を社会保険の扶養に入れる場合、医療費の自己負担限度額が変わる可能性があります。
社会保険の扶養に入ることで、健康保険の被扶養者として扱われますが、高齢者の場合は、自己負担割合が上がるケースもあります。また、親の年収が低く、十分な貯蓄がない場合、医療費や介護サービス利用料を扶養者が負担する必要があるため、家計への影響を考慮することが大切です。

合わせて読みたい「社会保険の無料相談窓口」に関するおすすめ記事
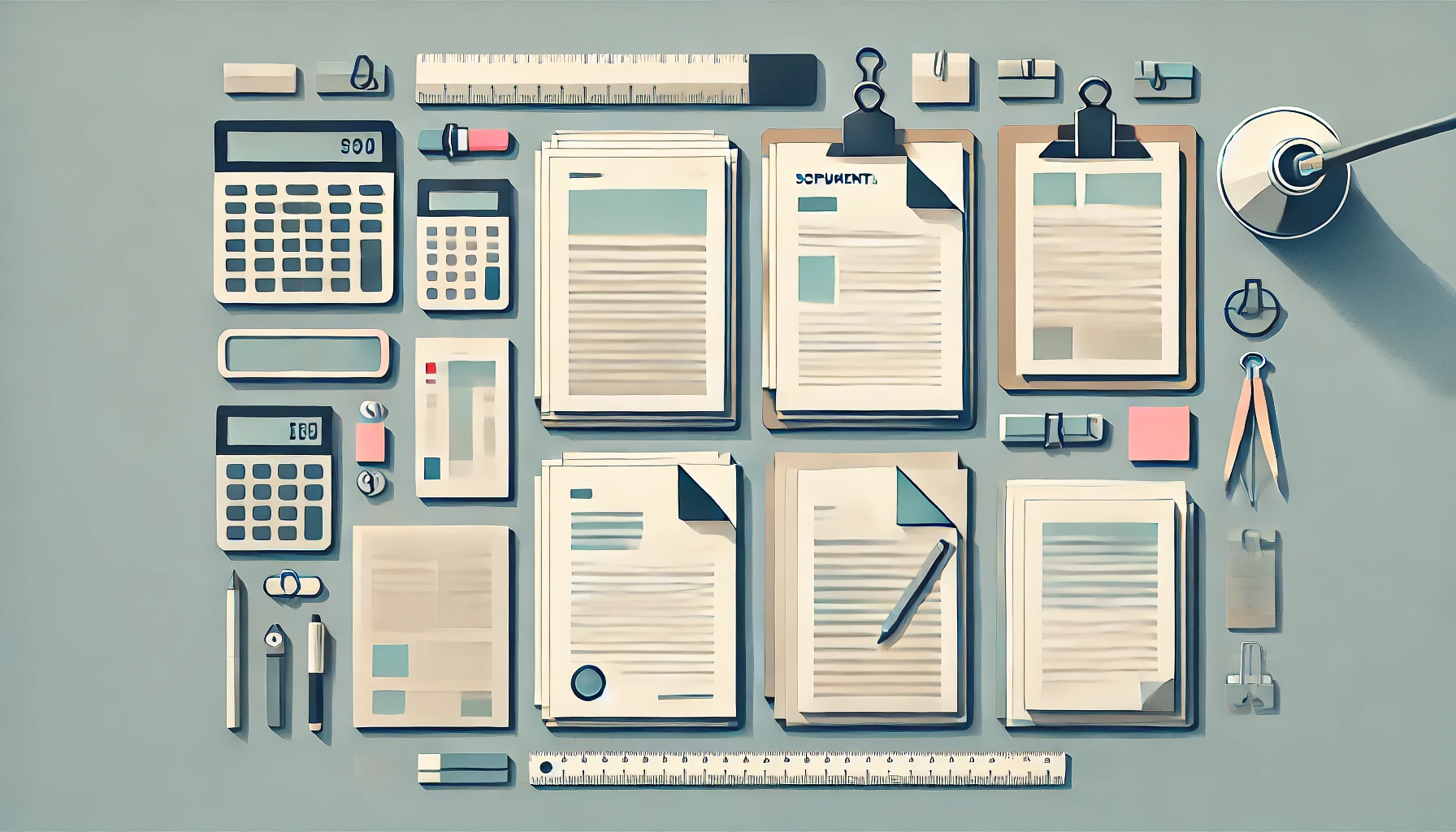
法人の社会保険の無料相談窓口はどこ?困ったときの問い合わせ先を紹介
② 生活費の負担が増える可能性がある
親族を新たに社会保険の扶養に迎えると、生活費の負担が増える可能性があります。
特に、高齢の親を社会保険の扶養に入れ、同居する場合、食費や光熱費などの生活費が増加することが考えられます。また、二世代・三世代で暮らす準備ができていない場合、新しい住まいへの引っ越し費用や、バリアフリー改修費などの初期費用がかかることもあります。
このように、社会保険の扶養制度を利用することで、税金や社会保険料の負担を軽減できるメリットがある一方で、医療費や生活費の負担が増える可能性もあるため、事前に検討することが重要です。
社会保険の扶養加入に関するおすすめ記事
社会保険の扶養に入るための手続き方法

配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる際は、社会保険の被扶養者の要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。社会保険の被扶養者となる事実が発生した日から5日以内に、「被扶養者(異動)届」と必要な添付書類を、所轄の年金事務所または事務センターに提出する必要があります。

合わせて読みたい「社会保険調査」に関するおすすめ記事

社会保険調査は厳しいのか?年金事務所の調査がくる理由と流れを解説
特に配偶者を社会保険の扶養に入れる場合、「被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」に記入することで、厚生年金の第3号被保険者への切り替え手続きも同時に行えます。厚生年金の扶養のみを切り替える場合は、「第3号被保険者関係届」を提出することで対応可能です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
提出方法には、窓口持参や郵送、電子申請に加え、CDやDVDなどの電子媒体を利用することもできます。社会保険の扶養に関する手続きを迅速かつ正確に行うため、適切な方法を選択しましょう。
社会保険の扶養加入に関するおすすめ記事:扶養とは? 扶養控除の条件や対象となる範囲などをわかりやすく解説
まとめ

社会保険における健康保険や厚生年金保険では、一定の条件を満たす親族を社会保険の扶養に入れることができます。特に健康保険では扶養の範囲が広く、配偶者だけでなく子や親なども対象となる一方、厚生年金保険の扶養(第3号被保険者)は配偶者のみに限定される点に注意が必要です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
また、社会保険の扶養に入れるためには、収入条件を満たしているかを正確に確認することが重要です。
社会保険の手続きは、年金事務所や協会けんぽで行うことができます。ただし、健康保険組合に加入している企業に勤務している場合は、各健康保険組合で手続きを行う必要があるため、自身の保険者(保険の運用元)がどこなのかを正しく把握しておきましょう。
社会保険の扶養加入に関するおすすめ記事:社会保険の扶養とは?年収の壁についても解説
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事

会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日














SoVaをもっと知りたい!