会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!
カテゴリー:
公開日:2025年10月
更新日:2026年1月10日
会社を立ち上げたいと考えたときに、最初に気になるのが「会社設立の流れ」ではないでしょうか。会社設立の流れを理解していないと、登記や定款、資本金の準備といった重要な手続きでつまずき、想定以上に時間や費用がかかってしまうことがあります。会社設立の流れは、会社の基本情報を決めるところから始まり、印鑑作成、定款作成と認証、資本金の払い込み、法務局への登記申請という複数のステップで構成されています。
会社設立の流れを正しく把握することで、スケジュールを無理なく組み立てられ、費用の見積りや必要書類の準備もスムーズになります。特に株式会社と合同会社では会社設立の流れや必要な費用が異なるため、自分の事業に合った形態を選ぶには会社設立の流れを比較することが欠かせません。
この記事では、会社設立の流れをスケジュールごとに整理し、登記費用や定款認証の手数料、資本金の考え方、必要書類の詳細までを徹底解説します。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
会社設立を目指す方が「会社設立の流れ」を具体的にイメージできるように、実践的な情報をわかりやすくまとめましたので是非ご覧ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
法人化に関する悩みは全て解決!
専門家が会社設立を無料でサポート
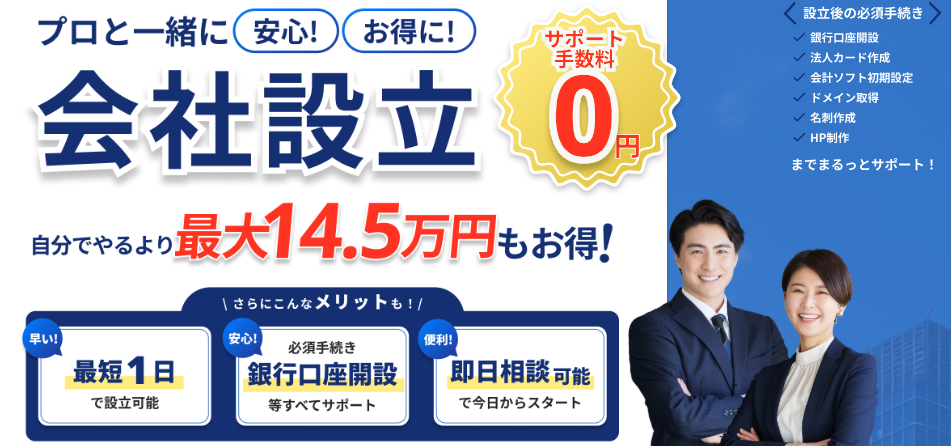
「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「会社設立って費用が高そうで不安…」
そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。
自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。
SoVa税理士ガイド編集部
定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!
参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」
「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。
「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。
会社設立とは?
会社設立とは、法務局で登記申請を行い、法律的に「法人格」を持つ存在を誕生させることを指します。会社設立の流れに沿って手続きを進めることで、事業は経営者個人から切り離された「法人」のものとなり、権利や義務を会社が負担する形になります。個人事業主と異なり、法人としての社会的信用が高まりやすく、資金調達の方法も広がる点が大きな特徴です。ただし、会社設立の流れには費用や事務手続の負担も伴うため、メリットとデメリットを正しく理解しておく必要があります。
会社設立のメリット
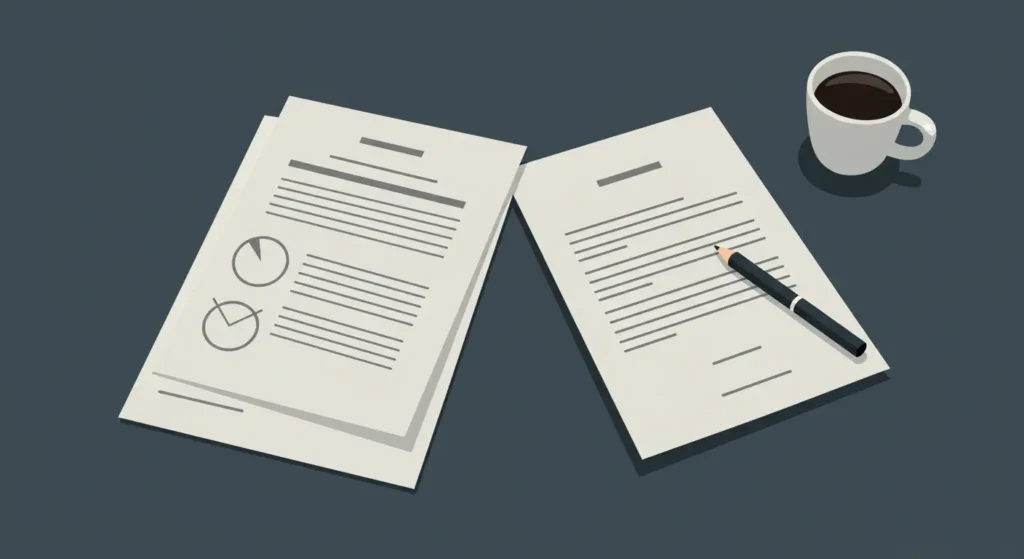
会社設立の流れを踏む最大の利点は、やはり「社会的信用度の向上」「資金調達の幅広さ」「節税効果」「有限責任によるリスク軽減」の4つに整理できます。ただし、実際にはこの4つ以外にも多くのメリットが存在します。以下で詳しく解説します。
会社設立の流れとスケジュールに関するおすすめ記事

会社設立の流れや、会社設立までのスケジュール、必要書類については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立の流れとスケジュールに関する参考記事:「会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について」
社会的信用度の向上
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立の流れを経て法人格を得ると、取引先や金融機関、さらには顧客からの信頼度が大きく高まります。特に法人名義で契約を結べるようになる点は、事業をスケールさせるうえで不可欠です。たとえば、法人向けのオフィス契約やリース契約は個人事業主では難しい場合がありますが、会社設立の流れを完了させて法人として取引を行えば、契約の幅が一気に広がります。
会社設立の流れとスケジュールに関するポイント!

求人の際にも「法人」としての安定感が応募者に伝わりやすく、優秀な人材を採用できる可能性も高まります。
資金調達の選択肢が増える
会社設立の流れを通じて法人化することで、資金調達の幅が一気に広がります。個人事業主の場合は自己資金や個人名義の借入が中心となりますが、法人化後は金融機関からの法人向け融資、ベンチャーキャピタルからの出資、補助金や助成金の利用など、多様な調達方法を検討できます。特にスタートアップ企業では、会社設立の流れを完了していなければ投資家からの出資を受けられないことが多いため、法人化は資金戦略の出発点となります。
節税効果が期待できる
会社設立の流れを経ることで、税務上のメリットも大きく得られます。法人税率は個人の所得税率に比べて低い水準に設定されており、利益が増えるほど法人化のメリットが顕著になります。また、会社設立後は役員報酬を経費として計上でき、給与所得控除を活用することで税負担を軽減できます。さらに、生命保険料や退職金積立金なども法人経費として扱えるケースがあり、将来に向けた資産形成にも有利です。経費にできる範囲が広がることは、会社設立の流れを進める上で大きな魅力といえるでしょう。

合わせて読みたい「株式会社を自分で設立する方法」に関するおすすめ記事

株式会社の設立は自分でできる?自分で株式会社を設立する際のポイントや設立手続きを解説!
有限責任でリスクを限定
会社設立の流れを踏んで法人化すると、経営者の責任範囲が「出資額まで」に限定される有限責任となります。個人事業主は事業の失敗で個人資産まで差し押さえられるリスクがありますが、法人であれば会社の資産と経営者個人の資産は切り離されます。これにより、思い切った事業投資や新規事業の展開にも挑戦しやすくなります。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
リスクを限定できることは、会社設立の流れを進める大きな動機となるでしょう。
会社設立のデメリット
会社設立の流れには大きな利点がある一方で、避けられないデメリットも存在します。特に「設立・維持にかかるコスト」「事務手続の煩雑さ」「社会保険料の負担増」の3つは、多くの経営者が最初に直面する壁です。
設立時・維持にかかる費用
会社設立の流れを進める際には、必ず初期費用が発生します。株式会社の場合、定款認証にかかる公証人役場での手数料(約5万円)、登録免許税(最低15万円)、その他印紙代などを合わせると25万円程度が必要です。
会社設立の流れとスケジュールに関するおすすめ記事

会社設立の流れや、会社設立までのスケジュール、必要書類については以下の記事も是非参考にしてください。
「株式会社設立の流れ|法人登記9ステップ+登記後4ステップを解説」
合同会社であれば10万円前後に抑えられますが、それでも個人事業主として開業する場合に比べて格段に高い出費です。さらに、会社設立の流れを完了した後も、決算ごとの申告や税理士への顧問料、会計ソフトの費用など、維持費用が毎年発生します。
事務手続が煩雑になる
会社設立の流れを踏むと、税務署・都道府県税事務所への届出、年金事務所や労働基準監督署への手続など、数多くの行政手続きを行う必要があります。設立後も法人税や消費税、社会保険関連の申告や納付が発生し、個人事業主に比べて事務負担は大幅に増加します。これを怠ればペナルティが課される可能性もあるため、会社設立の流れを選択する際には、必然的に税理士や社労士などの専門家の力を借りるケースが多くなります。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
会社設立の流れやスケジュールについては、以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立の流れとスケジュールに関する参考記事:「会社設立とは?必要な手続と費用、設立までの流れを詳しく解説」

合わせて読みたい「会社設立 司法書士」に関するおすすめ記事

会社設立の手続きは司法書士に依頼できる?委託できることと費用相場を解説!
社会保険料の負担増
会社設立の流れを経て法人になると、社会保険への加入が義務となります。役員も従業員と同様に健康保険・厚生年金に加入する必要があり、その保険料は会社と個人が折半して支払います。従業員を雇用する場合は会社側の負担も増え、結果としてキャッシュフローに影響を及ぼすことがあります。個人事業主の国民健康保険や国民年金に比べて保険料が高額になることが多いため、会社設立の流れを進める前に資金計画をしっかり立てておくことが重要です。
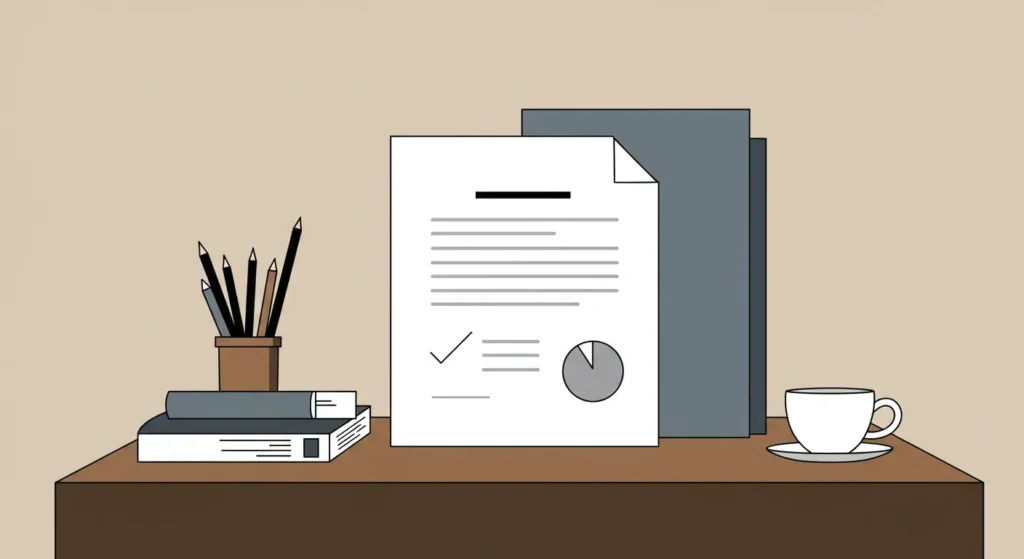
会社設立の流れ|登記完了までの6ステップ
会社を立ち上げたいと考えたとき、最初に押さえておくべきなのが「会社設立の流れ」です。会社設立の流れを理解していないと、必要書類を揃えられなかったり、費用やスケジュールで予想外のトラブルに直面したりする恐れがあります。一般的な会社設立の流れは、法務局に登記申請を行い、10日前後で登記が完了することで法人が正式に誕生します。
特に株式会社の設立では「発起人」と呼ばれる人が会社設立の流れを主導します。発起人は会社設立に必要な情報を決め、定款を作成し、資本金を払い込み、登記申請までを進める重要な役割を担います。会社設立の流れを円滑に進めるためには、発起人が全体のステップを正しく理解し、効率的に準備を進めることが欠かせません。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
ここからは会社設立の流れを6つの手順に分けて、登記完了までの詳細を解説します。
会社設立の流れ①
会社設立に必要な基礎情報を決定する
会社設立の流れの第一歩は、会社の基本情報を決めることです。定款に記載する内容として、会社形態、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金、会社設立日、会計年度、役員や株主の構成などがあります。これらの項目を定めることで、会社設立の流れにおける土台が固まります。

合わせて読みたい「会社設立時に法務局で行う手続き」に関するおすすめ記事

会社設立時に法務局で行う手続きを解説!会社設立登記に必要な書類も紹介
会社形態としては、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つがあり、最も一般的で社会的信用度が高いのは株式会社です。会社設立の流れを重視して信用力や資金調達の可能性を広げたいなら株式会社、設立費用を抑えてシンプルに会社設立の流れを進めたいなら合同会社、といった選択肢があります。
会社設立の流れとスケジュールに関するポイント!

商号は会社名であり、会社設立の流れにおける看板となる存在です。使用できる文字や符号にはルールがあり、他社と紛らわしい名称を避ける必要があります。
事業目的は将来のビジネスも見据えて記載し、本店所在地は自宅やバーチャルオフィスも利用可能ですが、変更の際には再び登記手続きが必要になります。資本金については1円から設立可能ですが、あまりに少額だと会社設立の流れを進めても信用を得にくいため、運転資金を見据えた設定が望ましいです。

合わせて読みたい「会社設立の費用」に関するおすすめ記事

会社設立の費用はいくらかかる?株式会社と合同会社の設立相場を解説!
会社設立の流れ②
会社用の印鑑(実印)を作成する
会社設立の流れにおいて欠かせないのが印鑑の準備です。法改正により押印義務は緩和されましたが、契約や各種申請で印鑑が必要となる場面は依然として多いです。代表者印(実印)は法務局に届け出る必要があり、サイズや形状に関する規定も存在します。会社設立の流れをスムーズに進めるためには、専門業者に早めに発注し、実印・銀行印・角印などを揃えておくと安心です。
会社設立の流れとスケジュールに関するおすすめ記事

会社設立の流れや、会社設立までのスケジュール、必要書類については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立の流れとスケジュールに関する参考記事:「会社設立の流れを解説!株式会社設立や法人設立に必要な手続き」
会社設立の流れ③
定款を作成する
会社設立の流れで最も重要といえるのが定款の作成です。定款は会社の憲法とも呼ばれ、会社名、事業目的、本店所在地、資本金、発起人の情報などの絶対記載事項を盛り込みます。誤りや記載漏れがあると、会社設立の流れ自体が進まなくなるため注意が必要です。
会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」
定款は紙で作成する方法と電子定款の方法があり、電子定款にすれば収入印紙代4万円を節約できます。会社設立の流れを効率的かつ低コストで進めたい場合は電子定款の利用が一般的です。
会社設立の流れ④
公証役場で定款の認証を受ける
株式会社を設立する場合、会社設立の流れの中で必須となるのが定款認証です。公証役場で定款を提出し、認証を受けることで法的効力が生じます。
会社設立の流れとスケジュールに関する注意点

合同会社の場合はこのステップは不要ですが、株式会社では避けて通れない会社設立の流れです。

必要書類は定款3部、発起人の印鑑証明書や実印、認証手数料、謄本代などです。電子定款を利用すると印紙代が不要になり、会社設立の流れのコスト削減に大きく貢献します。
定款の認証にかかる主な費用
会社設立の流れにおいて、株式会社を設立する場合は定款を公証役場で認証してもらう必要があります。このとき発生する費用は主に「認証手数料」「収入印紙代」「電磁的記録の保存手数料」「謄本代」の4種類です。それぞれの詳細を整理してみましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
認証手数料
定款を公証役場で認証する際には、資本金の額によって手数料が変わります。会社設立の流れを意識して準備するうえで、この手数料は必ず確認しておきたいポイントです。
- 資本金100万円未満:1万5千円(※一定条件を満たす場合)または3万円
- 資本金100万円以上300万円未満:4万円
- 資本金300万円以上:5万円
資本金の金額が定款に明記されていない場合は、会社設立の流れにおける出資額を基準として手数料が決まります。また「◯◯万円以上」といった記載をすると、上限扱いとなり、結果として5万円の手数料が必要になることもあるため注意が必要です。

合わせて読みたい「freee会社設立の費用」に関するおすすめ記事

freee会社設立の費用は無料?会社設立で実際にかかる費用を紹介
収入印紙代(紙の定款のみ)
会社設立の流れとスケジュールに関するおすすめ記事

会社設立の流れや、会社設立までのスケジュール、必要書類については以下の記事も是非参考にしてください。
「会社設立までの手順は?必要な手続きと費用の内訳、メリットを網羅的に解説」
紙の定款を提出する場合には、印紙税法に基づいて4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。これは会社設立の流れの中でも避けられないコストですが、電子定款なら不要になるため、多くの起業家が電子定款を選ぶ理由のひとつです。
電磁的記録の保存手数料(電子定款のみ)
電子定款を利用した場合、公証役場から交付される認証済み定款はCD-RやUSBメモリなどの電子媒体に保存されます。
会社設立の流れとスケジュールに関する注意点

電磁的記録の保存手数料として1回あたり300円が必要です。
紙の定款では発生しない費用ですが、印紙代4万円が不要になるため、会社設立の流れ全体で見れば電子定款の方が費用を抑えやすい仕組みになっています。
謄本代
会社設立の流れで公証役場に定款認証を依頼すると、定款の謄本代がかかります。紙の場合は1ページあたり250円の交付手数料が必要で、認証文のページも含まれます。ページ数によって金額は変わりますが、一般的には2,000円前後になることが多いです。
電子定款の場合は「同一情報」と呼ばれるデータが交付され、電子で取得すれば1通700円、書面で受け取る場合は「700円+20円×(ページ数+1枚)」となります。会社設立の流れを電子化して進める場合でも、この点を見落とさないようにしましょう。
会社設立の流れ⑤
資本金の払い込みを行う
次に進む会社設立の流れは、資本金の払い込みです。発起人の個人口座に資本金を振り込み、その証明書類を作成します。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
この払い込み証明は登記申請の際に必要不可欠であり、会社設立の流れの中でも実務的に非常に重要な工程です。
資本金は法律上1円から可能ですが、実際には社会的信用や運転資金を考慮し、数十万円から数百万円を準備するのが一般的です。会社設立の流れを踏んで法人を立ち上げた後の信用度にも影響するため、戦略的に設定しましょう。
会社設立の流れ⑥
登記申請書類を準備し、法務局で登記申請する
会社設立の流れの最終ステップは、法務局での登記申請です。登記申請書、定款、資本金の払い込み証明、就任承諾書、印鑑届出書など、多くの書類を揃える必要があります。登録免許税として株式会社は15万円以上(資本金額によって変動)を納付します。
会社設立の流れとスケジュールに関するおすすめ記事

会社設立の流れや、会社設立までのスケジュール、必要書類については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立の流れとスケジュールに関する参考記事:「会社設立の流れを7ステップで解説。メリットや費用、補助金まで」
すべてが整っていれば、申請からおよそ10日前後で登記が完了し、正式に法人が誕生します。これで会社設立の流れは完了となり、事業活動を法人として開始できるようになります。
会社設立の流れは6つのステップで構成されており、基礎情報の決定から印鑑作成、定款の作成と認証、資本金の払い込み、そして法務局への登記申請へと進んでいきます。それぞれのステップで必要な書類や費用があり、一つでも欠ければ会社設立の流れは進みません。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!
会社設立の流れとスケジュールに関するポイント!

特に株式会社は会社設立の流れが複雑になりやすいため、事前にスケジュールを立て、必要な準備を整えておくことが成功のカギです。
効率よく会社設立の流れを進めたい場合は、専門家に相談するのも有効です。正しい知識をもとに準備をすれば、会社設立の流れは決して難しいものではありません。
会社設立までのスケジュール例
会社設立の流れを理解するうえで欠かせないのが「スケジュール感」を掴むことです。会社設立の流れを無計画に進めると、必要書類の準備不足や登記の遅れが生じ、予定通りに会社をスタートできない可能性があります。一般的に会社設立の流れは1〜2ヵ月ほどかかりますが、事業目的の調査や定款作成の段階で時間を要するとスケジュールはさらに長引きます。逆に、会社設立の流れを専門家に依頼すれば、スケジュールを短縮できる場合もあります。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
ここでは、株式会社と合同会社に分けて、会社設立の流れとスケジュールの例を紹介します。
自分の状況に合わせて会社設立の流れを選び、スケジュールを最適化することが成功のポイントです。
株式会社設立の流れとスケジュール例
株式会社を設立する際の会社設立の流れとスケジュールは以下の通りです。会社設立の流れを一つひとつ進めることで、登記完了までおおよそ4〜5週間を目安に考えられます。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
会社設立の流れやスケジュールについては、以下のサイトも是非ご覧ください。
「【司法書士監修】会社設立の基礎知識と設立までの流れ・必要な手続」
- 法人の基本情報の決定(約1週間)
会社設立の流れの最初のステップは、会社名、本店所在地、事業目的、役員構成、資本金額といった基本情報を固めることです。会社設立の流れを正しく進めるためには、この基礎を確実に決めることが重要です。 - 会社実印の作成(数日〜1週間)
会社設立の流れに欠かせないのが実印の作成です。代表者印や銀行印、角印を準備し、会社設立の流れの中で必要になる契約や登記の手続きに備えます。 - 定款の作成と認証(約1週間)
会社設立の流れの中心的な工程が定款の作成です。株式会社は公証役場で認証を受ける必要があり、電子定款を選べば印紙代4万円を節約できます。会社設立の流れを効率的に進めるためには、事前予約をしてスケジュールを調整しましょう。 - 出資金の払い込み(約1週間)
会社設立の流れにおいて、資本金の払い込みは登記に直結する重要な手続きです。発起人の口座に資本金を振り込み、証明書を作成して会社設立の流れを次の段階へ進めます。 - 設立登記の申請(約1〜2週間)
会社設立の流れの最終ステップは、法務局での設立登記申請です。登記申請に必要な書類を揃え、提出します。会社設立の流れの中でも登記は最終的なゴールであり、ここを完了することで法人として認められます。通常は1週間程度で登記が完了しますが、法務局の混雑状況によってスケジュールが延びることもあります。
この一連の会社設立の流れを経て、株式会社設立のスケジュールは合計で約4〜5週間が目安です。

合わせて読みたい!「会社設立時の費用」に関するおすすめ記事
会社設立時に税理士に依頼した時にかかる費用とメリットを解説

合同会社設立の流れとスケジュール例
合同会社は株式会社に比べて会社設立の流れが簡易的で、スケジュールも短縮されやすいのが特徴です。
- 法人の基本情報を決定(約1週間)
会社設立の流れの第一歩として、会社名や所在地、事業目的、代表社員などを決めます。会社設立の流れの出発点として重要です。 - 会社実印の作成(数日〜1週間)
代表者印や銀行印を作成します。合同会社の会社設立の流れにおいても、印鑑は契約や届出に必要です。 - 定款の作成(数日)
合同会社の会社設立の流れでは、株式会社と異なり公証役場での定款認証が不要です。そのためスケジュールを短縮でき、数日で手続きが進みます。 - 出資金の払い込み(数日)
出資金を払い込み、払込証明書や領収書を作成します。会社設立の流れの中でもシンプルで、短期間で完了できる工程です。 - 設立登記の申請(約1週間)
会社設立の流れの最終段階として、法務局で登記を申請します。必要書類を整えて提出し、通常は1週間弱で登記が完了します。
合同会社設立にかかる会社設立の流れ全体のスケジュールは、合計で約2〜3週間程度が一般的です。
会社設立の流れとスケジュールに関するポイント!

会社設立の流れは、株式会社なら約4〜5週間、合同会社なら約2〜3週間が標準的なスケジュールです。会社設立の流れは準備不足や法務局の混雑で長引く可能性があるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
また、会社設立の流れを専門家や会社設立支援サービスに依頼すれば、スケジュールを短縮でき、効率的に登記まで進められます。会社設立の流れをしっかり把握し、スケジュール管理を徹底することで、スムーズに法人をスタートさせることができるでしょう。
| ステップ | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| ① 基本情報の決定 | 会社名・所在地・事業目的・役員構成・資本金額などを決定 (約1週間) |
会社名・所在地・事業目的・代表社員などを決定 (約1週間) |
| ② 会社実印の作成 | 代表者印・銀行印・角印を作成 (数日〜1週間) |
代表者印・銀行印・角印を作成 (数日〜1週間) |
| ③ 定款の作成・認証 | 定款を作成し、公証役場で認証を受ける (約1週間・電子定款なら印紙代不要) |
定款を作成するが、公証役場での認証は不要(数日で完了) |
| ④ 出資金の払い込み | 発起人の口座に資本金を振り込み 払込証明書を作成 (約1週間) |
代表社員が出資を履行し、払込証明書や領収書を作成 (数日) |
| ⑤ 設立登記申請 | 法務局に登記申請 (約1〜2週間) |
法務局に登記申請 (約1〜2週間) |
| 合計期間 | 約4〜5週間 (1〜2ヵ月を目安にスケジュールを組むのが安全) |
約2〜3週間 |
会社設立の流れでかかる費用とは?

会社設立を考えるとき、必ず直面するのが「会社設立の費用」です。そして会社設立の費用は、会社設立の流れを進める各ステップごとに発生します。会社設立の流れには、登記申請、定款の作成、資本金の払い込み、印鑑の準備、専門家への依頼といった複数の工程があり、それぞれに会社設立の費用が必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立の流れとスケジュールに関するおすすめ記事

会社設立の流れや、会社設立までのスケジュール、必要書類については以下の記事も是非参考にしてください。
会社設立の流れとスケジュールに関する参考記事:「会社設立の方法や流れは?必要な手続き・費用・最短で成功させるコツを解説」
会社設立の流れを把握せずに準備すると、思わぬ追加コストや時間のロスが発生するため、事前に会社設立の費用の全体像を理解しておくことが重要です。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円(電子定款なら不要) | 40,000円(電子定款なら不要) |
| 定款謄本手数料 | 約2,000円(1ページあたり250円) | 0円 |
| 定款認証手数料(公証人に支払う費用) | 15,000円〜50,000円(資本金や条件によって変動) | 0円 |
| 登録免許税 | 150,000円 または 資本金×0.7%(いずれか高い方) | 60,000円 または 資本金×0.7%(いずれか高い方) |
| 合計 | 約222,000円〜 | 約100,000円〜 |
会社設立の流れでかかる費用①
会社の設立登記にかかる費用
会社設立の流れの最終段階である登記には、会社設立の費用として登録免許税がかかります。株式会社の会社設立の流れでは最低15万円、合同会社の会社設立の流れでは最低6万円が必要です。また「資本金×0.7%」の金額がこれを上回る場合は、その金額が会社設立の費用として必要になります。つまり、会社設立の流れを計画するとき、資本金の大きさによって登記の費用が大きく変動する点を必ず考慮する必要があります。
会社設立の流れでかかる費用②
定款にかかる費用
会社設立の流れでは、必ず定款を作成しなければなりません。会社設立の費用として、紙の定款なら収入印紙代4万円が必要です。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
電子定款であれば印紙代が不要になり、会社設立の費用を大幅に節約できます。
株式会社を設立する会社設立の流れでは、公証役場での定款認証も必要で、ここでも1.5万円〜5万円の費用が発生します。
会社設立の流れとスケジュールに関する注意点

定款のページ数によっては謄本代もかかるため、会社設立の流れを進める際には定款関連の費用も大きな項目になります。
会社設立の流れでかかる費用③
資本金に関する費用
会社設立の流れにおいて、資本金は避けて通れない要素です。法律上は1円からでも設立可能ですが、実際の会社設立の流れでは信用面を考慮して数百万円規模の資本金を準備するのが一般的です。資本金は会社設立の費用としてだけでなく、設立後の会社経営に直結するため、会社設立の流れを考える際には長期的な資金計画と合わせて検討することが求められます。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
会社設立の流れやスケジュールについては、以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立の流れとスケジュールに関する参考記事:「株式会社の設立手続(発起設立)について」
会社設立の流れでかかる費用④
会社印鑑や印鑑証明書の費用
会社設立の流れの中では、会社印鑑の準備も必須です。会社設立の費用として、代表者印や銀行印、角印の作成費用、さらに印鑑証明書の発行費用が発生します。
会社設立の流れとスケジュールに関するポイント!

印鑑の価格は数百円から数万円まで幅広く、印鑑証明書は1通100円〜1,000円程度です。
会社設立の流れを進める中で複数回必要になることが多いため、会社設立の費用には必ず含めておきましょう。
会社設立の流れでかかる費用⑤
専門家に依頼する費用
会社設立の流れを自分で進めることも可能ですが、司法書士や税理士など専門家に依頼すれば手続きがよりスムーズになります。その際の会社設立の費用は5万〜20万円程度が目安です。登記申請を代行できるのは司法書士のみですが、会社設立の流れ全体を安心して任せられる点は大きなメリットです。会社設立の費用は増えますが、正確性やアフターフォローを考慮すると依頼する価値は十分にあります。
会社設立の流れとスケジュールに関するおすすめ記事

会社設立の流れや、会社設立までのスケジュール、必要書類については以下の記事も是非参考にしてください。
「株式会社の設立登記の流れ」
会社設立の費用は、登記費用、定款関連費用、資本金、印鑑費用、専門家依頼費用など多岐にわたります。会社設立の流れを円滑に進めるためには、これらの費用をあらかじめ把握してスケジュールに組み込むことが不可欠です。株式会社であれば会社設立の費用は20万円以上、合同会社であれば10万円前後が最低限の目安ですが、資本金を含めるとさらに大きな金額が必要です。
会社設立の流れを理解し、会社設立の費用を具体的に試算しておけば、安心して法人設立を進められます。これから会社を立ち上げる方は、会社設立の流れを一つひとつ確認しながら、会社設立の費用を計画的に準備することが成功への近道です。
会社設立の流れで必要となる書類
会社設立の流れを進めていく中で、最も重要なのが必要書類の準備です。会社設立の流れでは、登記申請や資本金の払い込み、定款の認証など複数のステップがありますが、それぞれの手続きに必要な書類を揃えておかなければスムーズに進められません。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
特に株式会社と合同会社では、会社設立の流れの中で必要になる書類が一部異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
会社設立に必要な書類は大きく分けて9種類あり、登記申請書や定款、印鑑届出書などは会社設立の流れにおいて必須となります。ここからは、会社設立の流れを意識しながら、それぞれの書類がどの段階で必要になるのか、どんな意味を持つのかを詳しく見ていきましょう。
会社設立の流れで必要となる書類①
登記申請書
登記申請書は、会社設立の流れにおいて最終的に法務局へ提出する中心的な書類です。会社名や本店所在地、資本金、登記すべき事項などを記載し、会社設立の流れを正式に完了させるために欠かせません。

合わせて読みたい「会社設立 法人 種類 税理士」に関するおすすめ記事

【会社設立】法人の種類や設立方法は?会社設立に税理士が必要な理由まで解説!
不備があると登記自体が受理されず、会社設立の流れが止まってしまうため、正確に作成することが求められます。
会社設立の流れで必要となる書類②
登録免許税納付用台紙
会社設立の流れでは、資本金の額に応じて登録免許税を納める必要があります。現金ではなく収入印紙を貼付する台紙を用意し、これを添付して登記申請します。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
株式会社と合同会社では最低税額が異なり、会社設立の流れを進めるうえで注意すべきポイントのひとつです。
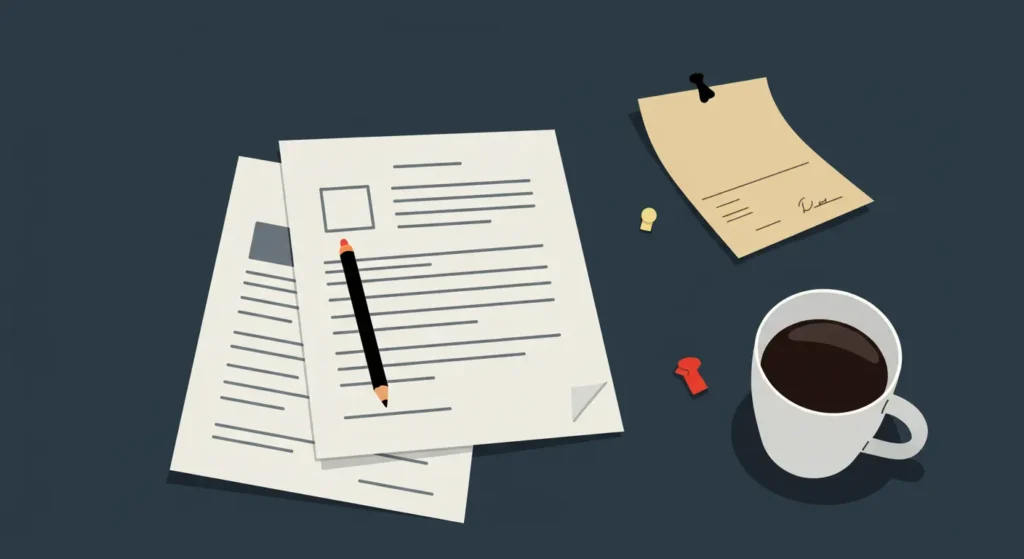
会社設立の流れで必要となる書類③
定款
定款は、会社の憲法ともいえる書類で、会社設立の流れの初期段階で作成します。事業目的や本社所在地、資本金、発起人の情報などを記載し、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます。
会社設立の流れとスケジュールに関する注意点

定款は会社設立の流れの根幹を担うため、漏れや誤りがないよう注意しましょう。
会社設立の流れで必要となる書類④
発起人の決定書
会社設立の流れの中で、本店所在地や代表者を定める際に必要となるのが発起人の決定書です。定款にすべて明記していない場合に提出が必要で、会社設立の流れにおける役割を補完する書類といえます。
会社設立の流れで必要となる書類⑤
設立時取締役・代表取締役の就任承諾書
会社設立の流れでは、役員の就任を正式に承諾したことを証明する書類も必要です。株式会社では取締役と代表取締役それぞれの就任承諾書が求められ、合同会社では代表社員の就任承諾書を提出します。これは、会社設立の流れを法的に有効にするための重要な書類です。
会社設立の流れで必要となる書類⑥
設立時取締役や代表社員の印鑑証明書
会社設立の流れの中で、役員の身元確認として必要になるのが印鑑証明書です。取締役や代表社員の人数分を用意しなければならないため、早めに準備しておくことで会社設立の流れを滞らせずに進められます。
会社設立の流れとスケジュールに関する参考記事:「株式会社の設立手続き」
会社設立の流れで必要となる書類⑦
資本金の払込み証明書
資本金を払い込んだことを示す証明書も、会社設立の流れの中で必須です。通帳のコピーを製本し、発起人が会社に資金を拠出したことを証明します。資本金の払い込みが確認できなければ、会社設立の流れは進められません。
会社設立の流れで必要となる書類⑧
印鑑届出書
会社の実印を法務局に登録するために必要な書類です。会社設立の流れにおける登記申請の段階で提出し、会社の実印を正式に認めてもらうために使われます。

合わせて読みたい!「株式会社と合同会社の設立費用に関する違い」におすすめ記事
株式会社と合同会社の設立費用の違いから会社設立後の費用まで徹底解説!

会社設立の流れで必要となる書類⑨
登記すべき事項の書面またはCD-R
最後に、会社設立の流れを完了させるために必要なのが「登記すべき事項」の提出です。書面やCD-Rに保存したデータを添付し、登記簿に登録される情報として反映されます。これがなければ会社設立の流れは完結しません。
会社設立の流れを正しく理解し、必要な9種類の書類を一つひとつ準備することが、スムーズに法人を立ち上げるカギです。会社設立の流れを把握せずに進めてしまうと、書類不備や提出漏れで登記が遅れるリスクがあります。
「会社設立の流れとスケジュール」編集部
株式会社と合同会社で必要な書類が異なる点も意識しながら、会社設立の流れを段階的に確認して準備を進めましょう。
まとめ:会社設立の流れを理解してスムーズに会社を立ち上げよう
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社を作ろうと考えたとき、最も重要なのが「会社設立の流れ」をどれだけ理解しているかです。会社設立の流れを知らずに準備を始めてしまうと、定款の作成や認証、資本金の払い込み、印鑑の準備、登記申請といった重要なステップで手間取ってしまい、想定以上の時間や費用がかかることになります。だからこそ、会社設立の流れを事前に整理して把握しておくことが、効率的に法人を立ち上げる第一歩です。
会社設立の流れは、株式会社と合同会社で違いがあります。株式会社の会社設立の流れでは、定款認証や登録免許税などの費用が高く、スケジュールも長めになりますが、その分社会的信用度が高く、資金調達もしやすいメリットがあります。合同会社の会社設立の流れは、認証が不要で費用が抑えられ、スケジュールも短期間で済むため、スピード感を重視する起業家に向いています。自分の事業に合った形態を選ぶには、両者の会社設立の流れを比較し、それぞれの特徴を理解することが欠かせません。
また、会社設立の流れにおける費用も無視できないポイントです。登記費用、定款関連費用、資本金、印鑑費用、さらには専門家に依頼する費用まで、会社設立の流れの各段階で発生します。会社設立の流れを正しく理解していれば、必要な費用を事前に見積もり、スケジュールに合わせて余裕をもって準備することができます。
さらに、会社設立の流れを専門家に依頼することで、スケジュールの短縮や手続きのミス防止が可能です。司法書士や税理士などのサポートを活用すれば、会社設立の流れをより確実に、かつスムーズに進められるでしょう。
結局のところ、成功するためには「会社設立の流れ」を全体像としてつかみ、その流れの中で費用、スケジュール、必要書類を一つずつクリアしていくことが大切です。これから起業を考える方は、会社設立の流れを徹底的に理解し、計画的に準備を進めることで、安心して新しい事業をスタートできます。

合わせて読みたい!「会社設立サポート」の税理士依頼に関するおすすめ記事
会社設立時に税理士は必要?依頼するメリットとおすすめのタイミングとは

税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!