役員に社会保険の加入義務はある?役員の社会保険の加入要件についても解説!
カテゴリー:
公開日:2024年9月
更新日:2026年1月9日

今回は、代表取締役を含む役員が社会保険に加入する義務があるかについて詳しく解説します。社会保険の加入義務がある役員が適切に社会保険に加入していない場合、罰則を受けるリスクがあります。そのため、役員の社会保険加入条件をしっかりと把握しておくことが重要です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
一人社長が会社設立をしても社会保険に加入する必要があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
「一人社長でも会社設立時には社会保険は必要?手続きや必要書類を解説!」
「代表取締役を含む役員には社会保険加入の義務があるのか?」「役員が社会保険に加入する条件とは?」などの疑問がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
代表取締役を含む会社役員の社会保険加入に関連する参考サイト:「会社役員の社会保険加入は義務?」
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
【労務手続きを自分でするのはリスク大!】
社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由
社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。
社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。
ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。
また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」
社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。
だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険とは
社会保険制度とは、社会生活の中で生じるさまざまなリスクに備えるための公的な強制保険制度です。国や公的な団体が運営し、主に会社員や役員、公務員が社会保険に加入し、病気やケガ、老後の生活、介護、失業、労働災害といったリスクに対して給付を受けることができます。
社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。代表取締役を含む会社役員や従業員が加入する社会保険のうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを「狭義の社会保険」と呼ぶこともあります。これに対して、雇用保険と労災保険は「労働保険」として分類されます。代表取締役を含む会社役員が社会保険に加入する際には、この区別を理解することが重要です。
役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

役員が社会保険に加入する際の説明をする前に、社会保険のていぎについて以下の記事を参考に確認しておきましょう。
「社会保険とは?加入条件や種類、国民健康保険との違いをわかりやすく」
役員の社会保険の加入条件
会社の役員の場合、労働時間や賃金が定められていないため、社員のような社会保険の加入要件が明確に存在しません。

しかし、代表取締役のような役員であって、役員報酬が支払われている場合は、社会保険に加入しないといけません。常勤の取締役など、役員報酬が支払われる役員も同様に社会保険の加入対象です。
「社会保険の加入条件」編集部
社会保険の適用対象が段階的に拡大され、50人以下の企業にも順次義務化されます。
令和9年から令和17年にかけて、従業員数の条件が段階的に引き下げられ、最終的には全ての企業が対象になります。
参考:厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」
ただし、役員報酬が支払われていない場合は、社会保険に加入する義務は発生しません。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

役員報酬を支払わない場合の社会保険の加入に関する概要については以下の記事がおすすめです。
「解説!一人法人の社会保険加入|「役員報酬ゼロ」の加入義務は?「副業で法人設立」は本業先にばれる?」
なぜなら、役員報酬をゼロに設定した場合、役員の報酬から厚生年金保険料や健康保険料を差し引くことができないため、社会保険には加入できません。さらに、役員報酬が非常に低額で、標準報酬月額表に記載されている第1等級の保険料を徴収できない場合も、社会保険の非加入扱いとなります。このように、役員報酬の額によって社会保険への加入が制限されるケースがあります。

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介
【参考】役員報酬とは?
役員報酬とは、税務上「役員」に支払われる報酬を指し、役員が受け取る報酬です。この「役員」は、実際に従業員として業務を行うのではなく、会社の経営陣としての役割を果たす人々を指します。
役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

役員報酬の定義は以下の記事が参考になるでしょう。
「役員報酬とは?給与との違いや金額の決まり方について解説」
会社の「役員」に支給される報酬は、社会保険の「役員報酬」として扱われます。たとえ役員報酬の支給頻度が少なくても、この報酬は社会保険の「役員報酬」に該当します。
次に、役員報酬の対象となる役員の種類について見ていきます。社会保険の「役員報酬」の対象となる役員は以下のとおりです。
・取締役
・会計参与
・監査役
・執行役または会計監査人
・理事
・監事

合わせて読みたい「みなし役員とは」に関するおすすめ記事

みなし役員とは?判定フローチャート付きで配偶者や給与の影響を解説
【参考】役員報酬の設定を株主総会議事録に記載するポイント
会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって決定する」と定められています。
ただし、定款に詳細を記載してしまうと、変更が必要な際に手続きが煩雑になることから、実務上は株主総会で決議する方法が一般的です。通常、株主総会で役員報酬の総額を決定し、その後、取締役会で各役員への配分額を決めるケースが多く見られます。なお、取締役会が設置されていない場合は、取締役が分配額を決定します。決定した内容については議事録として作成し、保管しておくことが重要です。この議事録は、税務調査の際に説明資料として役立つため、正確に記録しておきましょう。
詳しくは以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい「役員報酬の株主総会議事録の作成方法」に関するおすすめ記事

役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

会社法第329条では、役員として「取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人」が規定されています。理事は主に団体で使用される役職であり、監事は公益法人や協同組合で監督の役割を担う「役員」に該当します。これらの「役員」が受け取る役員報酬は、社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の「役員報酬」として適用されることがあります。
「役員の社会保険加入」解説部
役員の範囲などについては、こちらの記事がおすすめです。
記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
社会保険に加入できる事業所は?
役員には社会保険の加入要件が存在しませんが、従業員にはいくつか社会保険の加入要件が存在します。
まず、社会保険への「加入」は、事業所ごとに判断されます。社会保険の「加入」には、事業所が「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つのタイプに分かれます。それぞれの役員や従業員に関する条件について詳しく見ていきましょう。
「社会保険」編集部
社会保険の未加入や、社会保険料の滞納に科される罰則については、【社会保険未加入の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!】の記事をご覧ください

合わせて読みたい「月の途中で 入社 社会保険料」に関するおすすめ記事

月の途中で入社した場合の社会保険料はどうなる?計算方法も解説!
強制適用事業所

「強制適用事業所」とは、法律に基づいて社会保険への加入が義務付けられている事業所です。この場合、事業所の意向にかかわらず、以下の条件を満たす事業所は社会保険に加入しなければなりません。社会保険の種類によって条件が異なるため、注意が必要です。
役員の社会保険加入義務に関する参考記事:「一人社長も会社設立時には社会保険加入が必須!必要な書類や手続きをわかりやすく解説」
・常に5人以上の従業員や役員を雇用している事業所(農林漁業やサービス業を除く)
・国、地方公共団体、または法人で、常時従業員や役員を雇用している事業所
任意適用事業所
「任意適用事業所」とは、強制適用事業所に該当しない場合でも、従業員や代表取締役を含む会社役員の半数以上が社会保険への加入に同意すれば、社会保険に加入できる事業所です。この場合、事業主が年金事務所で手続きを行い、社会保険への加入を確保する必要があります。

合わせて読みたい「社顔保険料は4月から6月で決まる?」に関するおすすめ記事
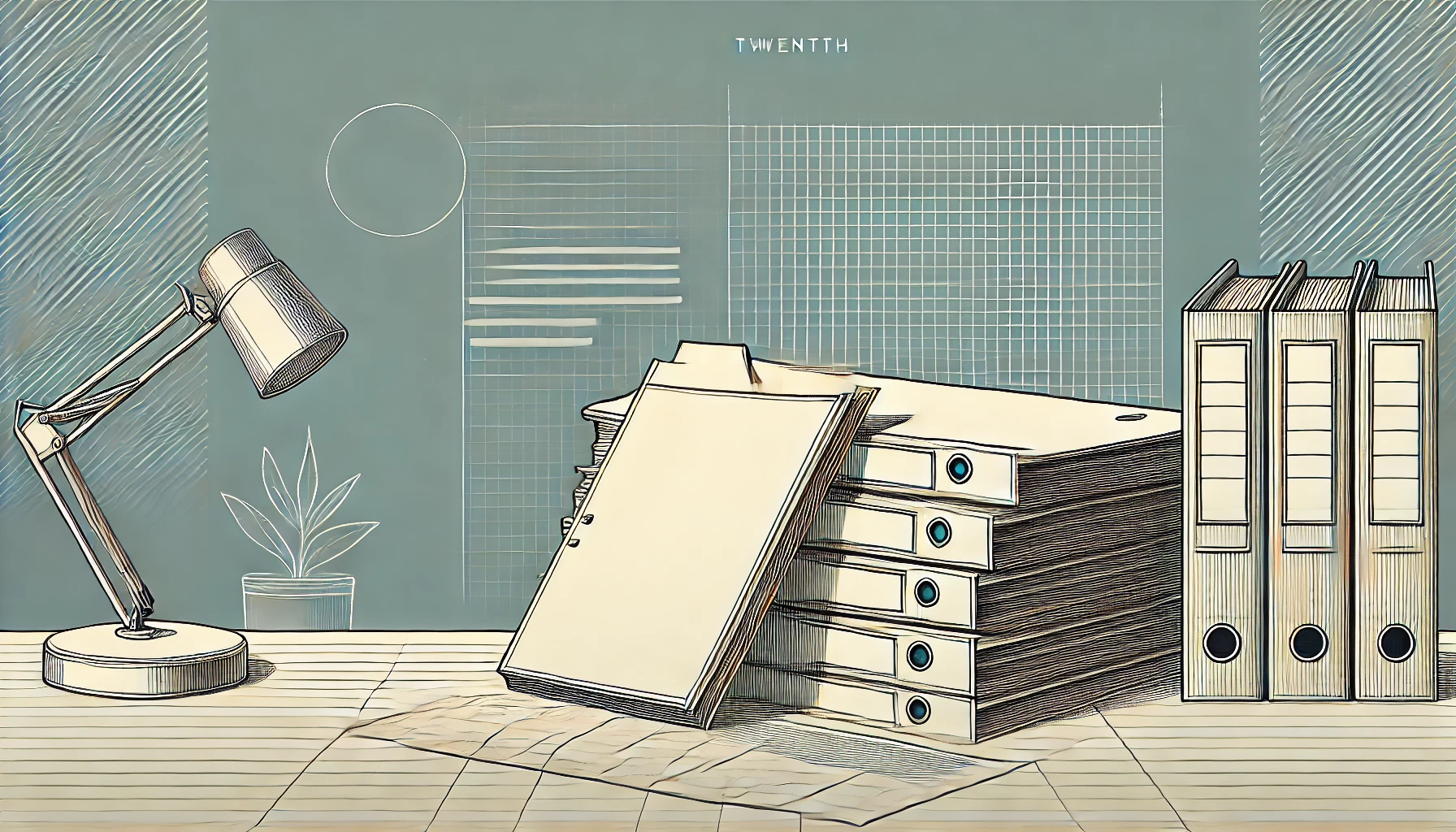
社会保険料は4月から6月で決まる!4月5月6月に残業すると手取りが減る理由を解説
2024年10月からの社会保険に関する法改正
「役員の社会保険加入」解説部
社会保険の加入要件に関する法改正の詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。
役員の社会保険加入義務に関する気をつけておきたい注意点

法改正により、2024年10月から社会保険の「加入条件」が変更されます。この変更により、社会保険の「加入条件」は、従業員数が「101人以上」の事業所から「51人以上」に引き下げられます。
役員の社会保険加入義務に関する参考記事:「二つ以上の会社の役員になった時の社会保険の手続は」
ここで言う「従業員数」とは、社会保険の「加入条件」を満たす被保険者数を指します。具体的には、フルタイム勤務の従業員と、週または月の労働日数がフルタイムの3/4以上の「従業員」が対象です。
従業員数が51人以上の事業所は、条件を満たす短時間労働者も社会保険に加入しないといけません。未加入のままだと、罰則が科せられる可能性がありますので、法改正前に新たに社会保険の「加入対象」となる「従業員」の人数を事前に確認しておくことが重要です。

従業員の社会保険加入条件
健康保険と厚生年金保険への「加入」条件について、役員や常時雇用されている従業員を対象に説明します。

合わせて読みたい「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか?」に関するおすすめ記事

個人事業主から法人化したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリも解説!
・常時雇用されている役員や従業員
・週の所定労働時間が常時雇用されている代表取締役を含む会社役員や従業員の4分の3以上であること、または1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている役員や従業員の4分の3以上であること
まず、社会保険への加入条件として、常時雇用されている役員や従業員が挙げられます。これらの代表取締役を含む会社役員や従業員は、一定の労働時間と労働日数を満たす必要があります。この条件を満たす役員や従業員は、健康保険および厚生年金保険に加入する義務があります。
つまり、常時雇用されている役員や従業員がこれらの基準を満たせば、社会保険の加入対象となり、健康保険と厚生年金保険に加入しないといけません。
パートとアルバイトの社会保険の加入要件

社会保険は、正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートやアルバイトの従業員にも加入が義務付けられています。
具体的には、「所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3以上」のパートやアルバイトの従業員については、報酬額や雇用形態に関係なく、社会保険への加入が必要です。これに該当する従業員がいる場合は、社会保険に加入させることが義務となります。
また、「所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3未満」の場合でも、以下の条件を満たすと社会保険に加入しないといけません。

合わせて読みたい「マイクロ法人の社会保険料」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
・月額賃金(所定)が8.8万円以上であること
・学生でない(定時制や夜学などの学生は除く)
・従業員が101人以上の事業所で勤務していること
役員の社会保険加入に関連する気をつけておきたい注意点

なお、令和4年10月からは「1年以上の継続勤務が見込まれる」という条件がなくなり、社会保険の適用となる事業所の規模も、501人以上から101人以上に変更されました。さらに、2024年(令和6年)10月には、事業所規模の基準が51人以上に引き下げられる予定ですので、加入条件の変更には注意が必要です。
参考:「会社役員の社会保険は義務?加入条件や取り扱いを解説」
「役員の社会保険加入」解説部
令和4年改正の詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
派遣労働者の社会保険の加入要件
派遣労働者における社会保険の加入条件は、フルタイムの正社員やパート・アルバイトの従業員と同様の基準が適用されます。具体的には、派遣労働者が社会保険に加入するには以下の条件を満たす必要があります。
まず、派遣労働者がフルタイムと同じ労働時間である場合、または「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上(一般的には週30時間以上)」かつ「契約期間が2か月以上」である場合には、社会保険への加入が求められます。

合わせて読みたい「個人事業主から法人化 社会保険手続き」に関するおすすめ記事

個人事業主から法人化(法人成り)したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!

もしこれらの条件を満たさない場合は、次の5つの条件を確認して、社会保険への加入が必要かどうかを判断します。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
・月額賃金(所定)が8.8万円以上であること
・学生でないこと(定時制や夜学の学生は除外)
・従業員が101人以上の事業所に勤務していること
役員の社会保険加入に関連するポイント!

このように、社会保険の加入条件はフルタイムの従業員と同じ基準で適用されるため、派遣労働者も含めて、これらの条件を満たすかどうかを確認することが重要です。
「社会保険の加入条件とは?2022、2024年10月の適用範囲の拡大や未加入時の罰則について解説!」

合わせて読みたい「非常勤役員の社会保険」に関するおすすめ記事

非常勤役員は社会保険の加入対象?加入条件について詳しく解説!
役員は社会保険の加入義務があるのか
役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

常勤役員と非常勤役員の社会保険加入義務の違いについては以下の記事を参考にしてみましょう。
「常勤や非常勤役員は社会保険の加入対象になる?加入義務や条件について詳しく解説」
代表取締役を含む会社役員に関する社会保険の加入義務については、いくつかの条件が存在します。役員が社会保険に加入するかどうかは、主に報酬の有無やその額に基づいて判断されます。

専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
具体的には、代表取締役を含む会社役員が報酬を受け取っていない場合や、報酬が非常に低く、労務内容に対して相応でないと見なされる場合には、社会保険への加入義務が発生しません。このため、役員の報酬が社会保険の加入基準に満たない場合は、社会保険に加入する必要はありません。
一方で、代表取締役を含む会社役員が企業から相当の報酬を得ている場合は、基本的に社会保険への加入が必要です。ただし、例外として、報酬があっても非常勤の役員である場合には、原則として社会保険に加入する必要はありません。
常勤役員と非常勤役員の判断基準

合わせて読みたい「役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

役員報酬を経費にする方法を解説!経費にするための要件とは?
非常勤役員については、会社法などで具体的に定義されていないため、社会保険の適用が曖昧になることがあります。例えば、経営会議に月数回出席する社外取締役や非常勤監査役であれば、一般的には社会保険の加入対象外となる可能性が高いです。ただし、非常勤役員であっても、毎週何日か出勤している場合は、以下の基準を総合的に判断して社会保険の加入要件が検討されます。
以下の基準は、社会保険の加入における代表取締役を含む会社役員の状況を判断するためのものです。特に、短時間労働者向けの「社会保険の4分の3基準」(週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であれば社会保険の被保険者となる基準)は、役員には適用されないことに注意が必要です。
1. 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
2. 当該法人における役職以外に、多くの職を兼任していないかどうか
3. 当該法人の役員会などに出席しているかどうか
4. 当該法人の役員として、連絡調整や職員の指揮監督に従事しているかどうか
5. 当該法人において、求めに応じて意見を述べる立場にとどまっているかどうか
6. 当該法人から支払いを受ける報酬が、社会通念上、労務内容に見合ったものであり、実費弁償程度の報酬にとどまっていないかどうか
これらの基準をもとに、非常勤役員が社会保険に加入する必要があるかどうかを判断します。

合わせて読みたい「社長の社会保険」に関するおすすめ記事

社長は社会保険に入れない?社会保険に入れる場合と、入れない場合や注意点を解説します!
役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

常勤役員と非常勤役員の判断基準はこちらのサイトがおすすめです。
「役員と社会保険① ~ 常勤役員・非常勤役員・使用人兼務役員~」

加入義務のある役員が社会保険に加入していない場合の罰則
会社が社会保険に加入しない状態を放置した場合、法的なペナルティや経営リスクが生じる可能性があります。
社会保険の加入義務があるにもかかわらず、事業所や従業員、あるいは代表取締役を含む会社役員を未加入のままにしていると、厳しい罰則が科されることがあります。

合わせて読みたい「社会保険と国民健康保険の違い」に関するおすすめ記事

社会保険と国民健康保険の違いは?切り替え時の手続きについて解説!
本記事では、社会保険(健康保険)と国民健康保険の概要、それぞれの社会保険制度の違い、国民健康保険への切り替えが必要なタイミングや社会保険から国民健康保険への手続きを詳しく解説します。
社会保険に加入しない場合の罰則①
6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
社会保険に加入しないまま、悪質な未加入状態が続いている事業所は、健康保険法第208条などに基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
社会保険の未加入が「悪質」と判断されるのは、虚偽申告を行っていたり、複数回の加入指導にも応じなかったりした場合です。特に代表取締役を含む会社役員についても、加入要件を満たしているのに社会保険に加入しないままでいると、こうした重い処分の対象となることがあります。

合わせて読みたい「従業員50人以下の社会保険加入義務」に関するおすすめ記事
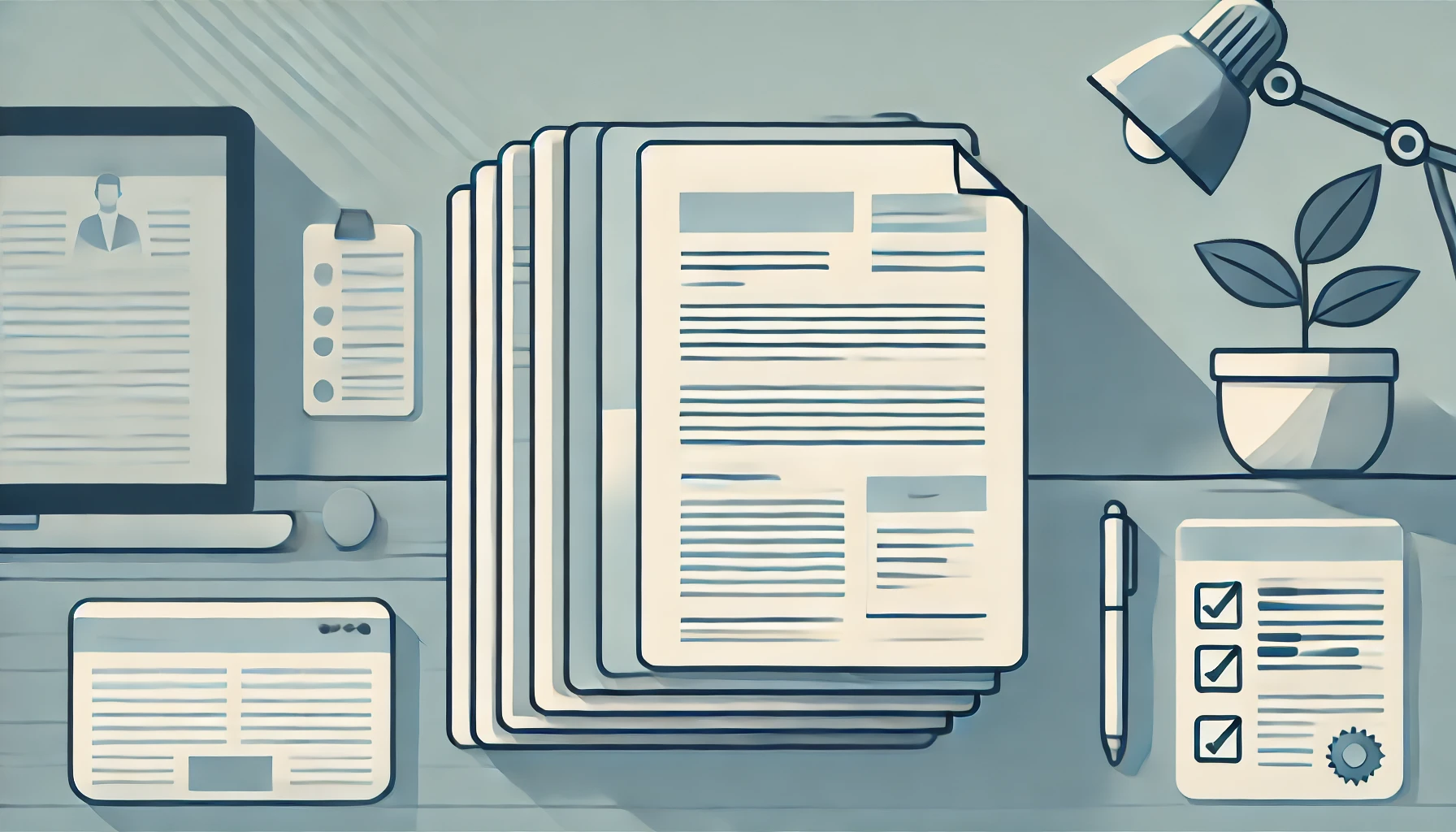
従業員50人以下の会社は社会保険の加入条件に該当する?今後の加入対象拡大についても解説!
本記事では、50人以下の企業が社会保険の加入条件に該当するかどうかの判断基準や、今後の段階的な適用スケジュールについて詳しく解説します。
社会保険に加入しない場合の罰則②
過去2年間に遡及して保険料を徴収される
「会社役員が社会保険に未加入」編集部
会社役員に社会保険の加入義務があるのにも関わらず未加入であった場合、遡って社会保険に加入する必要があるのかに関しては以下のサイトを是非ご覧ください。
参考:「社会保険の遡り加入をすべきケースや支払い方法について」
社会保険の未加入が年金事務所などに発覚すると、強制的に加入手続きをさせられた上で、過去2年間に遡って社会保険料を徴収される可能性があります。
この社会保険料には、代表取締役を含む会社役員に支払った報酬も含まれ、加入対象となる役員が未加入だった場合にも、その分の保険料が遡って請求されます。
役員が社会保険に加入しない場合の罰則に関する気をつけておきたい注意点

保険料は給与だけでなく賞与にも課されるため、一度に多額の現金が必要になり、会社の資金繰りに深刻な影響を与えることがあります。

合わせて読みたい「社会保険の無料相談窓口」に関するおすすめ記事
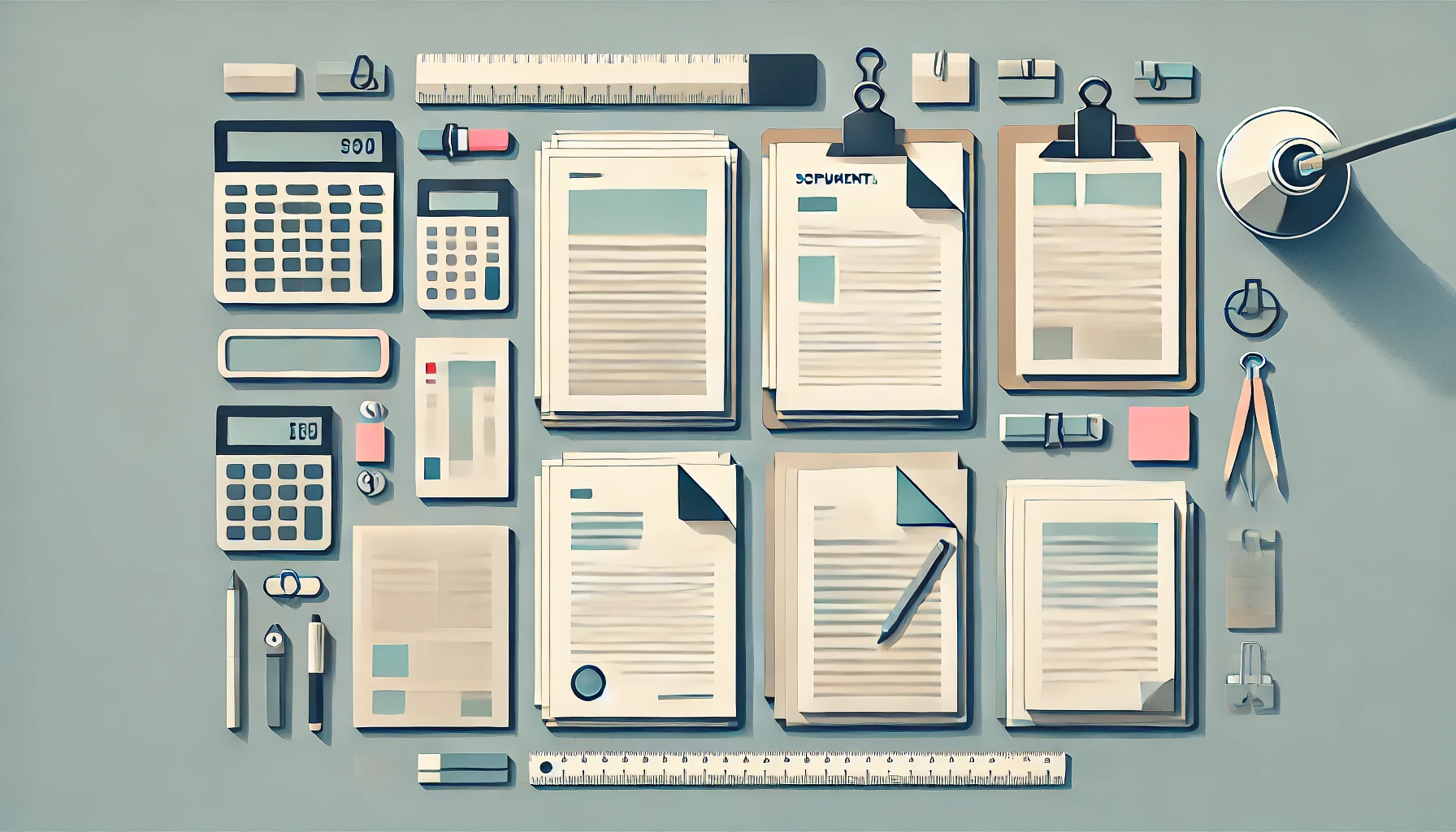
法人の社会保険の無料相談窓口はどこ?困ったときの問い合わせ先を紹介
社会保険に加入しない場合の罰則③
従業員負担分の保険料も企業が支払う可能性がある
社会保険料は、本来は会社と従業員(または役員)が折半して負担しますが、過去に未加入だった分については、会社側が従業員負担分を立て替えて支払う必要があります。
特に、既に退職した従業員や代表取締役を含む会社役員については本人から保険料を回収できないケースが多く、結果的に企業が全額を負担することになります。
役員が社会保険に未加入に関する参考記事:「《会社設立》役員報酬ゼロなら社会保険の加入義務はない?」
「役員が社会保険に未加入」編集部
社会保険に加入しないままでいたことが、後に大きな金銭負担として跳ね返ってくるのです。
社会保険に加入しない場合の罰則④
延滞金が発生する

合わせて読みたい「社会保険料の会社負担割合」に関するおすすめ記事

社会保険料の会社負担割合は?社会保険の計算方法や会社負担の注意点を徹底解説!
社会保険料の納付を怠ると、年金事務所から督促状が届き、指定期日までに納付しなければ延滞金が発生します。
この延滞金は未納額に応じて加算されるため、役員報酬や従業員給与に基づく保険料が高額な場合、延滞金の負担も無視できません。社会保険に加入しない状態が続けば続くほど、最終的な負担額は膨れ上がってしまいます。
社会保険に加入しない場合の罰則⑤
ハローワークに求人を出せない
役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

役員の社会保険加入義務や、役員が社会保険に加入しない場合の罰則に関しては以下の記事が参考になるでしょう。
参考:「社会保険未加入での罰則とは?未加入によって発生する問題や加入条件も解説」
社会保険に加入しない事業所は、ハローワークに求人を掲載することができなくなる可能性があります。
会社として正規の雇用活動を行うには、代表取締役を含む役員や従業員に対して適切に社会保険へ加入していることが前提となるため、未加入の状態では公共機関での採用活動にも制限がかかります。
社会保険に加入しない場合の罰則⑥
会社が損害賠償を請求される可能性がある
社会保険に未加入だったことにより、従業員やその遺族から会社に対して損害賠償請求がなされるケースも報告されています。
たとえば、代表取締役を含む役員や従業員が退職後に年金請求を行った際、厚生年金に未加入だったために給付が受けられず、損害賠償に発展する可能性があります。社会保険に加入しないまま放置することは、後に重大な法的トラブルを引き起こすリスクを含んでいます。
会社役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

代表取締役を含む会社役員が社会保険に加入しない場合の罰則に関しては以下の記事が参考になるでしょう。そもそも代表取締役や社外取締役などの会社役員に社会保険加入義務があるのかについて気になる方は是非ご覧ください。
会社役員の社会保険加入義務に関する参考記事:「会社役員の社会保険は義務?加入条件や取り扱いを解説」
特に、遺族厚生年金などの給付が受けられなかった場合には、企業の責任が問われる可能性もあるため、会社設立後は速やかに役員や従業員の社会保険加入義務を確認し、適切な手続きを行うことが不可欠です。
役員報酬と社会保険でよくある疑問|Q&A
Q.会社設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できる?
会社設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できるケースもあります。
労働者性が強く雇用関係があると認められる場合に限って、雇用保険の加入が認められています。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!
会社設立後の社会保険料に関するポイント

【使用人兼務役員とは】
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者
参考:「使用人兼務役員の範囲」
Q.使用人兼務役員の使用人給与は定期同額である必要がある?
使用人兼務役員の役員報酬に関しては、通常の役員報酬と異なる扱いが認められています。一般的に、役員報酬は「定期同額給与」として、1年間にわたり同額で支給しなければ損金算入が認められません。しかし、使用人兼務役員の場合には、役員報酬に使用人としての給与が含まれており、使用人部分については、毎月金額を変更して支給することが可能です。

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事

会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
つまり、役員報酬ではない使用人としての給与は定期同額である必要はありません。
まとめ
役員の社会保険への加入義務について理解することは重要です。基本的に、役員が報酬を受け取っている場合、社会保険への加入が必要です。ただし、報酬が非常に低く、その労務内容に見合わない場合は、社会保険の加入義務が免除されることがあります。
一方で、非常勤役員に関しては、会社法において明確な定義がないため、社会保険の加入が不確定になる場合があります。例えば、月に数回出勤する社外取締役や非常勤監査役は、一般的には社会保険の加入対象外とされることが多いですが、毎週何日か出勤する場合には、社会保険の加入要件が適用される可能性があります。
社会保険の加入要件には、役員が定期的に事業所に出勤しているかどうか、他に多くの職を兼任していないか、役員会に出席しているか、法人内で指揮監督を行っているか、意見を述べる立場にとどまっていないか、そして報酬が社会通念上妥当であるかが含まれます。これらの基準に基づいて、役員の社会保険への加入が判断されるのです。
総じて、役員の社会保険加入については、その役職の具体的な職務内容や報酬状況に応じて適切な対応を行うことが必要です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「社会保険手続きの期限を超えた場合の対応」に関するおすすめ記事

会社設立から社会保険手続きが5日過ぎたときの対処法とは?会社設立後の社会保険手続きの期限も紹介
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドとの違いを徹底比較!ビジネスオーナーズ ゴールドを持つメリットとは
-
ビジネスカード

2026年1月27日
2
三井住友カードビジネスオーナーズ2枚持ちのメリットは?2枚持ちにおすすめの個人カードや選び方も紹介
-
ビジネスカード

2026年1月27日
3
三井住友ビジネスオーナーズのメリット・デメリットとは?ゴールドとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月27日
4
三井住友ビジネスオーナーズゴールドのメリットは?一般カードやfor Ownersとの違いも解説
-
ビジネスカード

2026年1月27日
5
即日ファクタリング来店不要おすすめ15選!選び方から注意点まで徹底解説
-
資金調達

2026年1月24日













SoVaをもっと知りたい!