役員社宅は経費にできる?要件や節税方法など、役員社宅のメリットと注意点を紹介!
カテゴリー:
公開日:2025年2月
更新日:2026年2月7日
役員社宅は、会社の経費として家賃を計上できるため、経営者や役員にとって大きな節税効果が期待できる制度です。
「役員社宅は経費できる?」編集部
しかし、役員社宅を経費として認められるには、適切な要件や正しい経費計上の手続きが必要です。
本記事では、役員社宅を経費として計上するための具体的な要件や仕組みを分かりやすく解説し、役員社宅を活用した節税のポイントを紹介します。また、役員社宅を経費にする際の注意点や、知っておきたいメリット・デメリットについても詳しくご紹介!役員社宅と経費の関係をしっかり理解して、会社と個人の税負担を賢く軽減しましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
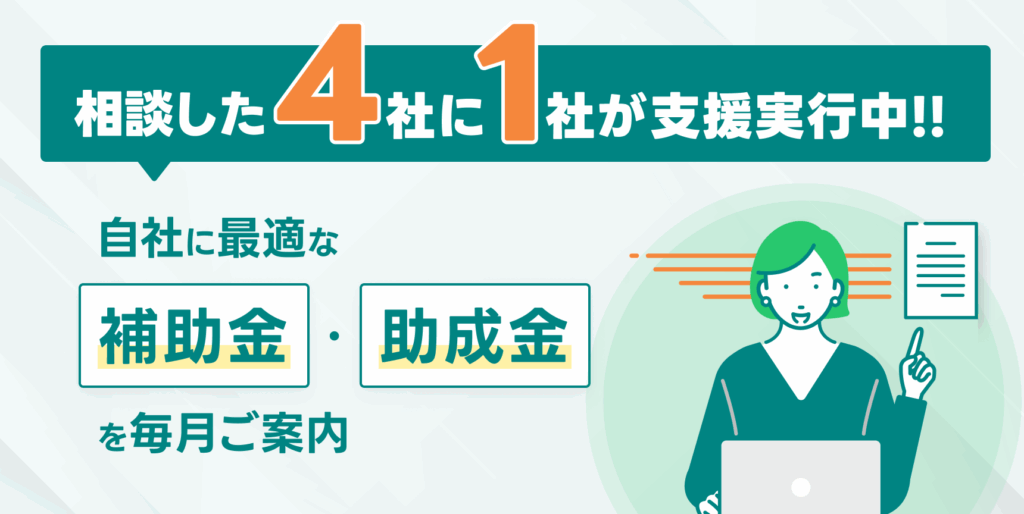
目次
役員社宅とは?

役員社宅を経費にできるのかを解説する前に、そもそも役員社宅とはどのようなものかについて確認しましょう。
役員社宅とは、役員を対象に会社が提供する社宅のことで、通常の従業員向け社宅とは異なる制度です。役員社宅は、法人名義で物件を保有または借り上げ、役員に貸し出す仕組みであり、会社側が家賃の一部を負担することで大きな節税効果が期待できます。
この役員社宅を経費として計上するには、税法上の要件を満たす必要があります。具体的には、次の3つがポイントです。
- 賃貸契約を法人名義で結ぶこと
- 役員が家賃の一部を自己負担すること
- 法人が名義人として大家に家賃を直接支払うこと
また、役員社宅は物件の床面積によって種類が分類されており、それによって役員が支払う家賃額も変わります。役員社宅のルールを守り、正しく活用することで、企業にとっては家賃分の損金算入が可能となり、役員個人にとっても税負担の軽減が図れます。
役員社宅 経費に関するここがポイント!

役員社宅は、節税効果が高い一方で要件やルールを守ることが重要です。役員社宅をうまく活用し、会社と役員双方にとって効果的な経費管理を実現しましょう。
住宅手当と役員社宅の違い
役員社宅と似た制度に「住宅手当」がありますが、両者には明確な違いがあります。住宅手当は福利厚生の一つであり、企業が従業員の住宅費用の一部を補助する制度です。一方、役員社宅は会社が法人名義で物件を借り上げ、役員に貸し出す仕組みです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
役員社宅と住宅手当の違いのポイントは名義人にあります。
- 役員社宅の名義人は「法人」
- 住宅手当の場合の名義人は「個人(役員本人)」
例えば、賃貸マンションの家賃が10万円だとします。
- 住宅手当では、役員が自分の財布から10万円を支払い、その後企業から5万円の住宅手当を受け取ります。
- 役員社宅では、会社が家賃を法人名義で直接支払い、役員がその一部を給与から自己負担する形になります。
このように、役員社宅は法人が家賃を負担する形になるため、家賃の一部を経費として計上できる大きな節税効果があります。役員社宅の導入は、会社と役員双方にとって税務上有利な制度と言えますが、運用には正確なルールに従うことが重要です。
役員社宅を経費にする方法に関連する記事

役員社宅を経費にする方法や、役員社宅を経費にする場合の注意点に関連して、以下の記事も参考になるでしょう。
役員社宅とは?【税理士がコメント】 導入するメリットや経費にして節税する方法・注意点を解説
役員社宅を経費にして節税するメリット

役員社宅を活用する最大のメリットは、家賃の一部を経費(損金)として計上できることです。会社が負担する役員社宅の家賃は法人の経費として損金算入が認められるため、法人税の節税効果が期待できます。さらに、役員社宅を導入すれば、役員個人の家賃負担を大幅に軽減できる点も魅力です。
役員社宅を経費に関する参考記事:「社員の社宅を経費にして節税可能?住宅手当との違いも解説」
このように、役員社宅は会社が家賃を経費として処理できることから、法人と役員双方にとって非常に有利な制度と言えます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
ここでは、役員社宅を経費計上(損金算入)することで得られる具体的な節税効果や、役員にとっての利点について詳しく解説します。
役員社宅を経費にして節税するメリット①
会社負担分を全額経費(損金)にすることで節税が可能!
役員社宅の家賃を会社が負担する際、「会社が支払った家賃の総額から役員が負担した金額を差し引いた額」が経費として計上されます。また、会社が事前に規定を設けておくことで、以下のような費用も経費として計上することが可能です。
- 仲介手数料
- 共益費
- 火災保険料
- 引っ越し費用 など
例えば、役員社宅の家賃が月10万円で役員から5万円を徴収している場合、「10万円-5万円」の5万円が会社の経費として計上されます。さらに、役員社宅の家賃として月10万円を会社が負担する場合、1年間では合計120万円が損金として計上されることになります。
役員社宅を経費にする方法に関連する記事

役員社宅を経費にする方法や、役員社宅を経費にする場合の注意点に関連して、以下の記事も参考になるでしょう。
役員社宅で節税できる?経費にする方法と注意点を解説します
このように、役員社宅の家賃や関連費用を経費にすることで、会社の経費総額が増え、課税対象となる所得が減少します。その結果、法人税の負担が軽減され、節税効果が生まれる仕組みです。役員社宅を活用することで、会社にとっての大きな節税効果が期待できるだけでなく、役員にとっても家賃負担が軽減されるメリットがあります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「法人の節税方法と節税相談に強い税理士への依頼方法」に関するおすすめ記事

法人の節税方法と知っておくべき節税相談に強い税理士の特徴
役員社宅を経費にして節税するメリット②
役員報酬を引き下げて社会保険料を抑えることができる

役員社宅を導入することで、役員の家賃負担が減少し、それに伴い役員報酬を引き下げることが可能になります。役員報酬を引き下げることで、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は報酬額に連動して計算されるため、負担額が減少します。また、所得税や住民税の引き下げにもつながり、役員の手取り額を増やすことが期待できます。

合わせて読みたい「一人社長の自宅を経費」に関するおすすめ記事

一人社長は自宅の家賃を経費にできる?経費計上する方法や注意点を解説!
さらに、役員社宅の家賃を経費として計上することにより、会社全体の経費が増え、課税対象となる法人所得が減少します。その結果、法人税の負担を軽減できるため、会社にとって大きな節税効果があります。また、社会保険料には個人負担分だけでなく法人負担分も発生するため、役員報酬の調整により法人の社会保険料負担も軽減されます。
役員社宅を活用することで、家賃を経費に計上しつつ、社会保険料や税金の負担を抑えられるため、会社と役員の双方に大きなメリットが生まれます。役員社宅を適切に運用して、効率的な節税対策を実現しましょう。
役員社宅を経費にする方法に関連する記事

役員社宅を経費にする方法や、役員社宅を経費にする場合の注意点に関連して、以下の記事も参考になるでしょう。
ひとり社長でも使える!役員社宅を活用した節税方法
役員社宅を経費にして節税するメリット③
役員報酬の手取り額を増やすことが可能
役員社宅を導入することで、役員の手取り(役員報酬)を増やすだけでなく、会社としても経費の有効活用が可能となります。その理由は、役員社宅では家賃の一部を会社が経費として負担できるため、役員個人の家賃負担が軽減されるからです。また、役員報酬から会社へ支払う社宅家賃分が差し引かれることで、所得税や社会保険料、住民税といった税負担も軽減されます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
一方で、役員社宅制度を導入せずに役員が個人で住居を契約した場合、その家賃は役員自身が給与(役員報酬)から全額負担することになります。これでは税効果を最大限に活用できません。しかし、役員社宅を経費として取り入れることで、会社の節税対策にもつながり、個人と会社の双方にメリットが生まれます。
役員社宅を経費にする方法とは?


合わせて読みたい「法人保険で節税」に関するおすすめ記事
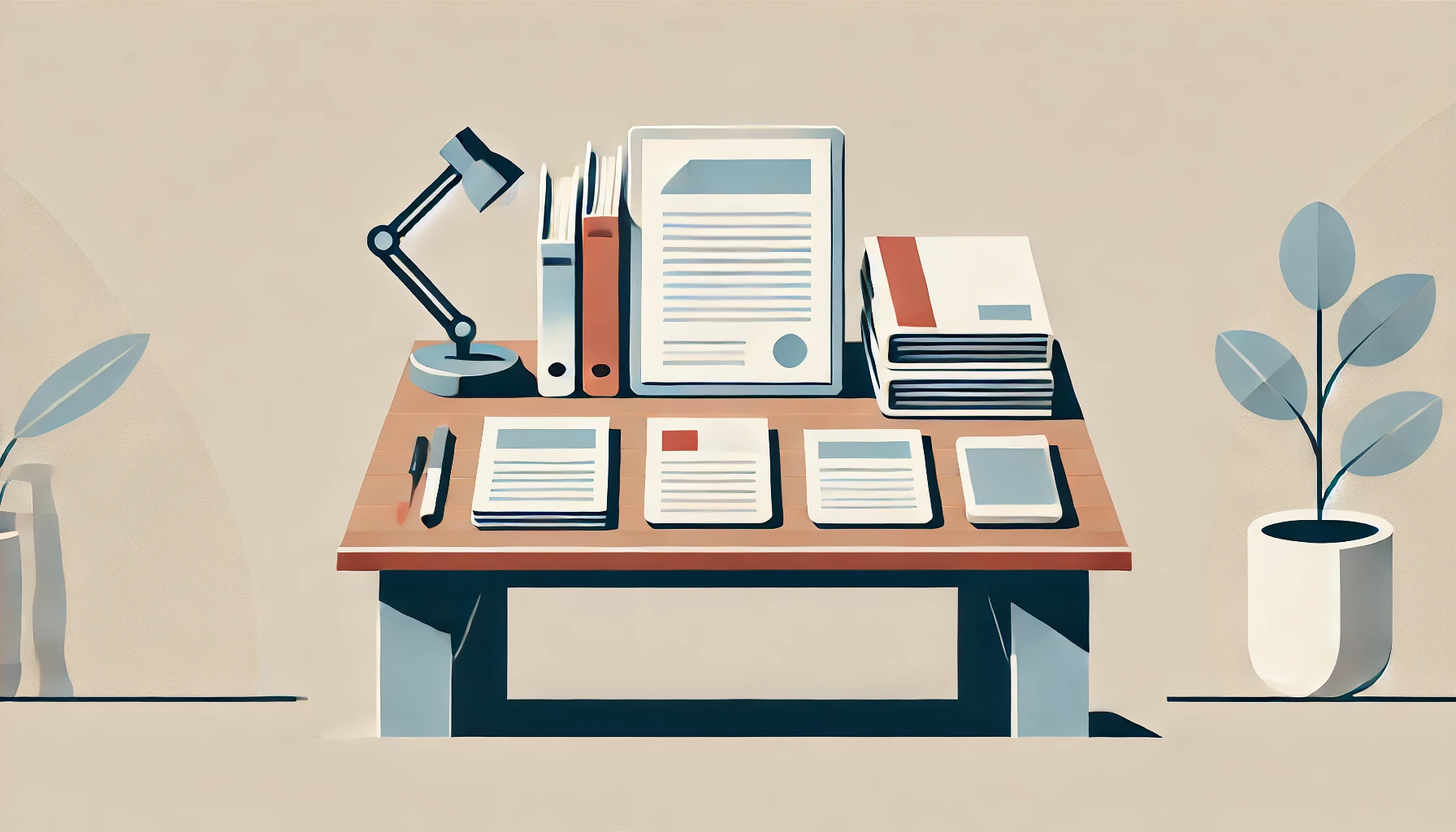
法人保険で節税できる?メリット・デメリットや損金算入について解説
ここでは、会社が役員社宅を導入することで得られる経費計上の仕組みや具体的な方法について解説します。役員社宅を活用することで、会社の節税対策が可能になるだけでなく、役員個人の負担軽減にもつながります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
役員社宅を経費にするための2つの方法をご紹介します。
役員社宅を経費に関する参考記事:「役員社宅を活用した節税方法 | 給与課税に注意」
役員社宅を経費にする方法①
自社所有

合わせて読みたい「非常勤役員の社会保険」に関するおすすめ記事

非常勤役員は社会保険の加入対象?加入条件について詳しく解説!
会社が物件を購入し、その物件を役員社宅として社長や役員、従業員に提供する方法があります。この役員社宅制度を活用すれば、物件の取得にかかる費用(不動産取得税、登記費用、仲介手数料など)や、維持管理に必要な修繕費や固定資産税といったコストを会社の経費として計上することができます。また、物件取得のために借り入れた資金の利息も経費として処理できるため、役員社宅は会社の経費節減や税効果を得るための有効な手段といえます。
役員社宅を経費にする方法に関連する記事

役員社宅を経費にする方法や、役員社宅を経費にする場合の注意点に関連して、以下の記事も参考になるでしょう。
役員・従業員の社宅家賃を経費にする方法
役員社宅を経費にする方法②
借り上げ
一般的な住宅を会社名義で借り、役員社宅として利用する方法があります。この役員社宅の仕組みを活用すれば、会社が貸主に支払う家賃や賃貸契約に関する仲介手数料などを経費として処理することが可能です。役員社宅として運用することで、家賃や関連費用を経費に計上できるため、会社としての節税効果が期待でき、役員個人の負担も軽減されます。役員社宅制度を導入することで、会社の経費を効率的に活用しながら、役員の手取り向上にもつながるメリットがあります。

合わせて読みたい「会社設立で税金対策」に関するおすすめ記事

会社設立で税金対策をしよう!会社設立で節税する方法を紹介
役員社宅の家賃の計算方法
会社の社長や役員であっても、役員社宅制度を利用することで、家賃を経費として処理することが可能です。ただし、役員社宅として認められるためには、会社が「一定金額以上の家賃」を役員から徴収する必要があります。この金額に満たない場合、その差額が給与として課税され、役員社宅を経費として計上することが難しくなります。特に、役員への追加の給与は「役員賞与」とみなされ、経費(損金)として認められないため、会社の税負担が増えるリスクがあります。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
また、「一定金額以上の家賃」の計算方法は、小規模な住宅とそれ以外の住宅で異なります。役員社宅を経費化する際は、これらの条件を満たし、正確な運用を行うことが重要です。役員社宅を経費として有効に活用することで、会社と役員の双方に節税効果をもたらします。
役員社宅を経費にする方法に関する注意点

国税庁が定めた賃貸料相当額とは、住宅の床面積によって「小規模な住宅」「小規模でない住宅」「豪華住宅」の3つのタイプに分類されます。
ただし、これらのうち「豪華住宅」に該当する物件については、法人名義で所有していても経費として計上することが認められません。そのため、以下では「小規模な住宅」と「小規模でない住宅」に関する規定および賃貸料相当額の計算方法について詳しく解説します。
【役員社宅の家賃の計算方法①】
役員社宅が小規模な住宅の場合
小規模住宅の定義
小規模住宅は、以下の条件を満たす住宅を指します。
- 法定耐用年数30年以下の場合:床面積が132平方メートル以下の住宅
- 法定耐用年数30年を超える場合:床面積が99平方メートル以下の住宅
区分所有建物については、共用部分の床面積を按分し、専有部分の床面積に加えた合計で判定されます。
「役員社宅を経費にする方法」編集部
詳しくは以下の国税庁HPをご確認ください。
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
賃貸料相当額の計算方法
小規模住宅における賃貸料相当額は、以下の3項目の合計で算出されます。
・建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
・12円 × (建物の総床面積(平方メートル) ÷ 3.3平方メートル)
・敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
これらを基に賃貸料相当額を計算することで、役員社宅の適正な家賃を算出することができます。
賃貸料相当額の具体例
以下の条件で賃貸料相当額を計算します。
【前提】
- 建物の固定資産税課税標準額:400万円
- 建物の総床面積:70㎡
- 敷地の固定資産税課税標準額:600万円
【計算手順】
建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
400万円 × 0.2% = 8000円
12円 ×(建物の総床面積 ÷ 3.3㎡)
12円 ×(70㎡ ÷ 3.3㎡)= 255円
敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
600万円 × 0.22% = 13,200円
【合計賃貸料相当額】
8000円 + 255円 + 13,200円 = 21,455円
役員社宅を経費にする方法に関連する記事

役員社宅を経費にする方法や、役員社宅を経費にする場合の注意点に関連して、以下の記事も参考になるでしょう。
役員社宅とは?【税理士がコメント】 導入するメリットや経費にして節税する方法・注意点を解説
このように計算することで、役員社宅の賃貸料相当額が21,455円となります。この金額を基に、適正な家賃設定が可能です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
賃料相当額21,455円以上を毎月役員から徴収すれば、所得税の課税は行われないことになります。

合わせて読みたい「マイクロ法人 節税 (税理士)」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は節税できる?個人事業主から法人化するおすすめタイミングも解説!
【役員社宅の家賃の計算方法②】
役員社宅が小規模でない住宅の場合

役員に貸し出す社宅が小規模住宅に該当しない場合、社宅が自社所有か借り上げかによって賃貸料相当額の計算方法が異なります。
1. 自社所有の社宅の場合
賃貸料相当額は、以下の A と B を合計した金額の12分の1で計算します。
A:建物の固定資産税課税標準額 × 12%
※ただし、建物が法定耐用年数30年を超える場合は、12%ではなく10%を使用します。
B:敷地の固定資産税課税標準額 × 6%
この計算式に基づき、自社所有社宅の賃貸料相当額を正確に算出します。

合わせて読みたい「マイクロ法人の社宅」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は社宅を経費にできる?社宅制度を導入する方法や注意点を解説!
賃貸料相当額の具体例
以下の前提で賃貸料相当額を計算してみます。
【前提】
- 建物の固定資産税課税標準額:2,000万円
- 敷地の固定資産税課税標準額:3,000万円
- 建物の法定耐用年数:30年を超える場合(10%を適用)
【計算手順】
・建物の固定資産税課税標準額 × 10%
2,000万円 × 10% = 200万円
・敷地の固定資産税課税標準額 × 6%
3,000万円 × 6% = 180万円
・AとBを合計し、12分の1を計算
(200万円 + 180万円)÷ 12 = 31万6,667円
【賃貸料相当額】
この条件の場合、賃貸料相当額は月額 31万6,667円 となります。この金額を基に、役員社宅の家賃を適正に設定することができます。

合わせて読みたい「出張費を経費」に関するおすすめ記事

出張費はどこまでが経費になる?経費処理の仕訳や相場感を解説!
2.借り上げ社宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、前述の「自社所有の社宅」の計算式で求めた賃貸料相当額のうち、より高い方の金額が賃貸料相当額として適用されます。
賃貸料相当額の具体例
以下の条件で賃貸料相当額を計算します。
【前提】
- 建物の固定資産税課税標準額:1,500万円
- 敷地の固定資産税課税標準額:2,000万円
- 1カ月当たりの家賃:50万円
- 建物の法定耐用年数:30年を超える場合(10%を適用)
【計算手順】
・建物の固定資産税課税標準額 × 10%
1,500万円 × 10% = 150万円
・敷地の固定資産税課税標準額 × 6%
2,000万円 × 6% = 120万円
・AとBを合計し、12分の1を計算
(150万円 + 120万円) ÷ 12 = 22万5,000円
・1カ月当たり家賃の50%を計算
50万円 ÷ 2 = 25万円
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【賃貸料相当額】
賃貸料相当額は「22万5,000円」と「25万円」のうち、より高い金額である 25万円 となります。この金額が役員社宅の適正な賃貸料相当額です。

合わせて読みたい「税理士に無料相談のをするための5つの方法」に関するおすすめ記事
税理士に無料相談の依頼をするためのおすすめの5つの方法を解説!

役員社宅を経費にするポイント

役員社宅を経費にすることで、会社の節税効果を高めると同時に、役員の負担軽減も期待できます。しかし、役員社宅を経費として正しく計上するには、税務上の要件やルールを十分に理解し、適切な運用を行うことが不可欠です。
ここでは、役員社宅を経費にする際の具体的なポイントをわかりやすく解説します。
【役員社宅を経費にするポイント①】
役員社宅の節税効果を最大化させる
役員社宅の家賃を設定する際には、会社負担が賃貸料相当額の50%を下回る範囲内で決めることが重要です。ここで注意すべき点は、役員社宅の賃貸料相当額と実際の家賃が同じではないということです。不動産会社が設定した家賃の50%を役員から徴収してしまうと、役員社宅の経費計上による節税効果が十分に発揮されません。必ず事前に計算した賃貸料相当額を基に設定しましょう。
役員社宅を経費にする方法に関連するポイント!

実際には、役員社宅の経費計上を活用することで、役員の負担割合を50%より低く抑えられる場合が多く、一般的には10~20%程度が目安となります。
例えば、月額家賃が100万円の役員社宅を利用する場合、経費処理は以下のようになります。
- 役員負担が50%の場合:会社の経費(損金)は50万円/月
- 役員負担が20%の場合:会社の経費(損金)は80万円/月
このように、役員社宅の負担割合によって、会社が計上できる経費の額に大きな差が生じます。役員社宅制度を効果的に活用し、経費を最大限に活かした家賃設定を行うことで、節税効果を高めることができます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【役員社宅を経費にするポイント②】
役員社宅を導入する前に社内規定を制定する
役員社宅制度を導入する際には、事前に「役員社宅専用の規程」を作成することが不可欠です。従業員向けの社宅制度がすでに整備されている場合でも、役員社宅については別途規程を設ける必要があります。これは、役員と従業員では税務上の経費計上のルールが異なるためです。
規程には、以下のような重要な項目を盛り込むことが推奨されます。
- 役員と会社の家賃負担割合の設定(経費として計上できる範囲を明確化)
- 光熱費や管理費などの諸費用の支払い方法(経費処理の詳細)
- 役員社宅の利用に関する具体的なルール
適切に規程を整備していない場合、税務調査で役員社宅に関連する経費が否認されるリスクがあります。役員社宅制度を導入する際は、経費計上をスムーズに行うためにも、制度の導入と同時に規程の作成を進めることが重要です。これにより、役員社宅を有効に活用し、会社の節税対策を強化することができます。
役員社宅を経費にする方法に関連するおすすめ記事

役員社宅を経費にするメリットとデメリットについて、以下の記事もおすすめです。
社長の自宅を社宅に?節税になる理由とメリット・デメリットを解説!
役員社宅で節税する場合の注意点

役員社宅を活用することで、家賃や関連費用を経費として計上し、会社の節税効果を高めることが可能です。しかし、役員社宅として経費を正しく計上するには、税務上の要件を満たすことが重要です。適切な運用がされていない場合、役員社宅の経費が否認される可能性があり、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。この段落では、役員社宅を経費として活用する際に特に注意すべきポイントを詳しく解説します。
役員社宅を経費に関する参考記事:「社長の自宅を社宅にする方法| メリット・デメリットや賃料設定も解説」
【役員社宅で節税する場合の注意点①】
役員社宅は住宅ローン控除が適用されない
役員社宅として会社が住宅を購入する場合、個人で住宅を購入する際に利用できる住宅ローン控除が適用されない点に注意が必要です。これは、法人名義での住宅購入が住宅ローン控除の対象外であり、役員社宅にかかる経費として計上する形で運用されるためです。
役員社宅を経費にする方法に関連する記事

役員社宅を経費にする方法や、役員社宅を経費にする場合の注意点に関連して、以下の記事も参考になるでしょう。
役員社宅を知らないと大損!賢く節税するための必須知識
結果として、個人で住宅を購入した場合に得られる税制上のメリットを享受できなくなる可能性があります。そのため、役員社宅として住宅を購入し、経費として計上する方法が自社にとって最適かどうか、慎重に検討することが重要です。役員社宅制度を活用する際には、経費計上のルールや税制の仕組みを正確に理解しておきましょう。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
【役員社宅で節税する場合の注意点②】
家賃以外の負担金は経費にすることができない
役員社宅に関連する経費の中には、損金として計上できない項目がある点に注意が必要です。たとえば、水道光熱費や駐車場代などは、役員個人が負担すべき費用とされるため、課税対象となる場合があります。
役員社宅を経費にする方法に関連する注意点

税理士の費用に関する記事についてはこちらの記事もおすすめです。
具体例として、会社が役員社宅の水道光熱費を経費として負担した場合、それが役員報酬の一部とみなされる可能性があります。その結果、所得税や社会保険料が課され、会社としての経費計上が否認されるリスクが生じます。
このようなトラブルを防ぐため、役員社宅にかかる経費負担のルールをあらかじめ社内規程で明確に定めておくことが重要です。適切な管理を行い、役員社宅の経費を正しく処理することで、税務リスクを回避しつつ、制度を効果的に活用することが可能になります。
【役員社宅で節税する場合の注意点③】
すでに所有している住宅を役員社宅にすることが困難

現在住んでいる住宅を役員社宅に変更したいと考える方も多いでしょう。しかし、もともと個人名義で契約している住宅を法人名義に変更し、役員社宅として扱うことは簡単ではありません。手続きとしては、賃貸契約の名義を個人から法人に切り替え、会社が家賃を支払い、役員負担分を役員報酬から天引きする形を取ることが可能です。

合わせて読みたい「会計ソフト比較一覧」に関するおすすめ記事
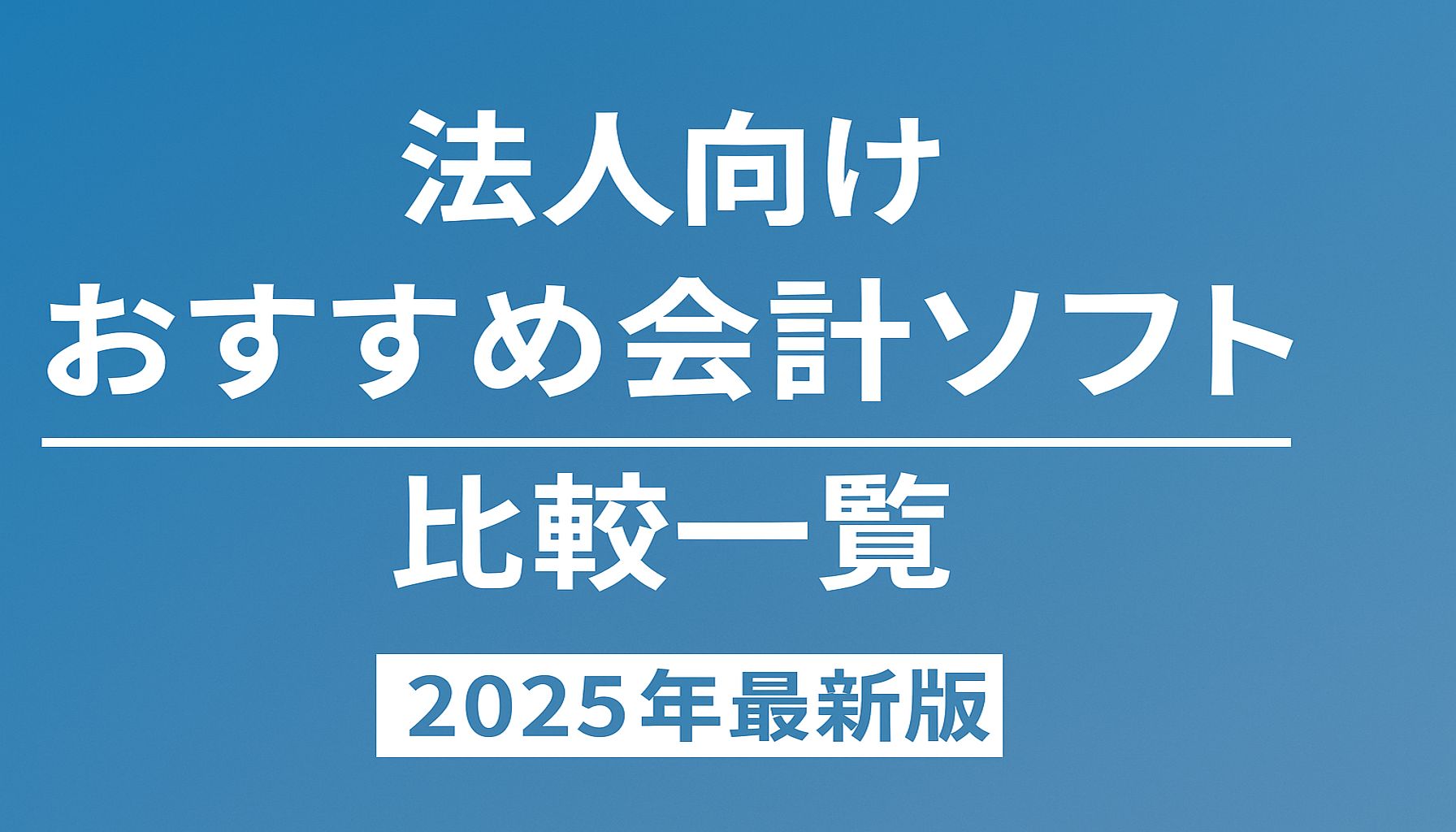
法人のおすすめ会計ソフト比較一覧【2025年最新版】
しかし、役員社宅は福利厚生の一環として、従業員や役員の住環境をサポートする目的で提供されるものです。すでに役員が問題なく居住している住宅を役員社宅とし、会社が経費を負担する場合、その理由が税務上認められないケースがあります。その結果、税務署から「役員社宅」としてではなく「住宅手当」と判断され、課税対象となるリスクがあります。
「役員社宅を経費にする方法」編集部
役員社宅を経費として適切に計上するためには、税務リスクを回避する運用方法を検討し、事前に明確な基準を設定しておくことが重要です。これにより、役員社宅の経費を正しく処理し、節税効果を最大限に活用できます。

合わせて読みたい「税理士への相談料を抑えるポイント」に関するおすすめ記事
税理士に経営相談やアドバイスを依頼できる?メリットと選び方のポイントを紹介

【参考】資金調達と節税は税理士に相談を!経営に役立つ資金調達と節税の知識とは?
中小企業や個人事業主が資金繰りを安定させるためには、節税と資金調達をいかにうまく組み合わせるかが重要です。特に、無駄な税負担を減らすための節税は、経営の根幹に関わる戦略です。こうした節税を実現するには、やはり税理士の専門的な知識とアドバイスが不可欠です。税理士は、最新の税制や制度に精通しており、企業の状況に応じた効果的な節税プランを提案してくれます。例えば、役員報酬の設定、減価償却の活用、各種控除の適用、繰延資産の処理方法など、税理士ならではの視点で細かい節税ポイントを逃さずサポートしてくれます。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
また、資金調達の面でも、税理士は頼れる存在です。日本政策金融公庫や銀行融資の書類作成、補助金や助成金申請など、資金調達に関わる場面でも税理士のアドバイスが大いに役立ちます。しかも、資金調達の内容によっては、将来的な税負担にも影響が出るため、資金調達と節税をセットで考えることが非常に大切です。だからこそ、信頼できる税理士に相談し、節税と資金調達の両方を見据えた経営計画を立てることが成功の近道なのです。
| 資金調達方法の種類 | 概要 |
|---|---|
| 銀行融資 | 民間金融機関からの借入。 金利や審査基準はやや厳しめだが安定した資金調達が可能。 |
| 日本政策金融公庫からの融資 | 政府系金融機関による融資制度。 創業時や設備投資時などに利用しやすく、低金利で借入可能。 |
| ビジネスローン | 比較的短期間で審査が完了するが、金利は高め。 緊急の運転資金に向いている。 |
| 補助金・助成金 | 返済不要の資金。 要件や申請手続きが複雑なため、 専門家(税理士・社労士)に相談するのが効果的。 |
| 出資(VC・エンジェル) | ベンチャーキャピタルや個人投資家からの資金提供。 将来の成長を見込んだ資金調達方法。 |
| ファクタリング | 売掛金を早期に現金化する手段。 返済不要だが、手数料がかかる点に注意が必要。 |
| 社債発行 | 一定の信用力がある企業が投資家から資金を募る方法。 中小企業にはハードルが高め。 |
特に中小企業にとって、節税は資金を守る重要な手段です。
資金調達と節税方法の種類に関する気をつけておきたい注意点

制度を正しく理解せずに誤った節税を行えば、逆に税務調査やペナルティのリスクが高まります。
資金調達と節税方法の種類に関する参考記事:「法人の節税に効果的な12のテクニックを紹介-会社の税金対策まとめ」
こうしたリスクを避けつつ、合法的かつ効果的な節税を実現するには、やはり税理士のサポートが欠かせません。正確な申告、最適な控除の活用、将来を見据えた税務戦略など、税理士と一緒に進めることで、本当に意味のある節税が可能になります。
役員社宅を経費にする際によくある質問|Q&A
Q:タワーマンションは役員社宅として経費にできる?
A.タワーマンションを役員社宅として利用することは可能です。しかし、タワーマンションは「豪華社宅」として、役員社宅と認められず、経費にできない可能性が非常に高いと言えるでしょう。
したがって、タワーマンションは役員社宅にできず、全額役員負担になると考えておくと無難です。
Q:役員社宅として利用している住居は本当に経費にできますか?
役員社宅として要件を満たしていれば、役員が住んでいる住居であっても会社の経費として計上できます。ポイントは「会社が契約者となっていること」と「役員から適正な社宅使用料を受け取っていること」です。これらを満たさず、単に役員個人の自宅を会社経費として処理している場合は、役員社宅ではなく私的利用と判断され、経費として否認されるリスクが高くなります。役員社宅を経費として安全に扱うには、契約形態と使用料の設定が非常に重要です。
Q:役員社宅として経費にできる範囲にはどこまで含まれますか?
役員社宅の経費として認められるのは、主に家賃、共益費、管理費などの住居に直接関係する費用です。条件を満たしていれば、これらは法人の経費として処理できます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
一方で、水道光熱費やインターネット代などは、会社負担にすると役員への経済的利益と判断されやすく、役員社宅の経費として扱うには慎重な判断が必要です。
役員社宅に関連する経費は「どこまでが会社負担として妥当か」を意識して整理することが欠かせません。
参考:「会社が役員等に対して社宅を貸与する場合の家賃、水道光熱費はどうするの?」
Q:役員社宅の家賃は全額を経費にしても問題ありませんか?
役員社宅の家賃を全額経費にできるケースは多いですが、役員が支払う社宅使用料を適正に設定していることが前提です。使用料が著しく低い場合、差額部分が役員報酬とみなされ、結果として経費として認められなくなる可能性があります。役員社宅を経費として活用する際は、「相当家賃額」を基準に使用料を計算し、税務上問題のない水準にしておくことが重要です。
Q:役員社宅が経費として否認されるのはどんなケースですか?
役員社宅の経費が否認されやすいのは、契約が役員個人名義のままになっている場合や、社宅使用料を受け取っていない場合です。また、役員社宅と称しながら実態は高級マンションや広すぎる物件で、業務との関連性や合理性が説明できないケースも注意が必要です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
役員社宅は経費として強力な制度ですが、形式だけでなく実態も整っていなければ否認リスクが高まります。
Q:役員社宅と給与(役員報酬)はどう違うのですか?
役員社宅は、一定の要件を満たすことで役員報酬とは異なり、法人の経費として処理できる点が大きな違いです。役員報酬として現金で支給すると所得税や社会保険料の負担が増えますが、役員社宅を経費として活用すれば、役員個人の税負担を抑えつつ、会社側でも経費計上が可能になります。そのため、役員社宅は経費の使い方として非常に有効な選択肢といえます。
Q:役員社宅を経費にするメリットは何ですか?
役員社宅を経費として処理する最大のメリットは、役員個人の可処分所得を実質的に増やせる点です。会社が家賃を負担し、それを経費にできれば、役員が個人で家賃を支払うよりも税負担を抑えられます。
ここがポイント!

法人税の圧縮にもつながるため、役員社宅は節税と経費活用の両面で効果があります。ただし、要件を誤ると経費否認のリスクがあるため、制度理解が欠かせません。
Q:役員社宅を経費として使う際の注意点はありますか?
役員社宅を経費として使う際は、契約書、社宅規程、使用料の計算根拠などをきちんと残しておくことが重要です。税務調査では「本当に役員社宅として妥当か」「経費処理は適正か」が細かく確認されます。役員社宅は経費として認められやすい一方、形式を誤ると一気に否認される可能性があるため、専門家のチェックを受けながら運用することが安心です。
まとめ
役員社宅は、会社が負担する家賃や関連費用を経費として計上できる点が大きな魅力です。役員社宅制度を導入することで、会社は家賃や修繕費、契約にかかる仲介手数料などを経費として処理でき、節税効果が期待できます。
また、役員個人にとっても家賃負担の軽減や手取りの向上につながるため、役員社宅と経費をうまく活用することで、会社と役員双方にメリットをもたらします。
ただし、役員社宅を経費化するには一定の条件を満たす必要があるため、制度を正しく理解し、適切に運用することが重要です。役員社宅を経費として活用し、会社の税務戦略をより効果的なものにしましょう。

合わせて読みたい「期の途中から就任した役員の役員報酬」に関するおすすめ記事

期の途中から就任した役員の役員報酬はどうする?定期同額給与や損金算入する方法を紹介
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します














SoVaをもっと知りたい!