法人で赤字の場合に免除される税金とは?納税の有無や赤字決算のメリット・デメリットを紹介!
カテゴリー:
公開日:2025年7月
更新日:2026年1月16日
法人が赤字になったとき、どの税金が免除されるのか?
赤字が続く法人にとって、赤字でも支払う必要がある税金と、赤字だからこそ発生しない税金の違いは、経営に直結する重要なテーマです。赤字であっても一部の税金は発生するため、「赤字=すべての税金が免除される」と考えるのは危険です。
たとえば、赤字の法人でも支払いが必要な税金(均等割や消費税など)がある一方で、赤字によって法人税や地方法人税が免除される場合もあるなど、赤字と税金の関係性は非常に複雑です。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
法人の赤字による税金の軽減メリットがある反面、金融機関からの信用低下や税務調査リスクといった赤字ならではの税金トラブルや注意点も存在します。
この記事では、法人が赤字になった場合に免除される税金の種類を詳しく紹介しつつ、赤字によって得られる税金メリットや、逆に赤字によって発生しうる税金面でのデメリットやリスクについてもわかりやすく解説します。
赤字の活用方法と税金の正しい知識を持つことで、法人経営における税金リスクを減らし、長期的な節税にもつなげることが可能です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
目次
赤字とは?赤字の意味と税金との関係を徹底解説
赤字とは、事業活動において収入よりも支出の方が多くなり、最終的に利益がマイナスになる状態のことを指します。つまり、売上などの収益から人件費や経費などの支出を差し引いた結果、残るべき利益が赤字、すなわち損失となっている状態です。
法人の場合、赤字かどうかは決算書上の損益計算書をもとに判断されます。1年間の会計期間で法人の収支を集計し、利益がマイナスになっていれば赤字決算となります。個人事業主の場合も同様に、1月から12月の間の収支によって赤字か黒字かを判断します。
ただし、赤字=経営破綻とは限りません。法人が赤字であっても、手元資金が潤沢にあり、資金繰りが安定していれば、赤字でも事業継続は可能です。一時的な赤字であれば、戦略的な投資や景気の影響によるものであることも少なくありません。
法人が赤字の場合の税金に関するおすすめ記事

法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金や、法人が赤字決算のメリット・デメリットについては以下の記事も参考になるでしょう。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「税理士監修|法人が赤字の時に免除される・されない税金【節税にも】」
重要なのは、赤字になることで税金への影響が大きく変わるという点です。たとえば、法人が赤字であれば、法人税や地方法人税といった所得に対して課される税金は免除される可能性があります。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
赤字であることによって「課税所得がゼロ」となるため、法人税の対象外となるためです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
一方で、赤字であっても完全にすべての税金が免除されるわけではありません。たとえば、赤字でも消費税や法人住民税の均等割といった税金は発生することがあり、赤字=税金ゼロと考えるのは誤りです。
また、赤字が続くことで税金面での節税効果はあるものの、税金リスクも高まります。
法人が赤字の場合の税金に関する注意点

意図的に赤字を出して税金を減らそうとした場合、税務署から脱税を疑われる可能性もあり、過去の申告内容が精査されるケースもあります。
このように、赤字とは単なる損失ではなく、税金との関係に大きく影響を与える要素でもあります。
赤字によって発生する税金の有無、赤字を活用した節税効果、赤字が続いた場合の税金リスクなど、赤字と税金の関係性を正しく理解することが、法人経営において非常に重要です。
法人が本来支払うべき税金の種類

「決算前にできる節税方法」編集部
決算前にできる節税方法に関しては、【決算前に経費を使う理由とは?利益調整や節税対策について解説】の記事も是非ご覧ください。
法人を設立して事業を行う以上、避けて通れないのが税金の問題です。法人にとって、利益が出ているかどうかにかかわらず、さまざまな税金が課される仕組みになっています。中には赤字でも課される税金があり、法人としての活動を継続する以上、必ず向き合わなければならない義務です。
ここでは、法人が一般的に支払う必要がある主要な税金について、各税金の性質や違いを詳しく解説します。法人に課される税金の種類を正しく理解することは、経営管理と税務対策の基本です。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「法人が赤字の場合に納付が不要な税金は?種類や条件などを解説」
法人が本来支払うべき税金の種類①
法人税・地方法人税|法人の所得に対する基本の税金
法人税は、法人の利益(課税所得)に対して課される基本的な税金で、国に納める国税です。法人が商品やサービスを販売して得た収益から費用を差し引いた所得に対して、一定の税率で計算されます。

合わせて読みたい「法人税・法人事業税・法人住民税の違い」に関するおすすめ記事

法人税・法人事業税・法人住民税の違いとは?計算方法や課税対象、納付先まで詳細解説!
また、法人税と併せて納めるのが地方法人税です。地方法人税も国税ですが、地方自治体に再配分される仕組みで、法人税額に一定の割合を掛けて計算される補完的な税金です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
「法人が赤字の場合の税金」編集部
法人の所得に対しては、複数の税金が連動して課税されることになります。
法人が赤字の場合の税金に関するおすすめ記事

法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金や、法人が赤字決算のメリット・デメリットについては以下の記事も参考になるでしょう。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「赤字の時、法人税は発生しない?赤字決算で免除される税金と節税ポイントを解説」
法人が本来支払うべき税金の種類②
法人事業税|地方自治体が課す所得連動型の税金
法人事業税は、都道府県に納める地方税のひとつで、法人の所得を基準に課される税金です。所得額が大きくなると、比例して法人事業税の金額も増えます。さらに、資本金1億円を超える法人には、付加価値割や資本割といった別計算の税金も課されるため、法人の規模によって税金負担が重くなる仕組みです。
「合同会社の決算申告」編集部
決算や平時に合同会社にかかる税金については、【合同会社が売上なしでも払う税金とは?赤字(利益ゼロ)の場合の納税について解説】の記事も是非ご覧ください。
このように、法人事業税は事業活動そのものに対する公共的な見返りとして位置付けられる税金であり、法人が社会インフラを利用して事業を行っている以上、避けられない税金といえます。

合わせて読みたい「決算直前の節税対策」に関するおすすめ記事
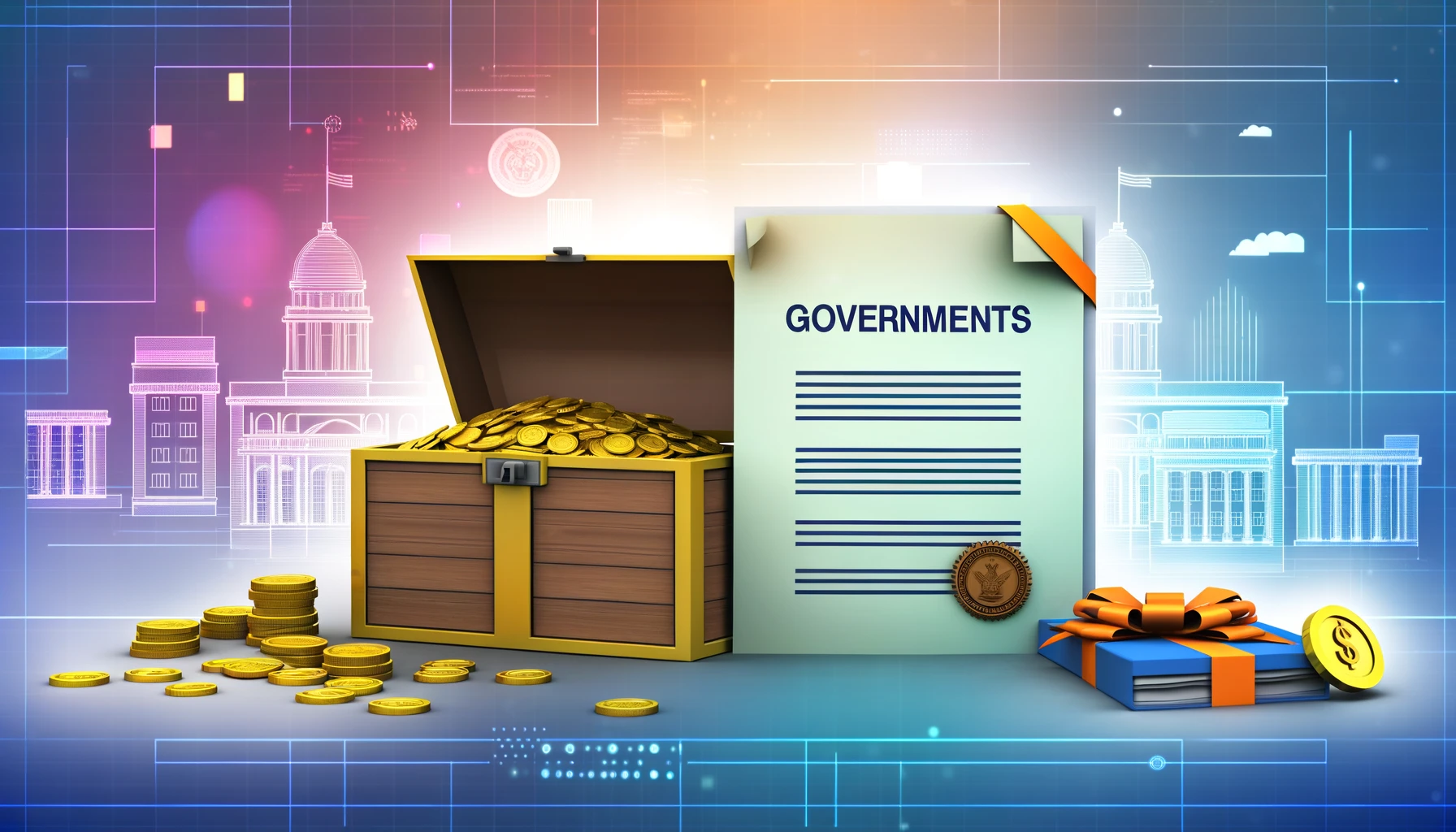
決算直前の節税対策を解説!3ヶ月前に対策すべきこととは?
法人が本来支払うべき税金の種類③
法人住民税|赤字でも均等割として必ず発生する税金
法人住民税は、法人の所在地となる都道府県および市区町村に対して納める地方税です。法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つで構成されます。
このうち法人税割は法人税額に応じて課される税金ですが、均等割は所得にかかわらず発生する税金です。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
つまり、法人が赤字であっても、事業を継続している限り、均等割の税金は毎年必ず発生します。
法人が赤字の場合の税金に関するポイント!

均等割の税金は、法人の規模や資本金、従業員数などに応じて定額で決まるため、利益の有無にかかわらず必要な税金として認識しておくことが重要です。
法人が本来支払うべき税金の種類④
特別法人事業税|法人事業税に連動して課される追加の税金
特別法人事業税は、2019年度から新たに導入された税金で、法人事業税の一部を切り分けて創設された国税です。これは、地方自治体間の財政格差を是正する目的で設けられた税金であり、法人事業税と同様に法人の所得を基準として課税されます。
法人が赤字の場合の税金に関するおすすめ記事

法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金や、法人が赤字決算のメリット・デメリットについては以下の記事も参考になるでしょう。
「法人税が免除される条件は?赤字になったときの税金について解説」
つまり、法人事業税が発生すれば、必然的に特別法人事業税も発生する構造となっており、法人の税務処理において見落とせない税金のひとつです。
法人が本来支払うべき税金の種類⑤
消費税|赤字でも納税が必要となる税金の代表格
消費税は、法人が顧客から商品・サービスの代金とともに預かる形で発生する税金です。法人自身が負担する税金ではありませんが、預かった消費税を国に納付する義務があるため、法人の立場では納税者としての役割を果たす必要があります。

合わせて読みたい「消費税の申告義務」に関するおすすめ記事
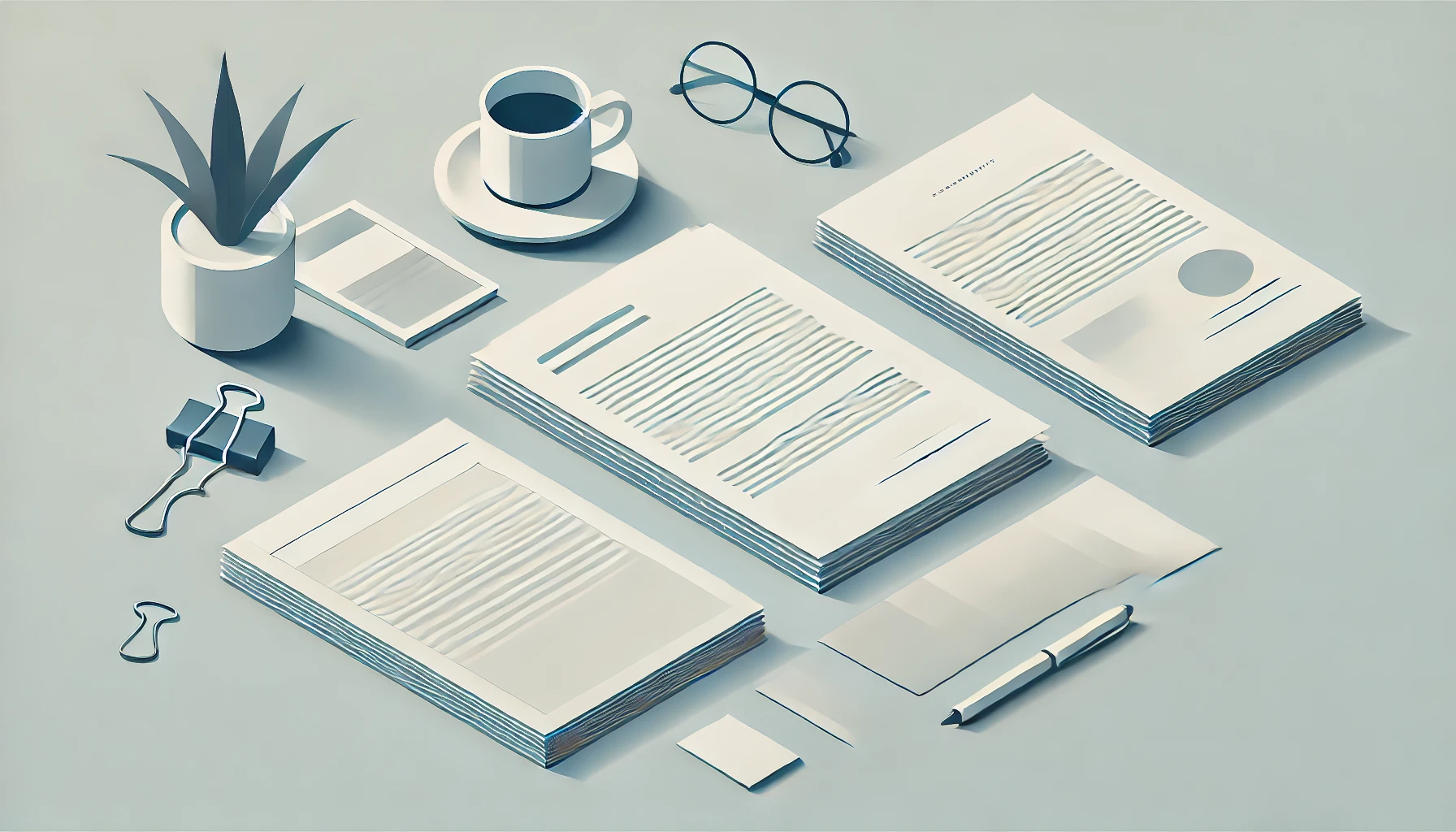
消費税申告義務の対象となる条件とは?計算方法や課税事業者と免税事業者の違いも解説!
課税事業者となる条件を満たした法人は、たとえ赤字であっても、消費税の納税義務は免れません。この点において、消費税は赤字か黒字かに関係なく発生する性質の税金であるため、資金繰りや税務計画においても重要な税金となります。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
法人が赤字の場合に免除される税金や、赤字でも免除されない税金一覧は以下の表を是非参考にしてください!
| 納税先 | 赤字でも発生するか | 税金の概要・特徴 | |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 国税 | × (所得があれば) |
法人の所得に対して課される基本の税金。 課税所得に応じて金額が変動。 |
| 地方法人税 | 国税(地方へ再配分) | × (法人税に連動) |
法人税額に一定率をかけて計算される国税。 地方財源として活用される。 |
| 法人事業税 | 地方税(都道府県) | △ (一部発生) |
所得に応じて課されるが、資本金1億円超の法人などには 赤字でも課税される場合あり。 |
| 特別法人事業税 | 国税(地方に交付) | × (法人事業税連動) |
法人事業税に連動して課される国税。 地方間格差是正のための制度。 |
| 法人住民税(法人税割) | 地方税(都道府県・市町村) | × (法人税に連動) |
法人税額に基づいて課税される。 税率は自治体により異なる。 |
| 法人住民税(均等割) | 地方税(都道府県・市町村) | ○ | 赤字でも必ず支払う必要のある定額の税金。 法人の規模や資本金により金額が異なる。 |
| 消費税 | 国税 | ○ (課税事業者なら) |
売上に応じて発生。赤字でも納税義務がある間接税。 課税売上高が要件を満たすと発生。 |
法人が赤字の場合に免除される税金
法人が赤字の場合でも、すべての税金が免除されるわけではありません。とはいえ、赤字の法人には納税が不要となる税金もあり、「赤字だからこそかからない税金」が存在します。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
ここでは、法人が赤字のときに発生しない税金、つまり赤字法人にとって“かからない税金”の種類について詳しく解説します。

赤字の法人には課税されない「法人税」と「地方法人税」
法人の代表的な税金である「法人税」は、法人の所得に応じて課される税金です。法人が赤字であれば、所得金額がゼロまたはマイナスとなるため、法人税そのものが発生しません。つまり、赤字法人にとっては、この法人税は「かからない税金」となります。

合わせて読みたい「住民税の特別徴収と普通徴収」に関するおすすめ記事

住民税の特別徴収とは?普通徴収との違いや手続き方法についても解説!
さらに、地方法人税も赤字の法人には不要です。地方法人税は法人税額に比例して算出されるため、法人税がゼロなら地方法人税もゼロです。赤字であれば、この2つの税金はどちらも納付不要となるのです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
赤字なら免除されることが多い「法人事業税」と「特別法人事業税」
「法人が赤字の場合の税金」編集部
法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金については以下のサイトも是非ご覧ください。
「赤字でも法人税がかかるって本当?費用と損金の違いを解説」
法人事業税は、法人が行う事業に対して課される地方税で、法人の所得が基準です。赤字の法人であれば所得が存在しないため、法人事業税も課税されません。つまり、赤字であれば法人事業税という税金も納税不要となるケースが多いのです。
ただし、注意すべきは資本金が1億円を超える法人です。このような法人では、赤字であっても「付加価値割」や「収入割」といった別基準で課税される法人事業税があります。つまり、大規模な法人は、赤字でも一部の税金が発生する可能性があるということです。
法人が赤字の場合の税金に関するポイント!

また、特別法人事業税も法人事業税に連動する税金です。赤字で法人事業税がかからない場合は、特別法人事業税も当然かかりません。赤字であれば、この税金も支払い不要となります。

合わせて読みたい「税理士に決算のみを依頼するメリット」に関するおすすめ記事

決算申告のみを税理士に依頼する場合のおすすめの方法を解説!
赤字でも一部発生する税金「法人住民税」の扱いに注意
法人住民税は、法人が赤字でも一部の税金が発生する例です。法人住民税は、「法人税割」と「均等割」という2種類で構成されています。
「法人税割」は法人税額に応じて課税されるため、赤字で法人税がゼロなら、この法人税割の部分もゼロになります。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
赤字であれば、ここでも税金の支払い義務は発生しません。
しかし、「均等割」は赤字かどうかに関係なく、資本金の額や従業員の数に応じて定額で課税される仕組みです。つまり、赤字であっても均等割の税金だけは必ず納付しなければならないということになります。赤字法人であっても完全に税金ゼロとはならない代表例がこの均等割です。
法人が赤字の場合の税金に関するおすすめ記事

法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金や、法人が赤字決算のメリット・デメリットについては以下の記事も参考になるでしょう。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「法人で赤字が出た際に免除される税金・されない税金は?赤字決算での法人税の取り扱いも紹介」
赤字でも免除されない税金とは?
法人が赤字決算となった場合、多くの税金は「所得がない=課税されない」と思われがちですが、実際には赤字の法人でも納めなければならない税金がいくつも存在します。赤字だからといってすべての税金が免除されるわけではありません。ここでは、赤字の法人でも必ず発生する税金について、わかりやすく詳しく解説します。

法人が赤字でも免除されない税金①
消費税
消費税は、法人がどれだけ赤字であっても免除されない代表的な税金です。消費税は法人の利益に対して課される税金ではなく、あくまで「消費者から預かった税金」を国に納める仕組みとなっています。したがって、法人が赤字であっても、消費税は納税義務が発生します。
赤字法人であっても、売上がある限り消費税の支払いは避けられません。たとえ利益が出ていない赤字決算でも、売上に対する消費税を預かっている以上、その税金を納める責任は免れません。
法人が赤字の場合の税金に関するおすすめ記事

法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金や、法人が赤字決算のメリット・デメリットについては以下の記事も参考になるでしょう。
「決算が赤字の場合法人税は支払わなくていいの?」
一部の小規模な法人が条件を満たせば「免税事業者」となり、一定期間だけは消費税の納税が免除される場合もありますが、それでも赤字であること自体が消費税の免除理由にはなりません。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
「赤字=消費税ゼロ」という考え方は大きな誤解です。
法人が赤字でも免除されない税金②
法人住民税の均等割
次に、赤字でも法人が必ず負担する税金の代表例が「法人住民税の均等割」です。法人住民税には、法人税額に連動して計算される「法人税割」と、会社の規模に応じて固定的に課税される「均等割」があります。このうち「均等割」は、赤字かどうかに関係なく課税される税金です。

合わせて読みたい「還付金」に関するおすすめ記事

還付金とは?還付が発生しうる税金の種類と還付条件についても解説!
つまり、法人が赤字決算で利益が出ていない場合でも、法人住民税の均等割だけは毎年必ず支払う必要がある税金となります。
法人が赤字の場合の税金に関するポイント!

赤字でも避けられないこの税金は、特に中小法人や利益が安定しない法人にとって重荷となる可能性があります。
法人が赤字でも免除されない税金③
法人事業税の一部(資本割・付加価値割・収入割)
一般に、法人事業税は所得をもとに計算されるため、法人が赤字であれば法人事業税はゼロになると考えられがちです。しかし、実際にはそう単純ではありません。一部の法人には、赤字でも発生する法人事業税が存在します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
具体的には、資本金が1億円を超える法人には、通常の所得割に加えて「資本割」や「付加価値割」という課税項目があります。これらは、法人の所得ではなく、資本金や人件費、支払利息などに基づいて計算される税金です。したがって、法人が赤字でも、これらの法人事業税は発生します。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金については以下のサイトも是非ご覧ください。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「法人税は赤字でも払う必要がある? 法人にかかる税金について解説」
さらに、電気・ガス・水道などの公共性の高い事業を営む一部の法人については、「収入割」という課税方式もあり、赤字でも事業の収入に応じて税金が発生するしくみになっています。

合わせて読みたい「法人が納める消費税」に関するおすすめ記事
法人が納める消費税について解説! 税理士のサポートを受けるメリットも紹介

つまり、赤字決算であっても一部の法人には法人事業税の納税義務があるため、事前に確認しておくことが非常に重要です。
赤字決算で得られる法人の税金メリット3選
法人が赤字決算になってしまったら、もう終わりなのでは?
そんなふうに不安を感じる経営者も多いかもしれません。確かに、赤字決算は企業にとって好ましい状態とは言えませんが、実は赤字決算によって税金面で得られるメリットも数多く存在します。

合わせて読みたい「法人 決算月 決め方 変更 税理士」に関するおすすめ記事

法人の決算月は税理士に相談すべき?決め方と変更方法について解説!
実際、赤字決算=経営失敗ではありません。むしろ、法人の多くが赤字決算を経験しています。国税庁の調査によると、2022年度に決算を迎えた法人のうち、61.1%が赤字決算だったという結果が出ています。つまり、赤字決算は珍しいものではなく、むしろ一般的な経営の一局面なのです。
ここでは、法人が赤字決算になった場合に得られる代表的な税金メリットを3つに絞ってご紹介します。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
赤字や赤字決算に不安を感じている方こそ、ぜひ最後までご覧ください。
赤字決算で得られる法人の税金メリット①
赤字決算なら法人税が発生しない|赤字=税金ゼロの代表例
法人が赤字の場合の税金に関するおすすめ記事

法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金や、法人が赤字決算のメリット・デメリットについては以下の記事も参考になるでしょう。
「法人税が免除されるケース|法人が赤字の場合に免除される税金は?」
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
赤字決算の一番のメリットは、法人税が課されないという点です。法人税は、法人が得た利益(課税所得)に対して課される代表的な税金ですが、赤字決算になるとその所得がゼロまたはマイナスになるため、法人税の納付義務がなくなります。

法人税は金額が大きく、数十万円~数百万円になることもあります。そのため、赤字決算によって高額な法人税を支払わずに済むことは、法人にとって大きな節税効果となります。
法人が赤字の場合の税金に関するポイント!

法人税に連動して発生する地方法人税や法人住民税の法人税割も、赤字決算であれば税金がゼロになります。
つまり、赤字決算=法人税などの税金を抑えられる節税チャンスなのです。
赤字決算で得られる法人の税金メリット②
赤字決算を活かして将来の黒字と相殺|欠損金の繰越控除で長期的に節税
赤字決算のもうひとつのメリットが、欠損金の繰越控除です。これは、赤字決算で発生した「赤字額(欠損金)」を、将来の黒字と相殺して課税所得を減らすことができる制度です。
青色申告を行っている法人であれば、赤字決算で生じた欠損金を最大10年間繰り越すことができ、将来黒字になった際にその欠損金を使って法人税や地方法人税などの税金を節税することが可能です。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「合同会社が赤字になった場合の税金はどうなる?納税の有無を解説」
たとえば、今年度200万円の赤字決算となった法人が、翌年度に150万円の黒字を出した場合、前年の赤字と相殺することで、法人税がかからない=税金ゼロになるのです。さらに未使用の赤字50万円分は、翌々年度に繰り越して再び使うことができます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
青色申告はメリットが多いため、会社設立をしたら必ず提出するようにしておきましょう!
個人事業主では赤字の繰越期間は3年間に制限されていますが、法人の場合は10年間の繰越が可能なので、赤字決算による税金対策は長期的な節税戦略として非常に有効です。
赤字決算で得られる法人の税金メリット③
赤字決算によって前期に支払った法人税を取り戻せる|欠損金の繰戻し還付
さらに、赤字決算の法人には還付という形で税金を取り戻すことも可能です。これは「欠損金の繰戻しによる還付制度」という仕組みで、前期に黒字で法人税を支払っていた法人が、当期赤字決算になった場合に、その赤字を前期の所得に適用して、支払った法人税の一部を還付してもらえる制度です。
たとえば、前期500万円の所得に対して75万円の法人税を納めていた法人が、当期に200万円の赤字決算になった場合、
75万円 ×(200万円 ÷ 500万円)= 30万円の法人税還付
となり、30万円の現金が戻ってくる計算になります。赤字決算でも税金を「取り戻す」ことができる制度があるのは、法人ならではの大きな魅力です。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「インボイス 2割特例 いつまで」に関するおすすめ記事
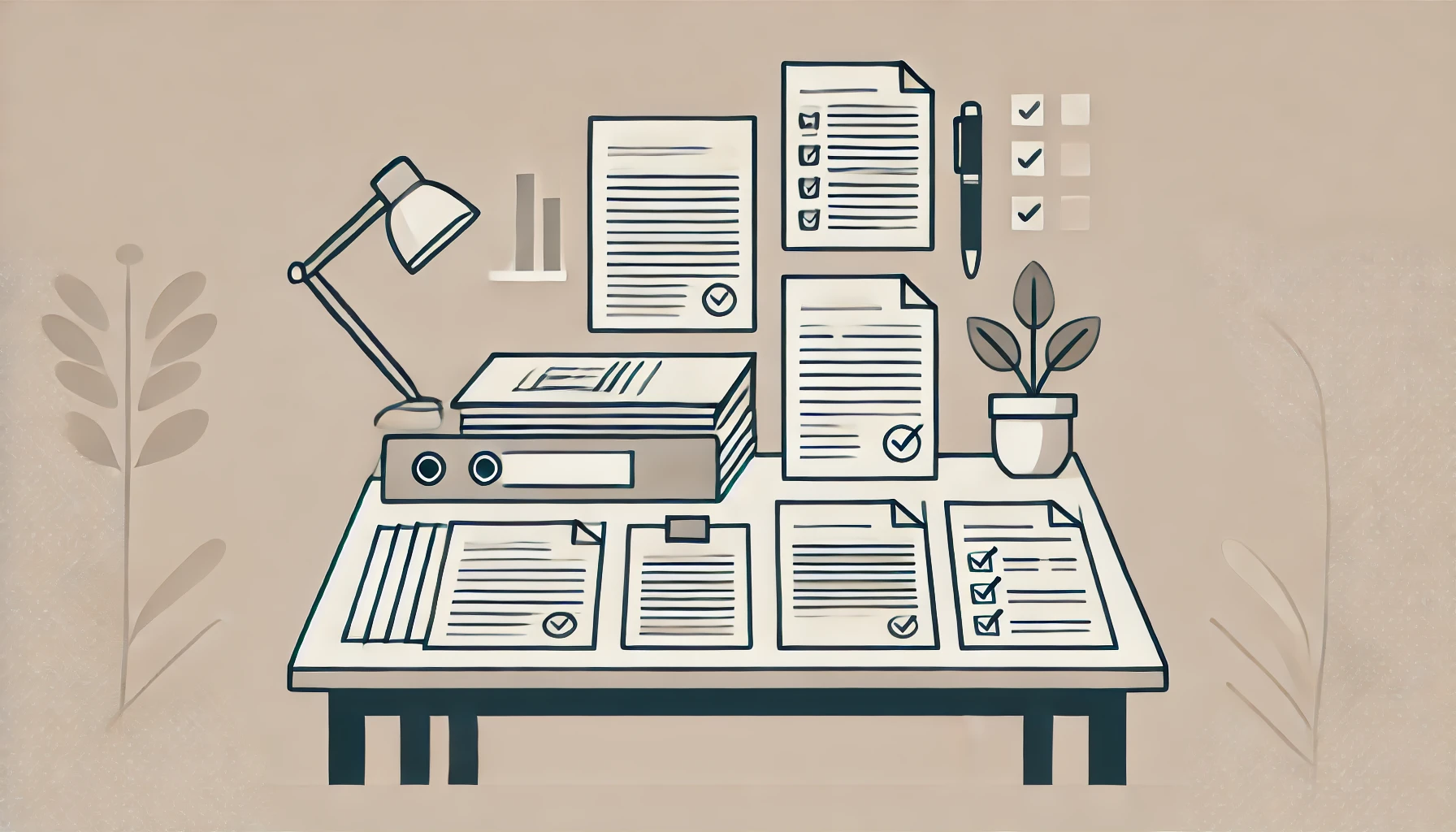
インボイスの2割特例はいつまで?2割特例の計算方法も解説!
このように、赤字決算によって税金を減らすだけでなく、すでに支払った税金を還付として受け取れるというのは、非常にありがたい節税制度といえるでしょう。
法人の赤字決算による税金メリットの裏に潜むリスク
赤字決算による税金の軽減効果は、たしかに法人にとって魅力的です。赤字決算で法人税がゼロになったり、欠損金の繰越控除で将来の税金を抑えられたりと、赤字ならではの税金上の恩恵は存在します。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金については以下のサイトも是非ご覧ください。
「赤字の場合、前期に納めた税金を返してもらえるそうですが、どのような制度ですか?」
しかし、安易に赤字や赤字決算を選ぶことは非常に危険です。法人が継続的に赤字決算を続けると、税金の軽減以上に深刻な経営リスクが表面化してきます。赤字決算は、税金の節約だけで判断すべきではないということを理解しておく必要があります。
ここでは、赤字決算による代表的な5つのデメリットをわかりやすく解説していきます。
法人が赤字の場合のリスク①
赤字決算が続くと金融機関の評価が下がる
法人が赤字決算を連続して行っている場合、金融機関による信用格付けである「債務者区分」が引き下げられる可能性があります。これは、赤字が続く法人には返済能力がないと見なされ、金融機関からの融資が厳しくなることを意味します。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
「法人が赤字の場合の税金」編集部
金融機関からすれば、赤字続きの法人に融資することは大きなリスクを伴います。いくら赤字で税金がかからないとしても、返済原資が確保できない法人に資金を貸すメリットはありません。

金融庁の「金融検査マニュアル」にも、赤字であっても5年以内に黒字化できる法人は融資対象として検討可能であると明記されていますが、これは裏を返せば、赤字が長期化する法人は融資対象から外れるということを示しています。
法人が赤字の場合の税金に関する注意点

実際に赤字が3期連続すると、「経営悪化による融資停止」といった金融実務上の判断が下されるケースも多く、赤字が信用格付けの大幅なダウンにつながることがあるのです。
つまり、赤字によって税金が減ることばかりに目を向けてしまうと、資金繰りというもっと重要な法人経営の根幹が揺らぐ可能性があります。赤字が節税に有利でも、それが金融機関の信用を失うきっかけになれば、赤字によって得た税金のメリット以上の損失が発生するのです。
法人が赤字の場合の税金に関するおすすめ記事

法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金や、法人が赤字決算のメリット・デメリットについては以下の記事も参考になるでしょう。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「赤字決算になった場合の法人税の取り扱い」
税金の支払いは減るかもしれませんが、赤字決算によって資金調達ができなくなるという根本的な問題が発生します。赤字によって節税できたとしても、信用低下によって事業資金がショートすれば、法人経営全体が危機にさらされるのです。
法人が赤字の場合のリスク②
赤字決算により既存の融資条件が悪化する恐れ
赤字決算を続ける法人に対しては、すでに受けている融資の条件が見直されるリスクも高まります。金利の引き上げや担保の追加要求、返済期間の短縮など、赤字による信用低下が法人に直接跳ね返ってくるのです。
税金が減ったことによるキャッシュフロー改善よりも、赤字決算が信用を失う要因になることの方が、法人にとっては遥かにダメージが大きい場合があります。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金については以下のサイトも是非ご覧ください。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「赤字になった株式会社が支払わなくても良い税金と赤字になるメリット」
法人が赤字の場合のリスク③
赤字が続けば債務超過や倒産リスクが急上昇
赤字決算が何期も続くと、法人は利益を内部に留保できず、自己資本が減少します。その結果、負債が資産を上回る「債務超過」に陥り、法人としての信用や経営基盤が大きく崩れることになります。
法人が赤字の場合の税金に関する注意点

赤字によって税金が減ったとしても、赤字決算が続けば法人は立ち行かなくなります。税金の節約よりも、赤字そのものが事業継続を阻む最大の要因になりかねません。

合わせて読みたい「法人が支払う税金の種類について」に関するおすすめ記事
法人が支払う税金、種類と納付タイミングを税理士が解説!

法人が赤字の場合のリスク④
赤字決算では経営者保証が外せないリスクが続く
赤字決算をしている法人は、財務状況が健全ではないと判断されるため、金融機関からの融資において「経営者保証」を外す交渉が困難になります。これは、法人の赤字状態が続く限り、経営者が個人として借入金を保証するリスクを背負い続けることを意味します。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
赤字決算による税金の免除があっても、経営者が個人資産で債務を負うリスクが残るため、総合的に見れば大きなデメリットです。
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
法人が赤字の場合のリスク⑤
赤字を続けると税金逃れを疑われるリスクも
赤字は税金を抑えるうえで非常に有効な方法ですが、赤字決算が何年も続く法人は税務署から「不自然な赤字」としてマークされる可能性があります。
特に、赤字によって法人税や地方法人税、法人住民税の法人税割がゼロになることを意図的に狙って、経費を過剰に計上したり、収益の計上時期をずらしたりする法人も一部には存在します。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
法人が赤字の場合に免除される税金と、法人が赤字でも免除されない税金については以下のサイトも是非ご覧ください。
法人が赤字の場合の税金に関する参考記事:「会社が赤字になったら税金はどうなる?赤字でも納める税金は?」
こうした「意図的な赤字」は、節税ではなく脱税と判断される可能性があるため非常に危険です。税務署は、赤字を利用して税金逃れをしていると判断すれば、税務調査を実施し、過去3年〜5年分の申告内容を徹底的に精査します。

たとえ法人が意図的に赤字を作っていなかったとしても、赤字を続けたことで税務署に目をつけられ、申告ミスや記帳漏れによって税金の追徴課税が発生するケースもあります。
つまり、赤字=税金がかからないから得、という考え方だけで赤字を出し続けることは、逆に税金リスクを高める行為になりかねないのです。節税のつもりで赤字にしても、税金の監視を強められてしまえば本末転倒です。
法人が赤字の場合のリスク⑥
赤字決算により従業員の不安と士気の低下を招く
赤字決算が連続している法人では、従業員にも「この会社は大丈夫なのか?」という不安が広がりやすくなります。給与の減額、賞与の未払い、倒産リスクへの警戒などが原因で、社員のモチベーションが下がり、離職につながる可能性もあります。
法人が赤字の場合の税金に関する注意点

法人が赤字決算を続けていると、税金だけでなく人材面でも重大な損失が生まれることになりかねないため注意が必要です。
Q&A|よくある質問
Q. 法人が赤字になった場合、消費税や源泉所得税は免除されますか?
A. いいえ、法人が赤字になったとしても、売上に対する消費税や、給与・報酬の支払に伴う源泉所得税などは、利益に関係なく発生する税金です。
法人が赤字の場合の税金に関する注意点

これらの税金はあくまで取引や支払に基づいて発生するため、赤字かどうかにかかわらず法人は納税義務を負う点に注意が必要です。
Q. 赤字でも法人税の申告は必要ですか?
A. はい、法人が赤字で法人税の納税額が0円であっても、必ず法人税の確定申告書の提出が必要です。申告しなければ税務署から申告漏れとみなされ、延滞税や無申告加算税といった税金リスクが発生する可能性があります。
「法人が赤字の場合の税金」編集部
赤字決算の法人も、正確な申告と書類管理が求められます。
Q. 赤字の法人が繰越控除を使うためには何が必要ですか?
A. 赤字を繰り越して法人税の節税を行うには、所定の手続きをきちんと行う必要があります。まず、青色申告の承認を受けている法人であることが前提です。さらに、赤字が発生した事業年度ごとに適切な確定申告書の提出が求められます。これらが守られていない場合、赤字の繰越による法人税軽減は認められません。
まとめ|法人が赤字の場合の税金納付有無
専門家費用を46%カット!!
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
赤字になった法人にとって、税金との関係を正しく理解することは非常に重要です。
赤字だからこそ免除される税金がある一方で、赤字でも支払わなければならない税金も存在します。たとえば、赤字になれば法人税や地方法人税といった所得課税型の税金は発生しませんが、赤字であっても法人住民税の均等割や消費税などは納税が必要です。
このように、赤字と税金の関係は単純ではなく、赤字による税金の減少メリットと、赤字でも課税される税金との違いを明確に把握しておくことが、法人にとって大切な経営判断材料となります。
また、赤字が続くことで税金リスクが高まり、税務調査や信用低下といった副次的な影響が発生する可能性もあります。節税目的で赤字を狙うことが、結果的に税金トラブルを招くケースもあるため、赤字と税金のバランスを慎重に見極める姿勢が必要です。
法人が赤字になったとき、どの税金が免除されるのか、逆に赤字でもどの税金を支払う必要があるのかを理解することが、安定した法人経営と健全な税金対策の第一歩です。
赤字=悪ではありませんが、赤字と税金の関係を正しく把握しなければ、法人の将来に大きな影響を及ぼす可能性があるという点を常に意識しておきましょう。

合わせて読みたい「税理士に依頼できる税金計算シミュレーション」に関するおすすめ記事
法人税とは?税金計算シミュレーションと税理士依頼時のおすすめポイント!

税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)~
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して
ビジネスに集中しましょう
人気記事ランキング
1
アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
2
アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介
-
ビジネスカード

2026年2月25日
3
アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!
-
ビジネスカード

2026年2月25日
4
個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説
-
ビジネスカード

2026年2月25日
5
アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?
-
ビジネスカード

2026年2月24日













SoVaをもっと知りたい!